岩見沢市教育大学コンサートをふりかえり・・・
プロのクリップで聞き直してみることにした。学生の演奏はみずみずしく、新鮮。だからこそ、プロの演じるその曲をもう一度、比較してみました。^^
楽譜、音楽の解釈の違い。世界観の相違。きっとおもしろいのではと。
(結果は、最高にわくわくするほど、楽しかったです。)
★マスカーニ 「友人フリッツ」 「わずかな花を」
★グロンダール 「トロンボーン組曲」
★ラウタヴァーラ 「エチュード集」
ラウタヴァーラその2
その3 光の天使
★レオン・カヴァッロ
「道化師」
次なるは、コープランドの「クラリネット協奏曲」
★ラフマニノフ 「ピアノコンチェルト」
ここで、休息でした。トイレへ行って、エコノミー症候群にならぬように、気をつけて、気分転換。・・・・・・・
次なる曲は。
★ベッリー二 「夢遊病の女」でしたが、岩見沢市教育大学の出演する筈の人が、たしか、風邪かなにかで、中止となりました。残念でした。
★次なるは、プロコフィエフ ヴァイオリン協奏曲でした。
庄司紗矢香さんのを聞いてみます。
★フランセ 「花時計」
いよいよ、最後の曲です。
★ラシド・カリムリン(タタール自治共和国作曲家同盟議長),変貌するソヴィエト作曲界の音楽家。なかなか資料がありません。クリップはようやっと見つけました。貴重です。
というわけで、全曲を聞き直してみたのですが、あらためて、クラシック界の革新、を感じました。というのは、1950年代に作曲された曲が耳についたからです。
1950年代には、jazzがまだまだ、革新せずに、スタート点にたっているだけで、70年代のフリーjazzまで待つしかなかったということをあらためて、考えさせられました。(50年代のjazzはjazzで、大好きなのですが、クラシックの方が、良くも悪くも、音の革新を考えていたという点が、興味深かったです。)
クラシックは、おもしろいです。深いです。
jazzミュージシャンが、最後の最後に、誰もが、クラシックに憧れるということも、含めて、興味深い西欧の音楽界です。
残念だったのは、日本の、武満徹などの作品がひとつも演奏されなかったことです。ここは、日本ですから、ひとつくらいは、誰かが、チャレンジしてもらいたかったところです。
明日もまた、クラシックコンサートを、友人の Oさんと、聞きに行きます。楽しみです。・・
◎資料
マスカーニ
ピエトロ・マスカーニ(Pietro Mascagni, 1863年12月7日リヴォルノ - 1945年8月2日ローマ)は、イタリアのオペラ作曲家、指揮者。
経歴
パン屋の両親の元に生まれる。父はピエトロに法律を学ばせたが、彼は音楽に強い関心を持ち、伯父を味方につけて故郷の音楽院で本格的に音楽を学ぶ。20歳にならぬうちに交響曲、オペラ、カンタータなどを作曲し、その才能を認められる。そして後援者の後押しでミラノ音楽院に入り、アミルカレ・ポンキエッリに師事したが、途中で学校を飛び出し、指揮者として活動を始める。その後、チェリニョーラの音楽学校の教師となる。
1890年にローマの楽譜出版社ソンゾーニョ(Musicale Sonzogno)の一幕歌劇コンクールに応募して当選した代表作『カヴァレリア・ルスティカーナ』によって驚異的な成功を収めるが、不幸にもこれがその後の多くの作品を霞めてしまった。それでも15曲のオペラと1曲のオペレッタ、いくつかの美しい管弦楽曲や声楽曲、歌曲、ピアノ曲を残した。1895年にはペーザロのロッシーニ音楽院院長に就任。
存命中は、オペラで驚くほどの成功をおさめ、同時に指揮者としても非常に成功を収めた。マスカーニの作風は、友人でライバルだったプッチーニとは大変に異なっている。おそらくそのために評論家筋からマスカーニ作品は過小評価されてきたのだろう。
ファシスト党政権が誕生すると、スカラ座監督の座を狙ってムッソリーニに接近。このため、第二次世界大戦でイタリアが降伏した後、全財産を没収され、ローマのホテルで寂しく生涯を閉じた。遺体はローマに葬られたが、1951年に故郷のリヴォルノに再埋葬され、それと共に名誉回復された。
彼がいくつか残した自作自演(『カヴァレリア・ルスティカーナ』、『友人フリッツ』など)は、現在もCDで入手することができるほど評価が高い。
◎資料
ラウニ・グレンダール(Launy Grøndahl、1886年6月30日 - 1960年1月21日)はデンマークの作曲家、ヴァイオリニスト、指揮者。
1886年にオードロップに生まれた。8才からヴァイオリンを学び始め、13才でコペンハーゲンのカジノ劇場のオーケストラでヴァイオリン奏者となった。ルドルフ・ニールセンに作曲を、アクセル・ゲーゼにヴァイオリンを師事し、パリやローマ、ウィーンでも学んだ。
1925年に設立されたデンマーク放送交響楽団の初代指揮者に就任し、同時代の自国の作曲家の作品を積極的に取り上げた。1956年まで在任し、レコード録音も残されており、現在でもその演奏を聞くことができる。
1960年にフレデリクスベア(en:Frederiksberg)で亡くなった。
作曲家としては、交響曲や協奏曲、弦楽四重奏曲などの作品があるが、現在でも演奏され最もよく知られているのは『トロンボーン協奏曲』である。イタリア滞在中の1924年に作曲されたこの曲は、作曲者の友人であったコペンハーゲンの王立管弦楽団のトロンボーン奏者、ヴィルヘルム・オールクローのために作曲された。
◎資料3
エイノユハニ・ラウタヴァーラ(Einojuhani Rautavaara 1928年10月9日 - 2016年7月27日)は、フィンランドの現代音楽の作曲家。同国における同世代の作曲家のなかでは代表的存在である。
ヘルシンキに生まれる。1948年から1952年まで、ヘルシンキのシベリウス・アカデミーにてアーッレ・メリカントに師事。後に、シベリウスの勧めでニューヨークのジュリアード音楽院に移る。ジュリアード音楽院では、ヴィンセント・パーシケッティに師事するほか、タングルウッド音楽センターにてセッションズとコープランドのレッスンも受けている。ラウタヴァーラは、1954年にThor Johnson Contestへ出品した「我らの時代のレクイエム A Requiem in Our Time」で国際的な注目を集めた。
1957年から1959年まで、シベリウス・アカデミーにて短期の講師として働いた後、1959年から1961年までヘルシンキ・フィルハーモニックのアーキヴィストとして働いた。1965年から1966年までは、Käpylä Music Institute in Helsinkiの学長を務め、1966年から1976年まで、再びシベリウス・アカデミーにて講師になった。そのうち、1971年からは国家任命の芸術教授となった。1976年から1990年までは、シベリウス・アカデミーにて作曲学の教授に就いた。2004年に急病に倒れたものの、すぐに回復している。
ラウタヴァーラは多作の作曲家であり、さまざまな形式やスタイルで作品を発表している。彼の作品は、楽譜も容易に手に入れることが出来る。ラウタヴァーラは初期にセリー主義へ傾倒し、たとえば交響曲第3番ではセリアルな語法が目立つが、ブーレーズのような難解なセリー音楽ではなく、ブルックナーのようなきわめて明快な音楽を作る傾向にあった。しかし1960年以降はセリー主義を離れ、それ以後の作品では題名に「天使」などの語が織り込まれ、清澄で神秘的な要素を帯びてくる。こうしたラウタヴァーラの音楽では、弦楽器による簡素で民俗的な主題や、旋回するフルートの旋律、ベルによる静かな不協和音、牧歌的なホルンが特徴的なものとして挙げられる。
ラウタヴァーラの作品は、8つの交響曲のほか、いくつかの協奏曲、声楽曲、さまざまな楽器のためのソナタ、弦楽四重奏曲、その他室内楽曲、そしてたくさんのオペラなど、広いジャンルに亘る。 また、テープのためのパートが与えられた作品も多く、「カントゥス・アルティクス Cantus articus」(テープに録音された鳥の声と管弦楽のための協奏曲)や、合唱と管弦楽とテープのための「真実と偽りのユニコーン True and False Unicorn」が名高い。
ラウタヴァーラの作品の多くは既に録音されているが、なかでもレイフ・セーゲルスタム指揮によるヘルシンキ・フィルハーモニック・オーケストラの交響曲第7番「光の天使」は大成功を収めており、1997年度のグラミー賞にノミネートされた。
◎資料
ルッジェーロ・レオンカヴァッロ(Ruggero Leoncavallo, 1857年4月23日ナポリ - 1919年8月9日モンテカティーニ)は、イタリアのオペラ作曲家、台本作家。
ナポリ音楽院で学ぶ。数年間の教育活動の後、自作のオペラ上演の機会を得ようと努力したが、果たせなかった。オペラ『道化師 (Pagliacci)』が1892年にミラノで上演されるとたちまち成功をおさめた。これは今日標準的なオペラの演目に残っている唯一のレオンカヴァッロ作品であり、それ以外の歴史的歌劇などは上演される機会はない。翌年『メディチ家の人々 (I Medici)』を、1896年には『チャタートン (Chatterton)』を発表するが、どちらも興行的には失敗に終わった。その後のオペラは、『ザザ (Zazà, 1900年)』や『ベルリンのローラント (Der Roland, 1904年)』がある。
文才に恵まれ、また同時代のフランス文学に通暁していたレオンカヴァッロは、台本作家としてもそこそこの成功を収めた。レオンカヴァッロは初期のオペラでは自ら台本を書いており、また他の作曲家のオペラの台本も書いている。プッチーニの出世作『マノン・レスコー』の脚本にも協力した。
◎コープランド 資料
アーロン・コープランド(Aaron Copland、1900年11月14日 - 1990年12月2日)は20世紀アメリカを代表する作曲家のひとり。アメリカの古謡を取り入れた、親しみやすく明快な曲調で「アメリカ音楽」を作り上げた作曲家として知られる。指揮や著述、音楽評論にも実績を残した。
ニューヨーク州ブルックリンにおいて、ユダヤ系ロシア移民の息子として生まれた。14歳で本格的にピアノを習い始め、作曲家を志したのは15歳のときという。16歳からルービン・ゴールドマーク(オーストリアの作曲家カール・ゴルトマルクの甥)に作曲を師事する。
1921年、21歳のときにパリに留学、個人的にナディア・ブーランジェの弟子となる。パリ留学中にはジャズの要素を取り入れた曲を多く書いていたが、次第に一般大衆と現代音楽の隔たりを意識するようになる。
1924年に帰国すると、「アメリカ的」音楽を模索、アメリカ民謡を取材・研究し、これを取り入れた簡明な作風を打ち立てる。出世作『エル・サロン・メヒコ』(1936年)を経て発表された、『ビリー・ザ・キッド』(1938年)、『ロデオ』(1942年)、『アパラチアの春』(1944年)などのバレエ音楽が、コープランドのスタイルとして確立された作品といえる。
その後、再び純音楽的作品に戻り、12音技法を用いるなど曲折の後、晩年は非常な寡作となった。このようなコープランドの音楽スタイルの変遷は、そのままアメリカの音楽文化の形成過程を象徴しているとも指摘されている。
◎資料
セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・ラフマニノフ(Серге́й Васи́льевич Рахма́нинов、ラテン文字転写例: Sergei Vasil'evich Rachmaninov[註 1]は、(1873年4月1日(当時ロシアで用いられていたユリウス暦では3月20日) - 1943年3月28日))ロシア帝国出身の作曲家、ピアニスト、指揮者。
ラフマニノフ、1885年
1873年4月1日(ユリウス暦では3月20日)、父ヴァシーリイ・アルカージエヴィチと母リュボーフィ・ペトローヴナの第3子としてノヴゴロド州セミョノヴォに生まれ[註 2]、幼少期を同州オネグで過ごした。父母ともに裕福な貴族の家系の出身で、父方の祖父はジョン・フィールドに師事したこともあるアマチュアのピアニスト、母方の祖父は著名な軍人だった。父親は音楽の素養のある人物だった[註 3]が受け継いだ領地を維持していくだけの経営の資質には欠けていたようで、セルゲイが生まれた頃には一家はすでにかなり没落していたらしい。ノヴゴロド近郊のオネグは豊かな自然に恵まれた地域で、多感な子供時代を過ごした。
4歳の時、姉たちのために雇われた家庭教師がセルゲイの音楽の才能に気がついたことがきっかけで、彼のためにペテルブルクからピアノ教師としてアンナ・オルナーツカヤが呼び寄せられ、そのレッスンを受けた。9歳の時ついに一家は破産し、オネグの所領は競売にかけられ、ペテルブルクに移住した。まもなく両親は離婚し、父は家族の元を去っていった。セルゲイは音楽の才能を認められ、奨学金を得てペテルブルク音楽院の幼年クラスに入学することができた。
しかし彼は教科書の間にスケート靴を隠して出かけるような不良学生で、12歳の時に全ての学科の試験で落第するという事態に陥った。悩んだ母はセルゲイにとって従兄に当たるピアニストのアレクサンドル・ジロティに相談し、彼の勧めでセルゲイはモスクワ音楽院に転入し、ニコライ・ズヴェーレフの家に寄宿しながらピアノを学ぶことになった。
音楽家としての目ざめ
ズヴェーレフとその弟子たち
ズヴェーレフは厳格な指導で知られるピアノ教師で、ラフマニノフにピアノ演奏の基礎を叩き込んだ。ズヴェーレフ邸には多くの著名な音楽家が訪れ、特に彼はピョートル・チャイコフスキーに才能を認められ、目をかけられた。モスクワ音楽院ではアントン・アレンスキーに和声を、セルゲイ・タネーエフに対位法を学んだ。後にはジロティにもピアノを学んだ。同級にはアレクサンドル・スクリャービンがいた。ステパン・スモレンスキイの正教会聖歌についての講義も受け、後年の正教会聖歌作曲の素地を築いた。
ズヴェーレフは弟子たちにピアノ演奏以外のことに興味を持つことを禁じていたが、作曲への衝動を抑えきれなかったラフマニノフはやがて師と対立し、ズヴェーレフ邸を出ることになった。彼は父方の伯母の嫁ぎ先に当たるサーチン家に身を寄せ、そこで未来の妻となるナターリヤと出会った。この後彼は毎年夏にタンボフ州イワノフカにあるサーチン家の別荘を訪れて快適な日々を過ごすのが恒例となった。
1891年、18歳でモスクワ音楽院ピアノ科を大金メダルを得て卒業した。金メダルは通例、首席卒業生に与えられたが、当時双璧をなしていたラフマニノフとスクリャービンは、どちらも飛びぬけて優秀であったことから、金メダルをそれぞれ首席、次席として分け合った(スクリャービンは、小金メダル)。同年ピアノ協奏曲第1番を完成させた。
1892年、同院作曲科を卒業、卒業制作として歌劇『アレコ』をわずか数日のうちに書き上げ、金メダルを授けられた。同年10月8日(ユリウス暦では9月26日)にモスクワ電気博覧会で前奏曲嬰ハ短調を初演した。この曲は熱狂的な人気を獲得し、ラフマニノフの代名詞的な存在になった。
翌1893年5月9日(ユリウス暦では4月27日)、『アレコ』がボリショイ劇場で上演された。同年11月6日、チャイコフスキーが亡くなると、追悼のために悲しみの三重奏曲第2番を作曲した。
挫折
ラフマニノフは1895年に交響曲第1番を完成させ、2年後の1897年にはアレクサンドル・グラズノフの指揮によりペテルブルクで初演されたが、これは記録的な大失敗に終わった。特にツェーザリ・キュイが「エジプトの七つの苦悩」に例えて容赦なくこき下ろしたのはよく知られている。この曲はラフマニノフの存命中は二度と演奏されることはなかった。失敗の原因として、グラズノフの指揮が放漫でオーケストラをまとめ切れていなかった可能性[註 4]や、ペテルブルクがラフマニノフの属したモスクワ楽派とは対立関係にあった国民楽派の拠点だったことの影響などが指摘されている。
この失敗によりラフマニノフは神経衰弱ならびに完全な自信喪失となり、ほとんど作曲ができない状態に陥った。この間、彼はサーヴァ・マモントフの主宰する私設オペラの第二指揮者に就任し、主に演奏活動にいそしんだ。マモントフ・オペラではフョードル・シャリアピンと知り合い、生涯の友情を結んだ。シャリアピンの結婚式では介添人の一人として立ち会った。
ラフマニノフ、1899年
1898年にはシャリャーピンと連れ立っての演奏旅行で訪れたヤルタでアントン・チェーホフと出会い、親交を結んだ。チェーホフはラフマニノフの人柄と才能を称賛し、大きな励ましを与えた。
一方、彼の落胆を心配した知人の仲介により、1899年にレフ・トルストイと会見する機会にも恵まれた。ラフマニノフはシャリャーピンを伴ってトルストイの自宅を訪ね、交響曲第1番の初演以降に作曲した数少ない作品の一つである歌曲「運命」(後に作品21の1として出版された)を披露した。しかしこのベートーヴェンの交響曲第5番に基づく作品は老作家の不興を買い[註 5]、ラフマニノフはさらに深く傷つくことになった。
作曲家としての成功
つい最近までは、ラフマニノフの作曲家としての成功に決定的に寄与したのが、彼を心配した周囲の人たちの紹介で出会った精神科医のニコライ・ダーリだったということになっていた。しかし実際には数回の診療を受けただけで、現在ではその暗示療法の効果が疑問視されている。事実、難航していたピアノ協奏曲第2番第1楽章が完成したのは、治療に通った時期から1年以上経過している。
やがて創作への意欲を回復した彼は1900年から翌年にかけて、2台のピアノのための組曲第2番とピアノ協奏曲第2番という二つの大作を完成させた。特にダーリに献呈されたピアノ協奏曲第2番は作曲者自身のピアノとジロティの指揮により初演され、大成功を収めた。この作品によってラフマニノフはグリンカ賞を受賞し、作曲家としての名声を確立した。
1902年、従妹のナターリヤ・サーチナと結婚した。当時、従姉妹との結婚には皇帝の許可証が必要だったが、伯母の奔走により無事許可を得ることができた。結婚式の行われた4月に作曲した「12の歌曲集」作品21には妻に捧げた「ここは素晴らしい」(第7曲)や、後に自身でピアノ独奏曲にも編曲した「ライラック」(第5曲)といった作品が含まれている。
1904年から1906年初めまで、ボリショイ劇場の指揮者を務めた。神経を集中して指揮に取り組んでいたため、楽員には気難しくやかましい指揮者と恐れられた。1906年1月には自作のオペラ、『けちな騎士』と『フランチェスカ・ダ・リミニ』を初演した。
同年秋から1909年にかけて、家族とともにドレスデンに滞在した。このドレスデン滞在中の1907年に完成させた交響曲第2番は翌1908年の1月にペテルブルクで、2月にモスクワで作曲者自身の指揮により初演され、熱狂的な称賛を以て迎えられた。この作品によりラフマニノフは2度目のグリンカ賞を受賞した。1908年にはアムステルダムでウィレム・メンゲルベルクとの共演でピアノ協奏曲第2番を演奏した[3]。
1909年春、スイスの画家、アルノルト・ベックリンの同名絵画の複製画に着想を得た交響詩『死の島』を作曲した。同年夏にはイワノフカの別荘で、秋に予定されていたアメリカへの演奏旅行のためにピアノ協奏曲第3番を作曲した。同年11月にニューヨークで自身ピアニストとして初演(この作品は、当時まだ出来上がったばかりだったらしい。‘The Classic Collection’第80号より)し、翌年1月にはグスタフ・マーラーとの共演でこの作品を演奏した。
ラフマニノフ、1910年代
この頃ラフマニノフは女流文学者のマリエッタ・シャギニャンと文通で意見を交わすようになり、1912年には彼女の選んだ詩による歌曲集作品34を作曲した。またこの曲集には終曲としてソプラノ歌手のアントニーナ・ネジダーノヴァのために作曲された「ヴォカリーズ」が収められている。
1913年の1月から4月にかけてはローマに滞在した。スペイン広場の近く、かつてチャイコフスキーが滞在し創作に励んだのと同じ家を借りて住み、そこでエドガー・アラン・ポーの詩のコンスタンチン・バリモントによる翻訳に基づく合唱交響曲『鐘』を作曲した。1915年1月には正教会の奉神礼音楽の大作『徹夜禱』を作曲した。1917年の秋には十月革命の進行する中、ピアノ協奏曲第1番の大掛かりな改訂作業を行った。
祖国を離れて
1917年12月、ラフマニノフは十月革命が成就しボリシェヴィキが政権を掌握したロシアを家族とともに後にし、スカンディナヴィア諸国への演奏旅行に出かけた。そのまま彼は二度とロシアの地を踏むことはなかった。(1930年6月の、『ミュージカル・タイムズ』のインタビュー記事にラフマニノフ自身の「僕に唯一門戸を閉ざしているのが、他ならぬ我が祖国ロシアである。」という言葉が引用されていたという。‘The Classic Collection’第80号より)
しばらくはデンマークを拠点に演奏活動を行った後、1918年の秋にアメリカに渡り、以後は主にコンサート・ピアニストとして活動するようになった。それまでラフマニノフのピアニストとしてのレパートリーは自作がほとんどだったが、アメリカ移住を機にベートーヴェンからショパンまで幅広いレパートリーを誇る、極めて活動的なコンサート・ピアニストへと変貌を遂げたのである。1925年以降はヨーロッパでの演奏活動も再開した。
この時期には同様の境遇にあったベンノ・モイセイヴィチやウラディミール・ホロヴィッツと親交を結んだ。フリッツ・クライスラーとの共演による演奏、録音も度々行った。またピアノ制作者のスタインウェイと緊密な関係を保ち、楽器の提供を受けた。
ロシア出国後は作曲活動は極めて低調になった。これは多忙な演奏活動のために作曲にかける時間を確保できなかったのみならず、故郷を喪失したことにより作曲への意欲自体が衰えてしまったためでもあった。同じロシアの作曲家、ピアニストとして旧知の仲であるニコライ・メトネルになぜ作曲をしないのかと尋ねられると、「もう何年もライ麦のささやきも白樺のざわめきも聞いてない」ことを理由に挙げたという[1]。それでも1926年にはロシア出国後初の作品となるピアノ協奏曲第4番を作曲した。
1931年、スイスのルツェルン湖畔にセナールと呼ばれる別荘を建て、ヨーロッパでの生活の拠点とした。「セナール (Senar) 」とは、セルゲイ (Sergei) 、ナターリヤ (Natalia) 、ラフマニノフ (Rachmaninov) の頭文字を取ったものである。パガニーニの主題による狂詩曲と交響曲第3番はここで作曲された。1939年8月、ルツェルン音楽祭に出演し、エルネスト・アンセルメとの共演でベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番と自作の狂詩曲を演奏した[4]。
ラフマニノフの墓。八端十字架が建てられている。
やがてナチスが勢力を拡大するとスイスにも滞在することができなくなった。最後の作品となる交響的舞曲を作曲したのはロングアイランドでのことだった。1942年には家族とともにカリフォルニア州のビバリーヒルズに移り住んだ。左手小指の関節痛に悩まされながらも、演奏活動は亡くなる直前まで続けられた。
1943年3月28日、70歳の誕生日を目前にして癌のためビバリーヒルズの自宅で死去した。ラフマニノフ自身はモスクワのノヴォデヴィチ墓地に埋葬されることを望んでいたが戦争中のことでもあり実現できず、6月1日にニューヨーク州ヴァルハラのケンシコ墓地に埋葬された[註 6]。
◎ベッリー二
ヴィンチェンツォ・ベッリーニ(Vincenzo Bellini, 1801年11月3日 - 1835年9月23日)はシチリア島・カターニアに生れ、パリ近郊で没したクラシック音楽の作曲家で、主としてオペラ作曲家として有名である。名字はベルリーニ、ベリーニとも表記する。1985年から1996年まで発行された5000イタリア・リレ(リラの複数形)紙幣に肖像が採用されていた。
ロッシーニやドニゼッティと共に19世紀前半のイタリアオペラ界を代表する天才である。中でも特にベッリーニについてはショパン、ベルリオーズ、ワーグナーらの賞賛と愛情の言葉を得ている事で知られている。父親も祖父も音楽家であり、音楽を学ぶ前から作曲を始めたという神童であった。
1819年(18歳)- 貴族の後援者を得てナポリの王立音楽院に入学。
1825年(24歳)- 音楽院内で公演されたオペラの処女作『アデルソンとサルヴィーニ』が認められる。その後、オペラ『ビアンカとジェルナンド』、『海賊』の相次ぎ成功。
1831年(30歳)- オペラ『夢遊病の女』を発表。大好評を博すが、自身では管弦楽法の未熟さを認識しており、改めて学習したと言われている。
1835年(34歳)- 病を得て9月23日短い生涯を閉じた(慢性の腸疾患という)。パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されたが、その後遺体はカターニアに再埋葬された。
◎資料 セルゲイ・プロコフィエフ
Прокофьев シェルギェーイ・シェルギェーイェヴィチュ・プラコーフィイェフ;ラテン文字転写の例:Sergei Sergeevich Prokofiev、1891年4月23日 - 1953年3月5日)は、ロシアの作曲家、ピアニスト、指揮者。
現在のウクライナ、ドネツィク州(当時はロシア帝国領)ソンツォフカ(Сонцовка;ラテン文字転写の例:Sontsovka)生まれのロシア人。帝政期のロシアに生を受け、サンクトペテルブルク音楽院で作曲・ピアノを学ぶ。革命後、シベリア・日本を経由してアメリカへ5回渡り、さらにパリに居を移す。20年近い海外生活の後、1936年に社会主義のソヴィエトへ帰国。作風は、こうした外的な環境に応じて大きく3つの時期に区分できる。
ソヴィエト時代には、ショスタコーヴィチやハチャトゥリアン、カバレフスキーらと共に、社会主義国ソヴィエトを代表する作曲家とみなされたが、ジダーノフ批判を受けるなど、必ずしも総て順風であった訳ではない。
交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽曲、ピアノ曲、声楽曲、オペラ、映画音楽などあらゆるジャンルにわたる多くの作品が残されており、演奏頻度が高い傑作も多い。特に、自身が優れたピアニストであったことから多くのピアノ作品があり、ピアニストの重要なレパートリーの一つとなっている。
◎資料
ジャン・ルネ・デジレ・フランセ(Jean René Désiré Françaix , 1912年5月23日 - 1997年9月25日)は、フランスの新古典主義音楽の作曲家。ピアニストや編曲家としても活躍し、多作家で、生気あふれる作風で知られる。没後の翌年から、フランス国内でフランセを讃えたジャン・フランセ国際音楽コンクールも開催されている。
フランセの天与の才能は、幼い頃から家庭環境によって育まれた。父親は音楽学者・作曲家・ピアニストであり、母親は声楽教師だった。6歳で作曲を始め、1922年の最初の出版作品は、ナディア・ブーランジェの注目を集める。当時彼女は、楽譜出版社のための仕事をしており、ブーランジェはフランセに音楽活動を薦めた。フランセ自身はしばしば自作を演奏して、公衆の注目を集めた。たとえば、「ピアノと管弦楽のためのコンチェルティーノ」のバーデン=バーデン初演(1932年)が有名である。
フランセは若い頃から洗練されたピアニストで、パリ音楽院ピアノ科では首席に輝いており、ソリストや伴奏者としての道を模索したこともあった。チェリストのモーリス・ジャンドロンとの共演が有名だが、ジャック・フェヴリエの代役として、フランシス・プーランクの「2台のピアノのための協奏曲」で作曲者自身とピアノを共演することもあった。
しかしフランセの、やはり主要な業績といえば、きわめて積極的な作曲活動であった。生涯を通じて多作家であり、1981年においてさえ、「いつでも作曲している」と公言していたように、別々の作品を掛け持ちで書き上げるのが常だった。この習慣は没年まで続けられた。
作品
モーリス・ラヴェルはフランセの少年時代に、その両親に次のように述べている。「この子の才能のうちで、私が見る限り、一人の芸術家として最も将来が有望視されるのは、旺盛な好奇心に恵まれているということです。くれぐれも親御さんが、かけがえないこの才能を潰したり、坊ちゃんの感受性をしなびさせたりしませんように」
フランセは多産な作曲家であり、幅広い作曲様式によって200曲以上の作品を残した。
作品はピアノ曲が中心を占めており、あらゆる管絃楽曲や合奏曲、とりわけ多くの室内楽曲では、ピアノの存在が目立っている。フランセは管弦楽法の手腕に長けており、音色の扱い方にその能力が発揮されている。フランセは大形式の楽曲を数多く手懸け、協奏曲や交響曲、オペラ、劇場音楽、バレエ音楽を残した。またカンタータなど、20世紀に関心が失われつつあった伝統的な楽種にも手を染めている。フランセは、古くからの表現方法に現代的なスピード感を付け加えたものの、自他ともに認める新古典主義者として、無調性や無形式の迷宮を斥け、声楽曲の作曲では、過去の偉大な前例に倣っている。また10点の映画音楽も残した。
作曲様式は、生涯を通じてほとんど変わらず、軽快さと機智にあり(自ら述べたところによると、目指したところは「喜びを与えること」だった)、旋律線同士のやりとりも目立っている。尊敬していた作曲家、たとえばイーゴリ・ストラヴィンスキーやラヴェル、プーランクらに影響されたが、取り入れたものは自分自身の確たる美学へとまとめ上げている。こういう側面は初期作品にも認められる。










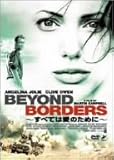












































 ^_^)散歩スタートします。
^_^)散歩スタートします。






































































































