最近、ネットを見ていますと。
たとえば、「元カレが、どうしようもない、女好きで、金銭にだらしなく、貯金もなく、仕事も低賃金だった。今の主人は、性格もおだやかで、高収入。子どもにも恵まれ、幸福。元カレと早く別れて良かった。どうしてあんなに好きだったか、今では信じられない。」という記事があり、そのコメントに対して、多くの、若者たちが、賛同をしている・・・・・・・
そんな記事を見ていて、私は、首をひねります。
あまりにも、単純で、打算的というか、合理的すぎる。そんな感じがします。
今が、幸福だからと言って、昔別れた、大好きだった人の悪口・愚痴をネットに、吐き出して、賛同してもらう心理。
男と女。そんなに単純なものではありません。
私は、個人的な意見ですが、このような女性には、げんなりしてしまいます。
(このような女性は、こんどまた、人生の荒波のなかで、違う厳しい場面にぶつかった時に、ひとり嘆いて、きっと、なんでもかんでも、相手や環境の責任にするんだろうなあ・・・そう考えてしまいます。)
・・・・・・・
この世。この宇宙は、もっともっと、複雑で、込み入ったいわば、タペストリーのような糸で、縦横に、くみあわさっている、「縁」の世界です。
今の、幸福の花の中にも、確実に、不幸の種はあるものです。
(逆に言えば、不幸の花の種のなかにも、幸福の種はひそんでいます)
幸福という名の不幸 上 (講談社文庫 そ 1-1)/講談社
¥524
Amazon.co.jp
つまり、今、どんなに幸福であっても、たとえば、主人が急に病気で倒れてしまえば、会社を止めなければいけなくなるかもしれませんし、子どもだって、前回のシネマ記事「ラビット・ホール」ではありませんが、突然の交通事故にて、死すかもしれません。
そこにある危機。そこにある死。・・・・・
それは人ごとではないのだと、私は、思います。
私も、生後まもない赤子=娘を、失くしています。
あの悲しみは、今でも、忘れません。
人生とは、そんな、危機が誰にでも、訪れるのだと思います。
・・・・・・・
そのようなことを、普通に、自然に、想像したり、危機をきちんと、考えることができるような、人であるならば、
今の幸福の花は、実は、これまでの過去のいろいろな出来事の糸が、因果応報で、今の現実の糸と、固く、むすびついていることに気がつく筈ですね。
また、そのような人であれば。
昔、大好きだった、異性のことを、悪く言うようなことはないでしょう。
彼が、いたからこそ、今の自分があるんだなあ・・・・・・そのような余裕も、もてる筈。
私の知り合いに、ホストと知らずに好きになって、1000万くらいを貢いだという女性がいました。
でも、彼女は、一言も、その今は別れた彼氏のことの悪口を言ったことはありません。
「あれだけ、人を好きになれて、私はまったく後悔していない」。
気持ちの良い一言を聞けました。素晴らしい女性だとも感じました。
小林秀雄は、「芸術は、歴史に埋もれたる人間を救い出すひとつの術を編み出す」と、書いています。
要は、人は、何かに夢中になって、たとえば、人を好きになったり、映画などの芸術などに感動したときに、過去現在未来と続く時間と空間の呪縛からときはなたれて、「今ここ」の、永遠の現在のなに、恍惚として、浸ることができる、そう私は、解釈していますが。
何かに夢中になる。
何かを大好きになる。
とことん、何かにうちこむ。
恋であれ、仕事であれ、芸術であれ、スポーツであれ、そのような人達は、そんな「今ここ」に浸る幸福をしっかり感じることができるので、
みんな、「感謝」という言葉をつかうようになりますね。
ところで映画です。
1970年代。私が、16歳、高校生の頃ですが、ベトナム戦争がありました。
そんな時代の映画ですが。
この映画は、あまりにも、大甘な映画で、かなり批判もされましたが、淀川さんの次に好きな、荻昌弘さんは、「これはある意味、反戦映画なんだ」と、言っていたことをなつかしく、思い出します。
つまり、危機的状況の時だからこそ、朝起きて一杯の珈琲が幸福のシンボルになるということでしょう。
なにげのない普通の日々。
そこで、出会う、普通の人達。
普通の太陽、普通の草木、普通のコーヒー。
普通の抱擁、普通のキス。
「愛とは決して後悔しないこと」(Love means never having to say you're sorry)という生前ジェニファーがオリバーに残した言葉、今でも、はっきり覚えています。
Love means never having to say you're sorry
・・・・・・・・・
戦争で、自国の若者がつぎつぎと死んで行くそんなアメリカ。
反戦反戦と騒ぐ若者たち。
でも、選挙などでもわかったように、普通のアメリカ市民は、ベトナム戦争に命をかけて行った若者を支持しましたし、普通の時間が普通にある普通の生活にあこがれていたのでしょう、批判を受けながらも、この映画はヒットしました。日本でも、同じです。
反戦と叫べば、良いわけではありません。
人には自分の命を犠牲にしてまで、守るべき人達や場所があるのだと私は、個人的に、思っています。
70年代。
良くも悪くも、それまで、禁止されていたこと、隠されていたこと、秘密にされていたこと、そんな多くのことが、次第に、表面の世界へと、浮き上がろうとした時代です。
レズビアン・ホモセクシャル・そんな言葉が平気で使われるようになりました。
ウッドストック。
実になつかしい。
私も、普通の高校生でしたから、岩見沢市から札幌まで、この「ウッドストック」を、
見に行きました。テンイヤーズアフターの大ファンでしたので、大感激をしたことを今でもはっきりと、思い出せます。
(クリップのジャニス・ジョプリンも、天才歌手でしたが、麻薬などで死んでしまいました。その他、この映画に登場する素晴しいロック・ミュージシャンたちも、麻薬などで、つぎつぎと、亡くなって行きました。良くも悪くも、超熱い時代です。)
この映画の中のシーンにもでてきますが、性の解放というテーマがありました。
日本のZENの書物がつぎつぎに、翻訳され、アメリカの詩人たちがそれからインスパイアされた自由の詩を歌い始め、魂の次の次元をということで、麻薬が乱用された時代です。
性の解放。
アメリカでは今でも、ソドミー法という、「男色」を禁じた、法律が、、たしか、ほとんどの州に残っているのではないでしょうか。
その厳しさ、激しさを描いた映画では、好き嫌いはあるでしょうが、
この映画が思い出されます。メインのテーマではないので、忘れていた方も多いでしょうが。
大好きな映画です。「アメリカン・ビューティ」
音楽が良いですし、映像が素晴らしい。
(平凡な核家族が崩壊する過程で、現代アメリカ社会の抱える闇を時にコミカルに描き出す。娘の同級生に恋する中年男性をケヴィン・スペイシーが演じている。
第72回アカデミー賞で作品賞を受賞した。)
好きなシーンはたくさんありますが、今の記事のテーマで書くと、ケヴィン・スペイシーが、娘の友達に惚れて、体を鍛え直すのですが、その鍛えていることや、自分の息子との関係を怪しまれて、ホモ・セクシュアルと勘違いされて、殺されてしまうわけですね。(いや、そうではないと、いろいろな解釈が今でもされている不思議なラスト・シーンでしたが。私は、そう考えています。)
ああ、やっぱり、ニューヨークなどの最先端の町とはちがって、この映画の舞台でもあるシカゴの郊外、田舎であれば、こういうのが、ホモ・セクシャルの男性に対する普通の感覚・感情なんだろうな、と、考えさせられました。
私はホモ・セクシャルでも、ゲイでもありませんので、この映画は、その他にも、美しい女性達がたくさん出てきますので、楽しめました。
ただ、私は、ホモ・セクシャルという観点から、見ました。・・・
男と女。
不思議な相反する性の存在。
もちろん、子孫繁殖というのは、当然ながら、自然の神が遺伝子のなかに組み込んだ意図ですから、男と女が愛し合うのは基本。
ただ、当然例外もでてきます。
それが、プラスなのかマイナスなのか。
私にはわかりませんが。
今、沈んでいたものが、つぎつぎに、カミングアウトされる時代ですから。
ところで、日本のホモ・セクシャルと言うと。私が尊敬する人だけでも、
美輪明宏・淀川長治・稲垣足穂・・・・その他、たくさんおりますが。
もともと、日本は、カソリックなどの影響の強い海外の同性愛とは違って、
女性を妻としてめとった上での、美少年やお稚児さんを愛するという、
両刀使いという意味では、たくさんの例があり、また、西洋のような
強い反感などは意外になかったのではないでしょうか。
たとえば、森鴎外の森鴎外は、自分自身の性的経歴を書き記した作品『ウィタ・セクスアリス』(1909年)のでこう述べています。
学校には寄宿舎がある。授業が済んでから寄ってみた。ここで初めて男色
ということを聞いた。僕なんぞ同級で、毎日馬に乗って通ってくる蔭小路と
いう少年が、彼ら寄宿生たちの及ばぬ恋の対象物である。蔭小路はあまり課
業はよくできない。薄赤いほっぺたがふっくりとふくらんでいて、かわいら
しい少年であった。その少年という言葉が、男色の受け身という意味に用い
られているのも、僕のためには、新知識であった。僕に帰りがけに寄ってけ
と言った男も、僕を少年視していたのである。
と、あります。)
また、
川端康成とその弟子である中里恒子との合作としての、「乙女の港」という女性と女性の絆というテーマの小説もありましたね。乙女の港 (実業之日本社文庫 - 少女の友コレクション)/実業之日本社
¥823
Amazon.co.jp
横浜のミッション系女学校に通う女学生たちの交友関係を綴った作品で、上級生と下級生が擬似的な姉妹となって交際するという、当時の女学生の間で広くおこなわれていた エス (sisters-in-law)という風習について描かれている。
三島由紀夫・・・・・・
「私の永遠の女性」。
私の所有する、三島由紀夫全集のなかの評論のひとつです。
真の男性を常に目指す、男として男を愛する彼が、「永遠の女性」について語っています。
明治時代の女の全身像の写真が好きだというところからそれは始まります。
実際の写真がないので、クリップにたよるしかありませんが。
彼が大好きだった、ラディゲの、「ドルジェル伯の舞踏会」に登場する、フランソワの母親の、ド・セリウズ夫人について引用しながら、
ドルジェル伯の舞踏会 (新潮文庫)/新潮社
¥432
Amazon.co.jp
「今日、われらは、弱々しいものでなければ、女らしいとは思なくなっている。ド・セリュウズ夫人のしっかりした顔の輪郭が、彼女を愛嬌のないものに見せるのだった。この美しさは、男達の心を誘わなかった」
凛としたもの。
いかつさ。
犯しがたいもの。
明治の名芸妓たちの顔にもあるもの。
近代能楽集 (新潮文庫)/新潮社
¥529
Amazon.co.jp
・・・・・・・・
ところで。
三島由紀夫は、おもしろいことに、彼は普段好きな女のタイプは、
「現代風な丸顔で、輪郭のあまりはっきりしない、普通の愛らしい顔である」と書いている。
(奥様、平岡瑤子とともに)
しかしながら。
彼が、書いた、名作の能の現代化としての「近代能楽集」。
そのなかの、傑作の一編「卒塔婆小町」を、武智鉄二が演出した能を三島由紀夫が、
見た時。
その感想を書いています。
(武智鉄二のクリップはありませんので、このクリップにしました。)
「有名なるシーンで、舞台の中央に置かれた台の後ろを老婆と詩人が踊りながら通過して、あちらがわからこちらがわに出てくると、その台が、鹿鳴館に変わって、老婆は、美しいワルツにのつて、ありし日の美しき若き小町となって出てくるのである。」
そのときの驚愕・・・・。
「ありし日の小町が、閉じた黒い扇をかざし、そのいかにも、明治風な鼻の線と受け口の横顔をあらわしたとき、あまりの美しさに息を吞んだ。そればかりか、戦慄したのである。」
彼は言いいます。
「 舞台の上の小町は、私の好尚とはひとつひとつ違うのにかかわらず、現実の女性は、これほど奥深い感動で私の心をゆすぶりはしない。こんなに私の全精神をゆすぶり、私の歩んできた人生を縦に貫く稲妻のような感動で、私を戦慄させはしない。
舞台が、すんで、舞台関係者と吞んだ席では、小町を演じた浜田洋子さんは普通の美しい女性であり、残酷ながら、けっしてさっきの小町ではなかった。 」
彼は、そこで、自分の母親のことについて触れているが、このあたりはかなり興味深いです。
「実際、永遠の女性らしいものを近代文学に探して失望しないのは、泉鏡花の小説ぐらいなものでろう。そのヒロインたちは、美しく、凛としており、男性に対して永遠の精神的庇護者である」
上の三島由紀夫の言葉は深くて興味深い。
小さな頃から、母と離れて、祖母に育てられた、そのいきさつは、彼の傑作「仮面の告白」のなかにも、詳細に書かれています。
特に、彼の、女装に対する偏愛のことまでも・・・・
現代。女性がすでに男性を愛する力を失った時代とも言われいます。
この現代の情報のあらゆることを、ひたすら、頭に詰め込んだ女性達は、ひょっとすると、細かな部分の欠如にだけよくよく気がつき、そこからノイローゼ的に離れることができなくなっているのではないか???
分析ではなくて、統合として、男性を包み込むことを体験できなくなった・・???
そんな時代。三島由紀夫のひとつひとつの言葉は、
アンドロギュヌスの彼だからこそ、納得できる言葉でもあります。
(しかしながら、彼の女性観は、永遠の精神的庇護者と、書いたり、褒めたり、あるいは、けなしたり、少しぶれている部分もありますが、「笑う」ことこそ、女性の本質なのだと看破するようなセンテンスを、とある小説、たしか、「春子」だったかに、書いています。)
「春子」・・・主人公は19歳の男子学生。主人公の叔母、春子と叔母の義理の妹の18歳の路子とのレズを取り上げています
真夏の死―自選短編集 (新潮文庫)/新潮社
¥594
Amazon.co.jp
ところで。三島由紀夫の愛したドイツの作家。トーマス・マンに、アンドロギュヌスの傑作があります。
「ベニスに死す」です。
(ドナルド・キーンによれば、三島は自身の代表作『金閣寺』の文体を「鴎外 プラス トーマス・マン」だと述べており、キーンは『暁の寺』にも『魔の山』からの文体的影響を指摘している(『悼友紀行』、中央公論社)。)
淀川長治さんも、アンドロギュヌスでしたから、この映画を愛していました。
ビョルン・アンデルセン「言うまでもなく、ベニスに死すですね」

こんなに成長してしまいました。人生とは、実に、過酷なものです。
花の色は うつりにけりな いたづらに
わが身世にふる ながめせしまに
小野小町
やはり、美というものは、ブレイクではありませんが、「今ここ」=「瞬間のなかの永劫」ですから、花もいつまでも咲きつづけることはできません、・・・いつかは、枯れて、しおれてしまうのですから、・・・・・・たがら、逆に今の美しさが、みずみずしく、なおさら、美しい、そういうことでしょうか。
・・・・・・・・・・・・
美男子の世界。
ところで。
私が好きな映画評論家は、もちろん、淀川長治氏です。名作はあなたを一生幸せにする―サヨナラ先生の映画史/淀川 長治
¥1,890
Amazon.co.jp
理屈、理論よりも、好きで好きでもうどうしょうもないくらいに映画が好き、というそのはちゃめちゃが好きです。
稲垣足穂をだすまでもなく、男色家の人は両刀使いの人が多い筈で、要は、人間の美しさというものを普段から考えています。
そこで、少年好きの、淀川長治氏はどんな美少年が好きだったかということを、最後に、備忘録しておきましょう。
まずは、鉄道員。私の愛するイタリア映画の傑作古典です。監督は、戦後のイタリア映画復興の基礎を築き、ネオ・レアリズモの三大巨匠がロベルト・ロッセリーニ、ヴィットリオ・デ・シーカ、ルキノ・ヴィスコンティで、ネオ・レアリズモの最後の旗手が監督、脚本家、それに俳優のピエトロ・ジェルミであると、資料にありますね。
エドワルド・ネヴォラ
サンドロ少年として、出演しています。
淀川さんが大好きだった美少年子役です。
はにかんだ感じが素晴らしい。
次に、「旅情」。これは素晴しき作品でした。・・・キャサリン・ヘプバーン。
ほんとうの美人です。
この、はだしの少年らしいです。 「旅情」でキャサリン・ヘプバーンに万年筆を売ろうとつきまとう少年なんですが、クリップ中に、少ししかでてきません。
淀川さんは、生涯、「映画と結婚する」と小さな頃に決意して、一生独身でしたから、
子どもさんもいませんでしたので、小さな少年=自分の憧れとして、見ていたのかもしれません。
日本でも、歌がヒットしました。
(ストーリー
アメリカの地方都市で秘書をしている独身の38歳のジェーン・ハドソン(キャサリン・ヘップバーン)は長期休暇を取り、念願であったヨーロッパ旅行の夢を実現させて、ロンドンとパリを観光後、オリエント急行に乗って、この旅行の最終目的地である水の都・ヴェネツィアを訪れる。ヴェネツィアは街中に水路が張り巡らされた歴史のある美しい都であり、ジェーンは駅から船でフィオリーニ夫人(イザ・ミランダ)が経営するペンシオーネに到着する。その後観光に出かけたヴェネツィアのサンマルコ広場で一人のイタリア人男性レナード(ロッサノ・ブラッツィ)と出会う。)
オブィデュー・バラン少年。
「モンド・・・フランス映画」 クリップは発見できませんでした。
笑顔がさわやかですねえ。
日本の美少年は、花にたとえれば、「梅」
外国人の美少年は、花にたとえれば、「薔薇」か「水仙」なんでしょうか。
ところで、淀川さん。
わが映画人生に悔なし (ハルキ文庫)/淀川 長治
¥441
Amazon.co.jp
淀川長治氏がテレビに出てきて「みなさん こんにちは」とか言いながら、「本日の映画は」と話を始めると、とにかくその記憶力の凄さといいますか、今はネットなどでスター情報などはすぐに見れますが、当時はいちいち書物などにあたらねばならなかった筈で、きっと彼の想像するに「映画ノート」にはぎっしりと情報が書かれていたでしょうね。
たしか、英語も映画でマスターしたと言っておられました。
初対面でむこうのスターと、会ってもすぐに映画の原題やら、スターの情報が機関銃のように連発できた彼は、きっと快くスター達との初対面をなごやかにしたことでしょう。
ところで、美少年。
まずは、ウィリアム・ワイラー監督の「デッド・エンド」に出ていた五人の少年。マンハッタンの泥だらけの少年達。
1937年ウィリアム・ワイラー監督『デッド・エンド』でデビューしたの不良少年グループ。実際映画会社もキッズ達には自由にカメラの前で演じろといっていたので、その調子で最初のシーンである廃ビルの地下室のシーンで、台本を無視したキャグニーをおちょくったせりふを生意気そうな少年が、ギャグニーをからかうと、キャグニーは生意気そうな少年の鼻っ面めがけて、強烈なパンチをくらわせた。「いいか、キッズ、よく聞けよ。俺たちゃここで仕事をやってるんだ。ふざけたまねはお互いにしないようにしようぜ。撮影をやってるときは俺たちはプロだ。やるように言われた仕事はきちんとやることだ。わかったか!」
こうやって少年たちも大人になっていくのでしょう。
ワイラー監督は、「ローマの休日」や「ベンハー」をつくった監督ですね。
これらの映画は、若き頃に、数十回も見ました。
今でも、たまに、突然見たくなるシーンがあり、バッと、DVDを見てしまいます。
このシーンが、この時代によく撮れたと今でも背筋が、ぞっとするほど感激します。
素晴しき作品群、素晴しき監督です。
つぎに、「エデンの東」「ジャイアンツ」のジェームズ・ディーン。エデンの東 新訳版 (1) (ハヤカワepi文庫)/ジョン・スタインベック
¥798
Amazon.co.jp
なんとディーンが、「銃剣を装備せよ」という映画に数カット脇役で出ていただけなのに、すでに、あまりの美しさにワーナーの宣伝部に淀川さん、問い合わせしています。宣伝部でさへ知らなかったらしいですが。
(エデンの東。完璧なまでに、となりの女優よりも美しいです。)
余談ですが、三島由紀夫氏がアメリカでジェームズ・ディーンのよく行くバーに行ったとききました。
帰国後、ディーンの大ファンの小森和子のおばちゃまが、三島由紀夫にそのズボン(ディーンが座っていたイスに座ったからか?)をくれくれと、ねだったといいます。
まあ噂は噂ですが・・・・ありそうな話ですね。

つぎに、エルヴィス・プレスリーって今の若い人は知っているのでしょうか?
この人もかっこよかったというか、スペイン系の美しさだと淀川長治氏は言いますが、そのとうりかもしれません。
生涯にたしか、32本。すべて、主演ででています!!!!!
この下の映画100年記念の切っては、先日も記事にしましたが、マリリン・モンローとプレスリーのツー・ショットですネ。
淀川さんは実に清潔感のある方、美意識が強い方でしたから、たしか死ぬ数年前から東京の有名一流ホテルを借り切って住むようになったのですが、その理由が、「まんがいちの時に下着などが汚れていると嫌だから」と言ったといいますね。
ホテルであれば、いつでも、下着だろうが、スーツだろうが、いつでもクリーニングしてくれますし、掃除もやってくれますから。
ところで、美少年。
エンデの傑作果てしない物語の映画化された「ネバーエンディングストーリー」に、出て来たふたりの少年。
ヒーローはアトレーユ少年ながら、もう一人の主役はその彼の冒険世界を本の中で見ているバスチアン少年でもあります。
淀川氏は、このバスチアン少年を美少年だと判断しています。彼の美意識でしょうか。

はてしない物語/ミヒャエル・エンデ
¥3,003
Amazon.co.jp
モモ―時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にかえしてくれた女の子のふしぎな物語 (岩波少年少女の.../ミヒャエル・エンデ
¥1,785
Amazon.co.jp
ところで、美少年ではなく、美男。・・・・・・・
最後の最後は、やはり、淀川さん愛するアラン・ドロン。(私も昔も今も、大ファンです)。
この映画、「太陽がいっぱい」
実は、主人公のふたりの男性たちは、ホモ・セクシャルだったと、淀川さんが、指摘しています。
たしか、ヨットから、おりてくる時に、普通だと、使用人からおりる筈なので、ここは、映画のルールから判断して、絶対に、アラン・ドロンから先におりるはずはないというのです。
先におりたという、映画ルールを守らないところから見ても、あえて、2人の関係をここに、象徴させている、というわけです。
興味深く、この映画をその後、何回も見た記憶があります。
アラン・ドロンはこんどまた記事を書いてみたいフェボリット男優のひとりです。
彼の歌も良いです。
昔、ダリダと一緒に歌って有名だった、「甘いささやき」。
日本でも、ヒットしましたが、セリーヌ・ディーオンと歌っていた
クリップをたまたま、先日、見つけました。
何歳になっても、彼は、渋くて、素敵な男だなと思いました。・・・・
淀川長治= 良い映画を何回も見ることが大切です。・・・
FIN
◎資料
卒塔婆小町[編集]
1952年(昭和27年)、雑誌『群像』1月号に掲載された。原典の『卒塔婆小町』を翻案した試みや主題について三島は、時空間を超越した「詩のダイメンション」を実現しようとしたとし、「詩人のやうな青春を自分の内にひとまづ殺すところから、九十九歳の小町のやうな不屈な永劫の青春を志す」という自身の「芸術家としての決心の詩的告白」だと説明し[11]、作品の意図については、「現代における観念劇と詩劇とのアマルガム」であるとし、「形而上学的生の権化」の小町と、「現実と共に流転する生の権化」の詩人との対比を語っている[12]。
あらすじ[編集]
夜の公園のモク(煙草の吸殻)拾いの老婆が、ベンチの恋人たちの邪魔をしながら拾ったモクを数えている。それを見ていたほろ酔いの詩人が老婆に声をかける。詩人は、ベンチで抱擁している若いカップルたちを生の高みにいると言うのに対し、老婆は、「あいつらは死んでるんだ」、「生きているのは、あんた、こちらさまだよ」と言う。そのうち老婆は自分が昔、小町と呼ばれた女だと言い、「私を美しいと云った男はみんな死んじまった。だから、今じゃ私はこう考える、私を美しいと云う男は、みんなきっと死ぬんだと」と説明した。笑う詩人に老婆は、80年前、参謀本部の深草少尉が自分の許に通ってきたこと、鹿鳴館の舞台のことを語り出す。
すると、公園は鹿鳴館の舞台に変貌し、舞踏会に招かれた男女が小町の美貌を褒めそやす。詩人(深草少尉)は19歳の令嬢となった美しい小町とワルツを踊り、小町(老婆)の制止も聞かず、「何かをきれいだと思ったら、きれいだと言うさ、たとえ死んでも」と宣言し、「君は美しい」と言ってしまう。そして、「僕は又きっと君に会うだろう、百年もすれば、おんなじところで…」と言い死ぬ。
「もう百年」と老婆が言う。すると、再び舞台が公園のベンチに戻る。死んだ詩人は警官たちに運ばれ、99歳の皺だらけの老婆は、またモクの数を数えはじめる。
関西歌劇団創作オペラ第2回公演
1956年(昭和31年)3月13日 - 14日 大阪・産経会館
作曲:石桁真礼生。指揮;朝比奈隆。演出;武智鉄二。
出演:木村四郎、桂斗伎子、浜田洋子、窪田譲、安則雄馬、伊勢川佳子
※ オペラ化
※ 谷崎潤一郎作『マンドリンを弾く男』と併演。
1970年
1960年代後半から70年代にかけてアメリカでは「性革命」という大きなムーヴメントが起こった。1968年「ワイセツとポルノに関する諮問委員会」が設置され、ポルノ解禁を検討し始めたのである。この諮問委員会は、二年間という時間と200万ドルの費用をかけて、あらゆる種類のポルノの実態と、その社会に及ぼす影響を調査し、さらにポルノの全面解禁した場合の社会におけるインパクトを予測したのである。その研究の結果は、全面的に解禁すべしというのものであり、その報告書を当時のニクソン大統領に提出した。しかし、保守派であったニクソンは、アメリカ社会の伝統を守るために勧告を受け入れることはできないとはねつけた。そのためポルノ全面解禁にはいたらなかったが、当代の有識者たちの書いたレポートは、ポルノ容認論に大きな影響をあたえ、「性革命」の大きな礎となったのである。そのためニューヨーク州で妊娠中絶が合法化され、翌71年には、フロリダ州でそれまで州法で禁じられていたオーラル・セックスを州最高裁が容認するなど、性開放の動きが活性化されたのである[立花1984年a]。
同性愛者たちも「性革命」の動きに呼応して活発化した。1970年、サンフランシスコで開催されたアメリカ精神医学会の総会で、初めて同性愛の病理的扱いに対して意義が申し立てられた。同性愛者とフェミニストの団体が同性愛を病理とみなす医学会に対し、徹底批判をし、会場は大混乱になったのである。その後も同性愛者の学会に対する批判はいたるところで続いたが、もっとも衝撃的な事件は1972年ダラスで起きた。その精神医学会の総会のパネルディスカッションの席で、マスクをした匿名の男性が「私は同性愛者です。そして精神科医です」と公言したのである。この事件は精神科医の中にも同性愛者がいるという事実を明るみにし、また沈黙を保っていた同性愛者の精神科医たちに結束を促したのである[風間1997年]。
1971年、デニス・アルトマンが『同性愛-抑圧と開放』という論文を刊行した。これは1960年代のアフリカ系アメリカ人や女性の公民権運動をヒントにし、同性愛のアイデンティティを創造することに焦点を当てた先駆的な理論であった。彼は、この本の中でこう述べている。
◎資料 鉄道員
『鉄道員』(てつどういん、Il Ferroviere)は、1956年製作のイタリア映画。モノクロ作品。
鉄道機関士アンドレアは、幼い末っ子サンドロの誇りだった。だが、長男マルチェロや長女ジュリアからは、その厳格な性格が嫌われていた。
ある日、アンドレアの運転する列車に若者が投身自殺をする。しかもアンドレアは、そのショックにより赤信号を見すごし、列車の衝突事故を起こしかけ、左遷されてしまう。
アンドレアは、ストライキを計画中だった労働組合に不満を訴えるが、とり上げられることはなく、酒に溺れ始める。
その頃、流産し夫婦仲が悪くなっていたジュリアの不倫が原因でマルチェロは父と口論となり二人とも家を出ていった。
職場ではストライキが決行されたが、アンドレアは機関車を運転し、スト破りをする。
アンドレアは友人達からも孤立し、家にも帰らぬようになる。
末っ子サンドロは酒場をめぐって父を探し出し、以前に父が友人たちとギターを弾いて歌った酒場に連れ出した。
旧友たちは再びアンドレアを温かく迎え入れてくれた。そして、家族との和解の兆しも見えた。
しかし、すでに彼の体は……
男と女の糸 (メス化する男たち)「アメリカン・ビューティ」 「ベニスに死す」「旅情」
「ブリッジ オブ スパイ」「アメリカン・スナイパー」『ステップフォード・ワイフ』
わたしは、ひとつの問いを突きつけるような映画が好きだ。観客に問いかけ、しかも答えは与えないような映画」 クリント・イーストウッド。
自分で考えなさいと!!!
ここ最近。
見る映画は、あいかわらず、まったく非・体系的。
てきとー。
それでも、ひとつひとつ、どの映画も、知的好奇心をくれる。
そして、お前のすんでいる世界はここなのだと、言ってくれる。私が期待している言葉を。
けっこう
パッと見て、わおっ、おもしろかった・・という映画は、ここ最近、なかった。
たまたま、自律神経のおかしい身体が欲しているのだろうか?
わからないが。しょうがない。
「ステップ フォーワード ワイブズ」
ジョアンナはニューヨークでやり手のテレビ・プロデューサーとして働いていたが、過激な番組が元で辞任させられてしまう。すっかり意気消沈した彼女を気遣う夫のウォルターは、家族のためにコネティカット州のステップフォードに移り住むことを提案。ステップフォードは治安もよく、豊かで大変美しい町だったが、そこに住む女性たち(妻たち)は揃いも揃ってグラマーで貞淑で、あまりに完璧な妻であることにジョアンナは気がつく。
実に、実に、不思議な作品。
ドイツ語で見てもこれまた興味深いです。
Die Frauen von Stepford - Das Workout
ニコール・キッドマンがでているだけで、個人的には、満足してしまいます。

西洋的というかキリスト教的というか。
世界では意外に知られていませんが、フェミニズム運動やら、レズビアンやらホモセクシュアルやらの運動やら宣伝で、日本人の大半が、世界はそんなもんだ、アメリカはすすんでいると、誤解しています。
おおよそ、そのような町といえば、ニューヨークくらいなものでしょう。
その他、大きな都市。
私の友達も何人もアメリカやブラジルにもいますが、
田舎の普通のアメリカ人たちは、かなり封建的らしいですよ。
良くも悪くも、男性と女性の役割がはっきりしていて、保守。
逆にいえば、その保守としての男性女性の役割のあまりの強固さに、辟易している人が、
今や増えているのでしょう。
一時、アホなマスゴミがもてはやした「結婚しない生き方」とか、「子どもを産まないスタイル」やら、自由主義社会ですから、誰がなにを言おうといいのですが、匿名で描かれるマスコミ記事は、
誰も責任を取る人はマスゴミにはいませんから。注意しましょう。
我々、普通の人間は、くだらない情報や、テレビの悪い意味での変人達(良い意味での変人は大好きです)は、あくまで、参考程度に聞くべきですね。
昔は、もう亡くなってしまいましたが、小室直樹さんという評論家がおりましたが、彼の変人ぶりは、まさに、尊敬すべき変人ぶりでした。
勉強のしすぎで、??、よく救急車で運ばれたといいますから、やはり心不全で亡くなったのでしょうか。彼の実際の講演を聞いた事がありますが、天才風というか、世俗的なことにはまったく興味がないという良い意味での学問研究の徒でした。
(彼の著作は、今でも、識者の間では本物の古典として定着しております、たしかに、主婦の目線でという意見も大事でしょうが、あまりにも素人ばかり・・・。自由というよりも、好き勝手な意見ばかりで、つまりません。私は、個人的な意見ですが、複眼的に専門家の意見こそが今重要だと思います。)
人には、聖なるものを求めたいという本能もありますから。
時期がくれば、異性が欲しくなり、時期がくれば、赤子ができ、時期がくれば、そうかんがえなければ生きてはいけないという普通の生活の持つ厳しさがわかるようになるだけです。
それだけのことです。
若い時に感情的になって、家出をしようと、変わった事をしようと、「生活だけが、人を錬磨・陶冶する」のですから。
あせる必要はありません。
・・・・・・・・・・
しかし、この映画゜フォーワードワイブズ」では、
その人生における、陶冶は、まったく無視です。
男の地位があまりにも低くなりすぎてきた(もともと、女の方が優秀なんだからこれはしょうがありません。)
だから、女たちを、自分たちつまり男が理想とするようなAndroid的な妻にしていこうといく壮大なる計画を考え始める人がではじめます。・・・・・・・・・・
個人的な意見を書かせてもらえば、いつも書いていますが、名作ブレードランナーの
あの彼女のようなAndroidならば、そんなことはありえませんが、一緒に暮らしてみたいなとも思うこともありますが・・・・・
ここにでてくる、「理想の妻」たちは、まるで、「痴呆のできそこないのロボットたち」のごとくです。
まったく色気もなければ、神秘もなければ、エニグマもなけれは、・・・・・・。
実は、アイラ・レヴィンの本はまだ読んだことがありません。
「ブラジルから来た少年」は持っています。「ローズマリーのあかちゃん」が、あまりにも、強烈すきで、・・・・何か持った作家だということは理解できます。
しかしながら。
すこし、アイデアとしては、このThe Stepford Wives は、幼稚かも。
1975年のキャサリン・ロスのも見てみたいと思います。
クリップ見つけました!!! 1975年版です。
「卒業」以来、彼女の美しさにはまいりました。・・・・・・・
しかしながら、彼女は、「卒業」と「明日に向かって」しか見ていない私ですから偉そうな事は言えませんが、あまり良き作品には恵まれていないような気も・・・
主な出演作品[編集]
公開年邦題
原題役名備考
1965シェナンドー河
Shenandoahアン・アンダーソン
1966歌え!ドミニク
The Singing Nunニコル
1967悪魔のくちづけ
Gamesジェニファー・モンゴメリー
卒業
The Graduateエレイン・ロビンソン
1968ヘルファイター
Hellfightersティシュ・バックマン
1969明日に向って撃て!
Butch Cassidy and the Sundance Kidエッタ・プレース英国アカデミー賞主演女優賞 受賞
夕陽に向って走れ
Tell Them Willie Boy Is Hereローラ
1970愛のさざなみ
Foolsアナイス・アップルトン
1972大捜査
They Only Kill Their Mastersケイト
潮騒
Le hasard et la violenceコンスタンスフランス映画
1975ステップフォードの妻たち
The Stepford Wivesジョアンナ・エバハート
1976続・明日に向って撃て!
Wanted: The Sundance Womanエッタ・プレーステレビ映画
さすらいの航海
Voyage of the Damnedミラゴールデングローブ賞助演女優賞 受賞
1978ベッツィー
The Betsyサリー
スウォーム
The Swarmヘレナ・アンダーソン
レガシー

The Legacyマーガレット・ウォルシュ
1979謎の完全殺人
Murder by Natural Causesアリソン・シンクレアテレビ映画
1980ファイナル・カウントダウン
The Final Countdownローレル・スコット
1981テキサス殺人事件
Murder in Texasアンテレビ映画
1982シークレット・レンズ
Wrong Is Rightサリー・ブレイク
Katharine Ross Tribute
Tony R
シャドー・ライダー
The Shadow Ridersケイト・コネリー/シスター・キャサリンテレビ映画
1986夕陽のストレンジャー
Red Headed Strangerローリー
199115年目の殺意
A Climate for Killingグレース・ヘインズ
2001ドニー・ダーコ
Donnie Darkoリリアン・サーマン
私の好きなニコール・キッドマンとともに出演している、
ボビー役の、ペッド・ミドラーもまたいいですね。
ジャニス・ジョプリンを演じたこの映画の歌。ヒットしました。
日本でも、たくさんの人が歌っていて、いやされます。
たしかに、世界中で、今でも名曲は作られ続けているでしょうが、ジャニスの曲は、
名曲というか、・・・・・あまりにも、魂に響きすぎるので、祈りのようにも聞こえます。
The Stepford Wives is a 1975 American sci-fi horror thriller film based on the 1972 Ira Levin novel of the same name.[3] It was directed by Bryan Forbes with a screenplay by William Goldman, and stars Katharine Ross, Paula Prentiss, Peter Masterson, Nanette Newman, and Tina Louise.
While the film was a moderate success at the time of release, it has grown in stature as a cult film over the years.[4] Building upon the reputation of Levin's novel, the term "Stepford" or "Stepford Wife" has become a popular science fiction concept and several sequels were shot, as well as a remake in 2004 using the same title, but rewritten as a comedy instead of a serious horror/thriller film.[5]
ステップフォード・ワイフ 1975アメリカでのSF ホラー スリラー映画 1972に基づいて、 アイラ・レヴィンの小説同じ名前の 。[3]それは、によって指示されたブライアン・フォーブスと脚本によってウィリアム・ゴールドマン 、と星キャサリン・ロス 、 ポーラ・プレンティス 、 ピーターマスターソン 、 ナネット・ニューマン 、とティナ・ルイーズ 。
フィルムは、リリース時に適度な成功を収めましたが、それはのように身長で成長してきたカルトフィルム年間の。[4]レヴィンの小説の信用に対して建物、用語「ステップフォード」または「ステップフォードの妻は"となっています人気の空想科学小説の概念といくつかの続編を撮影し、同様にしたリメイク同じタイトルを使用して、2004年には、しかし、喜劇の代わりに深刻なホラー/スリラー映画のように書き換える。[5]
『ステップフォード・ワイフ』(The Stepford Wives)は、2004年製作のアメリカ映画である。フランク・オズ監督。
1975年に製作されたハリウッド映画『ステップフォードの妻たち』のリメイク。原作はアイラ・レヴィン。
ジョアンナはニューヨークでやり手のテレビ・プロデューサーとして働いていたが、過激な番組が元で辞任させられてしまう。すっかり意気消沈した彼女を気遣う夫のウォルターは、家族のためにコネティカット州のステップフォードに移り住むことを提案。ステップフォードは治安もよく、豊かで大変美しい町だったが、そこに住む女性たち(妻たち)は揃いも揃ってグラマーで貞淑で、あまりに完璧な妻であることにジョアンナは気がつく。
死の接吻(A Kiss Before Dying, 1952年)
ローズマリーの赤ちゃん(Rosemary's Baby, 1967年)
◎この映画はホラーと言われていますが、
独特の悪魔学のセンスがしゃれていて、不思議と忘れられない名作になっています。
いわゆるキリスト教の国の映画ですから、ある意味道徳映画にはちがいないですが。
サドが、道徳であるように・・・・・・・
この完全なる時代(This Perfect Day, 1970年)
ステップフォードの妻たち(The Stepford Wives, 1972年) - 映画『ステップフォード・ワイフ』原作
ブラジルから来た少年(The Boys from Brazil, 1976年)
ローズマリーの息子(Son of Rosemary, 1997年)
硝子の塔(Sliver, 1991年)
◎この硝子の塔も、印象強いです。
この現代であれば、どこにでもあるプライバシーの侵害の映画なのですが、
1991年ですから、25年前に予告されていたというわけですね。
ここでは、敬愛する淀川長治さんに、語ってもらいましょう。
ひとつの映画が、何倍も何倍も、面白くなる筈です。
Deathtrapは、まだ見ていませんが、ここに記録しておきます。
「アメリカン・スナイパー」
クリント・イーストウッドについては、たくさん描きたいことがありすぎます。
いつか、彼についてのこれ迄見た映画をまとめたいといつも思っていますが、
とにかく・・・・・・・・・気がついたら、疲れ果てて、寝ています。・・・駄目ですね。
映画をひとつの政治的偏見で見るのはもったいない。
ここには、実に多くの戦争そのもののイメージがあり、
途中で何回も、見るのを止めながら見た。涙も出た。
「アメリカン・スナイパー」
戦争を賛美せず、かといって、自国を襲うテロリスト達に立ち向かうカレルの勇気を
無視するわけにもいかない。
しかしながら。
結局のところは、歴史のなかで、人類は、こうやって、自分たちの正義=神のために、相手達の異端の神=不正義、と、戦ってきている。
まさに、人類がかかえた悲惨な業である。
この映画が誰でもが知っているように、実話であることもまた、作品を重くしている。
アメリカでは、賛否両論がくりひろげられたという。当然のことだろう。
よく、戦時中の人達は国に騙されて洗脳させてうんぬんと、・・・偉そうに評論する輩がいますが、このような連中にかぎって、上目視線で、自分たちの意見にそぐわない人達を排除しようとするのは、左巻き思想の特異技。
家族は家族の利益のために、会社は会社の利益のために、国は国の国益のために、
必死に、一丸となって、生き延びて行く、・・・・・・・そんなあたりまえのことが、わからない人が、多いですね。
この映画を見ていると、ほんとうに「歴史が泣いている」という意味が、切実に、感じられます。
(そして、命が一番大切と言っている人、たとえば学校の先生などに、かぎって、「いじめ」の現実に鈍感というのは不思議です。
「いじめ」問題がおこって、少年少女が犠牲になると、例のごとく、アホな教育委員会や校長が、その無表情の仮面のような顔で、お詫びをしつづける。
命が一番大切です。・・・・・そればかり言う人。
その人にとっての、命は、自分の命だけが大切であって、他人の命には無関心なのです。)
理想論や、きれいごとなどは、言葉だけだったら誰にでも言えることです。
自分以外の人達のために、ふんばれる。
私はそんな人になりたいといつも考えます。
三島由紀夫は、そのようにして、「命以上に大切なものがある」と言って、切腹しました。
飽食ざんまいの、惰眠を貪っている現代人に、彼を、批判する権利などありません。・・・・
よく人間を性善説とか、性悪説とか、簡単にわけることが一時、はやりましたが、人生そんなにシンプルではないでしょう。
この善と悪はともに人の心の奥の奥に誰にでもひそんでいるものです。
問題は、そのパンドラの箱の重要性を考えもせずに、無意識に悪の蝶を好き放題に飛ばしてみたりする人がいることですね。
また逆に、この箱のなかにあるsomthingを忍耐しながら、コントロールしようとする人。
そんなこむずかしい問題を「人間の建設」をよみながら、そこにでてくる「無明」という言葉も連想しながら、かんがえていた今日このごろ。
体調はあまり良くないのですが、
札幌に家人と行く機会があり、大好きなトム・ハンクスの「ブリッジ・オブ・スパイ」を
大きな画面で、見るチャンスがありました。
冷戦時、人々は核戦争の恐怖や、まだ記憶が生々しい世界大戦が再び来るのではないかという恐怖におびえていた。そのため、ドノバンがもし失敗すれば世界が再び戦火に包まれると考える者や、彼の行動を阻止しようとする者が現れる。しかし、彼は自らの信念を曲げず、苦悩しながらも、戦争の可能性を取り除き、人命を救助するために懸命に行動する。彼に与えられた交渉の舞台は、ドイツのベルリンにあるグリーニカー橋。彼は交渉を成立させ、戦争の危機を回避できるのか?
本作は、これまでのスピルバーグ作品同様、全編が35ミリフィルムで撮影されており、予告編でも陰影に富んだ重厚な映像も堪能できる。
しかも。
あの冷戦時代でしたから。
わたしなぞも、大学時代から、アメリカとソ連が核戦争を起こすということが、今から見ると想像もできないくらいに、現実的に思えた時代でしたから、いつも、暗い気持ちで「核で終わる地球の最後」の日のことをよく考えていました。
淀川長治さんが、スピルバーグくらいの力があるのであれば、獲ろうと思えばアカデミー賞は獲れるんだけども、それが見え見えだから、この映画は嫌いだと言っていた「シンドラーズリスト」を私は連想しました。(実際にアカデミー賞を初めて彼はとりました。)
冷戦時代で思い出す映画といえば・・・・・・・
『ファントム/開戦前夜』(ファントムかいせんぜんや、Phantom)は2013年のアメリカ合衆国の戦争映画。 東西冷戦下にあった1968年に、ソ連(当時)の潜水艦K-129(英語版)が通常の作戦海域を大きく逸脱した末にハワイ近海で謎の撃沈を遂げた事件を題材にしている
あとは、死を覚悟して、放射能を浴びる映画を描く軍人の覚悟を描いたこの映画をいつも思い出します。
これは傑作でしょう。
「K19」 ハリソンフォードは実に軍服が似合います。
米ソ冷戦下、ソ連の原子力潜水艦K-19は航行実験において、突然原子炉の冷却装置に故障をきたした。原子炉のメルトダウンも考えられた危機的状況に対して立ち向かう艦長(フォード)と放射能の危険と隣り合わせで修理に奮闘する搭乗員の活躍を描く。
トム・ハンクス、いいですね。
資料を見ると、
映画のプロモーションでは数回来日しており、近年では『ポーラー・エクスプレス』、『ターミナル』、『ダ・ヴィンチ・コード』プロモーションで、それぞれジャン・レノやロバート・ゼメキス監督らと共に来日している。『ポーラー・エクスプレス』の来日でインタビューを受けた際には、タイプライター集めに凝っていると語っていた。また、自身が監督も務めた『すべてをあなたに』の来日の際には、出演者らと共に日本テレビ系の歌番組『THE夜もヒッパレ』にゲスト出演。ハンクスはその際に歌も披露した。2009年5月に『天使と悪魔』のプロモーションのために、プロデューサーのブライアン・グレイザー、監督のロン・ハワード、そして共演のアイェレット・ゾラーらと来日した際には、東京ドームで行われた巨人対中日戦の始球式に登場した。そして、監督である原辰徳との対面も果たした。
私生活
サマンサ・ルイスとの間に1977年11月、現在俳優として活躍するコリン・ハンクス誕生。翌年、サマンサと結婚[7]。1982年、長女エリザベス誕生[8][9]。1987年、離婚。1988年、リタ・ウィルソンと再婚。2人の子供をもうける。
エイブラハム・リンカーンと遠縁である(リンカーンの母親ナンシー・ハンクス(英語版)の曾祖父の兄弟がトム・ハンクスの先祖、8代前)[10]。
民主党を支持しており、2008年の大統領選の際にはバラク・オバマを支持した[11]。
『幸せの教室』で共演しているジュリア・ロバーツとは長年の友人で、家族ぐるみの付き合いだという
「Bridge of Spies」
たしかに、これは、恋人たちと一緒に、わいわい、楽しむ映画ではないけれども、
無名のひとりの弁護士が、その想像力を駆使して、あの冷戦時代に起こりうる様々なる
生涯を、不屈の闘志というか、フレキシブルな思考によって、大胆なる人質の交換を成功させるというたしか実話である。
「ノーカントリー」で、アカデミー賞を獲得した、さすが、ジョエル&イーサン・コーエンの脚本だけあって、
レヴューを見ても、地味な映画ではあるが、
高い評価がめだって、嬉しくなった。
参考資料
「ノーカントリー」
2013/07/11 に公開
"荒野で狩をしていたベトナム帰還兵のモ は、偶然ギャングたちの死体と麻薬絡みの大金200万ドルを発見。 その金を奪ったモスは逃走するが、ギャングに雇われた殺し屋シガーは、邪魔者を次々と殺しながら執拗に彼の行方を追う。事件の発覚後、保安官のベルは二人の行方を探るが、彼らの運命は予測もしない衝撃の結末を迎える。
「ブリッジ・オブ・スパイ」ひさびさに感動した。淀川長治さんなら、どう、解説するだろうか。
それを想像しながら、寝るとしましょう。
「ウェルカム・トラブル!!!! 苦労よ、来い!! 」
「苦労がない人は駄目だよ・・・」
淀川長治
トム・ハンクスの演技の重厚さ・味、そんなものを見ているうちに、淀川さんの言葉を連想した。
FIN
◎資料には、全米長寿バラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』や、『スプラッシュ』『メイフィールドの怪人たち』『ビッグ』といった軽妙なコメディ映画を得意とする若手コメディアンとして活躍していた、とある。
カリフォルニア州コンコード生まれ。父親は料理人、母親は病院職員。両親は1960年代に離婚し、トムは兄ラリー(現在は昆虫学者)と姉サンドラ(現在は著述家)と共に父親の元で育つ。末っ子の弟ジムは母親の元で育った。
カリフォルニア州ヘイワードのChabot Collegeで演劇を学んだ後、カリフォルニア州立大学サクラメント校に編入。
1979年にニューヨークに移り、翌年『血ぬられた花嫁』で映画デビュー
とあるので、日本のたけし、ではないけれど、コメディアンとしての、独特のユーモラスな、それでいて、奥のある懐を感じさせる情愛をもかんじさせる良き俳優だと思う。
貴重な彼のこの映画についての、インタヴュークリップがありすので、ここにコレクションしておきます。
「ブリッジ・オブ・スパイ」インタヴュークリップ
・・・・・・・・・・・・
スティーヴン・スピルバーグ監督、マット・チャーマン(英語版)及びコーエン兄弟脚本による2015年のアメリカ合衆国の歴史・伝記・ドラマ(英語版)・政治(英語版)・アクション・戦争・スパイ(英語版)・スリラー映画である。出演はトム・ハンクス、マーク・ライランス(英語版)、エイミー・ライアン、アラン・アルダらであり、U-2撃墜事件でソ連の捕虜となったフランシス・ゲーリー・パワーズの解放のために動く弁護士のジェームス・ドノバン(ハンクス)が中心に描かれる[1]。
題名の『ブリッジ・オブ・スパイ』とはスパイ交換が行われたグリーニッケ橋を指す。
撮影は『St. James Place』というワーキングタイトルで2014年9月8日よりニューヨーク市ブルックリン区で始まった。北アメリカではタッチストーン・ピクチャーズ、それ以外では20世紀フォックスの配給により公開される
◎ニコール・キッドマン
生い立ち[編集]
アメリカ系オーストラリア人の両親のもとにハワイ州ホノルルで生まれたため、アメリカ合衆国とオーストラリアの二重国籍である。4歳でオーストラリア・シドニーに戻った。3歳下の妹にアントニアがおり、アントニアはオーストラリアでテレビ番組のプレゼンターをしている。
4歳からバレエを習い始め、Australian Theatre for Young Peopleで発声や演劇史を学ぶようになる。
キャリア[編集]
カンヌ国際映画祭にて(2001年)
15歳からテレビやミュージック・ビデオなどに出演、映画にも出るようになり、オーストラリア映画で実績を積む。1988年に出演した『デッド・カーム/戦慄の航海』を偶然目にしたトム・クルーズに招かれてハリウッド入りし、『デイズ・オブ・サンダー』で共演、1990年に結婚した。
ハリウッド進出当時は、当時の夫であり、ハリウッド進出に導いたトム・クルーズ夫人としての側面が強く、いわゆる型どおりの美人女優として平凡なキャリアに甘んじた。しかし2001年にトム・クルーズとの離婚を機に、充実したキャリアを開花させ、以降、アメリカを代表する演技派女優として変身を遂げた。キッドマン自身離婚後、「いままでは結婚生活というものが、私にとって一番優先することだった。でも、いまの私には、仕事と子供たちしか残されていない。独身になったから、女優として成長できる時期だ、というふうには思わないけれど、確かに、演じたいという情熱は結婚していたときよりも強くなった。」と語っている[1]。
2001年公開の『ムーラン・ルージュ』でゴールデングローブ賞(ミュージカル・コメディ部門)を受賞。2003年公開の『めぐりあう時間たち』では、特殊メークによる付け鼻で完全に自らの容姿を隠し、ヴァージニア・ウルフを演じきり、アカデミー主演女優賞やゴールデングローブ賞 主演女優賞(ドラマ部門)などを受賞した。
2004年には日本をはじめ世界各国で放映されたシャネルの香水「No.5」のテレビコマーシャル(監督:バズ・ラーマン)に出演し、120秒(一部の国では240秒)という異例の長さのCMに注目が集まった。また、出演料も破格であった。現在はオメガの顔として広告に出演している。
映画1作品の出演料が高額なことで知られており、2006年には「最も出演料の高い女優1位」となる[2]。
2007年1月、アメリカの経済誌『フォーブス』がエンターテイメント界で活躍する女性で資産の多い女性トップ20を発表し、ニコールは総資産72億円で18位にランクインした。
2008年の『フォーブス』誌では高額なギャラ相応の興行収入が稼げないことから、「コストパフォーマンスの悪い俳優1位」になってしまった[3]。
2010年の映画『ラビット・ホール』の演技によって再び評価を高め、アカデミー主演女優賞をはじめとする多くの賞にノミネートされた。
2012年のテレビ映画『私が愛したヘミングウェイ』では、文豪ヘミングウェイの3番目の妻マーサ・ゲルホーンを演じた。この演技が絶賛され、プライムタイム・エミー賞をはじめ数々の賞にノミネートされた[4]。
2015年、ロンドンのウエストエンドで舞台『Photograph 51』に主演し、「Evening Standard」紙の演劇賞で最優秀女優賞を受賞した[5]。
イタリア映画 「ひまわり」 フェリーニ「道」 「カザノバ」・・モニカ・ベルッチ を見て
イタリア映画が好きです。
最近では、たしか、昨日あたりに、ソフィア・ローレンが、高松宮殿下記念世界文化賞」をとりましたね。これはイタリア映画好きにとっては、しみじみと感じることがあります。
この「ひまわり」の素晴らしいこと!!!!!!
戦時中にひきさかれた、恋人達が、その後、夫を探し出すと、すでに、別の女性と暮らしている・・・
しかしながら、ソフィアは、子どもには、アントニオとつけて・・・、涙涙。
この音楽がまた、素晴らしく印象的です。
ソフィア・ローレンがまた迫真の演技です。まさに、イタリアの最高の女優だと思います。
彼女いわく・・・
「実は、私は日本に行くと、まるでわが家にいるような気がするんです。それくらい居心地がいいわ。皆、いい人たちだから。私は日本人が大好き。本当にとても素晴らしい人々です。独特の座り方で食事をしたり、お茶をいただいたりするのが好きだし、日本の方たちと言葉を交わすのもたのしいです。そして、日本ではイタリア映画がとても知られていますね。私の映画についても大勢の人が話していました。たとえばマルチェロ・マストロヤンニとロシアで撮った映画など、ずっと泣き通しの女性がいて、本当に素晴らしかったです。(注 おそらくこの「ひまわり」だと思われます。)ですから、今回の受賞のためにまた日本を訪れることができて、とても、とてもうれしいです。日本は、本当にわが家のように感じられる国ですから」
そんわけで、このところ、イタリア映画について考えています。
たとえば、「カザノバ」。
淀川長治さんは、いつも言っていました。
「映画ばかり見ていてはダメ」
「文学や、音楽や、美術をよく勉強すると、映画の素晴らしさが何倍にもなる」
ガザノヴァについての三島由紀夫氏の言葉なんかも、思い出しながら・・・
彼の魂の孤独。悲壮。ぎりぎりの死のところでなんとか間に合った創作。
生涯に数千人もの女性を愛した男だったが、常に魂は孤独。
余白の心の道を歩みながらも、あらたな女性に夢と希望をつなぎながら。・・・・
( 違うジャンルではありますが、フィギア。
フィギアは、音楽が演技とからみあうところがすごく良いです。特に、「道」のような古い映画を、高橋選手が選んで、スケートをしたということに、時代や年令を超えた、映画芸術の力を感じました。)
ところで。この昔の映画ですが。
イタリア映画には、他にも、たくさん傑作がありますが、
「道」「鉄道員」「アポロンの地獄」・・・
どれも素晴らしきすでに古典的名作といわれています。
特に、このやはりフェリーニの「道」
サーカスの男と気がつくと旅をしながら無為の生活をおくっている少女。
少し頭が悪いのかもしれない、そんな無垢の彼女にしだいにひかれていく・・・男。
最後のシーンが素晴らしい。
泣きながら彼女をさがしつづける・・・・・・・・・。
イタリア映画には、かつての日本映画のなかに遺伝子的につながる「あはれ」の美というか、余情の美しさがあります。
そして、進化しつづけるイタリア映画。
そして、この「リメンバー・ミー」。今年の映画ではありませんが、考えさせられる素敵なシネマです。
世界で最高の美女と噂されるモニカがヒロインです。
イタリア。
ユーロ圏では、けっこうな優等生ぶりを、ギリシアやスペインと違って見せてくれています。
イタリアの国民の柔軟性、明るさ、美的センスの良さ、そんなものが国の経済を比較的強くしているのでしょうか。
たしかに、「祈って食べて」の映画でも、プロヴァンスの関連のたくさんの映画でも、
アメリカ人にとっての、イタリアは、人の良い、神経症などのない、おおらかで、自然に恵まれた、美食とおしゃれと本能のままに生きれる国なのかもしれませんね。このヒントは、
「マイ・インターン」にも書きましたが。
最後には、イタリアの現代の作品。「リメンバー・ミー」
◎テーマ 映画「リメンバー・ミー」を見て・こんな感想を持ちました。
(喜怒哀楽 と 冷静 の間に)
喜んだり、怒ったり、悲しんだり、うわーっと喜ぶ・・・つまり、自分の魂の底から発せられる感情そのものに乗っかって、この世に発信する。
当然、日本では、まわりの人からは、うるさがれることが多いと思いますが。
私の知る限り、外国人の方はこの表現が実に激しく、そして、まわりの人達も、あっけらかんとして、それを受け止めてけらけらしていますね。
こんどは自分が受け止めてもらえるからでしょうか。
ブラジルに嫁に行ったかつての友人は、ブラジルの子供たちが自分の子供をまきこんでくれて、非常にあたたかく遊んでくれるということをメールで書いていました。
なにかわかる気がしますね。
観察したり、自分がどう相手に見えるかとか、考えすぎずに、なかに溶け込んでゆくそんな生活習慣。
いいもんです。
でも、日本では、無理でしょうが。
ただ、日本人も、喜怒哀楽を出したくないのではなく、日本人独特の感性、つまり、シャイな他人からの視線を気にしすぎるとか、めだちすぎる連中にたいしての少しいじわるな無視なんかもあるのかもしれません。
心の底では、だれしも、子供の心は持っている筈。
司馬遼太郎氏も、宮崎駿との対談のなかで、「心の中に子供こころが残っていない人はダメだ」ともどこかで書いていましたね。
だから、日本人は、宴会とか、居酒屋では、なんでもかんでも言い合って、そこにいる連中がひとつの輪になるように、気持ちを打ち解け合わせることを一番にするのかもしれません。
イタリア映画の「リメンバーミー」。
自分の嫉妬心をだしまくる男女。喜怒哀楽のなかで、闘っているような映画でしたね。
すごいです。
それがひとつの文化になりえる、ということは。
ただ、日本人には日本人の素晴らしいところがあるはず。
(イタリアのサッカー。
ゴール・キーパーのあの感情の塊のような闘士。
イエローカードまでもらってしまうほどまでに、熱い気持ちをぶつけてきますね。
そんな選手とはまったく対照的に、日本のゴールキーパー、始終冷静に、自分の気持ちをじっと押さえつけたかのような表情。
昔、日本に来たあるjazzピアニスト。
日本人の観客が持つ不思議な沈黙のような感覚、について語っていました。
外国の観客とはまったく違うと言っていましたね。
そして、また、最近は日本の観客がすこしずつ、変化してきたとも。
はたして、それが良いのか悪いかの、わかりませんが。)
私はそんなわけで、あこがれつつも、何かのライブ会場へ行っても、立ち上がって踊ったり、サッカーの応援サポーターのように顔に何かを塗り付けて、ずっと、声を出し続けることはできません。
それで、良いのだと思っております。自然体で、いつでもどこでも。
リメンバー・ミー [DVD]/モニカ・ベルッチ,ファブリッツィオ・ベンティヴォリオ,ラウラ・モランテ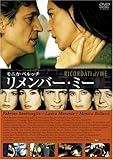
¥3,990
Amazon.co.jp
■イタリア映画ジャーナリスト協会賞3部門受賞!
モニカ・ベルッチは元より、彼女と関係となるカルロ役には、
ヴェネチア国際映画祭にて男優賞を受賞したこともあるファブリッツオ・ベンティヴァリオ、
そしてその妻ジュリア役には、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールに輝いた『息子の部屋』での好演が光ったラウラ・モランテと、
監督を始め、イタリア映画界最高のスタッフとキャストが集結!
現代の家族が抱える問題をそれぞれの愛にまつわる物語を絡ませながら見事に演出!
◎資料「道」
主題曲を始めとする本作の音楽は、フェデリコ・フェリーニ監督作品を数多く手掛けたニーノ・ロータが作曲した。
日本語歌詞が付き、本作が日本で公開された1957年(昭和32年)の第8回NHK紅白歌合戦で中原美紗緒が歌っている(『ジェルソミーナ』として)。
2010年のバンクーバー冬季オリンピックでフィギュアスケート男子シングルの高橋大輔選手がこの曲を採用し、同種目日本人選手初のメダリスト(銅メダル)になった。
Brahms : Double Concerto/Anne-Sophie Mutter, Max
PR: 地震に備えて!住宅・建築物の耐震化のススメ-政府広報
入れ墨と献血
サッカー界のスーパースター、クリスティアーノ・ロナウド。彼の体には、他の多くのサッカー選手が入れているようなタトゥーがありません。
SOCCER DAILYさん (@soccernewtvp)が紹介したその理由が反響を呼んでいます。
レアル・マドリードのエースC・ロナウドは子供達のために定期的に献血を行う為、体には刺青を入れないと決めている
カッコいいと思う人RT
2016年6月6日 22:56
7,249 7,249件のリツイート 8,847 いいね8,847件
多くの国では、主に感染症を予防するため、新しく刺青を入れた人は一定の期間(日本の場合は6ヶ月間)、献血への参加ができないよう決まりが設けられています。
過去には、病気の子供のために多額の寄付を行ったことも報じられたロナウド。米YAHOO! SPORTSの記事によると、彼は年に2回の献血を行っており、あるインタビューに対して「僕はたびたび献血に行くから、刺青をしないんだ」と答えたと報じられています。
フィールド上のスーパープレイのみならず、こうした積極的な慈善活動を通しても、人々にたくさんの夢と憧れを与えてくれるロナウド。自らの信念を貫き、他者を思う彼の姿勢に、強く心を打たれます。
PR: 毛穴ごっそり体験が500円!
♪ 青春の坂道 / 岡田奈々
【HD】 ザ・リリーズ/好きよキャプテン (1975年14歳当時)
「図書館戦争」「オールユーニードイズキル「マイインターン」
札幌のJRシネマ館。
最近ここで、時間をすごすのが楽しい。
「マイ・インターン」「100年の恋」と、楽しめたので、期待して、この「図書館戦争」を見たが、がっかり。
・・・・・・・
映画「図書館戦争 THE LAST MISSION」予告動画
普通のサラリーマンや、OLさんならば、2000円も出してこの映画を見たら、きっと、もったいないことをしたと思うに違いない。
テレビで見たり、せいぜい、ビデオレンタル店で、100円で見るのならば、ソンはないと思うけれども。
私は、基本、淀川長治さんではないけれども、どんなつまらない作品にでも、ひとつやふたつは良いところがあると思うし、この映画も、もちろん、おおっというシーンは数カ所はあるけれども、そして、作者の、有川浩さんのファンが多いらしいので、彼らだったら、楽しめるのだろうね。
◎私は本の虫なので、図書館の内部のさまざまなる映像や、図書館における規約みたいなものは新鮮。
◎本物の自衛隊の全面的な協力を得ての撮影なのでこれまた、興味深いシーンがたくさんあった。
しかし・・・・・「表現の自由=本を読む自由」を死守するというのは理解できるし、賛同するけれども。
・・・・・・・
「図書館戦争」の元ネタ??かどうかは、わからないが、この映画が連想された。
ただ、こちらは、ブラッドベリの大傑作。 (個人的にだが)
本が燃える温度は、(本の素材である)紙が燃え始める温度(華氏451度≒摂氏233度)なのだけども、それを題材にした映画を若い頃に、見た。
尊敬するブラッドベルの「華氏451度」という作品である。
華氏451度 ハヤカワ文庫SF/早川書房
¥価格不明
Amazon.co.jp
映画もつくられた。
この「華氏451度」という作品、小説や映画のなかでは、要は、テレビなどに脳細胞をやられて、単純な思考しかできなくなった人類の滅亡と、本による救済を描く。
この作品の映画化は、まだ他にもあって、『リベリオン』 - カート・ウィマー監督のアメリカ映画作品で、本作を原案とする、思考(感情)統制され、書物が焚書される未来を描くSF。
少数の人達が、燃やされる本のなかから、数冊の本を大切に守っていくわけだが、この「図書館戦争」の作者もまた、おそらく、見ていることだろう。
有川浩。
ファンも多そうで、この作品には、一作目があるらしい。
私はそれは見ていない。
かなりのアンケートで、男性と女性の比率は、女性が圧倒的に高いという。
しかしながら。
期待して、見たけれども、どうもはいれこめなかった。感情移入がしずらい映画だ。
というか。
「フルメタル・ジャケット」や、「プライベート・ライアン」、それに、最近ならば、「フューリー」や、「アメリカン・スナイパー」などの、戦争ものの、傑作名作を見ていると、
戦争場面が、戦争にまったく見えない。
この「プライベートライアン」と比較するのはかわいそうだが、しかし。
この映画のなかの、戦いは、どう見ても、
戦争ごっこ。
「フューリー」など、ほんとうの戦争そのものを描いている。
しかも、このヒロインの、榮倉奈々という女の子。(??まちがいかな )
天然というか、大胆なのは魅力だけれども、まったく、この映画では、浮いています。
なんで、本を命をかけて守るのかということを、深くほりさげて、キャラづけされていないので、まったく、戦争ごっこにしか見えず。
なぜ、命をかけて本を守るのかということが、丁寧に描かれていないからだろう。
これは本人の責任というよりも、シナリオが悪いんだと思う。
彼女が、可哀想。
その分、岡田准一は、良い意味で、ダスティ・ホフマン風な味があると思った。
榮倉奈々が、背が高いんだから、彼の背の低さを強調して、役づくりをしても、
またまた、原作とは違う味の、作品になった可能性があるだろうれども、もう遅し。
(映画と原作小説は、まったくの別物)
2019年の日本という設定らしいが、考証がきちんとされていないので、どうみても、今の現代の日本にしか見えない。
そこで、図書館の中だけで、内乱のようなことがあり、銃撃戦があり、人が死ぬ。
どう考えてもありえない。
ちょっと考えたのだが、どうせ、原作を広げて、映画をつくるのならば、中国共産党に支配された後の日本の生活を描けばよかったのではなかろうか???
◎中国では、過激なビデオを見たものは死刑になると言う。
◎とうぜん、共産党の思想に叛逆するすべての思想や、書物、集会などは禁止され、その著者などは、逮捕されて、拉致監禁され、殺されたりもする。共産党という思想を信じている立場からすると、「俺たちが正しい」から、そのようなことをするわけだが、日本のような民主国家からするとありえない。
◎中世界に自国を広めて行くという中華思想にもとづき、その他の国を中国の属国にせんと、企んでいる可能性がある。
◎人類の理想を共産主義とはしながらも、結局はマルクス主義を都合のよいように、置き換えただけのシステムの国家であり、そこでは、賄賂と、さぼり、拝金主義が、蔓延している。
というわけで、日本が、自国を自分たちで守ることも忘れて、気がつけば、中国の属国になっており、メディアはすべて、中国語、純粋日本人たちは、地下で、焚書にされなかった数冊の日本語の本を持ち寄って、日本語でコミュニケートする集団をつくりあげていく。
これは私の勝手な妄想空想だけれども、こちらの方が、自衛隊のかなりの応援もあっていろいろな場面の撮影がスムーズにいったと言われているので、自衛隊の方にも喜んでもらえると思う。
この映画のなかで、ひとつだけ、気に入った言葉は、
「正しいことしか言わない人間だけしかいないの世界は、おそろしい」という言葉。
自由社会。
わたしたちが、守るべきは、どんな議論にせよ、今の日本やアメリカや世界の民主国家のなかでは、どんなことでも言える、それが許されているわけだし、その世界に、マンネリしてのほほんと住むあまりに、その自由というものの大切さが、わからなくなる、麻痺してしまうということが、問題なのだろうと思う。
(ただ、実際には、差別用語を使えば、筒井康隆に団体から文句がくる。このあたりの表現の自由の問題はかなりむずかしいが。ブログだって、書けないこともある。書く自由には責任もまた必須なのだ。)
狂信的な連中が自分の思想だけを他人や国民に押し付けて、自分たち以外の考えやらメディアを叩き潰そうとする社会、それがほんとうは、怖いのだと思う。
以前、どこかの図書館であった実話。
そこに勤める女子が、たしか、渡部昇一氏らの本だけを、ひっぱりだして、捨てた=焚書にした、という事件である。
(この図書館戦争の映画とはまったく逆のバージョンですね。表現の自由、読書の自由を、図書館のスタッフが、制限するという前代未聞の事件・・・)
つまり、自分の意見や、思想だけが、正しく、それに対立する意見などは、認めない、耳を塞ぐ連中ですね。こういう「自分だけが正しい」と信じている人たちほど、つきあいずらい人種はいませんよ。ユーモアセンスがなく、いつも感情的で、変に純粋まっすぐ君なんですからね。
こまったもんです。
●●新聞やら、テレビのおおかたのメデイアなども、最近はその傾向があると思う。
ひとつの議題に対して、たとえば、安保法案・・・これに、反対意見だけのコメンテーターを集めて、放映する。
まさに、この「図書館戦争」のなかで手塚がやっている、洗脳そのものですね。
真の民放メディアであれば、反対意見と、賛成意見と両方あるはずなので、両方の専門家を呼んで、カメラの前で、議論させる。
そのときに、司会者はよけいなことを言わずに、ふたりの、言いたいことを徹底的に言わせることに集中する。
そして、最後に、この番組を見て、見ている民衆、わたしたちが、自分の頭で、判断する。これが、民主主義でしょう。
昨日の新聞でも、NHKに、「なんで片方の意見だけの映像を流し続けるのか」という、投書が、驚くほど届いているという記事がありましたが、テレビの洗脳は今にはじまったことではありませんから、気をつけるべきことのひとつでしょう。
「華氏450度」で描かれているように、本を読まなくなり、テレビだけで、ものを考えるようになった未来の人類達は、もはや単純な思考しかできなくなり、複雑なるこの現実の世界を、変革していこうとは考えなくなってしまう。
テレビに洗脳され、テレビに操られる人達が、増えてくる未来は恐ろしい。(今の若い人は、あまりテレビを見ないし、ネットもあるので、それが救いかもしれない。)
フランスには、シャルル・ドゴールのこんなジョークがある。
「フランスには246ものチーズがあるんだ、こんな国を統治できると思うかね」
つまり、人をまとめるのは、この21世紀、ネットの普及などで、どうしようもないくらいに個性が複雑かして、まさに、一人十色になってきている。
そんな世界を、民主主義は、やはり、多数決という原理で、まとめるのではないだろうか。
民主国家では、さまざまなる意見があり、議論があり、文句があり、批判があり、喧嘩や軋轢もある、それが、当たり前なことなのだろう。
つまり、ああだこうだ、といいながら、まとまらないこの世界。それを、ひとつの方向にうまく収斂させていくのが、政治家の仕事だし、政治家に一番求められているのは、リーダーシップだ。
この「表現の自由」という問題は大変に難しい問題だと思う。
最近では、週刊文集でしたか、春画を載せたということで、騒がれましたが、呉さんによれば、週刊文集だから問題になったけど、ポストだったらまったく問題にならなかったというようなことを書いていましたね。
北欧などは、性の解放などで、有名ですが、子どもたちの、通行するようなところには、アダルト本を買えるような販売機などは絶対に置きません。
性については、解放していても、子ども達には、普通の日々を送らせて学業に専念できるようにしてあるわけですね。
個人的には、「ワイセツ」などという言葉で、国が作品や書物を禁書にするというのは納得はできません。
渋沢竜彦氏の、「サド」シリーズでも、あれが「ワイセツ」などという裁判官の頭の中をしらべてみたくなります。ソドム百二十日 (河出文庫)/河出書房新社
¥821
Amazon.co.jp
しかしながら。
児童ポルノは違うでしょう。
メディアに対する自由侵害とか騒いでいる人がいましたが、アホです。
無垢な子どもを、大人が勝手にポルノ作品に、参加させるような、アダルトの世界は表現の自由ではありません。
言い尽くされた言葉ですが、自由と責任は、必須の組み合わせ。
子ども達をのびのびと、彼らの内在化された才能をのばすために、大人はいるわけですから、
小さな頃から、それをひとつの枠のなかに、押し込めようとする自由などはありません。
というわけで。
この、「図書館戦争」。有川浩さんや、岡田准一さん、
榮倉奈々さんのファンの人たちだけが、楽しめる映画かな。
映画は、つくりあげるために大変な額の金がかかりますから、原作をはしょってしまうことはあるのかもしれませんが、それにしても、この戦争ごっこのような、迫力のない、画面にはがっかりしました。
(個人的には、映画がつまらなかった分、日本が他国の属国になりさがった時を想定し、日本が日本でありつづけるために、過去の日本人たちの歴史に学びながら、日本語を大切に守りたいとますます、考えたことがプラスだったかな)
次の映画は、「マイインターン」
(ネタバレありですが、勝手な感想を書かせていただきます)
12時に、札幌に着いて、いつものようにきれいなJRシネマ館に行く。最近の楽しみのひとつ。
時間はまったく考えずに、行き当たりばったりを楽しむので、その日は、「マイ・インターン」を観る。
この映画は、「プラダを着た悪魔」の続編と聞いてはいたけれども、もうすっかり以前の作品のことは忘れていた。
いつもそうだ、私は、偏見を持たないで作品を観たいので、パンフも、予告編も、何も観ないで、それで良いと思っている。そのかわりに、見終わると、けっこう調べて資料は集めるかも。
(ただ、この映画は、以前観た、「進撃の巨人」やら、「100年の恋」やら、作品上映の前にかならず、この予告編を繰り返しやるので、何回も観ていたが・・・・)
予告編を観ればわかるけれども、とにかく、女性であればわくわくするような、ファッションサイトの職場。実際にこんな会社があるかどうかはともかく、さすがに、ニューヨークという雰囲気があり、楽しい。
そこに、インターンとして、70歳のロバートデニーロが入社してくるわけだから、おもしろくない筈はないと思う。
ただ、予告編からの印象は、あてにならない。
この映画は、予告編よりも作品そのものは、何倍もおもしろい。
おしゃれな女性がわくわくするこの映画の秘密はそれとして、この映画は、今や、四人に一人と言われる高年齢のシルバー世代の観客にも、わくわくするような仕掛けがしてあると思う。
じっさいに、映画の観客も、平日ということもあるけれども、半分くらいが、シルバー世代。あとは、恋人どうしみたいな観客がめだった。
アメリカは、誰でもが知っているけれども、歴史が浅い国。たかが、数百年くらいで、世界のグローバリニズムにのし上がった国。
今や、いろいろな問題を抱えて、喘いでいるけれども、それでもなかなかの国。
そんな彼らが憧れるのは、やはり、日本やイタリアのような歴史の長い国だと思う。
この映画の中にも、日本語が多用されていて楽しい。
「幸福のレシピ」という映画があって、私は大好きだったけれども、完璧主義のシェフがひとりで店をきりもりしていたが、彼女が、人生の困難にぶつかったときに、ひとりの男性シェフが入ってくるという筋書きだったと思うけど、彼は、イタリア人的な雰囲気を持っていたと思う。
この「マイリターン」のロバートデニーロの役柄も、イタリア人とは主張しないまでも、それ風の、雰囲気を持たせてある。
たとえば、私の好きな、ダイアン・レインの映画で、「トスカーナの休日」という映画があったけれど、これまた、アメリカで離婚をした女流作家が、ふとした自分を癒す旅、つまりイタリアへの旅で、見つけた、レトロな家での生活を描いた作品だったけれども、アメリカの魂の傷をイタリア・トスカーナの自然と料理と人間たちが、癒すという筋書き。
あと、「食べて、祈って、恋をして」。
これまた、離婚と失恋を経験してボロボロになったジュリア・ロバーツが、イタリアとインドなどに旅に出て、魂を癒すという映画だったと思う。
その意味では、ファッションサイトの社長として、日々、狂ったように、働く、まるで、「プラダを着た悪魔」のメリル・ストリープのように変身したかのような、アン・ハサウェイの、苦しみや心の壁を、さりげなく、溶かしていく役柄としては、このデニーロは個人的によく抜擢したなと思う。
なんとなく私はこんなイメージを持っている。
○合理的で、時間時間に追われつつ、自己主張と、結果がすべてという仕事主義のニューヨーカー達。「友達が欲しければ、犬を飼え」式。
○仕事の結果は大切にしつつも、人生の夾雑物を排除せずに、非合理的なものもとりこんで、喜怒哀楽のなかで、ユーモアを武器に、人生を楽しんでいくイタリア式ライフスタイル。「困ったらまずワイン式」
当然私も、イタリア式が好きだな。
ロバート・デニーロ。
母親がたしか、イタリア系だし、父親も、西洋人系。
「ゴットファーザー」では、完璧にイタリア語もマスターして、どことなく、私は、彼はイタリア人ではないかとも思っていた。
(もちろんアメリカ人だけども)
だから、私のイメージとしては、アメリカのニューヨークの最先端の仕事のなかで、ギスギスと生活に追われるアン・ハサウェイの心をしだいに、彼が、柔らかくさせて、その結果として、彼女の仕事の幅が驚異的に広がって行くというシナリオは、カタルシス効果満点で、スカットする。
50代まで、とある会社で部長までやって、今はただのんびり老後を楽しんでいる、デニーロもまた、社会とのリンクを求めて、この会社に入って来て、その「復帰」を静かに楽しんでいるのが伝わって来て、涙がでるくらいに、しみじみと、素敵だなと思える。
たしかに、FBに写真をアップすることもまだできないような、70歳の高齢者ではあっても、
魂の髄にまでしみ込んでいる、その的確な人心掌握スキルと、問題解決能力や判断力で、しかも、柔らかくユーモアをまじえながら、自分の孫くらいの女社長に尽くして行くところが見物。
しかも、恋愛でも、まだ現役!!!
もちろん、これはあくまでも映画なので、70歳でまだまだすべての人がこのように、現役復帰できるかどうかはともかく、シルバー世代にも夢を与えてくれるシネマだと思う。
また、若い人であれば、ニューヨークの最先端の仕事の現場のイメージをつかむだけでも、楽しめる映画だと思う。
日本であれば、ちょいと信じられないような、職場のやりとりやら、光景があって、これまた、楽しい。
狭い職場を時間が惜しいという理由で、自転車ではしりまわる、美しい女社長。
笑えるし、理屈抜きで、目を楽しませることのできる、映画らしい映画だと思う。
おかげで、「プラダ」や「トスカーナ」などの関連映画をまたまた、思い出せて、それまた嬉しかった。アンテナさへ、意識していれば、自然と欲しい情報はあつまってくるものだ。
○資料
役作り[編集]
ロバート・デ・ニーロ(1988年)
上述の通り、デ・ニーロは役に成りきるための努力を惜しまない。その例を挙げる。
『ゴッドファーザー PART II』では、シチリア島に住んで、イタリア語をマスターした後に、マーロン・ブランドのしゃがれ声を完璧に模写した。
『タクシードライバー』では3週間、ニューヨークでタクシードライバーとして働いた[8]。
『ディア・ハンター』では、物語の舞台となったピッツバーグに撮影数ヶ月前から偽名で暮らしていた。さらに鉄工所で働こうとしたが、現地の人に拒否されたという。
『レイジング・ブル』ではミドル級ボクサーの鍛え抜かれた肉体を披露し、その後、引退後の姿を表現するために体重を20キロも増やした。[1]このためにイタリアに赴いて、現地のあらゆるレストランを食べ回った。
主人公がユダヤ人の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』では、ユダヤ人家庭にホームステイした。
『アンタッチャブル』では頭髪をそり上げ、アル・カポネを演じた。体重は直後に別の映画出演が決まっていたので太るわけにいかず、ボディスーツを着用したが、顔だけは太らせて撮影に臨んだ。
『ミッドナイト・ラン』では、マーティン・ブレストと共に実際の賞金稼ぎと共に行動し、捕獲の瞬間、張り込みを見学し、捜査の方法などを習得した。
『ロバート・デ・ニーロ エグザイル』でホームレス役で出演するため、役づくりのためにホームレス施設に潜入した[9]。
○資料2
1999年にテレビシリーズ『ゲット・リアル』の主人公に抜擢され、ティーン・チョイス・アワードやヤング・アーティスト・アワードの女優賞(ドラマ部門)にノミネートされる。
2001年公開の『プリティ・プリンセス』で映画デビュー。全米で1億ドルを超えるヒットとなり、ブレイクする。王女役の役作りのために、スウェーデンのヴィクトリア王女関連の本を読み漁ったという。2002年2月にミュージカル『Carnival!』でブロードウェイデビューを果たす。2004年には『プリティ・プリンセス』の続編が公開され、9500万ドルのヒットとなる。これにより人気女優となったが、プリンセスのイメージが定着し、理想の役が得られずに低迷する。
2005年公開の『ブロークバック・マウンテン』でアイドル女優的なイメージを払拭。2006年公開の『プラダを着た悪魔』ではメリル・ストリープ扮する鬼編集長のアシスタントを演じ、1億ドルを超えるヒットとなった。2007年公開の『ジェイン・オースティン 秘められた恋』ではイギリスの作家ジェーン・オースティンを演じた。
2009年 アカデミー賞授賞式にて
2008年公開の『レイチェルの結婚』で元薬物中毒者を演じ、放送映画批評家協会賞主演女優賞などを受賞し、アカデミー主演女優賞にノミネートされた。
2010年公開の『ラブ & ドラッグ』でゴールデングローブ賞 主演女優賞(ミュージカル・コメディ部門)にノミネートされた。第83回アカデミー賞の司会をジェームズ・フランコと共に務める。
2012年は、ハサウェイにとって大きな飛躍の年となった。『ダークナイト ライジング』にセクシーかつグラマーな美しい女怪盗・セリーナ・カイル役で出演。ボディラインが一目で分かる体にピッタリ密着した衣装(ボディスーツ)を身にまといながらも華麗にアクションをこなす必要があるため、肉体改造を徹底的に行った。クリストファー・ノーラン監督から映画『インセプション』でジョゼフ・ゴードン=レヴィットが2ヵ月間トレーニングを積み、戦いのシーンなどをすべて自分で演じきったエピソードを告げられ、その足で「彼のオフィスを出た後、すぐにジムに向かいました」とコメントしている[6]。しかし、このボディスーツは彼女のウエストサイズより5cmも小さいために常にウエストを締め付けられ、シェイプアップした彼女にとっても着続けるのが困難で、「一日が終わる頃には苦しかった。撮影を終えて脱いだ時の解放感がたまらなかった」という[7]。また、12月公開の『レ・ミゼラブル』にてファンティーヌ(英語版)を演じ、吹き替えなしのミュージカルに挑戦し、第85回アカデミー賞助演女優賞を受賞した[8]。また、同作にてこれまで2度、ノミネートしていたゴールデングローブ賞助演女優賞を3度目にして受賞した。この二作の記録的なヒットでハリウッド女優としての地位を不動のものにした。
私生活[編集]
次の映画は、All You Need Is Kil
小畑健 「All You Need Is Kill」PV
たまたま、この映画Edge of Tomorrowを見た。
日本語の原作ということもまったく知らなかった。
日本語の原作は、All You Need Is Kill・・・。ライトノベルの作品が、ハリウッドで実写化というのはこれまで聞いた事がない。
マンガもあるそうだ。上のクリップ。
映画を見てから、下の資料を見つけて、読んでみると、かなりの違いが日本版との間にあるらしいけれど、楽しめてみれた。
それにしても、アメリカ映画のSFの映画づくりのtecnicは、すさまじい。
この映画を見ていて、すぐに、思い出したのは、マトリックスの戦いのシーン。
あるいは、スターシップトルーパーズ。
「2001年宇宙の旅」や、「惑星ソラリス」のような、神秘感までを漂わすことにはまったく成功していなけれど、想像力がかなり刺激される。
筒井康隆氏が絶賛しているのもうなづける。
外人さんのレヴューを見てみても、実に日本のマンガやアニメの情報をよく知っているし、また、映画の構成、特にlogicが、納得がいったとか、いかないとか、議論されていた。
だいたい、このような、タイムパラドックスというのか、このジャンルのSFは、ややこしいし、おおよそ論理的に作り上げる事自体が、タイムマシンがいまだに完成していないわけで、
想像力の力をかりるだけである。
それを言えば、「アンツマン」や、「・・・マン」ものの、いわゆるアメリカンコミックなんかのタイムトラベルものは、ロジックはいいかげんだと思う。でも、それでいいのだ。
思えば、私が、中学生の頃は、SF映画と言っても、「日本版のゴジラ」や、HGウェルズ、あるいは、ブラッドベリ、フレドリック・ブラウンなんかの小説を通じて、楽しんでいたくらい。
日本ではやはり筒井康隆が、SFマガジンにいろいろ短編を書いていて、わくわくしながら読んだものだった。
(彼は、もうそのときに、クローンの物語を書いていた・・・。)
だから、たしかに、石森章太郎の「霧と薔薇と星と」とか、「幻魔大戦」、手塚治虫の「火の鳥」なんかが、最高のSF作品だった。
それから、はや、40年。
映画の表現は、もう、完全に私たちの脳を刺激するためにつくられているかのようだ。
この映画のなかのmimicの表現なんかは、少しギーガー風のアルファとかオメガを見ると、なんだと思うかもしれないが、mimicの戦いぶりの表現は想像を超えている。
これでは、人類が負けるのは当然だと思うだろう、誰しもが。
エヴァンゲリオンではないけれども、日本のマンガやアニメは、マッチョな強い主人公というよりは、フラジャイルな、少年少女たちをヒロインやヒーローにする。
その意味では、このハリウッド映画のなかにでてくる、トム・クルーズや、リタはまったく違う。
資料によると、リタ・ヴラタスキは、
US特殊部隊に所属している精鋭で[15]、階級は准尉[16]。公称は22歳だが[17]、実年齢は19歳[18]。他の兵士からは戦場の牝犬(せんじょうのビッチ)という渾名でも呼ばれる。モンゴメリの小説『赤毛のアン』のヒロインを連想させるような容姿の[19]小柄な少女だが、圧倒的な戦闘能力を持っており英雄扱いされている。わざと目立つ赤の蛍光色に塗装した機動ジャケットを着込み[20]、重量200キログラムのタングステンカーバイドの戦斧を武器として愛用する[21]。他人には伏せているものの、過去にキリヤ同様の経緯から時間のループを211回[22]繰り返した経験があり、その後もギタイ側が引き起こしているループを逆手に取り、人類を有利な戦いに導いている。
故郷や家族がギタイによる虐殺の犠牲となり、その復讐のために兵士となった経験を持つ[23]。リタ・ヴラタスキという名は本名ではなく、年齢を偽って入隊するために盗用した身分証明に記されていた人物の名であり[24]、彼女自身の本名は明かされない[注釈 2]。ループする時間をキリヤと共有することはできないため[26]、キリヤのループを観測することはできないが、158回目のループの終わりでキリヤがループを繰り返していることに気がつき、159回目および最後の160回目のループではキリヤと行動を共にする。
エミリー・ブラントはイギリスの女性。
品がある。
が、あまり印象に残る強い存在感は個人的には感じなかった。
歴史物の作品があるので見てみたい。
私は、昭和時代のマンガは得意というか、かなり知っているが、働き始めてからは、朝六時から真夜中まで働き尽くめで、ほぼ、マンガは見る暇がなく、その後、ぷっつんと、マンガ通読はできなくなってしまった。
今、時間があるので、読みまくっているが、
いつも書いているけれども、文学と、マンガと、映画は、まったく違って良いと思っているし、その方が、また、原作者の書いたものが膨らむというか、新鮮なるひろがりを持てるのではないだろうか。
たしかに、「シャイニング」の時だったか、キューブリックと、スチーブン・キングがかなり喧嘩をしたとか聞くけれども、それはそれでまた、読者から見ると、興味深くて、おもしろい。
できれば、このような作品群は、小説とマンガと映画とすべてを見てみることも、暇のある人は、最高の体験ができることだろうと思う。
○個人的に好きなscene
兵士達の鎧のような防具?機械
戦闘シーンのすさまじさ
mimicの表現
兵士達を鍛える時の言葉=キューブリックの戦争映画フルメタルジャケット同様に。
時間をコントロールしながらもこの宇宙のなかで征服を可能にするエイリアンの表現。
パターンではあるけれども、人類救済のために結束するグループの仲間たち。
死を恐れない勇気のシーンの数々。その他。
○資料
5 Differences between Edge of Tomorrow and All You Need is Kill

Hopefully you’ve gotten a chance to go see the excellent movie Edge of Tomorrow over the weekend. I took some time on Friday to go see the movie a second time, and I still love the film. Now that the movie is out I wanted to go into a deep dive into how the source materialAll You Need is Kill compares to the Edge of Tomorrow. This is going to be very spoiler heavy so don’t read on if you haven’t seen the film yet.
1) Major Bill Cage and Private Keiji Kiriya are entirely different

Keiji Kiriya is a Japanese soldier in the UDF, fighting for his country, as this story takes place in Japan. Keiji signed up, and wanted to fight against the mimics, while Cage was an American that never wanted to fight. By the time they do wind up fighting, they are both new to it all, but Keiji wanted to be there while Cage was constantly looking for a way out.
Keiji was also trained by Sgt. Farrell, while Cage was trained by Rita. For the most part Keiji didn’t have anywhere near as much interaction with Rita as Cage did, until the last few resets. Keiji was going to forgo everything to make himself the best he could, while it seemed obvious that Cage had fallen for Rita and was training in part because he loved her and wanted to save her.
2) Rita Vrataski from All You Need is Kill would bitch slap Emily Blunt

Don’t get me wrong, Emily Blunt was awesome in Edge of Tomorrow. She was one of the best parts of the film, but Rita Vrataski from All You Need is Kill is the real Full Metal Bitch. In the novella, Rita had killed more Mimics on her own before she gained the ability to “reset the day” and became a famous war hero. Once she gained the Mimics ability she got even better, going through several hundred attempts at the battle of Verdan. The movie version of Rita had her first battle at Verdan. She learned how to be really good, but I don’t think she would hold a candle to her novella counterpart.
Another significant change was the age of the character. The Rita in the book was somewhere between 19 and 22 years old. She signed up for the UDF illegally at 16, and fought battles for years before Verdan ever happened. I don’t think they ever say how old Emily Blunt is supposed to be, but she’s definitely older than 22, let alone 19.
3) The Mimics are much scarier in the movie

The book described them as giant bloated frogs with 4 legs, a tale, and a hard endoskeleton. I have no idea on how to describe the movie version. It seemed like they crossed a giant metal dog with a psycho octopus, and gave it the speed of a cheetah. The book Mimics are also very fast, but they don’t have the same tentacle action going on, that the movie version has.
The hierarchy between the mimics are very different as well. The movie has normal Mimics that seem to be grunt soldiers, and Alpha Mimics that are the Generals in a battle. Then there is the Omega Mimic that is the pretty much the King of all Mimics. If an Alpha dies, the Omega Mimic will “reset the day”, and use the info that it gained to help win the war next time.
In the book you didn’t have an Alpha and an Omega. The book has Antennae’s and Servers. At every battle there are several Antennae and one Server. The Antennae kind of control the standard grunt Mimics, and send information to the Server. If the Server dies, it “resets the day” and then passes that info onto the other Antennae the next time around. In order to win the battle the UDF has to kill all of the Antennae in the area, and then the Server so it can’t send the info anywhere and properly “reset the day”.
While this sounds similar, it’s very different, in that there is only 1 Omega, while there are many Servers. This has a large difference on humanities ability to win a battle, and the progression of the war.
4) The War, and our world are very different

In the book, the Mimics landed over 20 years before the battle in Japan. The Mimics were sent by an alien race looking to colonize a planet. They didn’t know if there were sentient life forms on this planet, and they didn’t have time to check. They sent the Mimics to help terraform earth to make it more habitable for them when they get here. The Mimics landed and initially were very peaceful. The problem was that they eat earth and excrement poison gas that was transforming the planet. Humanity attacked and tried to stop them, which started the war. The Mimics evolved, and got smarter and stronger with better weapons and started to win.
In the movie, they landed 5 years before the battle of Europe. There really isn’t any info on what they are doing or why, or what started the fight. We just know that there was a lot less time for this all to escalate so far.
Because of the time difference, the world of the book and the world of the movie are very different. Having a World War for over 20 years where parts of the world are wiped out, means that you start running out of stuff. Some things become extinct, and can only be read about in books. The novella version of Rita being so young, only knew of war growing up, and it made her a very different person from the one we have seen in the movie.
Another distinction in the war is that in the movie, we only won a battle because the Mimics let us think we won. They regroup and change tactics to make it easier to pummel us later. In the novella humanity legitimately won those battles. The movie definitely had a much bleaker outlook on our prospects of survival in the end.
5) The endings are drastically different

In the novel because Keiji and Rita have both stolen the alien’s abilities at some point, they both act as Antennae. Unfortunately that means that the day will keep resetting as long as both of them are alive. The only way for the day to end is if one of them dies. So at the end of everything they have an all-out slugfest with each other to see who is worthy of surviving the day and fighting for humanity. Keiji winds up killing Rita, and goes on to become the next hero of the UDF for the battles to come.
In the movie, they walk into a situation where neither is going to get out alive, and they have to sacrifice their lives to save humanity, but Tom Cruise gets the Omega’s blood on him, and regains the power to reset the day on his death. In doing so everyone that dies is alive again, with a fairy tale ending. The war is over and humanity can celebrate.
アレクサンドリア [DVD]/レイチェル・ワイズ,マックス・ミンゲラ,オスカー・アイザック
¥3,990
Amazon.co.jp
実話というけれど、彼女の考えた天空の太陽と地球との惑星の軌道が「楕円」ということを、ケプラー?よりも1600年も早く、発見したというこのシネマのディテールにまず感動。
私は、この「楕円」というキーワードを見ると、即、花田清輝の「楕円幻想」を連想した。
好きで好きで、何回も読み返したレトリックにあふれた文体の贅沢な本だった。
先日亡くなった吉本隆明だったか、彼を議論で打ち負かして、その後はあまり紙面には出てこなくなったと聞いたが、私から言わせれば、吉本隆明以上の閃く素晴らしいセンスを持っていて、魅力的な作家だった。
花田清輝 (日本幻想文学集成)/著者不明
¥2,039
Amazon.co.jp
要は、彼が言いたいのは、「円」という神学的に言うとまさに完璧なる図形はいいとして、現代という時代は、「円」にこだわることなく、二極を中心とする円=「楕円」こそが、必須の思想の核になるのではないか、そんなエッセイだったような記憶がある。
もう絶版の書物だ。
その「楕円幻想」を思い出しながらこの映画を見た。
彼女がたくさんの男たちに、ギリシアの哲学を教えている。
「考える」ことが、ニーチェのいわば「知の快楽」になっていて、彼女には宗教は必要がない。
彼女自身が言うように、「哲学」こそが、彼女の「宗教」になっている。
このあたりは、たとえば、曖昧な記憶だが、ジョイスのエピファ二ィだったか、パリでの経験と比較してダブリン市民の知的な麻痺、無気力を彼独特の「エピファニィ」で、書き留めている。
エピフィ二ィはキリストの現出を意味するものだと思う。
あるいは、コリン・ウィルソンの「至高体験」のようなものだろう。
それらの体験を哲学を通じて経験できる、現代ならばそうとうの地位にまであがれるような美しき女性、それが、ヒュパティアである。
彼女は、たしか、「ナイロビの蜂」にも出演していて私が気に入っていた女性だったので、この映画でこんなすばらしい役柄をやってのけて、感心した。
新プラトン派と言われるが、それは後世の人がつけたレッテルであって、この映画の描く彼女の生き様は、「知の快楽」や「真理愛」に憑かれた天才の生き様だ。
キリスト教の信奉者が70%をしめると言われるスペインで、こんな映画が出来た。
ある意味では、映画として皆それを冷静に観ているのだと思う。
そして、この映画にしょっちゅう現れる「巨の視点から見た地球」。
それは、宗教でさえも、彼女の真理愛から見ると、小さく見えてしまうものだ。
物語も非常に上手く書かれていると思うし、時代考証もなかなか説得力があり、ひきこまれた。
古代の人の精神までにはとうていたどりつくことは不可能だとは思うが、少なくとも、ギリシアの哲学やら、キリスト教の布教、ユダア教の布教、人々の暮らし、知識人達の生活と奴隷達の日常。
そんなものが、リアルに画面に出て、非常に刺激となった。
映画は見るものさしは、皆、自由だと思う。
車好きな人は車のたくさん出る映画に驚喜するのだと思うし、自分の好きなスタアが出れば皆、小躍りするではないか。
私の、ツボにはまる映画とは、○音楽家のエピソードを扱った映画○まだ見ぬ風景などの自然がたっぷり見られる映画○神秘や幻想や心の綾をテーマにする映画○「天才」達を扱った映画○好きな男優女優の出る映画○まったく自分が考えたこともない視点からの映像や問題点をなげかけてくる刺激的な映画だ。
この映画も、その意味では、私のツボにはまった映画だった。
なによりも映像が美しい。
タイタニックの監督が、今、3Dであの「タイタニック」のリバイバルをつくっているらしいが、楽しみだ。
映画とは、私の脳に刺激を与えてくれる最高の娯楽だ。
こんなアホな脳であっても、少しくらいは、進化してくれるかもしれない。
この映画の中で、何回も考えていることだが、現代人の頭の構造は、テレビやゲームや下らない人間関係などに押さえ込まれてるのと比較して、なんと古代人は自然の中でそれらを研究し学習しそこから大きなものを学んでいることだろうか、という驚きである。
今の現代にもしも彼らがやってくることができたとしても、彼らがうらやましがることは何もないだろう。
少女の妄想・・「15歳、アルマの恋愛妄想」デニーロ「グリフィン家のウェディングノート」
医者は生活の安定を約束していた。
しかし、僕は画が描きたかったのだ。
手塚治虫
ブラックジャックを毎日読んで、コマ割りなどを勉強している。
手塚治虫氏は、やはり「物語性」が抜群に、うまいということが理解できる。
小さなディテールは、??というところもあるのだけれども、全体的な流れでは、スムーズに
読んで行けるので、すごいと思う。


たとえば、この「クリスマス」の日に、ブラッククィーンとあだ名される女医が、ブラック・ジャックと逢う。
・・・・・・・・・・ 普段は、患者の足や手をバンバン切りまくって、冷静にオペをする彼女、ブラッククィーーンも、自分の愛する彼が、事故で、両足を切らねばならないとき、悩みに悩むのだった。
そのとき、ブラックジャックはどういう行動をとるのか・・・・
こんな小さなミニ短編なんだけど、ハッとさせられる。さすがに、手塚。
個人的な意見としては、アイデアが多すぎて、もっと煮込んで物語をつくりあげてもいいのではないかと思ったが、それは理想論。
アニメ会社を倒産させてしまい、必死に、彼も、このブラック・ジャックを書き始めている!!!! まさに、命がけで、書いた作品。
それが、ブラック・ジャックだと思う。
サマセット・モームという短編の上手い作家がいるが、ちょっと、手塚治虫氏との相似を感じた。もちろん、絵と文章という違いはあるけれども。
こんな物語があったような記憶。
貧乏な夫婦だったか、恋人だったか。
クリスマスの夜に、男の方は大切にしている腕時計を売り払って、妻にかんざしをプレゼントしようとする。
妻は妻で、彼のために腕時計のチェーンかなにかをプレゼントしようとして、自分の髪を切ってしまう。
・・・・・・・・・・・・・・
切なくて、深い愛を感じる一編だった。
「谷口ジロー」もよく読む。
嫌いではないけれども、絵が上手すぎて、原作者つきのマンガを描いているのも、もったいないと思う。
やはり、原作者なしで、マンガを書いてもらいたい。
夏目漱石についてマンガを書く事自体は良いと思う。
ただ、自分で、構成を考えた方が良いのではないか。
あせってはいけません。
頭を悪くしてはいけません。
根気ずくでおいでなさい。
世の中は根気の前に
頭を下げる事を知っていますか。
花火の前には
一瞬の記憶しか与えてくれません。
うんうん死ぬまで押すのです。
それだけです。 夏目漱石
『坊っちゃん』の時代 (第5部) (双葉文庫)/双葉社
¥669
Amazon.co.jp
最近読んだ漫画。
マンガは、よく暇なときに読む。
最近読んだのは、「人間交差点」「ギャグゲリラ」「夏子の酒」・・・・・・・
なんでも読む。
・・・・・・・・・・・・・・
谷口ジロー。
夏目漱石の胃潰瘍。
ある意味、責任感が強い。
ここに描かれた漫画の物語のディテールがもしも、考証が正しいとするならば、
あまり個人的に惹かれる人物ではない。
刺身も、胃に悪いという理由で食べずに、甘いものと、胃に重いものを食べ続ける漱石。
卵をぶっかけて、ご飯を三杯も、食す。
医者から注意を受けているにもかかわらず。
一度、死んだ漱石が、臨死体験のようにして、まるで、キューブリックの、ラストシーンの、あの不思議な老人との対面のようにして、すでに死んでいる面々と逢うシーンは感心した。
谷口ジローの熱烈なファンがいるので、少し褒めると、彼の小さなところまで細部をないがしろにしない絵には感銘。
養老さんが、解説しているけれど、昭和生まれの原作者が描く明治・・・
興味深いけれども、やはり、表面的に思えてしまうのが残念。
絵だけでも、これは手塚治虫賞というのは納得。
漫画はやはり、絵。 原作付きの漫画はあまり好きではない。 個人の好みだけれども。
夏目はやはり、活字で読みたい。彼が胃を痛めた執筆の跡が読み取れると思う。
「15歳、アルマの恋愛妄想」見ました。
ここに備忘録しておきます。ほんとうに忘れっぽい私です。
性を扱った映画はどこの国にもあるけれども、お国柄がおもしろい。
この映画、『15歳、アルマの恋愛妄想』(Få meg på, for faen)は、2011年のノルウェーのコメディ映画。原作はオーラウグ・ニルセン。
ノルウェー西部の架空の小さな街を舞台とし、性に目覚める15歳の少女のアルマが描かれる。

この少女。
そして、お母さん役の、ヘンリエッテ・ステーンストルプが、目立っています。
きわだっています。
・・・・・・・
実にリアルで、日本ではありえない、家庭にリアルな感覚を肉付けしております。
やはり、映画を見る楽しみは、物語が良い悪いとかそれだけではなくて、役者の魅惑もありますし、それにくわえて、なんといっても、ノルウェイの今の自然・都会の雰囲気が、味わえることだと個人的に思っています。
アルマの妄想というアイデア、がいいです。
田舎に不満を持って都会に出て行きたいというまことに普通の少女。
妄想が爆発しているのに、さわやか感があるのは、彼女=ヘレーネ・ベルグスホルムの
人柄、個性、そして、女優魂ということだろう。
青春時代のあの独特なもやもや感・性への憧れ・・そんな誰しもが持つ感覚をモダンなコメディに完成させたということだろう。
好きな作品。
◎資料から
監督・脚本は、本作が長編デビュー作となるヤンニッケ・シースタ・ヤコブセン。トライベッカ映画祭最優秀脚本賞、ローマ映画祭最優秀デビュー作品賞、モンズ国際恋愛映画祭最優秀ヨーロッパ作品賞受賞。
次なる見た映画。
「グリフィン家のウェディングノート」。
「マイ・リターン」を見て、アン・ハサウェイと素敵な関係だった、ロバート・デニーロ。
気になってみてしまいました。
原題「The Big Wedding」 2013年アメリカ映画
◎資料から
次男アレハンドロの結婚式のために、グリフィン家は10年ぶりに集まった。父親である奔放な性格の彫刻家ドンは、前妻のエリーと離婚した後、10年も愛人のビービーと暮らしており、実質今では彼女が一家の母親代わりになっていた。長女のライラはそんな父親を嫌っており、長男のジャレドは医師という立派な職に就きながら女性と上手く付き合えない等、家族はそれぞれ複雑な事情を抱えていた。
いよいよ結婚式間近となったある日、アレハンドロは思いもよらない問題に直面する。幼い頃グリフィン家に養子に入った彼には、超がつくほど保守的な思想を持った実の母親がおり、彼女に家族の複雑な関係を知られてしまうと、絶対結婚には賛成してくれそうになかったのだ。そこでアレハンドロはドンとエリーに、二人は今でも仲の良い夫婦だという演技を結婚式までの間してほしいと頼む。息子の幸せのため、渋々了承した二人だったが、これにより複雑だった家族関係は余計にこじれてしまうのだった。
これ、コメディ映画。
コメディだから、ドタバタ劇。
はっきり言って、想像を絶するくらいのハチャメチャ人生劇。
まじめすぎる人が見たら、あきれ果てるくらいの、いい加減な映画。
そこが良い。そう個人的に思う。
これだけ、つまらない脚本を、といっても、「最高の人生の見つけ方」の脚本を書いた監督でもありますが、さらに、アホ的なまさに安吾的ファルスの精神でつくりあげた・・・・・・・
B級映画。
あまりにも、軽いので、涙もでなければ、さほどコメディにしては、笑えもしないのだけれども、湿気の多い日本的な人間関係の重厚なる風土から見ると、それはそれで、興味深い。
規則やルールはあるけれども、結局は、人生を楽しむ・・・自分の盲目的な本能に忠実に生きるという映画。
モテモテの中年男性におすすめの映画とレヴューにあり、笑ってしまう。
これから、21世紀、世界的に、高齢者の時代が来るというのに、中年というだけで、毛嫌いする若者の精神の厚みのなさに、びっくり。
会田雄次教授の「バサラの精神」、龍角散社長の「もっと遊ぼう」ではないけれども、
生真面目で、視野の狭い人ほど、この映画は見ると良いと思った。
ところで、ミレーユ・ダルクのことを最近考えています。
「恋するガリア」を再視聴しました。
レジオンドヌール勲章シュヴァリエ章を、2009年、国家功労章コマンドゥール章をそれぞれ受章
声がこんな可愛い声とはしりませんでした。
資料を備忘録しておきます。
ミレーユ・ダルク
* 『何がなんでも首ったけ』、監督ロジェ・ヴァディム、1961年
* 『大貴族』、監督ジル・グランジェ / ジョルジュ・ロートネル、1965年
* 『恋するガリア』、監督ジョルジュ・ロートネル、1965年 - 主演
* 『海と女と泥棒と』、監督ホセ・マリア・フォルケ、1966年
* 『皆殺しのバラード』、監督ドニス・ド・ラ・パトリエール、1966年
* 『太陽のサレーヌ』、監督ジョルジュ・ロートネル、1966年
* 『女王陛下のダイナマイト』、監督ジョルジュ・ロートネル、1966年
* 『エヴァの恋人』、監督ピエール・ガスパール=ユイ、1966年
* 『牝猫と現金 (げんなま)』、監督ジョルジュ・ロートネル、1967年 - 主演
* 『ブロンドの罠』、監督ニコラス・ジェスネール、1967年 - 主演
* 『ウイークエンド』、監督ジャン=リュック・ゴダール、1967年 - コリンヌ役、共演ジャン・ヤンヌ
* 『枯葉の街』、監督ジョルジオ・ボンテンピ、1968年
* 『モンテカルロ・ラリー』、監督ケン・アナキン、1969年 - 共演アラン・ドロン
* 『ボルサリーノ』、監督ジャック・ドレー、1969年 - 共演アラン・ドロン
* 『ジェフ』、監督ジャン・エルマン、1969年 - 共演アラン・ドロン
* 『栗色のマッドレー』、監督ロジェ・カーヌ、1970年 - 共演アラン・ドロン
* 『狼どもの報酬』、監督ジョルジュ・ロートネル、1972年 - 共演ジャン・ヤンヌ
* 『愛人関係』、監督ジョルジュ・ロートネル、1973年 - 共演アラン・ドロン
* 『プレステージ』、監督エドゥアール・モリナロ、1976年 - 共演アラン・ドロン
* 『チェイサー』、監督ジョルジュ・ロートネル、1978年 - 共演アラン・ドロン
* 『ソフィー/遅すぎた出逢い』、1988年 - 監督・脚本
* 『女性弁護士マリオン』、テレビ映画、1998年
* 『ディープ シークレット ~殺人者の海~』、監督ディディエ・アルベール、テレビ映画、2003年 - 共演アラン・ドロン
* 『アラン・ドロンの刑事フランク・リーヴァ』、監督パトリック・ジャマン、テレビ映画シリーズ、2003年 - 2004年 - 共演アラン・ドロン
ミレーユ・ダークを見ていると実にフランスの女優は、センスが違いますね。
白黒の映画というのも、彼女の美をひきだしていると思います。
ドヌーブ・バルドー・ミレーユ・ダーク・・・・・・・・
◎資料
1965年、ジョルジュ・ロートネル監督の『恋するガリア』に主演し、マール・デル・プラタ国際映画祭主演女優賞を受賞、以降、ロートネル作品の常連となる。
「恋するガリア」
次なる鑑賞映画は、「ラジュテ」
◎資料から
1962年のフランス映画であり、監督クリス・マルケルによる時間と記憶をモチーフにしたSF映画。
近未来の廃墟になったパリで少年時代の記憶に取り憑かれた男の時間と記憶を、「フォトロマン」と呼ばれるモノクロ写真を連続し映す手法で描く、上映時間29分の短編映画。SFであるが、SF的な美術などは見られない。
1963年、トリエステSF国際映画祭グランプリ受賞。ジャン・ヴィゴ賞受賞。
12モンキーズをはじめ、多くの映画の原案になったといいます。
12 Monkeys
わたしは、すぐにキューブリックの「時計仕掛けのオレンジ」の目にクリップをさせられて拷問にかけられる男を連想しましたね。
あとは、フィフスエレメントの、「エリアンの歌」のシーン。
圧巻です。
いまでも、このシーンは、ビデオにとりこんで、よくココだけ見ます。
背中がぞくぞくするほどの圧倒的な美しさがあります。
グロテスクな美。
・・・・・・・・
このソプラノ歌手のことを知りたくて、調べてみたことがあります。
インヴァ・ムラ(Inva Mula、1963年6月27日 - )はアルバニア・ティラナ出身のソプラノオペラ歌手。父のアヴニ・ムラ(Avni Mula)はコソボ出身でアルバニアの歌手。インヴァ(Inva)の名前は、父親の名前(Avni)を逆に読んで付けられた。デビュー間もなくは夫の名チャコ Çakoを読みやすくしたTchakoも併記していたが、96年頃から使用しなくなった。イタリア・オペラの出演が多いことからか、日本ではインヴァ・ムーラとイタリア風な読み方もされるが、特に音引きは必要ない。
この歌の部分の、80%は彼女が実際に歌っているというから素晴しいです。
彼女のソプラノ、クラシック、ベルディの「リゴレット」でも聞けます
このような基本があるので、あのフィフスエレメントに、つながるのだと思います。
それにしても、ブルース・ウィルスは素晴しいですね。
大好きです。どの映画を見ても、実に存在感を感じさせてくれて、画面がピシッとひきしまるというか、味のある画面にしてくれます。
◎資料から
ウォルター・ブルース・ウィリス(Walter Bruce Willis, 1955年3月19日 - )は、ドイツ生まれのアメリカ人俳優であり、プロデューサー、ミュージシャンでもある。彼のキャリアは1980年代から始まり、それ以来コメディ、ドラマ、アクションといったジャンルで、テレビと映画の両方で活躍している。『ダイ・ハード』シリーズの主人公ジョン・マクレーン役でよく知られている。他にも60作品以上に出演し、『パルプ・フィクション』(1994年)、『12モンキーズ』(1995年)、『フィフス・エレメント』(1997年)、『アルマゲドン』(1998年)、『シックス・センス』(1999年)、『アンブレイカブル』(2000年)、『シン・シティ』(2005年)、『森のリトル・ギャング』(2006年)、『RED/レッド』(2010年)のように興行的成功を収めた作品も多い。
彼は2度エミー賞とゴールデングローブ賞を受賞し、4度サターン賞にノミネートされた。ウィリスはデミ・ムーアと結婚し、2000年に別れるまでに3人の子供をもうけた。現在はモデルのエマ・ヘミングと結婚しており、1人の娘が生まれた。左利き。身長183cm。
ミラ・ジョヴォヴィッチが、この映画で、デヴューしたことも印象的ですね。
話しがすこし、それました。
この「「ラジュテ」
詩的SF。
一枚のファッション雑誌に出てくるような美しい(残酷な)写真が、手作業で、編集されています。
ナレーションがリアルで、第三次世界大戦のパリを表現しています。
ただ、イメージだけの画像の連続で、未来の地球を救うために過去にエナジーを持って帰るためにも、過去についての強烈なイメージを持っている男を選んで、タイムマシーンで過去に送るというテーマは苦しいかもしれない。
とにかく、画像が強烈なために、いろいろなことを考えることができる妙な映画とも言えますね。
なんだかんだ言っても、飽きずに見れました。
63年のトリエステのSF国際映画祭グランプリ、ジャン・ヴィゴ賞受賞しております。
1971年に、時計じかけのオレンジの制作発表されていますから、やはり、影響を受けていると思いますね。
ラ・ジュテ[ビデオ]/著者不明
¥3,990
Amazon.co.jp
つぎなる大好きな映画は 「しあわせの隠れ場所 」 サンドラ・ブロック & キャッシー・ベイツ
この映画のなかにでてくる、
キャッシー・ベイツいいですね。
スチーブン・キングの「ミザリー」は彼女の最高傑作でしょう。
「ミザリー」
大衆向けロマンス小説「ミザリー・シリーズ」の作者である流行作家のポール・シェルダンは、「ミザリー・シリーズ」最終作に続く新作を書き上げた後、自動車事故で重傷を負ってしまう。そんな彼を助けたのは、ポールのナンバーワンのファンと称する中年女性アニー・ウィルクスだった。看病といいつつポールを返さず、拘束・監禁するアニーは、次第にその狂気の片鱗を垣間見せ始める。そんな時、「ミザリー・シリーズ」最終作が発表されるが、内容が自分のイメージと違うと書き直しなど無理難題を付けはじめ、ポールも彼女の狂気に気づき脱出を試みる。
2009年公開。
しあわせの隠れ場所
The Blind Side
監督ジョン・リー・ハンコック
製作総指揮ティモシー・M・ボーン
モリー・スミス
アーウィン・ストフ
製作ブロデリック・ジョンソン
アンドリュー・A・コソボ
ギル・ネッター
脚本ジョン・リー・ハンコック
出演者サンドラ・ブロック
ティム・マッグロウ
クィントン・アーロン
キャシー・ベイツ
音楽カーター・バーウェル
2009年のNFLドラフト1巡目でボルチモア・レイブンズに指名されて入団したマイケル・オアーの実話とある。
まさに奇跡好きのアメリカ人好みの映画。今、ハリウッド映画はワンパターンだから嫌いという人が増えていますが、このワンパターンがまたたまらないし、そこにこそ、ヒット作の本質も垣間見えるわけで、勉強になります。日本で言えば寅さんや水戸黄門たみいなものでしょうからね。
「はなのすきなうし」のイメージを持つマイケル。寒い夜に、ひとり家もなく体育館で寝泊まりする巨漢の黒人の男の子を見るに見かねて家につれて帰るサンドラ・ブロックことリー・アン・テューイ家族。
ちょいと作り物的な感じはあるが、勇気のある家庭である。途中、銃を持つヤクの販売人でもあるマイケルの昔の悪友などにからまれても、毅然と「彼をおどすことは私を脅すこと。私は全アメリカライフル教会に入っていていつでも銃をぶっぱなせるわ」と啖呵をきるような女でなければ、法的な後見人にはなれないだろう。
見ていて疑問は数々出てくるが、きちんとのめり込んで楽しめた。
というのは、サンドラ・ブロックの演技が実に切れ味があり、さわやか。深みには欠けるような気もしないではないが、強い気性を渋く押さえた演技と見る。
この映画を見ながら以前書いた記事を思い出していた。
ピレシュの逸話で有名なのが、彼女が娘が出産をしてその孫が寝ているとなりのベッドに、同じ頃に生まれた黒人の男の子がいた。
もうすぐ孤児院に入れられると聞いて、一晩考えた末に、ひきとることにしたと言う。
50歳を過ぎてから赤ちゃんを育てるなんてなんとすごいことですかネ。
「でもほおっておけなかった」そうビレシュは言うんです。
彼女は今の世界では人気者なので世界のどこの国でも行くが、必ずこの男の子、クラウディオ君を連れて行く。
そして、ホテルではなくて、アパートを借りてもらうのが条件だというのですから、なぜならば、少しでも家にいるような雰囲気で育てたいからだと言うのです。・・・
ピリスは、クラシックを聞くように教えてくれたtakatakaさんから教えてもらったピアニスト。一番好きなクリップは、これ。
・・・・・・・・・・・
アメリカでは、このような里子というのか、制度がしっかりしているようだ。
聞いた話でも、黒人の子供だけではなく、韓国、中国などの子供達を自分の生んだ子供と一緒に育てると言う。うがった見方をすれば白人の有色人種に対する優越感をくすぐるためだとも考えることもできなくないが、やはり、実際に里子を育てている人が日本に比較すると問題にならないくらい事実いるわけで、このようなことはそんなたわいもない理由ではできそうもない。
やはり、良い意味でのキリスト教的な慈善の流れのひとつではないかと私は考えている。そして、素直に私はすごいと思う。
が、もともと神の概念もなく、真の意味でのヒューマニズムも育っていない日本ではたぶん無理な制度だとも思う。
そんな私の疑い深い心をひっくりかえすくらいにこの映画の粗筋は感動的だ。
実に、子供が生き生きと描かれている。マイケルを兄と慕うチビちゃんもユーモアを誘うし、年頃でむづかしい年代でもある姉の娘もまたのびのびとした良い子。
それにしてもこの映画の中、父親の父権というものがあまり感じられないのはおもしろい。ニューヨークみたいなところをのぞけば、アメリカは良い意味での父権制がまだまだ強い筈だが、実に妻をうまくのせ、主人公にしながらも陰で応援するまるで日本人の父親みたいな男をテイム・マッグロウが好演している。(アカデミーとゴールデンブローグ賞を取ったサンドラ・ブロックや、途中から出て来て私はびっくりしたのだが、あの「」に出ていた個性俳優のキャッシー・ベイツほどではないが・・)
黒人の差別の問題、ホームレス、白人中心の教育制度、先生たちを含む偏見の目、フットボールチームにおけるモチベーションの問題、大学入試における家庭教師、さまざまなる問題があるが、サンドラ・ブロックことリー・アン・テューイは悩み考えながらも、ひとり、突き進んで行くのが実にカッコいいですね。
金持ち付き合いの友人から「彼はあなたによって変わったか?」と聞かれて、はっきりとサンドラ・ブロックことリー・アン・テューイが、「いや、私が変わったのよ」と実に自分がよくわかっている。
ここらあたりも思うのは、確かに里子制度はむづかしいし、へ理屈をつけてそれを避難するのも簡単だが、もっと現実的に考えてみると、このサンドラ・ブロックことリー・アン・テューイの四人家族はもともと幸福だったのだが、新たに黒人の少年マイケルを家に招き入れることによって、さらに幸福になる鍵を得たのだ。
そして、マイケルもまたやわらかいベッドで寝ることができ、三度の食事と風呂に入ることができる。
ほんとうはこれだけでもシステムはうまくいっている筈だが、しかしながら、人は無償の愛をもとめてしまうのだから、物語はまた違う展開となっていく。・・・・・
<ヒント>
● 皆がテレビを見ながら行儀悪く食事をする習慣も、マイケルがひとり小さくきりとったパンと、少しのサラダだけを皿についで、テーブルで行儀よく食しているではないか、と。気づいた彼女が偉いということだろう。
● 85店舗も店を持つバリバリの経営者である夫。それを支える知的で敬虔なる妻。素直でのびのびとした二人の姉と弟。豪邸に、BMW。誰から見ても幸福そのものの家族が、さらに変容していくのだった。
●マイケルが最後にママに甘えるようにして、「もしも自分が食堂の店員でもいいのか」と聞くシーンがあり、心に響いた。
誰しもが無償の愛を求めているのだ。
●キャッシー・ベイツの家庭教師のシーン。「奇跡の人」のアンバンクロフトの演技を思い出す。子供がやる気をだすまでが大変なのだ。単に記憶だけをさせようと必死になっても無駄。その子の一番のびる部分をしっかり見て行く。マイケルの場合は、「守る」こと「保護本能」の才能が異常に強いということだった。<母親から無理矢理はなされたりしたことなどがあるのだろう。過去の記憶のフラッシュバック>
●最後のどんでん返しのチェック。ミシシッピー大学に入ったことの理由を咎められて、マイケルは疑いの結晶作用に陥る。だがそれもまた、恋愛においてマイナスの疑いの心がさらなる恋の炎を強くする作用と同じである。
ここのシーンはしかしながら意味不明のところも多い。
●運転免許にトラック。これはやりすぎか?
●図書館における姉がマイケルの机に来るシーン。
●クライマックスのフットボールのシーンは少し迫力がなかったかも。
●言葉の問題。コミュニケーションの問題。心が落ち着き、自分に自信がつき、勇気を持つ習慣が出来、、始めて信頼関係のあるコミュニケートができるのでは。
しかしながら。
このサンドラ・ブロック。
この映画「ゼログラヴィティ」の彼女も圧巻。
個人的には、数回も見ました。
素晴しい。「インターステラ」との比較もしてみました。
サンドラ・ブロック=ゼログラヴィティ
アン・ハサウェイ= インターステラ
ということですね。
この「インターステラ」、昨年の五月に見た、グラヴィティとのシンクロもある。
こまかな映像のテクニックよりも、今のこの時代、SFよりも生な現実が突き進んでいるという恐ろしい世の中で、あえて、SFに挑戦して映画をつくるというのも、すごいことだと思う。
◎次元のイメージのつくりかたが面白い。
◎本とチリのイメージのはさみこみかたが上手い。
◎ブラックホールとワームホールなどのこむづかしい理論の説明よりも、映像でずばり
魅せてくれるのが、好き。
◎ラストシーンはかなり好きだ。
◎かなり2001年宇宙の旅からの、キューブリックからのオマージュともいえる画像が多いけれども、それが嫌みではなくて、素直に楽しめる。
◎小林秀雄氏が言うまでもなく、自己犠牲というような言葉が素直に受け取られる時代がなくなれば、もう人類はおしまいだと思う。「我」や「個」が、われさきに、自己主張だをするような時代や国に、未来はない。
◎ もっとこのようなタイプのSFを見てみたい。もちろん。エイリアンものも楽しめるけれども、科学の現実に裏打ちされているかのような真摯な映像は私の好みだ。
(真に裏打ちされていなくても良い。ニュアンスが上手く出ていれば良いと思う。わかりやすいというのも、すごく大切だから。)
◎基本、「この地球」よりも、素晴らしい惑星はないんだという結論が、くりかえしくりかえし、どのシネマでも語られる。実際にそういうことなんだろうと思う。ワーグナーの音楽が印象的だった、地球最後の日をテーマにした作品でも、そのことを強く言葉で印象づけていたことを思い出す。
◎資料
上記のような「インターステラー」に登場する科学的なフレームワーク、特にブラックホールに関する点などは理論物理学者、キップ・ソーンの監修で作られています。
キップ・ソーンはカリフォルニア工科大学の有名な教授であっただけでなく、カール・セーガンが「コンタクト」を執筆した際にワームホールについての情報を提供したことでも知られています。
「インターステラー」が「2001年宇宙の旅」「コンタクト」の伝統に名をつらねた映像表現を試みていることを考えると、昔からの宇宙ファンは胸が熱くなるわけです。私個人は1991年のTVシリーズ「The Astronomers」でキップ・ソーンが登場していたのを覚えている年代で、それをみて物理を専攻しようと思ったのでなおのこと思い出深い流れです。
キップ・ソーンの今回の映画での貢献は、作中では「ガルガンチュア」と名付けられている弱い、しかし回転するブラックホールの重力についての計算や、その周辺での光のねじ曲がり方についてです。
特に通常のレイトレーシングでは光は直進することが仮定されているのですが、ブラックホール周辺ではその前提が崩壊してしまうためにまったく新しい計算手法を用いる必要があったそうです。
これら「インターステラー」の背景となっている科学についてはキップ・ソーン自身による「The Science of Interstellar」が発刊していますのでぜひこちらもどうぞ。また、”Black Holes & Time Warps”も、いまでも読み物としてとても楽しめます(邦訳は絶版のようですが)。
◎資料
映画「インターステラー」の筋を支えているさまざまな宇宙的な現象は、概ね実際に理論で知られているものです。
ブラックホールは有名ですが、空間と空間のあいだに近道をつくるワームホールも、実際に観測されたことはないものの一般相対性理論の解に含まれていることが知られています。
「ホール」がふたつあるので混乱しそうですが、ブラックホールは質量が大きすぎるために光さえも抜け出すことができない天体のことを指しています。この光が抜け出せなくなる境界部分は「事象の地平線」と呼ばれていて、この平面から外側には、内部の情報はぬけだせません。これが映画の筋に大きくかかわる知識ですので、ブラックホールについては読んでおいてもいいでしょう。
ワームホールは時空のある場所とある場所をつなぐトンネルのような抜け道で、それが使えれば光よりも速く移動することができるとされています。紙、すなわち2次元の平面をたたんでから鉛筆で穴をあけると、紙のある場所からある場所に通り道を作ったことになりますが、これに似ています。
もっとも、三次元における穴ですから、球形の穴をしていて、その向こう側には宇宙の別の場所が広がっているということになるわけです。この仕組はカール・セーガンの「コンタクト」でも用いられています。
「インターステラー」においてはブラックホール周辺や、ワームホール周辺の光のねじ曲がり方も、なるべく正確になるように計算が行われていますので、奇妙な風景にも理屈があると思ってみるといいでしょう。
傑作と好きな映画は違う。
たとえば、「シェーン」は傑作だろうが、私はあまり西部劇は見ない。
逆に、「愛は限りなく」というB級イタリアカンツォーネシネマは私の好きな映画のナンバー1。
昔夢中で見た、「宇宙家族ロビンソン」もまた、そういう映画のひとつ。
そんなように、人それぞれ、好きな映画があるのだと思う。
好きな映画とは、何回も何回も見たくなり、また、見てしまう映画である。
ところで、傑作でありながら、大好きな映画というのもあり、私の場合は、
「2001年宇宙の旅」や、「ブレード・ランナー」や、「惑星ソラリス」や、「コンタクト」というシネマがそれらにあたる。
私が男性だからか、すべて、SF映画。
サラリーマン時代は、日々の人間関係のしがらみやら、煩わしい細かなストレスなどから逃れるためにだろうか、科学についての本を読み、広大で巨大なる宇宙について想像をすることが一番の楽しみだった。
傑作でもある、たとえば、「ドクトル・ジバコ」などの映画を見たりして、ロシアの当時の、時代考証の衣装やら、食べ物やら、建築などにイマジネーションを羽ばたかせ、素晴らしい映像と音楽に身をゆだねるというのも、楽しきひとつの映画のジャンルでもあるけれども、SF映画というのは、「人類の夢」を、ある意味叶えるというよくも悪くもimaginationの極地ともいうべきものであり、映像とアイデアが必須なので、なかなか、傑作はできない。
これまで、たくさんのSF映画を見てきたけれども、ほとんどが、ガッカリしてしまうことも多い。
だったら、大好きなフレドリック・ブラウンの小説を珈琲でも飲みながら読んでいる方がずっとまし。
ところが、この「ゼロ・グラブィティ」。
脳は「新しいもの」が大好きだということを裏書きするように、脳にビンビン、刺激を与えてくれる。それもまた、ただの最近のはやりの効果効果だけの、画面づくりではなくて実に美しい。
私はいつも書いているように、閉所恐怖と、高所恐怖の毛があるうえに、目眩恐怖でもあるので、この映画の中でのサンドラ・ブロックのようにぐるぐると、あんなに高いところで、たったひとりで回転したり、息苦しくなるような狭いロケットの部屋の中で、暮らすなんていうことのできない人間だからか、・・・・見ていて、かなり息苦しさを感じてしまいまた、目眩をおこしそうになる。
この監督アルフォンソ・キュアロン。これ一作だけでも、映画史に残るかもしれない。
サンドラ・ブロックも、wikにあるように、「2001年9月11日に起きた米同時多発テロの支援として、赤十字に100万ドルを寄付をした[13]。
2004年に発生したスマトラ島沖地震・津波被害に際し、医療用品にあてるため再び赤十字へ100万ドル(約1億500万円)を寄付した[14]。
2010年に発生したハイチ地震の後、ハイチの首都ポルトープランスでの救済活動を行う国境なき医師団に100万ドル(約9200万円)を寄付した。国境なき医師団を選んだ理由について、「この大惨事に巻き込まれたハイチの人々のニーズにすぐに対応できる方法で寄付金を役立ててもらいたいと考えました」と声明を出した[15]。
2011年3月11日に東日本大震災が発生した際、ハリウッドの俳優の中で真っ先に義援金として100万ドル(約8000万円)を寄付した。のちに当時を振り返り、「幸運にもわたしはそういう支援できる環境にあるから、やるべきことを行っただけ」と行動に至った経緯を明かした。義理の兄弟に日本人とアメリカ人のハーフがいるというサンドラは、自身が行った寄付について「これまで意味をなさなかったお金が、必要とされる場所で理にかなった使われ方をしただけなの。またそれを寄付することで、新たな息吹が目覚めるとも思ったわ」とコメントした。また、「日本人であろうとなかろうと、わたしたちはみんなつながっていると思っている。もし、同じような被害をアメリカが受けたら、日本はきっと同じことをしてくれるとも信じているわ!」と話した[16]。」
イメージからすると、私はこれまで見たなかでは、サンドラ・ブロックのインパクトは、例えば「スピード」とか、
「プラクチカル・マジック」のイメージが強く、さらにいえば、「幸福の隠れ家」の彼女が一番好きなので、wikそのままの、人類愛が深い女性、優しく、情感あふるるという印象だったけれども、
今回の役柄のなかで、その気質をぐっとぐっと、渋く押さえて、ひとりのおんな科学博士に成りきっている。
カール・セーガン博士の遺作でもある、「コンタクト」のなかで、ジョディ・フォスターが演じた理科系女子に通じていて、そこが私の好きなツボになっている。
どんな絶体絶命の逆境におかれていても、なんとか生き抜こうとするまさに「女性の本質=生命力」の化身となりきるところと、赤ちゃんの声や犬の声にふと死んだ娘に会おうと思って酸素を減らしていくシーンなどなど、サンドラ・ブロックの相反するアンヴイヴァレンスな気質を上手に、引き出しているし(冷静と愛のパッション)、それだからこそ、私に不思議な感銘の余韻を与えることができたのだし、彼女サンドラは、結局はすごいあたり役を演じきってしまうことになったのではないだろうか。
「幸福の隠れ場所」と「ゼロ・グラブィティ」をこれから続けて再視聴する予定。
ベストセラーも読まない。
人が読まなくなり、話題にしなくなった頃に、読み始めるへそまがりの私。
このシネマも、その映画の中のひとつであり、それが正確なる感銘を味わえる。
ひとり部屋で休息時間に見ていたが、思わず号泣してしまう。
気がつくと、夢中で、拍手をしている自分がいる。・・・・
日常生活にぼんやりしている人を、美しくも過酷な宇宙空間へ、思いっきり、ひきずりだすような圧倒的な力を有するシネマだ。
傑作でありながら、大好きな映画。これでまたひとつ増えた。
今夜もまた、カール・セーガン博士の「コスモス」をじっくり読みたい。
宇宙は、21世紀に遺された人類最後のイマジネーションの場所でもある。
かつての、冒険家達が、狂気のように地球を探検しまわったように、人類は、これから
数千年もかけて、宇宙のなかに飛び出していくに違いない。
この映画は、その想像を絶するような人類の未来の膨大なる冒険活劇のフィルムのなかの一枚なんだろう。
つらくても仕事は仕事。
やらなければならないのだから絶対に逃げ出すということはアドバイスしないわ。
それは、試練であり、乗り越えないと人は成長できないから アン・ハサウェイ
FIN
愛を描くシャガールがピカソは愛を知らないと言った・・・光 恋と笑 横尾忠則
やはり、ぶったおれてしずかにしていると映画よりも、音楽や本になってしまいます。
ここ最近見た映画は、マルチェロ・マストロヤンニとソフィア・ローレンの映画を比較しながら、笑いながら、泣きながら、考えていました。
ひとつは
「過去現在未来」。
昔のイタリア映画はなんと楽しく、笑えるのでしょうか。とにかくたくましい。
「ナポリのアデリーナ」
復員後失業中の夫カルミネ(マルチェロ・マストロヤンニ)に代わって妻アデリーナ(ソフィア・ローレン )は闇タバコの商売で一家を支えていた。しかし未払いの罰金を徴収に来た役人を追い払った為に逮捕されることに 、相談した弁護士から「妊婦は出産後半年間まで逮捕されない」と助言され夫婦は子作りに励むのだが…
「ミラノのアンナ」
社長夫人のアンナはパーティーで知り合った青年レンツォとドライブに出かけた。 ドライブ中アンナは裕福ながらも心が満たされない不満をレンツォにぶつけて、 二人で遠くへ行こうとレンツォを誘う。
「ローマのマーラ」
神学生のヴィンチェンツォは休暇のため祖父母のいるローマのマンションに遊びに来た。 ヴィンチェンツォは隣に住むコールガールのマーラに一目惚れするが、祖母はマーラを嫌い悪態をつく 。ヴィンチェンツォと祖母は喧嘩をして仕舞いには神学生を辞めるとまで言い出す。 祖母は孫を説得して欲しいとマーラに頼み込み、頼まれたマーラは祖母にある約束をする。
妊娠していれば、警察にぶちこまれなくてすむ。
それなのに、妊娠していないということがばれる。
そこで、ローレンは、最近元気のないダンナの親友に子づくりをしてくれと
必死に頼む・・・刑務所にぜったいに生きたくないからだ。子どもが6人もいるというのに。
笑える。
しかし、最後には、そのぎりぎりの刑務所にははいりたくないという彼女の心が、泣きながら、やっぱり、ダンナでなければ嫌だと呟かせる・・・・・・笑って泣けるシーン。
マルチェロの本を30年前頃に神田で手に入れた。
理由はなく、ただ、安かったから、リュックにつめこんでたまにペラペラ見ていた。
その彼が、これだけ今のイタリアを代表する俳優になるとは、まったく想像していなかった。
若い頃からアニタ・エクバーグ、ソフィア・ローレン、フェイ・ダナウェイ、カトリーヌ・ドヌーヴなど多くの女優などと浮名を流したが、結婚は生涯で1度、1948年にイタリア人女優のフローラ・カラベッラとのみであった。しかし後年マストロヤンニはマスコミのインタビューで、「本当に自分が心底愛した女はエクバーグとドヌーブの2人だけだった」と語った。
子供
妻のフローラとの間に一女をもうけたほか、長年の愛人でフランス人女優のカトリーヌ・ドヌーヴとの間にも一女(女優のキアラ・マストロヤンニ)をもうけている。なお、『プレタポルテ』(1994年)など複数の作品でキアラと共演を行った上、ドヌーブとキアラの母子は晩年のマストロヤンニの看護も行い、臨終にも立会っている。

昨日、「プレタポルテ」は注文した。楽しみである。
もうひとつは、「ひまわり」。何回みたことか・・・
日本人は、良くも悪くも、見た目=美=あはれ=姿(小林秀雄の言葉)を大切にするから、
この「過去現在未来」よりは、「ひまわり」の方が、好きな人が多いと思う。
しかしながら。
人生はとは、ひとつのコインの裏表なのだと思う。
したたかでなければ人生は生きては行けないが、純粋がなければ生きて行く意味もない。
このふたつの映画を、同じ俳優つまりソフィア・ローレンと、マルチェロ・マストロヤンニで、見るからこそ、楽しく、また、興味深い。
ソフィア・ローレンは、先日、日本に来ていて、「ひまわり」を見て泣いている人を見て、ひどく感動していた。かつて、同じような戦争体験をし、貧しく、悲惨な生活をおくってきた国民同士だからこその、共感かもしれない。
淀川さんは映画をつうじて、ものを「考えた」人だとおもう。
マックの「think different 」ではないけれど、いくらたくさんの映画をただ見ても、たくさんの本を速読しても、「考える」力は養えない。
やはり、渡部昇一氏が言うように、真夜中に、ひとり、「ウィスキーをちびちびやるようにしてモノをコトを考えている人」が、すごい人なのだとおもう。
あるいは、無名であっても、ひとりしずかに日曜日にでも絵を描くためにキャンバスを向かうような人・・・・・・対象そのものを静かに観察して、手指で脳で感じたことを、写して行く訓練をする人・・・・・・ 。
だから、私はいつもいきあたりばったりに、若き頃に乱読・乱鑑賞・乱試聴した文学映画音楽漫画絵画をその日の自分の胃袋の好き嫌い・体調にあわせて、食べて行く・・・。
朝こんな曲を聴いて、いろいろ考えていた。
「待ちくたびれた日曜日」
(作詞:小園江圭子、作曲:村井邦彦)
今。こんな歌は、若い人はどういうふうに聞くのだろうか?
個人的には、もしも、私が女だったら、こんなように相手を迎えてあげたいなと
おもう。
「あなたの好きなアネモネを、さかしておいたのに」
「お菓子もこんがりやきあがり、・・・」
時代的には、おそらく、男性が威張っていた??時代だから、こんなつつまやかしい女性の歌ができたのだろうが、個人的にはいつの時代でも、このような女性というか、人は、愛されるのだとおもう。
この歌は、「去年の人とまた比べている」と女性の心の変化を強調しているけれども、
歌っている歌手が、まったくそのタイプとは逆の、中森明菜や百恵ちゃんだからいいのだと思う。
すれっからしの、ヤンキーだったら、聞きたくもない歌だ。
この後、しだいに、「男に尽くす女の像」が、その逆に、「おんなに尽くす男性の像」に人気がでてきたように思える。しかしながら、個人的な意見だけれども、男も女も、
やはり、わがままで自己中心的な人はいつか滅んで行く・・・・・・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・
こんなアホなことを考えているうちに、時間はどんどんたっていく。
朝は、光が、入る時間がきまっているので、やることが多いのだから、・・・
今、一番興味のある「詩」と、「画像」のコラージュについて考えながら、
緑茶をがんがん飲む。アトリエの窓から入る自然光は二時間くらいだから、少なくても、
一時間は描きたい。
・・・
机の隣に積んである数百冊の本を、すこしずつ、写真をとったり、読んだり、イメージしたり、付箋をはりつけたり、そのまま、アカボールペンでカンガンと記録したり、・・・。
趣味のレコードは、井上陽水を今は聞いている。
「飾りじゃないのよ 涙は」
私は泣いた事がない
本当の恋をしたことがない
誰の前でもひとりきりでも
瞳の奥の涙はかくしていたから
いつか恋人にあえる時
私の世界が変わる時
私、泣いたりするじゃないかと感じている
きっと泣いたりするんじゃないかと感じている。
この「感じている」というのがいいですね。
中森明菜のバージョンも好きですが、ききくらべると最高です。

ブラッジャックのピノコが好きなので、朝からめずらしく着物姿の彼女がかわいいな、と見ていたら、朝曇っていた岩見沢市、なんと昼頃から晴れてきた。雑用も終わっていたので、この「奇跡のような光」を自分のものにしたいというムラムラとした欲望が・・・
全身にこの光をあびたい!!!!!!!!!
(安スマホですので、360角度にひろがる、この地球の丸さと円球のひかりの渦は感じられないとおもいますが・・・北欧ではたまにこんな日があります。雪の粉がきらきらしています。)



正月。
昨日は、すばらしき晴れでした。
光が、岩見沢市のすみずみにまで、溢れ、雪やつららや屋根から舞い散る雪の粉までが、ひかりかがやき、もうこれは「すべてオレのものだ」とばかり、散歩していました。
自然の素晴しいところは、心の中や魂のなかで、感動した美しさは、そのままそこに残りますから、そのような気持ちの余裕がある人ならば、私と同じような気持ちで昨日をすごしたとおもいます。
ひさびさに、血圧検査。
異常なし。
これにすこし油断して、好きな珈琲をちょっぴり飲みながら、大好きな多数手観音像の絵を描いていました。
幸福な時です。
しかも。散歩の途中でいつもの小さな本屋に寄ると、
芸術新潮 2016年 01 月号 [雑誌]/新潮社
¥1,550
Amazon.co.jp
が並んでいるでは在りませんか。一冊のみ。
あわてて、買いました。雪がふりはじめていましたから、大切にリュックにいれて・・・・。
ぬれないように。
そして、光あふるるココ北欧の自然の中の散策というか、ほっつきあるきが、二時間ほどで完了したあと、ちらり、と見て、そのまま書庫へ。
あとで、じっくり見る予定。楽しみ。
最近はまっている、「すんきそば」。
買うと、バカみたいに高いので、自分で、すんきを作っては、あじを確かめていましたが、キャベツでもいけますね。
昨日、すんきのキャベツで、焼きそばをつくりましたが、美味いコト美味い事!!!!!!!
31日に、はやめに、神社へ行くと、誰もいなかったので、さすが田舎。
12時近くになって再度、でかけると、そろそろ人のではいりが。
神社に入ったら、まず御手洗(みたらし,水舎(みずや)とも)で左手から手を洗い、正式には手 ... 拍一礼」といって、二回おじぎをした後、2回柏手を打って、最後にもう1回おじき。
といっても、むちゃくちゃ流です。
心をこめましたが。
おみくじなどをひいて、賽銭。
好きなモーツアルトとバッハざんまいの元旦。
雪かきはしましたが、おせち料理は三日分つくりましたので、
三日間は、好きなことをやらせてもらいます。
すこし、テレビをつけると。やはり。げんなり・・・・・・・・・・
学生マラソン以外は、まったく駄目。
駄目な理由を業界人が話し合っていたが、まるで、漫才。
世界はもうすでに100チャンネルを超えたメディアをたくさん持っているわけだから、
もう「きめられた」「限定された」「つまらん」テレビは見たくない。
どこのチャンネルを見ても同じ顔、顔。
はやく100チャンネルになって、好きな番組だけを特化してみたい。(ネットが今そのかわりをしてくれていますが、・・・・・)
個人的には、「ニュース番組」を深くみたい。
しかも、意図的に編集されたものではなくて、事実に肉薄するもの。
共◎通信ニュースなんか、あれなにかと思いますね。朝日同様ぜったいに信じられないメディア。
野球賭博。
相撲の暴力。
サッカーの世界の詐欺。
自民の油断と分裂。
ロシアの好き放題、中国の好き放題。
アメリカの世界の警察放棄。
埋もれて行く国。
巨大化していく台風に、水害に、干害。
絶滅種。外来種にやられっぱなしの日本種。
経済が人生の基本だというのは理解できなくもないけれども、そのために、いろいろなことが
犠牲になる。
マスゴミなどは、10年くらい前には、「フリー」「アルバイト」的な若者の生き方を絶賛して、起業にしばられない新しい生き方とか言って、もてはやしてから、はや10年。
今や、マスゴミが、なぜ非正規社員が増えないんだとか言っている。自分のやってきたことも忘れて。
自民党の談合政治・派閥政治を批判してきたマスゴミたちもまた、それをぶっこわした小泉首相や安倍首相に対して、派閥から文句がでている・・・などと偉そうにのたまう。
マスゴミはほんとうにこまったもんだ。
ところで。
経費をだまして号泣して記者会見するバカな政治家がどんどん増えている。
国民をバカにしているとしか思えない。
かとおもえば、これらのことをさかんに発しては、われわせれはぶれないとか、偉そうに言っている、共◎党。
2600年の日本文化を認めない頭でっかちのマルクス主義政党に、感情と大義に熱い、日本人の誰が投票するか。
ことしの希望は、はやく、インチキ自民党と、本物の自民党が別れて、しっかりした、日本をつくりあげてもらいたいと思う。
そうしないと手遅れになるぞ。
麻薬を子どもに飲ませるバカ親。
タバコをふざけて子に飲ませてFBにアツプする狂った親。
いじめの定義をはっきりしないから今回の事件はいじめではないと、頑固で、古くさい体質、子どもの魂のことをまつたく考えない今の学校の多く。
こんな学校なんか行かなくてよいのだよ。
人生なんかは、ひとりでも、勉強できるし独学こそが真の学問だ。
自分を磨くのに金もかからない。
他人の目をきにしないこと。
親も今や、子どもを金を産む卵としか考えていないバカ親も多いので、
これも、その場合は家出をすすめる。
そこにある危機。
たしかに、ひとりではなんにもできないわけだが、自分が世界にできる最大の貢献は、ただただ、普通に当たり前のことをあたりまえに最大限に一生懸命、自分ひとりで、やるだけのこと。
主義政党思想はなんであれ、私は「日本を愛する人」であれば、とりあえずは、話しはできるし、認める。
陛下の映像。
ノーベル賞関連の話し。特にニュートリノ。
元素番号のニュース。
・・・・
テレビをちょこっとつけたら、古本屋の世界をやっていて、めずらしく、興味深かった。
リアルでのお客様との出会いを大切にしているとのこと、それは納得できるのではあるけれども、ヤフーに出品するロシア語の古書についての言葉はちょっと気になった。「本そのものよりも、装幀で売るんだ」というようなニュアンスのことを呟いていた。
古いなと、思ったけど。(もうみんなやっているし)
竹村健一の言葉ではないけれども、マクルーハンが言うように、もはや、古本を買う人も含めて消費者が商品の中身そのものよりも、パッケージデザインなどに惹かれて買ってしまうというのは、あたりまえすぎる・・・・。
そこから、はじまるはずでしょう。
常連のおじいちゃんが、かつて大学かどこかで学問した、ロシア語の作家を見つけて、顔を近づけて見ていて好ましく感じた。いつでもどこでも、このような人はいるのだと確信する。小林秀雄氏がいつも書いているように、チープなものよりも、難しいもののほうが、人間の脳を強く刺激するのだと思う。
入門編としては、装幀でもなんでもよいのだけれども、本質的に学問好きな人がこの世に増えることが望ましいのではないだろうか。
では、そのためには何が必要か・・・?
答えは、子供に読書を強要する前に、大人が本を読む事である。
まるで、ひとりの女を愛するように本を読むことである。
そして、そんな環境をつくるためにも、テレビのスウィッチは、なるべく消す癖をつけることだろう。
寺田寅彦氏の本を読んでいてもそれを感じる。

私は、映画と、絵画とクラシックと、jazzと、漫画と、文学を、区切ったりはしないし、
違う範疇とは思わない。
むしろ。いろいろ混じっていた方が楽しい。
寺田寅彦氏のエッセイなんかは、ほんとうは映画化されると良いと思う。
谷口ジローが漫画にしても良いと思うくらい。(孤独のグルメはいまいち。もっち立原正秋氏の小説を読んでもらいたい・・・じつに、ママや客や料理人との関係をときめいて書くのが巧い)
描いていることをむずかしいそうだが、本質的なところから、日常のひとつひとつの小さなことをきりとって、わかりやすくその感銘を描いてくれている。
個人的に最近強く読んでいる本をすこしあげると。
もっと本気で遊びなさい。―遊びかたひとつで人生が豊かになる (サンマーク文庫)/サンマーク出版
¥503
Amazon.co.jp
『仕事と遊びは掛け算でいけ ゆきづまった脳の働きを刺激する本』大和出版 1987
『一流の人間は女の本心が読める "しつけ"のよさで決まる女の能力・26のキーワード』大和出版 1988
などの本もあるけど、この本「遊びかたひとつで人生が豊になる」が一番好き。
龍角散社長だけあって、言う事がでかい。
最近のあたまでっかちで、女の心理もまったく共感できないような、糞まじめ学者などはおよびもつかない。・・・・・・・・・
よみがえれ、バサラの精神―今、何が、日本人には必要なのか?/PHP研究所
¥1,296
Amazon.co.jp
これは名著だと思う。
上にも書いてきた今そこにある日本の危機を救えるヒントがある。
死=生。
これをある意味ひとつの冗談のようにしてとらえて、のりこえていきすさまじい生き方。
かつて日本人が実際にやっていた生き方。
ヒントにならないはずがない。
ひとにめくるめく感動を与えるものは、合理で計算されてたくみにつくられた東京都庁ではなくて、ひとつの霊のために人智を総動員したまさにバカアホ的行為=ピラミッドなのだから。
「無秩序の読書」
この人はあまり知らないけれど、共感できるところがある。
小林秀雄氏と同じようなことを言っている。
大正的体系的読書なぞ、否定して、自分なりの好きな好きなどうしょうもないくらいの宇宙を見つけて行く・・・・
三浦じゅんのように。・・・
ちょっとおもしろいと思えました。ヒントもらえます。
彼が言っていた、
高円寺の腐ったような本屋。知っている。
私は、ここで、ドストエフスキーの白痴を買ったところですが、
モラヴィアをここで彼が発見したということを聞いて、おおおおっ、と思いました。
やはり、居る人はいるものですね。嬉しくなってしまいました。
本は、自分との愛の偶然=必然の交流ですからね。他人がなんといおうと、嫌いなものは嫌いなんですよね。
私は自分の書庫の本は、すべて、三島由紀夫・渋沢竜彦・つながりで、いもづり式に揃えたものです。
・・・・・・・・・・・・
不思議と三島由紀夫氏は、「音楽」はあまり得意ではなかったようだ。好きな音楽家は、ワーグナーだけだったし、カラオケでは、黒猫のタンゴを歌うだけだっよう。
ただ、彼の、視覚的な彼の好きな画家はきになるところ。
少し、三島由紀夫氏の好きな画家を調べてみました。
油絵の構想を練りつつ、構図を何回も描きなおしていて、疲れたのでぼんやり澁澤龍彦氏の追悼号を読んでいたら、mizueのNO945号の彼のエッセイに、三島由紀夫氏の愛したデカダンスの作家が紹介されていたので、調べてみた。
まあ、皆知っている作家ですが、ここに並べて確認してみよう。
三島由紀夫氏のデカダンス論については、その作品などを読んでいただくとして、これらの彼好みの絵は、まあ、いつも私が言っているように「好き嫌い」は、いわゆる傑作・名作の視点とはまったく違うものですね。
イギリスの某作家が言っているように好き嫌いという人間の本能的な原始的な行為こそ、彼の血や生の本能などがそこに露呈されているのかもしれないので、しっかり見ておくことにする。

これらの絵は、私も専門でもないし、詳しくもないのだが、澁澤龍彦氏は「大蘆芳年」と書いているが、この月岡芳年のことなのか?
ただ、この絵を見ていて、この「残酷趣味」「怪しさの表現」などを見るとそうだと私は勝手に思っているが、誰か詳しい人に聞きたいものだ。


竹久夢二もまた、三島由紀夫氏が好きだった作家。
だいたいが、日本画家は、大家になって「花と鳥」しか書かなくなり、マンネリして、つまらなくなることが多いし、そのあたりにたいするアンチ・テーゼとしての岡本太郎氏や、横尾忠則氏の存在価値があるのだとしたら、この竹久夢二もまたその部類に属する異端の作家だと思う。
文壇はつまらない、臭い、といつも言っていた三島由紀夫氏、偽善や「生温さ」を嫌い、世間で認められていなくても、自分の嗜好と合えば「息」を吹きかけていた。
確か、詩人の春日井健氏だったか、三島由紀夫氏に褒められて、嬉しい反面ものすごい緊張したというようなことを書いていた記憶があるが、違うかもしれない。

そして、ビアズリーは、有名ですね。
しかしながら、当時はさほどの評価がなく、ワイルドからも敬遠された時期もあったらしいですから、
まさにビアズリーは時代をさきどりしていたのだと思う。
ワイルドの嫌われ者の栄光という言葉も三島氏は確か好きだった筈。
モンス・デシデリオは17世紀のナポリの作家。
廃墟ばかり描いた作家らしい。

あまり情報はとれませんが、なんとかこれくらいの情報です。聞いた話では、澁澤龍彦氏が三島由起夫氏に教えたと聞きました。
フランス幻想作家というグループがあることはうすうす聞いていましたが、やはり、
イタリア・フランスのラテン気質の画家達・・・廃墟をテーマに描いていました。
デシデリオの作品は少し見ましたが、このアラン・マルゴトンという作家の作品は初めて見ました。
彼はデッサンにこだわる画家です。
確かディマシオにかなり影響をうけたのではないでしょうか。
三島由紀夫氏にぜひ見せたかった作品群です。この女性のポーズも 世界的な奇書の「薔薇刑」の表紙によく似ているような気がします、そう感じるのは私だけでしょうか。

三島由紀夫氏が大好きだった、作品そのものはここに資料としてあげておきます。
ネットでは画像が探せませんでした。
また見つかり次第、スキャンして、載せたいと思います。
ビアズレイの「僧侶」、竹久夢二の「長崎十二景」から「阿片窟」、大蘇芳年(1839~1892。幕末から明治初期にかけての浮世絵師。月岡芳年)の「英名二十八衆句」から「笠森於仙」、モンス・デシデリオの「火災」の四枚。
ところで。
ピカソと、シャガールと、マチス。
この三人はおもしろいですね。
個人的には、バルテュスと、シャガールと晩年のマチスが好きだな。
特に、晩年のマチスの協会の絵ときたら・・・・・・

もう手足も完全に動かせなかったから、ながい杖のような、棒にチョークをつけてかいたものですね。
マチスの作品というよりも、むしろ、ほぼ天使になりつつ脱皮していたマチスの作品かな。
日本では、明治と大正の挿絵画家たち。みんな。
中原淳一も素晴しい。
金子さんも自分のスタイルがありましたね。
金子さんは、中原さんのようにあまりにもポピュラーになることをいつも極度に恐れていましたが、
結局は、中原さんの詩情あふるる絵は、古くなりませんね。おもしろいものです。
ピカソの妻はartはエニグマだと書いているし、ピカソ本人も私の絵は共産主義の絵だろうと
言っていて、それを知ってから、私は個人的にはピカソからはなれていった。・・・妻の言葉は大好きだが、ピカソの思想は興味なし。ただ、あれだけ、絵の構造と色彩を駆使したことがすごいのだと思う。
ピカソの絵には、愛がない、いつもシャガールはそう言っていたそうです。
そりゃあそうでしょう。キャンバスの白の強迫観念にいつも悩まされていたピカソにとってみれば、町で歩いている美女も皆、自分のアートのキャンバスの白の強迫観念から救ってくれるモデルたちですから。
シャガールは、もっと普通ですね。良い意味で。
国を愛し、自然を愛し、妻や家族や友人を愛して、個人的には個人の心理や思想を超えたところまで到達した昇華絵画を描きたいと思っていた事でしょう。
・・・・
日本ではまだまだ、真面目な国ですから、クリムトやシャガールは人気がありませんが、
もっともっと評価されても良い作家達です。
・・・・・・・・・・・・・
30代の頃。
パルコで働いていたので、昼飯の時間ともなると、本屋へ飛び込む。
もちろん。
画集をぱらぱらと見るためだ。
この頃、よく見たのは、石岡瑛子・・デザイナーの佐藤氏。
あとは、やっぱりこのエリック・フィッシェルだろうな。
A Review of ‘Eric Fischl - Beach Life,’ Eric Fischl: Early Paintings/Skarstedt Fine Art
¥3,844
Amazon.co.jp
Eric Fischl: Paintings and Drawings 1979-2001/Hatje Cantz Pub
¥4,011
Amazon.co.jp
Dive Deep: Eric Fischl and the Process of Painting/Pennsylvania Academy of the Fine
¥5,125
Amazon.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・
{エリック・フッシェルクリップ・・・}
自分では、特に、彼の、「バッドボーイ」という作品に惹かれた。
影響されて、何作か、書いたものである。
横尾忠則氏も彼から何か学んだような形跡がある。
絵の上手い下手を超えて、理性をひょいと乗り越えた感覚がすきだった。
確かに、デイビッド・ホイックニーも嫌いではないけれども、飽きる。
ワイエスは飽きない。そして、このフィッシェルも、原始的で、飽きない。
この絵のテーマは、たしかに、映画「卒業」と同じなんだろうけれども、そのような、
説明や、分析を、無視して、不思議な、静けさもあると思う。
日本でいえば、横尾氏よりも、私は、つげ義春に近いと感じる。
感じるだけなので、違っているかもしれないけれども、私がそう感じるので、それで、良いのだ。
見たい映画が、机の横に積んである。
ああ、はやく、見たい。・・・・・・・
体の調子もよくなってきたので、すこしずつ、絵画と漫画と映画と外国語学習と散歩、がんばろうと思う。
序の舞
小早川家の秋
新源氏物語
青い沼の女
蔵
蔵の中
続忍びのもの
大病人
大菩薩
中心蔵
天守物語
桃太郎サムライ
豚と軍艦
目が悪くなって来たので、眼鏡もなおしてもらった。
パソコンも、五年もたつと、調子がわるくなって、見ていると途中でぷつんと切れたりもする。
しかしながら。
それらすべてをふくめて、楽しむことにしている。・・・・・・・
人生では、どんなことであろうと、すべてが、肥やしになるのだからこそ。
「負け惜しみではなく、女の人のことを知りすぎた」 淀川長治
FIN
男と女の相性「あした来る人 」深津絵里 CM 「女の子ものがたり」「悪人」
「映画に説明やオチなど必要ない」(ミヒャエル・ハネケ)
「あしたくる人」見ました。
原作は、井上靖です。
監督は、 川島雄三 。
昔の映画ですので、白黒ですし、スピードもリズムもなく、じっくりじっくり、物語はすすみます。
でも、そこがいいですね。
男女には相性というものがあると思います。
反撥したり、くっついたり、理由はわかりませんが、まるで磁石のように、
プラスマイナスが人にはあるようです。
この映画もそんな人間模様を、丁寧に丁寧に、描いているのだと思います。
物語資料から
実業家梶大助のホテルへ彼の娘八千代の紹介で、曾根二郎という青年がカジカの研究資金を出して貰うためにやって来た。心よく迎え入れた梶も、決して金を出すとは云わなかった。八千代は夫克平に不満を持っていたが、その夜も遅くなって一匹の小犬をかかえて帰ってきた彼と冷い戦争をはじめ、八千代は大阪の実家へ戻ってしまった。克平は八千代がいなくなってから、相棒の三沢やアルさんとカラコルム山脈征服の計画を実行しようとしていた。ある日例の小犬を見ず知らずの女性が連れているのを見つけた。なつかしさに近寄ると、それは洋裁店に働く杏子だった。八千代は梶に叱られて東京に戻ってきたが、克平の登山計画をなじった。梶の世話を受けていた杏子は、それが克平の義父とも知らず、克平と結婚したい旨打明けた。名前を云わなかったため梶も色々と杏子を励ますのであった。克平は鹿島槍登山に出掛け、直後新聞がその遭難を伝えてきた。早速杏子は遭難現場に急行したが、克平は無事で思わず二人は抱き合った。克平が帰宅したとき曾根が来ていた。その後八千代が余りに曾根をほめるのと、遭難のことに冷淡であったため、克平も感情を害したが、八千代は杏子と彼の仲を知ってのことであった。曾根の取持ちも空しく克平の心も最早八千代にはなかった。その頃杏子は偶然八千代に会い、克平が梶の娘の夫であることを知って悩んだ。克平は遂に山の征服の雄途に乗り出すべく羽田を出発した。結婚のことは最後まで云い出せなかった杏子だった。
上の資料の物語を読むより映画のほうがずっとおもしろいのは、井上靖の小説をじっくり読むのと、また、ヒロインなどの美しさに魅惑されながら、映画を楽しむという、まったく別の楽しみ方を私はしているからでしょうか。
監督の川島雄三。好きです。
いいんです。軽くて・・・・・・・
作風
日本軽佻派を名乗り、独自の喜劇・風俗映画を中心的に、露悪的で含羞に富み、卑俗にしてハイセンスな人間味溢れる数々の作品を発表した。
人間の本性をシニカルかつ客観的な視点で描いている作品が多く、弟子の今村昌平の作品ともども「重喜劇」と称されることが多い。川島の場合、脚本を担当した藤本義一が命名したとも、フランキー堺が呼称したとも言われる。今村がムラといった地方の土着社会に関心が移行していったのに対し、『洲崎パラダイス赤信号』や『しとやかな獣』に見られるように川島は都市に関心を持ち続け、都会に生きる現代社会の人間達をテーマの中心に据えていた。
作家・織田作之助と親交が深かった。一方で同郷の小説家としばしばみなされた太宰治は嫌いであり、太宰より織田の作品を読むことを薦めていた。また井伏鱒二のファンであり、強く影響を受けていた。「サヨナラダケガ人生ダ」という詩訳の科白を愛用しており、『貸間あり』の中で桂小金治にこの科白を言わせている。
死亡時、寝床にはインタビュー記事が載った中央公論と、次回作に考えていた写楽を主人公にした「寛政太陽傳」用の青蛙房版の江戸風俗資料が置かれてあった。[2]この映画で主人公写楽を演じる予定だったフランキー堺は、後年、篠田正浩監督で「写楽」を製作・出演。完成後の1996年6月10日にこの世を去った。
勧君金屈巵 君きみに勧すすむ 金屈卮きんくつし
満酌不須辞 満酌まんしゃく 辞じするを須もちいず
花発多風雨 花はな発ひらけば 風雨ふうう多おおし
人生足別離 人生じんせい 別離べつり足たる
この漢詩です。
井伏が、この詩を自分の好きなように、訳したのが、有名になりました。
コノサカヅキヲ受ケテクレ
ドウゾナミナミツガシテオクレ
ハナニアラシノタトヘモアルゾ
「サヨナラ」ダケガ人生ダ
月丘夢路は、三島由紀夫氏の「美徳のよろめき」にでているところも、シンクロの糸を感じます。
新玉三千代は、そうなんです、「霧の旗」に出ていました。なつかしい。

まるでフランス映画、ヌーヴェルヴァーグの作品を見ているような、白黒の美しいシネマ。
何回もテレビでも放映されたようで、筋書きそのものは誰でも知っている復讐もの。
私は、三島由紀夫が、「日本文学全集」を川端康成などと一緒に、作家を選んでいる時に、松本清張を断固として拒んだということをふと、思い出した。
三島由紀夫は、「あるべきもの・ことを描くのが小説」というのが持論。
松本清張は、「現実の裏側にあるもの・ことをえぐりだす」のが得意だったから、小説に対する美意識が違ったのだろうと思う。
そのことが悔しくて、松本清張は、のちほど、とある賞を獲得したとか。
まあ、そんなことはどうでも良いのだが、私は、倍賞千恵子の演技に感心した。
獲得が山田洋次で、カメラも、撮影:高羽哲夫とくれば、「寅さん」を連想すると思うけれども、「さくら」のイメージで、最初、私はこの古い日本の白黒シネマを見てしまった。
素晴らしい!!!! 倍賞千恵子。
この作品の少し前に作られた松本清張の、「張り込み」にも感心したが、やはり、印象に残っているのは、高峰秀子の美しさ。
現代の日本映画の女優達も、皆美しいけれど、やはりシネマ界にも、歴史があり、女性美の長い歴史があってこそ、今の女優達がいるのだと再認識。
倍賞千恵子は、フランスの、ブリジット・バルドーや、ジェーン・フォンダや、たちにも、ひけをとらない。日本の美だ。


たしかに、ブリジット・バルドーは、わたしたちの時代のアイドルだったし。
ジャンヌ・モローの独特の美も印象深い。
黒衣の花嫁は好きだった。
雨の忍び逢いも良かった。
フランス映画と言えばやはり、この女優。
見事なフランス人の美しさがある。
でも、やっぱり、私は日本人の女性美が良い。
タモリではないけれど、吉永小百合を超える日本女優はまだいないと思っている私だ。
◎霧の旗物語資料から
殺人事件の容疑者として逮捕された兄の無実を信じ、高名な弁護士に弁護を依頼する妹。 しかし、貧しさゆえに断られた妹は弁護士に復讐を誓う。 松本清張原作の映画化。山田監督初のそして唯一のミステリー映画。
◎資料
映画『張込み』の製作以降、著者と面識のあった橋本忍の発言によれば、当時著者は、アラブ人男性のフランス人医師に対する復讐を描くフランス映画『眼には眼を』を観て非常に感心し、こういう(趣向の)ものを書きたいとさかんに言っており、そうした発言ののちに著者が本作を執筆したとされている[2]。
本作は単行本化の際、最終回連載部分に原稿用紙30枚分の加筆がなされた。特に大塚の懇願に対する桐子の態度の描写や、第二の殺人に関する大塚の推理部分、桐子が検事に宛てて送った手紙の部分が大幅に加筆、精緻化された[3]。
詩人・翻訳家の天沢退二郎は、小説の描写において、桐子の意識に入り込んだ描写と、大塚・阿部の意識に立ち入りつつ桐子に関して外面模写のみに終始する描写が振り分けられ、二つの異なる桐子像が小説内で峻別されていることを指摘している[4]。社会学者の作田啓一は、本作において大塚弁護士の側に罪があるとすればそれは「無関心の罪」であり、現代人の多くがひそかに心あたりのある感覚であると分析している[5]。評論家の川本三郎は、本作が発表された時期には、現在の東京一極集中に通じる、地方と東京の大きな格差が生まれていて、桐子の大塚弁護士に対する恨みの背景には、地方出身者の東京に対する恨み(と強い憧れ)があると指摘している[6]。
このあたりが、松本清張の良いところであり、悪いところ。評価が別れると思う。
シンプルにするのであれば、もっとユーモアを入れると良いと思うのだが・・・
原作:松本清張
監督:山田洋次
製作:脇田茂
脚本:橋本忍
撮影:高羽哲夫
美術:梅田美千代
編集:浦岡敬一
音楽:林光
ところで。
・・・・・・・・・・
最近このコマーシャル、なかなかいいな、と思ってみていました。シリーズもののCMです。
テレビもあまり見ないですし、ここ五年間は、多忙でしたから、女優の名前も浮かばず、・・・・・・・・。
アホです。
それで、調べてみると、深津絵里。
資料を見ると、なかなかおもしろいというか、ユニークな感じでしたので、
・・・・・・・・
それに、42歳にしては、かわいすぎる。

◎資料から
大分県大分市出身であり、『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』で1シーンだけ大分弁を話すシーンがある。同シリーズでは同じ大分市出身のユースケ・サンタマリアとも共演している。
映画『阿修羅のごとく』で酔っているシーンを撮影する際、実際にお酒を顔が赤くなるまで飲んで撮ったという。本人は酒好きであり「お食事を頂いているときにちょっと飲む程度。好きなのはシャンパン。酔っぱらうことはありません」とインタビューで話している。
JCBのCMで激辛トムヤンクンを食べるシーンで、スタッフが空のお皿を食べている演技をしてもらうつもりだったが「それではリアルさが伝わらないのでは?」と自ら提案し辛さ20倍のスープを涙ながらに飲んだというエピソードがある。
同じ事務所所属の福山雅治に自身の1月11日の誕生日に111本のバラをプレゼントしてもらったことがある。
女優の握力を予想するゲームにおいて、周りの予想を上回る32kgをだし場内を沸かした。
ドラマ『カバチタレ!』は、かつて『悪魔のKISS』で共演した常盤貴子が、「また深津と共演したい」という希望が叶ったドラマであり、話を聞いた時お互いが逆の役をやるのとばかり思っていた。
常盤貴子とはドラマで共演して以来仲がよく、プライベートでも一緒に遊んだりしている。天海祐希とも仲がよい。天海が30代の時、常盤も含んだ3人で「カッコよく楽しく生きる三十路会」を開いていた。
木村拓哉、福山雅治、田村淳、臼田あさ美、佐藤健、水川あさみ、星野真里など芸能人にファンが多い。木村拓哉は「深津絵里さん=女優。 優れた女と書いて女優。」と評している。また臼田あさ美は自身のブログで憧れているとコメント、同じアミューズ所属の佐藤健は原宿でスカウトされた際、アミューズが深津の所属する事務所だと知って芸能界入りを決心したほどであり、『恋するハニカミ!』にゲスト出演した際、「中学の頃からのファン」「ハニカミデートしたい」と語るほど深津のファンである。
三谷幸喜は深津を映画『ザ・マジックアワー』に起用した理由について、2007年(平成19年)に公開した映画『西遊記』で共演し会話をした際「感じが良かったから」だと話す。劇中で深津はアフレコではなく撮影時の生歌を披露しているほかエンディングにはロングバージョンも歌っている。このことについても「深津さんは歌でも芝居でもホントにカンの良い人でした。(アドリブも)深津さんは絶対に笑わない。彼女はNGも出さない。もう、鉄の女。絶対に崩れないタイプ」「耳もいいし、英語の発音も完璧。エンディングは圧巻でした」と評している(『ザ・マジックアワー』オフィシャルブックより)。
彼女が、主演している作品をとりあえず、2本。
「おんなのこものがたり」と「悪人」を見てみようと思い、まずは、ゲオへ。
「おんなのこものがたり」
2009年に封切りされたのに、今頃みている、わたし。
ということは、もともとは、縁のない映画だったんです。
でも、深津絵里のCMを見ていたら、自分の好きなジャンルではないのですが、見たくなってしまい・・・・・・・・
西原女史の自伝的漫画がもともとの作品なんで。
漫画家というのは、しかしながら、おもしろい職業だなあ。そう思います。
ある意味。女性の枠を、超えて、男性に近い考え方ができて、それでいて、女性のこころもありますので、かなわないところがありますね。
普通は、「女子の友情というものはなかなか続かない」と、言われているわけですが、
言われているだけで、私の妹なんかも、小学校時代の友達たちと今でも、月1くらいのペースで、食べたり飲んだりして仲良くやってますから、一概に友情はないとか言えないのでしょう。
作品にするわけですから、自分のリアルな過去の記憶をすこしばかり、小麦粉で膨らませてみたり、ひっぱったりのばしたり、小さく切ったりしていることは当然のこと。
ただ、残念なのは、深津絵里は、今現在で漫画家になっており、過去を思い出すという視点で、作品が出来上がっていますので、印象的には、なっちゃんという若き日のイメージは、
高原菜都美(現在):深津絵里
高原菜都美(あだ名はなっちゃん。高校生時代):大後寿々花
きみこ(あだ名はきいちゃん。高校生時代):波瑠
みさ(あだ名はみさちゃん。高校生時代):高山侑子
となっております。
私は、テレビが見る暇がないので、まったく、邦画やCMの女優達を知りません。
が、たまに、おっと思う存在感のある女優を見つけると、だれかな??と調べてみるだけ。
深津絵里さんもそうだったように。
この大後寿々花さん。
「サユリ」で、新人賞を獲っているんですね。それに、以前の記事で書いた「北の零年」にも出演していたとか言われると、えっ、まったく覚えていません。
あわてて、調べ直すと、子役でした。

「sayuri」の、小森和子賞は、すごいと思います。
きみこ(あだ名はきいちゃん。高校生時代)役の波瑠さん。テレビドラマでも、ここ最近がんばっていますね。
朝ドラの。
NHK連続テレビ小説『あさが来た』のヒロイン・白岡あさ役に決定したわけですから、これはすごいと思いました。
それに、役柄のきいちゃんは、死んでしまいますが、ドラマが変われば、また再生するところが、嬉しいです、再会できるわけですから。ファンにはたまらないでしょう。
おんなのこものがたりのなかの、詩のような描き方の映画で、ほんわりほんわかムードの映画でしたが、最後の三人のケンカするところ・・・・ここは素晴しいかったですね。
義父がいうところの、「人と違う人世をおくれるかもしれん」という言葉を胸に、なっちゃんは上京するわけですが、たしかに、たくましく、自分の限界をきちんと知って、自分の立場をしっかりと知っている友達達との・・・・・・・・距離感はたまらなかったでしょう。
あと、
高山侑子さん。
父親は、航空自衛隊新潟救難隊の救難員でしたが、2005年4月、訓練中の墜落事故で殉職しています。同年秋に防衛庁(当時)で実施された自衛隊殉職隊員追悼式に出席するため家族で上京した際、原宿でスカウトされたこと、・・・・
2008年、映画『空へ-救いの翼 RESCUE WINGS-』で映画初出演・初主演を果たしたこと・・・
2015年、「新・戦国降臨ガール」にて初舞台・・・・・などなど。
父親の追悼式でスカウトされたことや初主演映画が航空自衛隊を扱った作品であることに運命的なものを感じるそうで、「父に導かれたような気がする」と語っている。
深津絵里。
もう一本のビデオを見ながら、最初のシーンで、あれれ?
これ見たという感じでした。
記憶力というのはほんとうにあてにならないものです。
どうしようもないアホです。
しょっちゅう、一度見た作品をまた、借りてしまいます。
二度見るのは楽しいので、あまり気にはしていませんが、ボケはじまっているかも。
彼女は、この作品で、ふたつ賞を獲っています。
なかなかないことらしいです。
第34回モントリオール世界映画祭最優秀女優賞、並びに第34回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞(尚、日本アカデミー賞での最優秀主演/助演女優賞のダブル受賞は桃井かおり・大竹しのぶ・小柳ルミ子・倍賞美津子・原田美枝子・和久井映見・樹木希林に次いで史上8人目)。
映画が小説とするならば。
でも、CMも、なかなか素晴しい、一編の詩・和歌短歌。
こんな記事を書いておりました。記事まで書いているのに、すっかりわすれているんだからどうしょうもありません。
日本映画の売り上げが外国映画より多くなったという逆転劇から、数年。
今はどうなっているのか?
「フラガール」の監督だったから以前から見たかったが、見たい映画が多過ぎ、今頃見る。
レヴューを見ても、自分の気持ち・気分・鑑賞フイーリングと添うものがないというのは、やはり、映画は見る人によっていろいろな見方があると言うことだろうと、思う。
撮影笠松則通
美術監督種田陽平
美術杉本亮
装飾田口貴久
照明岩下和裕
音楽久石譲
音楽プロデューサー岩瀬政雄 、 杉田寿宏
主題曲/主題歌福原美穂
とまあ、資料にもあるように、かなりの画像のハイレベルシネマ。
切ない音楽のタッチや、切々と流れてくる音の迫力やら、雨の音などの効果も高いのが印象的。
これはやはり、映画館で見た方が良い映画かも。
深津絵里はまさに適役。妻夫木聡を完全に食っている。
不思議だが、私はなにやら、この映画の途中、深津絵里のキャラに日本人特有?の任侠映画によく出てくる「待つ女」の原型みたいなものを感じていた。
ただ、個人的な意見としては、小説とはまったくの別物としての映画としてコメントすると、この金髪男性がなぜあの娘を衝動的にでも殺してしまうのかがちょいと不明、理解できない。
ひょっとするとカミユだったか、太陽がまぶしかったから殺人をしたというような不条理な人間の悪の心理なのかもしれないが・・・
それにしても、普通の常識からこの映画の登場人物を見てみると、あの樹木希林が演ずるおばあさんの人物の設定からすると、とても、あのような殺人鬼の子を育て上げるとは思えない。
確かに、解体屋という職業のイメージから、彼の未来を暗示しているのかもしれないけれど、土木作業員やら解体屋やらの、世間的な信用のなさや、世間的な下位の職業として設定しているところに古さを感じてしまう。
離婚歴などの家庭、異性感からもたらされるコンプレックス、下位の職業などのいわゆる「環境」に、犯罪を犯す本質的な要因があるなどと、表現されるのは、どうも昔の「左翼的な発想」を無理矢理押し付けられている感じがしてとても嫌だ。
むしろ現代を表現するならば、あの非常にクネクネした、岡田将生なんかの方が、まさに太陽がまぶしいから人を殺したみたいなことが似合うかもしれない。
満島ひかりにしても、あの父親からあんなような娘が育つとはとてもとても思えない。
小さな頃に、父母が朝から必死に働いているような両親の後ろ姿を見ていると子供はぐれないと、よく言われる。
だからこそ、中流の、親が権威をかさに自分の正しさを子供たちに押し付けるような親が、子供をおかしくするとも言われているこのごろだ。
確かに、孤独な二人はそれを接点にして、要に引きつけられるということはあると思うが、どうも 、深津絵里と妻夫木聡が、それだけ、孤独だということがこちらに前半の物語だけからは、伝わってこないので、後半の二人の、愛の逃避行や、せっかくの深津の素晴らしい演技力、迫真の表情などが、100%の、クライマックスとして納得できないのだとも思う。
携帯サイトで、ナンパする連中を深津の姉?が、批判するシーンがあるが、これもまた、彼女の決めつけた極論で、時代が変われば、道路でナンパするアナグロ・ナンパからデジタル・ナンパに変化していったということだけでしょう。
うーん。
やはり、あの二人の、恋が成就していくプロセス、スタンダールの恋愛の塩の結晶のプロセスが、もっときちんと描かれていればなあと思う。
安物紳士服売り場の販売員と、建築解体屋の恋。
これは現実的には、販売員はもっと明るく、これだけの孤独を心の奧に持っている人はいるようなイメージ作りの職業としてはどうかなとも思う。
建築解体屋がコンプレックスを持つような職業というのも理解しがたい。
私の友だちにもたくさんそのような関係の人間がいるが、もっともっと「大人」で、あの
妻夫木聡が心に持っているような孤独はまたまた、理解しがたい。
どうもそんなわけで、二人の恋の逃避行にだけはついていけなかった。
そして、なんで、また深津の首を締めるのか? わからない。
しかしながら。
深津の演技力には見ていて、かなり引き込まれ、彼女の顔に時折現れる狂気にまで到達するような「過剰」性に感動した。
ニーチェについて小林秀雄氏が書いている文章があるが、こんな文章です。
大学時代に読んで、感動して、いまでも、よく覚えているのです。
「ニーチェは、ギリシア人がりっぱな悲劇を書いたということこそ、ギリシア人が厭世家ではなかったというはっきりした証拠だといいます。ちょっと聞くと、反語のようにも聞こえますが、それは、悲劇と厭世というふたつの概念を知らず知らずのうちに類縁のものと私たちが思っているからでありましょう。
おそらく、ニーチェは、そのことを頭において強く主張する、悲劇は、人生肯定の最高の形式だと。人間になにかが足りないから悲劇は起こるのではない、何かがありすぎるから悲劇がおこるのだ。否定や、逃避を好むものは悲劇人足りえない。何もかも進んで引き受ける生活が悲劇的なのである。不幸だとか、災いだとか、死だとか、およそ人生における疑わしいもの、嫌悪すべきものをことごとく、無条件で肯定する精神を悲劇的精神という。こういう精神のなす肯定はけっして無知から来るのではない。そういう悲劇的智慧を掴むには勇気を要する。勇気は生命の過剰を要する。幸福を求めるがために不幸を避ける、善に達せんとして悪を恐れる、
さような生活態度を理想主義というデカダンスの始まりとして軽蔑するには、不幸や悪はおろか、破壊さへ肯定する生命の充実を要する。
そういうディオニソス的生命肯定が、悲劇詩人の心理に通じる橋である、とニーチェは言いきるのであります。ニーチェの激しい気性は、アリストテレスのカタルシスの思想に飽き足らなかった。」
要するに、「幸福」だけを狙って「引き寄せる」なんていうのはとんでもないことで、間違って「悲劇」を引き寄せても人はその運命を愛するべきなのだということですネ。
これは恐るべき言葉です。
職業とあの孤独が、むすびつく論理は、納得はできないけれども、もしも、あのふたりが、なにやら、小さな頃から「過剰性」を持っていて、何をするにしても、人の数倍も夢中になっていく気質があり、そのおかげで、皆から少し変人扱いされていてひしひしと孤独を感じているという心理設定。
ならば、納得いくわけです。
西部邁と栗本氏の対談で、日本女性はもう男を愛する力を失ったとまで書かれた、最近の若い日本女性。
この深津理恵のようなキャラが、男性から強く求められているのか、それとも、演歌的でダサイと思われているのか、そのあたりは興味深いことである。
以上、自分自身のための記憶強化のための記事でした。
記憶強化のため、と書いておきながら、忘れているんだから、そうなっていないわけですね。
私は、前ばかり見て戦って来たいわばサラリーマン戦士でしたから、一年前、二年前などのことはすっかり忘れているのかもしれません。
ここ最近のこと、今日のこと、明日のこと、・・・・・・それだけで。
とにかく、思い出せて良かった。
「"好きになることが相手を助ける""知識は(異文化への)恐怖を取り除く"」「これらは全て映画が教えてくれた事」 淀川長治
FIN
◎深津絵里 CM資料
CM 1970年~1972年
<津軽三味線>北海道の菅野さん日本一
2013年の演奏しか発見できず。
本日、テレビにて日本一獲得と紹介されていた。
おめでとうございます。
北海道人として嬉しいです。
<津軽三味線>北海道の菅野さん日本一
優勝した菅野さん
拡大写真
第10回津軽三味線日本一決定戦が3、4の両日、青森市文化会館であった。大会は9部門に分かれ、全国から約330人が参加。最高部門の「日本一の部」で北海道比布町の三味線奏者、菅野優斗さん(20)が初優勝を果たした。
昨年は「優勝者なし」だった同部門には20人が出場。独奏の「曲弾き」と民謡の伴奏をする「唄付け」の総合点を競った。出場者は歌い手と息を合わせながら、真剣な表情で三味線を演奏した。
菅野さんは今大会最高得点の810点(1000点満点)を獲得。「昨年は唄付けの点数が伸びず、優勝を逃して悔しい思いをした。三味線を教えてくれた祖父や父に喜びを伝えたい」と笑顔で話した。
他部門の優勝者は次の通り。(東北関係分、敬称略)
▽A級女性の部 織江響(仙台市)▽A級男性の部 高橋勇弥(塩釜市)▽C級の部 水木奈美子(平川市)▽B級の部 成田涼真(弘前市)▽シニアの部 佐藤裕治(大仙市)▽ジュニアの部 佐藤竜雅(盛岡市)▽団体りんごの部 三絃小田島流(仙台市)
森田さん「やっと声に出し喜べる」=新元素「ニホニウム」

理化学研究所などのチームが合成に成功し、命名権が認められた113番元素の名称案「ニホニウム」の公表を受け、理研の森田浩介グループディレクター(九州大教授兼任)は9日、「共同研究者とも、やっと口に出して喜べる」と笑顔を見せた。
〔写真特集〕新元素の名称案公表~「ニホニウム」~
9日朝、新元素合成の舞台となった理研仁科加速器研究センター(埼玉県和光市)を視察に訪れた馳浩文部科学相を案内した森田さん。名称案は3月末までに国際純正・応用化学連合(IUPAC)に提出していたが、8日夜まで公表を禁じられていた。
4月に首相官邸で発見の概要を説明した時も名称案は言えなかったといい、「胸のうちにためていた名前を、きょうから『ニホニウム』と言えるところが大変、大変うれしい」と喜びを表現した。
昨年末に命名権を獲得。共同研究者と会議を開き、すんなりと決まったという。候補として「ジャポニウム」も取りざたされたが、森田さんは記者会見で「語感に抵抗を感じる人もいた」と説明。1908年に小川正孝博士が43番元素として命名した幻の「ニッポニウム」に触れ、「強い思いがあったが、過去に出たものは使えない。ニホニウムなら大丈夫だったので提案した」と述べた。
「基礎研究をさせてくださっている国民の皆さんに少しでも恩返しができる」と元素名に込めた思いを明かし、「周期表を見て、そこに日本のグループが作った元素があるんだと気づいてくれて、少しでも理科が好きな子が増えれば望外の喜びだ」と語った。
研究グループは113番元素合成に関する論文や、命名提案書などに「原発事故で傷ついた福島の人々にささげる」と加えた。森田さんは「原子力発電も原子核を扱っている。(基礎科学が専門で)工業的応用は分からないが、非専門家といって逃げてはいけない。われわれができるのは科学の信頼を回復することだ」と説明した。
LiSA - oath sign [Sub Español][Live]
新劇場版エヴァンゲリオン序 主題歌Beautiful World
新劇場版エヴァンゲリオン序 主題歌Beautiful World
宇多田ヒカル #13 I Love You [尾崎豊] @ Marine Stadium【HD】
宇多田ヒカル #13 I Love You [尾崎豊] @ Marine Stadium【HD】
谷口ジロー「新しい人生のはじめかた」ややこしい題名の理由「男と女」「ぼくの大切な友達」
食うのは自分で決めること
他人にその自由を奪う権利はない… 孤独のグルメ 谷口ジロー
最近、読んでいるマンガはフランスでも、彼の作品が、映画になっていますが、
谷口ジロー。
個人的には絵は好きですが、原作ものが多いので、その意味では、絵師という感じ。
私の大好きな、上村一夫氏のアシスタントをしてから独立。
漫画家のアシスタントで、ここまで、くる人ってけっこう少ないかも。
最近では、「坊ちゃん」を再読しましたが、坊っちゃん (小学館文庫)/小学館
¥473
Amazon.co.jp
やはり、夏目漱石の作品を読むのは敷居が高いけれど、とりあえず入門編として、マンガでも読んでみようという人向きなんでしょうね。
いつも言うように、原作の小説と、映画がまったくの別物であるように、夏目漱石の作品群と、谷口ジローのマンガはやはり別物。そう考えた方が良さそうです。
しかも。
この作品、マンガの原作者が別にいて、そのマンガ原作者=彼のイマジネートした夏目漱石ということですらか、ややこしいです。
しかし、谷口ジローの、
「遥(はる)かな町へ」は、原作なしのオリジナル。
遥かな町へ (ビッグコミックススペシャル)/小学館
¥1,512
Amazon.co.jp
欧州で評価が高い漫画家の谷口ジロー。代表作「遥(はる)かな町へ」は東京に住む48歳の主人公が昭和30年代の郷里の町にタイムスリップする物語だ。作品の舞台になった鳥取県倉吉市には昭和のレトロな街並みがそのまま残る。
フランス映画の「QUARTIER LOINTAIN 」谷口ジロー
谷口ジロー。恐らく、彼はメビウス(ジャン・アンリ・ガストン・ジロー)からかなり影響を受けているので、ジローはそこからとったのだと思う。


まさに、「フィフスエレメント」の世界。
逆に、メビウス(Moebius)のペンネームでも知られるフランスの漫画家ジャン・ジロー(ジャン・アンリ・ガストン・ジロー)は漫画家やイラストレーターに多大な影響を与えた漫画家ですが、一方で、日本の漫画に感銘を受け影響を受けてもいており、手塚のアニメを見てショックを受け、手塚の作品量の多さに驚愕し、また、自身が影響を与えた宮崎駿氏の大ファンでったようで娘に「風の谷のナウシカ」にちなんでノウシカと名付けている。
メビウスは、私が小さな頃、田舎から電車に乗って、札幌まで出ないと彼の作品は見れなかった。最初見たときは、ああこれはもはやartだなあと感激したことを覚えています。
彼のおかげで、フランスでは、古くから、マンガ=artと認識されていて、日本のマンガが世界的に広がることの、きっかけは、やはり、フランスマンガが大きく媒介したのだと個人的には考えています。
日本の、宮崎駿や、大友克洋、そして、谷口ジローがメビウスのことを尊敬している。
谷口ジローは、ここ最近は、フランスでも人気が出て来て、ルーヴル美術館からも依頼がきたりしてている。千年の翼、百年の夢 豪華版 (ビッグコミックススペシャル)/小学館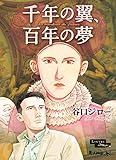
¥2,160
Amazon.co.jp
年齢もたしか、70歳ちかいので、漫画家としては、石森章太郎や手塚治虫ほど多作ではないことが早死にせずに、健康面で、良かったのだろうと思う。(手塚治虫氏は、三日間で三時間くらいしか寝れない生活を、40年間続けていると、どこかで書いていたが、ほんとうだろう。)
メビウスなどのマンガartは、BDと呼ばれている。
BD=バンド・デシネ(Bande Dessinée)とは、フランス語圏のマンガのこと。
しかし、今では、フランスにおける日本のコミックもすべてBDと呼ばれている。
◎資料によると・・・・・・
第二次世界大戦後のBDの流れを3つの世代にわけて分類。
【1】子供向け作品が主流の世代 (1950~1980年代)
・・・『タンタンの冒険』『スマーフ』
【2】ビジュアル面の優れた大人向けの作品の世代 (1970~1990年代)
・・・メビウス、エンキ・ビラル
【3】BD多様化の世代 (1990年代~現在まで)
・・・作家性の強いオルタナ系、娯楽色の強い大手出版社作品
ネットからお借りした資料によると、このように変遷してきている。
しかしながら。
専門誌は、廃刊があいつぎ、これだけで食べて行けるartistは少ないらしい。
やはり、漫画家は大変な仕事。
漫画家になりたくてもなれないから小説家になったという人は、日本にも、限りないほどたくさんいます。
・・・・・・・・・・・・・・
ところで、映画。
ダスティ・ホフマン健在!!!!
新しい人生のはじめかた [2010年2月6日公開]
いまさら、こんな古い映画を楽しむ。
離婚して一人暮らしをしているハーヴェイ・シャインは、一人娘の結婚式のためにロンドンを訪れた。 だが、ハーヴェイは仕事の関係で携帯電話をさわってばかりで、親族の集まりで浮いた存在になってしまう。しかも、娘からバージンロードは義父と歩きたいと言われ、ハーヴェイは落ち込んだ。 そんな中、ハーヴェイは同じく孤独を抱える女性ケイトと出会い、彼女に声をかけた。
ダスティ・ホフマンと言えば、「卒業」。
誰がなんといおうと、私の青春の映画。
中学生の頃に、神戸に妹とふたりで、母方の親戚の家にかなり泊めてもらったのだが、
神戸の風景の美しさ、坂道のロマンが忘れられない。
港。
空の青さ。
細い山に続く坂道。
坂道横に流れる苔むした水源。
六甲山だったか、夜景を今でもはっきり覚えている。
そのオジさんが私の好きだった、「卒業」の「サウンドオブサイレンス」のレコードを
買ってくれて、毎日のように聞いていた。
女がストッキングを足高くあげて履いているシーンのジャケットだったのに、何も驚いたような顔もせずに、笑いながら、一緒に聞いてくれた。
子供さんのいない家だったから、ずいぶん、可愛がってもらった。
今はふたりとも、この世にはもういないが。・・・・
エレーンを追いかけて、教会から花嫁を奪ったあのラストシーンから数十年もたつ。
彼は、今や、離婚経験者であり、
jazzピアニストになる夢が破れ、コンピューターでCMの曲をいやいや作っている。
感受性が人並み以上にあるせいか、彼は、実の娘と会っても、かつての前妻の彼氏を観ていると、どうも引ける。
このあたりのエピソードつくりが実に上手いなぁ。
「最後の初恋」にせよ、この「新しい人生のはじめかた 」にせよ、中年の恋は美しい。そして、笑えるから、また、味がある。
だいたい、若者の恋なんか、私から言わせると、肉欲の愛。
肉欲の愛が終わってくるあたりに、相手に対する「思いやり」が本当にできてくるのではないだろうか?
肉欲の垢尽きて道見える。
このヒロインの女性は実に魅力的だ。
そのけなげ。
不器用。
一所懸命。
落ち込み。
自信のなさ。
先日、男子友だちと、バカ話をしていると、今、「熟女バー」がおおはやりとか。
そりゃあそうだろうと、私は言ってやった。
自分のことがきれいだと思い込んでいて、男子にあれこれ注文ばかりつけているような最近の若い女性に、うんざりしている若者の男性も増えているとか。
比較すれば、けっして、美人ではないけれど、相手に対する思いやりがあり、自分のことを客観的に観れて、自分の顔や体のことを少し貶したり、笑い飛ばしたりするような、大人の女性は、いつの時代でも、男性は惹かれていくのだと思う。
少し大柄で、自分につねに自信が持てないキャラを実に上手く演じていますね。
そして、ヒーローのダスティ・ホフマンのまたまた、余計なことをついつい、言ってしまう、不器用な時代遅れの男をこれまた上手く演じています。
不器用。
へそまがり。
雰囲気にすぐになじめない。
感受性が強過ぎる。
時代の波に乗るのがへたくそ。
いつでも子供の心を持っている。
自分の娘の結婚披露宴には出なきゃダメ、とか言いながら、飛び入り参加したものの、幸福そうに踊っている皆の群れに入れきれずに、ひとり、ホテル会場から去ろうとするシーン。
すると、ダスティ・ホフマンが、ピアノを惹き始める。
サティではないですか。^^
派手なキスも、濃厚なベッドシーンもなし。
それでも、実に、ふたりは、おろおろと、愛の周りを低空飛行している。
その姿は、素晴らしく感動的。
器用に、カッコ良く今はやりの服を着こなし、話題のテーマでまわりを盛り上げて行くような 若者のグループと比較すれば、ダントツに、カッコいいのは実は、こちらのふたり。(あくまでも私の意見です。)
最後はハッピーエンドで終わって良かった。
ここは、「最後の初恋」のアンハッピーエンドになるかとふと思った私の心を軽くしてくれました。
河合隼雄の「中年クライシス」は何回読んでも、素晴らしい第二の青春のスタート本ですが、
これらのシネマもまた、第二の青春のスタートシネマとしては最高ですね。
少なくとも、私の魂にとってですが。
「恋愛小説家」
「恋愛適齢期」
「アバウトシュミット」 以上ジャック・ニコルソン。
「最後の初恋」 ダイアン・レイン
「新しい人生のはじめかた」 ダスティ・ホフマン
「新しい人生のはじめかた」資料A
名優ダスティン・ホフマンとエマ・トンプソンが演じるハーヴェイとケイトは出会ったばかりの他人同士。しかも、初対面の印象は最悪だ。それでも、一旦、言葉を交わせば会話は尽きることなく楽しい時間が過ぎてゆく。これぞ一生に一度あるかないかの運命の出会いか。もちろん、なんの確証もないけれど。これまでに充分過ぎるほど落胆と悔恨を繰り返し、夢よりも諦めを口にしてしまう大人の男女の心の機微を繊細さとユーモアを交えて描いたのは、イギリスの新鋭監督ジョエル・ホプキンス。トンプソンが惚れ込んだ希有な才能の持ち主はオリジナル脚本も手がけ、人生の仕切り直しに遅過ぎることなんてないと希望の光を与えてくれる。
ところで。
名前が良く似ている、こちらの、映画もまずまず好きだが、やはり、ダスティ・ホフマンの方が好きだな。
この「素敵な人生の始め方」という映画は、まさに、モーガン・フリードマンのためにつくられたような、独特のユーモアとペーソスのある映画です。
ある意味、「悲観」の女が、「楽観」の男に、刺激と教育を受けて行く映画です。
ここに記憶のコレクションをしておくて、似たような名前の映画がさらにもう一本。
「最高の人生のつくり方」
「最高の人生の見つけ方」のロブ・ライナー監督が、マイケル・ダグラスとダイアン・キートンという二人の名優を迎え、家族やパートナーといった“成熟した恋愛”をテーマに描いたラブロマンス。笑い合える人生を再び見つけようと心を開いてゆく男の心理を丁寧に描く。
自己中心的で、周囲からはガンコで変わり者と思われている不動産エージェントのオーレンの元へ、疎遠になっていた息子から孫娘を預かってほしいと依頼が来る。孫の存在さえ知らなかったオーレンは、9歳の少女に対して戸惑いを隠せず、隣人の女性リアに助けを求める。こうして奇妙な3人での生活が始まることになるのだが…。
洋画の現代そのままで良いものを、なにやらヒットさせたいがために、似たような名前をつけて、二匹目のドジョウを狙っていると思われますが、見ている方は、題名が似ているのですぐに忘れてしまいます。
そこで、ここに一気に、まとめて、自分の映画記憶コレクションをがっちりと強固にしたいと考えています。
「最高の人生の見つけ方」
余命6ヶ月を宣告された二人の男(ジャック・ニコルソン、モーガン・フリーマン)が、死ぬ前にやり残したことを実現するために二人で冒険に出るハートフル・ストーリー。
アメリカでは2007年12月25日に先行上映、2008年1月11日に拡大公開され、週末の全米興行収入で1位を記録。日本では2008年5月10日に公開され、初登場2位を記録した。
原題の「The Bucket List」は、“Kick the bucket”のイディオムが元になっている
これは、かなり傑作に入るのではないでしょうか。
個人的な意見ですが、ダスティ・ホフマンもそうですが、 の出ている映画は、びしっと画面がきまります。そこに、モーガン・フリードマンが加わるわけですから。脚本も良いですね。
そして、さらに。
こんなまた似た題名の映画があります。題名だけだと、混乱してきます。
「最高の人生のはじめ方」
著名な作家であるモンテ・ワイルドホーン(モーガン・フリーマン)は酒に溺れ、創作意欲を失っていた。あるとき彼が湖畔にあるキャビンを訪れたところ、隣家にやってきたシングルマザー(ヴァージニア・マドセン)とその娘達と知り合う。
「最強のふたり」
2011年10月23日、第24回東京国際映画祭のコンペティション部門にて上映され、最高賞である東京サクラグランプリを受賞し、主演の2人も最優秀男優賞を受賞した。また、第37回セザール賞で作品・監督・主演男優・助演女優・撮影・脚本・編集・音響賞にノミネートされ、オマール・シーが主演男優賞を受賞した。
フランスでの歴代観客動員数で3位(フランス映画のみの歴代観客動員数では2位)となる大ヒット作となった。日本でも興行収入が16億円を超え、日本で公開されたフランス語映画の中で歴代1位のヒット作となった。
題名を現代で調べますと、
「新しい人生のはじめかた」= Last Chance Harvey
「素敵な人生のはじめかた」=10 Items or Less
「最高の人生のつくり方」=AND SO IT GOES
「最高の人生の見つけ方」= The Bucket List
「最高の人生のはじめ方」=The Magic of Belle Isle
「最強のふたり」=Intouchables フランス映画
ここまで、書いてきて、わかったのは、このよく似た名前の題名、要は、同じ監督の作品なのでした。
みんな知っているのでしょうが、私は今迄まったく知りませんでした。
ロブ・ライナー監督です。
作品のつくられた年をここに書いて、その順番どうりに、並べると、
A「最高の人生の見つけ方」= The Bucket Listが、2007年。
B「最高の人生のはじめ方」=The Magic of Belle Isle が、2012年
C「最高の人生のつくり方」=AND SO IT GOES が、 2014年
ほんとうは、このことを知っていたら、この順番に、映画を見れば良いのでしょうが、おもしろそうな映画をほとんど、直感的に、匂いでかぎわけながら、乱読いや乱視聴している、私にとっては、そんなことも考えず、ただ、ややこしい、題名にしているなぁと、不満だったのですが、
同じ監督とわかれば、納得もできますし、記憶しやすくなります。
この監督。
けっこう名作つくっております。あくまで、個人的な好みですが。
「恋人たちの予感」
(こいびとたちのよかん、原題:When Harry Met Sally...)は、1989年に公開されたアメリカ映画。
ノーラ・エフロン脚本、ロブ・ライナー監督。ニューヨークを舞台にした恋愛映画。本作で主人公の男女が食事をするカッツ・デリカテッセンは、日本のガイドブックで掲載しない例外がない程の名所となった。
日本ではみゆき座の上映300本記念作品として話題となり、約2か月半のロングラン・ヒットとなった。
2002年に木村佳乃主演で舞台化された。
・・・・・・・・・・・・・・
メグ・ライアン。
素敵な女優さんだと思います。
大学在学中にエージェントに見いだされ、映画『ベストフレンズ』(1981年公開)でデビュー。1982年から1984年まで連続ドラマ『As the World Turns』に出演。
1986年公開の『トップガン』に出演して注目を浴びる。翌年公開の『インナースペース』で人気を獲得して、同年公開の『プロミストランド/青春の絆』でインディペンデント・スピリット賞主演女優賞にノミネートされた。
1989年公開のビリー・クリスタルと共演した『恋人たちの予感』の大ヒットによって人気を決定付ける。それ以降も、トム・ハンクスとの共演で『めぐり逢えたら』(1993)や『ユー・ガット・メール』(1998)などのロマンティック・コメディに主演しヒットを飛ばし、「ロマンティック・コメディの女王」と呼ばれ人気を博す。また、この三作品ではゴールデングローブ賞 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門)にノミネートされた。 一方、作品選びの悪さが有名で、これまで『ゴースト/ニューヨークの幻』、『プリティ・ウーマン』、『誘う女』、『羊たちの沈黙』などのオファーを断っている。
しかし、後述する不倫騒動や演技派への転向を図って出演した『イン・ザ・カット』の失敗もあってか、近年は出演作にも恵まれず低迷している。低迷の理由には、他に整形手術を受けて顔が大きく変わったためとも指摘され、「整形でキャリアが終わってしまった」とも言われている。
このロマンティック・コメディの三部作。
誰しもが、見ている有名な映画ばかりですが、ここにコレクションしておいて、記憶の強固をはかります。
「ユーガッタメール」個人的にはこれが一番の好みです。
脚本が良いのか、何回見ても、感動で胸をうたれます。
特に、ラストシーン。
「ユーガッタメール」
「めぐりあえたら」
そして、彼女が、運が悪いのかどうかはともかく、オファーを断った映画もコレクションしておきます。
私は、目が悪いのと、年齢のせいか、外国人女優では、ジュリア・ロバーツと、アン・ハサウェイなんかは、たまに、混同してしまいます。
もちろん、別々に見ればすぐにああ、っとわかるのですが、普段は、思い起こす時に、よく混同してしまいますし、名前がすぐにでてきません。
こまったものです。・・・・・・
「誘う女」
『誘う女』 (To Die For) は、1995年製作のアメリカ映画である。ガス・ヴァン・サント監督。サスペンススリラー。1990年に実際に起きた事件を題材にした、ジョイス・メイナード(英語版)の1992年発表の小説『誘惑』 (To Die For) の映画化作品である。
主演のニコール・キッドマンは、本作でゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した。
「ゴースト」
ロマンス、コメディ、ファンタジー、ホラーといったいくつかのジャンルに含まれる。愛する人が幽霊となって目の前に現れるというアイデアは、この映画のメガヒットで多くの亜流映画・小説を生む。
ウーピー・ゴールドバーグがアカデミー助演女優賞を受賞し、作品自体もアカデミー作品賞、編集賞、作曲賞にノミネートされたが、『ダンス・ウィズ・ウルブズ』という強豪の存在のため他はアカデミー脚本賞(ブルース・ジョエル・ルービン)を受賞するにとどまった。
主題歌は、ライチャス・ブラザーズの「アンチェインド・メロディ」(もともとは、1955年の映画『Unchained』(日本未公開)の主題歌だった。作曲はアレックス・ノース)。
そして、メグ・ライアンが断った最後の映画。
「羊たちの沈黙」
『羊たちの沈黙』(ひつじたちのちんもく、The Silence of the Lambs)は、1991年公開のアメリカ映画。監督はジョナサン・デミ。原作はトマス・ハリスの同名小説。主演はジョディ・フォスター、アンソニー・ホプキンス。
第64回アカデミー賞で主要5部門を受賞。アカデミー賞の主要5部門すべてを独占したのは『或る夜の出来事』、『カッコーの巣の上で』に次いで3作目である。
結論ですが、これらの映画は、すべて大ヒットした要因は、やはり、ジュリア・ロバーツであり、ジュディ・フォスターであり、ニコール・キッドマンだったから、名作足り得るのではないでしょうか。
すべては運命のなせる業。
運命おそるべし。
不思議な事だが、私が若い頃は、映画はほとんど悲劇的なものが非常に多かった。
ロミオ&ジュリエット。明日に向かって撃て。ボニー&クライド。・・・
アランドロンの映画なんかもそうだった。冒険者たち。
心中天の網島、肉弾、ヤクザもののすべて。
比率的には、ハッピーエンドは、二割程度だったかもしれない。
涙とともに銀幕は降りたものだった。
映画館を出ると、外の空気が実に新鮮で、空の青さが目に沁みた。
jazz喫茶にそれから入って、コルトレーンなんかを聞きながら、さきほどのシネマの
中身を何回も何回も、コルトレーンのソロのように、反芻したものだった。
「ニーチェは、ギリシア人がりっぱな悲劇を書いたということこそ、ギリシア人が厭世家ではなかったというはっきりした証拠だといいます。ちょっと聞くと、反語のようにも聞こえますが、それは、悲劇と厭世というふたつの概念を知らず知らずのうちに類縁のものと私たちが思っているからでありましょう。
おそらく、ニーチェは、そのことを頭において強く主張する、悲劇は、人生肯定の最高の形式だと。人間になにかが足りないから悲劇は起こるのではない、何かがありすぎるから悲劇がおこるのだ。否定や、逃避を好むものは悲劇人足りえない。何もかも進んで引き受ける生活が悲劇的なのである。不幸だとか、災いだとか、死だとか、およそ人生における疑わしいもの、嫌悪すべきものをことごとく、無条件で肯定する精神を悲劇的精神という。こういう精神のなす肯定はけっして無知から来るのではない。そういう悲劇的智慧を掴むには勇気を要する。勇気は生命の過剰を要する。幸福を求めるがために不幸を避ける、善に達せんとして悪を恐れる、
さような生活態度を理想主義というデカダンスの始まりとして軽蔑するには、不幸や悪はおろか、破壊さへ肯定する生命の充実を要する。
そういうディオニソス的生命肯定が、悲劇詩人の心理に通じる橋である、とニーチェは言いきるのであります。ニーチェの激しい気性は、アリストテレスのカタルシスの思想に飽き足らなかった。」
この、悲劇は、人生肯定の最高の形式だと。人間になにかが足りないから悲劇は起こるのではない、何かがありすぎるから悲劇がおこるのだ。という、ニーチェの言葉が頭のなかをすうーっと、流れて行きました。
珈琲の味の苦いこと、苦いこと。
この世の中の、不条理な殺人事件。
いや、それだけではない、ありとあらゆる不条理な出来事。
はたして、神はいるのか? いないのか?
確か、聖書の中で、神を敬うこと大いなるとある人物。名前は覚えていませんが・・・・・・。
神様は、その信心ぶりを試そうとします。
彼の愛するものを殺してしまうわけですね。
そこで、彼の反応を見ようと・・・・・一神教の神様。
遠藤周作の本の中でも、日本人に西洋の文学が果たして理解できるのか? という投げかけがありました。
小林秀雄も、また、聖書がわからないと西洋文学は理解できないと書いています。
本人も、晩年に日本の古典ばかり読んでいるのもよく納得できます。
生まれた時から、キリスト教という信仰が生活の中のありとあらゆるところに、深く深く浸透している世界。西洋。
無意識からはては、理論構築がまるで天にそびえるゴシック建築のごとく、理論武装されている神学の意識の世界。
最近のテロ事件もまた、そのあたりを理解しないと、あれらの事件はまったく理解できないと思います。
「アマデウス」には、サリエリでしたか、神が女たらしのモーツァルトを選んで信心深い自分をなぜ選んでくれなかったかと、怒って、キリストの像を火の中にくべるシーンがありました。
まあ、この映画は、哲学をテーマにした映画でもありませんし、娯楽作品として作られた筈。
しかしながら。
かつて、貴族の肖像画を描かされていた宮廷画家達が、しだいにただ似せてキレイに描く絵に飽きて、自分の色彩とトーンの美を追求しはじめたように、この映画も、けっこう良い意味で、我がままにつくられてる。
・・・・・・・・・・・・・・・
ところで、次の映画。
仕事に疲れると、ふとレコード棚からひっぱりだすレコード群。
朝から聞く曲ではないなぁと思ったが、かけると、昔の記憶が次から次へと。
「ヨーロッパ映画の魅惑」というレコード。
男と女がいるからこそ、この世は楽しい。
クロード・ルルーシュ監督の一番油の乗っていた頃の作品二作。
しかも、みずから作曲・シナリオ。
無名の作家がいちやく世界にはばたくきっかけとなった作。「男と女」
スタントマンの夫を事故で亡くしたスクリプト・ガールのアンヌは、娘を寄宿学校に預け、パリで一人暮らしをしていた。ある日、娘に会うために寄宿学校に行った帰り、パリ行きの列車を逃してしまう。そんなアンヌにジャン・ルイという男性が車で送ると申し出た。ジャン・ルイも同じ寄宿学校に息子を預けており、また、妻を自殺で亡くしていた。
アヌーク・エメと、ジャン・ルイ・トランティニィアン。
バツ1同士の大人の渋い愛情が実に軽いタッチでお洒落に描かれていました。
仏蘭西人は昼まっぱからワインを飲み、恋人同士がボルノ映画館で手を握り合いながらいちゃつくお国柄。
日本とは相性が良く中国とは相性はめちゃくちゃ悪い。
恋沙汰の事件はそれだけで刑が軽くなるとか。
恋の達人ぞろいのフランス。日本は不倫は文化だとほんとうのことを言ったばかりにふくろだたきにあった俳優もいますが、フランス人なら笑ってそのまますますでしょう。
揚げ足ばかりとる日本人とは違い、人生を楽しむコツは仏蘭西人ならではかな?
「パリのめぐりあい」も、不倫をキャンディス・バーゲンと楽しむ主人公が、最後はやはり不倫相手とはうまくいかなくなり、妻のもとへも帰れないということで、ひとり孤独になるのですが、最後のラストシーンで、妻がニコリと待っているシーン。
こんな妻ばっかりならば世の中の男性すべてが甘えてしまって大変になることは眼に見えていますが、めったにいない妻をやはりクロード・ルルーシュ監督はうまく描いていますね。
アニー・ジラルド素晴らしい。キャンでス・バーゲンの美しさ。
いつも、そうなんですが、「男と女」は、「パリのめぐりあい」といつも混同してしまいます。
フランスのTV界でもトップクラスのニュース・リポーター、ロベール・コロンブ(イヴ・モンタン)は、妻のカトリーヌ(アニー・ジラルド)との間が、決して不満だらけというわけではないが、単調な日常生活の繰返しに耐えられず、時には恋のアバンチュールを楽しんでいた。そんなある日、彼はキャンディス(キャンディス・バーゲン)というファッション・モデルをしながらソルボンヌ大学に通う娘と出会い、そのみずみずしい知性的美しさに強くひかれた。TV局からの電話で、アフリカへ取材に出かけることになったロベールはキャンディスに同行を誘うと彼女はすぐに同意した。ケニア砂漠での二週間は、二人の間をさらに深く結びつけ、野生の猛獣撮影が成功した夜、二人は初めてベッドを共にした。パリに帰ったロベールは、カトリーヌの発案で、アムステルダムへ休暇旅行に発った。久しぶりで夫婦は語りあい、愛しあった。そしてある日、ロベールはアムステルダムまで彼を追ってきたキャンディスの姿を見た。彼は二日だけ仕事でパリに帰ると妻に告げてキャンディスの待つホテルに向った。しかし、帰ってきたロベールを見て、カトリーヌはすべてを察し、パリへ帰る途中のブラッセル駅で一人降りてしまった。パリへ帰ったロベールは、キャンディスと一緒の生活をはじめた。しかし、その生活はなぜか空ろで虚しかった。ベトナムへの取材旅行をきっかけにロベールはキャンディスとの別離を決意し、その旨を伝え出発した。日が流れた。ベトコンの捕虜になり解放されたロベールは、カトリーヌを探してアルプスの近くの町へ走った。カトリーヌはロベールを友達として暖かく迎えてはくれたが、その時ロベールは、彼女はすでに自分の妻としては遠い人であることに気づき、静かにわかれを告げて外に出た。だが、雪におおわれた車のフロント・ガラスをはらい落した時、彼は再びその中に妻の笑顔をみたのだった。...
もうひとつ、・・・・・・この映画を思い出していたら、ふと、北海道出身の渡辺淳一氏を連想いたしました。
彼はエロ作家とか、陰口をたたかれることも多いようですが、私は好きです。
彼の「資料をもとにした時代劇やら歴史物は簡単に書ける。一番むずかしいし、誰もが書きたがらないのは恋愛小説だ」と豪語しているところが好きですね。
「化身」はそのなかでも特に傑作でしょうか。
良くも悪くも「男と女」が描かれているし、男の「教育好き」が描かれている。
かつて三島由紀夫氏は、「エロティシズムの本質は教育だ」と書きましたが、男は好きな女にいろいろ教えるのが大好き。そして、女は男に教えられることが大好きと私は見ています。
そして、化身の女主人公が最後の最後に、見事に成長して、自分を教育してくれた男性を棄てるわけですが、「パリのめぐりあい」とは違って、妻も彼女も、完璧に彼を見捨てます。
その彼が最後に孤独になってパタリと寝床かどこかに倒れて放心?するシーン、しみじみしていて、いいですねえ。
育て上げ、教育し、美しくそだてあげた自分の愛人に最後は棄てられる。
しかしながら、後悔はしていない。
やることはやったし、自分はそれしかできないのだというプライドみたいなものもあるのかも。
現実はいつも、厳しく、甘くなく、これらの映画や小説のような男や女はなかなかいないでしょうから、だからこそ、映画や小説の中では、彼らの存在が優美に私たちに語りかけてくれるのかもしれません。
これらの映画に少しでも近い「恋の破片」みたいなものを心の片隅の宝石箱に隠して、前に突き進んで行きたいものです。
ところで、このあたりで、気分をかえて、音楽。・・・・・・・
この曲。
この女性歌手。
その意味では、まさに女性の良きところだしてます。
不思議感。
退廃感。
ラナ・デル・レイ 欧米で大ヒット 耽美で退廃的60年代路線
耽美で退廃的といえば、私の得意分野。
たしかに、不思議な雰囲気。
時代は廻る。
次なる最後の映画は。
喜劇。
私の尊敬するルコント監督。素晴らしいできばえ。
今頃、2006年の作品を見て、感動している自分が笑える。
「ぼくの大切なともだち」
当時は、仕事が忙しすぎて、シネマをゆっくり見る時間がとれなかった。・・・
なんでも、ひとつのことしか見えなくなる自分の性格。これだけは今でも、過去でも、そしておそらく未来でも、しょうがないことだと思う。
◎資料から
美術商のフランソワ(ダニエル・オートゥイユ)は、自分の誕生日を祝う夕食会の席で、葬儀の参列者が7人しかいなかった話をすると、友達がいないからフランソワの葬式には誰も来ないと言われてしまう。そこで自分にも親友ぐらいいると言い張ったため、フランソワは十日以内に親友を連れてこれるかどうか、共同経営者のカトリーヌ(ジュリー・ガイエ)と賭けをすることになってしまう……
◎小さな頃から、クイズに熱中する変人。
幸福な王子。。。のひとこと。小さな狐の話がキー。
物語もありふれているし、マンガ的なところもあるけれども、それはそれで良い。
これ
また、ひとつのことに熱中するとその他のことが見えなくなる、私みたいなタイプの男ふたりの友情物語、というところが好みの映画。
もともと、他人に接する態度といっても、悪魔のように冷たい人や、まったく愛のない人はそういないので、少しでも、心を変容する気持ちさへあれば、・・・・・
感謝の気持ちさへあれば。
それに、自分の葬式に何人来てくれるかとか、そんなことがその人の価値をきめるものではないだろうと思うが、どうなんだろうか。
ルコトンの作品は、やはり、たとえば、
この「イヴォンヌの香り」なんかはやはり彼の最高傑作ですが、この「ぼくの大切な友達」もまた、
味わい深いコメディ作品だと思います。
◎資料
監督 - パトリス・ルコント
製作 - オリヴィエ・デルボス、マルク・ミソニエ
原案 - オリヴィエ・ダザ
脚本 - パトリス・ルコント、ジェローム・トネール
撮影 - ジャン=マリー・ドルージュ
美術 - イヴァン・モシオン
編集 - ジョエル・アッシュ
音楽 - グザヴィエ・ドゥメルリアック
衣装 - アニー・ペリエ
キャスト
ダニエル・オートゥイユ - フランソワ・コスト(美術商)
ダニー・ブーン - ブリュノ・ブーレー(タクシー運転手)
ジュリー・ガイエ - カトリーヌ(フランソワの共同経営者)
ジュリー・デュラン - ルイーズ・コスト(フランソワの娘)
ジャック・マトゥー - ブリュノの父
マリー・ピレ - ブリュノの母
エリザベート・ブールジーヌ - ジュリア
アンリ・ガルサン - エティエン・ドゥラモット(テレビ番組プロデューサー)
ジャック・スピエセル - レテリエ
フィリップ・デュ・ジャネラン - リュック
◎資料
ダニエル・オートゥイユ(オトゥイユ)(Daniel Auteuil 発音例, 1950年1月24日 - )は、アルジェリア・アルジェ出身のフランスを代表する男優。
来歴[編集]
父アンリはアヴィニョンを中心に活動するオペレッタ/オペラのバリトン歌手。母は元合唱団員。
6歳で初舞台を踏み、その後もアヴィニョンの舞台に立つ。パリで演技を学び、舞台ではコメディ、ミュージカル、古典と幅広く出演。映画界からも注目され『ザ・カンニング [IQ=0] 』の大ヒットで人気を獲得。連作『愛と宿命の泉』でシリアス演技に挑戦し、セザール賞を受賞。以後、演技派としても認知される。
1996年の『八日目』ではカンヌ国際映画祭男優賞を、1993年の『愛を弾く女』と2005年の『隠された記憶』でヨーロッパ映画賞の男優賞を受賞している。
プライベート[編集]
元妻エマニュエル・ベアールとの間に娘が一人いる。
「最悪なのは失敗することじゃない。
それは自分が傷つかないよう
無難に仕事をこなすこと。
それは、罪。」 ダスティ・ホフマン
FIN

