暑い。しかしながら。
いつもとおなじように生活する。・・・・・・・・・・
夏目はあまり読まないけれど。・・
夏目漱石の草枕をひもときながら、昨夜はベッドの上でごろごろしていたのだが、意外に直接的に詩人や音楽家などの存在に触れて、この世を豊かにするためにもそれらの詩や音楽や彫刻や小説のそれぞれも存在価値があるのだと、出だしのところに書いてある。
小林秀雄などは歴史の中に埋もれたる人々の孤独を救う方法を編み出すというような難解なる言い方をしているのだから夏目漱石のほうがわかりやすい。
いったいに、文章というものは、すらすらと書いたり読めるものではいけないという信念を昔の作家は持っていたようで、わざとに技巧を凝らしたりただ難解なるものを狙ったものは問題外ではあるが、確かに「何か」を表現するときに、けつまづいたり、文章のところどころで考え込んだり、読者に圧倒的な疑問符をつけたりして、思考とはそんなものなのかなと、若いころに思い今にいたっているので、私はあまりにもすらすらと読める小説はなにやら漫画みたいで読む気がおこらないのだ。
すらすらと読めるということは、一般読者の心の中にあるいわゆる「常識」や普通に使われている「言葉」を上手に使っているということであり、ほんとうは、そのような書き手の中にこそ、ひとつのエピソードを天才的に表現する作家がいてもらいたいのであるが、凡庸なテーマを凡庸な物語でしかも使い古された言葉で書いたものであれば、その本の代金の1000円ならばその1000円は、どこかの居酒屋で飲んでしまったほうがいいのではないかとも思ってしまう。
倉橋由美子もそんなことを書いていて、吉田健一や、吉行淳之介などをほめていた記憶がある。
岡本太郎が言うように芸術には、マンネリした日常生活に喝を入れるというような役割もあると思うので、
マンネリをただ増幅させるだけの本に1000円は出したくないということです。
しかし、人は失敗する生き物なので、これはいいと思って買った本がいまいちでがっかりということは、よくあることなので、そんな失敗を繰り返して繰り返して、次第に本に対する目が開けてくるのかなとも思う。
文章というものは、すらすらと書いたり読めるものではいけないという信念を昔の作家は持っていた
男と女の相性「あした来る人 」深津絵里 CM 「女の子ものがたり」「悪人」
「映画に説明やオチなど必要ない」(ミヒャエル・ハネケ)
「あしたくる人」見ました。
原作は、井上靖です。
監督は、 川島雄三 。
昔の映画ですので、白黒ですし、スピードもリズムもなく、じっくりじっくり、物語はすすみます。
でも、そこがいいですね。
男女には相性というものがあると思います。
反撥したり、くっついたり、理由はわかりませんが、まるで磁石のように、
プラスマイナスが人にはあるようです。
この映画もそんな人間模様を、丁寧に丁寧に、描いているのだと思います。
物語資料から
実業家梶大助のホテルへ彼の娘八千代の紹介で、曾根二郎という青年がカジカの研究資金を出して貰うためにやって来た。心よく迎え入れた梶も、決して金を出すとは云わなかった。八千代は夫克平に不満を持っていたが、その夜も遅くなって一匹の小犬をかかえて帰ってきた彼と冷い戦争をはじめ、八千代は大阪の実家へ戻ってしまった。克平は八千代がいなくなってから、相棒の三沢やアルさんとカラコルム山脈征服の計画を実行しようとしていた。ある日例の小犬を見ず知らずの女性が連れているのを見つけた。なつかしさに近寄ると、それは洋裁店に働く杏子だった。八千代は梶に叱られて東京に戻ってきたが、克平の登山計画をなじった。梶の世話を受けていた杏子は、それが克平の義父とも知らず、克平と結婚したい旨打明けた。名前を云わなかったため梶も色々と杏子を励ますのであった。克平は鹿島槍登山に出掛け、直後新聞がその遭難を伝えてきた。早速杏子は遭難現場に急行したが、克平は無事で思わず二人は抱き合った。克平が帰宅したとき曾根が来ていた。その後八千代が余りに曾根をほめるのと、遭難のことに冷淡であったため、克平も感情を害したが、八千代は杏子と彼の仲を知ってのことであった。曾根の取持ちも空しく克平の心も最早八千代にはなかった。その頃杏子は偶然八千代に会い、克平が梶の娘の夫であることを知って悩んだ。克平は遂に山の征服の雄途に乗り出すべく羽田を出発した。結婚のことは最後まで云い出せなかった杏子だった。
上の資料の物語を読むより映画のほうがずっとおもしろいのは、井上靖の小説をじっくり読むのと、また、ヒロインなどの美しさに魅惑されながら、映画を楽しむという、まったく別の楽しみ方を私はしているからでしょうか。
監督の川島雄三。好きです。
いいんです。軽くて・・・・・・・
作風
日本軽佻派を名乗り、独自の喜劇・風俗映画を中心的に、露悪的で含羞に富み、卑俗にしてハイセンスな人間味溢れる数々の作品を発表した。
人間の本性をシニカルかつ客観的な視点で描いている作品が多く、弟子の今村昌平の作品ともども「重喜劇」と称されることが多い。川島の場合、脚本を担当した藤本義一が命名したとも、フランキー堺が呼称したとも言われる。今村がムラといった地方の土着社会に関心が移行していったのに対し、『洲崎パラダイス赤信号』や『しとやかな獣』に見られるように川島は都市に関心を持ち続け、都会に生きる現代社会の人間達をテーマの中心に据えていた。
作家・織田作之助と親交が深かった。一方で同郷の小説家としばしばみなされた太宰治は嫌いであり、太宰より織田の作品を読むことを薦めていた。また井伏鱒二のファンであり、強く影響を受けていた。「サヨナラダケガ人生ダ」という詩訳の科白を愛用しており、『貸間あり』の中で桂小金治にこの科白を言わせている。
死亡時、寝床にはインタビュー記事が載った中央公論と、次回作に考えていた写楽を主人公にした「寛政太陽傳」用の青蛙房版の江戸風俗資料が置かれてあった。[2]この映画で主人公写楽を演じる予定だったフランキー堺は、後年、篠田正浩監督で「写楽」を製作・出演。完成後の1996年6月10日にこの世を去った。
勧君金屈巵 君きみに勧すすむ 金屈卮きんくつし
満酌不須辞 満酌まんしゃく 辞じするを須もちいず
花発多風雨 花はな発ひらけば 風雨ふうう多おおし
人生足別離 人生じんせい 別離べつり足たる
この漢詩です。
井伏が、この詩を自分の好きなように、訳したのが、有名になりました。
コノサカヅキヲ受ケテクレ
ドウゾナミナミツガシテオクレ
ハナニアラシノタトヘモアルゾ
「サヨナラ」ダケガ人生ダ
月丘夢路は、三島由紀夫氏の「美徳のよろめき」にでているところも、シンクロの糸を感じます。
新玉三千代は、そうなんです、「霧の旗」に出ていました。なつかしい。

まるでフランス映画、ヌーヴェルヴァーグの作品を見ているような、白黒の美しいシネマ。
何回もテレビでも放映されたようで、筋書きそのものは誰でも知っている復讐もの。
私は、三島由紀夫が、「日本文学全集」を川端康成などと一緒に、作家を選んでいる時に、松本清張を断固として拒んだということをふと、思い出した。
三島由紀夫は、「あるべきもの・ことを描くのが小説」というのが持論。
松本清張は、「現実の裏側にあるもの・ことをえぐりだす」のが得意だったから、小説に対する美意識が違ったのだろうと思う。
そのことが悔しくて、松本清張は、のちほど、とある賞を獲得したとか。
まあ、そんなことはどうでも良いのだが、私は、倍賞千恵子の演技に感心した。
獲得が山田洋次で、カメラも、撮影:高羽哲夫とくれば、「寅さん」を連想すると思うけれども、「さくら」のイメージで、最初、私はこの古い日本の白黒シネマを見てしまった。
素晴らしい!!!! 倍賞千恵子。
この作品の少し前に作られた松本清張の、「張り込み」にも感心したが、やはり、印象に残っているのは、高峰秀子の美しさ。
現代の日本映画の女優達も、皆美しいけれど、やはりシネマ界にも、歴史があり、女性美の長い歴史があってこそ、今の女優達がいるのだと再認識。
倍賞千恵子は、フランスの、ブリジット・バルドーや、ジェーン・フォンダや、たちにも、ひけをとらない。日本の美だ。


たしかに、ブリジット・バルドーは、わたしたちの時代のアイドルだったし。
ジャンヌ・モローの独特の美も印象深い。
黒衣の花嫁は好きだった。
雨の忍び逢いも良かった。
フランス映画と言えばやはり、この女優。
見事なフランス人の美しさがある。
でも、やっぱり、私は日本人の女性美が良い。
タモリではないけれど、吉永小百合を超える日本女優はまだいないと思っている私だ。
◎霧の旗物語資料から
殺人事件の容疑者として逮捕された兄の無実を信じ、高名な弁護士に弁護を依頼する妹。 しかし、貧しさゆえに断られた妹は弁護士に復讐を誓う。 松本清張原作の映画化。山田監督初のそして唯一のミステリー映画。
◎資料
映画『張込み』の製作以降、著者と面識のあった橋本忍の発言によれば、当時著者は、アラブ人男性のフランス人医師に対する復讐を描くフランス映画『眼には眼を』を観て非常に感心し、こういう(趣向の)ものを書きたいとさかんに言っており、そうした発言ののちに著者が本作を執筆したとされている[2]。
本作は単行本化の際、最終回連載部分に原稿用紙30枚分の加筆がなされた。特に大塚の懇願に対する桐子の態度の描写や、第二の殺人に関する大塚の推理部分、桐子が検事に宛てて送った手紙の部分が大幅に加筆、精緻化された[3]。
詩人・翻訳家の天沢退二郎は、小説の描写において、桐子の意識に入り込んだ描写と、大塚・阿部の意識に立ち入りつつ桐子に関して外面模写のみに終始する描写が振り分けられ、二つの異なる桐子像が小説内で峻別されていることを指摘している[4]。社会学者の作田啓一は、本作において大塚弁護士の側に罪があるとすればそれは「無関心の罪」であり、現代人の多くがひそかに心あたりのある感覚であると分析している[5]。評論家の川本三郎は、本作が発表された時期には、現在の東京一極集中に通じる、地方と東京の大きな格差が生まれていて、桐子の大塚弁護士に対する恨みの背景には、地方出身者の東京に対する恨み(と強い憧れ)があると指摘している[6]。
このあたりが、松本清張の良いところであり、悪いところ。評価が別れると思う。
シンプルにするのであれば、もっとユーモアを入れると良いと思うのだが・・・
原作:松本清張
監督:山田洋次
製作:脇田茂
脚本:橋本忍
撮影:高羽哲夫
美術:梅田美千代
編集:浦岡敬一
音楽:林光
ところで。
・・・・・・・・・・
最近このコマーシャル、なかなかいいな、と思ってみていました。シリーズもののCMです。
テレビもあまり見ないですし、ここ五年間は、多忙でしたから、女優の名前も浮かばず、・・・・・・・・。
アホです。
それで、調べてみると、深津絵里。
資料を見ると、なかなかおもしろいというか、ユニークな感じでしたので、
・・・・・・・・
それに、42歳にしては、かわいすぎる。

◎資料から
大分県大分市出身であり、『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』で1シーンだけ大分弁を話すシーンがある。同シリーズでは同じ大分市出身のユースケ・サンタマリアとも共演している。
映画『阿修羅のごとく』で酔っているシーンを撮影する際、実際にお酒を顔が赤くなるまで飲んで撮ったという。本人は酒好きであり「お食事を頂いているときにちょっと飲む程度。好きなのはシャンパン。酔っぱらうことはありません」とインタビューで話している。
JCBのCMで激辛トムヤンクンを食べるシーンで、スタッフが空のお皿を食べている演技をしてもらうつもりだったが「それではリアルさが伝わらないのでは?」と自ら提案し辛さ20倍のスープを涙ながらに飲んだというエピソードがある。
同じ事務所所属の福山雅治に自身の1月11日の誕生日に111本のバラをプレゼントしてもらったことがある。
女優の握力を予想するゲームにおいて、周りの予想を上回る32kgをだし場内を沸かした。
ドラマ『カバチタレ!』は、かつて『悪魔のKISS』で共演した常盤貴子が、「また深津と共演したい」という希望が叶ったドラマであり、話を聞いた時お互いが逆の役をやるのとばかり思っていた。
常盤貴子とはドラマで共演して以来仲がよく、プライベートでも一緒に遊んだりしている。天海祐希とも仲がよい。天海が30代の時、常盤も含んだ3人で「カッコよく楽しく生きる三十路会」を開いていた。
木村拓哉、福山雅治、田村淳、臼田あさ美、佐藤健、水川あさみ、星野真里など芸能人にファンが多い。木村拓哉は「深津絵里さん=女優。 優れた女と書いて女優。」と評している。また臼田あさ美は自身のブログで憧れているとコメント、同じアミューズ所属の佐藤健は原宿でスカウトされた際、アミューズが深津の所属する事務所だと知って芸能界入りを決心したほどであり、『恋するハニカミ!』にゲスト出演した際、「中学の頃からのファン」「ハニカミデートしたい」と語るほど深津のファンである。
三谷幸喜は深津を映画『ザ・マジックアワー』に起用した理由について、2007年(平成19年)に公開した映画『西遊記』で共演し会話をした際「感じが良かったから」だと話す。劇中で深津はアフレコではなく撮影時の生歌を披露しているほかエンディングにはロングバージョンも歌っている。このことについても「深津さんは歌でも芝居でもホントにカンの良い人でした。(アドリブも)深津さんは絶対に笑わない。彼女はNGも出さない。もう、鉄の女。絶対に崩れないタイプ」「耳もいいし、英語の発音も完璧。エンディングは圧巻でした」と評している(『ザ・マジックアワー』オフィシャルブックより)。
彼女が、主演している作品をとりあえず、2本。
「おんなのこものがたり」と「悪人」を見てみようと思い、まずは、ゲオへ。
「おんなのこものがたり」
2009年に封切りされたのに、今頃みている、わたし。
ということは、もともとは、縁のない映画だったんです。
でも、深津絵里のCMを見ていたら、自分の好きなジャンルではないのですが、見たくなってしまい・・・・・・・・
西原女史の自伝的漫画がもともとの作品なんで。
漫画家というのは、しかしながら、おもしろい職業だなあ。そう思います。
ある意味。女性の枠を、超えて、男性に近い考え方ができて、それでいて、女性のこころもありますので、かなわないところがありますね。
普通は、「女子の友情というものはなかなか続かない」と、言われているわけですが、
言われているだけで、私の妹なんかも、小学校時代の友達たちと今でも、月1くらいのペースで、食べたり飲んだりして仲良くやってますから、一概に友情はないとか言えないのでしょう。
作品にするわけですから、自分のリアルな過去の記憶をすこしばかり、小麦粉で膨らませてみたり、ひっぱったりのばしたり、小さく切ったりしていることは当然のこと。
ただ、残念なのは、深津絵里は、今現在で漫画家になっており、過去を思い出すという視点で、作品が出来上がっていますので、印象的には、なっちゃんという若き日のイメージは、
高原菜都美(現在):深津絵里
高原菜都美(あだ名はなっちゃん。高校生時代):大後寿々花
きみこ(あだ名はきいちゃん。高校生時代):波瑠
みさ(あだ名はみさちゃん。高校生時代):高山侑子
となっております。
私は、テレビが見る暇がないので、まったく、邦画やCMの女優達を知りません。
が、たまに、おっと思う存在感のある女優を見つけると、だれかな??と調べてみるだけ。
深津絵里さんもそうだったように。
この大後寿々花さん。
「サユリ」で、新人賞を獲っているんですね。それに、以前の記事で書いた「北の零年」にも出演していたとか言われると、えっ、まったく覚えていません。
あわてて、調べ直すと、子役でした。

「sayuri」の、小森和子賞は、すごいと思います。
きみこ(あだ名はきいちゃん。高校生時代)役の波瑠さん。テレビドラマでも、ここ最近がんばっていますね。
朝ドラの。
NHK連続テレビ小説『あさが来た』のヒロイン・白岡あさ役に決定したわけですから、これはすごいと思いました。
それに、役柄のきいちゃんは、死んでしまいますが、ドラマが変われば、また再生するところが、嬉しいです、再会できるわけですから。ファンにはたまらないでしょう。
おんなのこものがたりのなかの、詩のような描き方の映画で、ほんわりほんわかムードの映画でしたが、最後の三人のケンカするところ・・・・ここは素晴しいかったですね。
義父がいうところの、「人と違う人世をおくれるかもしれん」という言葉を胸に、なっちゃんは上京するわけですが、たしかに、たくましく、自分の限界をきちんと知って、自分の立場をしっかりと知っている友達達との・・・・・・・・距離感はたまらなかったでしょう。
あと、
高山侑子さん。
父親は、航空自衛隊新潟救難隊の救難員でしたが、2005年4月、訓練中の墜落事故で殉職しています。同年秋に防衛庁(当時)で実施された自衛隊殉職隊員追悼式に出席するため家族で上京した際、原宿でスカウトされたこと、・・・・
2008年、映画『空へ-救いの翼 RESCUE WINGS-』で映画初出演・初主演を果たしたこと・・・
2015年、「新・戦国降臨ガール」にて初舞台・・・・・などなど。
父親の追悼式でスカウトされたことや初主演映画が航空自衛隊を扱った作品であることに運命的なものを感じるそうで、「父に導かれたような気がする」と語っている。
深津絵里。
もう一本のビデオを見ながら、最初のシーンで、あれれ?
これ見たという感じでした。
記憶力というのはほんとうにあてにならないものです。
どうしようもないアホです。
しょっちゅう、一度見た作品をまた、借りてしまいます。
二度見るのは楽しいので、あまり気にはしていませんが、ボケはじまっているかも。
彼女は、この作品で、ふたつ賞を獲っています。
なかなかないことらしいです。
第34回モントリオール世界映画祭最優秀女優賞、並びに第34回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞(尚、日本アカデミー賞での最優秀主演/助演女優賞のダブル受賞は桃井かおり・大竹しのぶ・小柳ルミ子・倍賞美津子・原田美枝子・和久井映見・樹木希林に次いで史上8人目)。
映画が小説とするならば。
でも、CMも、なかなか素晴しい、一編の詩・和歌短歌。
こんな記事を書いておりました。記事まで書いているのに、すっかりわすれているんだからどうしょうもありません。
日本映画の売り上げが外国映画より多くなったという逆転劇から、数年。
今はどうなっているのか?
「フラガール」の監督だったから以前から見たかったが、見たい映画が多過ぎ、今頃見る。
レヴューを見ても、自分の気持ち・気分・鑑賞フイーリングと添うものがないというのは、やはり、映画は見る人によっていろいろな見方があると言うことだろうと、思う。
撮影笠松則通
美術監督種田陽平
美術杉本亮
装飾田口貴久
照明岩下和裕
音楽久石譲
音楽プロデューサー岩瀬政雄 、 杉田寿宏
主題曲/主題歌福原美穂
とまあ、資料にもあるように、かなりの画像のハイレベルシネマ。
切ない音楽のタッチや、切々と流れてくる音の迫力やら、雨の音などの効果も高いのが印象的。
これはやはり、映画館で見た方が良い映画かも。
深津絵里はまさに適役。妻夫木聡を完全に食っている。
不思議だが、私はなにやら、この映画の途中、深津絵里のキャラに日本人特有?の任侠映画によく出てくる「待つ女」の原型みたいなものを感じていた。
ただ、個人的な意見としては、小説とはまったくの別物としての映画としてコメントすると、この金髪男性がなぜあの娘を衝動的にでも殺してしまうのかがちょいと不明、理解できない。
ひょっとするとカミユだったか、太陽がまぶしかったから殺人をしたというような不条理な人間の悪の心理なのかもしれないが・・・
それにしても、普通の常識からこの映画の登場人物を見てみると、あの樹木希林が演ずるおばあさんの人物の設定からすると、とても、あのような殺人鬼の子を育て上げるとは思えない。
確かに、解体屋という職業のイメージから、彼の未来を暗示しているのかもしれないけれど、土木作業員やら解体屋やらの、世間的な信用のなさや、世間的な下位の職業として設定しているところに古さを感じてしまう。
離婚歴などの家庭、異性感からもたらされるコンプレックス、下位の職業などのいわゆる「環境」に、犯罪を犯す本質的な要因があるなどと、表現されるのは、どうも昔の「左翼的な発想」を無理矢理押し付けられている感じがしてとても嫌だ。
むしろ現代を表現するならば、あの非常にクネクネした、岡田将生なんかの方が、まさに太陽がまぶしいから人を殺したみたいなことが似合うかもしれない。
満島ひかりにしても、あの父親からあんなような娘が育つとはとてもとても思えない。
小さな頃に、父母が朝から必死に働いているような両親の後ろ姿を見ていると子供はぐれないと、よく言われる。
だからこそ、中流の、親が権威をかさに自分の正しさを子供たちに押し付けるような親が、子供をおかしくするとも言われているこのごろだ。
確かに、孤独な二人はそれを接点にして、要に引きつけられるということはあると思うが、どうも 、深津絵里と妻夫木聡が、それだけ、孤独だということがこちらに前半の物語だけからは、伝わってこないので、後半の二人の、愛の逃避行や、せっかくの深津の素晴らしい演技力、迫真の表情などが、100%の、クライマックスとして納得できないのだとも思う。
携帯サイトで、ナンパする連中を深津の姉?が、批判するシーンがあるが、これもまた、彼女の決めつけた極論で、時代が変われば、道路でナンパするアナグロ・ナンパからデジタル・ナンパに変化していったということだけでしょう。
うーん。
やはり、あの二人の、恋が成就していくプロセス、スタンダールの恋愛の塩の結晶のプロセスが、もっときちんと描かれていればなあと思う。
安物紳士服売り場の販売員と、建築解体屋の恋。
これは現実的には、販売員はもっと明るく、これだけの孤独を心の奧に持っている人はいるようなイメージ作りの職業としてはどうかなとも思う。
建築解体屋がコンプレックスを持つような職業というのも理解しがたい。
私の友だちにもたくさんそのような関係の人間がいるが、もっともっと「大人」で、あの
妻夫木聡が心に持っているような孤独はまたまた、理解しがたい。
どうもそんなわけで、二人の恋の逃避行にだけはついていけなかった。
そして、なんで、また深津の首を締めるのか? わからない。
しかしながら。
深津の演技力には見ていて、かなり引き込まれ、彼女の顔に時折現れる狂気にまで到達するような「過剰」性に感動した。
ニーチェについて小林秀雄氏が書いている文章があるが、こんな文章です。
大学時代に読んで、感動して、いまでも、よく覚えているのです。
「ニーチェは、ギリシア人がりっぱな悲劇を書いたということこそ、ギリシア人が厭世家ではなかったというはっきりした証拠だといいます。ちょっと聞くと、反語のようにも聞こえますが、それは、悲劇と厭世というふたつの概念を知らず知らずのうちに類縁のものと私たちが思っているからでありましょう。
おそらく、ニーチェは、そのことを頭において強く主張する、悲劇は、人生肯定の最高の形式だと。人間になにかが足りないから悲劇は起こるのではない、何かがありすぎるから悲劇がおこるのだ。否定や、逃避を好むものは悲劇人足りえない。何もかも進んで引き受ける生活が悲劇的なのである。不幸だとか、災いだとか、死だとか、およそ人生における疑わしいもの、嫌悪すべきものをことごとく、無条件で肯定する精神を悲劇的精神という。こういう精神のなす肯定はけっして無知から来るのではない。そういう悲劇的智慧を掴むには勇気を要する。勇気は生命の過剰を要する。幸福を求めるがために不幸を避ける、善に達せんとして悪を恐れる、
さような生活態度を理想主義というデカダンスの始まりとして軽蔑するには、不幸や悪はおろか、破壊さへ肯定する生命の充実を要する。
そういうディオニソス的生命肯定が、悲劇詩人の心理に通じる橋である、とニーチェは言いきるのであります。ニーチェの激しい気性は、アリストテレスのカタルシスの思想に飽き足らなかった。」
要するに、「幸福」だけを狙って「引き寄せる」なんていうのはとんでもないことで、間違って「悲劇」を引き寄せても人はその運命を愛するべきなのだということですネ。
これは恐るべき言葉です。
職業とあの孤独が、むすびつく論理は、納得はできないけれども、もしも、あのふたりが、なにやら、小さな頃から「過剰性」を持っていて、何をするにしても、人の数倍も夢中になっていく気質があり、そのおかげで、皆から少し変人扱いされていてひしひしと孤独を感じているという心理設定。
ならば、納得いくわけです。
西部邁と栗本氏の対談で、日本女性はもう男を愛する力を失ったとまで書かれた、最近の若い日本女性。
この深津理恵のようなキャラが、男性から強く求められているのか、それとも、演歌的でダサイと思われているのか、そのあたりは興味深いことである。
以上、自分自身のための記憶強化のための記事でした。
記憶強化のため、と書いておきながら、忘れているんだから、そうなっていないわけですね。
私は、前ばかり見て戦って来たいわばサラリーマン戦士でしたから、一年前、二年前などのことはすっかり忘れているのかもしれません。
ここ最近のこと、今日のこと、明日のこと、・・・・・・それだけで。
とにかく、思い出せて良かった。
「"好きになることが相手を助ける""知識は(異文化への)恐怖を取り除く"」「これらは全て映画が教えてくれた事」 淀川長治
FIN
◎深津絵里 CM資料
中森明菜 スローモーション~少女A 1983
週刊ビッグコミックスピリッツ 2016年37・38合併号(2016年8月8日発売) [雑誌]/小学館
¥価格不明
Amazon.co.jp
この中森明菜の「スローモーション」が大好きな高校生男子が主人公というのが良い。
「スロモーションをもう一度」というのが気になる。
(ビックコミックオリジナルでは、「黄昏流星群」を読んでいるし。
ビッグコミックでは、「月影ケン」あの裸婦を描かせるとまさに平成の絵師とも言える彼の連載がはじまったし。まいったまいった)
今の時代。あまりにも女尊男卑。
女達が、めだちすぎで、男性はとまどっている。
とくに若い男性は、コミュニケーション能力はまだまだ。
優しい、レトロな女性は、なにやら惹かれる存在なのだろう。
いつも、ひたすらに、手をふりかざして、元気すぎる女性達よりも、少し影があり、
友達も少ないような不器用な女性・少女にはなんとかしてあげたいと男心をくすぐるものが
あるのかもしれない。・・・・・・・・・・・
友達からは、ダサいと言われるのが嫌で、それを隠しているのだが、
ある日、中森明菜のブロマイドが彼の机の下に落ちていて、いいわけに終始する彼。最後には、そのブロマイドを破いてしまう。
ときに、隣のおんなのこ薬師丸が職員室に定期を忘れたので先生から、届けて上げてくれと言われる。
嫌々、家を訪問すると林のなかにちょこんとひとつだけ壊れそうな一家屋。
なかからは、「少女A」が聞こえている。
いるのか、そう叫んでも返事はない。
二階から落ちそうになったとき、彼女にぎりぎり救われる。
そして、彼女の部屋をたまたま見た彼は驚愕する。
・・・・・・・・・・・・・
ビッグコミック・スピリッツ、昨日セブンイレブンで買っていろいろ読んでいたら、こんな漫画があり、驚いた。まさに私の時代を愛するふたりのラブ物語。
やはり、AKBだけがアイドルではないのだと思う。笑。
70年代80年代、の曲は、アイドルは、格が違う。
明菜はアーティスト、聖子は芸能人。
格がちがう。これは個人的意見。
オリンピックの日々 柔道 内村 福原
ベイカー選手の裏話に感動する。
小さな頃にならっていたピアノの先生が姿勢がよくなるということで、柔道を習う。
すると、当時オリンピックで井上選手が亡くなった母親の遺影を持って金を獲ったという
シーン
-表彰台に立っているところを、見て、感動して、僕も金を獲りたいと夢になったという。
田知本選手の決まった瞬間の真剣なまなざし。
あと五秒五秒と必死にはなさないぞと考えていたという彼女。鼻血を出しても「いくしかない」と。
どちらも涙も出た。
life means striaf。
人生は過酷な戦いだ。
三島由紀夫氏も、また、「スポーツにおける国同士の戦いは戦争の雛形である」という、たしかそんなことを言っていたように記憶しているが、人が死なない戦い、それがオリンピック。
福原はおしかった。・・・・・・・・・
内村の個人の逆転優勝なども、もう涙なしには見られない。
「もう、なにも出ない。嬉しいというよりも幸福ですね」 内村航平
オレグを最後につきはなした!!!!!!
運が味方してくれた
嬉しいというより幸福です。
いつもどうり。
内村の言葉は、イチローの言葉とおなじように、心に深く沈殿していく。・・・・・・
Bill Evans & Shelly Manne - Empathy (1962 Album)
私がjazzの魅力にとらわれたのは、ピアノから。
キース・ジャレットに頭をやられたのだ・・・・。
それ以来、基本はピアノばかり聞いていて、前も書いたが植草甚一のマネをして、一日5時間くらい、毎日三年間は聞いたと思う。
5000時間くらいは聞いたと思う。レコードが三台壊れたし、バソコンも、三台潰れた。
このビルは、麻薬で晩年はかなりクレイジーな非日常のなかで演奏した。
良くも悪くも、オスカーピーターソンは好きなのだが、やはり、私はビルの方がすきだ。
特にこの時代。いろいろな実験もしていて楽しい。
2人の子どもの死にどう向き合うか「さらば愛する大地」根津甚八 秋吉久美子 山口美也子
「すべての男は息子ですね」 秋吉久美子
ここ、岩見沢市。
蝦夷梅雨という言葉があるけれど。雨ばっかりで、つまらない。
散歩もいつもの半分くらいしか歩けない。
それでも、部屋の書庫の整理整頓がはかどるのが良いところ。
最近は小津安二郎と、70年代の見忘れた作品中心に見ては、驚いたり、がっかりしたり、
また刺激されたりの日々。
いちいち、ブログに記録するのは、面倒だけども、あとでプリントして、字の間違いやら、文章のおかしなところをなおしたり、いずれは、英訳して、自分だけで楽しむとか、要は絵と、漫画と、小説と映画と音楽とを極めたい。
この映画のなかに、山口美也子という個性的な女優がでてきて、おっと思う。
しらべると、石井隆原作ものに出ているので、ここに、少し、アップしておこうと思う。
知る人ぞ知る。
今では当たり前くらいの描写だけれども、当時は、圧倒されるくらいの、過激な漫画だったのだった。
名美。この名前がよく出てくる。こだわりがあるのだろう。
戸峰の作品に聖子がよく出て来て、小津の作品には、紀子が何回もでてくるというのも、おもしろい。
こだわり。
石井隆の名美。
サラリーマン時代。10回以上も引っ越しをしたのに、どうしても、棄てることが出来なかった。良かった棄てないで。この線は貴重な線だ・・・・・・・・・・・
さらば愛する大地
最近、またDVD化されたらしいが、個人的に、良好な感覚を保てない。・・・・・・・・
考えてみた。
秋吉久美子は好きだし、根津甚八も好きな俳優だというのに。
なにか、救われなさに、胸がつまる。
もちろんこの70年代80年代は、問題作が多かったので、悲劇で終わる映画はたくさんあって、
それはそれで、感動として残るのだが、・・・・・・・・
考えてみた。
不思議なことに、この映画で、たくさんの賞を獲得しているわりには、秋吉久美子はもらっていない。山口美也子が豚をおいかけ、豚のいる小屋で男と性交するシーンがかなり強烈ではあるけれども、秋吉久美子は、まるで、空気のように、良くも悪くも、自我がなく、ないならない良さが出そうなものだけど、悲しいくらい、昔の悪い意味での愛人なのだった。
昔。
近くの風呂屋に行くと、たくさんの裸の男達が牛乳を飲みながら、プロレス中継に夢中で応援していた時代だ。
背中や腕や足に、入れ墨をしている男性はさほどめずらしくなかった。
それに特に、怖くもない。
・・・・・・・・・
時代は変わる。
もうヤクザが近くにいて喜ぶ人もいないと思うし、任侠なんていう言葉は若者は知らないだろう。
でも。
映画の世界は、非日常を描くのである。普段ありえない非日常を描くことで、わたしたちが、無意識におくっている日常生活の幸福や不幸、ちょっとした友情や裏切りや、恋や、愛の終わりや、別れなどを、はっきりと、目の前に、具現化してくれる。それが映画の素晴しいところ。
いつも書いているが、作品そのものは作品そのもので、評価すべきであり、現実にある、ちまちました、小さなくだらないこととむすびつけて、あーでもないこーでもないと、いちゃもんをつける、アホな人間とは酒を飲みたいと葉思わない。
ちょっと考えても。
◎ゴッドファーザー
◎仁義なき戦い
◎パルプフィクション
◎極道の妻達
◎激動の1750日
◎グッドフェロー
ちょっと思い出しただけでも、世界のヤクザ映画はかぎりなくある。
私の好きな、宮尾登美子の作品群には、高知のヤクザの連中がどっさりでてくる。
ヤクザが道徳的にいいかどうか。そんなことよりも、この映画群、作品群には、必須の脇役。そして、そういう時代があったことを日本人としてはわすれてはならないだろう。
ところで。
この「さらば愛しき大地」、茨城の大地を書いた作品には、特にヤクザがでてくるわけでもない。
70年代特有の、独特の、コンプレックス。淀んだ空気感。男同士の獣のようなぶつかり。
女ははっきりと女であり、男ははっきりと男だったな。
蓮の花が季節の変わり目にしずかに枯れて行くように、自然のままに沼のなかに溺れたふたりの少年の死。
その死を忘れないために、根津が扮する幸雄が、入れ墨を背中にいれるのだ。
白川和子が扮するイタコもでてくるので、たしかに、この時代はまだまだ、かつての風習の名残りがたくさん残っていて、その空気感は息苦しくもあり、日本人としては忘れてはならないものだろう。
たしかに。
私の父親の父が亡くなった岩手でも、その当時、40年代。
土葬だったことを思い出す。
幾重にも人が丸くなって、踊るようにして魂を癒すのだ。
はっきり覚えていないが、一週間くらいは、死の弔いはしたはずだ。
少年の死。
立派?な兄との葛藤。金をいつも彼から借りている。
建設現場で働く彼の、夢と希望と挫折。
気がつくと、駄目な男だとばかり、清原のように麻薬を腕にうっていく。
秋吉久美子扮する順子に叱られて、泣かれて、ここまで愛されていいのかというくらいに惚れられているのに、その小さな幸福感が、実感できないのは、麻薬常習者の常。
麻薬による強迫観念がいつも彼を襲う。
ちょっとしたことで、怒り、くだらないことで、どなり、大声でさけび、わめき、また、麻薬をうつ。
最後には、順子の背中にまで包丁を向ける男になってしまう幸雄。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
要は、駄目な男の駄目な日常を、その愛人とともに、くずれおちていく、最悪の時間を柳町監督が、泥臭く描いて行く。
・・・・・・・・・・・
◎資料
『さらば愛しき大地』(さらばいとしきだいち)は、柳町光男監督・脚本による1982年の日本の映画。
キャスト
山沢幸雄:根津甚八
順子:秋吉久美子
山沢文江:山口美也子
順子の母:佐々木すみ江
山沢明彦:矢吹二朗
大尽:蟹江敬三
フミ子:中島葵
山沢イネ:日高澄子
山沢幸一郎:奥村公廷
山沢竹二郎:草薙幸二郎
文江の実兄:松山政路
文江の兄嫁:猪俣光世
霊媒師:白川和子
台湾人の女:岡本麗
女子事務員:志方亜紀子
生コン会社部長:石山雄大
老事務員:港雄一
運転手:粟津號
銀座の雀の客:三重街恒二
評価
『The New York Times』のJanet Maslinは「平穏さと獰猛さが静かに衝突している」と指摘した上で、本作に好意的な評価を与えた[1]。
受賞
キネマ旬報ベスト・テン - 第2位[2]
第6回日本アカデミー賞 - 優秀監督賞(柳町光男)[3]
第6回日本アカデミー賞 - 優秀主演男優賞(根津甚八)[3]
第6回日本アカデミー賞 - 優秀助演女優賞(山口美也子)[3]
第25回ブルーリボン賞 - 助演女優賞(山口美也子)[4]
第37回毎日映画コンクール - 撮影賞(田村正毅)[5]
◎資料


秋吉 久美子(あきよし くみこ、1954年7月29日[1] - )は、日本の女優。静岡県富士宮市生まれ、徳島県日和佐町(現・美波町)、福島県いわき市育ち。本名は小野寺 久美子(おのでら くみこ)。身長162cm。最終学歴は早稲田大学大学院公共経営研究科専門職学位課程公共経営学専攻修了。学位は公共経営修士(専門職)。レジェンド・タレント・エージェンシー所属。
アジア映画祭主演女優賞、日本アカデミー賞優秀主演女優賞、ブルーリボン賞主演女優賞などを受賞している。2013年「「わたし」の人生(みち)~我が命のタンゴ」でモナコ国際映画祭主演女優賞を受賞。そのほかは#受賞歴を参照。
生い立ち[編集]
北海道函館市の出身で研究者だった父親が戦後結核を患い、静岡県富士宮市の療養所に入り、地元出身の看護師だった母親と結婚し当地で生まれた[2][3]。その後、父が徳島県日和佐町(現・美波町)の高等学校に化学教師として赴任したため家族で移り住む[2]。しかし高温多湿の気候が体の弱い父には辛く、本人が小学校入学直前に福島県いわき市に移り、6歳から18歳までいわき市で暮らす[2]。父は小名浜の福島県水産試験場に勤務し、アクアマリンふくしまの立ち上げにも尽力した[2]。福島県いわき市小名浜第一中学校、福島県立磐城女子高等学校(現・福島県立磐城桜が丘高等学校)卒業[2]。高校時代は文芸部の部長をしていた。あちこちの雑誌やテレビなどでもらした言葉を集めた「つかのまの久美子」(1977年、青春出版社)ではユニークで鋭い感性が光っており、五木寛之も「静かな平凡を夢見る卓抜な個性」と帯に感想を書いている。
1972年高校三年生の時、受験勉強中に聞いたラジオの深夜放送、吉田拓郎の『パックインミュージック』で、吉田が音楽を担当した松竹映画『旅の重さ』のヒロイン募集を聞き、親に内緒でオーディションを受けたのが芸能界入りしたきっかけ[4][5][6][7]。
女優として[編集]
『旅の重さ』の主役オーディションで、高橋洋子についで次点となり、自殺する文学少女に扮して本名で映画初出演[4]。翌1973年、大学受験に失敗し、いわき市で予備校通いをしていたとき、感銘を受けたアングラ演劇、はみだし劇場の劇作家・内田栄一の夫人・内田ゆきに身柄をあずけ上京[4]。同年、斎藤耕一監督の『花心中』に一シーンだけ顔を出したのち、芸名を「秋吉久美子」として松本俊夫監督の『十六歳の戦争』に主演して本格的に映画デビュー[4]。しかしこの作品は難解だという理由で1976年まで公開されなかった。1974年、藤田敏八監督の青春映画『赤ちょうちん』、『妹』、『バージンブルース』(日活)に立て続けに主演し人気が急上昇した[8]。
1979年、青い三角定規のメンバーで作曲家の岩久茂と結婚。男児を産み、およそ2年ほど芸能活動を休止した[9]。復帰後、ソープ嬢を演じた『の・ようなもの』 (1981年)、冷めているが可愛げのあるヒロインに扮した『冒険者カミカゼ -ADVENTURER KAMIKAZE-』 (1981年)を始め、『さらば愛しき大地』 (1982年)、『夜汽車』 (1987年)、『異人たちとの夏』 (1988年)、『誘惑者』 (1989年)、『レッスン』 (1994年)、『深い河』 (1995年)などがある。2004年、『透光の樹』では、深遠な性愛シーンを披露した。
近年[編集]
近年はバラエティにもゲスト出演している。TBS系人気番組『クイズダービー』にもゲスト解答者としても数多く出演。しかも1988年10月の特番で、当時産休中だった竹下景子に代わり、4枠に座っていた。ちなみに成績は12勝20敗、3割7分5厘と好成績を修めていた[10]。
作詞家としても活躍しており、DOGGY BAG、松尾光次にも楽曲を提供している。
2004年12月に26歳年下の日系アメリカ人と結婚したが、翌年夏に離婚。しかしその後、同じ男性と2006年2月に再び入籍した。
2006年8月12日、第38回NHK『思い出のメロディー』で司会に初挑戦。会見で「あのころは"痛がる時代"だったと思う」と独自の理論を披露した。
2007年1月からTBSでアナウンサーの中井美穂と共に一視聴者と同じ視点に立った素直な切り口で『世界陸上大阪大会 秋吉&中井 We Love アスリート』の司会を務めた。なお、番組内で出演した各アスリートの写真を秋吉自らカメラマンとなって撮影し、ポスターを制作するコーナーがあった。この時の写真が好評で、世界陸上の会場にポスターの展示場が開設された。
最終学歴は高卒であったが、個別の入学資格審査を経て、2007年9月より早稲田大学大学院公共経営研究科専門職学位課程公共経営学専攻に入学。2009年9月、同研究科を10人中の総代として修了。 2009年公共経営修士取得。世界遺産登録5周年記念事業「熊野古道国際交流シンポジウム尾鷲2009」にパネリストとして参加。 2013年には出身地である福島の風評被害払拭のため消費者庁「東北未来がんばっぺ大使」に就任のほか、「三重県文化審議会委員」も務める。 2013年「わたしの人生~我が命のタンゴ」でモナコ国際映画祭主演女優賞を受賞。
2014年に、映像クリエーターの二人目の夫と離婚[11][12]。
2015年1月、35歳の長男が事故死した[13][14]。
人物[編集]
趣味:旅行、特技:英会話。
シラケが流行した1970年代の時代性を象徴し、そのユニークな言動が話題を呼んだ。当時はカワイコちゃんタレント全盛の時代でもあり、秋吉の言動は余計に目立つこととなる[4]。芸能界にデビューしたての若い少女にありがちな発言を求めた記者に対抗して「面白くもないのにカメラの前で笑ったり、俳優ってバカみたい」などと発言し「シラケ女優」のレッテルを貼られた[4][15]。また『妹』の公開前、宣伝のために出演した番組にて共演者が礼儀正しくインタビューに答えていたのに対して、頬杖をついて別の方向を見ていた。なお、当時の様々なラディカルな言動については後に「不器用だったのかな」と振り返った発言もある。
個人的には、私は、松田聖子はあまり好きではない。
やはり、中森明菜なのだ。彼女は芸術家だと思う。
その意味で、秋吉久美子はやはりartistだと思う。
五木寛之の言葉は的確だ。
「静かな平凡を夢見る卓抜な個性」か。
この秋吉久美子は、少し男性的なのか、普通の女性のように、どんどん変容していかないところが良いと思う。
・・・・・・・・・・・個人的な好み。
しかしながら。
秋吉も息子を失くしているし、根津も事故で他人を死亡させていること。
・・・・・
芸能人って、なにやら、罪深い人が多い気がする。
気のせいか。
作家も、子どもに、障害を背負った人が多いような気がする。あくまでも直感のみ。
データーなどあるはずもない。気のせいか。
要は、みな人は、だれもかれも、順風万風の人生をゆうゆうとおくっている人などいないということだろう。
皆、笑顔でくらしているのは、ある意味生命力の強さかもしれない。
◎根津甚八も負けないくらいに暗い。
人物[編集]
歯科医師の家の三男として生まれる。日本大学第三高等学校卒業、獨協大学外国語学部フランス語学科中退。1969年、唐十郎が主宰する劇団・状況劇場に入団。状況劇場には1979年まで在籍した[3]。
1978年にはNHK制作の大河ドラマ『黄金の日日』に石川五右衛門役で出演、翌年には同局制作の『失楽園'79』、映画『その後の仁義なき戦い』などで主演した。黒澤明監督の映画にも何度か主要な登場人物役で出演している(1980年の『影武者』、1985年の『乱』)。2007年にユマニテに所属。
2002年頃から右目下直筋肥大という顔面の病気を患い活動を縮小していた。
2004年7月に交通事故を起こし、被害者を死亡させた[4]。警察の調べに対し「安全確認が足りなかった」と供述した。その後しばらくの間活動を停止していたが、2006年5月よりブログを運営している(2008年2月より休止中)。
2009年、雑誌『週刊現代』8月22・29日合併号に掲載された夫人の手記において、うつ病を患っていることが明らかにされた。持病の椎間板ヘルニアも悪化しており、療養生活を送っていた。
2010年9月、俳優業を引退することを公表した。演出家や脚本家としての活動は行うが、テレビ出演など表舞台には立たないとしている[5]。また同時に、夫人の取材と回想によって闘病生活と俳優時代を回顧した『根津甚八』(根津仁香著、講談社)が刊行された。
2015年、石井隆監督の要望に応え、映画『GONIN サーガ』に出演し、一度限りの銀幕復帰を果たした[6]。人物[編集]
歯科医師の家の三男として生まれる。日本大学第三高等学校卒業、獨協大学外国語学部フランス語学科中退。1969年、唐十郎が主宰する劇団・状況劇場に入団。状況劇場には1979年まで在籍した[3]。
1978年にはNHK制作の大河ドラマ『黄金の日日』に石川五右衛門役で出演、翌年には同局制作の『失楽園'79』、映画『その後の仁義なき戦い』などで主演した。黒澤明監督の映画にも何度か主要な登場人物役で出演している(1980年の『影武者』、1985年の『乱』)。2007年にユマニテに所属。
2002年頃から右目下直筋肥大という顔面の病気を患い活動を縮小していた。
2004年7月に交通事故を起こし、被害者を死亡させた[4]。警察の調べに対し「安全確認が足りなかった」と供述した。その後しばらくの間活動を停止していたが、2006年5月よりブログを運営している(2008年2月より休止中)。
2009年、雑誌『週刊現代』8月22・29日合併号に掲載された夫人の手記において、うつ病を患っていることが明らかにされた。持病の椎間板ヘルニアも悪化しており、療養生活を送っていた。
2010年9月、俳優業を引退することを公表した。演出家や脚本家としての活動は行うが、テレビ出演など表舞台には立たないとしている[5]。また同時に、夫人の取材と回想によって闘病生活と俳優時代を回顧した『根津甚八』(根津仁香著、講談社)が刊行された。
2015年、石井隆監督の要望に応え、映画『GONIN サーガ』に出演し、一度限りの銀幕復帰を果たした[6]。
◎資料
◎映画に関係があるかどうかはわからない。・・・・・・・・
さらば愛しき大地 - 横田年昭 with 常味裕司 -
◎山口美也子はたしかに、日活ロマンポルノが多い。石井隆の「天使のはらわた」の名美役というのがおもしろい。探してみよう。
少し、調べてみると。
映画[編集]
「市井」より 本番 (1977年、日活)
肉体の門(1977年) - 小政のせん
新宿乱れ街 いくまで待って (1977年、日活)
昼下りの情事 すすり泣き (1977年、日活)
オリオンの殺意より 情事の方程式 (1978年、監督:根岸吉太郎)
白い肌の狩人 蝶の骨 (1978年)
女教師 秘密 (1978年)
ピンクサロン 好色五人女(1978年)
赫い髪の女(1979年) - 春子
さらば映画の友よ インディアンサマー(1979年) - テンコ
天使のはらわた名美(1979年)
修道女 濡れ縄ざんげ(1979年)
むちむちネオン街 私たべごろ (1979年)
希望ケ丘夫婦戦争(1979年) - 夏海テル
レイプショット 百恵の唇 (1979年)
ホールインラブ 草むらの欲情 (1979年)
おんなの細道 濡れた海峡 (1980年)
女子大生の告白 赤い誘惑者 (1980年)にっかつ
夕暮まで(1980年)
さらば愛しき大地(1982年)
無能の人(1991年) - 石山たつ子
教祖誕生(1993年) - 司馬洋子
人間交差点(1993年) - 加納敏江
のぞき屋(1995年)
渚のシンドバッド(1995年) - 吉田公子
ありがとう(1996年) - 鈴木さくら
東京日和(1997年) - 山田
岸和田少年愚連隊(1997年) - リイチの母
新生 トイレの花子さん(1998年) - 倉橋暎子
ワンダフルライフ(1999年) - 食堂係
クロエ(2001年) - 叔母
白い船(2002年) - 養護教諭
凶気の桜(2002年) - 木村玉緒
温泉タマゴ 湯けむり奇談(2004年) - 旅館の女将
ガッツ伝説 愛しのピット・ブル(2006年1月14日(土)公開、 監督:野伏翔)
全身と小指(2006年7月15日公開、監督:堀江慶)
ミラクルバナナ(2006年9月16日公開 監督:錦織良成) - 外務省面接官
おばちゃんチップス(2007年1月27日公開、 監督:田中誠) - 赤銅麻衣子の母
サッド ヴァケイション(2007年9月8日公開、 監督:青山真治) - 小野
砂の影(2008年2月2日公開、監督:甲斐田祐輔)
笑ひ教(2009年)
トルソ(2010年、監督:山崎裕)
最高でダメな男 築地編(2010年4月3日公開、監督:内田英治)
デンデラ(2011年6月25日公開、監督:天願大介)
朱花の月(2011年)
くらげとあの娘(2014年8月9日公開、監督:宮田宗吉)
監督の柳町の記録をコレクションしておこう。
茨城県行方郡牛堀町(現在は潮来市)の出身。茨城県立水戸第一高等学校、早稲田大学法学部卒業。大学在学中から映画作家を志望しシナリオ研究所へ通う。
卒業後に就職するも、1969年からフリーの助監督として映画撮影に携わる。東映教育映画部では大和屋竺に師事。1974年に自らの製作会社「群狼プロダクション」を設立し代表に就任(現在は、株式会社プロダクション群狼)。
その後、当時日本で最大規模の暴走族であったブラックエンペラーを追ったドキュメンタリー映画の製作に着手。2年の製作期間を経て1976年に第1作『ゴッド・スピード・ユー! BLACK EMPEROR』を発表した。安田生命ホール(現・明治安田生命ホール)での小規模公開から始まったが、評判を呼び、東映系で拡大ロードショー公開される。
この第1作を戦後生まれで初の芥川賞作家中上健次が評価したことがきっかけとなり、『十九歳の地図』(中上健次の第69回芥川賞候補作)を映画化し、1979年に劇映画デビューすることになる。
以降、『さらば愛しき大地』(1982年、根津甚八・秋吉久美子主演)、『火まつり』(1985年、脚本 中上健次)、『愛について、東京』(1993年)などで各方面から高い評価を受ける。
1990年には当時の世界的スター、ジョン・ローンを主演に迎え日米香港合作映画『チャイナシャドー』を製作(原作は直木賞作家・西木正明の『蛇頭(スネークヘッド)』)。初となった海外との合作を成功させ中国、台湾、香港などへ積極的な関心を示している。
2001年度~2003年度に、早稲田大学客員教授。このときの経験をもとにした映画が『カミュなんて知らない』である。
2006年に第19回東京国際映画祭の国際審査員を務める。出身地である茨城県の「いばらき大使」、潮来市の「水郷いたこ大使」も務める。
好きな映画監督は、溝口健二、ジャン=リュック・ゴダールなど。
ノンフィクション作家佐野眞一、株式会社ボイジャーの萩野正昭社長は、同窓(早稲田大学)であり友人。
監督・出演作品一覧[編集]
監督作品[編集]
ゴッド・スピード・ユー! BLACK EMPEROR(1976年、ドキュメンタリー)
十九歳の地図(1979年)
さらば愛しき大地(1982年)
火まつり(1985年)
チャイナシャドー(1990年)
愛について、東京(1993年)
旅するパオジャンフー(1995年、ドキュメンタリー)
カミュなんて知らない(2005年)
ここでもわかるように、中上が、第1作『ゴッド・スピード・ユー! BLACK EMPEROR』を評価したことが奇縁で、中上の作品を映画化するようになっている。
個人的には、中上の作品の良き読者ではないけれども、もっと長生きして、作品を描けば、おっと思うような作品が出たかもしれない。
新宿の女達との感染で死んだのも彼らしい。
村上龍は蠅って感じだな。子供だましさ、そういうもんだよ。 中上健次
対談になると、すぐに、人の悪口。笑。
ずばずばとものを言う人が今あまりいないから、ある意味、貴重だったのだが。
・・・・・・・・・・・・・・・
初めての赤ちゃんを授かった秋吉久美子ついてひと言
「卵で産みたいです」 秋吉久美子
FIN
一神教と八百万神・・神隠しとは「千と千尋の神隠し」×「レフト・ビハインド」 「シンデレラ」
八百万神(やおよろずのかみ)とは
数多くの神,すべての神のこと。類似の語に八十神(やそがみ),八十万神(やそよろずのかみ),千万神(ちよろずのかみ)がある。森羅万象に神の発現を認める古代日本の神観念を表す言葉。
「三度やって駄目だったからもう一度やるんだ 」
Three times isn't enough.
史上最大の作戦
The Longest Day
北海道の今、またゆりかえしが、きたように、雪国になっております。
植草甚一のエッセイに、「雨ふりだからミステリーでも読もう」というのがありますが、
ここでは、「雪だから漫画でも読もう」という気持ちになるもんです。
もう絶版の「ビックゴールド」というおそらく、「ビックコミック」の前身みたいな漫画本。
創刊号から持っておりますが、そのナンバー2を、ぺらぺら見ておりました。
瀬戸内晴美原作の、「みずめ」を、牧美也子が描いていたり、(いやあほんとうに絵がうまいですね。)、
水野英子の「薔薇達」とか、すごい傑作漫画ばかり。
今の若者は、ジャンプかもしれませんが、昔の若者は、こんな漫画を読んでいたんです。
楳図かずおといえば、まことちゃんとか、ホラーのイメージがものすごく強いですが、
「smile」という傑作漫画が、この号にのっています。
とにかく、天才としか、思えない短編です。
絵は例によって、緻密。
コマが小さいのに、ぐいぐい、ひっぱっていく愛の童話物語のような。
レヴューでも、「火の鳥」と比較している人がたくさんいましたね。
今では、「イアラ」「内なる仮面」「ドアの向こうに」の三冊の短編集がでていますので、おそらく、このどれかの中に、含まれていることでしょうが。
手塚治虫の「火の山」。
なんと、この「昭和新山」物語なんですが、北海道に住んでいる私は、しょっちゅう、
行きましたし、修学旅行などのコースにもなっていました。
手塚治虫が、わざわざ、昭和新山の資料館の三松三郎氏や、役場の担当の方に、取材をして、このビックゴールドに、一挙に、100ページで発表した作品です。
今は、よく古本屋でも、見かける作品ですが、当時は、ものすごい意気込みで、手塚治虫氏がこの作品にチャレンジしていたということが、よく感じられる作品です。
それに、今では、文庫本くらいの大きさでしか読めませんが、このビックゴールドは、A4ですので、迫力があります。

以前も記事に描きましたが、男と女の不思議な縁。
どうしようもないろくでなしの男と、あばずれの女が、不思議と、ケンカしながら一緒に暮らし始める・・・・・・・・・最後は夫婦になって、火の山を守ろうとする。
その男の名前は、たまたま、昭和=としかず。
それで、尊敬する三松さんが、昭和新山という昭和にちなんでつけた名前は、「オレの名前をつけてくれたんだ」と感激するところ、やはり、上手いです、手塚治虫。
・・・・・・・・・・・・
あと・・・・・・・
私の好きな「トワイネラの白鳥」。
「トォネラの白鳥」を扱った作品といえば、水野英子。
それが、手塚治虫にもあるとは知らなかった。
「0次元の丘」だ。
いまでこそ、輪廻の科学的な研究もされるようになってきたけれども、
この宇宙、人間の知っていることなど、軒先の一本の草木の露みたいなものだろう。
解説の夢枕獏のあこがれにも似た手塚治虫の10の天才の秘密みたいなもの。
なかなかだと思う。
手塚治虫名作集 (5) (集英社文庫)/集英社
¥627
Amazon.co.jp
・・・・・・・・・・・
映画ですが。
この手塚治虫氏は、一時、400人程が働いていた虫プロダクションの社長。
管理がやはり苦手だったのか、つぶしてしまいます。
アニメ制作に、彼が、ぞっこん惚れ込んでいたのは、ディズニーに会いに行っていたことも記録に残っていますし、夢中で作品をつくっていたのですが、やはり高尚すぎる作品は、一般大衆の受けが弱いのでしょう。
それで、また、初心にもどって描き始めたのが、ブラック・ジャックという傑作です。
手塚治虫氏が死ぬ数年前の作品ですから、凄みがあります。
ガンもその頃、種がでていたのでしょうか、・・・・・・私にはわかりませんが、作品を描くのには、胃に負担がかかりますから。
宮崎駿氏の作品は好きですが、彼は暴言がおおいですね。
手塚治虫氏にも批判の言葉を投げつけていますので、けっこう、嫉妬心の強い人なんだろうと想像します。
それでも、「千と千尋の神隠し」はおもしろいです。
これは、英語版では、spirited awayと、訳されていますが、ちょっとこの言葉にひっかかったのです。
それは、たまたま、映画「レフト・ビハインド」という映画を見たのです。
(ニコラス・ケイジが、出ていたので見ただけなんですが・・・・・・・・)
神隠しの映画でした。・・・・・・・
不思議な映画。
でも、やっぱり西洋映画、一神教映画。
「千と千尋の神隠し」と比較すると、あまりにも、神の概念がちがいすぎる・・・・・・・
この「レフト・ビハインド」の挿入歌。
jack lenzは歌う・・・・・「こころを入れ替える暇はない、神はあらわれ、ひとびとは取り残された」
最初から、一種の飛行機のパニック映画だと思っていたし、なんせ、ヒロインが、私の好きなニコラス・ケイジなので、わくわくしながら見ていたのですが、不倫中の彼が、仕事に没頭するあまり、そして、神に夢中の妻に嫌気をさして、娘と息子との約束を反古にして、飛行機に乗るところまでは、どんな展開をするのかと・・・・・・・見ていたのですが、飛行機内で、子ども達が、突然、消え去るシーンがあり、びっくり。
これ、どうやって映画をまとめるのかなと、少し心配して見ていたのですが、神様の仕業ということになりました。
やはり、私たち日本、正月には、神社にお参りし、お盆の行事や、葬式は仏前なのに、クリスマスもみんなで、祝う・・・・大騒ぎ、そんな民族から見ると、せんとちひろのほうがなにやら、こころが、落ち着きます。
・・・・・・・・・・
最初の頃は、見ていて、神様に夢中になる物語のあらすじに対して、なにやら、その家族に不幸になった裏の伏線があって、たとえば、以前この記事で紹介した、「火宅の人」の檀一雄の妻のように、子どもが、突然、重病になって、そのために、祈祷をしたり、精神を少しわずらうような、振る舞いをしたり、そんな連想をしていたのですが、・・・・・
最後は、しっかりと、「神を信じるのであれば、ここで祈って下さい」というパニック状態でのニコラス・ケイジの言葉に、逆に、あまりにも単純ということで、おどろいてしまいました。
やはり、調べてみると、
さすがキリスト教の西洋・アメリカ・・・
『レフトビハインド』( Left Behind )とは、ティム・ラヘイ、ジェリー・ジェンキンズの共同著作によるアメリカの小説。およびその続編からならシリーズ。
公式サイトによれば全米で6,500万部を売り上げたベストセラーである[1]。アメリカ本国では映画化、ゲーム化もなされている[要出典]。日本語訳はいのちのことば社から刊行されている。
時は近未来、最後の審判が迫り「ヨハネの黙示録」の預言が実現していく世界を描く。「患難前携挙説」の立場をとっており、「携挙」によって信心深い人々や幼い子供が姿を消すところから物語が始まる。
「患難前携挙説」とか、「携挙」とか、エヴァンゲリオン用語みたいな響きの言葉です。
映画では、日本語字幕ですので、あんまりマニアックな言葉は省略したのかもしれません。
あとで、また、じっくりチェックしたいとは思っていますが。
たとえば、このような言葉は映画のなかでは、強調されてはいなかったと思うのですが。
原作のなかでのオリジナルの用語定義でしょう。
トリビュレーション・フォース (Tribulation Force)
患難時代(トリビュレーション)に備えて結成された。聖書を研究し、人々を信仰に導くだけでなく、反キリストとの戦いを目的とする。
グローバル・コミュニティー (Global Community)
ニコライ・カルパチアを「主権者」と仰ぐ世界政府。イラクの地に新たに建設した「ニュー・バビロン」を首都とする。人類の統合と世界平和という美しい理想をかかげつつ各国の武装解除をすすめるが、自らは兵力・暴力をもって、コミュニティーに反発する国家・個人を潰していく。
エニグマ・バビロン・ワン・ワールド・フェイス (Enigma Babylon One World Faith)
グローバル・コミュニティーにおいて事実上の国教の地位にある新しい宗教。世界中の宗教を寄せ集め統合した教義を持つ。この宗教の聖職者を信道士(フェイス・ガイド)という。その祈りでは「宇宙の父母」や「動物神」が語られる。聖書の記述もあくまで象徴や比喩として解釈し、トリビュレーション・フォースが信じるような「原理主義的」解釈を狭量なものとして否定する。
ニコラス・ケイジは、どんな映画でも、こなしてしまいますので、ちょっと、びっくりするような感覚もありますが、名作だけではなくて、このような映画でも、必死で演技しているところが好きです。
「せんとちひろの神隠し」
これの英語題名は、Spirited Awayとなっていますので、まさに、「レフト・ビハインド」同様に、突然消えてしまう子ども達そのものなのかもしれません。
「レフト・ビハインド」では、子ども達は、あっという間に、天国にまさに「携挙」されるわけですが、同じ「携挙」でも、ちひろは、異世界に迷い込み、神々の訪れる湯屋で働くことになった少女、でした。
宮崎駿監督作品。2001年7月20日に日本公開。興行収入300億円を超えた日本歴代興行収入第1位の大ヒット作品ですが、とにかく、その異次元異世界の神々の不思議さ・多様さに・西洋人は驚愕したようで、たまたま、見た番組では、宮崎監督は、フランスの女性ファン達からの絶賛の嵐を浴びていたと思います。
フランスの宗教。
調べてみますと、
宗教面では、国民の約7割がカトリックといわれている。カトリックの歴史も古くフランス国家はカトリック教会の長姉とも言われている。代表的な教会はノートルダム大聖堂、サン=ドニ大聖堂などが挙げられる。パリ外国宣教会はその宣教会。フランス革命以降、公共の場における政教分離が徹底され、宗教色が排除されている。
と、ありますので、やはり、プロテスタントと違って、フランスやアイルランドは、どこか、ケルトの自然への愛・・・つまり、日本人の自然の神秘への傾倒と近いところが、わたしには感じられますが。
どうなんでしょうか???
以前、ブルターニュの森のなかにいる妖精のことについての、自然観察の素晴しいドキュメンタリーを見ましたが、このブルターニュは、おもしろいです。
伝説と伝統の大地
海の国であると同時に森の国であるブルターニュ地方は、変化に富んだ気候と驚きの風景に満ちています。ブルターニュの生き生きとして力強い風に身を任せ、浜辺や、断崖絶壁、荒地、中世の町を訪れましょう。ブルターニュならではの風物と奥深いその歴史に触れ、文化と自然を満喫しましょう。馬に乗ったり、潜ったり、船に揺られたり、祭りやフェスティバルのリズムに合わせてスウィングしたり、パブの和気あいあいとした雰囲気に浸ったりしましょう。そして何より、心から安らいでくつろいでください。
独特の雰囲気を持つブルターニュの沿岸地帯
海賊の町として知られ城壁に囲まれたサン・マロのコード・デメロード(エメラルド海岸)から神秘的なコート・ド・グラニット・ローズ(バラ色の花崗岩海岸)まで、ブルターニュの沿岸地帯は、ほかのどこにも似ていない独特の雰囲気を持っています。税関吏の道は、ブルターニュ特有の荒地と断崖の間を歩くハイキング・コースで、気候の良い時には、ハリエニシダやエニシダの香りが、さわやかな海風と交じり合います。沖合では、ブルターニュの島々が魅力を競い合っています。グロワ島、ブレア島、グレナン諸島、ウェサン島、ベル・イル・アン・メール島で、野生のままの浜辺や自然保護区の入り江、灯台などを見学しましょう。セット・イル(七つ島)は、フランスで最大の鳥類保護区です。ニシツノメドリ、ヨーロッパヒウメ、シロカツオドリが、優雅に暮らしています。フレエル岬からは、海と荒地の間で踊る鳥たちのバレーが見物できます。ブルターニュ地方の言葉で「小さな海」を意味するモルビアン湾を臨む海岸に沿った100㎞ほどの遊歩道を、保護された自然を眺めながら散策しましょう。イル・オ・モワンヌ(修道士の島)などの野生のままの自然が残る場所がいくつも隠されています。
伝説と歴史遺産の狭間で
この地方の歴史の証人でありシンボルであるブルターニュ高等法院は、今では控訴院となっていますが、ブルターニュ地方の中心都市であるレンヌの主要な建築遺産です。ポン・タヴェンの美術館では、モーリス・ドニからポール・ゴーギャンに至るブルターニュ地方を描いた画家たちの作品を見ることができます。ブルターニュ地方はあらゆる年代の人々に愛されている観光地です。子供たちは、サン・マロの大水族館やポン・スコルフの動物園やブレストの水族館オセアノポリスが大好きです。ブロセリアンドの森で、伝説の魔術師マーリンと妖精ヴィヴィアンとアーサー王の足跡をたどり、フジェール城では、妖精メリュジーヌの魔法の虜になりましょう。伝説と遺産といえば、モン・サン・ミッシェル修道院(ノルマンディー地方ですが、ブルターニュ地方からわずか4㎞です)や、ロカマドゥールやカルナックの巨石群もあります。キリスト受難群像や、パルドン祭り、礼拝堂など、ブルターニュ地方には宗教の伝統が根強く残されており、中でもボーポールの海の修道院とヴァンヌのサン・ピエール大聖堂は、中世の宗教建築を代表する建物です。
ブルターニュ地方のスペシャリテ
伝統と民俗芸能によって形作られているブルターニュ地方は、食の伝統も大切に守っています。たとえば、そば粉のガレット、シードル、ブルターニュ風蜂蜜酒、豪華なシーフード・プレート、ブルターニュ風ポトフのキ・カ・ファース、焼き菓子のファー・ブルトン、そしてクイニー・アマンなどなど・・・。
こんな資料を読むと、やはり、フランス人は、「せんとちひろの神隠し」は理解できてあたりまえなんだなあ、と妙に感心してしまいます。
モンサンミッシェルも、一度だけ行きましたが、実に、思い出深いところです。
パリから、たしか、六時間くらいバスに乗って、ついて、二三時間の自由時間だけで、また六時間かけてもどってきただけですが、写真はたくさん撮ってきました。
日本の伊勢神宮。
ここだけは、死ぬ前に一度は行きたいところです。
五十鈴川で、手を洗う。・・・・・
みそぎ。
日本の水道水は、昔ほど、きれいではないにしても、十分に飲むに耐えうる。
外国の水はひどいですから。
水。
外出して家にもどったら、誰しも、日本人ならば、手を洗う。
トイレに入ったら、手を洗う。
神社の入り口で手を洗う。
茶道でも、手を洗う。
天照大神つまり、アマテラスオオミカミのことを、最近の若者は、テンテルダイジンとよぶそうです。
それでも、光、太陽の光が、私たちをなにか守ってくれている、見守っていてくれている、
日本人が死んだら、墓のなかにじっとしているんではなくて、この自然界のなかで飛び回れる、・・・・・・・・そう、日本の豊かな自然界こそが、日本人の天国というか、ゆっくり永劫の休息場所という感覚が、個人的な意見ですが、私にはあります。
「千と千尋の神隠し」は、「霧のむこうのふしぎな町 」
柏葉 幸子をアニメ化しようとした話しかジブリにあったときに、宮崎駿氏が、断念したあとに、ライバル意識を持って「千と千尋の神隠し」を制作したということらしいです。
私もこんな年になってから、初心にもどり、高校生の時の夢をおいかけています。
それが、なにか?
「北国のふたり」
「シンデレラ」
ディズニー・・・・・・・
以前記事に書いた「ファンタジア」の他の短編も素晴しいですね。
最近は、それをすべてまとめた、DVDも発売になったということ。
でも、シンデレラのディズニー版はやはりちょっとすごすぎます。
特に、この後半。
ネズミたちや、犬たちが、協力しあい、いじわる猫をやっつけて、継母に閉じ込められたシンデレラに、部屋の鍵を渡すシーンなどは、こんな年になっても、感激します。
そして、単純ではありますが、彼女の夢の実現するあたりの、彼女の表情や動き。
いまでも、これだけ、何回見ても、感激するわけですから、
制作発表当時の、私の記憶を思い出しても、もうびっくりしました。
なんで、こんなスムーズな動きが、アニメーションでできるのだろうかと・・・
そして、あの有名な歌。
女性でなくても、わくわくします。
テレビをつけると、朝から晩まで、マイナスな情報ばかり。
そこに、いつもの言葉の乱暴な、そして、勝手なことばかり言うコメンテイター。
あんなものばかり見ていると、俗な自分が、さらに、俗俗になる感じがしますので。
なるぺく良き番組を見つけて見るようにしています。
ところで・・・・・・・・
森有正という文学者。
好きなのですが、ずっとパリで暮らしています。
森氏の母親はピアノを弾くし、牧師であった父親もヴァイオリンを弾く。
そんな環境のなかで森氏は成長し、文学と音楽がひとつになったような自己の体験を、信じるようになったのかもしれない。
彼はボードレールとリルケの「文学+音楽」の仕様に感じ入る。
しかしながら。
日本人でありながら、日本の楽曲をまったく知らずに、環境の中から育ったとはいえ、森氏のような日本人はおもしろいと私はいつも思う。
日本人は果たして魂まで西洋人になれるのか?
確かに、私が、絵本と言えば、やはり、「マッチ売りの少女」や「人魚姫」の圧倒的な印象は、脳裏に焼き付いて離れない。

「ぶんぶくちゃがま」かな、日本の絵本で怖いような不思議な印象を持つのは。
私が、幼稚園の頃。
読んだ記憶がある。
あとは「サルカニ合戦」。
なぜ、日本の民謡を皆はあえて、聞くことはしないのだろうか?
昔お世話になった三味線奏者の三宅氏の「牛追い」の民謡歌は素晴らしかった。
三味線には日本の魂があると思う。
三宅良二氏。
奥様にも、お世話になりました。
ほんとうにいまでも、感謝しています。
ふたりの舞台のバックの絵まで、描かせていただいて、感謝感謝でした。
そんなわけで、西洋東洋・・
せめて、半分西洋、半分日本。それくらいの比率で音楽や映画や文学を楽しみたい。
想像妄想空想。
しかしながら、外国の子供達も日本のアニメを観て育つ。無国籍ということの、メリットとデメリット。根無し草のメリットとデメリット。
根無し草という生き方もまた、あるのかもしれない。日本人。
悩むところ。
まあ、「流れる」ように交互に聞きつづけよう。読み続けよう。
「女性は我々の作品を評価できる最良の判断者である。
彼女たちの好みは非常に重要だ。
映画館に足をよく運び、男性たちを引っ張って来てくれる」
女性たちが好んでくれれば、男がなんと言おうがかまうものか!!!!
ウォルト・ディズニー
FIN
PR: 大規模な自然災害でローン返済が困難な方へ-政府広報
プラス思考の技術―仕事・人間関係を変える心理技法
プラス思考の技術―仕事・人間関係を変える心理技法/ごま書房
¥1,363
Amazon.co.jp
書いてあることはあたりまえのこと。しかし、具体的なコツが書いてあり、確認するにあたり、良き本。
たとえば、完全を期待しないとか、わからないところはどんどんとばせとか、
プラス思考の本質がよくわかる。
この手の本は、多いけれど、脳内革命なんかもおもしろかった。
本の仕事をしている人なんかには参考になると思う。
女性写真集の ある一冊 FINaL―小松美幸写真集
仕事がら、たくさん写真集はチェックしているが、女性の写真集はなかなかこれはすごいというのは見つからない。
もちろん、買うのは男性だとおもうので、好みはあるだろうが、・・・・・(最近、女性の写真集を手にとって立ち読みしている女性が増えているのは現代的だなあと思う)
その中でも、
このFINaL―小松美幸写真集は、素晴しいと思う。
もちろん個人的に、クラシックバレエの衣装があるというのもいいのだが・・・小松の表情が素晴しい。若い時にこれくらいの軽いタッチの写真集なら誰でも撮ってもらいたいと思うだろうと、わたしに思わせたくらいのレベルである。
FINaL―小松美幸写真集/音楽専科社
¥2,097
Amazon.co.jp


◎資料
実践女子大学在学中の1990年、「小松 美幸」として『週刊プレイボーイ』10月23日号の水着グラビアでデビュー。美しいフォルムを描く美乳が話題となり、グラビアモデルとしてトップクラスの人気を得る。
雑誌のグラビア、写真集、イメージビデオを中心に活動し、1992年には星野陽子とともに共同石油のカレンダーガールに起用された。この間、Vシネマ『ダウンタウン・ガールズ』(1991年)に出演したことはあったが、1992年7月に出版された4冊めの写真集『The LAST SHOW』で女優への転身を宣言、同年8月の城戸賞受賞シナリオの映画化作品『福本耕平、かく走りき』では準主役を務めた。
1994年、「小松みゆき」に改名。しばらくは『TOKYO BALLADE 危険な誘惑』『女教師』といった従来路線のセクシー系作品への出演や、ヘアヌード写真集のモデルとしての活躍が目立ったが、その後はVシネマ、テレビドラマを中心により幅広い役柄を演じた。
演技力は非常に高い水準にあり、主な出演作に『イグアナの娘』(テレビドラマ、1996年)、『イグナシオ』(1996年)、『北京原人 Who are you?』(1997年)、『新・バブルと寝た女たち』(1998年)、『ノストラダムス滅亡録〜遺伝子の新世紀』(1999年)などがある。近年ではフジテレビのテレビドラマ『大奥』(2003年)にレギュラー出演し、話題になった。
2009年12月6日婚姻。
子供に残す財産とは
よくうちの妹と話すのだが、「おにいちゃん、うちみたいに、遺産がなにもないといいね。喧嘩もないし、ははははは」と笑ったので、「それだけがうちのいいところだよ」と私も笑う。
うちの母親など、自分の葬式代さへ残さなかったのだから。笑。
子供に遺産を残すのは親の義務と考える人もいて、私はいつもアホな親だなあと考えている。
人生は、いつも戦いだ。
親からの遺産をあてにして暮らすようになることが目に見えているのに、それをあえてするのは、
現代人の最悪の思考だろう。
岡本太郎氏が書いているように、苦労すればするほど、人は幸福になるのだから。
名前は忘れてしまったが、昔の偉い武士もまたそんなことを書いている。子供に金を遺してはいけないと!!!
・・・・・・・・・・・・・
だいたい、本日のやりたいことをやって、少しのんびりしていて、ジョブスの本を読んでいたら、こんなことを書いていてなるほど偉い人はみな子供を、真の意味で愛しているのだなと感じた。
スティーブ・ジョブズ 神の遺言 (経済界新書)/経済界
¥864
Amazon.co.jp
錦織勝利!!!!!!!!! 錦織から感動と勇気をもらう
なんだ?????
すごすぎて、涙がでた!!!!!!!!
彼も泣いていた。
こんな試合ばかりで、錦織の足は大丈夫だろうか?
この試合は、歴史的な名試合だと思った。魂が震えた。
サイコパス「ゴーン・ガール」『KIZU―傷―』『冥闇』ギリアン・フリン ロザムンド・パイク
映画の長さは、人間の膀胱がどのくらい耐えられるかで決めるべきだ。 アルフレッド・ヒッチコック
「サイコ」
私は血が出まくりの映画は若い頃は苦手だった。
しかしながら。
歴史をひもとくと、どこの国もいつでもどこでも殺戮の歴史はかならずある。
人類のパンドラの箱のなかの悪。
意識の善と無意識の悪。
遺伝子と魂の井戸の奥の奥の奥のなかの秘密。
いつしか、「血」そのものというよりも、人間そのものの残酷性やら、歴史やらに、
興味そのものもうつっていく。
あらゆる動物・生物のなかで、これだけ殺戮を繰り返している生物はいるだろうか?
そう考えると、また、違う視点からの、ミステリーサスペンスサイコ的作品の見方も変容してくるような気がしている。
ゴーン・ガール 上 (小学館文庫)/小学館
¥812
Amazon.co.jp
映画好きの友達からの、新年会の時に、熱心な薦めで、見た「ゴーン・ガール」。
いわゆる、サイコパス的人格者を描いた映画。 と、自分では勝手に考えている。
若い頃はまったくミステリーは駄目だったけれども、やはり、年のせいか、興味深く見ることができた、。友達に感謝。
子どもや、家族で見るような映画ではないけれど。・・・
すでに、たくさんの人がこの映画は見ているだろうし、賛否両論はあたりまえ。
嫌いな人は嫌い。好きな人は好き。そんなテーマでもありますね。
ただ、淀川さんがいつも言うように、映画・文学・小説・芸能・音楽・漫画・・・どれも、見る人が見たいように見れば良いと、思うので、自分なりの楽しみ方をして、そのあたりを備忘録しようと思っている。
最初のナレーションの声や雰囲気は好きだ。
なにやら、「アメリカン・ビューティ」のファーストシーンのようだ。
あるいは、かつての、名作ぞろいの、フランス映画ヌーヴェルヴァーグなどで、
最初のシーンで、語られる言葉・・言葉・・言葉。
しびれる。
たまたま、この男性、たしか、ミズーリー州出身。
ミズーリー??
あれ、なんだったかしら? 私は考えた、何か、感じる・・・・
たまたま、今比較文明を研究している学者さんから、依頼されている、コリンズビルのカホキア遺跡の油絵の作品にとりかかっていたのです。
◎インディアンがたくさんすんでいたところですね・・・・・・
この作品は、意外に、時間がかかっています。後少しで完成です。
びっくりしました。
やっぱり、こうやって、ランダムにてきとーに見ているような映画作品であっても、どこか、自身の無意識のなかでは、縁があるようで。
それに、このヒロイン。ロザムンド・パイクは、イギリス出身ですし、
なんと、三島由紀夫氏の「サド公爵夫人」の主演もつとめているんです。
サド侯爵夫人・わが友ヒットラー (新潮文庫)/新潮社
¥497
Amazon.co.jp
これまた、なにかの糸ですね。



原作者は、ギリアン・フリンという美しい女性。
だいたいのあらすじ・・・・ふりかえると。
ニックは三十四歳、ニューヨークで雑誌のライターをしていたが、電子書籍の隆盛で仕事を失い、二年前、妻エイミーとともに故郷ミズーリに帰ってきた。しかし都会育ちの妻にとってその田舎暮らしは退屈きわまるものだった。結婚五周年の記念日、エイミーが、突然、謎の失踪を遂げる。家には争った形跡があり、確かなアリバイのない夫ニックに嫌疑がかけられる。夫が語る結婚生活と交互に挿入される妻の日記。異なるふたつの物語が重なるとき衝撃の真実が浮かび上がる。大胆な仕掛けと予想外の展開、「NYタイムズ」で第一位に輝いた話題のミステリ登場。
この「ゴーン・ガール」の成功について、自身、語っているクリップもある。
聞いた話しでは、男性よりも女性の方が、血の事件に興味を持つ割合が高いそうである。
なぜならば。
自分が被害者にならないように、無意識に、自分をどうやったら守ったら良いか、探っているのかもしれない。
しかしながら。
その美しき女性そのものが、パンドラの箱をあけることもあるのだ。
また、どうして、この小説が、アメリカで、大ベストセラーとなったのか、
キャスター番組のようなところでも、この「ゴーン・ガール」について語られる。
『KIZU―傷―』『冥闇』「ゴーン・ガール」の、まだ三作しか発表がないようですが、これからミステリーファンの間では、人気がでてくるのでしょうか。
◎資料から
処女作『KIZU―傷―』は、ミズーリでシリアルキラーによる事件が起こり、その調査のため新聞記者がシカゴから故郷へ戻ってくる物語で、家庭崩壊や暴力、自傷行為などがテーマとなっている。第2作『冥闇』は、24年前に自分の証言により母と姉を殺した罪で逮捕された兄は本当に真犯人だったのか明らかになる物語である。近著である第3作『ゴーン・ガール』は2012年6月に出版された。第1作、第2作共に数々の賞を受賞するなど高い評価を受け[4]、スティーブン・キングに絶賛された。
小説はだいぶん前に発売されていて、Amazonでもすでに安いです。
KIZU―傷― (ハヤカワ・ミステリ文庫)/早川書房
¥907
Amazon.co.jp
歯を引き抜かれた少女たちの遺体が発見され、新聞記者カミルは取材のためにやってきた。母との確執で飛び出した故郷の町に。取材を始めた彼女は、犯人は被害者の身内なのではとの町の噂を聞く。そんなとき、カミルは母と異父妹に再会した。そして、事件の真相とともに彼女の過去の傷がぱっくりと口をあけ…傷つき壊れる直前の人々が、悲劇を紡ぐサスペンス。英国推理作家協会賞二部門を受賞した大型新人のデビュー作。
ギリアン・フリンの一作目の映画『KIZU―傷―』
フィンの書評などを聞いていると、楽しい。
また、この作者本人、ギリアン・フリンのイギリス人らしいインタヴューもあって、興味深い。
彼女の二作目、「冥闇」
冥闇 (小学館文庫)/小学館
¥998
Amazon.co.jp
7歳のときに母と二人の姉を惨殺されたリビー。彼女の目撃証言によって兄のベンが殺人犯として逮捕される。それからから24年、心身に傷を負い、定職にも就かず、殺人事件の哀れな犠牲者として有志からの寄付金を食いつぶしながら、無気力に生きるリビーのもとへ、有名殺人事件の真相を推理する同好の士である「殺人クラブ」から会への出席依頼が。集まりに参加し、殺人クラブのメンバーが自分の家族に起こった忌まわしい事件に関心を抱いていることを知り、リビーは謝礼金を目当てに、事件の真相を探りはじめる……。
現在のリビーの視点と、事件当日の兄ベンと母パティの視点から物語が交互に語られ、やがて悲劇的な真実が明らかにされる衝撃のダーク・スリラー。
シネマは、やはり、日本では未公開。
不思議なのは、フリンのこれらの二作ともに、日本では公開されていないのではないかと思う。クリップはあるが、日本版はない。
おそらく、映画公開のプロが決定することだろうから、日本人向きではないというか、あまりにも、血のシーンが多いからではないだろうか。
逆に言えば、「ゴーン・ガール」は血のシーンが割合と少なく、普通の日本人が見ていても、許せる範囲なんではないだろうか。(なんといっても、勝手なことを描かせてもらうけれども、西洋映画のミステリーの在る一部の作品など、血・殺戮場面の多い事多い事!!! そして、観客はポップコーンとコーラを飲みながら、それらの血の映画を楽しむのだから、・・・・・・)
二作目の「」についても、フリンは雄弁だ。
GILLIAN FLYNN TALKS ABOUT DARK PLACES
・・・・・・・・・・・・・・
サイコパスとは?wikipedia
サイコパスは社会の捕食者(プレデター)であり、極端な冷酷さ、無慈悲、エゴイズム、感情の欠如、結果至上主義が主な特徴で、良心や他人に対する思いやりに全く欠けており、罪悪感も後悔の念もなく、社会の規範を犯し、人の期待を裏切り、自分勝手に欲しいものを取り、好きなように振る舞う。その大部分は殺人を犯す凶悪犯ではなく、身近にひそむ異常人格者である。北米には少なくとも200万人、ニューヨークだけでも10万人のサイコパスがいると、犯罪心理学者のロバート・D・ヘアは統計的に見積っている
資料だけを見ると、あちこちにこんなような人がいそうだけれども、どうなんだろうか?
実は、三島由紀夫氏のとある小説のなかの一説を思い出す。
・・・・・・・・・
と、書こうとしたけれども、その小説が思い出せない。
「美しい星」だったと思いさきほどまで、いろいろめくってみたけれども、その肝心なところがでてこない。
なんだったろうか。
とにかく、この世の「普通に暮らしている人たちのその深層心理」というものは、奥の奥の方までその井戸をおりていくと、とんでもないくらい恐ろしい深層心理が、ひそんでいるものなんだ・・・しかしながら・・それらの怪物たちは、毎日毎日、普通の日は、いつものように朝起きて、パンを食べ、家族に挨拶をして、会社に行き、友達と飲んでは、日々普通にくらしているものなのだというシーン・・・・・・・・・。
なんだったかな??
とにかく、人はこのような恐ろしいパンドラの箱を持っている生物だということだろう。
700万年もかけて人類は進化してきたわけで、最初から、現代のような「博愛」とか「自由」とか
「責任」とか「人類愛」がそのあたりにころがっていたわけではないだろう。
まさに、生臭い血と血が、その凶暴なる戦いのなかで、流されてきた歴史があると思う。
テレビなどで、若い子が、「人を殺してみたかった」と呟くのを聞く度に、ドキッとする。
・・・・・・・・
「文化的理性は本能を抑える事である」とは、誰しもが、頭ではわかっている。
ところが、理性が破壊されるような事態・状態になったとき、だれが、それをかならずや、守れるだろうか。
自分の身内や、家族が、酷い目に合った時には、人は、どうリアクションするのだろうか?
そうやって、いろいろ、考えさせられ、自身について、そのことをシュミレーションできるるというのも、映画の楽しみ方かもしれない。
聞いた話しでは、サイコパスの映画はたくさんあるので、何がサイコパスなのかということを、(サイコパスと映画)という論文が、医学的に証明しているらしい。・・・
その正統のサイコパスの人間が出てくる映画はというと・・・
たとえば、「ノーカウントリー」。
前回、「ブリッジ・オブ・スパイ」の脚本も描いた、コーエン兄弟のアカデミー賞作品。
「ノーカウントリー」が、サイコパスの正統とされています。
◎「愛情を抱く能力を持たず、恥や後悔の感覚に欠け、過去の経験から学ぶことがなく、決断が素早い。何の感情の動きも見せず、およそ人間的な喜怒哀楽が見られない」(サイコパスと映画)
その次、誰もが知っている名作の「ウォール街」
◎「ゴードン・ゲッコーは、人心操作に長けたサイコパスの1人だ。 近年、フィクションの世界では、こうした他人を操るタイプのサイコパスを描くことが多い」(サイコパスと映画)
美しい少女の出てくる、ラブリー・ボーン。
◎「ハーベイは、シガーやヘンリーよりも社会に適応したサイコパスだ。立派な一軒家に住み、周囲との社会生活も良好。どこにでもいる普通の男にしか見えない。しかし、その実態は倒錯した性犯罪者だ」(サイコパスと映画)
よくよく、考えると、恐らく、サイコパスの一番古い映画は、ヒッチコックの「サイコ」ではないでしょうか?
さきほどの、三島由紀夫氏の分析ではありませんが、一見普通のどこにでもいるような人達が、凶悪で残虐な殺戮をおこし、完全犯罪を狙って行く。
たしか、すでに、記憶がはっきりしませんが、江戸川乱歩氏が、こんなふうに語っていたことを思い出しました。ニュアンスだけですが・・・・
「ボクは、いつも、完全犯罪について考えている。あと、人の殺し方、それまでのプロセス、・・・・・だから、ときおり、自分自身が、他人からは一見普通の人間に見えているだろうけれども、心のなかでこんなことをいつも考えているとは、誰が想像しえようか?」
たしか、そんなような記憶だったような・・・・・・・・
フライドチキンにかぶりつきながら、血の残虐なシーンを楽しむ外国人たちとちがっているせいか、日本では、あまり、サイコパス的映画はないのではないだろうか。
わたしなぞ、ほとんど、日本の最近のミステリーのことは知らないので、「黒い家」「悪の教典」なんかは、サイコパスに入るのかもしれない。
これまで、書いてきた「ゴーン・ガール」の他のサイコパス的映画を少しひろって、みると。
「ノーカウントリー」「ラブリーボーン」「ウオール街」の他には、
◎「アメリカンサイコ」
◎「sou」
◎「モンスター」
◎「セブン」 だいたい、西洋文化は、とにかく、キリスト教をしっかり理解しないと、本当の意味では、理解できないような気がして来ています。
◎「サイコ」ヒッチコック 元祖??
◎「時計仕掛けのオレンジ」
◎「ケープフィア」
◎「ハロウィン」
◎「羊達の沈黙」
◎「シン・シティ」
ということでしょうか。
時計仕掛けのオレンジは、ちょいと、普通のサイコパスとは違って、もっともっと、ぶっとんでいる最高の大傑作ですが。・・・・・・・・・・・
あと、この「ゴーン・ガール」で連想するのは、あまりミステリーは得意ではないけれども、というか血が苦手なのだが、「ドラゴンタトゥーの女」を思い出す。
第一部 ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女
2009年2月27日にスウェーデン及び、デンマークで同時公開された。日本では第22回東京国際映画祭で特別招待作品として上映され、2010年1月16日にギャガの配給で一般公開。また、未公開シーンを含む完全版はCSチャンネルAXNミステリーにて3部作全てが放送された。
全世界で1億ドル以上を稼ぐヒット作となり[12]、英国アカデミー賞 外国語作品賞を受賞した。
第二部 ミレニアム2 火と戯れる女
第1作目の公開から約半年後となる2009年9月18日に北ヨーロッパで公開された。
ミカエル・ニクヴィストやノオミ・ラパスら主要キャストは続投するが、監督にはダニエル・アルフレッドソン、脚本にはヨナス・フリュクベリが新たに起用される。
第2部・第3部はテレビドラマ化のみの予定であったが、第1部の興行的成功により、映画用に編集した上で、テレビドラマに先行して第2部は2009年9月に、第3部は同年11月に劇場公開されることになった。
第三部 ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士
第2作目の公開から約2か月後となる2009年11月27日に北ヨーロッパで公開された。日本では第2作と同日となる2010年9月11日に公開された。
監督、脚本は2作目から引き続いてダニエル・アルフレッドソンとヨナス・フリュクベリ。
映画が好きなので、仕事の合間に見る事がリラックスタイム。
いつも書いているが、物語はともかく、映像の美しさや、男優女優の肉感・クオリア感・魂なんかを感じながら見る。
とくに、風景の映像が普段いったこともない土地の場合は、ひきつけられる。
そんなわけで、ブログ記録をつけないと忘れてしまうので、書こう書こうとして、ついそのままになってしまう映画が多いけれど、まあ、そんな映画はそれなりの映画だと思う。
この「ドラゴンタトゥーの女」は、記録をつけようというだけ、印象が強いのだと思う。
あくまでも自分用備忘録、偏った映画論なので興味のない方はスルーしてください。^^
まず、タトゥー。
まず浮かぶのは、小さな頃に共同浴場に行くと、昔のことだからよくいました。背中に観音様や龍の彫り物をしているおっちゃん。
熱い湯で気持ちよく赤くゆであがった肌に藍の色のきれいなこと。
この体験は貴重かもしれないな。
今では形の上だけかもしれないけれど、「刺青おことわり」などの紙がサウナなどにも貼られている。
谷崎潤一郎の「刺青」は19才の時に読んで、ほんとうに感動した。
それと、「異端者の悲しみ」。
まだ、刺青をされた少女のほんとうの心は19才の私にはまったく理解はできなかったが、文章の理屈抜きの美しさ。
あの頃は、三島由紀夫と谷崎を交互に読んでいた。
三島由紀夫の「春の雪」。
川端康成が日本語の最高峰と絶賛した豊饒の海の第一巻。
まあ、谷崎と川端と三島由紀夫と言えば、皆ノーベル賞をもらって良い日本の耽美派の巨匠たち。
そのノーベル賞と言えば、スウェーデン。
回り道となったが、私の知っているスウェーデン映画と言えば、ベルイマンの「処女の泉」と「ベルソナ、ヴィルゴット・シェーマンの「私は好奇心の強い女」、それぐらいである。
独特の世界観。
スウェーデンを舞台とした五木寛之の「青年は荒野をめざす」も何回も読んだ傑作。
非常にわかりやすい文章だが、刺激を受ける彼の創作態度はいつも刺激を受ける。
そんなわけで、見る前に、ハリウッド映画やヨーロッパ映画などはよく見ている人でも、このスウェーデン映画ははじめてという人が多い筈。
北海道に極めてよく似た風景。
それが実に美しい。
ミステリー的にはおおいにサスペンス性のこの物語にはよく似合う風景なのだと思う。
それにしても、かつて福祉の国として名を馳せた国なのにこれだけひどいレイプが横行しているとは初めて、知った私だった。
この原作者はこの小説の初版が出る前に死んだと聞いたがどうなのだろうか?
何を書きたかったのか?
人間の心の中に潜む悪か?
あるいはどんな状況におかれようとも自身の美と信念を貫き、悪を許さないという断固たる正義か?
リスベットという観点から見ると、私は個人的にはスウェーデン版のリスベットの方が、なにやら可愛いと思うのだが・・・
個人的な好み。

少し、ボーイッシュで、カッコいいと思います。
「プロメテウス」にも出ていたということを知って、ちょっとびっくり。
まったく気がつきませんでした。
「私はあなたとの仕事が好き」というリスベットの心の中に芽生えた男性への興味と愛の片鱗。
男性への嫌悪は確かにあったのだろう。
異性への憧れや興味がとことん無くなった人間とはいったいなんなんだろうか?
リスベットに対して限りなく凄惨なレイプを繰り返すアホな好色オッサンを、彼女が胸がスカットするくらいに痛めつけて、それで果たして喜んでいて良いものなのだろうか?
胸に少しずつ芽生えていたミカエル・ブルムクヴィストへの愛情が、手をつないで仲良く夜の闇に消えて行くシーンを見て、プレゼントをゴミ箱に棄てるリスベットの心の傷。
アラン・ドロンの名作「あの胸にもう一度」よろしく、バイクに乗って前に進むリスベットはカッコ良く、そして、いじらしい。
やはり時代は「女」の時代なのだろう。
しかしながら、「男」の心の中の「悪魔」を退治するニュー・ヒロインのリスベットもまた、自分が心ときめかせる「男」を探す旅にバイクで出かけたように私の心には映ることが私にとっての一番の興味である。
二作三作目でも、普通であれば自分をアガペーの愛で包んでくれる筈の父親の「悪魔」があらわれる。
父親を殺そうと、レイプ犯を気持ちよくやっつけようと、リスベットの心は晴れない。
ネットから「ドラゴンタトゥーの女」豆知識お借りしてきました。ありがとうございます。
この映画豆知識。
●ミレニアムシリーズ3部作は全世界で6500万部を売り上げる超ベストセラー。
●原作者のスティーグ・ラーソンは1作目(2004年)の出版直前に心筋梗塞で急死(享年50歳)。
●一人当たりのGDPは49,000ドル。失業率8.4%(2010年)。
●通貨スウェーデンクローネ(SEK)は1クローネ=約12円(2012年2月現在)
劇中に出てくる金額は以下のようになる。
・ヴァンネルストレムの不正利益→6000万クローネ=約7億2000万円
・ミカエルに科せられた裁判による賠償金→15万クローネ=約180万円
●スウェーデンの国土は日本よりやや広いが人口は12分の1の約942万人。
●首都はノーベル賞で有名なストックホルム(人口約83万人)
●スウェーデン発の有名企業はボルボ、サーブ、エリクソン、イケヤなど
●高福祉国家であるがドメスティクマターとして移民問題、女性への暴力、将来の社会保障制度、企業・役所の汚職が社会問題としてある。
●男性から女性への暴力が他国と比べると多い。
・スウェーデンでは女性の18%が男に脅迫された経験を持つ。
・スウェーデンでは女性の46%が男性に暴力をふるわれた経験を持つ。
・スウェーデンでは女性の13%が性的パートナー以外から深刻な性的暴行を受けた経験を持つ。
・スウェーデンでは性的暴行を受けた女性のうち92%が警察に被害届けを出していない。
この「ドラゴンタトゥーの女」における、レイプの問題。
・スウェーデンでは女性の18%が男に脅迫された経験を持つ。
・スウェーデンでは女性の46%が男性に暴力をふるわれた経験を持つ。
・スウェーデンでは女性の13%が性的パートナー以外から深刻な性的暴行を受けた経験を持つ。
・スウェーデンでは性的暴行を受けた女性のうち92%が警察に被害届けを出していない。
それとおなじように、「ゴーン・ガール」では、別の恐ろしい人の深層心理の問題として、 描かれている。
スウェーデンではないけれども。・・・・
あと、連想するのは、サイコパスかどうかはともかく、ヒロインの雰囲気が、ちょいと気になる映画群です。
いま、50歳から60歳くらいの人であれば、誰しもが、知っている筈ですが、若い人ではまったく知らない人もいるかもしれません。
「氷の微笑」を連想します。
なんと、さきほどの、「ウォール街」に出ていた、マイケル・ダグラスがでています。
監督は、私も大好きな、ポール・バーボーヘン。
気になるので、調べてみると、こんなに傑作群があります。
Wat Zien Ik?(1971年)
ルトガー・ハウアー/危険な愛 Turks fruit(1973年)
娼婦ケティ Keetje Tippel (1975年)
女王陛下の戦士 Soldaat van Oranje (1977年)
SPETTERS/スペッターズ Spetters(1980年)
4番目の男 De Vierde man(1982年)
グレート・ウォリアーズ/欲望の剣 Flesh & Blood(1985年)
ロボコップ Robocop(1987年)
トータル・リコール Total Recall(1990年)
氷の微笑 Basic Instinct(1992年)
セブン
この最後のシーンは救いようがありません。嫌いなシーンです。
ショーガール Showgirls (1995年)
スターシップ・トゥルーパーズ Starship Troopers(1997年)
これはSF映画の大傑作ですね。
インビジブル Hollow Man(2000年)
ブラックブック Black Book(2006年)
ポール・ヴァーホーヴェン/トリック Tricked (2012年)
下線のあるのが、見た作品ですが。
・・・・・・・
「氷の微笑」は、レズビアンを差別していると言われましたが、続編もできました。
できが最悪という評価を得ていますね。
マーク・ダグラスも出演拒否という映画です。・・・・・

最後に、マイケル・ダグラスといえば、これでしょう。
「危険な情事」
この映画も、恐らく、よほど、映画好きな人でないかぎり、今の10代、20代の若者で知っている人はいないでしょうね。
サイコパスとは違うでしょうが、女のストーカーとでもいう映画かもしれません。
マイケル・ダグラス・・・・・・・
それにしても、味のある演技、独特のまさにサイコ的雰囲気。
私の記憶がまちがいなければ、
「友達がほしければ犬を飼え」・・・これは彼が言うと、ぴったりという感じでした。
日本にこれだけの雰囲気のある俳優ははたしているでしょうか???
「映画で、おもしろい言葉や会話を勉強してください」 淀川長治
FIN
「図書館戦争」「オールユーニードイズキル「マイインターン」
札幌のJRシネマ館。
最近ここで、時間をすごすのが楽しい。
「マイ・インターン」「100年の恋」と、楽しめたので、期待して、この「図書館戦争」を見たが、がっかり。
・・・・・・・
映画「図書館戦争 THE LAST MISSION」予告動画
普通のサラリーマンや、OLさんならば、2000円も出してこの映画を見たら、きっと、もったいないことをしたと思うに違いない。
テレビで見たり、せいぜい、ビデオレンタル店で、100円で見るのならば、ソンはないと思うけれども。
私は、基本、淀川長治さんではないけれども、どんなつまらない作品にでも、ひとつやふたつは良いところがあると思うし、この映画も、もちろん、おおっというシーンは数カ所はあるけれども、そして、作者の、有川浩さんのファンが多いらしいので、彼らだったら、楽しめるのだろうね。
◎私は本の虫なので、図書館の内部のさまざまなる映像や、図書館における規約みたいなものは新鮮。
◎本物の自衛隊の全面的な協力を得ての撮影なのでこれまた、興味深いシーンがたくさんあった。
しかし・・・・・「表現の自由=本を読む自由」を死守するというのは理解できるし、賛同するけれども。
・・・・・・・
「図書館戦争」の元ネタ??かどうかは、わからないが、この映画が連想された。
ただ、こちらは、ブラッドベリの大傑作。 (個人的にだが)
本が燃える温度は、(本の素材である)紙が燃え始める温度(華氏451度≒摂氏233度)なのだけども、それを題材にした映画を若い頃に、見た。
尊敬するブラッドベルの「華氏451度」という作品である。
華氏451度 ハヤカワ文庫SF/早川書房
¥価格不明
Amazon.co.jp
映画もつくられた。
この「華氏451度」という作品、小説や映画のなかでは、要は、テレビなどに脳細胞をやられて、単純な思考しかできなくなった人類の滅亡と、本による救済を描く。
この作品の映画化は、まだ他にもあって、『リベリオン』 - カート・ウィマー監督のアメリカ映画作品で、本作を原案とする、思考(感情)統制され、書物が焚書される未来を描くSF。
少数の人達が、燃やされる本のなかから、数冊の本を大切に守っていくわけだが、この「図書館戦争」の作者もまた、おそらく、見ていることだろう。
有川浩。
ファンも多そうで、この作品には、一作目があるらしい。
私はそれは見ていない。
かなりのアンケートで、男性と女性の比率は、女性が圧倒的に高いという。
しかしながら。
期待して、見たけれども、どうもはいれこめなかった。感情移入がしずらい映画だ。
というか。
「フルメタル・ジャケット」や、「プライベート・ライアン」、それに、最近ならば、「フューリー」や、「アメリカン・スナイパー」などの、戦争ものの、傑作名作を見ていると、
戦争場面が、戦争にまったく見えない。
この「プライベートライアン」と比較するのはかわいそうだが、しかし。
この映画のなかの、戦いは、どう見ても、
戦争ごっこ。
「フューリー」など、ほんとうの戦争そのものを描いている。
しかも、このヒロインの、榮倉奈々という女の子。(??まちがいかな )
天然というか、大胆なのは魅力だけれども、まったく、この映画では、浮いています。
なんで、本を命をかけて守るのかということを、深くほりさげて、キャラづけされていないので、まったく、戦争ごっこにしか見えず。
なぜ、命をかけて本を守るのかということが、丁寧に描かれていないからだろう。
これは本人の責任というよりも、シナリオが悪いんだと思う。
彼女が、可哀想。
その分、岡田准一は、良い意味で、ダスティ・ホフマン風な味があると思った。
榮倉奈々が、背が高いんだから、彼の背の低さを強調して、役づくりをしても、
またまた、原作とは違う味の、作品になった可能性があるだろうれども、もう遅し。
(映画と原作小説は、まったくの別物)
2019年の日本という設定らしいが、考証がきちんとされていないので、どうみても、今の現代の日本にしか見えない。
そこで、図書館の中だけで、内乱のようなことがあり、銃撃戦があり、人が死ぬ。
どう考えてもありえない。
ちょっと考えたのだが、どうせ、原作を広げて、映画をつくるのならば、中国共産党に支配された後の日本の生活を描けばよかったのではなかろうか???
◎中国では、過激なビデオを見たものは死刑になると言う。
◎とうぜん、共産党の思想に叛逆するすべての思想や、書物、集会などは禁止され、その著者などは、逮捕されて、拉致監禁され、殺されたりもする。共産党という思想を信じている立場からすると、「俺たちが正しい」から、そのようなことをするわけだが、日本のような民主国家からするとありえない。
◎中世界に自国を広めて行くという中華思想にもとづき、その他の国を中国の属国にせんと、企んでいる可能性がある。
◎人類の理想を共産主義とはしながらも、結局はマルクス主義を都合のよいように、置き換えただけのシステムの国家であり、そこでは、賄賂と、さぼり、拝金主義が、蔓延している。
というわけで、日本が、自国を自分たちで守ることも忘れて、気がつけば、中国の属国になっており、メディアはすべて、中国語、純粋日本人たちは、地下で、焚書にされなかった数冊の日本語の本を持ち寄って、日本語でコミュニケートする集団をつくりあげていく。
これは私の勝手な妄想空想だけれども、こちらの方が、自衛隊のかなりの応援もあっていろいろな場面の撮影がスムーズにいったと言われているので、自衛隊の方にも喜んでもらえると思う。
この映画のなかで、ひとつだけ、気に入った言葉は、
「正しいことしか言わない人間だけしかいないの世界は、おそろしい」という言葉。
自由社会。
わたしたちが、守るべきは、どんな議論にせよ、今の日本やアメリカや世界の民主国家のなかでは、どんなことでも言える、それが許されているわけだし、その世界に、マンネリしてのほほんと住むあまりに、その自由というものの大切さが、わからなくなる、麻痺してしまうということが、問題なのだろうと思う。
(ただ、実際には、差別用語を使えば、筒井康隆に団体から文句がくる。このあたりの表現の自由の問題はかなりむずかしいが。ブログだって、書けないこともある。書く自由には責任もまた必須なのだ。)
狂信的な連中が自分の思想だけを他人や国民に押し付けて、自分たち以外の考えやらメディアを叩き潰そうとする社会、それがほんとうは、怖いのだと思う。
以前、どこかの図書館であった実話。
そこに勤める女子が、たしか、渡部昇一氏らの本だけを、ひっぱりだして、捨てた=焚書にした、という事件である。
(この図書館戦争の映画とはまったく逆のバージョンですね。表現の自由、読書の自由を、図書館のスタッフが、制限するという前代未聞の事件・・・)
つまり、自分の意見や、思想だけが、正しく、それに対立する意見などは、認めない、耳を塞ぐ連中ですね。こういう「自分だけが正しい」と信じている人たちほど、つきあいずらい人種はいませんよ。ユーモアセンスがなく、いつも感情的で、変に純粋まっすぐ君なんですからね。
こまったもんです。
●●新聞やら、テレビのおおかたのメデイアなども、最近はその傾向があると思う。
ひとつの議題に対して、たとえば、安保法案・・・これに、反対意見だけのコメンテーターを集めて、放映する。
まさに、この「図書館戦争」のなかで手塚がやっている、洗脳そのものですね。
真の民放メディアであれば、反対意見と、賛成意見と両方あるはずなので、両方の専門家を呼んで、カメラの前で、議論させる。
そのときに、司会者はよけいなことを言わずに、ふたりの、言いたいことを徹底的に言わせることに集中する。
そして、最後に、この番組を見て、見ている民衆、わたしたちが、自分の頭で、判断する。これが、民主主義でしょう。
昨日の新聞でも、NHKに、「なんで片方の意見だけの映像を流し続けるのか」という、投書が、驚くほど届いているという記事がありましたが、テレビの洗脳は今にはじまったことではありませんから、気をつけるべきことのひとつでしょう。
「華氏450度」で描かれているように、本を読まなくなり、テレビだけで、ものを考えるようになった未来の人類達は、もはや単純な思考しかできなくなり、複雑なるこの現実の世界を、変革していこうとは考えなくなってしまう。
テレビに洗脳され、テレビに操られる人達が、増えてくる未来は恐ろしい。(今の若い人は、あまりテレビを見ないし、ネットもあるので、それが救いかもしれない。)
フランスには、シャルル・ドゴールのこんなジョークがある。
「フランスには246ものチーズがあるんだ、こんな国を統治できると思うかね」
つまり、人をまとめるのは、この21世紀、ネットの普及などで、どうしようもないくらいに個性が複雑かして、まさに、一人十色になってきている。
そんな世界を、民主主義は、やはり、多数決という原理で、まとめるのではないだろうか。
民主国家では、さまざまなる意見があり、議論があり、文句があり、批判があり、喧嘩や軋轢もある、それが、当たり前なことなのだろう。
つまり、ああだこうだ、といいながら、まとまらないこの世界。それを、ひとつの方向にうまく収斂させていくのが、政治家の仕事だし、政治家に一番求められているのは、リーダーシップだ。
この「表現の自由」という問題は大変に難しい問題だと思う。
最近では、週刊文集でしたか、春画を載せたということで、騒がれましたが、呉さんによれば、週刊文集だから問題になったけど、ポストだったらまったく問題にならなかったというようなことを書いていましたね。
北欧などは、性の解放などで、有名ですが、子どもたちの、通行するようなところには、アダルト本を買えるような販売機などは絶対に置きません。
性については、解放していても、子ども達には、普通の日々を送らせて学業に専念できるようにしてあるわけですね。
個人的には、「ワイセツ」などという言葉で、国が作品や書物を禁書にするというのは納得はできません。
渋沢竜彦氏の、「サド」シリーズでも、あれが「ワイセツ」などという裁判官の頭の中をしらべてみたくなります。ソドム百二十日 (河出文庫)/河出書房新社
¥821
Amazon.co.jp
しかしながら。
児童ポルノは違うでしょう。
メディアに対する自由侵害とか騒いでいる人がいましたが、アホです。
無垢な子どもを、大人が勝手にポルノ作品に、参加させるような、アダルトの世界は表現の自由ではありません。
言い尽くされた言葉ですが、自由と責任は、必須の組み合わせ。
子ども達をのびのびと、彼らの内在化された才能をのばすために、大人はいるわけですから、
小さな頃から、それをひとつの枠のなかに、押し込めようとする自由などはありません。
というわけで。
この、「図書館戦争」。有川浩さんや、岡田准一さん、
榮倉奈々さんのファンの人たちだけが、楽しめる映画かな。
映画は、つくりあげるために大変な額の金がかかりますから、原作をはしょってしまうことはあるのかもしれませんが、それにしても、この戦争ごっこのような、迫力のない、画面にはがっかりしました。
(個人的には、映画がつまらなかった分、日本が他国の属国になりさがった時を想定し、日本が日本でありつづけるために、過去の日本人たちの歴史に学びながら、日本語を大切に守りたいとますます、考えたことがプラスだったかな)
次の映画は、「マイインターン」
(ネタバレありですが、勝手な感想を書かせていただきます)
12時に、札幌に着いて、いつものようにきれいなJRシネマ館に行く。最近の楽しみのひとつ。
時間はまったく考えずに、行き当たりばったりを楽しむので、その日は、「マイ・インターン」を観る。
この映画は、「プラダを着た悪魔」の続編と聞いてはいたけれども、もうすっかり以前の作品のことは忘れていた。
いつもそうだ、私は、偏見を持たないで作品を観たいので、パンフも、予告編も、何も観ないで、それで良いと思っている。そのかわりに、見終わると、けっこう調べて資料は集めるかも。
(ただ、この映画は、以前観た、「進撃の巨人」やら、「100年の恋」やら、作品上映の前にかならず、この予告編を繰り返しやるので、何回も観ていたが・・・・)
予告編を観ればわかるけれども、とにかく、女性であればわくわくするような、ファッションサイトの職場。実際にこんな会社があるかどうかはともかく、さすがに、ニューヨークという雰囲気があり、楽しい。
そこに、インターンとして、70歳のロバートデニーロが入社してくるわけだから、おもしろくない筈はないと思う。
ただ、予告編からの印象は、あてにならない。
この映画は、予告編よりも作品そのものは、何倍もおもしろい。
おしゃれな女性がわくわくするこの映画の秘密はそれとして、この映画は、今や、四人に一人と言われる高年齢のシルバー世代の観客にも、わくわくするような仕掛けがしてあると思う。
じっさいに、映画の観客も、平日ということもあるけれども、半分くらいが、シルバー世代。あとは、恋人どうしみたいな観客がめだった。
アメリカは、誰でもが知っているけれども、歴史が浅い国。たかが、数百年くらいで、世界のグローバリニズムにのし上がった国。
今や、いろいろな問題を抱えて、喘いでいるけれども、それでもなかなかの国。
そんな彼らが憧れるのは、やはり、日本やイタリアのような歴史の長い国だと思う。
この映画の中にも、日本語が多用されていて楽しい。
「幸福のレシピ」という映画があって、私は大好きだったけれども、完璧主義のシェフがひとりで店をきりもりしていたが、彼女が、人生の困難にぶつかったときに、ひとりの男性シェフが入ってくるという筋書きだったと思うけど、彼は、イタリア人的な雰囲気を持っていたと思う。
この「マイリターン」のロバートデニーロの役柄も、イタリア人とは主張しないまでも、それ風の、雰囲気を持たせてある。
たとえば、私の好きな、ダイアン・レインの映画で、「トスカーナの休日」という映画があったけれど、これまた、アメリカで離婚をした女流作家が、ふとした自分を癒す旅、つまりイタリアへの旅で、見つけた、レトロな家での生活を描いた作品だったけれども、アメリカの魂の傷をイタリア・トスカーナの自然と料理と人間たちが、癒すという筋書き。
あと、「食べて、祈って、恋をして」。
これまた、離婚と失恋を経験してボロボロになったジュリア・ロバーツが、イタリアとインドなどに旅に出て、魂を癒すという映画だったと思う。
その意味では、ファッションサイトの社長として、日々、狂ったように、働く、まるで、「プラダを着た悪魔」のメリル・ストリープのように変身したかのような、アン・ハサウェイの、苦しみや心の壁を、さりげなく、溶かしていく役柄としては、このデニーロは個人的によく抜擢したなと思う。
なんとなく私はこんなイメージを持っている。
○合理的で、時間時間に追われつつ、自己主張と、結果がすべてという仕事主義のニューヨーカー達。「友達が欲しければ、犬を飼え」式。
○仕事の結果は大切にしつつも、人生の夾雑物を排除せずに、非合理的なものもとりこんで、喜怒哀楽のなかで、ユーモアを武器に、人生を楽しんでいくイタリア式ライフスタイル。「困ったらまずワイン式」
当然私も、イタリア式が好きだな。
ロバート・デニーロ。
母親がたしか、イタリア系だし、父親も、西洋人系。
「ゴットファーザー」では、完璧にイタリア語もマスターして、どことなく、私は、彼はイタリア人ではないかとも思っていた。
(もちろんアメリカ人だけども)
だから、私のイメージとしては、アメリカのニューヨークの最先端の仕事のなかで、ギスギスと生活に追われるアン・ハサウェイの心をしだいに、彼が、柔らかくさせて、その結果として、彼女の仕事の幅が驚異的に広がって行くというシナリオは、カタルシス効果満点で、スカットする。
50代まで、とある会社で部長までやって、今はただのんびり老後を楽しんでいる、デニーロもまた、社会とのリンクを求めて、この会社に入って来て、その「復帰」を静かに楽しんでいるのが伝わって来て、涙がでるくらいに、しみじみと、素敵だなと思える。
たしかに、FBに写真をアップすることもまだできないような、70歳の高齢者ではあっても、
魂の髄にまでしみ込んでいる、その的確な人心掌握スキルと、問題解決能力や判断力で、しかも、柔らかくユーモアをまじえながら、自分の孫くらいの女社長に尽くして行くところが見物。
しかも、恋愛でも、まだ現役!!!
もちろん、これはあくまでも映画なので、70歳でまだまだすべての人がこのように、現役復帰できるかどうかはともかく、シルバー世代にも夢を与えてくれるシネマだと思う。
また、若い人であれば、ニューヨークの最先端の仕事の現場のイメージをつかむだけでも、楽しめる映画だと思う。
日本であれば、ちょいと信じられないような、職場のやりとりやら、光景があって、これまた、楽しい。
狭い職場を時間が惜しいという理由で、自転車ではしりまわる、美しい女社長。
笑えるし、理屈抜きで、目を楽しませることのできる、映画らしい映画だと思う。
おかげで、「プラダ」や「トスカーナ」などの関連映画をまたまた、思い出せて、それまた嬉しかった。アンテナさへ、意識していれば、自然と欲しい情報はあつまってくるものだ。
○資料
役作り[編集]
ロバート・デ・ニーロ(1988年)
上述の通り、デ・ニーロは役に成りきるための努力を惜しまない。その例を挙げる。
『ゴッドファーザー PART II』では、シチリア島に住んで、イタリア語をマスターした後に、マーロン・ブランドのしゃがれ声を完璧に模写した。
『タクシードライバー』では3週間、ニューヨークでタクシードライバーとして働いた[8]。
『ディア・ハンター』では、物語の舞台となったピッツバーグに撮影数ヶ月前から偽名で暮らしていた。さらに鉄工所で働こうとしたが、現地の人に拒否されたという。
『レイジング・ブル』ではミドル級ボクサーの鍛え抜かれた肉体を披露し、その後、引退後の姿を表現するために体重を20キロも増やした。[1]このためにイタリアに赴いて、現地のあらゆるレストランを食べ回った。
主人公がユダヤ人の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』では、ユダヤ人家庭にホームステイした。
『アンタッチャブル』では頭髪をそり上げ、アル・カポネを演じた。体重は直後に別の映画出演が決まっていたので太るわけにいかず、ボディスーツを着用したが、顔だけは太らせて撮影に臨んだ。
『ミッドナイト・ラン』では、マーティン・ブレストと共に実際の賞金稼ぎと共に行動し、捕獲の瞬間、張り込みを見学し、捜査の方法などを習得した。
『ロバート・デ・ニーロ エグザイル』でホームレス役で出演するため、役づくりのためにホームレス施設に潜入した[9]。
○資料2
1999年にテレビシリーズ『ゲット・リアル』の主人公に抜擢され、ティーン・チョイス・アワードやヤング・アーティスト・アワードの女優賞(ドラマ部門)にノミネートされる。
2001年公開の『プリティ・プリンセス』で映画デビュー。全米で1億ドルを超えるヒットとなり、ブレイクする。王女役の役作りのために、スウェーデンのヴィクトリア王女関連の本を読み漁ったという。2002年2月にミュージカル『Carnival!』でブロードウェイデビューを果たす。2004年には『プリティ・プリンセス』の続編が公開され、9500万ドルのヒットとなる。これにより人気女優となったが、プリンセスのイメージが定着し、理想の役が得られずに低迷する。
2005年公開の『ブロークバック・マウンテン』でアイドル女優的なイメージを払拭。2006年公開の『プラダを着た悪魔』ではメリル・ストリープ扮する鬼編集長のアシスタントを演じ、1億ドルを超えるヒットとなった。2007年公開の『ジェイン・オースティン 秘められた恋』ではイギリスの作家ジェーン・オースティンを演じた。
2009年 アカデミー賞授賞式にて
2008年公開の『レイチェルの結婚』で元薬物中毒者を演じ、放送映画批評家協会賞主演女優賞などを受賞し、アカデミー主演女優賞にノミネートされた。
2010年公開の『ラブ & ドラッグ』でゴールデングローブ賞 主演女優賞(ミュージカル・コメディ部門)にノミネートされた。第83回アカデミー賞の司会をジェームズ・フランコと共に務める。
2012年は、ハサウェイにとって大きな飛躍の年となった。『ダークナイト ライジング』にセクシーかつグラマーな美しい女怪盗・セリーナ・カイル役で出演。ボディラインが一目で分かる体にピッタリ密着した衣装(ボディスーツ)を身にまといながらも華麗にアクションをこなす必要があるため、肉体改造を徹底的に行った。クリストファー・ノーラン監督から映画『インセプション』でジョゼフ・ゴードン=レヴィットが2ヵ月間トレーニングを積み、戦いのシーンなどをすべて自分で演じきったエピソードを告げられ、その足で「彼のオフィスを出た後、すぐにジムに向かいました」とコメントしている[6]。しかし、このボディスーツは彼女のウエストサイズより5cmも小さいために常にウエストを締め付けられ、シェイプアップした彼女にとっても着続けるのが困難で、「一日が終わる頃には苦しかった。撮影を終えて脱いだ時の解放感がたまらなかった」という[7]。また、12月公開の『レ・ミゼラブル』にてファンティーヌ(英語版)を演じ、吹き替えなしのミュージカルに挑戦し、第85回アカデミー賞助演女優賞を受賞した[8]。また、同作にてこれまで2度、ノミネートしていたゴールデングローブ賞助演女優賞を3度目にして受賞した。この二作の記録的なヒットでハリウッド女優としての地位を不動のものにした。
私生活[編集]
次の映画は、All You Need Is Kil
小畑健 「All You Need Is Kill」PV
たまたま、この映画Edge of Tomorrowを見た。
日本語の原作ということもまったく知らなかった。
日本語の原作は、All You Need Is Kill・・・。ライトノベルの作品が、ハリウッドで実写化というのはこれまで聞いた事がない。
マンガもあるそうだ。上のクリップ。
映画を見てから、下の資料を見つけて、読んでみると、かなりの違いが日本版との間にあるらしいけれど、楽しめてみれた。
それにしても、アメリカ映画のSFの映画づくりのtecnicは、すさまじい。
この映画を見ていて、すぐに、思い出したのは、マトリックスの戦いのシーン。
あるいは、スターシップトルーパーズ。
「2001年宇宙の旅」や、「惑星ソラリス」のような、神秘感までを漂わすことにはまったく成功していなけれど、想像力がかなり刺激される。
筒井康隆氏が絶賛しているのもうなづける。
外人さんのレヴューを見てみても、実に日本のマンガやアニメの情報をよく知っているし、また、映画の構成、特にlogicが、納得がいったとか、いかないとか、議論されていた。
だいたい、このような、タイムパラドックスというのか、このジャンルのSFは、ややこしいし、おおよそ論理的に作り上げる事自体が、タイムマシンがいまだに完成していないわけで、
想像力の力をかりるだけである。
それを言えば、「アンツマン」や、「・・・マン」ものの、いわゆるアメリカンコミックなんかのタイムトラベルものは、ロジックはいいかげんだと思う。でも、それでいいのだ。
思えば、私が、中学生の頃は、SF映画と言っても、「日本版のゴジラ」や、HGウェルズ、あるいは、ブラッドベリ、フレドリック・ブラウンなんかの小説を通じて、楽しんでいたくらい。
日本ではやはり筒井康隆が、SFマガジンにいろいろ短編を書いていて、わくわくしながら読んだものだった。
(彼は、もうそのときに、クローンの物語を書いていた・・・。)
だから、たしかに、石森章太郎の「霧と薔薇と星と」とか、「幻魔大戦」、手塚治虫の「火の鳥」なんかが、最高のSF作品だった。
それから、はや、40年。
映画の表現は、もう、完全に私たちの脳を刺激するためにつくられているかのようだ。
この映画のなかのmimicの表現なんかは、少しギーガー風のアルファとかオメガを見ると、なんだと思うかもしれないが、mimicの戦いぶりの表現は想像を超えている。
これでは、人類が負けるのは当然だと思うだろう、誰しもが。
エヴァンゲリオンではないけれども、日本のマンガやアニメは、マッチョな強い主人公というよりは、フラジャイルな、少年少女たちをヒロインやヒーローにする。
その意味では、このハリウッド映画のなかにでてくる、トム・クルーズや、リタはまったく違う。
資料によると、リタ・ヴラタスキは、
US特殊部隊に所属している精鋭で[15]、階級は准尉[16]。公称は22歳だが[17]、実年齢は19歳[18]。他の兵士からは戦場の牝犬(せんじょうのビッチ)という渾名でも呼ばれる。モンゴメリの小説『赤毛のアン』のヒロインを連想させるような容姿の[19]小柄な少女だが、圧倒的な戦闘能力を持っており英雄扱いされている。わざと目立つ赤の蛍光色に塗装した機動ジャケットを着込み[20]、重量200キログラムのタングステンカーバイドの戦斧を武器として愛用する[21]。他人には伏せているものの、過去にキリヤ同様の経緯から時間のループを211回[22]繰り返した経験があり、その後もギタイ側が引き起こしているループを逆手に取り、人類を有利な戦いに導いている。
故郷や家族がギタイによる虐殺の犠牲となり、その復讐のために兵士となった経験を持つ[23]。リタ・ヴラタスキという名は本名ではなく、年齢を偽って入隊するために盗用した身分証明に記されていた人物の名であり[24]、彼女自身の本名は明かされない[注釈 2]。ループする時間をキリヤと共有することはできないため[26]、キリヤのループを観測することはできないが、158回目のループの終わりでキリヤがループを繰り返していることに気がつき、159回目および最後の160回目のループではキリヤと行動を共にする。
エミリー・ブラントはイギリスの女性。
品がある。
が、あまり印象に残る強い存在感は個人的には感じなかった。
歴史物の作品があるので見てみたい。
私は、昭和時代のマンガは得意というか、かなり知っているが、働き始めてからは、朝六時から真夜中まで働き尽くめで、ほぼ、マンガは見る暇がなく、その後、ぷっつんと、マンガ通読はできなくなってしまった。
今、時間があるので、読みまくっているが、
いつも書いているけれども、文学と、マンガと、映画は、まったく違って良いと思っているし、その方が、また、原作者の書いたものが膨らむというか、新鮮なるひろがりを持てるのではないだろうか。
たしかに、「シャイニング」の時だったか、キューブリックと、スチーブン・キングがかなり喧嘩をしたとか聞くけれども、それはそれでまた、読者から見ると、興味深くて、おもしろい。
できれば、このような作品群は、小説とマンガと映画とすべてを見てみることも、暇のある人は、最高の体験ができることだろうと思う。
○個人的に好きなscene
兵士達の鎧のような防具?機械
戦闘シーンのすさまじさ
mimicの表現
兵士達を鍛える時の言葉=キューブリックの戦争映画フルメタルジャケット同様に。
時間をコントロールしながらもこの宇宙のなかで征服を可能にするエイリアンの表現。
パターンではあるけれども、人類救済のために結束するグループの仲間たち。
死を恐れない勇気のシーンの数々。その他。
○資料
5 Differences between Edge of Tomorrow and All You Need is Kill

Hopefully you’ve gotten a chance to go see the excellent movie Edge of Tomorrow over the weekend. I took some time on Friday to go see the movie a second time, and I still love the film. Now that the movie is out I wanted to go into a deep dive into how the source materialAll You Need is Kill compares to the Edge of Tomorrow. This is going to be very spoiler heavy so don’t read on if you haven’t seen the film yet.
1) Major Bill Cage and Private Keiji Kiriya are entirely different

Keiji Kiriya is a Japanese soldier in the UDF, fighting for his country, as this story takes place in Japan. Keiji signed up, and wanted to fight against the mimics, while Cage was an American that never wanted to fight. By the time they do wind up fighting, they are both new to it all, but Keiji wanted to be there while Cage was constantly looking for a way out.
Keiji was also trained by Sgt. Farrell, while Cage was trained by Rita. For the most part Keiji didn’t have anywhere near as much interaction with Rita as Cage did, until the last few resets. Keiji was going to forgo everything to make himself the best he could, while it seemed obvious that Cage had fallen for Rita and was training in part because he loved her and wanted to save her.
2) Rita Vrataski from All You Need is Kill would bitch slap Emily Blunt

Don’t get me wrong, Emily Blunt was awesome in Edge of Tomorrow. She was one of the best parts of the film, but Rita Vrataski from All You Need is Kill is the real Full Metal Bitch. In the novella, Rita had killed more Mimics on her own before she gained the ability to “reset the day” and became a famous war hero. Once she gained the Mimics ability she got even better, going through several hundred attempts at the battle of Verdan. The movie version of Rita had her first battle at Verdan. She learned how to be really good, but I don’t think she would hold a candle to her novella counterpart.
Another significant change was the age of the character. The Rita in the book was somewhere between 19 and 22 years old. She signed up for the UDF illegally at 16, and fought battles for years before Verdan ever happened. I don’t think they ever say how old Emily Blunt is supposed to be, but she’s definitely older than 22, let alone 19.
3) The Mimics are much scarier in the movie

The book described them as giant bloated frogs with 4 legs, a tale, and a hard endoskeleton. I have no idea on how to describe the movie version. It seemed like they crossed a giant metal dog with a psycho octopus, and gave it the speed of a cheetah. The book Mimics are also very fast, but they don’t have the same tentacle action going on, that the movie version has.
The hierarchy between the mimics are very different as well. The movie has normal Mimics that seem to be grunt soldiers, and Alpha Mimics that are the Generals in a battle. Then there is the Omega Mimic that is the pretty much the King of all Mimics. If an Alpha dies, the Omega Mimic will “reset the day”, and use the info that it gained to help win the war next time.
In the book you didn’t have an Alpha and an Omega. The book has Antennae’s and Servers. At every battle there are several Antennae and one Server. The Antennae kind of control the standard grunt Mimics, and send information to the Server. If the Server dies, it “resets the day” and then passes that info onto the other Antennae the next time around. In order to win the battle the UDF has to kill all of the Antennae in the area, and then the Server so it can’t send the info anywhere and properly “reset the day”.
While this sounds similar, it’s very different, in that there is only 1 Omega, while there are many Servers. This has a large difference on humanities ability to win a battle, and the progression of the war.
4) The War, and our world are very different

In the book, the Mimics landed over 20 years before the battle in Japan. The Mimics were sent by an alien race looking to colonize a planet. They didn’t know if there were sentient life forms on this planet, and they didn’t have time to check. They sent the Mimics to help terraform earth to make it more habitable for them when they get here. The Mimics landed and initially were very peaceful. The problem was that they eat earth and excrement poison gas that was transforming the planet. Humanity attacked and tried to stop them, which started the war. The Mimics evolved, and got smarter and stronger with better weapons and started to win.
In the movie, they landed 5 years before the battle of Europe. There really isn’t any info on what they are doing or why, or what started the fight. We just know that there was a lot less time for this all to escalate so far.
Because of the time difference, the world of the book and the world of the movie are very different. Having a World War for over 20 years where parts of the world are wiped out, means that you start running out of stuff. Some things become extinct, and can only be read about in books. The novella version of Rita being so young, only knew of war growing up, and it made her a very different person from the one we have seen in the movie.
Another distinction in the war is that in the movie, we only won a battle because the Mimics let us think we won. They regroup and change tactics to make it easier to pummel us later. In the novella humanity legitimately won those battles. The movie definitely had a much bleaker outlook on our prospects of survival in the end.
5) The endings are drastically different

In the novel because Keiji and Rita have both stolen the alien’s abilities at some point, they both act as Antennae. Unfortunately that means that the day will keep resetting as long as both of them are alive. The only way for the day to end is if one of them dies. So at the end of everything they have an all-out slugfest with each other to see who is worthy of surviving the day and fighting for humanity. Keiji winds up killing Rita, and goes on to become the next hero of the UDF for the battles to come.
In the movie, they walk into a situation where neither is going to get out alive, and they have to sacrifice their lives to save humanity, but Tom Cruise gets the Omega’s blood on him, and regains the power to reset the day on his death. In doing so everyone that dies is alive again, with a fairy tale ending. The war is over and humanity can celebrate.
アレクサンドリア [DVD]/レイチェル・ワイズ,マックス・ミンゲラ,オスカー・アイザック
¥3,990
Amazon.co.jp
実話というけれど、彼女の考えた天空の太陽と地球との惑星の軌道が「楕円」ということを、ケプラー?よりも1600年も早く、発見したというこのシネマのディテールにまず感動。
私は、この「楕円」というキーワードを見ると、即、花田清輝の「楕円幻想」を連想した。
好きで好きで、何回も読み返したレトリックにあふれた文体の贅沢な本だった。
先日亡くなった吉本隆明だったか、彼を議論で打ち負かして、その後はあまり紙面には出てこなくなったと聞いたが、私から言わせれば、吉本隆明以上の閃く素晴らしいセンスを持っていて、魅力的な作家だった。
花田清輝 (日本幻想文学集成)/著者不明
¥2,039
Amazon.co.jp
要は、彼が言いたいのは、「円」という神学的に言うとまさに完璧なる図形はいいとして、現代という時代は、「円」にこだわることなく、二極を中心とする円=「楕円」こそが、必須の思想の核になるのではないか、そんなエッセイだったような記憶がある。
もう絶版の書物だ。
その「楕円幻想」を思い出しながらこの映画を見た。
彼女がたくさんの男たちに、ギリシアの哲学を教えている。
「考える」ことが、ニーチェのいわば「知の快楽」になっていて、彼女には宗教は必要がない。
彼女自身が言うように、「哲学」こそが、彼女の「宗教」になっている。
このあたりは、たとえば、曖昧な記憶だが、ジョイスのエピファ二ィだったか、パリでの経験と比較してダブリン市民の知的な麻痺、無気力を彼独特の「エピファニィ」で、書き留めている。
エピフィ二ィはキリストの現出を意味するものだと思う。
あるいは、コリン・ウィルソンの「至高体験」のようなものだろう。
それらの体験を哲学を通じて経験できる、現代ならばそうとうの地位にまであがれるような美しき女性、それが、ヒュパティアである。
彼女は、たしか、「ナイロビの蜂」にも出演していて私が気に入っていた女性だったので、この映画でこんなすばらしい役柄をやってのけて、感心した。
新プラトン派と言われるが、それは後世の人がつけたレッテルであって、この映画の描く彼女の生き様は、「知の快楽」や「真理愛」に憑かれた天才の生き様だ。
キリスト教の信奉者が70%をしめると言われるスペインで、こんな映画が出来た。
ある意味では、映画として皆それを冷静に観ているのだと思う。
そして、この映画にしょっちゅう現れる「巨の視点から見た地球」。
それは、宗教でさえも、彼女の真理愛から見ると、小さく見えてしまうものだ。
物語も非常に上手く書かれていると思うし、時代考証もなかなか説得力があり、ひきこまれた。
古代の人の精神までにはとうていたどりつくことは不可能だとは思うが、少なくとも、ギリシアの哲学やら、キリスト教の布教、ユダア教の布教、人々の暮らし、知識人達の生活と奴隷達の日常。
そんなものが、リアルに画面に出て、非常に刺激となった。
映画は見るものさしは、皆、自由だと思う。
車好きな人は車のたくさん出る映画に驚喜するのだと思うし、自分の好きなスタアが出れば皆、小躍りするではないか。
私の、ツボにはまる映画とは、○音楽家のエピソードを扱った映画○まだ見ぬ風景などの自然がたっぷり見られる映画○神秘や幻想や心の綾をテーマにする映画○「天才」達を扱った映画○好きな男優女優の出る映画○まったく自分が考えたこともない視点からの映像や問題点をなげかけてくる刺激的な映画だ。
この映画も、その意味では、私のツボにはまった映画だった。
なによりも映像が美しい。
タイタニックの監督が、今、3Dであの「タイタニック」のリバイバルをつくっているらしいが、楽しみだ。
映画とは、私の脳に刺激を与えてくれる最高の娯楽だ。
こんなアホな脳であっても、少しくらいは、進化してくれるかもしれない。
この映画の中で、何回も考えていることだが、現代人の頭の構造は、テレビやゲームや下らない人間関係などに押さえ込まれてるのと比較して、なんと古代人は自然の中でそれらを研究し学習しそこから大きなものを学んでいることだろうか、という驚きである。
今の現代にもしも彼らがやってくることができたとしても、彼らがうらやましがることは何もないだろう。
映画『プロメテウス』
「二つの人格の出会いは化学物質の接触のようなものだ。
なんらかの反応があれば両者が変形することになる」
The meeting of two personalities is like
the contact of two chemical substances:
if there is any reaction, both are transformed. ユング
プロメテウス (映画)
プロメテウス
Prometheus
監督リドリー・スコット
脚本デイモン・リンデロフ
ジョン・スペイツ
製作リドリー・スコット
トニー・スコット
デヴィッド・ガイラー
ウォルター・ヒル
製作総指揮マーク・ハファム
マイケル・エレンバーグ
マイケル・コスティガン
出演者ノオミ・ラパス
シャーリーズ・セロン
マイケル・ファスベンダー
ガイ・ピアース
イドリス・エルバ
音楽マルク・ストライテンフェルト
撮影ダリウス・ウォルスキー
編集ピエトロ・スカリア
製作会社スコット・フリー・プロダクションズ
ブランディーワイン・プロダクションズ
デューン・エンターテインメント
配給20世紀フォックス
公開アメリカ合衆国の旗 2012年6月8日
日本の旗 2012年8月24日
上映時間123分46秒
製作国アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
イギリスの旗 イギリス
言語英語
製作費$130,000,000[1]
興行収入$403,354,469[1]世界の旗
18.1億円[2] 日本の旗
次作エイリアン:コブナント
テンプレートを表示
『プロメテウス』(Prometheus) は、リドリー・スコット監督による2012年のアメリカのSF映画である。当初、同監督の『エイリアン』(1979年)の前日譚として企画されたが、後にその見解の確定性を弱める発言がなされるようになった。撮影は2011年3月に開始された。フランス(2012年5月30日)、イギリス(同年6月1日)などで先行公開された後、アメリカでは20世紀フォックスの配給によって2012年6月8日に公開、日本では同年8月24日にPG12指定作品として公開された。
たまたま、先日テレビで、「ゼログラヴィティ」をやっていたので再視聴。
すると、この「プロメテウス」を再度、見直したくなくなり、昨日再視聴。
ジョージ・ハリスンのレコードを聞きながら、観ていたが、しだいにはまりこむ。
SFが好きではないという人もおおい。私の友達にもたくさんいる。
理由を聞くと、歴史的な史実は好きだという。
つまり実話にもとづく物語などは観ていて納得できるが、ただの想像力だけ、空想妄想でつくりあげた映画は観たいとも思わないと言う。
もったいないと思う。
個人的にも、私も、歴史的な史実の物語は好きだし、実話に基づいた映画は感動も倍になる。
しかしながら。
私の、小さな頃からの、古典的な基本のずっと考え続けている問題、つまり、「人間はどこからやってきて、どこへ行こうとしているのか」。
ゴーギャンにも同じ題名の絵画あると思うが、これのヒントをもえらるのは、この種の映画なのだ。
ワトソンの「生命潮流」のなかで、ユングはこう書いている。
「私は世界のへりまで進んで来たような気がした。私が燃えるような関心を持つものは、他人にとっては、無や空虚であり、怖れの原因ですらあった。それは何に対する怖れなのか、、わたしには説明がつかなかった。
空間や時間、因果律などの限定された枠を超える出来事があるかもしれないという考えには、なんら非常識なところも世界をゆるがすようなところもなかったのである」
カール・グスタフ・ユング「 思い出 夢 思想」
この「プロメテウス」に描かれた世界が、いつか、そのまま現実になる日がくるのかもしれない。
CNNニュースでも、
このような記事があったので、コレクションしておいた。
「(CNN) 強大な力を持ったIT企業が2023年までに世界を支配する――。今夏劇場公開されるSF映画「プロメテウス」(リドリー・スコット監督)はそんな未来を描く作品だ。映画に登場するウェイランド社のピーター・ウェイランド社長は、「我々は人間と見分けが付かないアンドロイドを作り出せる」「我々は神になった」と宣言する。
スコット監督が描く2023年は、単なるSFに終わらないかもしれない。グーグル、フェイスブック、アップルなどの巨大ハイテク企業は、巨額の富と力を手にしているという点で、「神」の様相を帯びている。
フェイスブックは9億人の会員を擁し、過去最大規模となる1000億ドル規模の株式公開(IPO)も目前だ。だがこれは同社による世界変革の始まりにすぎないとマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)は言い、いずれ地球上の全人類80億人を結び付けたいと公言する。
一方、強い影響力を持つようになったグーグルは、メガネ型ディスプレーや自動走行車といった未来志向のプロジェクトに加え、世界のGDP(国内総生産)を一気に押し上げる可能性を秘めた小惑星の資源探査プロジェクトに資金提供を申し出た。
グーグルがロボット(つまりウェイランド社長の言うアンドロイド)の開発に乗り出すのは時間の問題かもしれない。シリコンバレーでは、私たちの仕事をすべてアンドロイドがやってくれる未来を夢見る夢想家もいる。プロメテウス [Blu-ray]/出演者不明」
手塚治虫は、しかしながら、すごかった。
すでに、「火の鳥」などの未来編で、世界はたった3つの企業で、支配されていた、との記述があったような記憶があります。
人間とは不思議な存在だなあといつも思うのは、私の場合でも、1年後3年後というよりも、この三ヶ月くらいのことを考えることでもう精一杯なのですが、たまに、こうやって、遠い未来の地球や、日本の将来のSF的なシチュエーションを考えるのも楽しいものです。
少なくとも、自分の仕事がアンドロイドに変わってもらえるようなレベルの仕事はしたくないですね。
ノオミ・ラパスも、いいですね。何回観ても。



イェヴレボリ県フーディックスヴァル出身。父親はスペイン人(バダホス出身のフラメンコシンガー ロジェリオ・ドゥラン、母親は女優ニナ(出生名クリスティーナ)・ノーラン。フォトグラファーの妹が一人いる。幼少期はストックホルム県や南アイスランド地方で過ごす。しかし父親が死亡。その後、実母、妹、継父と5歳から南アイスランドで過ごし、15歳の時家を出てストックホルム・シアター・スクールに通う。母国語のスウェーデン語、英語に加え、アイスランド語、ノルウェー語、デンマーク語を話す。
7歳の時、アイスランド映画『I skugga hrafnsins』にセリフの無い小さい役で出演。これが演技への情熱の始まりであった。1996年にテレビシリーズ『Tre kronor』でデビュー。2007年公開の『Daisy Diamond』で注目を集める。2009年公開の『ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女』ではヒロインのリスベット・サランデルを演じ、世界的に注目を集める女優の一人となる。2010年フランスのサイコスリラー・ラヴ犯罪の英語リメイクでレイチェル・マクアダムズと共演。2011年公開の『シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム』でハリウッド作品に初出演する。リドリー・スコット監督のSF映画『エイリアン』の前日譚の『プロメテウス』の主役に抜擢され、2012年に公開された。2013年ミレニアムの一作目を作った監督のハリウッドデビュー作、『デッドマン・ダウン』に出演。
◎「ドラゴンタトゥーの女」豆知識
ネットから「ドラゴンタトゥーの女」豆知識お借りしてきました。ありがとうございます。
この映画豆知識。
●ミレニアムシリーズ3部作は全世界で6500万部を売り上げる超ベストセラー。
●原作者のスティーグ・ラーソンは1作目(2004年)の出版直前に心筋梗塞で急死(享年50歳)。
●一人当たりのGDPは49,000ドル。失業率8.4%(2010年)。
●通貨スウェーデンクローネ(SEK)は1クローネ=約12円(2012年2月現在)
劇中に出てくる金額は以下のようになる。
・ヴァンネルストレムの不正利益→6000万クローネ=約7億2000万円
・ミカエルに科せられた裁判による賠償金→15万クローネ=約180万円
●スウェーデンの国土は日本よりやや広いが人口は12分の1の約942万人。
●首都はノーベル賞で有名なストックホルム(人口約83万人)
●スウェーデン発の有名企業はボルボ、サーブ、エリクソン、イケヤなど
●高福祉国家であるがドメスティクマターとして移民問題、女性への暴力、将来の社会保障制度、企業・役所の汚職が社会問題としてある。
●男性から女性への暴力が他国と比べると多い。
・スウェーデンでは女性の18%が男に脅迫された経験を持つ。
・スウェーデンでは女性の46%が男性に暴力をふるわれた経験を持つ。
・スウェーデンでは女性の13%が性的パートナー以外から深刻な性的暴行を受けた経験を持つ。
・スウェーデンでは性的暴行を受けた女性のうち92%が警察に被害届けを出していない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
聞いた話しでは、映画はどんどん進化しているので、私たちの脳に最高の刺激をくれる。
それを感じることができるだけでも、たまたま、21世紀に生きている幸福を感じることができる。
パリでは、珈琲を飲んでいてテロリストに射殺され、熊本では寝ていると屋根がおっこちてきて、死んでしまう。昨日のアメリカでは、ゲイのたまり場で、一気に50人が殺され、100人近くの人が怪我をする。
クマが人を食い、家で団らんしていると小型飛行機が突っ込んでくる。
スーパーで買い物をしていると高齢者の車がつっこんでくる。
整列して歩いているのに、これまたボケ老人の車が少年少女をはねていく。
・・・・・・・・・・・・・・・・
21世紀。起こる事件は奇々怪々だが、よくよく考えると、古来、人類は、その時代時代の「敵」や「災害」や「危機」と戦って生き延びて来た。
生き延びて来た子孫がわれわれなのでもあった。
ノオミ・ラパス扮するショー博士は、最後の最後に、地球にもどらずに、自分たちのルーツ探しに、再度、チャレンジして宇宙船に乗り込む。そこがしびれるほど、カッコいいと思った。
デイヴッドという、Androidがでてくるけれども、たしか、「エイリアン」のAndroidを連想させますが、この物語を観ていると、人類にはかならずや、必須の、なくてはならない友人なのだということが、よく理解できる。
◎資料 エイリアン2に出てくる印象的なAndroid。
ビショップ(Bishop)
演 - ランス・ヘンリクセン
医療従事用アンドロイド。APCの運転も担当しさらに降下艇の操縦資格も持つ。当初は前作におけるアッシュの件もありリプリーに嫌悪されるが、暴走したアンドロイド(アッシュ)は古い型の不具合であり自身は問題ないと説明する。人間ではないが恐怖心はあると語っている。ナイフを使った曲芸(広げた手の指の間を高速で突き立てていくもの)が得意で、劇中でハドソンの手に自分の手を重ねて人間離れした速さで行っていた。この時に珍しく手を傷付け、白い血液をリプリーに見られアンドロイドだと発覚する。
◎ディヴィッド
・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワグナーの音楽を使った地球に小惑星が衝突する名作が最近あったけれど、人類はいつかは、宇宙の果にでていかねばならない日がくるだろうと思う。
はっきりした記憶ではないが、「もう地球のような星はこの宇宙にはないのよ」と叫ぶ主人公の声が今でも耳に残っている。
・・・・・・・・・・・・
この「プロメテウス」でも、出会うエイリアン、つまり宇宙人は皆グロテスクで、無目的に自分の生命を広げようとするだけの、醜い、生物ばかり。
しかしながら。
・・・・・・・・・・・・・そうなのかもしれない。
ホーキング博士も、宇宙人との邂逅はなるぺくしない方が良いとどこかで書いていた。
ジルベスターの星から (サンコミックス) の、竹宮恵子の想像した、宇宙の果の美しい少年。
昔はあこがれたものだったけれど。
「プロメテウス」のこの筋肉質だらけの、真っ白な、人類とDNAとほぼ100%同じであるエイリアンなど、私が若い頃は、想像もできなかった。
しかも、彼らが武器としてつくりあげていたコブラのような生物が、進化して、いわゆるギーガーのイラストのような怪物になっていくシーン。
ぞっとする。
ノオミ・ラパス扮するショー博士。
何回も書くけれども、「生存者すべて死亡」という連絡だけを残して、宇宙の果てに、Androidの力を借りながら、旅立つシーンには、鳥肌がたった。
人類とは、そんな生物なんだろうと思う。
どんな苦難のなかでも、希望と勇気と、好奇心だけは、失わない。
少なくとも、悲劇であるはずのこの「プロメテウス」の唯一の光でもあったラストシーン。
「私たちが認識できる限り、人間存在の唯一の目的は
単に生きることの暗闇に火をつけることである」
As far as we can discern, the sole purpose of human existence
is to kindle a light in the darkness of mere being.
ユング
FIN
◎資料
太古の昔、岩山と激流しか見当たらない惑星。その地表に降り立った人型異星人が半球形の容器に満たされた黒い液体を飲むと、その体は急激に溶解し始め自らのDNAを惑星に拡散させた。
時は流れて西暦2089年、考古学者のエリザベス·ショウとチャーリー·ホロウェイは新たに古代遺跡を発見した。その壁画の構図はそれまで複数の古代文明で見つかった物と明らかに共通点が見られるものであった。ここから人類が追い続けていた種の起源の答えとなる未知の惑星の存在が浮かび上がる。
ウェイランド・コーポレーション選抜の科学者たちを中心に編成された調査チームは、宇宙船プロメテウス号に乗り込み星図の示す別の太陽系を目指して出発する。乗組員が冷凍休眠で眠る間、アンドロイドのデイヴィッドが航行を担当し、来るべき宇宙人との意思疎通に備え祖語の学習・研究に励む。
2093年12月21日、機関が自動停止しLV-223が目前に迫った事を知らせた。冷凍休眠から目覚めた乗組員は、故人となったウェイランド社長からのホログラム映像による激励と今回の調査目的について説明を受ける。ショウは創造論的発想でエンジニアなる宇宙人が存在し、それが人類誕生の謎を解く創造主だと語る。ウェイランド・コーポレーションの重役にして調査ミッション責任者のメレディス・ヴィッカーズは計画自体に懐疑的で、万が一エンジニアと遭遇しても一切コンタクトを取らず、直ちに自分へ報告するよう忠告する。
12月25日、プロメテウス号はLV-223の大気圏に突入。着陸地点の探索中、複数の滑走路のような直線と複数の巨大なドーム状の岩山を発見し、その付近の平坦な場所へ着陸。日没が迫るので船外活動に難色を示す船長の制止を聞き入れないホロウェイたちは、クリスマスプレゼントを開けずにいられるかとばかりに、即席で調査隊を結成し岩山へ向かう。
岩山に見えたのは実は人工的に造られた何らかの構造物であった。途中から別行動をとったデイヴィッドが映像記録装置を発見し、起動させるとエンジニアとおぼしき人間大の生命体が走って行くホログラムが再生され、その先にドアで頭部が切断されたエンジニアの死体を発見する。測定により、その死体は約二千年前のものと分かった。ドアを開くとエンジニアの頭部と巨石人頭像のような巨大な頭像、および円筒形の容器が無数に置かれた部屋が発見される。部屋の床面にはミミズのような小生物が棲息していた。一方、外では急速に天候が悪化し、嵐が接近しつつあった。そのため調査隊は一時撤収を余儀なくされる。混乱に乗じてデイヴィッドは、秘密裏に容器の一つを持ち出す。彼が立ち去った後、残された容器からは黒い液体があふれ始めていた。 一方、人間型異性人の死体に驚いて先に帰ったはずの生物学者と地質学者ら二人は構造物の中に取り残されてしまった。彼らは内部をさまよい歩くうちにエンジニアたちの死体の山を発見する。
プロメテウス号に戻ったショウたちは、持ち帰ったエンジニアの頭部からDNA型を分析し、人間のそれと完全に一致するとの結論に達する。同じ頃、別室でデイヴィッドは円筒を開き、中のアンプルから黒い液体を採取する。一方、ホロウェイは船内でくつろいでいたが、そこへデイヴィッドが現れ語りかける。彼は採取した黒い液体の正体を確かめるべく、それをシャンパンにそっと混入しホロウェイにすすめる。ホロウェイは笑顔でデイヴィッドからすすめられたシャンパンを一気に飲み干した。ショウも自室に戻ってくつろいでいるところへホロウェイが現れ、二人はそのまま性交する。
夜もふけて、船長以下プロメテウス号の乗組員全てがくつろいでいる最中、二人の学者たちはなおも構造物内をさまよい歩き続け、やがて円筒形の容器が無数に置かれた部屋に差し掛かる。するとあふれ出た黒い液体のたまり場から何か生き物が飛び出した。それはミミズのような小生物が変異した、乳白色でコブラのような軟体の生命体であった。突然それが生物学者に襲い掛かり、腕に巻きつく。引き剥がそうと地質学者が生命体の身体を傷つけると酸性の体液が噴き出す。体液は地質学者のヘルメットを溶かし、苦悶する彼は黒い液体の中へ転倒する。コブラ型生命体は生物学者のヘルメットを破壊し、口から体内へ侵入して彼を殺してしまう。
翌朝、ホロウェイは自分の身体に何か異変が生じているのに気づく。嵐は静まり、調査隊は再び構造物へ向かう。その内部で生物学者の死体を発見するが、地質学者の姿は消えていた。デイヴィッドはまたも別行動で秘密裏にエンジニアの宇宙船の操縦室を発見し、ホログラム映像からその操縦法を学習、エンジニアの一人が冷凍冬眠状態で生存していることを知る。 ホロウェイは急速に体調が悪化し、調査隊は彼をプロメテウス号に連れ帰ろうとするが、ヴィッカーズは彼の乗船を拒み火炎放射器で殺害してしまう。
それを見たショウは、ショックのあまり気絶する。やがて彼女が目覚めると、目の前にデイヴィッドが戻ってきていた。体内スキャンの結果、わずか10時間前の性交で、彼女は先天的不妊にもかかわらず妊娠3ヶ月の状態と知らされ、しかもそれは人間以外の生命体だという。正体不明の生命体が体内で急速に成長していると確信したショウは、ヴィッカーズの居室兼専用の地球帰還モジュール内にある全自動手術装置で帝王切開手術を受けようとする。その装置は男性専用のため堕胎は不可能と処置を拒否されるが、腹部の異物摘出に指示を変更する。彼女は苦しみながらも手術に成功。体中から取り出されたのは何と、イカのような姿をした肌色で軟体の生命体であった。パニックに陥ったショウはそれを全自動手術装置の中に閉じ込め逃げる。
一方、行方不明だった地質学者がプロメテウス号に戻ってきた。しかし、彼はもはや人間ではなくなっていた。知性は失われ、顔は融解したように変貌し、人間以上の身体能力を身に着けていた。彼に歩み寄った隊員がまず殺され、暴れ回った地質学者はさらに数人を殺したが、プロメテウス号のヤネック船長達によって焼き殺された。
その間、ショウは寿命が尽きたと思われたウェイランドが、実はプロメテウス号の一室に同乗していることを知った。デイヴィッドがヴィッカーズの指示に従わない行動を見せたのは、社長であるウェイランドの指示命令が優越されたからであり、ウェイランドは創造主たるエンジニアと会い、自分を老衰による死から救ってくれるよう直接頼みこむ考えであった。しかしショウはこの場所に来たことは間違いだったと述懐する。
ヤネック船長は、この場所はもともとエンジニア達の母星ではなく、彼らが作りだした生物兵器 (黒い液体) をテストするための試験場で、生物兵器が暴走したのではないかという仮説をショウと話し合うが、答えは出ない。
ウェイランドたちは支度をしてエンジニアの宇宙船操縦室へ向かう。見送るヴィッカーズはウェイランドを父と呼んだ。デイヴィッドは冷凍冬眠中のエンジニアを目覚めさせウェイランドの延命を申し入れるが、突如エンジニアは彼の頭部を引きちぎり、ウェイランドたちを次々と殺害してしまう。更にその宇宙船操縦室に乗り込みハッチを閉め、離陸の準備を始める。ショウは宇宙船から脱出するが、機能し続けるデイヴィッドから、エンジニアが黒い液体を地球に拡散させるつもりであると連絡を受ける。ディヴィッドはエンジニアの行動をずっと監視し続けていたのだった。
ショウはエンジニアが地球の破壊に向かうとヤネック船長に報告し、飛び立とうとする宇宙船を阻止するよう説得する。船長と副操縦士二人はプロメテウス号を宇宙船に激突させ墜落させることに同意するが、ヴィッカーズは船との心中を拒否。そこで船長は彼女に脱出ポッドを使用し40秒以内の退船を指示した。まず彼女専用の居住モジュールを本船から射出し、次に非常脱出ポッドで脱出。船長たちはそのままプロメテウス号でエンジニアの宇宙船を追跡し、それに追突して見事撃墜した。すんでのところでプロメテウス号から脱出したヴィッカーズだが、そこへ爆発した宇宙船の破片が降り注ぎ、果ては墜落してきた宇宙船の残骸で圧死してしまう。
同じく残骸で圧死したと思われたショウは岩と宇宙船との隙間でかろうじて助かった。やがて気密服の酸素残存量減少警告音声で目を覚まし、追加の酸素を得るためヴィッカーズの居住モジュールへ入るが、摘出処置を受けた全自動手術室内に、今や巨大なヒドラのように成長した肌色の生命体が居るのを見る。するとそこへ墜落から生き延びたエンジニアが復讐にやって来て、ショウに襲い掛かるが、彼女は絶妙なタイミングで全自動手術室の扉を開放し、巨大化した生命体がエンジニアを襲っている間に逃げ出す。エンジニアは巨大生命体と格闘するうちに頭部に巻きつかれて昏倒する。
ショウは絶望に打ちひしがれたが、その耳にいまだ機能するデイヴィッドの声が聞こえてきた。そこでショウは無事に残っていたバギーで例の構造物へ向かい、エンジニアの宇宙船操縦方法を習得したデイヴィッドを回収し、更に別のドームに残されていたエンジニアの宇宙船へ向かう。彼女らは、LV-223は死の星でありこのメッセージを受信しても決して発信源を探すな、という警告を残す。そして一連の行動の動機を探求すべく、エンジニアの宇宙船を使って彼らの母星を目指し旅立った。
一方その頃、残された居住モジュール内に倒れていたエンジニアの胸を突き破り、尖った頭を持つ新たな生命体が出現した。それは起き上がると奇怪な産声を上げる。その口の中には、もう一つの「飛び出す口」があった。
Kate Liu – Sonata in B minor Op. 58 (third stage
バッハはグールド。
モーツアルトはハスキル。
そして、ショパンはケイトかな。
シネマ「倦怠」を見ました モラヴィア原作
(story)
哲学の教授マルタンは妻と別居中、執筆中の本も進まず、人生のあらゆる面で行き詰まりを感じていた。そんなある日、マルタンは一人の老画家の死をきっかけに、彼の絵のモデルをしていた若い娘セシリアと知り合う。そして、次第に彼女に惹かれていったマルタンは、いつしか彼女との官能的な愛の日々に溺れていく。しかし、普段の彼女のそっけない態度や、自由奔放で別の男とも関係を持ってしまう彼女の行動に、マルタンは苦悩し常軌を逸した行動を取り始める。
愛のかたち。
いろいろな愛のかたちがあるんだと思う。
よく、惚れた方が負けという言葉があるけれど、深い言葉かもしれない。
たしか、故谷沢 永一氏が、「愛だ恋だという思想を生活のなかにいれるべきではない」というようなちょっと違うニュアンスを書いていたけれども、彼はその意味では、常識のある現実化。
「悪魔の思想」や「人間通」は傑作だ。
表面的な良き評価のなかの、深い疑念やインチキ思想の見破り、あるいは人間と人間というもののつきあいかた、そんなもの・ことが、さりげなくわかりやすい言葉で書いている。
彼なら、この「倦怠」という映画をなんという言葉で呟くだろうか?
そのを考えていたら愉快になって笑ってしまった。
それくらいに、この映画の主人公の男は、モラヴィア得意の「観念的な」男だ。
べつな言い方をすれば、右脳で感じたことをすべて左脳の言語に一度変化させて唇にのせないと、気が済まない男。
日本人には少ないタイプだけれども、ロゴスのヨーロッパにはおそらく無数にいるタイプだろう。
この太めの少女。

素晴しい演技で、圧倒的に、シャルル・ベルリングを食っている。
新しい愛人のモモをつくったりもする、自由な女だ。
それに嫉妬し、狂ったように、精神の変調をきたしていく哲学者マルタン。
そのあたりの、恋するふたりの、愛というか恋というか、sexの重さが、日々、メカリではかられるかのようだ。
当然、セシリアは、暇つぶしでこのマルタンとつきあっているだけだろうから、ずっと優位なのだ。
しかも、右脳の感情というものをそのまま心のなかに内包して安心してしまう女独特の強さもある。
これは、男の負けにきまっている。
インテリ男は、大胆な猫型の少女にかならず負ける。
すくなくとも、支配しようとする男独特の戦略で攻めているうちは・・・・・・・
饒舌な男は寡黙の無意識の得意な女性にはどうやっても勝てない。
天才的な言葉の男であれば、別だが。
出演者 シャルル・ベルリング 、 ソフィー・ギルマン 、 アリエル・ドンバール 、 ロバート・クレイマー 、 アリス・グレイ 、 モーリス・アントーニ
監督 セドリック・カーン
脚本 セドリック・カーン 、 ロランス・フェレイラ・バルボザ
原作者 アルベルト・モラヴィア
撮影 パスカル・マルティ
◎資料
ソフィー・ギルマン
SOPHIE GUILLEMIN
1977年12月1日、フランス・パリ生まれ。女優になる前は、パリのディズニーランドや、ウェートレスなどをして働いていたという。
20歳のとき、セドリック・カーン監督に見出され「倦怠」でデビュー。演技を学んだことのない全くの素人だったにもかかわらず、フランスのトップスター、シャルル・ベルリングを相手に、体当たりの演技を見せた。この作品でセザール賞有望若手女優賞にノミネートされる。
以来、ロベール・キュベルベルグ監督の「Une famille ordinaire」、フィリップ・ベランジェ監督の「On fait comme on a dit」など、次々に出演依頼を受けるようになる。
2000年には、本国フランスで200万人以上の観客を集め、社会現象にもなった「ハリー、見知らぬ友人」に出演。セルジ・ロペス演じるハリーの恋人役を色っぽく演じ、再びセザール賞有望若手女優賞にノミネートされた。
その後も、2002年には「愛してる、愛してない…」で、オドレイ・トトゥやイザベル・カレと共演した。
■ 主な作品
2002年 愛してる、愛してない…
2001年 DU COTE DES FILLE
2000年 ハリー、見知らぬ友人
2000年 On fait comme on a dit
1998年 倦怠
ソフィー・ギルマン
SOPHIE GUILLEMIN
1977年12月1日、フランス・パリ生まれ。女優になる前は、パリのディズニーランドや、ウェートレスなどをして働いていたという。
20歳のとき、セドリック・カーン監督に見出され「倦怠」でデビュー。演技を学んだことのない全くの素人だったにもかかわらず、フランスのトップスター、シャルル・ベルリングを相手に、体当たりの演技を見せた。この作品でセザール賞有望若手女優賞にノミネートされる。
以来、ロベール・キュベルベルグ監督の「Une famille ordinaire」、フィリップ・ベランジェ監督の「On fait comme on a dit」など、次々に出演依頼を受けるようになる。
2000年には、本国フランスで200万人以上の観客を集め、社会現象にもなった「ハリー、見知らぬ友人」に出演。セルジ・ロペス演じるハリーの恋人役を色っぽく演じ、再びセザール賞有望若手女優賞にノミネートされた。
その後も、2002年には「愛してる、愛してない…」で、オドレイ・トトゥやイザベル・カレと共演した。
■ 主な作品
2002年 愛してる、愛してない…
2001年 DU COTE DES FILLE
2000年 ハリー、見知らぬ友人
2000年 On fait comme on a dit
1998年 倦怠
た
モラヴィア作品資料
倦怠 (1998)原作
金曜日の別荘で (1991)原作
ふたりの女 (1989)原作
ミー&ヒム (1989)原作
ベルト (1988)原作
鏡の向う側 (1987)原作
蒼い本能 (1981)原作
デシデーリア=欲望 (1980)原作
魔の獣人部落 マジアヌーダ (1976)脚本
グレートハンティング/地上最後の残酷 (1975)ナレーション
暗殺の森 (1970)原作
野性の眼 (1967)脚本
愛の集会 (1964)出演
軽蔑 (1963)原作
禁じられた抱擁 (1963)原作
太陽の誘惑 (1960)脚本
狂った情事 (1960)脚本
河の女 (1955)原案
ローマの女 (1954)
ジャンヌ・モロー 「クロワッサンで朝食を」「恋人たち」 吹石一恵「新撰組」「デスノート」
年をとるにつれて、誰でも自分らしくなるのだ。年とともに、良くなるとか悪くなるとかではない。 ロバート・アンソニー

この言葉を思い出しながら、「クロワッサンで朝食を」というフランス映画を見ました。
主演は、なんと、あの大女優、ジャンヌ・モロー。
私の大好きな「ラ・マノン」のファーストシーンからのナレーションは彼女。
その低い声に味があり、素晴しい出だし。
フランス映画の魅惑がとことん、つまっています!!!! 私の好みの映画のひとつです。
感想のひとつも書いてみようという気持ちになりました。
昔、アテネフランセで、英語字幕の彼女の映画を見て感動した記憶があります。
「恋人たち」「突然炎のごとく」の二本です。
独特の美しさ。
流れるような、新鮮な映像。
ほんとうに感動しました。
書物の方もまた、良いです。たしか、「ジュールとジム」とかいう題名がついていました。
惜しいことに、売り払ってしまいましたが。
またこの本には、出会うでしょう。
もうひとつは、これも、また私の愛するデュラスの作品ですが、
なかなか見る事のできない映画ですが、ここ最近やっと見る事が出来ました。
「雨の忍び逢い」です。
備忘録はまたのちほど。
フランスのあの頃の名女優といえば、バルドーや、カトリーヌ・ドヌーブ・・そしてやはり、ジャンヌ・モローでしょう。
「クロワッサンで朝食を」というあいかわらず、観客の受け狙いの題名でうんざりしますが、原題は、Une Estonienne à Paris・・・・・「パリのエストニア」このまま、で良いと思うのですが。
・・・・・・・・・・・・
(見終わった後に、ネットで、感想を探すと・・・・・・・・
やはり、この映画も、賛否両論のレヴューでした。)
この映画、何回も書きますが、フランス映画なんです。
ですので、現在、今の、フランスの国の空気や、風景やら、ひとびとのファッションやら、通行人の雰囲気、パリの現在の生き生きした動き、エッフェル塔の美しさなどが、見れる嬉しさもあります。
私は、人生で、二回しかフランスには言った事がありませんが、その目的は、美術館めぐりでした。
でも、この映画のひとりの主人公、モロー扮するフリーダは言います。
「地元のパリ人は、ルーブルなんかはいかないわ」
なんていっても、ここは、パリなんですから。
ニューヨーカーという言葉もありますし、東京人という言葉もあります。
フランスのとある名言ジョークに。
how can you be expected to govern a country that has 246kinds of cheese?
フランスには246種類ものチーズがあるんだ。こんな国を統治できると思うかね?
というのがありますが、そんな国の映画、それが、「クロワッサンで朝食を」。
まず、題名が、なにやら、優しく温かいヒューマンドラマかと想像させます。
あるいは、ヒット作品の、老いた男性のもとへ、ひょんなことから雇われた黒人との、友情物語・・・・・・・そんな物語を連想もしましたが。
やっぱり、モローの映画なんです。
難解ではありませんが、深いです。
嫌いな人は嫌いでしょう。
バルト三国からパリ人になった主人公のフリーダ(モロー)。85歳本人と同じ年齢の役柄。
これがまずすごいですね。
この年齢で、言葉は矛盾しますが、凍り付く程孤独ではあるもののいぶし銀の老年です。
すっかりパリっ子になって、まるで、「化身」の霧子のように、愛人のステファン50くらい?
に、店をまかせて、自分はのんびりと朝はかならず、クロワッサンと紅茶の生活を続けています。
我がままで、個性的で、他人から強制されることが大嫌いな道をこれまで歩んで来た成功者の金持ちですから、自分の人生に後悔はないのですが、とにかく、誰も、寄ってこない。
孤独。
老い。
これまで、愛人のステファンが何人も召使いをやとっても、すぐに、辞めてしまう。
普通の日本人の視点からこの映画を見ると、不道徳な道を歩んできた昔は美女であっただろうが、今は老いてしまっているモローにあまり共感できる人が、多いとは思いませんが。
日本人のように、近所付き合いやら、人間どうしの絆を第一に考える民族の視点だけでこの映画を見てもつまらないと思います。
やはり、西洋は、我の世界。個人の世界。その個が、直接に神様につながっているわけですから、人づきあいでも、良い意味で、合理的で、言いたいことを言い合い、喧嘩するときはがっちりするわけです。
それで、そこで、おわりではないのですね。フランスは。
こんなことわざも思い出します。
「フランスでは、けんかは愛情関係を強くするが、アメリカはけんかで愛が終わる」 ネッド・ローレム
最近の日本の若者達もまた、アメリカ式が多いですから。・・・・・・・
フリーダは、自分のことをさておいて、エストニアからパリにやってきて長く住んでいるエストニア人が嫌い。
そんな連中から、とあることを批判されると、即、持論をぶちまける。
「愛国者ぶるのはやめて」と・・・・
そんなに好きならエストニアに帰ればいいじゃないのと。
まあまあが、嫌い。なあなあが嫌い。孤独であっても、寂しくとも、老いても、とにかく、モロー扮するフリーダは、妥協せずに、生きているのですね。
まれに、彼女も、薬を飲んで、自殺未遂のようなこともしますが、ライネ・マギというエストニア出身の、これまた少し老いたアンヌ・・・・・に、最初のころは冷たく接して、まるで、試験のようなことをいろいろするのですが。
アンヌが、出て行った後に、モローが、「アンヌ アンヌ」と彼女にプレゼントしたパリのしゃれたコートを抱きしめるところとか、・・・・・・・
愛人の、年齢的には息子のような、髭面のパトリック・ピノー扮するステファンが、アンヌが出て行ったあとに、ベッドに添い寝するところ・・・
名場面ですね。涙がでます。ちっとも感傷的な描写はありません。むしろ、ぞっとするくらいに、むきだしの老いがでてくるのですが。
泣けます。
たしかに、健康で、笑のたえない、フランスのことも知らない、日本の歴史や日本人についてあまり普段考えたこともないような、人が見ても、おもしろいとは思えないかもしれせん。
でも、昔の光り輝くジャンヌ・モローのことを少しは知っている人。
フランスに興味がある人。
両親の介護を少しはしたことがある人。
自分自身の「死」について、いろいろ、考えた事がある人。
そういう人が見ると、まるで、宝石のような映画に変容していきます。
そして、エストニアからやってくる、お手伝いさん。
ライネ・マギ・・・・・・ジャンヌ・モローの存在感にすこしも、負けていませんでしたね。たいしたものです。
・・・・・・・・・
つい最近は、日本では、原節子さんが、亡くなって、日本人は、彼女が芸能界・映画界を去ってから、完全に普通人になり、マスコミにまったく姿をあらわさないままに逝ったことを、絶賛していました。
お国柄です。
それとは、まったく対照的なフランスの国のジャンヌ・モロー。
85歳になっても、彼女の表情から、昔のあの神秘性やら、冷たい強さ、強情ともとれるような知性、わがままな美、そんなもののある意味「残骸」を、堂々とまき散らすんです。
それが、素晴しい!!! お国柄の違い。それがまた楽しく、おもしろい。
・・・・・・・・「本物の大人の映画」だと思いました。
◎エストニアの位置は北海道よりも北のヨーロッパ。フランスは雪がふらないのではない。私が行った二月には雪がふるなかで、珈琲を飲んだ記憶がある。
◎カセットテープはよく洋画にでてくる。日本は電化製品はすすんでいる。
◎以前見たフランス映画によく女中には、スペイン人が多くでたり、イタリア映画にはポーラン時人が大工としてよく出ていた。
◎「私が愛したのは夫とステファンだけ。
◎アンヌの表情は非常によみずらい。常に相手の表情を読み取る訓練をしている日本人から見るとそういうことになる。
◎マニキュアの意味
◎エストニアはロシアから独立。
◎美男のインテリに口説かれてもあなたはなにも感じないの? フリーダ
◎なぜ、男は変わらないの 女は変わるの ? フリーダ
◎エストニアの子どもの子守唄がでてくる
◎エストニアの母の墓のとなりで死にたい
◎あなたが孤独なのは自分のせいなのよ アンヌ
◎アンヌ来て どこにいるの フリーダ
◎死を待たれるモンスターとしての存在・・・・・私も母の死をねがっていたわ
アンヌ&フリーダ 複雑な立場 心理状況
ところで。
「写真」について。
基本、わたしは、写真家で言うと、篠山紀信も悪くはないけれど、アラーキーのほうがおもしろいと思っているのだけれど、篠山の「サンタフェ」「ヴィスコンティ」なんかは好きだ。
毎日の日課ですので、
ブルータスの古書を朝から、いろいろ書庫の整理整頓をしていますと。
あらら、おもしろい写真が、味のある、・・・そう私の好きな写真の一枚をみつけました。
吹石一恵、、、「ときめきメモリアル」でデヴュー、伊東四朗と親子役で、「新撰組」で共演。


ただ、ここ最近、映画をどっぷりつかりはじめているので、この吹石一恵という女優さんのことは、まったく知らなかった。
この写真なかなかいいな、と古書を整理整頓しながら、魅入った。
「伊東四朗さんは理想の男性です」と、朝から調べていた、2010年発売のブルータスで、のたまうていた。
あれ? 雰囲気のある女優さんだなと、感心して、ちょいと調べてみると、・・・・・驚愕。
福山雅治と結婚していたんだ・・・・・・・・・・・・ほんとうになにも知らない私でした。
お恥ずかしい。
東京都港区のne plus ultra六本木店 ・・・・・このあたりは、なつかしい。
ここは、自分の管轄するお店がメルサに入っていたので、このあたりは、けっこう歩きました。
中原淳一展などは、銀座の松屋でやっていましたし。
退職後、このあたりはよくまわっては、友達と食事したりしたものです。
でも、この店は知りませんでした。
この写真は、計算すると、吹石は、当時28歳。伊藤は、73歳。・・・
さすが、篠山紀信。えぐるようにしてふたりの瞬間の、空気感をとらえています。
吹石一恵・・・・・・も、実に味のある雰囲気を漂わせています。
彼女は、不思議な美人さんだと思います。
なにやら、ただの美人ではなく、少し、文学少女的なところもあって、良いですね。
「紀子の食卓」にも出ていました。
田舎に住む17歳の平凡な女子高生・島原紀子は、家族との関係に違和感を覚えていたが、ある日インターネットのサイト「廃墟ドットコム」を知る。彼女はそこで知り合った女性を頼って東京への家出を敢行、「レンタル家族」という虚構の世界で生きていくが…。
この監督、興味深いのは漫画も描くんですね。
愛知県豊川市出身。17歳の時に詩人として、『現代詩手帖』や『ユリイカ』等に投稿、20歳の時には漫画雑誌『ガロ』に漫画を二度持ち込むも二度とも入選を逃す(一応は90年代に映画監督としてガロにコラム「東京ガガガ新聞」の連載を持つ)[1]。23歳の時に自主制作映画『俺は園子温だ!』を製作し、ぴあフィルムフェスティバルに入選する。
また大河ドラマ初出演作品となる『新選組!』では初めての男装役に挑戦しています。(2005年に卒業した大学の卒業論文のテーマは「脚本における日本語」で、三谷幸喜によるこの大河ドラマの脚本を取り上げた)。
また、「ゲゲゲの鬼太郎」にも。
映画『ゲゲゲの女房』予告編
話しはそれますが、私は、水木しげるの漫画のコレクターなので、ほとんど彼の作品は持っていますが、
・・・・・・・・・
以前。
こんな記事も描きました。「デスノート」の物語とよく似た作品があるのです。
「デスノートの元ネタかも」
水木しげると言えば、「ゲゲゲの鬼太郎」と「悪魔君」が二大代表作とされているが、実はそれ以外にも、私の大好きな作品がたくさんある。
「縄文少年ヨギ」「猫楠の生涯」「ヒットラー」「雨月物語」「近藤勇」「ラバウル小唄」「カッパの三平」「異界への旅」など、他にもまだまだ、傑作があるのである。白戸三平のマルクス主義の絵解きの忍者武芸長とは違い、彼の「忍法屁話」などは自由な発想が快い。
さて、今回のテーマである「デスノート」とよく似た作品のことであるが、私の水木の蔵書をこれかなと一冊とりあげてみると、やはり、神秘と幻想の作家だけあってその顔をすぐに見せてくれる。この偶然も水木の作品らしく、これもシンクロニシティのひとつではあろうが、題名が、「風刺の愉しみ」 呉智英編の中央公論社から出ている1200円の愛蔵版である。
諷刺の愉しみ (水木しげる作品集 (2))/中央公論社
¥1,258
Amazon.co.jp
この愛蔵版の中に、三十四作の作品が忍法屁話からはじまり、ねこ忍、コブ、未来をのぞく男など、名作が詰まっている中に、このデスノートとテーマがよく似ている「不思議な手帳」がある。
笑えるのは、怖い女房の憂さ晴らしで飲んでいた主人公の山田さんが、酒に酔って家に帰ると女房に怒られるので、しょうがなく、あるほこらで、ひと休みしていて、ノートを拾うのである。
そしてその横にはなんと男性の死体!!
そのようにして、知る人ぞ知るガロの編集長の花田勝一さんがこのデスノートをなぜか持ち歩いていたのだが、彼の怪死とともに、三島や川端などの有名人の名前が書いてある不思議な手帳を平凡な公務員の山田が拾うのである。
山田はそこに自分によく吠えつく隣の家のポチの犬の名前を書くと、なんと翌日、ポチが犬狩りにひっぱられていくではないですか。
このあたりは、よく「デスノート」とよく似ています。
天才少年ライト君みたいな格好良さのまったくない山田さんという水木漫画に必ず登場する冴えないおじさんが、主人公なんです。それが逆に親近感を感じさせるし水木の漫画の独特の世界の開放感につなげさせるんです。
呉さんは、「ゲゲゲの鬼太郎」と「悪魔君」は代表作ではない、とまで、書いてますが、これはこれで傑作です。
ひとつのパターンの中に、目玉の親父と鬼太郎とそして妖怪達との戦いをとうして子供心に怪物や妖怪に対する愛情や好奇心や神秘に対する興味を湧かせる力を持つ作品です。
「悪魔くん」も、天才的な少年が悪魔の力を利用してこの世の中に理想の楽園を造り出すという作品のテーマからして、デスノートの原作者がこの「悪魔くん」や「不思議な手帳」だけではなくて、水木の作品に通暁していることはほぼ、間違いないでしょう。
ただ、その事自体はまったく問題はなくて、もともとの自分の愛する作品を換骨奪胎してそれがまったく分らない程にまで噛み砕いてて昇華した作品は盗作ではありません。それが盗作ならば、ピカソもゴッホも、三島由起夫も村上春樹も、皆盗作者になってしまいます。
ジェームズ・W・ヤングという世界的なアイデアの達人は「アイデアとは新しいくみあわせ」だと、はっきり断言しております。
つまり、Aからまったくそれとは違うGは、生まれず、AがA1になり、A2になり、A8ぐらいになってはじめて、それが、Bに見えるというイメージでしょうか。
いちばん難しいのは自分が大好きな作品を、特に絵ですが、勉強のために模写しているうちにだんだんそれが自分が作り上げた作品と錯覚していくという「やつ」がこまりもんですが。
以前これで盗作疑惑になった日本画家がいました。本人は「自分の尊敬する画家へのオマージュ」という言葉で逃げていましたが。
水木しげるがこの作品で、短編の名手であることが更に世に知られ、そして、彼のような、「汚さ」の中に潜む「美しさ」や、「偽善」をさらりと笑い飛ばす柔らかい心や、「日常」の退屈の中に実は「神秘の扉」があるのだという彼の遊び心には敬服するファンが増えればいいですね。
余談ですが、水木さんの奥様とお嬢様とご本人には以前お会いしたことがあり、確か右手が戦争で無くしたために残りの手で漫画を書いていることを発見しました。
ほんとうに感動しました。
金儲けのためだけの漫画家が不勉強な漫画編集者によって、量産されている今、こんな漫画もあるんだということは忘れないでほしいですね。
「新撰組」 これは、見ていません。仕事でこの時間帯は無理でした。
「漫画」ですが・・・・・・・・
「新撰組」は、手塚治虫氏の傑作名作があります。
新選組 (手塚治虫文庫全集)/講談社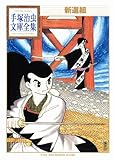
¥950
Amazon.co.jp
喪失と再生。
日本人の歴史の中で、戦後の我々の魂の状態とは?
世界のその他の国のように、リアルに家族が殺されたり、戦争に自分の子供達が参加したりするようなこともなければ、キリスト経の伝統の中で常に神の存在や不在について考えている国とは違って、飽食日本は心のむなしさを一番敏感に感じ取っているとよく言われます。
小さな頃に脳幹、つまり体の奥の奥を鍛えなければ人は大人になれないという説もありますし。
河合隼雄氏の意見では、のほほーんと育った人もいつかは「旅」に出るときが必ず人生にはあるとも示唆しています。
もちろんそれはいわゆる実際の「旅」でなくとも、「不倫」だったり、「退社」だったり、あるいは、「独立」だったり、いろいろ心の状態の中での旅のことである。
その旅の中で出会うさまざまなる人や、事件が彼や彼女を鍛えるのである。いわばイニシエーション的なものでもあると思う。
たんなる備忘録なのだが、この手塚治虫氏の「新撰組」の中で萩尾望都氏が、こんな解説を書いている。
「おさないころから不安な夢を見ていた。誰もいない、何もない、窓の外には霧しかない。世界はあるのか。私は存在するのか。成長しながらも何かが指の間からサラサラと失われていく虚無感がつきまとう。その喪失はどこから来たのか。世界からだろうか。両親だろうか。あの大戦の終了後、世界は何かを閉じ込めてしまったのだろうか。言語化も、視覚化も、意識化もできない無意識の中に浮遊する何か。
私にとっての手塚治虫作品は、その何かを言語化し、絵として視覚化し、物語として意識化した、具体的なものにみえた。不安を不安なものとして自覚させてくれたのである。」
さすが萩尾望都女子。
すごいと思う。
若い頃は妙な言葉だが、「苦労したがる」のです。
生きている実感をつかみたいのである。それができない、自分の目的を明確に萩尾望都のように見つけることが出来ない人は、仕事に夢中になる。
そこまでは良いが、その仕事からあぶれた人がやはりあぶない。あるいは、もんもんと悩んでいる敏感なる人達。
以前確か、神戸の殺人事件、酒鬼薔薇聖斗事件でしたか、「透明な」という言葉を自分の心の分析に使っていましたね。中学生が・・・・
リアルな実体験に乏しく、仕事もせず、友達もできず、つきあう異性もいなければ、その浮遊するパッションはまさに無目的な性行動にもつきあたることとなる。<例えば小説で言えば、限りなく透明なブルー>
1949年5月12日、萩尾望都は生まれている。
1949年1月12日、村上春樹。
1952年2月19日、村上龍。
経験が何もないまさに透明なる私の学生時代には、「生は単なる現象にすぎない」と、たわいもない議論ばかりしていました。
(小林秀雄氏もたしか、若い頃は、舌で壁をなめたりして、その確かな実在を感じとろうとしていたらしいことを何かの本で読んだ記憶がある)
やはり生きて行くということは、人間同士の絆の中のしっかりした実感の中で生きることが、体にとってのビタミン剤のように、魂にとってのビタミン剤になるのでしょう。
「クロワッサンで朝食」も同じ。
それは、ある時には、喧嘩であったり、軋轢であったり、恋だったり、たいていが人間関係の問題でもあるが、人はそこから逃げればあとは、何も残らないということも知る必要があるのではないでしょう。
先日も書きましたが、村上春樹氏が、誰とも会わずに創作をする中において、あまりにもすらすら小説が書けた時期があり、こんなことをやっていると人間としてダメになるのではないかと、不安にとらわれたことを何処かで読んだ記憶があります。
ところで、萩尾望都は、この手塚治虫氏の「新撰組」を読んで、たった二行の「大作、許してくれ」に衝撃をうけ、「何か」を具体化する目的を持つ、ひとりの漫画家になろうと決心したのですから。
「ノルウェイの森」ではないが、「喪失」と「再生」、軽く使いたい言葉ではないが、最近なにやら、私の頭をふらふら、飛び交うのである。
「ノルウェイの森」
・・・・・・・・・・・
「苦しい目に遭うと、どうしても「なんで俺だけがこんな苦労を…」って思っちゃうけど、そんなことないね。
みんな、あるの。
死ぬまであるもんなの。
だいたい苦労がなかったら、面白くもないし、人間じゃないよね。」
・・・・・・・・・・・淀川長治
FIN
デュ・ソートイ教授
ボルヘスと宇宙の関連。
・・
今再読している小林秀雄氏と岡潔氏の「人間の建設」そのものではないか。
あっという間の一時間であった。それにしても、ハーバード大学とは
実に不思議なおもしろい授業をするものだなあとつくづく思う。
いろいろと考えてみたい内容だった。
◎数学の不思議を追う第3回は、数学と芸術の関係を探る。音楽家や画家、作家たちは、意識的に、あるいは無意識に数学を利用し作品を作り出している。その驚きの世界とは?
番組内容
数学の不思議を、世界的に知られる数学者、デュ・ソートイ教授が解き明かすシリーズ第3回。今回は数学と芸術の関係を探る。音楽家や画家、作家たちは、意識的に、あるいは無意識に数学を利用し、作品を作り出している。素数を利用し人々の不安をかきたてる四重奏曲、黄金比にとりつかれたルネッサンスの画家たち、数学的な宇宙を体現した壮大な文学…。その驚きの世界を、さまざまな楽しいエピソードと驚きの事実で紹介する。
出演者
出演
オックスフォード大学教授…マーカス・デュ・ソートイ素数の音楽 (新潮文庫)/新潮社
¥961
Amazon.co.jp
