医者は生活の安定を約束していた。
しかし、僕は画が描きたかったのだ。
手塚治虫
ブラックジャックを毎日読んで、コマ割りなどを勉強している。
手塚治虫氏は、やはり「物語性」が抜群に、うまいということが理解できる。
小さなディテールは、??というところもあるのだけれども、全体的な流れでは、スムーズに
読んで行けるので、すごいと思う。


たとえば、この「クリスマス」の日に、ブラッククィーンとあだ名される女医が、ブラック・ジャックと逢う。
・・・・・・・・・・ 普段は、患者の足や手をバンバン切りまくって、冷静にオペをする彼女、ブラッククィーーンも、自分の愛する彼が、事故で、両足を切らねばならないとき、悩みに悩むのだった。
そのとき、ブラックジャックはどういう行動をとるのか・・・・
こんな小さなミニ短編なんだけど、ハッとさせられる。さすがに、手塚。
個人的な意見としては、アイデアが多すぎて、もっと煮込んで物語をつくりあげてもいいのではないかと思ったが、それは理想論。
アニメ会社を倒産させてしまい、必死に、彼も、このブラック・ジャックを書き始めている!!!! まさに、命がけで、書いた作品。
それが、ブラック・ジャックだと思う。
サマセット・モームという短編の上手い作家がいるが、ちょっと、手塚治虫氏との相似を感じた。もちろん、絵と文章という違いはあるけれども。
こんな物語があったような記憶。
貧乏な夫婦だったか、恋人だったか。
クリスマスの夜に、男の方は大切にしている腕時計を売り払って、妻にかんざしをプレゼントしようとする。
妻は妻で、彼のために腕時計のチェーンかなにかをプレゼントしようとして、自分の髪を切ってしまう。
・・・・・・・・・・・・・・
切なくて、深い愛を感じる一編だった。
「谷口ジロー」もよく読む。
嫌いではないけれども、絵が上手すぎて、原作者つきのマンガを描いているのも、もったいないと思う。
やはり、原作者なしで、マンガを書いてもらいたい。
夏目漱石についてマンガを書く事自体は良いと思う。
ただ、自分で、構成を考えた方が良いのではないか。
あせってはいけません。
頭を悪くしてはいけません。
根気ずくでおいでなさい。
世の中は根気の前に
頭を下げる事を知っていますか。
花火の前には
一瞬の記憶しか与えてくれません。
うんうん死ぬまで押すのです。
それだけです。 夏目漱石
『坊っちゃん』の時代 (第5部) (双葉文庫)/双葉社
¥669
Amazon.co.jp
最近読んだ漫画。
マンガは、よく暇なときに読む。
最近読んだのは、「人間交差点」「ギャグゲリラ」「夏子の酒」・・・・・・・
なんでも読む。
・・・・・・・・・・・・・・
谷口ジロー。
夏目漱石の胃潰瘍。
ある意味、責任感が強い。
ここに描かれた漫画の物語のディテールがもしも、考証が正しいとするならば、
あまり個人的に惹かれる人物ではない。
刺身も、胃に悪いという理由で食べずに、甘いものと、胃に重いものを食べ続ける漱石。
卵をぶっかけて、ご飯を三杯も、食す。
医者から注意を受けているにもかかわらず。
一度、死んだ漱石が、臨死体験のようにして、まるで、キューブリックの、ラストシーンの、あの不思議な老人との対面のようにして、すでに死んでいる面々と逢うシーンは感心した。
谷口ジローの熱烈なファンがいるので、少し褒めると、彼の小さなところまで細部をないがしろにしない絵には感銘。
養老さんが、解説しているけれど、昭和生まれの原作者が描く明治・・・
興味深いけれども、やはり、表面的に思えてしまうのが残念。
絵だけでも、これは手塚治虫賞というのは納得。
漫画はやはり、絵。 原作付きの漫画はあまり好きではない。 個人の好みだけれども。
夏目はやはり、活字で読みたい。彼が胃を痛めた執筆の跡が読み取れると思う。
「15歳、アルマの恋愛妄想」見ました。
ここに備忘録しておきます。ほんとうに忘れっぽい私です。
性を扱った映画はどこの国にもあるけれども、お国柄がおもしろい。
この映画、『15歳、アルマの恋愛妄想』(Få meg på, for faen)は、2011年のノルウェーのコメディ映画。原作はオーラウグ・ニルセン。
ノルウェー西部の架空の小さな街を舞台とし、性に目覚める15歳の少女のアルマが描かれる。

この少女。
そして、お母さん役の、ヘンリエッテ・ステーンストルプが、目立っています。
きわだっています。
・・・・・・・
実にリアルで、日本ではありえない、家庭にリアルな感覚を肉付けしております。
やはり、映画を見る楽しみは、物語が良い悪いとかそれだけではなくて、役者の魅惑もありますし、それにくわえて、なんといっても、ノルウェイの今の自然・都会の雰囲気が、味わえることだと個人的に思っています。
アルマの妄想というアイデア、がいいです。
田舎に不満を持って都会に出て行きたいというまことに普通の少女。
妄想が爆発しているのに、さわやか感があるのは、彼女=ヘレーネ・ベルグスホルムの
人柄、個性、そして、女優魂ということだろう。
青春時代のあの独特なもやもや感・性への憧れ・・そんな誰しもが持つ感覚をモダンなコメディに完成させたということだろう。
好きな作品。
◎資料から
監督・脚本は、本作が長編デビュー作となるヤンニッケ・シースタ・ヤコブセン。トライベッカ映画祭最優秀脚本賞、ローマ映画祭最優秀デビュー作品賞、モンズ国際恋愛映画祭最優秀ヨーロッパ作品賞受賞。
次なる見た映画。
「グリフィン家のウェディングノート」。
「マイ・リターン」を見て、アン・ハサウェイと素敵な関係だった、ロバート・デニーロ。
気になってみてしまいました。
原題「The Big Wedding」 2013年アメリカ映画
◎資料から
次男アレハンドロの結婚式のために、グリフィン家は10年ぶりに集まった。父親である奔放な性格の彫刻家ドンは、前妻のエリーと離婚した後、10年も愛人のビービーと暮らしており、実質今では彼女が一家の母親代わりになっていた。長女のライラはそんな父親を嫌っており、長男のジャレドは医師という立派な職に就きながら女性と上手く付き合えない等、家族はそれぞれ複雑な事情を抱えていた。
いよいよ結婚式間近となったある日、アレハンドロは思いもよらない問題に直面する。幼い頃グリフィン家に養子に入った彼には、超がつくほど保守的な思想を持った実の母親がおり、彼女に家族の複雑な関係を知られてしまうと、絶対結婚には賛成してくれそうになかったのだ。そこでアレハンドロはドンとエリーに、二人は今でも仲の良い夫婦だという演技を結婚式までの間してほしいと頼む。息子の幸せのため、渋々了承した二人だったが、これにより複雑だった家族関係は余計にこじれてしまうのだった。
これ、コメディ映画。
コメディだから、ドタバタ劇。
はっきり言って、想像を絶するくらいのハチャメチャ人生劇。
まじめすぎる人が見たら、あきれ果てるくらいの、いい加減な映画。
そこが良い。そう個人的に思う。
これだけ、つまらない脚本を、といっても、「最高の人生の見つけ方」の脚本を書いた監督でもありますが、さらに、アホ的なまさに安吾的ファルスの精神でつくりあげた・・・・・・・
B級映画。
あまりにも、軽いので、涙もでなければ、さほどコメディにしては、笑えもしないのだけれども、湿気の多い日本的な人間関係の重厚なる風土から見ると、それはそれで、興味深い。
規則やルールはあるけれども、結局は、人生を楽しむ・・・自分の盲目的な本能に忠実に生きるという映画。
モテモテの中年男性におすすめの映画とレヴューにあり、笑ってしまう。
これから、21世紀、世界的に、高齢者の時代が来るというのに、中年というだけで、毛嫌いする若者の精神の厚みのなさに、びっくり。
会田雄次教授の「バサラの精神」、龍角散社長の「もっと遊ぼう」ではないけれども、
生真面目で、視野の狭い人ほど、この映画は見ると良いと思った。
ところで、ミレーユ・ダルクのことを最近考えています。
「恋するガリア」を再視聴しました。
レジオンドヌール勲章シュヴァリエ章を、2009年、国家功労章コマンドゥール章をそれぞれ受章
声がこんな可愛い声とはしりませんでした。
資料を備忘録しておきます。
ミレーユ・ダルク
* 『何がなんでも首ったけ』、監督ロジェ・ヴァディム、1961年
* 『大貴族』、監督ジル・グランジェ / ジョルジュ・ロートネル、1965年
* 『恋するガリア』、監督ジョルジュ・ロートネル、1965年 - 主演
* 『海と女と泥棒と』、監督ホセ・マリア・フォルケ、1966年
* 『皆殺しのバラード』、監督ドニス・ド・ラ・パトリエール、1966年
* 『太陽のサレーヌ』、監督ジョルジュ・ロートネル、1966年
* 『女王陛下のダイナマイト』、監督ジョルジュ・ロートネル、1966年
* 『エヴァの恋人』、監督ピエール・ガスパール=ユイ、1966年
* 『牝猫と現金 (げんなま)』、監督ジョルジュ・ロートネル、1967年 - 主演
* 『ブロンドの罠』、監督ニコラス・ジェスネール、1967年 - 主演
* 『ウイークエンド』、監督ジャン=リュック・ゴダール、1967年 - コリンヌ役、共演ジャン・ヤンヌ
* 『枯葉の街』、監督ジョルジオ・ボンテンピ、1968年
* 『モンテカルロ・ラリー』、監督ケン・アナキン、1969年 - 共演アラン・ドロン
* 『ボルサリーノ』、監督ジャック・ドレー、1969年 - 共演アラン・ドロン
* 『ジェフ』、監督ジャン・エルマン、1969年 - 共演アラン・ドロン
* 『栗色のマッドレー』、監督ロジェ・カーヌ、1970年 - 共演アラン・ドロン
* 『狼どもの報酬』、監督ジョルジュ・ロートネル、1972年 - 共演ジャン・ヤンヌ
* 『愛人関係』、監督ジョルジュ・ロートネル、1973年 - 共演アラン・ドロン
* 『プレステージ』、監督エドゥアール・モリナロ、1976年 - 共演アラン・ドロン
* 『チェイサー』、監督ジョルジュ・ロートネル、1978年 - 共演アラン・ドロン
* 『ソフィー/遅すぎた出逢い』、1988年 - 監督・脚本
* 『女性弁護士マリオン』、テレビ映画、1998年
* 『ディープ シークレット ~殺人者の海~』、監督ディディエ・アルベール、テレビ映画、2003年 - 共演アラン・ドロン
* 『アラン・ドロンの刑事フランク・リーヴァ』、監督パトリック・ジャマン、テレビ映画シリーズ、2003年 - 2004年 - 共演アラン・ドロン
ミレーユ・ダークを見ていると実にフランスの女優は、センスが違いますね。
白黒の映画というのも、彼女の美をひきだしていると思います。
ドヌーブ・バルドー・ミレーユ・ダーク・・・・・・・・
◎資料
1965年、ジョルジュ・ロートネル監督の『恋するガリア』に主演し、マール・デル・プラタ国際映画祭主演女優賞を受賞、以降、ロートネル作品の常連となる。
「恋するガリア」
次なる鑑賞映画は、「ラジュテ」
◎資料から
1962年のフランス映画であり、監督クリス・マルケルによる時間と記憶をモチーフにしたSF映画。
近未来の廃墟になったパリで少年時代の記憶に取り憑かれた男の時間と記憶を、「フォトロマン」と呼ばれるモノクロ写真を連続し映す手法で描く、上映時間29分の短編映画。SFであるが、SF的な美術などは見られない。
1963年、トリエステSF国際映画祭グランプリ受賞。ジャン・ヴィゴ賞受賞。
12モンキーズをはじめ、多くの映画の原案になったといいます。
12 Monkeys
わたしは、すぐにキューブリックの「時計仕掛けのオレンジ」の目にクリップをさせられて拷問にかけられる男を連想しましたね。
あとは、フィフスエレメントの、「エリアンの歌」のシーン。
圧巻です。
いまでも、このシーンは、ビデオにとりこんで、よくココだけ見ます。
背中がぞくぞくするほどの圧倒的な美しさがあります。
グロテスクな美。
・・・・・・・・
このソプラノ歌手のことを知りたくて、調べてみたことがあります。
インヴァ・ムラ(Inva Mula、1963年6月27日 - )はアルバニア・ティラナ出身のソプラノオペラ歌手。父のアヴニ・ムラ(Avni Mula)はコソボ出身でアルバニアの歌手。インヴァ(Inva)の名前は、父親の名前(Avni)を逆に読んで付けられた。デビュー間もなくは夫の名チャコ Çakoを読みやすくしたTchakoも併記していたが、96年頃から使用しなくなった。イタリア・オペラの出演が多いことからか、日本ではインヴァ・ムーラとイタリア風な読み方もされるが、特に音引きは必要ない。
この歌の部分の、80%は彼女が実際に歌っているというから素晴しいです。
彼女のソプラノ、クラシック、ベルディの「リゴレット」でも聞けます
このような基本があるので、あのフィフスエレメントに、つながるのだと思います。
それにしても、ブルース・ウィルスは素晴しいですね。
大好きです。どの映画を見ても、実に存在感を感じさせてくれて、画面がピシッとひきしまるというか、味のある画面にしてくれます。
◎資料から
ウォルター・ブルース・ウィリス(Walter Bruce Willis, 1955年3月19日 - )は、ドイツ生まれのアメリカ人俳優であり、プロデューサー、ミュージシャンでもある。彼のキャリアは1980年代から始まり、それ以来コメディ、ドラマ、アクションといったジャンルで、テレビと映画の両方で活躍している。『ダイ・ハード』シリーズの主人公ジョン・マクレーン役でよく知られている。他にも60作品以上に出演し、『パルプ・フィクション』(1994年)、『12モンキーズ』(1995年)、『フィフス・エレメント』(1997年)、『アルマゲドン』(1998年)、『シックス・センス』(1999年)、『アンブレイカブル』(2000年)、『シン・シティ』(2005年)、『森のリトル・ギャング』(2006年)、『RED/レッド』(2010年)のように興行的成功を収めた作品も多い。
彼は2度エミー賞とゴールデングローブ賞を受賞し、4度サターン賞にノミネートされた。ウィリスはデミ・ムーアと結婚し、2000年に別れるまでに3人の子供をもうけた。現在はモデルのエマ・ヘミングと結婚しており、1人の娘が生まれた。左利き。身長183cm。
ミラ・ジョヴォヴィッチが、この映画で、デヴューしたことも印象的ですね。
話しがすこし、それました。
この「「ラジュテ」
詩的SF。
一枚のファッション雑誌に出てくるような美しい(残酷な)写真が、手作業で、編集されています。
ナレーションがリアルで、第三次世界大戦のパリを表現しています。
ただ、イメージだけの画像の連続で、未来の地球を救うために過去にエナジーを持って帰るためにも、過去についての強烈なイメージを持っている男を選んで、タイムマシーンで過去に送るというテーマは苦しいかもしれない。
とにかく、画像が強烈なために、いろいろなことを考えることができる妙な映画とも言えますね。
なんだかんだ言っても、飽きずに見れました。
63年のトリエステのSF国際映画祭グランプリ、ジャン・ヴィゴ賞受賞しております。
1971年に、時計じかけのオレンジの制作発表されていますから、やはり、影響を受けていると思いますね。
ラ・ジュテ[ビデオ]/著者不明
¥3,990
Amazon.co.jp
つぎなる大好きな映画は 「しあわせの隠れ場所 」 サンドラ・ブロック & キャッシー・ベイツ
この映画のなかにでてくる、
キャッシー・ベイツいいですね。
スチーブン・キングの「ミザリー」は彼女の最高傑作でしょう。
「ミザリー」
大衆向けロマンス小説「ミザリー・シリーズ」の作者である流行作家のポール・シェルダンは、「ミザリー・シリーズ」最終作に続く新作を書き上げた後、自動車事故で重傷を負ってしまう。そんな彼を助けたのは、ポールのナンバーワンのファンと称する中年女性アニー・ウィルクスだった。看病といいつつポールを返さず、拘束・監禁するアニーは、次第にその狂気の片鱗を垣間見せ始める。そんな時、「ミザリー・シリーズ」最終作が発表されるが、内容が自分のイメージと違うと書き直しなど無理難題を付けはじめ、ポールも彼女の狂気に気づき脱出を試みる。
2009年公開。
しあわせの隠れ場所
The Blind Side
監督ジョン・リー・ハンコック
製作総指揮ティモシー・M・ボーン
モリー・スミス
アーウィン・ストフ
製作ブロデリック・ジョンソン
アンドリュー・A・コソボ
ギル・ネッター
脚本ジョン・リー・ハンコック
出演者サンドラ・ブロック
ティム・マッグロウ
クィントン・アーロン
キャシー・ベイツ
音楽カーター・バーウェル
2009年のNFLドラフト1巡目でボルチモア・レイブンズに指名されて入団したマイケル・オアーの実話とある。
まさに奇跡好きのアメリカ人好みの映画。今、ハリウッド映画はワンパターンだから嫌いという人が増えていますが、このワンパターンがまたたまらないし、そこにこそ、ヒット作の本質も垣間見えるわけで、勉強になります。日本で言えば寅さんや水戸黄門たみいなものでしょうからね。
「はなのすきなうし」のイメージを持つマイケル。寒い夜に、ひとり家もなく体育館で寝泊まりする巨漢の黒人の男の子を見るに見かねて家につれて帰るサンドラ・ブロックことリー・アン・テューイ家族。
ちょいと作り物的な感じはあるが、勇気のある家庭である。途中、銃を持つヤクの販売人でもあるマイケルの昔の悪友などにからまれても、毅然と「彼をおどすことは私を脅すこと。私は全アメリカライフル教会に入っていていつでも銃をぶっぱなせるわ」と啖呵をきるような女でなければ、法的な後見人にはなれないだろう。
見ていて疑問は数々出てくるが、きちんとのめり込んで楽しめた。
というのは、サンドラ・ブロックの演技が実に切れ味があり、さわやか。深みには欠けるような気もしないではないが、強い気性を渋く押さえた演技と見る。
この映画を見ながら以前書いた記事を思い出していた。
ピレシュの逸話で有名なのが、彼女が娘が出産をしてその孫が寝ているとなりのベッドに、同じ頃に生まれた黒人の男の子がいた。
もうすぐ孤児院に入れられると聞いて、一晩考えた末に、ひきとることにしたと言う。
50歳を過ぎてから赤ちゃんを育てるなんてなんとすごいことですかネ。
「でもほおっておけなかった」そうビレシュは言うんです。
彼女は今の世界では人気者なので世界のどこの国でも行くが、必ずこの男の子、クラウディオ君を連れて行く。
そして、ホテルではなくて、アパートを借りてもらうのが条件だというのですから、なぜならば、少しでも家にいるような雰囲気で育てたいからだと言うのです。・・・
ピリスは、クラシックを聞くように教えてくれたtakatakaさんから教えてもらったピアニスト。一番好きなクリップは、これ。
・・・・・・・・・・・
アメリカでは、このような里子というのか、制度がしっかりしているようだ。
聞いた話でも、黒人の子供だけではなく、韓国、中国などの子供達を自分の生んだ子供と一緒に育てると言う。うがった見方をすれば白人の有色人種に対する優越感をくすぐるためだとも考えることもできなくないが、やはり、実際に里子を育てている人が日本に比較すると問題にならないくらい事実いるわけで、このようなことはそんなたわいもない理由ではできそうもない。
やはり、良い意味でのキリスト教的な慈善の流れのひとつではないかと私は考えている。そして、素直に私はすごいと思う。
が、もともと神の概念もなく、真の意味でのヒューマニズムも育っていない日本ではたぶん無理な制度だとも思う。
そんな私の疑い深い心をひっくりかえすくらいにこの映画の粗筋は感動的だ。
実に、子供が生き生きと描かれている。マイケルを兄と慕うチビちゃんもユーモアを誘うし、年頃でむづかしい年代でもある姉の娘もまたのびのびとした良い子。
それにしてもこの映画の中、父親の父権というものがあまり感じられないのはおもしろい。ニューヨークみたいなところをのぞけば、アメリカは良い意味での父権制がまだまだ強い筈だが、実に妻をうまくのせ、主人公にしながらも陰で応援するまるで日本人の父親みたいな男をテイム・マッグロウが好演している。(アカデミーとゴールデンブローグ賞を取ったサンドラ・ブロックや、途中から出て来て私はびっくりしたのだが、あの「」に出ていた個性俳優のキャッシー・ベイツほどではないが・・)
黒人の差別の問題、ホームレス、白人中心の教育制度、先生たちを含む偏見の目、フットボールチームにおけるモチベーションの問題、大学入試における家庭教師、さまざまなる問題があるが、サンドラ・ブロックことリー・アン・テューイは悩み考えながらも、ひとり、突き進んで行くのが実にカッコいいですね。
金持ち付き合いの友人から「彼はあなたによって変わったか?」と聞かれて、はっきりとサンドラ・ブロックことリー・アン・テューイが、「いや、私が変わったのよ」と実に自分がよくわかっている。
ここらあたりも思うのは、確かに里子制度はむづかしいし、へ理屈をつけてそれを避難するのも簡単だが、もっと現実的に考えてみると、このサンドラ・ブロックことリー・アン・テューイの四人家族はもともと幸福だったのだが、新たに黒人の少年マイケルを家に招き入れることによって、さらに幸福になる鍵を得たのだ。
そして、マイケルもまたやわらかいベッドで寝ることができ、三度の食事と風呂に入ることができる。
ほんとうはこれだけでもシステムはうまくいっている筈だが、しかしながら、人は無償の愛をもとめてしまうのだから、物語はまた違う展開となっていく。・・・・・
<ヒント>
● 皆がテレビを見ながら行儀悪く食事をする習慣も、マイケルがひとり小さくきりとったパンと、少しのサラダだけを皿についで、テーブルで行儀よく食しているではないか、と。気づいた彼女が偉いということだろう。
● 85店舗も店を持つバリバリの経営者である夫。それを支える知的で敬虔なる妻。素直でのびのびとした二人の姉と弟。豪邸に、BMW。誰から見ても幸福そのものの家族が、さらに変容していくのだった。
●マイケルが最後にママに甘えるようにして、「もしも自分が食堂の店員でもいいのか」と聞くシーンがあり、心に響いた。
誰しもが無償の愛を求めているのだ。
●キャッシー・ベイツの家庭教師のシーン。「奇跡の人」のアンバンクロフトの演技を思い出す。子供がやる気をだすまでが大変なのだ。単に記憶だけをさせようと必死になっても無駄。その子の一番のびる部分をしっかり見て行く。マイケルの場合は、「守る」こと「保護本能」の才能が異常に強いということだった。<母親から無理矢理はなされたりしたことなどがあるのだろう。過去の記憶のフラッシュバック>
●最後のどんでん返しのチェック。ミシシッピー大学に入ったことの理由を咎められて、マイケルは疑いの結晶作用に陥る。だがそれもまた、恋愛においてマイナスの疑いの心がさらなる恋の炎を強くする作用と同じである。
ここのシーンはしかしながら意味不明のところも多い。
●運転免許にトラック。これはやりすぎか?
●図書館における姉がマイケルの机に来るシーン。
●クライマックスのフットボールのシーンは少し迫力がなかったかも。
●言葉の問題。コミュニケーションの問題。心が落ち着き、自分に自信がつき、勇気を持つ習慣が出来、、始めて信頼関係のあるコミュニケートができるのでは。
しかしながら。
このサンドラ・ブロック。
この映画「ゼログラヴィティ」の彼女も圧巻。
個人的には、数回も見ました。
素晴しい。「インターステラ」との比較もしてみました。
サンドラ・ブロック=ゼログラヴィティ
アン・ハサウェイ= インターステラ
ということですね。
この「インターステラ」、昨年の五月に見た、グラヴィティとのシンクロもある。
こまかな映像のテクニックよりも、今のこの時代、SFよりも生な現実が突き進んでいるという恐ろしい世の中で、あえて、SFに挑戦して映画をつくるというのも、すごいことだと思う。
◎次元のイメージのつくりかたが面白い。
◎本とチリのイメージのはさみこみかたが上手い。
◎ブラックホールとワームホールなどのこむづかしい理論の説明よりも、映像でずばり
魅せてくれるのが、好き。
◎ラストシーンはかなり好きだ。
◎かなり2001年宇宙の旅からの、キューブリックからのオマージュともいえる画像が多いけれども、それが嫌みではなくて、素直に楽しめる。
◎小林秀雄氏が言うまでもなく、自己犠牲というような言葉が素直に受け取られる時代がなくなれば、もう人類はおしまいだと思う。「我」や「個」が、われさきに、自己主張だをするような時代や国に、未来はない。
◎ もっとこのようなタイプのSFを見てみたい。もちろん。エイリアンものも楽しめるけれども、科学の現実に裏打ちされているかのような真摯な映像は私の好みだ。
(真に裏打ちされていなくても良い。ニュアンスが上手く出ていれば良いと思う。わかりやすいというのも、すごく大切だから。)
◎基本、「この地球」よりも、素晴らしい惑星はないんだという結論が、くりかえしくりかえし、どのシネマでも語られる。実際にそういうことなんだろうと思う。ワーグナーの音楽が印象的だった、地球最後の日をテーマにした作品でも、そのことを強く言葉で印象づけていたことを思い出す。
◎資料
上記のような「インターステラー」に登場する科学的なフレームワーク、特にブラックホールに関する点などは理論物理学者、キップ・ソーンの監修で作られています。
キップ・ソーンはカリフォルニア工科大学の有名な教授であっただけでなく、カール・セーガンが「コンタクト」を執筆した際にワームホールについての情報を提供したことでも知られています。
「インターステラー」が「2001年宇宙の旅」「コンタクト」の伝統に名をつらねた映像表現を試みていることを考えると、昔からの宇宙ファンは胸が熱くなるわけです。私個人は1991年のTVシリーズ「The Astronomers」でキップ・ソーンが登場していたのを覚えている年代で、それをみて物理を専攻しようと思ったのでなおのこと思い出深い流れです。
キップ・ソーンの今回の映画での貢献は、作中では「ガルガンチュア」と名付けられている弱い、しかし回転するブラックホールの重力についての計算や、その周辺での光のねじ曲がり方についてです。
特に通常のレイトレーシングでは光は直進することが仮定されているのですが、ブラックホール周辺ではその前提が崩壊してしまうためにまったく新しい計算手法を用いる必要があったそうです。
これら「インターステラー」の背景となっている科学についてはキップ・ソーン自身による「The Science of Interstellar」が発刊していますのでぜひこちらもどうぞ。また、”Black Holes & Time Warps”も、いまでも読み物としてとても楽しめます(邦訳は絶版のようですが)。
◎資料
映画「インターステラー」の筋を支えているさまざまな宇宙的な現象は、概ね実際に理論で知られているものです。
ブラックホールは有名ですが、空間と空間のあいだに近道をつくるワームホールも、実際に観測されたことはないものの一般相対性理論の解に含まれていることが知られています。
「ホール」がふたつあるので混乱しそうですが、ブラックホールは質量が大きすぎるために光さえも抜け出すことができない天体のことを指しています。この光が抜け出せなくなる境界部分は「事象の地平線」と呼ばれていて、この平面から外側には、内部の情報はぬけだせません。これが映画の筋に大きくかかわる知識ですので、ブラックホールについては読んでおいてもいいでしょう。
ワームホールは時空のある場所とある場所をつなぐトンネルのような抜け道で、それが使えれば光よりも速く移動することができるとされています。紙、すなわち2次元の平面をたたんでから鉛筆で穴をあけると、紙のある場所からある場所に通り道を作ったことになりますが、これに似ています。
もっとも、三次元における穴ですから、球形の穴をしていて、その向こう側には宇宙の別の場所が広がっているということになるわけです。この仕組はカール・セーガンの「コンタクト」でも用いられています。
「インターステラー」においてはブラックホール周辺や、ワームホール周辺の光のねじ曲がり方も、なるべく正確になるように計算が行われていますので、奇妙な風景にも理屈があると思ってみるといいでしょう。
傑作と好きな映画は違う。
たとえば、「シェーン」は傑作だろうが、私はあまり西部劇は見ない。
逆に、「愛は限りなく」というB級イタリアカンツォーネシネマは私の好きな映画のナンバー1。
昔夢中で見た、「宇宙家族ロビンソン」もまた、そういう映画のひとつ。
そんなように、人それぞれ、好きな映画があるのだと思う。
好きな映画とは、何回も何回も見たくなり、また、見てしまう映画である。
ところで、傑作でありながら、大好きな映画というのもあり、私の場合は、
「2001年宇宙の旅」や、「ブレード・ランナー」や、「惑星ソラリス」や、「コンタクト」というシネマがそれらにあたる。
私が男性だからか、すべて、SF映画。
サラリーマン時代は、日々の人間関係のしがらみやら、煩わしい細かなストレスなどから逃れるためにだろうか、科学についての本を読み、広大で巨大なる宇宙について想像をすることが一番の楽しみだった。
傑作でもある、たとえば、「ドクトル・ジバコ」などの映画を見たりして、ロシアの当時の、時代考証の衣装やら、食べ物やら、建築などにイマジネーションを羽ばたかせ、素晴らしい映像と音楽に身をゆだねるというのも、楽しきひとつの映画のジャンルでもあるけれども、SF映画というのは、「人類の夢」を、ある意味叶えるというよくも悪くもimaginationの極地ともいうべきものであり、映像とアイデアが必須なので、なかなか、傑作はできない。
これまで、たくさんのSF映画を見てきたけれども、ほとんどが、ガッカリしてしまうことも多い。
だったら、大好きなフレドリック・ブラウンの小説を珈琲でも飲みながら読んでいる方がずっとまし。
ところが、この「ゼロ・グラブィティ」。
脳は「新しいもの」が大好きだということを裏書きするように、脳にビンビン、刺激を与えてくれる。それもまた、ただの最近のはやりの効果効果だけの、画面づくりではなくて実に美しい。
私はいつも書いているように、閉所恐怖と、高所恐怖の毛があるうえに、目眩恐怖でもあるので、この映画の中でのサンドラ・ブロックのようにぐるぐると、あんなに高いところで、たったひとりで回転したり、息苦しくなるような狭いロケットの部屋の中で、暮らすなんていうことのできない人間だからか、・・・・見ていて、かなり息苦しさを感じてしまいまた、目眩をおこしそうになる。
この監督アルフォンソ・キュアロン。これ一作だけでも、映画史に残るかもしれない。
サンドラ・ブロックも、wikにあるように、「2001年9月11日に起きた米同時多発テロの支援として、赤十字に100万ドルを寄付をした[13]。
2004年に発生したスマトラ島沖地震・津波被害に際し、医療用品にあてるため再び赤十字へ100万ドル(約1億500万円)を寄付した[14]。
2010年に発生したハイチ地震の後、ハイチの首都ポルトープランスでの救済活動を行う国境なき医師団に100万ドル(約9200万円)を寄付した。国境なき医師団を選んだ理由について、「この大惨事に巻き込まれたハイチの人々のニーズにすぐに対応できる方法で寄付金を役立ててもらいたいと考えました」と声明を出した[15]。
2011年3月11日に東日本大震災が発生した際、ハリウッドの俳優の中で真っ先に義援金として100万ドル(約8000万円)を寄付した。のちに当時を振り返り、「幸運にもわたしはそういう支援できる環境にあるから、やるべきことを行っただけ」と行動に至った経緯を明かした。義理の兄弟に日本人とアメリカ人のハーフがいるというサンドラは、自身が行った寄付について「これまで意味をなさなかったお金が、必要とされる場所で理にかなった使われ方をしただけなの。またそれを寄付することで、新たな息吹が目覚めるとも思ったわ」とコメントした。また、「日本人であろうとなかろうと、わたしたちはみんなつながっていると思っている。もし、同じような被害をアメリカが受けたら、日本はきっと同じことをしてくれるとも信じているわ!」と話した[16]。」
イメージからすると、私はこれまで見たなかでは、サンドラ・ブロックのインパクトは、例えば「スピード」とか、
「プラクチカル・マジック」のイメージが強く、さらにいえば、「幸福の隠れ家」の彼女が一番好きなので、wikそのままの、人類愛が深い女性、優しく、情感あふるるという印象だったけれども、
今回の役柄のなかで、その気質をぐっとぐっと、渋く押さえて、ひとりのおんな科学博士に成りきっている。
カール・セーガン博士の遺作でもある、「コンタクト」のなかで、ジョディ・フォスターが演じた理科系女子に通じていて、そこが私の好きなツボになっている。
どんな絶体絶命の逆境におかれていても、なんとか生き抜こうとするまさに「女性の本質=生命力」の化身となりきるところと、赤ちゃんの声や犬の声にふと死んだ娘に会おうと思って酸素を減らしていくシーンなどなど、サンドラ・ブロックの相反するアンヴイヴァレンスな気質を上手に、引き出しているし(冷静と愛のパッション)、それだからこそ、私に不思議な感銘の余韻を与えることができたのだし、彼女サンドラは、結局はすごいあたり役を演じきってしまうことになったのではないだろうか。
「幸福の隠れ場所」と「ゼロ・グラブィティ」をこれから続けて再視聴する予定。
ベストセラーも読まない。
人が読まなくなり、話題にしなくなった頃に、読み始めるへそまがりの私。
このシネマも、その映画の中のひとつであり、それが正確なる感銘を味わえる。
ひとり部屋で休息時間に見ていたが、思わず号泣してしまう。
気がつくと、夢中で、拍手をしている自分がいる。・・・・
日常生活にぼんやりしている人を、美しくも過酷な宇宙空間へ、思いっきり、ひきずりだすような圧倒的な力を有するシネマだ。
傑作でありながら、大好きな映画。これでまたひとつ増えた。
今夜もまた、カール・セーガン博士の「コスモス」をじっくり読みたい。
宇宙は、21世紀に遺された人類最後のイマジネーションの場所でもある。
かつての、冒険家達が、狂気のように地球を探検しまわったように、人類は、これから
数千年もかけて、宇宙のなかに飛び出していくに違いない。
この映画は、その想像を絶するような人類の未来の膨大なる冒険活劇のフィルムのなかの一枚なんだろう。
つらくても仕事は仕事。
やらなければならないのだから絶対に逃げ出すということはアドバイスしないわ。
それは、試練であり、乗り越えないと人は成長できないから アン・ハサウェイ
FIN
少女の妄想・・「15歳、アルマの恋愛妄想」デニーロ「グリフィン家のウェディングノート」
「ブリッジ オブ スパイ」「アメリカン・スナイパー」『ステップフォード・ワイフ』
わたしは、ひとつの問いを突きつけるような映画が好きだ。観客に問いかけ、しかも答えは与えないような映画」 クリント・イーストウッド。
自分で考えなさいと!!!
ここ最近。
見る映画は、あいかわらず、まったく非・体系的。
てきとー。
それでも、ひとつひとつ、どの映画も、知的好奇心をくれる。
そして、お前のすんでいる世界はここなのだと、言ってくれる。私が期待している言葉を。
けっこう
パッと見て、わおっ、おもしろかった・・という映画は、ここ最近、なかった。
たまたま、自律神経のおかしい身体が欲しているのだろうか?
わからないが。しょうがない。
「ステップ フォーワード ワイブズ」
ジョアンナはニューヨークでやり手のテレビ・プロデューサーとして働いていたが、過激な番組が元で辞任させられてしまう。すっかり意気消沈した彼女を気遣う夫のウォルターは、家族のためにコネティカット州のステップフォードに移り住むことを提案。ステップフォードは治安もよく、豊かで大変美しい町だったが、そこに住む女性たち(妻たち)は揃いも揃ってグラマーで貞淑で、あまりに完璧な妻であることにジョアンナは気がつく。
実に、実に、不思議な作品。
ドイツ語で見てもこれまた興味深いです。
Die Frauen von Stepford - Das Workout
ニコール・キッドマンがでているだけで、個人的には、満足してしまいます。

西洋的というかキリスト教的というか。
世界では意外に知られていませんが、フェミニズム運動やら、レズビアンやらホモセクシュアルやらの運動やら宣伝で、日本人の大半が、世界はそんなもんだ、アメリカはすすんでいると、誤解しています。
おおよそ、そのような町といえば、ニューヨークくらいなものでしょう。
その他、大きな都市。
私の友達も何人もアメリカやブラジルにもいますが、
田舎の普通のアメリカ人たちは、かなり封建的らしいですよ。
良くも悪くも、男性と女性の役割がはっきりしていて、保守。
逆にいえば、その保守としての男性女性の役割のあまりの強固さに、辟易している人が、
今や増えているのでしょう。
一時、アホなマスゴミがもてはやした「結婚しない生き方」とか、「子どもを産まないスタイル」やら、自由主義社会ですから、誰がなにを言おうといいのですが、匿名で描かれるマスコミ記事は、
誰も責任を取る人はマスゴミにはいませんから。注意しましょう。
我々、普通の人間は、くだらない情報や、テレビの悪い意味での変人達(良い意味での変人は大好きです)は、あくまで、参考程度に聞くべきですね。
昔は、もう亡くなってしまいましたが、小室直樹さんという評論家がおりましたが、彼の変人ぶりは、まさに、尊敬すべき変人ぶりでした。
勉強のしすぎで、??、よく救急車で運ばれたといいますから、やはり心不全で亡くなったのでしょうか。彼の実際の講演を聞いた事がありますが、天才風というか、世俗的なことにはまったく興味がないという良い意味での学問研究の徒でした。
(彼の著作は、今でも、識者の間では本物の古典として定着しております、たしかに、主婦の目線でという意見も大事でしょうが、あまりにも素人ばかり・・・。自由というよりも、好き勝手な意見ばかりで、つまりません。私は、個人的な意見ですが、複眼的に専門家の意見こそが今重要だと思います。)
人には、聖なるものを求めたいという本能もありますから。
時期がくれば、異性が欲しくなり、時期がくれば、赤子ができ、時期がくれば、そうかんがえなければ生きてはいけないという普通の生活の持つ厳しさがわかるようになるだけです。
それだけのことです。
若い時に感情的になって、家出をしようと、変わった事をしようと、「生活だけが、人を錬磨・陶冶する」のですから。
あせる必要はありません。
・・・・・・・・・・
しかし、この映画゜フォーワードワイブズ」では、
その人生における、陶冶は、まったく無視です。
男の地位があまりにも低くなりすぎてきた(もともと、女の方が優秀なんだからこれはしょうがありません。)
だから、女たちを、自分たちつまり男が理想とするようなAndroid的な妻にしていこうといく壮大なる計画を考え始める人がではじめます。・・・・・・・・・・
個人的な意見を書かせてもらえば、いつも書いていますが、名作ブレードランナーの
あの彼女のようなAndroidならば、そんなことはありえませんが、一緒に暮らしてみたいなとも思うこともありますが・・・・・
ここにでてくる、「理想の妻」たちは、まるで、「痴呆のできそこないのロボットたち」のごとくです。
まったく色気もなければ、神秘もなければ、エニグマもなけれは、・・・・・・。
実は、アイラ・レヴィンの本はまだ読んだことがありません。
「ブラジルから来た少年」は持っています。「ローズマリーのあかちゃん」が、あまりにも、強烈すきで、・・・・何か持った作家だということは理解できます。
しかしながら。
すこし、アイデアとしては、このThe Stepford Wives は、幼稚かも。
1975年のキャサリン・ロスのも見てみたいと思います。
クリップ見つけました!!! 1975年版です。
「卒業」以来、彼女の美しさにはまいりました。・・・・・・・
しかしながら、彼女は、「卒業」と「明日に向かって」しか見ていない私ですから偉そうな事は言えませんが、あまり良き作品には恵まれていないような気も・・・
主な出演作品[編集]
公開年邦題
原題役名備考
1965シェナンドー河
Shenandoahアン・アンダーソン
1966歌え!ドミニク
The Singing Nunニコル
1967悪魔のくちづけ
Gamesジェニファー・モンゴメリー
卒業
The Graduateエレイン・ロビンソン
1968ヘルファイター
Hellfightersティシュ・バックマン
1969明日に向って撃て!
Butch Cassidy and the Sundance Kidエッタ・プレース英国アカデミー賞主演女優賞 受賞
夕陽に向って走れ
Tell Them Willie Boy Is Hereローラ
1970愛のさざなみ
Foolsアナイス・アップルトン
1972大捜査
They Only Kill Their Mastersケイト
潮騒
Le hasard et la violenceコンスタンスフランス映画
1975ステップフォードの妻たち
The Stepford Wivesジョアンナ・エバハート
1976続・明日に向って撃て!
Wanted: The Sundance Womanエッタ・プレーステレビ映画
さすらいの航海
Voyage of the Damnedミラゴールデングローブ賞助演女優賞 受賞
1978ベッツィー
The Betsyサリー
スウォーム
The Swarmヘレナ・アンダーソン
レガシー

The Legacyマーガレット・ウォルシュ
1979謎の完全殺人
Murder by Natural Causesアリソン・シンクレアテレビ映画
1980ファイナル・カウントダウン
The Final Countdownローレル・スコット
1981テキサス殺人事件
Murder in Texasアンテレビ映画
1982シークレット・レンズ
Wrong Is Rightサリー・ブレイク
Katharine Ross Tribute
Tony R
シャドー・ライダー
The Shadow Ridersケイト・コネリー/シスター・キャサリンテレビ映画
1986夕陽のストレンジャー
Red Headed Strangerローリー
199115年目の殺意
A Climate for Killingグレース・ヘインズ
2001ドニー・ダーコ
Donnie Darkoリリアン・サーマン
私の好きなニコール・キッドマンとともに出演している、
ボビー役の、ペッド・ミドラーもまたいいですね。
ジャニス・ジョプリンを演じたこの映画の歌。ヒットしました。
日本でも、たくさんの人が歌っていて、いやされます。
たしかに、世界中で、今でも名曲は作られ続けているでしょうが、ジャニスの曲は、
名曲というか、・・・・・あまりにも、魂に響きすぎるので、祈りのようにも聞こえます。
The Stepford Wives is a 1975 American sci-fi horror thriller film based on the 1972 Ira Levin novel of the same name.[3] It was directed by Bryan Forbes with a screenplay by William Goldman, and stars Katharine Ross, Paula Prentiss, Peter Masterson, Nanette Newman, and Tina Louise.
While the film was a moderate success at the time of release, it has grown in stature as a cult film over the years.[4] Building upon the reputation of Levin's novel, the term "Stepford" or "Stepford Wife" has become a popular science fiction concept and several sequels were shot, as well as a remake in 2004 using the same title, but rewritten as a comedy instead of a serious horror/thriller film.[5]
ステップフォード・ワイフ 1975アメリカでのSF ホラー スリラー映画 1972に基づいて、 アイラ・レヴィンの小説同じ名前の 。[3]それは、によって指示されたブライアン・フォーブスと脚本によってウィリアム・ゴールドマン 、と星キャサリン・ロス 、 ポーラ・プレンティス 、 ピーターマスターソン 、 ナネット・ニューマン 、とティナ・ルイーズ 。
フィルムは、リリース時に適度な成功を収めましたが、それはのように身長で成長してきたカルトフィルム年間の。[4]レヴィンの小説の信用に対して建物、用語「ステップフォード」または「ステップフォードの妻は"となっています人気の空想科学小説の概念といくつかの続編を撮影し、同様にしたリメイク同じタイトルを使用して、2004年には、しかし、喜劇の代わりに深刻なホラー/スリラー映画のように書き換える。[5]
『ステップフォード・ワイフ』(The Stepford Wives)は、2004年製作のアメリカ映画である。フランク・オズ監督。
1975年に製作されたハリウッド映画『ステップフォードの妻たち』のリメイク。原作はアイラ・レヴィン。
ジョアンナはニューヨークでやり手のテレビ・プロデューサーとして働いていたが、過激な番組が元で辞任させられてしまう。すっかり意気消沈した彼女を気遣う夫のウォルターは、家族のためにコネティカット州のステップフォードに移り住むことを提案。ステップフォードは治安もよく、豊かで大変美しい町だったが、そこに住む女性たち(妻たち)は揃いも揃ってグラマーで貞淑で、あまりに完璧な妻であることにジョアンナは気がつく。
死の接吻(A Kiss Before Dying, 1952年)
ローズマリーの赤ちゃん(Rosemary's Baby, 1967年)
◎この映画はホラーと言われていますが、
独特の悪魔学のセンスがしゃれていて、不思議と忘れられない名作になっています。
いわゆるキリスト教の国の映画ですから、ある意味道徳映画にはちがいないですが。
サドが、道徳であるように・・・・・・・
この完全なる時代(This Perfect Day, 1970年)
ステップフォードの妻たち(The Stepford Wives, 1972年) - 映画『ステップフォード・ワイフ』原作
ブラジルから来た少年(The Boys from Brazil, 1976年)
ローズマリーの息子(Son of Rosemary, 1997年)
硝子の塔(Sliver, 1991年)
◎この硝子の塔も、印象強いです。
この現代であれば、どこにでもあるプライバシーの侵害の映画なのですが、
1991年ですから、25年前に予告されていたというわけですね。
ここでは、敬愛する淀川長治さんに、語ってもらいましょう。
ひとつの映画が、何倍も何倍も、面白くなる筈です。
Deathtrapは、まだ見ていませんが、ここに記録しておきます。
「アメリカン・スナイパー」
クリント・イーストウッドについては、たくさん描きたいことがありすぎます。
いつか、彼についてのこれ迄見た映画をまとめたいといつも思っていますが、
とにかく・・・・・・・・・気がついたら、疲れ果てて、寝ています。・・・駄目ですね。
映画をひとつの政治的偏見で見るのはもったいない。
ここには、実に多くの戦争そのもののイメージがあり、
途中で何回も、見るのを止めながら見た。涙も出た。
「アメリカン・スナイパー」
戦争を賛美せず、かといって、自国を襲うテロリスト達に立ち向かうカレルの勇気を
無視するわけにもいかない。
しかしながら。
結局のところは、歴史のなかで、人類は、こうやって、自分たちの正義=神のために、相手達の異端の神=不正義、と、戦ってきている。
まさに、人類がかかえた悲惨な業である。
この映画が誰でもが知っているように、実話であることもまた、作品を重くしている。
アメリカでは、賛否両論がくりひろげられたという。当然のことだろう。
よく、戦時中の人達は国に騙されて洗脳させてうんぬんと、・・・偉そうに評論する輩がいますが、このような連中にかぎって、上目視線で、自分たちの意見にそぐわない人達を排除しようとするのは、左巻き思想の特異技。
家族は家族の利益のために、会社は会社の利益のために、国は国の国益のために、
必死に、一丸となって、生き延びて行く、・・・・・・・そんなあたりまえのことが、わからない人が、多いですね。
この映画を見ていると、ほんとうに「歴史が泣いている」という意味が、切実に、感じられます。
(そして、命が一番大切と言っている人、たとえば学校の先生などに、かぎって、「いじめ」の現実に鈍感というのは不思議です。
「いじめ」問題がおこって、少年少女が犠牲になると、例のごとく、アホな教育委員会や校長が、その無表情の仮面のような顔で、お詫びをしつづける。
命が一番大切です。・・・・・そればかり言う人。
その人にとっての、命は、自分の命だけが大切であって、他人の命には無関心なのです。)
理想論や、きれいごとなどは、言葉だけだったら誰にでも言えることです。
自分以外の人達のために、ふんばれる。
私はそんな人になりたいといつも考えます。
三島由紀夫は、そのようにして、「命以上に大切なものがある」と言って、切腹しました。
飽食ざんまいの、惰眠を貪っている現代人に、彼を、批判する権利などありません。・・・・
よく人間を性善説とか、性悪説とか、簡単にわけることが一時、はやりましたが、人生そんなにシンプルではないでしょう。
この善と悪はともに人の心の奥の奥に誰にでもひそんでいるものです。
問題は、そのパンドラの箱の重要性を考えもせずに、無意識に悪の蝶を好き放題に飛ばしてみたりする人がいることですね。
また逆に、この箱のなかにあるsomthingを忍耐しながら、コントロールしようとする人。
そんなこむずかしい問題を「人間の建設」をよみながら、そこにでてくる「無明」という言葉も連想しながら、かんがえていた今日このごろ。
体調はあまり良くないのですが、
札幌に家人と行く機会があり、大好きなトム・ハンクスの「ブリッジ・オブ・スパイ」を
大きな画面で、見るチャンスがありました。
冷戦時、人々は核戦争の恐怖や、まだ記憶が生々しい世界大戦が再び来るのではないかという恐怖におびえていた。そのため、ドノバンがもし失敗すれば世界が再び戦火に包まれると考える者や、彼の行動を阻止しようとする者が現れる。しかし、彼は自らの信念を曲げず、苦悩しながらも、戦争の可能性を取り除き、人命を救助するために懸命に行動する。彼に与えられた交渉の舞台は、ドイツのベルリンにあるグリーニカー橋。彼は交渉を成立させ、戦争の危機を回避できるのか?
本作は、これまでのスピルバーグ作品同様、全編が35ミリフィルムで撮影されており、予告編でも陰影に富んだ重厚な映像も堪能できる。
しかも。
あの冷戦時代でしたから。
わたしなぞも、大学時代から、アメリカとソ連が核戦争を起こすということが、今から見ると想像もできないくらいに、現実的に思えた時代でしたから、いつも、暗い気持ちで「核で終わる地球の最後」の日のことをよく考えていました。
淀川長治さんが、スピルバーグくらいの力があるのであれば、獲ろうと思えばアカデミー賞は獲れるんだけども、それが見え見えだから、この映画は嫌いだと言っていた「シンドラーズリスト」を私は連想しました。(実際にアカデミー賞を初めて彼はとりました。)
冷戦時代で思い出す映画といえば・・・・・・・
『ファントム/開戦前夜』(ファントムかいせんぜんや、Phantom)は2013年のアメリカ合衆国の戦争映画。 東西冷戦下にあった1968年に、ソ連(当時)の潜水艦K-129(英語版)が通常の作戦海域を大きく逸脱した末にハワイ近海で謎の撃沈を遂げた事件を題材にしている
あとは、死を覚悟して、放射能を浴びる映画を描く軍人の覚悟を描いたこの映画をいつも思い出します。
これは傑作でしょう。
「K19」 ハリソンフォードは実に軍服が似合います。
米ソ冷戦下、ソ連の原子力潜水艦K-19は航行実験において、突然原子炉の冷却装置に故障をきたした。原子炉のメルトダウンも考えられた危機的状況に対して立ち向かう艦長(フォード)と放射能の危険と隣り合わせで修理に奮闘する搭乗員の活躍を描く。
トム・ハンクス、いいですね。
資料を見ると、
映画のプロモーションでは数回来日しており、近年では『ポーラー・エクスプレス』、『ターミナル』、『ダ・ヴィンチ・コード』プロモーションで、それぞれジャン・レノやロバート・ゼメキス監督らと共に来日している。『ポーラー・エクスプレス』の来日でインタビューを受けた際には、タイプライター集めに凝っていると語っていた。また、自身が監督も務めた『すべてをあなたに』の来日の際には、出演者らと共に日本テレビ系の歌番組『THE夜もヒッパレ』にゲスト出演。ハンクスはその際に歌も披露した。2009年5月に『天使と悪魔』のプロモーションのために、プロデューサーのブライアン・グレイザー、監督のロン・ハワード、そして共演のアイェレット・ゾラーらと来日した際には、東京ドームで行われた巨人対中日戦の始球式に登場した。そして、監督である原辰徳との対面も果たした。
私生活
サマンサ・ルイスとの間に1977年11月、現在俳優として活躍するコリン・ハンクス誕生。翌年、サマンサと結婚[7]。1982年、長女エリザベス誕生[8][9]。1987年、離婚。1988年、リタ・ウィルソンと再婚。2人の子供をもうける。
エイブラハム・リンカーンと遠縁である(リンカーンの母親ナンシー・ハンクス(英語版)の曾祖父の兄弟がトム・ハンクスの先祖、8代前)[10]。
民主党を支持しており、2008年の大統領選の際にはバラク・オバマを支持した[11]。
『幸せの教室』で共演しているジュリア・ロバーツとは長年の友人で、家族ぐるみの付き合いだという
「Bridge of Spies」
たしかに、これは、恋人たちと一緒に、わいわい、楽しむ映画ではないけれども、
無名のひとりの弁護士が、その想像力を駆使して、あの冷戦時代に起こりうる様々なる
生涯を、不屈の闘志というか、フレキシブルな思考によって、大胆なる人質の交換を成功させるというたしか実話である。
「ノーカントリー」で、アカデミー賞を獲得した、さすが、ジョエル&イーサン・コーエンの脚本だけあって、
レヴューを見ても、地味な映画ではあるが、
高い評価がめだって、嬉しくなった。
参考資料
「ノーカントリー」
2013/07/11 に公開
"荒野で狩をしていたベトナム帰還兵のモ は、偶然ギャングたちの死体と麻薬絡みの大金200万ドルを発見。 その金を奪ったモスは逃走するが、ギャングに雇われた殺し屋シガーは、邪魔者を次々と殺しながら執拗に彼の行方を追う。事件の発覚後、保安官のベルは二人の行方を探るが、彼らの運命は予測もしない衝撃の結末を迎える。
「ブリッジ・オブ・スパイ」ひさびさに感動した。淀川長治さんなら、どう、解説するだろうか。
それを想像しながら、寝るとしましょう。
「ウェルカム・トラブル!!!! 苦労よ、来い!! 」
「苦労がない人は駄目だよ・・・」
淀川長治
トム・ハンクスの演技の重厚さ・味、そんなものを見ているうちに、淀川さんの言葉を連想した。
FIN
◎資料には、全米長寿バラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』や、『スプラッシュ』『メイフィールドの怪人たち』『ビッグ』といった軽妙なコメディ映画を得意とする若手コメディアンとして活躍していた、とある。
カリフォルニア州コンコード生まれ。父親は料理人、母親は病院職員。両親は1960年代に離婚し、トムは兄ラリー(現在は昆虫学者)と姉サンドラ(現在は著述家)と共に父親の元で育つ。末っ子の弟ジムは母親の元で育った。
カリフォルニア州ヘイワードのChabot Collegeで演劇を学んだ後、カリフォルニア州立大学サクラメント校に編入。
1979年にニューヨークに移り、翌年『血ぬられた花嫁』で映画デビュー
とあるので、日本のたけし、ではないけれど、コメディアンとしての、独特のユーモラスな、それでいて、奥のある懐を感じさせる情愛をもかんじさせる良き俳優だと思う。
貴重な彼のこの映画についての、インタヴュークリップがありすので、ここにコレクションしておきます。
「ブリッジ・オブ・スパイ」インタヴュークリップ
・・・・・・・・・・・・
スティーヴン・スピルバーグ監督、マット・チャーマン(英語版)及びコーエン兄弟脚本による2015年のアメリカ合衆国の歴史・伝記・ドラマ(英語版)・政治(英語版)・アクション・戦争・スパイ(英語版)・スリラー映画である。出演はトム・ハンクス、マーク・ライランス(英語版)、エイミー・ライアン、アラン・アルダらであり、U-2撃墜事件でソ連の捕虜となったフランシス・ゲーリー・パワーズの解放のために動く弁護士のジェームス・ドノバン(ハンクス)が中心に描かれる[1]。
題名の『ブリッジ・オブ・スパイ』とはスパイ交換が行われたグリーニッケ橋を指す。
撮影は『St. James Place』というワーキングタイトルで2014年9月8日よりニューヨーク市ブルックリン区で始まった。北アメリカではタッチストーン・ピクチャーズ、それ以外では20世紀フォックスの配給により公開される
◎ニコール・キッドマン
生い立ち[編集]
アメリカ系オーストラリア人の両親のもとにハワイ州ホノルルで生まれたため、アメリカ合衆国とオーストラリアの二重国籍である。4歳でオーストラリア・シドニーに戻った。3歳下の妹にアントニアがおり、アントニアはオーストラリアでテレビ番組のプレゼンターをしている。
4歳からバレエを習い始め、Australian Theatre for Young Peopleで発声や演劇史を学ぶようになる。
キャリア[編集]
カンヌ国際映画祭にて(2001年)
15歳からテレビやミュージック・ビデオなどに出演、映画にも出るようになり、オーストラリア映画で実績を積む。1988年に出演した『デッド・カーム/戦慄の航海』を偶然目にしたトム・クルーズに招かれてハリウッド入りし、『デイズ・オブ・サンダー』で共演、1990年に結婚した。
ハリウッド進出当時は、当時の夫であり、ハリウッド進出に導いたトム・クルーズ夫人としての側面が強く、いわゆる型どおりの美人女優として平凡なキャリアに甘んじた。しかし2001年にトム・クルーズとの離婚を機に、充実したキャリアを開花させ、以降、アメリカを代表する演技派女優として変身を遂げた。キッドマン自身離婚後、「いままでは結婚生活というものが、私にとって一番優先することだった。でも、いまの私には、仕事と子供たちしか残されていない。独身になったから、女優として成長できる時期だ、というふうには思わないけれど、確かに、演じたいという情熱は結婚していたときよりも強くなった。」と語っている[1]。
2001年公開の『ムーラン・ルージュ』でゴールデングローブ賞(ミュージカル・コメディ部門)を受賞。2003年公開の『めぐりあう時間たち』では、特殊メークによる付け鼻で完全に自らの容姿を隠し、ヴァージニア・ウルフを演じきり、アカデミー主演女優賞やゴールデングローブ賞 主演女優賞(ドラマ部門)などを受賞した。
2004年には日本をはじめ世界各国で放映されたシャネルの香水「No.5」のテレビコマーシャル(監督:バズ・ラーマン)に出演し、120秒(一部の国では240秒)という異例の長さのCMに注目が集まった。また、出演料も破格であった。現在はオメガの顔として広告に出演している。
映画1作品の出演料が高額なことで知られており、2006年には「最も出演料の高い女優1位」となる[2]。
2007年1月、アメリカの経済誌『フォーブス』がエンターテイメント界で活躍する女性で資産の多い女性トップ20を発表し、ニコールは総資産72億円で18位にランクインした。
2008年の『フォーブス』誌では高額なギャラ相応の興行収入が稼げないことから、「コストパフォーマンスの悪い俳優1位」になってしまった[3]。
2010年の映画『ラビット・ホール』の演技によって再び評価を高め、アカデミー主演女優賞をはじめとする多くの賞にノミネートされた。
2012年のテレビ映画『私が愛したヘミングウェイ』では、文豪ヘミングウェイの3番目の妻マーサ・ゲルホーンを演じた。この演技が絶賛され、プライムタイム・エミー賞をはじめ数々の賞にノミネートされた[4]。
2015年、ロンドンのウエストエンドで舞台『Photograph 51』に主演し、「Evening Standard」紙の演劇賞で最優秀女優賞を受賞した[5]。
集合的無意識 ユング「危険なメソッド」「戦慄の絆」「ダメージ」「ミリオンダラーベイビー」
尊敬する三島由紀夫氏が、マンガ好きとはあまり知られていない。
こんな彼の文章がある。
「いつのころからか、私は自分の小学生の娘や息子と少年週刊誌をうばいあって読むやうになった。「モーレツ・ア・太郎」は毎号欠かしたことなく、わたしは猫のニャロメと毛虫のケムンパスと奇怪な生物ベシのファンである。このナンセンスは徹底的で、かつ時代物劇画に私が求めていた破壊主義と共通する点がある。……(中略)……今の若者は手塚治虫や水木しげるのかういふ浅墓な政治主義の劇画・漫画を喜ぶのであらうか。「モーレツ・ア・太郎」のスラップスティックを喜ぶ精神と相反するではないか。」 ・・・・・・・・三島由紀夫
しかしながら。
彼の絶賛するマンガは、なにより、赤塚不二夫。そして、平田弘史。
これは私にはよくわかる。
白土三平氏の作品は、個人的には、「サスケ」や、「神話シリーズ」はずばぬけておもしろいけれども、「忍者武芸帳」などは、いわゆる唯物史観の歴史の資料の偏向的な視点が臭すぎて、私は好きではない。
手塚治虫氏も、ものすごい博学で、その「物語性」やら、幅広いジャンルのテーマの作品で、
私はそこが一番学ぶことのできるところだけれども、たしかに、三島由紀夫氏が書いているように、深みに欠けるところがあるのは、やはり、歴史をとことん読み込んでいたというよりも、締め切りに追われた人気マンガ家のある意味、欠点なのかもしれない。
水木しげる氏においては、これまた、個人的には、「神秘家シリーズ」と「悪魔君」シリーズは大好きだけれども、彼の戦記物などは、やはり、体験重視すぎて、感情にはしりすぎている感はいなめないと思う。
手塚治虫氏は医者、水木しげる氏は、戦争で右手を失っている体験あたりが、「命」重視の現代の、善くも悪くも、風潮と合うのだろうか。
英霊の魂のことを死ぬ迄考え続けた三島由紀夫氏から言わせるとそのあたりが、少し不満だったのだと思うが、・・・・・・・・・・。
そこへ行くと、赤塚不二夫のスラップスティックは徹底していて、漫画家の漫画家たる突き抜けた存在が、三島由紀夫氏の気に入ったのだと思う。
最近、たまたま、ビックコミックの前身である、ビックゴールドを整理していて、昭和55年発行のカスタム・コミックというマンガ雑誌を発見。
この雑誌を読んでいて、つげ忠男や、長島慎二、諸星大二郎、牧美也子・川崎のぼるなどのほかに、ふと、平田弘史の作品を見つけた。三島由紀夫氏が、絶賛する漫画家である。
圧倒的な線である。「大垣藩治水魂」という作品で、自分の藩の治水に成功した統治者の部下のリーダーと、失敗したリーダーの史実を描いている。
実話だろうが、白土三平氏の忍者武芸帳などと比較すると、頭でっかちにならない、独特の視点から描かれている。

感心した。
ところで、映画、
今日の映画は、「危険なメソッド」。
ずいぶん前の映画ですが、映画は、新しいから良い映画、感銘する映画とは言えません。
古い映画でも、ヒントはいくらでも、もらえます。
あなたが向き合わなかった問題は、いずれ、運命として出会うことになる。 ユング
このクリップです。
私のように、深層心理学やら、無意識やら、専門的に勉強などしてこなかった人間ですら、
なにやら、彼らの本、つまり、フロイトやユングの本を気がつくと、数十冊も持っていて、何かにつけて、辞書のようにひいていることに気がつきます。
小林秀雄氏も、死ぬ迄フロイトの本を愛読していましたし、アーティストの方はユングのファンが多いのではないでしょうか。
私が一番影響を受けた本は、「タオ自然学」というカプラの本ですが、そこにも、仏教やキリスト教の神学の言葉とともに、やはりユングの考え方などの基本みたいなものがよく出て来ていましたから。
アメリカではよく読まれた本らしく、クリップもたくさんあります。
要するに、カントなどの考え方から、いまや、量子理論まで、どんどん哲学や物理学も進化してきたわけですが、そのあたりの、人間の本質を見る目を、物理学と宗教人の言葉を使いながら、説明していて、非常におもしろい本です。
このフロイト、ユングたち、そして、彼らの患者。
基本、患者との付き合いは当然禁止の筈なのですが、それはまるで運命のように、
あらわれてきます。
そのあたりのドラマを描いた映画。
「危険なメソッド」
このザビーナという女性のことについて、興味がわいて、少し調べてみると。
ザビーナ・シュピールライン
ザビーナ・シュピールライン(Sabina Spielrein 1885年11月7日-1942年8月12日)はロシア出身の精神分析家。
ロストフの裕福なユダヤ人の家庭に生まれ育つ。父ニコライは商人、母エヴァは当時のロシアでは珍しい大学卒(歯学部)の女性だった。
ロストフの女子ギムナジウムを経て、1904年8月17日、統合失調症患者としてチューリッヒ近郊のブルクヘルツリ精神病院に入院し、ここで医師として働いていたカール・グスタフ・ユングと知り合い、恋に落ちる。1905年6月1日に退院した後、チューリッヒ大学医学部に入学し、1911年、統合失調症に関する論文を提出して医学部を卒業するまでユングとの関係は続いた。ユングは彼女が学位論文を書くにあたっての助言者だったが、同時に彼自身もシュピールラインから学問的に多大な影響を受けた。しかし既婚者のユングが、彼の子を産みたいというシュピールラインの希望を撥ねつけたため、二人の愛は破局を迎えた。同じ1911年、ウィーンでジークムント・フロイトと会い、ウィーン精神分析学協会に参加。ユングとの恋愛体験に基づく論文『生成の原因としての破壊』は、フロイトのタナトス概念に影響を与えた。
1912年、ロシア系ユダヤ人医師パヴェル・ナウモーヴィチ・シェフテルと結婚し、ベルリンで暮らした。第一次世界大戦中はスイスで暮らしたが、1923年、ソビエト政権下のロシアに帰国し、ロシア精神分析学協会に参加すると共に、モスクワにて幼稚園を設立。なるべく早い時期から子供たちを自由人として育てることを旨とした幼稚園であり、ヨシフ・スターリンが息子ヴァシリーを偽名で入園させたこともあったが、3年後、幼児たちへの性的虐待という冤罪をかけられたため、閉鎖を余儀なくされた。背後には、精神分析学に対するスターリン政権からの弾圧があった。
1936年、大粛清の最中に夫が病死し、シュピールラインと娘たちは1942年に故郷ロストフにて、侵攻したナチの手で殺害された。
2002年、『私の名はザビーナ・シュピールライン』と題するドキュメンタリーがスウェーデンの映画監督エリザベト・マルトンによって作られ、2005年には米国でも封切られた。近年、精神分析学に対する彼女の貢献に関して再評価が進みつつある。
2011年、シュピールラインとユング、フロイトの3者を描いた映画『危険なメソッド』が作られた。
1904年。ロシア系ユダヤ人女性ザビーナが、チューリッヒにある精神病院ブルクヘルツリ(チューリッヒ大学付属病院)へ重度のヒステリー患者として運び込まれた。29歳のユングはこの病院で精神科医として働いていた。精神分析学の大家フロイトが提唱する“談話療法”に刺激を受けた彼は、受け持ち患者であるザビーナにその斬新な治療法を実践する。間もなくユングは、ザビーナの幼少期の記憶を辿り、彼女が抱える性的トラウマの原因を突き止めることに成功する。しかし、医師と患者の一線を越えてしまった2人は、秘密の情事を重ねるようになり、ザビーナをめぐるユングの葛藤はフロイトとの友情にも亀裂を生じさせてゆく[3]。ユングは貞淑な妻よりも遥かに魅惑的なザビーナとの“危険なメソッド”に囚われ、欲望と罪悪感の狭間で激しく揺れ動く。
20世紀の最大の哲学者・心理学者・・・・・・フロイト&ユング。
良くも悪くも、彼らのイメージはこの映画で少し変わるのだと思います。
数学者や哲学者、作家や画家の自伝映画は、ともすると、やや敬遠されることがありますが、
逆ではないでしょうか。
これらの映画を見る事で、親近感を得て、彼らの実際の作品や、研究の結果の論文などに接することがよりスムーズにもなることでしょうから。
ユングについては。
ドイツとスイスに旅した時。
あまりにも、朝のパンとチーズとハムが美味いのにびっくりした。


それ以外の料理などはあまり印象に残っていないのに。
それに、三ツ星レストランを探すような趣味はないので、普通の人が普通に食べているものを食べたかった・・・
それで、普通のホテルの普通の朝ご飯を楽しみにしていて、旅の最初の日がドイツで良かった。ドイツはこれで印象が良くなるわけですから、食べ物は大切。
腕っ節の強そうな丸顔の性格の良さそうな、しかも愛想のない、きりっとしたトルストイの描く農民の娘みたいな雰囲気。
彼女が珈琲を最後に運んでくれた。またそれも美味い。
ふと、彼女の父親はどんな人なんだろうか・・・と考えた。
ドイツ。
旅の印象でも、一番強かったのはここドイツの協会やら、中世から続く町並み、ゲーテの歩いた散歩道、モンサンミッシェルなどやらの宗教関係の寺院や教会。
(ここの記録は旅記録で残してありますが・・・)

モンサンミッシェル、そして、ビーズ教会。その神秘感。
圧倒的な、キリスト教社会。
カソリックやら、プロテスタントやら、いろいろな宗派があるでしょうが、とにかく、
キリスト教関連・・・・
強烈なる二元論。
男と女。
悪と善。
悪魔と天使。
・・・・・・・・・容赦のない分析に、分析に、分析。理論理論理論。言葉言葉言葉・・・
の社会です。
まったく東洋とは違います。
以前。コリン・ウィルソンのユングの生涯は読んでいたので、だいたいの輪郭はわかるけれども、それでも、日本人の河合隼雄氏の書くユングはまた同じ日本人としてわかりやすいです。
父親が厳しいと、そしてまた影響力が圧倒的にあると考えにどんな印を残すのだろうか?
あるいは、逆に母親の影響が圧倒的に強いと、その子供の魂にはどんな印がつくのだろうか?
興味深いです。
フロイトが父親の影響からか「超自我」という考えを生み出し、ユングはその逆で母親からの影響で、「集団的無意識」か。
ユングの母親は、世間話が大好きで、精力的で明るい母親だったらしい。
比較すると、父親の方はまさにユングの造語ではありますが、「内向的」な牧師さんだったということでしょうね。
意識が強い人。
意識的な前頭葉の発達した人ほど、抑圧を無意識に落とし込みやすい。
だからヨーロッパ全体がそのように、文化もふくめて、なってきているところにユングは矛盾や、限界を考えたのかもしれませんね。
以前ブログで紹介した、キューブリックの最後の遺作の「アイズアンドシャット」なんかも、そうかもしれません。関連ヒントブログその1
仮面舞踏会。
そこでは、顔というまさに「日々の意識=自我」を隠して、無意識のままに、時間を過ごそうとする人々が集まるところです。
この映画でも、やはりアジア人である私にはなにやらピンとこないところもたくさんありましたが。
で、その抑圧=セックス。
ユングは、フロイトよりも、セックスだけではないところの、何かを生涯探し続けているところが、21世紀的です。
ここ二三年は、ユングばっかり読んでいますが。
まだまだ、何かをまとめて書こうとするのは無理なような気もします。
それだけ、ユングは、なんだかんだいっても、器が大きい。
音楽で言えば、バッハかもしれません。ユングの生涯とタオ/創元社
¥2,592
Amazon.co.jp
ユングの生涯 (レグルス文庫 100)/第三文明社
¥972
Amazon.co.jp
クローネンバーグ監督といえば、マイナーな作品ですが、
マイフェボリットに、「戦慄の絆」という作品があります。
若い頃に、見て、監督独特のスタイルに酔いしれました。
これもシチュエーションは、ひとりの女性を愛した双子の兄弟のこころの破壊の過程を
描いているところ、監督の好きな、シノプシスなのかもしれません。
◎資料
トロントで産婦人科を開業している一卵性双生児のエリオットとビヴァリーのマントル兄弟は幼い頃から文字通り一心同体で育ってきたが、性格は兄エリオットは社交的で野心家、弟のビヴァリーは内気で繊細な努力家と、全く正反対であった。
ある日、ビヴァリーのもとにクレアという女優が診察を受けに来る。クレアの子宮が3つの小部屋に分かれている事に驚いたビヴァリーはエリオットに相談、エリオットはクレアに子供が産めない体である事を宣告した後、抱き合った。
翌日、クレアは訪ねてきたビヴァリーを彼が双子である事を知らずにベッドに誘う。この事は兄弟の生まれて初めての秘密となる。
そして、この事が兄弟の均衡と境界を崩し、悲劇をもたらしてゆく。
男性原理とは、規律規則であり、女性原理とは、混沌カオスとは、よく言ったものですね。
クローネンバーグといえば、「裸のランチ」でしょうが、「ザ・フライ」という強烈な作品もあります。
『ザ・フライ』(The Fly)は、1986年のアメリカ映画。1958年に公開された同名の映画(邦題は『ハエ男の恐怖』)のリメイク作品。
この監督。なにやら、良くも悪くも、グロテスク趣味があり、好き嫌いは別れると思いますが。
物語は、よく練られていると思います。
よく石森章太郎氏などのマンガに出てくる、テレポート。
これがテーマですが、神をも恐れぬ実験にはリスクがつきもの。
ところで、ユングと言えば。
河合隼雄氏。
日本で初めてのユング学者です。
◎資料から
日本人として初めてユング研究所にてユング派分析家の資格を取得し、日本における分析心理学の普及・実践に貢献した。また、箱庭療法を日本へ初めて導入した。
臨床心理学・分析心理学の立場から1988年に日本臨床心理士資格認定協会を設立し、臨床心理士の資格整備にも貢献した。霊長類学者の河合雅雄は兄(三男)である。
昔は50才で、腰がまがってもう人生は終わり。
坂口安吾も人生50年と確か言っていた。
「人間五十年、下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり。
ひとたび生を得て滅せぬもののあるべきか」
(人間の一生は所詮五十年に過ぎない。
天上世界の時間の流れてくれべたらまるで夢や幻のようなものであり、命あるものはすべて滅びてしまう。)
・・・・・・・・織田信長です。
三島由紀夫も美しく散りたいと47歳で自決し、確か安吾が50歳、夏目漱石もそれくらいで死んだ筈。
ひるがえれば太宰や芥川などは30代で死している。
思うに、作家としての力量と、人生という風や水や火のなかにただ浸されさらされる時間の長さとはあまり関係がないのかもしれないと思っていた。
三島由紀夫氏も、作家の人生などというものは実世界の苦労をしている人と比較すればたいしたものではないと、経験については、謙虚な言い方をする。
ところが、ユング。
さすが、ヨーロッパ。
体力があるというのか、思想界の巨人というべきか。
彼の主立った著作のほとんどが、70歳をすぎてからの著作だと言う。(河合隼雄)
『転換のシンボル』 Symbole der Wandlung, 1912, /1950, GW Bd.5.
『心理学的類型』 Psychologische Typen, 1921/1950, GW Bd.6.
『心理学と宗教』 Psychologie und Religion, 1940/1962 (GW Bd.11).
『アイオーン』 Aion, 1950, GW Bd.5-2.
『心理学と錬金術』 Psychologie und Alchemie, 1944/1952, GW Bd.12.
『ヨブへの答え』 Antworf auf Hiob, 1952/1967 (GW Bd.11).
『結合の神秘』 Mysterium Coniunctionis, 1955/1956, GW Bd.14.
たしかに、身体のほうは50もすぎれば次第におとろえもくるのかもしれなかが、経験や思想の方は、ますます深く、井戸のなかにおりることが可能になってくるのだろう。
死をみじかに感じられるということも井戸に深く深く降りることを可能にするひとつのきっかけ。
「われわれは、人生における芸術家たり得る人は、あまりにも少数の人であり、生きることの芸術はあらゆる芸術のなかでも、もっとも傑出したものであり、稀有なものでもあることを知っていなくてはならない」 ユング
雑に自分の人生をつくることだけはしたくない。
丁寧に手間ひまかけて色を塗って行く事が大事だとおもう。
オスカーワイルドは意地悪にも、作品が素晴らしい人は実人生がつまらなく、作品がつまらない人は実人生は素晴らしいと書いたが、ユングにはあてはまらないようだ。
人間の寿命がのびている時代にはそれなりの哲学もまた必須なのだと思う。
自我と無意識 (レグルス文庫)/C.G. ユング
¥840
Amazon.co.jp
ユング自伝―思い出・夢・思想 (1)/C.G.ユング
¥2,940
Amazon.co.jp
「第十二の予言 決意のとき (聖なる予言)」を読む。
第十二の予言 決意のとき (聖なる予言)/ジェームズ・レッドフィールド
¥1,995
Amazon.co.jp
この本のなかに神秘体験なるものが語られている。
簡単に言うと自然との一体感、自然をまるでみずからのように感じまた自分を自然の一部だと強烈に感じる。エナジーは食をとうして感謝のきもちでゆっくりいただくことでさらに強烈になる。
脳の中で人類の進化が一瞬にして感じられたそうだ。
しかしながら、知識がたんなる知識ではなくて「体験」として感じられるようになるまでは誰しもが苦労するところ。
日本人にはこの感覚は意外にわかりやすいのではないだろうか?
コリン・ウィルソンは「至高体験」とも言う。
あたまにいっぱい心配事やら悩みがつまった状態から、ある瞬間、うっとりとした恍惚の瞬間を味わうことがあることを指す。
それは特殊なコト、経験ではなくだれしもが、生活の枠のなかであくせくしないで、自らの身体と心の状態をリラックスされていれば経験されることなのかもしれない。
ここ最近、河上徹太郎氏と小林秀雄氏の対談を読んでいたが、メルロ・ポンティではないが、昔の日本人は心身と言うように心と身体を分けて考えていなかったという。
歴史について―小林秀雄対談集 (1978年) (文春文庫)/小林 秀雄
¥273
Amazon.co.jp
知覚の現象学 1/M.メルロー・ポンティ
¥5,040
Amazon.co.jp
「身」という言葉そのものが「心」を表していた。
というよりも、「身」という古言葉にふくまれているニュアンスが古人にちかづくひとつのアプローチにもなるということだ。
岩見沢市に志乃という喫茶が昔あった。
友だちのI氏がそこで珈琲をおとしていたので、よく通ったjazz喫茶だったが、昼間の誰一人いない店内で、ストープの横にすわって強烈に寒い外の空気から救われ、ただバッハの音楽に身体をまかせながらリラックスしていると、なにやら、自分というものが強烈に感じられたことを思い出せる。
バッハの音楽のせいなのかもしれない。
脳が普通の状態ではない至高体験のようなものにはいっていったのか。
小林秀雄氏の言葉を借りれば、喫茶店内から私が外の吹雪の風景を見ていたのではなくて、吹雪が外の風景が私をのぞきこんでいたような感覚。
バッハの音を私の耳が聴いていたというよりもバッハが私のエナジーの響きを聴いていたような不思議な感覚。
これはブログに何回も書いていることだけども、誰しも同じような、小さな経験は持っていることだと思います。
至高体験―自己実現のための心理学 (河出文庫)/コリン ウィルソン
¥1,260
Amazon.co.jp
しかしながら。
こむずかしい理屈はともかく、
産まれた時から、目が見えず、口がきけず、耳が聞こえないという三重苦のヘレンケラーの
ことを考えれば、
普通の生活ということじたいが、ものすごい奇蹟に、私には思える。
「奇蹟の人」
パティ・デュークの名演技が光ります。
「卒業」のアンバン・クロフトもここらあたりが、油ののった最高の演技とも言えます。
これは大好きな映画です。
今でも、たまに、元気を欲しい時に見る映画のひとつです。
これを見ると、愚痴や不満を、言う気持ちがなくなってしまいます。
目に見えるものだけが大切なのではない。
目に見えないもの、それもまた大切。
耳に聞こえるものだけが大切なのではない。
耳に聞こえないもの、それもまた大切。
口で喋るだけが大切なのではない。
口で喋ることができないこともまた大切。
そう思う。
ユングに書いてきてここで、祭りのこと。
人がこの世に生まれて、畠を耕しながら、人生喜怒哀楽、結婚と祭りと出産と育児にあけくれている時代の人々は、ある意味ではそれ以上のものは必要ないのかもしれない。
祭り。
祭りなんかも、「非日常」だ。
今でさえ、日本の伝統的な祭りで死者がでることはおおめに見られている。
死者はたまにでても、翌年は、また祭りはそのまま続けられる。
それは、「祭り」だからだ。
世界の祭り。
キリスト教社会は、基本、祭りは少ないと言われるが、
それでも、多種多様な、その国独特の、祭りがある。
これも祭りのひとつだと思う。
死者が出たからといって、祭りがそのまま永遠に中止ということはまずない。
リオのオリンピックが近づいています。
祭りでは、性の問題もまた、おおめに見られる。
リオのカーニバルでも、祭りの終わったあとで、何百人もの私生児が今でも生まれているのだろうか?
これは日本でも昔はどこの地方でもあったことであるし、それは祭りということで許されたことだったと思う。
だから、人はある意味で退屈で平凡な日常に「喝」をうちこんでくれる「なにか」をいつも望んでいる。
地道な生活は大切であるからこそ、その地道な生活がためこんだ垢落としが必要なのかもしれない。
友達と、飲みに行って、はめをはずしたり、それもまた、小さな小さなひとつの「現代の祭り」なんだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・
旅芸人がいる。
昔は、村から村へと旅する旅芸人なんかがその役割をしたのかもしれない。
雪のふる間に、寒村で、娘達が機織りをはじめたことも、もちろん、基本は、生活のための機織りから始まって、だんだんに、それを自分が着たり、売ったりすることに飽き足らなくなって、もっともっと、複雑で、美しい文様を求めてきたに違いない。
その意味では、貴族や殿様の豪奢な美に対する希求というものも、平民や農民に飢餓や貧乏というものを与えながらも、美の育成には、まちがいなく+になってきたものだと思う。
一度沖縄の首里の博物館や城を見たが、これはまた素晴らしいものだった。
琉球王国の歴史―大貿易時代から首里城明け渡しまで/著者不明
¥1,050
Amazon.co.jp
ルドウィヒ王のあの国の金を水のように浪費した美への投資がなかったら、あの城は今なかった。
会田雄次氏が書いているようにそれらの「婆娑羅精神」は、世界各国にある。
いくら、新宿の都庁が素晴らしい建築物で、金をかけたというものであっても、それを見ることを目的に世界から人はやってこない。
京都の禅寺やら、大仏やら、たとえばピラミッドやら、ルドウィヒの城やら、万里の頂上やら、ヨーロッパの城など、それらの美の目的というものは、まるで婆娑羅だ。
狂ったような一人の人間のイマジネーションがそこでは、幼児のように羽ばたいている。
そして、嫉妬心からくるヒステリーと、偽善と、監視と管理だらけで、未来ががんじがらめに糸で縛られているこの現代の地球では、それらの婆娑羅の精神は、見るものに圧倒的な「人間のわがままな美と放蕩の喜び」みたいなものを、かいま見せてくれる。
先日、たまたま小林秀雄氏と福田恆存氏、中村氏だったか、「対談」を読んでいて、美の問題がやはりやっかいだということもよく理解できたし、三島由紀夫氏と、小林秀雄氏の私が大好きな対談集「源泉の感情」なんかを読んでも、美の問題がいかに難儀なものかが話されている。
源泉の感情 (河出文庫)/三島 由紀夫
¥966
Amazon.co.jp
野の花を見よ、鳥を見よ。
美とはすべて役に立たないものだと書いたのはたしか、ラスキンだったか。
たしかに、それは「生活」のためには役にはたたないが、「夢見る」ためには、ぜひとも必要な麻薬の粉なのかもしれない。
そして、地道にくらせばなんの支障もケガもなく平凡にくらせる筈の人たちでさへが、危険をおかしてまで、手に入れたい「快楽の源泉」なのだろう。(ここでいう、麻薬とは、テレビをさわがせている麻薬ではない、あしからず・・)
芸術の真実と教育―近代画家論・原理編〈1〉 (近代画家論 (原理編1))/ジョン ラスキン
¥2,730
Amazon.co.jp
淀川長治氏・・・・・・・・・・・・・
私の映画遺言 (中公文庫)/淀川 長治
¥680
Amazon.co.jp
私はこの淀川長治氏が大好きだ。
だれもが、彼のさよならさよならさよならという名文句を愛しているし、記憶している。
だが、彼が、比類のない美意識の持ち主だったとは、理解していない。
彼独特の優しさで、絶対に公の場では、監督の悪口を言わなかった。
映画を、日本映画を真に愛していた人。
日本文化、歌舞伎や、能に精通していたから、プライベートでは日本の監督はかなり淀川さんから、叱られている筈。
そこらあたりの話を山田洋次がうまく書いています。
彼の作品の「息子」
ラストシーンの終わりかたが、誰もいない部屋にもどってきたオヤジが、ひとり電気をつけておしまいになる、そのシーンに淀川さんは、山田監督に注文をつける。
「あなたの映画は色気がないわね」と。
淀川さんが言うのには、その最後のシーンで、東京の息子に会った後、田舎のひとりずまいの暗い部屋にもどってきた父は、おもむろに、電話を始める。
そして、駅前の小料理屋でもなんでもよいが、女がでてきて、父親は言う。
「東京土産があるから、ちょいと、でてこないか」。
フランス仕込みの淀川さんならではの、ラストシーンの仕掛け。
愛人の出番を、観客にふと連想させる。
父親が愛人を持ったっていいじゃないの、それが淀川さんの自由な生き方の「色気」の味の出しかた。
ふと、私は、淀川さんがピーコとの対談で絶賛していた、ビノシェの「ダメージ」を思い出した。
ひとりの女性を父親と息子が、愛してしまう。
数十回も見たフランス映画。また見てみよう。
道徳的な映画ではないけれども、三島由紀夫氏がいうように、実人生のなかでは、約束を守り、律儀で、法律を守る常識人であっても、作品のなかでは、自由奔放にイマジネーションの羽を大きく原稿の空に広げるのでなければ、artは死んでしまう。
私はいつも、そう思う。
次は、ボクシングの映画です。
マイルスがボクサーのジャック・ジョンソンに捧げたというこの「ジャック・ジョンソン」が私はマイルスの作品のなかでは一番好きです。2番目はon the cornerかもしれない。
少し高かったが、completeを買ってしまったから。
ボクシングは良くも悪くも男のなかの男が戦う聖なる競技。
残酷であらゆるスポーツのなかで一番死に近いスポーツ。
三島由紀夫氏がこよなく愛したそれでもありました。
ところで、このミリオンダラーベイビー。
以前、ブログでも紹介しましたヒラリー・スワンク、良いです。
この映画、男の中の男のスポーツに女が出てくる。
時代は変わりました。
そして、クリント・イーストウッド扮するボスが、彼女に最後には愛を感じてしまうんですね。
しかも、死を賭けた彼女の男以上の戦いぶりに「やられて」しまう。
わたしは、映画好きですが、やはり見逃していた作品多いです。これもそのひとつ。
アカデミー賞を総なめにした、というのも見たあとで知った事。
最初は英語の勉強でもしようと気楽に見始めたのですが、そして、ボクシング映画が好きな私は、まさか、「傷だらけの栄光」や「ロッキー」の一作目を超えるだけの感銘をもらえるとは思ってもいませんでした。
尊厳死で問題になったとありますが、ヒステリーな観客はどこの国でもいます。
少なくても一線で活躍している修羅場をくぐっている監督やらライターが、そのことを知らない筈はありません。
日本でも、本来自由であるはずの、作品の中で、障害者についてなにやら書いたということで、筒井康隆氏も断筆しましたね。
わたしはそのような尊厳死のメッセージだけをするためにクリント・イーストウッド監督がこの映画をつくったとはとうてい思えません。
この問題はアメリカなどではかなりの永遠のテーマなようですが、私が一番感心したのは、クリント・イーストウッド ヒラリー・スワンク モーガン・フリーマン の演技です。
素晴らしい。
物語自体はたんなるサクセス・ストーリーなのですが。
それが、かれらの自然でありながら、「はまりこんでいる」まるで、「取り憑かれたような」演技で、絵で言えば、細部に神がやどるようなシーンがたくさん出てきます。
伏線としては犬のアクセルの死に様。
レモンパイの美味い店。
生活保護でぬくぬくと生きている恵まれない貧しい連中、考え方。
後半の30分が味噌です。
涙なくしては見れません。
私の映画のフェチをくすぐり、ツボにはまってしまったようです。・・・
平野仁の初期のSFには、素晴らしいものがありますが、ジェームズ三木の作品で、家族で宇宙にほうりだされて、しだいに食料が尽き、最後には二人分の酸素と食料しかなくなってしまい、夫がみずから宇宙に身を投じるという作品をふと関係はないのですが、連想してしまいました。
あのマギーの看病をあのまま一生、続けていくことを確かダンは呟いていましたね。
それが、マギーの美意識に添うか添わないか。
かつてアメリカには若者の美はあるが、老人の美はないと三島氏が言っていましたね。
それに比較して日本には老人=精神性の美があると。
でも、三島由紀夫氏もまた、桜みたいに散ってしまいました。
クリント・イーストウッドが日本のサムライに見えた夜でした。
備忘録。
ツボにはまった理由を書き連ねてみる。
●やはり、貧乏な人達にはわたしはめちゃ、弱い。あの彼らの部屋を見ているだけで勇気をもらえる。
アンデルセン好きな私の涙腺を刺激する。
つげ義春の作品群。特に紅い花の、おかっぱの女の子。
紫電改の鷹。二度ともどってはこない特攻隊の彼のために母と彼女はおはぎをつくって持って行くラストシーン。
亡き姉に捧げた石森章太郎の作品群。特に幻魔大戦。ジュン。霧と薔薇と星と。常に貧乏だった石森氏を蔭で支えた姉。
若くして死んだ三島由紀夫氏の妹。おにいちゃんという言葉。
あと、記憶に残しておくシーン。
ボスとマギーの老人と少女の愛?
ふたりのしゃれたユーモアのある会話。
資料B
マギーのガウンの背中に刺繍された言葉である「モ・クシュラ」(Mo Chúisle)が、映画の中では Mo Cuishle とスペルを間違われているという指摘がある。さらに映画の中では「モ・クシュラ」を「おまえは私の親愛なる者、おまえは私の血(My darling, my blood)」と訳している。(「モ・クシュラ」は「おまえは私の鼓動だ(My pulse)」[5]を意味するゲール語の親愛表現であり、『A chúisle mo chroí』(ああ、私の心臓の鼓動よ)の短縮形である。)
レモンパイをほおばる二人。
モーガン・フリーマンの後悔。演技。あの彼の部屋。
さりげない脇役。深く沈んだ表情の美。
男のなかの男をちょいとアホで間抜けな白人の若者で描き、こつこつと地道ではあるが努力家のマギーを対比させる。
そう今や、ボクシングもまた女でさへ、否女だからこそ、真に戦えるスポーツなのかもしれない。
このあたりはクリント・イーストウッドの女性に対する信頼が・・・・?
信頼が支える「師弟関係」
これは古いと言われるが、今一番の教育システムだ。
子弟が子弟を超えて愛になるのを批判することは簡単だが、当然のことでもある。
ブレードランナーではないが、是非逃げ切ってもらいたい。
クリント・イーストウッド 大好きな俳優です。
悲観的見方は好きではない。
思い通りに行かなくても先へ進もう。
雨になると思ったら本当に雨が降るものだ クリント・イーストウッド
FIN
「4.44人類滅亡」「お前は芸術を信じてこれまで必死で生きてきたじゃないか」そんなお前が誇らしい
最近、酒の量をへらしているせいか、体調良し。
朝、六時稀少。
妙な曲を見つけたので、聞きながら、まずは笑で体調をととのえる。・・・・・・
・・・・・・・・ 雑用をしながら。
「人間の建設」「禅による生活」を読み、岡崎京子と、石田徹也画集をじっと・・・。
素晴しい。

岡崎京子は、やはり正負の法則か。復帰はあるのだろうか???
人類が滅ぶというテーマの映画は限りなくあります。
人の頭のなかで考えられたものはすべて実現するともいいますから、
ある意味、人が脳のなかで、さまざまなる視点からこの愛すべき地球の、
最後の日を想像することで、「そうはさせないぞ」という覚悟と、
また、冷静にその日を描く事で、今のうちから人類としてやっておくことはないのか、
・・・・・・・そんなことを考えるためのヒントなのかもしれません。
有名な「アルマゲドン」と「デープインパクト」をのぞけば・・
けっこう「人類滅亡」をテーマにした映画がありますね。
当然、全部見れるはずもありません。見たのだけを列記すると・・・
「デイ・アフター・トゥモロー」
『デイ・アフター・トゥモロー』は、2004年製作のアメリカ映画。地球温暖化によって突然訪れた氷河期に混乱する人々を現実味を持って描く。SF映画でもあり、パニック映画であるとも言える。
監督をすこし調べますと・・・
スペースノア Das Arche Noah Prinzip (1983年) 監督・脚本
MOON44 Moon 44 (1990年) 監督・脚本・製作
ユニバーサル・ソルジャー Universal Soldier (1992年) 監督
スターゲイト Stargate (1994年) 監督・脚本
インデペンデンス・デイ Independence Day (1996年) 監督・脚本・製作総指揮、アカデミー視覚効果賞受賞
GODZILLA Godzilla (1998年) 監督・脚本・原案・製作総指揮
パトリオット The Patriot (2000年) 監督・製作総指揮
スパイダー パニック! Eight Legged Freaks (2002年) 製作総指揮
デイ・アフター・トゥモロー The Day After Tomorrow (2004年) 監督・脚本・原作・製作
紀元前1万年 10000 BC (2008年) 監督・脚本・製作
2012 2012 (2009年) 監督・脚本・製作総指揮
もうひとりのシェイクスピア Anonymous (2011年) 監督・製作
ホワイトハウス・ダウン White House Down (2013年) 監督・製作
インデペンデンス・デイ:リサージェンス Independence Day: Resurgence (2016年) 監督
「ザ・コア」
2013/07/25 に公開
地球の核停止。人類は1年以内に滅亡する...。
それは些細な予兆から始まった。
ペースメーカーをつけている人々の突然死。トラファルガー広場に散乱する無数の鳩の死骸。
このヒラリー・スワンク。
「ミリオンダラーズベイビー」でも素晴しき演技をしておりますね。
すごい存在感です。

「日本沈没」
1976年には、Michael Gallagher(en)により3分の1ほどの抄訳ながら、アメリカで『JAPAN SINKS』のタイトルで出版された。
元々は「日本人が国を失い放浪の民族になったらどうなるのか」をテーマに据えており、日本列島沈没はあくまでもその舞台設定で、地球物理学への関心はその後から涌いたものだという。しかし、そのために駆使されたのが当時やっと広く認知され始めていたプレート・テクトニクスであり、この作品はその分野を広く紹介する役割をも果たした。この分野に関する作品中の解説やアイデアは修士論文に相当するとの声もあったほどである。
◎資料
物語[編集]
地球物理学者・田所雄介博士は、地震の観測データから日本列島に異変が起きているのを直感し、調査に乗り出す。深海調査艇「ケルマデック (Kermadec)」号の操艇者・小野寺俊夫、助手の幸長信彦助教授と共に小笠原諸島沖の日本海溝に潜った田所は海底を走る奇妙な亀裂と乱泥流を発見する。異変を確信した田所はデータを集め続け、一つの結論に達する。それは「日本列島は最悪の場合2年以内に、地殻変動で陸地のほとんどが海面下に沈没する」というものだった。
最初は半信半疑だった政府も紆余曲折の末、日本人を海外へ脱出させる「D計画」を立案・発動する。しかし、事態の推移は当初の田所の予想すら超えた速度で進行していた。各地で巨大地震が相次ぎ、休火山までが活動を始める。精鋭スタッフたちが死に物狂いでD計画を遂行し、日本人を続々と海外避難させる。一方、敢えて国内に留まり日本列島と運命を共にする道を選択する者もいた。
四国を皮切りに次々と列島は海中に没し、北関東が最後の大爆発を起こして日本列島は完全に消滅する
「サンシャイン2057」
太陽が衰え人類が滅亡の危機に瀕している近未来(2057年)を舞台に、核爆弾で太陽の活動を蘇らせるために、宇宙船イカロス号で太陽へ向かった8人の乗組員を描いたSF映画。また、イカロス1号の遭難をめぐるホラー・サスペンス的な要素も含まれている。
全編を通して、最新のSFXを駆使してつくりあげた美麗な映像が印象的である。本編後半には、イカロス1号のクルーの写真がサブリミナル効果で挿入されている
たしか、マレーシア人のミシェール・ヨー、この女優さん。007にも出ていたのでしょうか。

「世界が燃えつきる日」
核戦争は地球と大気圏を完全に破壊した!
「宇宙戦争」
『宇宙戦争』は、2005年のアメリカ映画。H・G・ウェルズによる同名SF小説『宇宙戦争』を原作としたSF映画である。 スティーヴン・スピルバーグ監督作品。トム・クルーズは出演のほか、製作にも参加している。
「ノウイング」
1959年、マサチューセッツ州レキシントンのとある小学校では創立記念日を迎えようとしていた。この小学校の生徒の一人、ルシンダの提案が評価され、みんなでタイムカプセルを埋めることになる。それぞれが思い思いに描いた『絵』をその中に閉じ込めて。
50年後、それは予定通り掘り起こされた。この小学校に通う少年ケイレブは、不可解な数字で埋め尽くされた一枚の紙を持ち帰ってきた。彼の父親で宇宙物理学教授のジョンは、そこに記された数字の羅列が過去50年とこれから先に起きる未来の出来事を予言したものだと気づく。そして、紙の最後に書かれた数字は人類の存亡に関わるものだった。
ローズ・バーンについて・・・・・・・・・

アイルランド及びスコットランド系[1][2]。姉が二人、兄が一人おり、ローズは末っ子である。デビュー映画は12歳の時に出演したオーストラリア映画『Dallas Doll』である。シドニー大学で学ぶ[3]。以後、オーストラリアのテレビに多く出演していたが、1999年にはAtlantic Theatre Companyで学び[3]、2000年に入りアメリカ映画やイギリス映画にも進出している。2007年にアメリカで放送を開始したテレビドラマ『ダメージ』のエレン・パーソンズ役を演じエミー賞助演女優賞にノミネートされるなど、活躍の場を広げている。『ダメージ』は2011年にシーズン4が放送される。現在はシドニーとロンドンを往復する生活を送っている。
2000年の『The Goddess of 1967』にてヴェネツィア国際映画祭女優賞を受賞している。
ダレン・ヘイズの「I Miss You」のPVにも出演している。Max FactorのCMにも出演しており、日本でもローズ・バーンが出演したCMが流れていた。
2009年度の最も美しい顔トップ100で、1位になった。
「エンドオブザワールド」
1959年、マサチューセッツ州レキシントンのとある小学校では創立記念日を迎えようとしていた。この小学校の生徒の一人、ルシンダの提案が評価され、みんなでタイムカプセルを埋めることになる。それぞれが思い思いに描いた『絵』をその中に閉じ込めて。
50年後、それは予定通り掘り起こされた。この小学校に通う少年ケイレブは、不可解な数字で埋め尽くされた一枚の紙を持ち帰ってきた。彼の父親で宇宙物理学教授のジョンは、そこに記された数字の羅列が過去50年とこれから先に起きる未来の出来事を予言したものだと気づく。そして、紙の最後に書かれた数字は人類の存亡に関わるものだった[3]。
内容:中国とアメリカとの間で核戦争勃発。その為に、北半球の環境は放射能汚染により生物絶滅。かろうじて、南半球は汚染から免れたが、北からの難民でオーストラリアは混乱、無秩序状態に。しかし、放射能の恐怖はやがてこのオーストラリアのある南半球をも襲う・・・
戦争と事故では起因こそ違うが、「破滅を招く」という結果は同じ。
放射能の怖さはもう一つ、それは若い命から先に失われるということ!内容:中国とアメリカとの間で核戦争勃発。その為に、北半球の環境は放射能汚染により生物絶滅。かろうじて、南半球は汚染から免れたが、北からの難民でオーストラリアは混乱、無秩序状態に。しかし、放射能の恐怖はやがてこのオーストラリアのある南半球をも襲う・・・
戦争と事故では起因こそ違うが、「破滅を招く」という結果は同じ。
放射能の怖さはもう一つ、それは若い命から先に失われるということ!
その他にも限りなくたくさんの人類滅亡のテーマがあるんでしょう。
見たのはそのなかの数%です。
個人的に、私が、これらのテーマを好むのは、あまりにも現実的には、この世は金、株、車社会であり、人類がもうコントロールできることのできないぎりぎりの範囲まできているように感じるからです。(先日のフランスでの環境会議、あれは成功と言えるのでしょうか?? だれひとりとしして、地球そのもののことを考えて発言していたでしょうか??)
奇跡のような生命体なのに。いまだかつて、地球以外に人類のような高い知能を持った生物は発見されていないのに。
・・・
水素爆弾だ、シルバー詐欺に、ブラック起業に、インチキ自転車操業会社、ゆすりにたかりに、殺戮に、テロに、偽の歴史偽造・・・自分が信じる神のために異端の神を信じる人をいとも簡単に殺戮する・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
こんなことをやっている場合なんでしょうか・・・そういう素直な気持ちにさせられるから、これらの映画は好きです。別に地球に滅んでほしいわけではなく、その逆だからこそ、
なにやら、ヒントを欲しいのです。
真の人類の危機は最大最高の優先順位ですから。・・・・・・・・そこが人類の知能知性のみせどころなんですが・・・
(テレビばかりしか見ない想像力がない人が、最近多いですから、視点が近視眼的です。男の優しさばかりがもとはやされますが、いざ、エイリアンとの戦いになったら、誰が、戦うの? そのために、今なにをしなければいけないのか・・・・誰も考えていませんね。)
先日のNASAのニュースが、ほんのすこしだけ、新聞やテレビで放映されましたが、これは、素晴しいニュースです。もっともっと、広めてほしかったニュースです。
NASA が、小惑星が地球に衝突するような事態に備える専門部署、Planetary Defense Coordination Office (PDCO)の設立を発表しました。要するに隕石衝突から地球を守る防衛隊といったところです。
PDCO の具体的な役割は、地球に接近する小惑星や彗星をいち早く発見し、分析すること。そして危機が迫る場合は政府や関係各機関の間の調整役もこなします。 NASA はこれまでも地球に接近する天体があれば世界の宇宙機関と連携して対応してきました。PDCO はこれまで単発でこなしてきたこれらの緊急対応を受け持ち、連邦緊急管理庁(FEMA)ほかとも連携して"潜在的な危機・影響"の発見、警告、科学的分析を行います。
NASA が小惑星や彗星などの管理をし始めた1998年以来、地球近傍の宇宙空間には1万3500個の小天体が発見されてきました。現在でも、年間1500個ペースで新しい小惑星や彗星が発見されています。
ただ、すでに地球近傍の直径3000フィート(約915m)規模の小天体は、その9割ほどが発見されたと目されます。今後は PDCO が直径40フィート(約140m)級の天体の発見にシフトしていく計画です。このため、米国政府は2016年予算のうち5000万ドルを PDCO に割り当てました。これは5年前に比べると10倍以上の金額です。

2013年にロシア・チェリャビンスクに落下した隕石の例を思い出せば、いつ何時我々に危機が訪れるかはわかりません。NASA は2020年の実行を目標として、地球に衝突する恐れのある小惑星の軌道を意図的に変えさせる「小惑星再配置ミッション(Asteroid Redirect Mission)を計画しています。
またNASAと欧州宇宙機関(ESA)は共同で、小惑星に人工物(宇宙船など)を衝突させてその軌道を変えさせようとする Asteroid Impact and DeflectionAssessment(AIDA)計画の研究も進めています。こうした研究の成果を、いざ現実に実行に移す事態となったとき活躍するのが PDCO、ということになりそうです。
映画『アルマゲドン』の、小惑星に核爆弾を埋め込んで爆発させ、その軌道を変えるというストーリーは、我々一般市民が見ても「まあまあ、映画だから」と思わせるものでした。ところが実際はこのように、大真面目に検討されていることだというのは(別に石油採掘企業の中年オヤジを宇宙へ送り込むわけではないものの)なんとも面白いところです。
•
何回見ても感動的なシーンです。
私の好きなリヴ・タイラーが・・・


NASA が、小惑星が地球に衝突するような事態に備える専門部署、Planetary Defense Coordination Office (PDCO)の設立を発表しました。要するに隕石衝突から地球を守る防衛隊といったところです。
PDCO の具体的な役割は、地球に接近する小惑星や彗星をいち早く発見し、分析すること。そして危機が迫る場合は政府や関係各機関の間の調整役もこなします。 NASA はこれまでも地球に接近する天体があれば世界の宇宙機関と連携して対応してきました。PDCO はこれまで単発でこなしてきたこれらの緊急対応を受け持ち、連邦緊急管理庁(FEMA)ほかとも連携して"潜在的な危機・影響"の発見、警告、科学的分析を行います。
NASA が小惑星や彗星などの管理をし始めた1998ち年以来、地球近傍の宇宙空間には1万3500個の小天体が発見されてきました。現在でも、年間1500個ペースで新しい小惑星や彗星が発見されています。
ただ、すでに地球近傍の直径3000フィート(約915m)規模の小天体は、その9割ほどが発見されたと目されます。今後は PDCO が直径40フィート(約140m)級の天体の発見にシフトしていく計画です。このため、米国政府は2016年予算のうち5000万ドルを PDCO に割り当てました。これは5年前に比べると10倍以上の金額です。

2013年にロシア・チェリャビンスクに落下した隕石の例を思い出せば、いつ何時我々に危機が訪れるかはわかりません。NASA は2020年の実行を目標として、地球に衝突する恐れのある小惑星の軌道を意図的に変えさせる「小惑星再配置ミッション(Asteroid Redirect Mission)を計画しています。
またNASAと欧州宇宙機関(ESA)は共同で、小惑星に人工物(宇宙船など)を衝突させてその軌道を変えさせようとする Asteroid Impact and DeflectionAssessment(AIDA)計画の研究も進めています。こうした研究の成果を、いざ現実に実行に移す事態となったとき活躍するのが PDCO、ということになりそうです。
映画『アルマゲドン』の、小惑星に核爆弾を埋め込んで爆発させ、その軌道を変えるというストーリーは、我々一般市民が見ても「まあまあ、映画だから」と思わせるものでした。ところが実際はこのように、大真面目に検討されていることだというのは(別に石油採掘企業の中年オヤジを宇宙へ送り込むわけではないものの)なんとも面白いところです。
個人的には、思い出のある好きな人類滅亡のテーマの作品は、
◎「渚にて」
もちろんオリジナル版もはずせないのですが、とりあえずここでは、2000年版で。
◎「メランコリア」
アルマゲドンや、ディープ・インパクトなどのような、娯楽の要素はかなり少なく。
最初から最後まで、監督の美意識が、深刻な緊張感のまま続行していきます。
救いがないといえば、救いのない映画ですが、
もっと今のこの人生をしっかりと大切にせねば、と感じさせてくれる、傑作だと思います。
監督は、「ダンサーインザダーク」のラース・フォン・トリアー。
デンマーク映画ここにあり、と、世界に発信したひとりです。
このビョークの映画は、独特の映像と、カメラワークで実に印象に強く残っています。
『アンチクライスト』などの鬼才ラース・フォン・トリアー監督が、『スパイダーマン』シリーズのキルステン・ダンストを主演に迎えた終末観漂う人間ドラマ。惑星との衝突を目前に控え、残り時間の少ない地球を舞台に、うつろな心を抱えた花嫁と彼女を取り巻く人々の人間模様を映し出す。ヒロインの姉をシャルロット・ゲンズブールが演じ、その夫をキーファー・サザーランドが演じている。神秘的で美しい地球の最期の姿に心揺さぶられる。
このふたつですね。
キルスティン・ダンスト 素敵ですよ。
キルスティン・キャロライン・ダンストは、アメリカ合衆国の女優。Kirsten の正しい発音はキアステン 。キルステン・ダンスト、カーステン・ダンストと表記されることもある。子供のころからの愛称はキキ。これは日本のアニメ映画『魔女の宅急便』の英語版で主人公キキの声優を担当したことから。

「ノウイング」も、大好きな私の俳優、ででいますし、最後は救いがありますので、これはおすすめです。・・・
「渚にて」は救いはありません。
「メランコリア」も救いはありません。
さきほどのnasaのニュースではありませんが、ホーキング博士は、おそらく宇宙人との最初のファーストコンタクトは、恐ろしいものになると予言しているので、いまから、しっかりと、地球と人類を守るための、戦略を普段からうっておくべきでしょう。
人類ならばできるはずですし、しなければいけません。
たしか、専門用語でしたか、視界狭窄とかいう減少が人間にはあって、危機がすぐまぢかに迫っている時には、人はなかなか冷静な判断をくだせないとか。
ホテル火災の時に、とんでもない高さのところから飛び降りたりする人がいるのは、その視界狭窄からくるとか、聞いた事が在ります。
たまたま、昨日、「4.44」という人類滅亡をテーマにした映画を見ました。
レヴューが、かなり低く、点数などは、1点でしたから、ほとんどの人が、
おもしろくないという印象をもった映画です。
『バッド・ルーテナント/刑事とドラッグとキリスト』『キング・オブ・ニューヨーク』などで知られる鬼才アベル・フェラーラ監督が、世界の終末を独自の視点でとらえた異色作。地球温暖化が原因で地球最期の日を迎える人々の姿を描き、第68回べネチア国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされた。『ハンター』などの個性派俳優ウィレム・デフォーらが出演。地球最期の瞬間をどのように過ごすのか、不条理な運命に直面した登場人物それぞれの葛藤が印象深い。
記憶が悪いので、カードにメモしながら映画を見る癖があるのですが、
備忘録を少し見直してみると・・・
◎Skypeの映画のなかでの有効なる使い方・・・ しかも、ADSLというのが、また味がある。
◎ダライラマのシーンがある。ベトナム人がでてくる。家族に対する愛。お別れ。
◎飛行機残骸のシーンと絵画
◎恋人の描く龍のイメージ
◎人類がほろぶ前の人心の豹変の描き方が淡々としすぎていたからか、人気がないのか
私にはそれが現実的で良いと思うが。
◎「渚にて」の家族での自殺でのシーンなどはあまりにもイメージがすごすぎて二度と見ようとは思えない
◎恋人が中に出してと、滅亡ににさいしてもりんごの樹を植えるシーンは良し
◎開高健が、一冊の本にひとつの言葉が心に残れば、それで良い本と書いているが、
この映画にはこの言葉がある。
Skypeで、ヒロインの女性が、龍の絵を描きながら、母とこの世での最後の話しをしている。
最後に母はいう。
「お前は、芸術を信じてこれまで必死で生きてきたじゃないか」「この地球でも必死で生きてきたお前が誇らしい・・・」
「きっと別の星であえる。」
「一緒に光にむかっていくのよ」
そのころ、地球のオゾン層は崩壊し、4.44分ころ、世界は光の渦となる。
ふたりは、そのとき、すでに天使であった。
「つねに人間臭くあってください。映画からたくさんの愛をもらいましょう」淀川長治
FIN
John Coltrane- Lush Life(FULL ALBUM)
ジョン・コルトレーンのリーダー作。57年と58年にまたがって収録されている。「ライク・サム・ワン・イン・ラヴ」から「トレーンズ・スロー・ブル ース」までが、アール・メイ(b)、アート・テイラー(ds)。「ラッシュ・ライフ」がドナルド・バード(tp)、 レッド・ガーランド(p)、ポール・チェンバース(b)、ルイ・ヘイス(ds)。「アイ・ヒア・ア・ラプソディ」が レッド・ガーランド(p)、ポール・チェンバース(b)、アル・ヒース(ds)。
Out of This World/Soul Eyes/The Inch Worm/Tunji
Miles Mode. John Coltrane, Elvin Jones, Jimmy Garrison, McCoy Tyner.
John Coltrane - Kulu Sé Mama
John Coltrane — tenor saxophone
Pharoah Sanders — tenor saxophone, percussion
McCoy Tyner — piano
Brad Mehldau - Teardrop (Massive Attack cover)
Victoria de los Angeles,´´el mirar de la maja``,
Victoria de los Angeles,´´el mirar de la maja``, Enrique Granados, Gerald Moore
最近。朝はこればかり聞いている。
「ゴヤのマハ(美女)」という題名がついている。
私が聞いているソプラノは、ピラール・ローレンガー。
アリシア・デ・ラローチャ・・・・
不思議に哀愁のある曲だと思う。・・・・・・・・落ち着く。
これも良い。・・・・・・・
これで落ち着くと、コルトレーンを聴く。
アリスからはじまって、コルトレーンそのものになって、最後はファラオサンダースなどに広がって行く。
さあ。今日も一日がはじまる!!!!!!!!!!!! 雑用はすべて完了。散歩でも行く。風強し。
すべては愛のため「one day」「ビュファサンライズ」「モリエール」「こわれゆく世界の中で」
壁を越えるのはちょっと苦しいけれど、越えればそこには必ず新しい世界がある。
それを見られるだけでも楽しいじゃないか。人生は木のようなもので、まっすぐに伸びた幹だけの木よりも、枝があちこちに伸びている木のほうがおもしろい。
まっすぐな幹だけをスルスルと昇っていくより、枝々をいろいろな方向に伸ばしたほうがいろいろな方向が見渡せて人生が何倍も楽しめるぞ。
・・・・・・石森章太郎
「リュウの道」
石森章太郎の、「リュウの道」。
全5巻。今読んでいます。
「幻魔大戦」も傑作ですが、この「リュウの道」は、隠れた傑作。
ハリウッドで映画化してもおかしくないほどの構成と、絵のレベルの高さです。
手塚治虫と比較すると、物語性では、手塚治虫の方がおおきいと思いますが、
絵と、SFとファンタジーに限ると、石森のほうが、上でしょうか。
女性を描くのが非常に上手い石森の「009ノ1」
まずは、竹宮恵子を連想します。「テラへ」や、「ジルベスターの星から」なんかを読むと、
コマ割りは女性的ですが、キャラの顔などに、石森章太郎の影響が見え隠れています。
石森章太郎は、なんといっても、「jun」が最高傑作です。
彼の影響を受けている漫画家はたくさんいますが、この高橋留美子嬢なんかもそうでしょう。
「うるせいやつら」は、軽いタッチのなかにも、独特の魅力のコマ割りと線タッチが素晴しいです。
あと、個人的な意見ですが、吾妻ひでおは、昔はあまり好きではなかったのですが、今、よくよく読んでみると、おもしろいです。
絵が、可愛いです。
やはり、石森の影響はあるでしょう。
彼のここ最近の作品では、すべてを投げ打って、ホームレスのような生活をして、それを日記にした作品が好きでした。
彼も、SFが良いです。
最近のマンガ。
もちろん、「ワンピース」や、「アイアムヒーロー」や、「ガンツ」なんかも好きですが、
やはり、今一番、憧れている漫画家は、浦沢直樹の漫勉でも紹介されていた、五十嵐大介。
「魔女」からの画像です。
とにかく、美大出だけあり、少し宮崎駿を連想させる絵のタッチ。
独特のコマ割り。
アミの使い方もおもしろいですし、背景をボールペンでぎっしり書き込んで、背景の空気感まで出そうとする姿勢には共感します。
「魔女」を資料で調べると、・・・・・・・
魔女(2003年 - 2005年、月刊IKKI、小学館)
魔女をテーマにした連作集。トルコ、熱帯地方、北欧、日本とそれぞれ舞台の違う4つの作品から成り、単行本では描き下ろしの掌編2作も収録されている。2004年に文化庁メディア芸術祭優秀賞を受賞。またフランス語版が2007年アングレーム国際漫画祭ベストコミックブック賞にノミネートされた。既刊2巻。
SPINDLE(『月刊IKKI』2003年6、8月号)
KUARUPU(『月刊IKKI』2004年2月号)
PETRA GENITALIX(『月刊IKKI』2004年6 - 8月号)
うたぬすびと(『月刊IKKI』2005年1月号)

あと、五十嵐大介の作品は、映画にもなっております。
まだ、若いのに、絵だけにたよらず、テーマに広がりがあります。
吉行淳之介氏が、かつて、「作品を書くには、たくさんの経験があるだけでは駄目。
経験をどう感じたかというセンスも必要」と、書いていましたが、
若くして漫画家や、作家になった人は、特に、このセンスがないと、いつか作品が枯れる時がくることでしょう。
質と量。
どちらも、大切ということです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それでは、
映画。
淀川長治氏が、「良い映画を見ていると人生が幸福になる」と書いていますが、「悪い映画を見ていると人生が不幸になる」とも言えそうで、少し怖くもなります。笑。
しかしながら、人それぞれにとって、脳の一番本質的なところをジーンと刺激するのは、また違っていいのであって、それに、体調やら、その日の気分によっても、見た映画の感動は異なってきます。
小説の良いところは、読みたくなくなれば、ボイと文庫本を机や枕元に投げ出して、散歩にでかければいいですし、すこしずつ、何日にもわけて考えながら読む楽しみもあります。
でも、映画は、家族で見たり、友だちと見たりと、なかなかそう自由には見るわけには普通はいかないでしょう。
糸川氏などは、時間の有効活用として、多忙の日々、一時間のあいた時間に映画を一時間分見て、残りの半分の映画は、こんどはたとえば飛行機で着いた行き先で見るという具合に、映画の自由な見方を紹介していましたが、お金もかかりますし、みんなができるという映画鑑賞法ではありませんね。(その意味では、家でのひとりパソコン映画視聴は、便利です。)
「すべては愛のために」
ともかく、
エチオピア、カンボジア、チェチェン、イギリスという地域を美しい映画の画面で映し出しています。
映画のテーマである、紛争そのものの残酷はともかく、たぶん一生足を踏み入れることのない場所をうまく切り取って映画にしてまとめています。
それにもう、「今の時代の空気」を切り取るためには、「単純さ」だけでは無理なのかもしれない。
それだけ紛争戦争の残虐さは、単純なる物語にはなりえない?
見て、考え込むだけ。
見て、驚愕する。
これらの映画群を見て、簡単にレヴューで点数などつける気にはなれない。・・・・
そんな場所に、サラは踏み込んで行く。・・・・
ニックへの尊敬と愛によって。
しかしながら、この映画の題名は、なんとかならないか?
『すべては愛のために』(原題: Beyond Borders)は、2003年製作のアメリカ映画。裕福なイギリス人と結婚したサラとエチオピアやカンボジアなど貧困な地域で活動する医者ニックとの愛と感動のドラマ。
beyond bordersで良いと思いますが。
だれもが怖がるこのbordersをこのサラは、超えて行く。
それにしてもアフリカのあのやせ衰えた子供のシーンの驚愕。
もう眼をそむけたくなるほど。ホンモノの子供をよく撮ったものだ。
あの自殺した「飢餓の子供と禿鷹」の写真家が撮った写真を連想させるシーン。
この写真は、じつは、かなり深刻な議論を生みました。
写真家は受賞後、自殺。
考えさせられます。
ケビン・カーター
(1960年9月13日 - 1994年7月27日)南アフリカ共和国の報道写真家。
1994年、ハゲワシが餓死寸前の少女を狙っている『ハゲワシと少女』という写真でピューリッツァー賞を受賞。写真はスーダンの飢餓を訴えたものだったが、1993年3月26日付のニューヨーク・タイムズに掲載されると同紙には絶賛と共に多くの批判が寄せられた。そのほとんどは「なぜ少女を助けなかったのか」というものであり、やがてタイム誌などを中心に「報道か人命か」というメディアの姿勢を問う論争に発展した。
授賞式から約1ヶ月後、カーターはヨハネスブルグ郊外に停めた車の中に排気ガスを引きこみ自殺。彼は薬物依存症であっただけでなく、20代の頃に躁鬱病を患っており二度も自殺未遂を起こすなど精神的に不安定な側面があった。また、死の数年前から衝撃的な写真を撮ることと、そうした写真ばかりが喜ばれることに疑問を抱いていた。
1983年から続く内戦と干ばつのためにスーダンでは子供たちを中心に深刻な飢餓が起こっていた。しかし、スーダン政府は取材を締め出し国外に伝わらないようにしていた。そんな中カーターは、内戦の状況を伝えようとスーダンに潜入した。
カーターが訪れた国連などの食料配給センタ-があるアヨドという村では、飢えや伝染病で1日に10人から15人の子供たちが死んでゆく有様だった。やりきれなさから、その村から離れようとして村を出たところで、ハゲワシが うずくまった少女を狙うという場面に遭遇したのである。現場にいたカーターの友人でありフォトジャーナリストのジョアォン・シルバの証言などによると、写真の構図は母親が食糧を手に入れようと子どもを地面に置いた短い時間にできたものであったという。カーターは写真を撮った後、ハゲワシを追い払い、少女は立ち上がり、国連の食糧配給センタ-の方へよろよろと歩きだした。それを見た後は、すさんだ気持ちになり木陰まで行って泣き始め、タバコをふかし、しばらく泣き続けたと手記に記している。
サラは母子を必死で助ける。
新聞やテレビでよくニュース紹介されるこれらの地域。
しかし、この映画一本見れば、リアルに想像が可能になる。
物語はさておいてよく惨状をまとめあげたものと感心しきり。
その画像はかなり強烈で人生のスパイスになる。これでもう
くだらないことで弱音を吐きたくなるだろう、ということは、間違いない。
日本はいまのところ、ほんとうに、幸福だ。
逆にいえば、日本人の危機意識は、なまぬるいとも言える。
この映画も、連想しました。
「ナイロビの蜂」
この映画でも、サラのようにとてつもなく感受性が強くそして挫折してもへこたれない女としてのテッサという女性が出てきてやはり死んでいる。
レイチェル・ワイズです。
◎資料から
1993年にデビューし、主にテレビ映画などに出演。1995年に『デスマシーン』で映画デビュー。同年にショーン・マサイアス演出による舞台『生活の設計』での大胆演技が評判となり、これを見たベルナルド・ベルトルッチが1996年公開の『魅せられて』に起用。また、同年公開の『チェーン・リアクション』でキアヌ・リーブスの相方を演じハリウッド作品に初出演する。
1999年公開の大ヒット作『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』で国際的に名前が知られるようになる。以降、ラブコメやアクションなど、様々な映画に出演する。尚、出世作チェーン・リアクションでペアを組んだキアヌ・リーブスとはコンスタンティン (映画)で再共演している。
2005年公開のイギリス映画『ナイロビの蜂』の演技で、第78回アカデミー賞助演女優賞、第63回ゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞。
彼女たちの前では、なんと無力なサラの旦那。
そして、テッサによって次第に本能としての男性の野生をとりもどすジャスティン。
このような反体制的な映画の欠点として、思想をおしつけるあまり、見ていて席をたちたくなるようなシネマもありますが、この二作は、人間社会、世界、組織、そんなものの裏社会の醜さをリアルに描きつつも、自然の美しさも讃えることを忘れていないので、一方的なおしつけにならずに、脳に情報をインプットできるのかもしれない。
国連難民高等弁務官 緒方貞子。
断食直訴 瀬戸内寂聴。
男は「戦う意味」を求めるし、 おんなは「盲目的な生きる意志」そのものなのかもしれない。
それでいいのだと思う。
いや、あまりにも難しい問題だから簡単にはそう言えないのかもしれない。
朝起きて、光のなかに神さまへの感謝を感じ、食事がきちんとでき、風呂やトイレがきちんと日々つかえ、好きな音楽を聞いたり好きな本をいつでも読め、気分がのれば少し散歩をしたり買い物をしたりできる今の日本の日常から見ると、それらを抛って、ボーダーを超えて行くこれらの「おんなたち」の生き方は突飛に見えるかもしれないが、一度、見ていて、それらを脳にインプットしておくと、普段の日本の日常の贅沢さに眼がくらむだけの、経験は味わえる。
映画。
もうひとつのわたしたちの人生。
ひとつの苦労が皺をひとつふやすがごとく、脳に少しは皺をふやしてくれるかもしれない映画群。
サラは、ニックによって心の奧の奧まで、震駭されるほどに影響される。
ジャスティンは、テッサによって、心の奧の奧まで、やはり震駭されるほどに影響される。
命と魂。
命は確かに地球よりも重いのかもしれないが、それよりも重い魂を持つ人に影響されて
境界線を超えて行く人達。
それを人は愛と呼ぶのか?
・・・・・・・・・・
それにレイチェル・ワイズって、「魅せられて」にも出ていたとは・・・
またまた「魅せられて」のDVDをトレイにのせる楽しみも・・・
それに、アンジェリーナ・ジョリーが、最近見た映画、ジョニーディップと競演したあの女優だと気がつくのがおそすぎ。
反省。
「ツァーリスト」
次なる映画は、「one day」
アン・ハサウェイが出ているので、見てみましたが、不思議な映画でした。
個人的な勝手な感想ですが、「ノルウェイの森」を連想しました。
あら筋もまったく違うのですが、・・・・・・・・。
ひとりの親友の死についての回想。
それだけではありませんが。
「ジョー・ブラックによろしく」のことも、連想。
まったく関連のない映画ですが。
しかし、外国人は、顔立ちが立派なので、だまされてしまいますが、やっていることは、幼稚というか、子どもっぽいと感じます。(悪い意味ではなくて)
そして、素朴。
攻撃的。
単純。
雑。
そこが、良いのですが。
男と女の間には、親友という言葉は、なりたつか?
それがテーマなんでしょうか。
通り道をぐるぐる、回り道をカラカラ、めぐりにめぐって、
ふたりは、やっとひとつになって・・・・・・・・・・・・・
でも、運命の女神は、意地悪でした。
・・・・・・・・・・・・・
監督は、ロネ・シェルフィグなのですが、女性と知って納得。
ディテールのつみかさねが、女性らしいなと思いました。
ロネ・シェルフィグは、『17歳の肖像』(An Education)は、2009年に作成しています。リン・バーバーの自叙伝を映画化した作品です。
サンダンス映画祭やトロント国際映画祭などで上映。第82回アカデミー賞では作品賞、主演女優賞、脚色賞にノミネートされています。
この作品は、これから見てみたいのですが、いまのところ、ゲオ、TSUTAYAでは発見できず。
まだまだ、探します。
これまた、題名が、educationでそのままで良いのに、「17歳の肖像」と、わけのわからない題名に変えられています。
ただ、この女優さん。
どこかで見たなあと、・・・・・・・・。
それに、私の好きな顔です。
考えて考えて・・・・・
思い出しました。
資料で確認すると、やはり。
「ドライブ」に出ていました。
キャリー・マリガンです。
彼女の独特のまなざしは、すごいです。トークなしでも、存在感出せる女優。
英国アカデミー賞 助演女優賞ノミネートです。
「ドライブ」は、私のもっとも好きなタイプの映画。
饒舌ではなく、静かに静かに、こころのなかに降りてくる、
でも、アクション映画なのです。
Lynn Barber
1961年のロンドン郊外。中流家庭の一人娘である16歳のジェニーは成績優秀、オックスフォード大学を目指す優等生だ。しかし彼女の憧れの地はパリで、勉強の合間にこっそりシャンソンのレコードを聴いては、厳しい父親に叱られる毎日だった。ある土砂降りの雨の日、傘を忘れてしまったジェニーはチェロケースを引っ張りながら下校していた。すると小粋な車から男性が声をかけてきた。「君のチェロが心配だな。君ごと家まで送ろうか?」これがデイヴィッドとの出会いだった。彼はジェニーとは倍以上に年が離れているが、教養豊かで会話も面白く、ジェニーを家まで送った際に、音楽会に誘ってくれた。デイヴィッドやその友人達が導いてくれる大人の世界にジェニーは目を輝かせるが、それは彼女にとってほろ苦い人生教育の始まりでもあった…。
・・・・・・・・・・・・・次に。
ビフォアサンライズと、ビフォアサンセット、見ました。
1995年ベルリン映画際銀熊賞。
最優秀監督賞=リチャード・リンクレイター。
まだ見ていませんが、ミッドナイトもあるらしいです。
西洋の映画らしい。
日本のシネマは、台詞が少ないところに、「間」を感じさせるところが美なのだけれども、
このシネマ、よく、喋る喋る。
まさに、西洋文化は、「言葉」ロゴス文化です。
・・・・・・
埋め尽くすように。
日本で言えば、床の間のあの何もない空間の美がここにはなくて、
すべてがぎっしりと、つめこまれているような、最近のモダンな若者夫婦が住む、
マンションの一室のようなシネマ。
聖書にも、言葉がまずありき、とある。
なにがなんでも、まず、言葉なのだった。
西洋人は真空を嫌うから。
とにかく、ああでもないこうでもないと、詮索に詮索をかさね、
お詫びと、喜びを語り合いながら、自分と相手の心の重さを計っていく・・・・
日本人の私には、ちょいと、疲れるけれども。
西洋のシネマだと思えば、なかなか、それなりに面白いと思った。
最後のシーンが好きだ。
それに、このような映画は、優しさが満ち満ちているので、女性は雰囲気に酔えるだろうと思う。
それが映画の楽しみでもありますから。
連想といえば、私の好みの例の「the night of the rodante」の
ダイアン・レインが、離婚した前夫との電話での喧嘩のあとに、
リチャード・ギアに、少し甘えながらも、
好きなレコードをかけながら、踊り始めるシーン。
このシーンを連想した。
ニーナ・シモンというのも良いと思う。
「最後の初恋」でも、食事のシーンで、
ダイナ・ワシントンのボーカルで、不思議なふたりの関係に、はいっていく、
重要なBGMの役割をはたしていたと思う。
もちろん、すべての文学・シネマ・においても、音楽の役割は大きい。もちろん、「ノルウェイの森」の最初のシーンにおける、ビートルズのその曲のごとく。
ピアノを弾きながら、ただ、芸術至上主義的に、演奏を完了させるのではなくて、
まるで、自分の人生そのもののように、ピアノの最中でも、
ステージをのんびり歩きながら、観客に I Iove Youと話しかけたり、
まったく違う曲を弾き始めたり・・・・・・・・・・・・・・・・
ふと、多様性という言葉も連想する。
白人と、黒人と、日本人。
アメリカ人と、ウィーン・・ドイツ人、フランス人。
人種のるつぼ。
フランス語にドイツ語に英語。
ウィーンでの、たった一夜のラブロマンスを、ふたりは、どう見ているのか。
なかなか、味のある、演出が光っていた。
会話の中に、少しだけ、仏教の話がでてきて、すぐに、違う話題に。
興味深く感じた。
ラストシーンを深くするこの音楽。
ニーナシモンといえば、この曲。
私の大好きな曲だ、たまたま、昨夜も、CCRの曲でアップしたけれども、これまた、シンクロ。
なんともいえない、曲の味がある。
日本でいえば、「間」を感じる。黒人のこの雰囲気は、白人には出せないものなのかもしれない。
Nina Simone - I put a spell on you
ちなみに、この曲。
「あなたをなんとか魔法でとりこにしたい」そんな意味だろうか。
・・・・・・・・・・・・
サラリーマン時代は仕事から夜遅く帰宅してレンタルビデオを見ると、すぐに眠くなる。
よっぽど好きな監督ものでないと、とりつかれたようには見れなかった気がする。
しかしながら。
こうして、退職後、ひとり仕事をしながら昔見れなかった映画、あるいは、見た映画でも再度見てみると、風景やら、音楽やらが、やたら耳と目に沁みて、シネマってやっぱり素晴らしいなあと思うことが多くなった。
1644年、22歳の駆け出しの劇作家モリエール(ロマン・デュリス)は前年に旗揚げした劇団の借金が膨れ上がり、債権者から追われていた。多額の借金に苦しむ彼は、金持ちの商人ジュルダン(ファブリス・ルキーニ)に窮地を救われる。借金の肩代わりと引き替えに、ジュルダンの演劇指南役として雇われることになったモリエールは……。
「モリエール」。吉本がこの精神を受けづいていると思うが、彼の苦悩や彼の恋心、旅のさまざまなるエピソードが素晴らしい。
ヒットはしなかったシネマだと思うが、当時のフランスの貴族の生活様式や考え方がよく理解できた。
ベルグソンではないが、「笑い」は人生において、涙とともに、重要なものだと思う。
生活は、「人を磨く塩」だと思う。
その生活も工夫しないとすぐに退屈になる。
それに喝を入れるもののひとつが「笑い」ということは誰しも納得がいくはず。
彼の理想とした涙がでるくらいの、悲劇に匹敵するような喜劇。
それの一こまをかいま見ることのできる映画。
自分が使用されている貴族の奥方との愛・恋。
一時はふたりで逃げようとしたが、それでも、人生の悲喜劇によって、彼は最後はひとりでまた旅に出て、旅芸人の道を歩み始めるところなんかはとっても良い。
やれやれ。
村上春樹の得意言葉ではないが、人生は、「やれやれ」と言いながら、前に進むしかないのかもしれない。
モリエール 恋こそ喜劇 [DVD]/ロマン・デュリス,ファブリス・ルキーニ,ラウラ・モランテ
¥4,935
Amazon.co.jp
日本貴族にも、平安の「夜ばい」恋がある。
確か、自分の夫であっても、「気に入った歌」をきかせてもらえなければ追い出し、違う男の歌に感銘して、床に入れたとか。
おんなとは、まことにおもしろい存在。
男は観念であり、女は存在だ。
このモリエールの活躍した時代、貴族のサロンではそうやって、会話の言葉を皆で楽しんでは生活を豊にしていたことが伺われる。
渡辺昇一氏は、日本の「詩歌」こそは、天皇から名も無き庶民までが平等でいることができた唯一の文化と書いたが、このモリエールの喜劇を見ると、やはり、そこまではいかなくても、貴族から一般平民までが「劇」を見る事が最高の歓びであり、その次元においては平等だったのかもしれない。
というよりもやはりヨーロッパは神の名のもとにおいて平等だったのだが。
言葉を重要し、貴族のひとつの教養として、男の武器として、女を口説いたり、あるいは殿方の心を奥方達が窺いしるひとつの女の武器としても、文章を鑑賞することのできる力があることは、凄いことだったのだ。
次なる映画。
「気になる関係」
愛と自由を食べてきた根無し草の男を慕う少年と女たち
女から女へ渡り歩き、車を盗む生活から抜け出せない男ブノワ。だがなぜか彼の女たちは彼を憎めないのだった。父が去り、うつ病の母の面倒と生活費を稼ぐために窃盗に深入りしているジミは、ダメダメ男のブノワを父親のように慕う。そしてブノワは、なりゆきとはいえ、少年の母親まで面倒を見るはめに…。ここで描かれているのは、男と少年が父子のように互いにかけがえのない存在となっていく過程であり、またふたりの女を愛するのは許されないことだとやっと気づいた男が勇断を迫られる、三角関係の愛の物語でもある。モントリオール世界映画祭正式出品作品。
オンナ好きで盗みを繰り返す根無し草のダメ男。彼を慕い、鬱病の母と暮らす舎弟の少年。どん底から抜け出しまっとうな人生を歩もうとする男たちの友情、恋、そして家族を描いた群像劇。
気になる関係 [DVD]/ピエール・リヴァード,ベネディクト・デカリー,ケヴィン・ノエル
¥3,990
Amazon.co.jp
いやあ、実に惹かれるろくでなし男。
日本の神経質でヒステリーな社会と比較するととても大胆な設定でおもしろい。
ろくでなし男は車を盗むことがいけないとはわかっているがその泥沼生活からなかなか抜け出せない。
棄てる事の出来ない彼の気質・性格が可愛い。
女と遊んでいてもきれいに前の彼女を棄てることができない。
つぎからつぎへと、おんながたまってくる。
自分を父親のように慕う手下のジミーが気になる。
オレのまねなんかしないで、まっとうになれと言うものの、ジミーと別れる事もどうしてもできない。
あげくのはては、新しい彼女のところへジミーを連れて行って、彼女から飽きられ、別れを切り出される。
このあたりは、女は、見事に、きっぱりと愛を切る。
ろくでなし男の、ブロアは、二人とも好きだと開き直るがおんなたちが納得するわけもない。
足の障害を持つ男友達のところへジミーとともに駆け込むブロア。
最後はジミーの母親までも面倒を見ようとし、ジミーとともに新しい仕事を見つけようともする。
男と女の世界にはあきらかに深い溝がある。
うまく描いている。
この映画のなかで一見ワルで、ろくでなしで、どうしようもないダメな男のブロアが一番、自在で自由に見えてくるのは不思議。
ピカソはいつもポケットにゴミやらくずやら、石ころやらをたくさんつめこんでは、友だちに言う。
「すてることができないんだ、それだけ」と。
ふたりの愛する女を棄てず、自分を慕う少年を棄てず、彼の母親を棄てず、いつも、悩んで困っている。
それでも、見て見ぬふりはできない魂の優しさを持っている。
元気をつける方法。
パンチをうつ。
ジミーはブロアを蹴る。顔にピンタする。体にぶつかっていく。じゃれあうようにして、体と体が、ひとつになる。笑いが生まれる。
昔、背中に友だちを乗せて闘う騎馬戦があり、友だちの芋虫のように並んだ背中の上に飛び乗る遊びがあったことを思い出す。
虚な言葉を超えて生が走り出す。
こんなろくでなし男が悪い男の筈がない。
次の映画。
「こわれゆく世界の中で」
若き建築家のウィルは、ガールフレンドのリヴとその娘と共に暮らしていたが、リヴの娘ビーは自閉症で、それが原因でウィルとリヴとの間に緊張が生まれていた。そんな時、キングス・クロスにあるウィルの事務所に強盗が入る。
ギリシア人には、「自分の父親をわかる子供は賢い」という諺が
あります。
専門家ではないので、詳しくは知りませんが、まだ一夫一妻制などない時代。
ふらりと男がふらりと好きな女といると子供ができる。そんなことだろうと思います。
男はまた、ふらりとどこかへ、行ってしまう。
村上龍もたしか、父親にできることは、たしか「いっしょに夕日を見て感動することだ」みたいなことを書いていた記憶がありますが、さだかではありません。
どの本だったかなあ、探し出せません。
父親なんてそんなものです。
西洋では、人間はman、つまり男ですから、キリストの男性のイメージと重なり合って、男の地位は日本なんかよりは、高く置かれているのかもしれません。
だから、フェミニズムなんかが、極端に反動として、盛んになったのかもね。
むづかしいところですが・・・
この映画の批評を読むと、犯罪者に少し甘いのでは、という読者からの批評が多かったですね。
それはそれとして、人って、映画を見るときにも、そんな「大人としての道徳みたいなもの」を、ものさしのようにして、見るのでしょうか。
この映画が日本の映画ならば、まだしも、サラエボがテーマなんですからね。
昔の少年法とか、赤線地帯とか、まだまだ、人間が、純な時代には、たとえ悪に手を染めてもそれをなんとか更生させたいという流れがあったのかもしれませんね。
今の現代の日本やアメリカあたりでは、あまりにも、おぞましく、残酷な事件が、若い少年の年齢でも平気で起きてしまうからこそ、そんなレヴューもあるのでしょう。
ミンゲラ監督。
2008年に癌で死んでいますね。
彼の作品は、かなり、複雑で、癌にでもなるような、胃痛が起きるような、不思議な映画が多いですね。
イングリッシュ・ペイシェントが好きだったので、その映画のビノシェと、コールド・マウンテンのジュード・ロウ。
まさに、シンクロです。
なにげなく借りてきたレンタルビデオなのに。

◎資料から
ジュード・ロウ(David Jude Heyworth Law, 1972年12月29日 - )は、イギリス出身の俳優。1999年の映画『リプリー』でアカデミー助演男優賞にノミネートされ、その美貌と才能で一躍名を馳せた。
ロンドンにて、教師をしていた両親の間に生まれる。実姉のナターシャは画家として活躍中。名前のジュードはビートルズの『ヘイ・ジュード』とトーマス・ハーディの小説『日陰者ジュード』にちなんで名付けられた[3]。現在、両親はフランスでドラマスクールを経営
ちなみに、この「リプリー」は
資料によると、
『リプリー』(原題: The Talented Mr. Ripley)は、1999年のアメリカ映画。原作は1960年公開のフランスとイタリアの合作映画『太陽がいっぱい』と同一であるパトリシア・ハイスミスの同名小説(原題:The Talented Mr. Ripley)だが、より原作に忠実なプロットとなっている。主人公トム・リプリーのその後を描いた作品として『リプリーズ・ゲーム』などが映画化されている。
第72回アカデミー賞脚色賞、助演男優賞、音楽賞、美術賞、衣装デザイン賞ノミネート。
「太陽がいっぱい」と聞くと、わくわくします。
それに、ミンゲラ監督。
大好きな「イングリッシュペイシェント」や「コールド・マウンテン」をつくっていますから、・・・・・・・・・
「イングリッシュペイシェント」 淀川さん絶賛の映画です。
『イングリッシュ・ペイシェント』(The English Patient)は、1996年公開のアメリカの恋愛映画。ブッカー賞を受賞したマイケル・オンダーチェの小説『イギリス人の患者』を原作として、アンソニー・ミンゲラが監督と脚色を兼任した。主演はレイフ・ファインズ、クリスティン・スコット・トーマス。製作会社はミラマックス。
第二次世界大戦時代の北アフリカを舞台に、戦争で傷を負った男と、人妻との不倫を描く。第69回アカデミー賞作品賞ならびに第54回ゴールデングローブ賞ドラマ部門作品賞受賞作品。
「コールド・マウンテン」、ニコールキッドマンも素晴しい演技でした。
私は個人的に、例えば、1000本の映画を見たとして、そのうちの、50本ほどのフェボリットの作品を繰り返し繰り返し、見る事が好きです。
きっと、それは、他の950本の映画は、良い意味で、良き思いで=950の別の人生を生きたというような感覚なのですが、この50本の大好きな繰りかえし見る映画は、いわば、
まさに、こころのサプリみたいなもの。
なきたい時。
笑たい時。
感動したい時。
何かをもう一度、資料として見たい時。
そんな時には、必須の作品群なのです。
2003年製作のアメリカ映画。
南北戦争を背景にした純愛ドラマ。原作はチャールズ・フレイジャーの同名小説。
この映画でレネー・ゼルウィガーがアカデミー助演女優賞やゴールデングローブ賞 助演女優賞、 英国アカデミー賞 助演女優賞などを受賞した。
ニコール・キッドマン
ジュード・ロウ
レネー・ゼルウィガー
なんせ、この三人が共演ですから。
大作は基本、あまり見ないのですが、これだけは、感動ものの大作です。
こうやって、ミンゲラ監督の作品を見直すと、
愛しい人が眠るまで Truly Madly Deeply (1991年)
最高の恋人 Mr. Wonderful (1993年)
イングリッシュ・ペイシェント The English Patient (1996年)
リプリー The Talented Mr. Ripley (1999年)
コールド マウンテン Cold Mountain (2003年)
こわれゆく世界の中で Breaking and Entering (2006年)
と、この順番で、作品ができております。「愛しい人が眠るまで」と
「愛しい人が眠るまで」
「最高の恋人」は
これが予告編です。
まだ見ていないので、いつかはきっと、・・・・・・・・。
話しは、それました。
「こわれゆく世界の中で」・・・です。
他の作品と比較すると、少し、納得がいかないところもないわけではありませんが、
それなりに楽しめます。
それにしても、ビノシェの存在感がすごいです。生活感がからだ中から出ていますから、おどろきますね。殺された夫への愛や、厳しい生きる環境に対する反動なのか、驚くほどの強さも感じます。
逆に言えば、彼女の美しい映画ばかり見ている人は、その演技にびっくりするのでは。
疲れ果てた女性を見事に演じています。
・・・・・・・・・・・
頭では、こんなことおかしいと思いつつも、自分の肌感覚に、ひさびさの愛される感覚にあえて溺れていく。
そして、また覚めた日常にもどるためにも。
素直になれない男女がミンゲラ監督の映画には多いですね。
知識があり、経験があり、金もある。
恋も知っている、美貌にも恵まれている、結婚もしている、それなのに、
何かが足りない。
いつも不安におののいている。
言葉が軽い。
言葉に重さがない。でも、それは悪いという意味ではなく、たぶん、そんなに口がうまいわけではないからでしょう。
口がうまくない、素朴な人は、なにかしゃべると、ある時、無意味なことを口走ったりもしますから。
しゃべらなければいいんですね。
体とからだが、あるわけですから。
ビーという自閉症の少女がでてきます。
自閉症の役者がでてくるとなにやら映画がひきしまりますね。
素直なことをストレートに言いにくい時代。単純が一番怖いんだという小林秀雄氏の言葉。たまねぎの皮のように、むいても、むいても、中の芯がでてこないということに心の本質があるということを、そろそろ、気がついてもいい頃でしょうか。
安易な心理学は安酒にも似ている。そんな言葉がありますね。
人の心をあれこれ、ほじくることはやめたいものですね。
手足があり、目があり、唇があり、人にはなんといっても、「からだ」があるわけですから、まずしっかり相手を見つめることから、はじめることが大事なんではないでしょうか。
名医は一目みりゃあ、病気かどうか、わかるんだ。小林秀雄。
・・・・・・・・・・・
ニコールキッドマン。素敵です。身長は180センチはあるでしょう。
NICOLE KIDMAN, movie star, Oscar winner and red-carpet regular, recently played a cow. Talk about your glamour roles.

トムクルーズより10cm背が高いニコールキッドマンの離婚する際の言葉。
「これでやっとハイヒールが履ける ニコール・キッドマン
FIN
「暮れ逢い」「髪結いの亭主」「卍 「ドライヴ」 レイチェル・マクアダムス ライアン・ゴズリング
書斎。
私もたいしたことのない普通の書斎を持っていますが、作家の書斎はいつも気になります。
渋沢竜彦氏の書斎は魅惑的でした。
奥様もきれいですね。
四ツ谷シモン氏も、彼への心のこもった言葉、語っております。
三島由紀夫氏も、彼がいたからこそ、日本文学はおもしろくなったと言い切っています。
たしかに、アカデミックな作家ばかりだと、貧相なる実しかなりませんし。・・・
あと。
北海道に本だけの斜塔をたてた草森伸一氏の書斎は、最初見たとき、あいた口がふさがらないほど、羨望を感じました。(松岡正剛氏の興味深い文章あり)

彼は、あまり知られていませんが、漫画にも造詣が深いです。

三島由紀夫氏の書斎。坂口安吾氏の反古だらけの、書斎というか、部屋。
オーディオ評論家の池田圭氏の書斎というか、オーディオルーム。
漫画家竹宮恵子のそれはそれは可愛い部屋。
(やはり、女性の部屋に対するこだわりと、男性のこだわりは、全然違うように感じます。渋沢竜彦氏は、部屋のホコリはまったく気にならないとどこかで書いていました。女性ならば、それは許せないでしょうから。)
男の書斎はいいものです。
自分だけの宇宙。
とある落語家。地下に、jazz専門の部屋を贅沢につくって、家族の誰も近づけないとか。
これまた、うらやましい限り。
松岡正剛氏のプランで、つくられた、松丸書店。
今から何年前になるでしょうか。
出来た時に、わざわざ、飛行機で、行ってきました。
残念ながら三年ほどで、閉店になりましたが、ちょっと、こんな書店はなかなかありません。
今、彼の偏愛する書物でぎっしりの書店。
松岡正剛氏は、よく工作舎にいたころ、資料館の本をきちんとかえさない人がいると、文句を言ったそうだ。これは、マナー的なことからではなく、本と本との間には「糸」があり、この本はこの本の隣に並べるという哲学を松岡氏は持っているかです。
本と本との間の、隠れた糸が四方八方にはりめぐらされていました。
アンチーク・ドールが、さりげなく置かれており、松岡正剛氏の哲学を応援しているようにも思えました。
五万冊の本をよく一冊一冊の糸を考えて、本人自身が並べたというが、驚愕するような
本屋。
ただ、本を売れれば良いということで、漫然と並べている本屋ではなく、もしも地球が滅んでも残されたわずかな人々に図書館が残されていれば人類の復活は著しく速くなるというそんな人類の英知の書物が、ここかしこに、糸と糸でつながれたように、ある思想はこの思想の影響、この詩人はこの詩人の影響とばかり、縦横に書物がクモの巣のようにはりめぐされていた、そんな不思議で、わくわくするような本屋でした。
ところで。
紀田順一郎氏の書斎。
彼は、そこに、大量の映画のフィルムをコレクションしては、ひとり、見ていたという。
(資料1です。小さな右の画像でみずらいかもしれません。)
資料1
当時は、昭和56年。私が、会社勤めを始めた頃ですので、ビデオレンタル屋もまだありません。
一度映画館で、見た映画は、もう手軽に、自分の部屋ではまったく見る事ができなかった時代。
ですので、紀田順一郎氏は、これだけのコレクションをしていたというのは、私から見て、羨望あるのみ。
八ミリで、暗い部屋で、カシャカシャリールをひとりまわしながら、映画の名作を見ながら、贅沢な時間をすごしたのでしょう。
それから、40年!!!!
いまや、ゲオやTSUTAYAに行けば、(マイナーな作品と、ずいぶん昔の作品をのぞけば)、ほぼ、
どんな映画でも、100円ほどで、借りる事ができる素晴しき時代になりました。
いいかげんなことを喋っては、テレビにでていた自称映画評論家たちは、消滅し、小難しい理屈で映画を語るインチキ評論家達の本も、今や売れることはありません。
自分の美意識のコンパスさえ、持つことを努力さへすれば、自分の好きな映画は何回でも、安価に見る事ができる時代。
素晴しいと思います。
ただ、淀川長治さんが書いていますように、映画ばっかり見ていては駄目、文学・音楽・絵画・歌舞伎など日本の芸能などなど、いろいろ勉強するようにすすめています。
というわけで。
今回は、ルコント監督。(淀川さんが絶賛していた監督です)
彼は、けっこう映画を撮っていますが、初期の作品が私は好きです。
その中でも、まずは、「暮れ逢い」ですが。
ツヴァイクの小説を映画化したもの。
テーマは忍ぶ恋。
現代のように簡単にメイクラブしてしまう時代だからこそ、忍ぶ恋のテーマが生きてきます。
「髪結いの亭主」「イヴォンヌの香り」など、恋愛映画を得意とするフランスのパトリス・ルコント監督が、自身初の英語劇として、第1次世界大戦前夜のドイツを舞台に、孤独を抱える若妻と、美しい青年の8年間にわたる純愛を描いた。1912年、初老の実業家カール・ホフマイスタ―の屋敷に、個人秘書として若く美しく、才気にあふれた青年フレドリックがやってくる。カールの若き妻ロットは、裕福で優しい夫や可愛い息子にも恵まれていたが、孤独を抱えており、フレドリックにひかれていく。ひとつ屋根の下で暮らすうち、フレドリックもまたロットにひかれるが、許されない恋であることから、2人はその思いを口にすることはなかった。しかし、フレドリックが南米に転勤することになり、それをきっかけに2人は胸にしまっていた互いの気持ちを告白。2年後にフレドリックが戻るまで、変わらぬ愛を誓うが……。
ルコント監督は、尊敬する映画監督として、なんといっても、ジュリアン・デュヴィヴィエとゴダールをあげています。
ですので、昨年封切りになった、この最新作の、「暮れ遭い 」が、デュヴイヴィエの「望郷」と、ゴダールの「勝手にしやがれ」みたいな感じになれば・・・と、語っています。
デュヴイヴィエの「望郷」
ルコントの愛するギャバンがペペルモコ役で、出ています。
ゴダールの「勝手にしやがれ」 ジャン・ポール・ベルモンドいいですね。フランスでは、アラン・ドロンよりも、当時、彼の方が、人気があったとか。・・・
この「勝手にしやがれ」は、あとの記事でも書いていますが、トリフォーが、原案を書いているんですね。
「白い恋人たち」
シネマ。トリフォーの、「白い恋人たち」
(私は、この映画を見る時には、いつも自分が子供の頃に、山のてっぺんからすべりおりた北海道の山山を連想できます。
もちろん、ころんでばかりですが・・・・
そして、そこで、ビニールシートをひいて友達と食べた、おにぎりやら、卵焼きやら、魚ソーセージの美味さったら・・・)
「勝手にしやがれ」
ジャン・ギャパンといえば、ルコント監督が愛しているのはよくわかりますが、
私も高校生時代でしたか、「シシリアン」や、「地下室のメロディ」見ました。
「シシリアン」 音楽が素晴しい。
「地下室のメロデイ」
なつかしいです。
この「地下室のメロデイ」は、見るたびに、マイルスのトランペットはなんと素晴しいと、感じます。
立川で働いていた頃、よる九時ぎりぎりに社員用のエレベーターに乗ったら、突然、ドアがしまった瞬間に、電気が消えてしまいました。これは怖かったです。慌てて、携帯をボケットから出すと、携帯が圏外。・・・・・・・・・・心臓ばくばく。これは心臓に悪いです。
結局、この恐怖の10分間、今でも強烈に脳裏にやきついています。
大声で、恥もなく、助けを呼んでいたら、警備員が気がついてくれて、合鍵にて、脱出成功。
汗だくでした。このシネマもまた、その思い出につらなります。
昔から私は閉所恐怖ですから、なるべくそれからは、エレベーターはさけて、階段を利用するようにしています。
あの恐怖は、今でも、覚えています。幸いに、警備員に見つけてもらって、翌日まで、そこで、寝てすごさなくてもよくなりましたが、この「死刑台のエレベーター」を見るたびに、その
エレベーターに閉じ込められる時の閉塞感を、思い出してしまいます。
「死刑台のエレベケーター」傑作です。マイルスデイヴィスがフランスで、jazzを映画音楽に使ったのは初めてのことではないでしょうか。
ルコント監督が、尊敬する監督、俳優達。
・・・・・・・・
ルコントが、ペペルモコ役のギャバンに見ていたもの。
「勝手にしやがれ」のゴダールの映画手法(たしか、淀川さんは、美しい映画を壊したのはゴダールと、どこかで書いていたような気がしますが、彼の尊敬するルコント監督が、そのゴダールを敬愛していたとは、・・・・・・・・興味ぶかいです。)
そのあたりは、気になります。記憶力があまりないので、こんどじっくり調べることにしましょう。
「髪結いの亭主」。
ルコントの代表作。誰しもが見たとは思いますが。
ルコントは、実は自分でカメラをまわしています。
このようなことは、アメリカハリウッドでは、まず、ないでしょう。
ゴダールも四人ほどで、映画を撮っていたと書いていますから。
やはり、少人数でこつこつ、つくりあげていくプロジェクトでなければ、できないことですね。
ルコントが一度は、アメリカハリウッドに渡って、また、フランスにもどったのもわかるような気がします。
■パトリス・ルコント監督プロフィール Patrice Leconte, 1947年11月12日 パリ生まれ。IDHEC(L’Institut des hautes études cinématographiques)卒業後漫画雑誌『Pilote』のアシスタント、バンド・デシネの漫画家またイラストレーターとしてで働く。『仕立て屋の恋』(’89)、『リディキュール』(’96)でカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、『フェリックスとローラ』(’00)、『親密すぎるうちあけ話』(’04)がベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品。『列車に乗った男』(’02)はヴェネツィア国際映画祭のコンペで観客賞受賞。『リディキュール』で第22回(1996年度)セザール賞作品賞と監督賞を受賞している。コメディ、ドラマ、ラブストーリー、アクションまで幅広いジャンルの映画を製作している。© 2014 by Peter Brune
シネマ。「髪結いの亭主」
敬愛する淀川さんの尊敬するルコント監督の作品。
不思議で、謎のシネマ。
女性はいつも笑声の絶えないアリスなのですが、このシネマでは、もうひとつの、
魔女的な魅惑の理想の女性がでてきます。きっと、ルコント監督の理想のイメージが かさなっているのかもしれません。
この映画。淀川さんの顔がいつもいつも、連想されます。
彼にとって、生きるということは、シネマとともに、シネマを見ることだったのですから。
ところで、このルコント監督の映画。
個人的には、「タンゴ」「仕立て屋の恋」「髪結いの亭主」が好きです。「イヴォンヌの香り」もまた、素晴しいです。
彼の作品をよくよく見れば、わかるのですが、彼の理想の女性観・・・
それが、自分の気質と合うと思っています。
今はやりの、主義主張をアッピールする女性、頭の良さをガンガン見せるようなタイプの女性ではありません。
なんというか。
女そのもの。女の原型というか、善くも悪くも「男性が女性として、尊敬し、憧れ、また、くりかえし愛することのできる女性」、・・・
「永遠の女性」・・・そんな感じがあって、好きです。
ジョルジュ・バタイユが、エロティシズムは、モノに近づけば近づくほど高まる、と書いていますが、お喋りな、男性でも女性でも、色気がなくなっていくということですね。
たとえば、
ジョージ・ハリソンの「something」がこのパティ・ボイドに捧げられていた・・・
ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンの前妻として著名である。ハリスンの「サムシング」および「フォー・ユー・ブルー」、クラプトンの「いとしのレイラ」、「ワンダフル・トゥナイト」 や「ベル・ボトム・ブルース」といったラブソングにインスピレーションを与えたとされる。
いとしのレイラ

パティ・ボイド自伝 ワンダフル・トゥディ/パティ ボイド
¥2,940
Amazon.co.jp
確か、ダリもそうでしたね。ガラという他人の奥様を自分のものにしてしまい、自分の芸術に昇華してしまって、もう誰にも真似できない愛し方をする。・・・・
岡本かの子も、ふたりの若い男達と、旦那と一緒にくらしていた。
谷崎潤一郎氏が、妻の妹に、惚れて、その刺激からインスピレーションをもらって、
「ナオミ」つまり、「痴人の愛」を完成させたとか。・・・・
「痴人の愛」は、世界の若者にも、インスピレーションをひろげています。
たとえば、このクリップ。
自分の好きになった相手の女性がどんなに悪魔的な女であろうと、自分ののめり込む気持ちを押さえることはできない、そんな男性の心理を徹底して掘り下げていますが、
谷崎潤一郎の妻の妹に対する実際の気持ちが投影されているからこそ、
深くて、感動する作品にしあがっています。
晩年の谷崎潤一郎の作品にも、それらのエッセンスが、強く感じられますね。
儒教的な視点から見ると、とても、まともな人間とは思えない行為。
しかしながら。
芸術家は、そこを超えて、美=自分なりの宇宙を、つくりあげようとしますから。
それだからこそ、見ている人、読んだ人に、とてつもない感銘を与えるのだと、私は信じます。
『卍』もそうですね。
『卍』(まんじ)は、1928年に雑誌『改造』に発表された谷崎潤一郎の長編小説が原作ですが、
三島由紀夫のたしか「春子」同様に、女性と女性の関係を、微妙な観点から書いています。
どうやって、谷崎がこの小説のモチーフを拾って来たのかは、わかりませんが、
あれだけ、人間洞察力のある作家ですから、普段から、身の回りの人間を深く観察することによって、ヒントをもらって、書いたのだと思います。
『卍』
この、『卍』。
よくできた映画です。
くりかえし見ても飽きません。
監督の増村保造。
卍や、上記の「痴人の愛」の他に、三島由紀夫氏の「音楽」や、川端康成氏の「千羽鶴」もつくっているはずです。
異性への強い憧れ。・・・・・・特に男性がひとりの女性に対する強烈な憧れ。
artistの世界では、他人の妻に対しての憧れそして、あるいは、ひとりの女性の強い魅力、それをインスピレーションとして
作品をつくりあげていくというのは限りなく事例がおおいですね。
女性というのは、良く言われますが、マリア型とヴィーナス型がいると。
マリア型は、子供の愛し方、聖母マリアのイメージで母親像の清らかなイメージがあります。
ヴィーナスつまり、アフロディッテ型は、子供を生む事を拒否し、男から男へと自由奔放に蝶飛する女達。
ある作家が、家庭というものは女性を美しくはしないと書いていましたが、それはそれである意味あたっているでしょうね。
世俗の現実にどっぷりつかっていたら、美意識がなくなっていくのは、男も女も同じです。
(数十年も自分の伴侶を見つめ続ける人が家庭の天才です。
人は見つめられてこそ磨かれて行く訳ですから。)
ピカソの奥様、何人目だったか、artはエニグマなのよ、と言ったとか。
エニグマ・・・謎。 謎があるから、この世は楽しい。そこに宇宙がひらける。想像力の跋扈する世界です。
道徳はこの世の乱れを整え人々が暮らしやすくするためのもので必須なものですが、芸術もまた小林秀雄氏が、書いているように「歴史に埋もれたる人々の魂を救う網をつくりだすもの」。
そして、オーラを発する女性の存在はかずかずの、名作の触媒として、芸術家たちの心を虜にしてきたことも事実です。
たとえば、ルドン。
ルドンの絵にはあまり、女性は登場しないように思われていますが、
「ベアトリーチェ」とはダンテの「神曲」に出てくる女性で、愛を象徴する存在として神聖化された「永遠の淑女」がでてきます。
若い頃の黒色だらけの「黒の時代」をへて、晩年、長男の死を乗り越えて、次男が誕生し、また、個展開催や、作品が、国に買い上げされたりして、しだいに、色相が豊かになっていきます。
色というのは、心の部屋を暗示させる、不思議なひとつのキーワードです。
ルドンの理想の女性像のイメージから描いたのでしょうか。「ベアトリーチェ」

音楽は夜の芸術であり、夢の芸術だ。
絵画は太陽の芸術であり、光の芸術だ。 ルドン
「黒の時代」・・・
ココ・シャネルとストラヴィンスキーの恋ではありませんが、愛や、恋は、作品に艶を与えますね。
画家とモデルというのは実に不思議な関係です。
あるいは、作家と強烈なるオーラを放つ女性。・・・・・
モデルで絵の価値がぐっとあがった作家もいます。
というよりも、モデルが良いと、パッションが増大するんでしょうね。
その意味でも特に、女性という生き物はたいしたものです。
男を振り回し、男に情熱を沸き起こし、(子どもを産めない)男に作品を産ませる。
その分、飽きられて忘れられてしまうのも女性ですが。・・・・・人生は残酷な面もまたありますね。
ルコントから、谷崎、そして、ルドンときてしまいましたが。・・・
彼の馬。
じつにいいです。
さまざまな影響受けました。
このオレンジ。
光の捉え方が印象派とはまったく違う。
モローとそのあたりが似ているのです。
そのまま目に見えたように描くことからの、
一歩前にコマの進め方がそこにはあります。
人間は、脳でつくりだしたこの世に生きている以上、とにかく、好きなことを好きなだけしている時こそが、一番の幸福ということですし、それが出来ない人は、一生、脳で発生する、愚痴不満の時間と空間のなかに、ひとり、おいてきぼりされるというわけです。
これは苦しみ以外のなにものでもないですね。
最初の写真ですが、紀田順一郎氏の、部屋のなかで、本を探したり、映画のフィルムをまわしたり、・・・・・・彼の「幸福」を写真から感じます。


これまで、書いてきましたように、ルコント監督が、ゴダールに出会い、ギャバンに出会って来たように、あるいは、谷崎潤一郎が、千代夫人や、その妹に出会ったように、・・・・・・・・・・・・・人生は不思議な出会いに、満ち満ちています。
作家と、モデルの関係は、「名作」の誕生という観点からも、パッションの放出という観点から見ても、ある意味、運命的な、関係です。
そこに、普通の因果を超えた、運命的なシンクロ二シティを私は、感じます。つまり、偶然ではない必然の複数の糸!!!!
最初の「死刑台のエレベーター」。
マイルス・ディヴィスが、ミュートで、映画音楽をつくっているのですが、
彼のシンクロニシティについて、考えてみました。
ユングは、ノーベル物理学賞受賞理論物理学者ヴォルフガング・パウリと後に1932年から1958年までパウリ=ユング書簡と呼ばれるパウリの夢とそれに対するユングの解釈におけるシンクロニシティの議論をし、それをまとめて共著とした"Atom and Archetype:The Pauli/jung Letters, 1932 - 1958"(『原子と元型』)を出版している。[1]
同書のユングの説明によると、人々の心(複数の人々の心)にあるファンタズム(夢・ヴィジョン)と主観は同時的に起きているのであって、ファンタズムが起きている時には互いの心に(ファンタズムが)同時的に起きていることに気づいていないが、後になって客観的な出来事が、多かれ少なかれ同時的に、離れた場所ですら起きたと判明することになり、それについて(客観的な出来事が)シンクロ的に起きたのだと確信的に考えることになるという[2]。
なお、ユングは様々な著書で、人間の意識同士は実は、集合的無意識(collective unconscious)によって、そもそも交流しているということは述べている。集合的無意識が、人々の心、人々の主観的な意識に入ってゆく過程を、ユングは「個性化」と名付けた。またユングは個々の人の意識が集合的無意識へと反映されるプロセスもあるとしている。人の心は表面的には個別的であるかのように見えてはいても、実は根本的には交流しているのだとしているのである。
ユングは、coincidences コインシデンスについても、(その全てではないにせよ、少なくとも一部は)単なる「偶然」によって起きているのではなく、co-inciding(共に、出来事を起こすこと)、と見なしたのである。
このマイルスと、コルトレーンの二人の競演している貴重なるクリップを見ていて、いろいろ考えていた。
ふたりとも、同じ年に生まれている。1926年。
この二人がいなければ、現代のjazzもないくらいな存在であることは私のようなjazzにさほど詳しくない者でも知っている。
このような偶然。意味ある偶然(ユング)、複数の必然の運命の糸、は、私たちの、身近な生活のなかにも、にもたくさんあるのではないだろうか。
・・・・・むかしむかし。
高校生の頃、仲良しとともに、札幌に行く時に、朝みんなでカレーの立ち食いをして出かけた。札幌で、昼ご飯が面倒ということで、またまた、カレー。そのときに、ひょっとして、家でカレーじゃぁないかという、ふと、そんなことを強く思ったのだった。
案の定、家にもどって、母親が今日はカレーだよ、と言った時に、ひどく、興奮したことを思い出す。
つまらない偶然なんだろうけれど、いつまでも、覚えている、一日に三回のカレーライスだった。
・・・・・・むかしむかし。
埼玉の川越に出張した時。
電車の中で、昔大学生の頃の、友達Tのことをたまたま、考えていた。
「あいつとは、もう15年も会っていないなあ、何やってんだろうか」と。
静岡に実家がある男で、昔、そこへ泊まりにいったこともある。
シェークスピアの研究をしていた他の友達と仲が良かったのだけれど、三人で、よく茶を飲んだことも、多く、一度は、私が映画研究会にいたので、その二人の男性と、友人の女性に頼んで、30分ほどの、私が監督をして、八ミリ映画を作った事があったのだった。
「夏」という題名にした。
ふたりの仲の良い男性と、そこに現われた、ひとりの女性に対する複雑な気持ちを
自分なりにつくったのです。
その映画のBGMは、もちろん、マイルスの「サマータイム」。
そんなことを考えながら、本川越の駅に降り立った。
初めての場所だったので、駅の近くの本屋、こじんまりとした小さな本屋にまず入った。
(私は出張の時には、かならず、そのおりたった地の本屋や古本屋をまず見てみるという、癖があります。駅前にそれらがない場合は、しょうがありませんが。)
あまり時間がなかったので、10分ほど、文庫を見て一冊選んで、カウンターに行った。
男性が下を向きながら、ありがとうございますと言いながら、本にブックカバーをつけてくれた。
私は、彼のうつむいた顔をぼんやりと見ていて、何も考えていなかった。
釣り銭をもらい、ふと、彼の顔を見た。
Tだった。
この時の驚愕の瞬間だけは今でもはっきり覚えている!!!
神奈川の大学で一緒に学び、遊び、お互いに、15年前に卒業後、別々の道を歩いていた。
私は横浜から、北海道、そして、北海道から、池袋に転勤。
彼は、大学卒業後、まったくの音信不通。
それが、いくら日本は狭いとは言え、たまたま、本川越の小さな本屋のカウンターでばったり出会う・・・・そんなことがあるのだろうか・・・
彼もまた、目を丸くさせて、口をあんぐりあけて、「おまえか・・」と呟くのが 精一杯。
その後、喫茶店で、おちあう約束をして、懐かしき話をした。
・・・・・・・・・
このようなことは、思い出せば他にも数えきれないくらいある。この記事を読んでいただいてる方にも、きっとたくさんあると思います。
偶然。いや、複数の必然の糸によって、そこに導きだされるように操られる運命の糸。
昔の偉い哲学者も、この宇宙の混沌カオスというのは、たんなるランダムなのだけれども、その中に、不思議と、サクランボの数珠つながりみたいに、同じようなことが連鎖して起きるそんな力があると予言している。
めったにおこらないことは、二回三回続けて起こるというではありませんか。
・・・・・・・・
昔、とある本で読んだこと。
ネプラスカ州内のビアトリスという町だったか、そこで週1、合唱団として練習をしていた10人の男女。
その日だけ、たまたま、全員が遅刻している。
午後、7時半に集合ということになっていて、普段の日は、ほとんど遅刻も少なく練習がおこなわれるのだけれど、その日だけ、全員が遅刻したという。
確率的に、このような全員の遅刻というのは、数億分の1の可能性しかないという。
そして、さらに、意味ある偶然(ユング)、だったのが、
その日の、7時25分に、その練習の行なわれる筈の教会で爆発事故があり、教会が全壊していることだ。
これは事実であり、記録も残されている。
しかしながら。
確かに、なにやら不快な感覚。気持ちの悪い感じ。行きたくないという無意識の感情というものが、生まれていたのかもしれない。
記憶ははっきりしていないけれども、確か、アイロンの仕事がおくれていたとか、テレビのスポーツ中継が後少しで終わるはずだったからとか、自動車のエンジンがなかなかかからなかったとか・・・・・・・・・・そんな複雑なる複数の糸によって、・・・命が助かる。
不思議なこともあるものだ。
しかも、全員。たまたま。
ライオネル・ワトソンによれば、ある電車事故があり、その事故の7日前、14日前、21日前、28日前というふうに、乗車記録を調べた人がいたらしく、それを何年も何年も記録にとっていたのだが、やはり、事故の日の乗車の人数は普段よりも、かなり少ないと記録が物語っていたという。
人間には、そのような危機・危険から身を守るための、なにか力みたいなものがあるのだろうと思う。原始の時代にはその力は、必須なものだったから、皆が持っていたけれども、現代人のなかでは、限られた人だけのものになっていたのか、あるいは、カオスのなかの、意味ある偶然のサクランボの数珠の連鎖を、無意識として感じ取り、その事故から、逃避したのかもしれない。
ということは、さきほどの作家とモデルの話しにも、もどりますが、
普段から、作品のことばかり考えている、そして、それらのシードが、無意識界におりている人達にとってみれば、
出会う人たちや、出来事は、自分みずからで、ひきよせていることになります。
わたしは、このような話が好きだ。
なんでも、かんでも、ただ金金、合理的に分析、すべてのことを理解しているような顔をして、暮らしている人には興味はないし、話していても、つまらない。
まだまだ、人間には理解不能、科学の力でも、とうてい把握できないだろう「意味ある偶然(ユング) 」というものがあるのだと思う。
ユングは、それを有名な言葉で、「シンロクニシティ」と表して、ノーベル物理学賞をとったパウリと一緒に研究論文をだしている。
考えれば、考えれるほど、この世は「シンロクニシティ」で、それが、小さなものであっても、大きなものであっても、いっぱいである。
今ここに「在る」自分の存在でさへ、「シンロクニシティ」の力によって、生かされている、そう感じる今日この頃。
マイルスとコルトレーン。この奇跡のような、ふたりが、1926年に生まれた・・・そして、同じjazzの路を歩み始めて行く、というのはまことにすごいことだと思う。そして、その赤子のふたりが、いずれ、jazzを目指して、歩み始め、
実際に一緒に演奏をし始めたということ、今更ながら、感動した。
そこには、きっと、複雑に絡み合う、必然の糸がたくさんあるはず。
ところで映画。
ルコントを語るうちに、こんなところまで、きてしまいました。
最後に、好きな俳優。ライアン・ゴスリングのことを少し。
男性作家が、いつも心のなかで、おい続ける永遠の女性像。
ルコントの作品のなかにおける、無名の女優達にも、個人的にわたしは、
ルコントの理想の女性像を感じます。
その逆に。
私が好きな、永遠の男性像のひとり。
それが、彼です。ライアン・ゴスリング。
ジェームズ・ディーンのように、はにかみ、無口で、自分が思い立った事や、好きな人のためであれば、どんなことでもやりのける。
「きみに読む物語」の主人公は、適役でした。
現実的で、アリスのように、うさぎを追いかけては、あちこち、心の迷いとともに、運命の糸にひきまわされてしまう彼女。
彼女を思う気持ちが、ひとすじで、まったくそれ以外のことに動じない強い心のライアン・ゴスリング。
彼の映画は、まだまだ、全部見ていませんが、この二作は、とにかく、彼の魅力が上手にひきだされていると思います。
ライアン・ゴスリングは、2017年、「ブレードランナー2」に抜擢されていますので、
今から、楽しみです。
Rachel McAdams Audition Tape
ライアン・ゴスリング。
はにかむところがすごくチャーミングというか、無口がすごく似合う男。
もちろん、現実な彼は、生きていくためには、講演をしたりすることもあるだろうし、ファンへのリップサービスもあるだろうし、妻や恋人のための、リップサービスも欠かさないような男の優しい気質を感じる。
でも、それでも、彼は寡黙が似合うし、そのようなイメージをどうしても私のようなファンとしては持ってしまう。
「一途」とか、「信念」とかを感じさせる、俳優。
私の一番弱いタイプの俳優。
その彼の寡黙なところが、「きみに読む物語」以上に、さらに引き出されているシネマといえば。
「ドライブ」だろう。
男性のための男性による男性だけの映画。
男の本質がよく描かれている。
寡黙=男の色気という言葉を思い出す。
「君に読む物語」でも、ライアン・ゴスリングの「相手を一心不乱に愛するひたむきさ」の演技が光っていたが、もともと、何があってもやるといったらやる、という男性の遺伝子の一番良いところを持っている役者。
ある意味、顔の雰囲気は違うが、「サムライ」のアラン・ドロンをも連想する。
あるいは、昔の任侠映画。
死ぬとわかっていても、負けるとわかっていても、好きな人のために死すことを覚悟で、
勝負にでる・・・・泣ける映画。
私自身、寡黙などまったく似合わない人間なのでライアン・ゴスリングのこの寡黙さには憧れる。
映画のなかだけの男の中の男、いいではありませんか。
たしかに、彼の寡黙のイメージはあくまでも、私のイメージであり、現実の彼は、実に、スムーズに言葉をあやつる男性俳優です。
でも、やっぱり、クールだと思います。
映画からたくさんの愛をもらってください 淀川長治
FIN
愛を描くシャガールがピカソは愛を知らないと言った・・・光 恋と笑 横尾忠則
やはり、ぶったおれてしずかにしていると映画よりも、音楽や本になってしまいます。
ここ最近見た映画は、マルチェロ・マストロヤンニとソフィア・ローレンの映画を比較しながら、笑いながら、泣きながら、考えていました。
ひとつは
「過去現在未来」。
昔のイタリア映画はなんと楽しく、笑えるのでしょうか。とにかくたくましい。
「ナポリのアデリーナ」
復員後失業中の夫カルミネ(マルチェロ・マストロヤンニ)に代わって妻アデリーナ(ソフィア・ローレン )は闇タバコの商売で一家を支えていた。しかし未払いの罰金を徴収に来た役人を追い払った為に逮捕されることに 、相談した弁護士から「妊婦は出産後半年間まで逮捕されない」と助言され夫婦は子作りに励むのだが…
「ミラノのアンナ」
社長夫人のアンナはパーティーで知り合った青年レンツォとドライブに出かけた。 ドライブ中アンナは裕福ながらも心が満たされない不満をレンツォにぶつけて、 二人で遠くへ行こうとレンツォを誘う。
「ローマのマーラ」
神学生のヴィンチェンツォは休暇のため祖父母のいるローマのマンションに遊びに来た。 ヴィンチェンツォは隣に住むコールガールのマーラに一目惚れするが、祖母はマーラを嫌い悪態をつく 。ヴィンチェンツォと祖母は喧嘩をして仕舞いには神学生を辞めるとまで言い出す。 祖母は孫を説得して欲しいとマーラに頼み込み、頼まれたマーラは祖母にある約束をする。
妊娠していれば、警察にぶちこまれなくてすむ。
それなのに、妊娠していないということがばれる。
そこで、ローレンは、最近元気のないダンナの親友に子づくりをしてくれと
必死に頼む・・・刑務所にぜったいに生きたくないからだ。子どもが6人もいるというのに。
笑える。
しかし、最後には、そのぎりぎりの刑務所にははいりたくないという彼女の心が、泣きながら、やっぱり、ダンナでなければ嫌だと呟かせる・・・・・・笑って泣けるシーン。
マルチェロの本を30年前頃に神田で手に入れた。
理由はなく、ただ、安かったから、リュックにつめこんでたまにペラペラ見ていた。
その彼が、これだけ今のイタリアを代表する俳優になるとは、まったく想像していなかった。
若い頃からアニタ・エクバーグ、ソフィア・ローレン、フェイ・ダナウェイ、カトリーヌ・ドヌーヴなど多くの女優などと浮名を流したが、結婚は生涯で1度、1948年にイタリア人女優のフローラ・カラベッラとのみであった。しかし後年マストロヤンニはマスコミのインタビューで、「本当に自分が心底愛した女はエクバーグとドヌーブの2人だけだった」と語った。
子供
妻のフローラとの間に一女をもうけたほか、長年の愛人でフランス人女優のカトリーヌ・ドヌーヴとの間にも一女(女優のキアラ・マストロヤンニ)をもうけている。なお、『プレタポルテ』(1994年)など複数の作品でキアラと共演を行った上、ドヌーブとキアラの母子は晩年のマストロヤンニの看護も行い、臨終にも立会っている。

昨日、「プレタポルテ」は注文した。楽しみである。
もうひとつは、「ひまわり」。何回みたことか・・・
日本人は、良くも悪くも、見た目=美=あはれ=姿(小林秀雄の言葉)を大切にするから、
この「過去現在未来」よりは、「ひまわり」の方が、好きな人が多いと思う。
しかしながら。
人生はとは、ひとつのコインの裏表なのだと思う。
したたかでなければ人生は生きては行けないが、純粋がなければ生きて行く意味もない。
このふたつの映画を、同じ俳優つまりソフィア・ローレンと、マルチェロ・マストロヤンニで、見るからこそ、楽しく、また、興味深い。
ソフィア・ローレンは、先日、日本に来ていて、「ひまわり」を見て泣いている人を見て、ひどく感動していた。かつて、同じような戦争体験をし、貧しく、悲惨な生活をおくってきた国民同士だからこその、共感かもしれない。
淀川さんは映画をつうじて、ものを「考えた」人だとおもう。
マックの「think different 」ではないけれど、いくらたくさんの映画をただ見ても、たくさんの本を速読しても、「考える」力は養えない。
やはり、渡部昇一氏が言うように、真夜中に、ひとり、「ウィスキーをちびちびやるようにしてモノをコトを考えている人」が、すごい人なのだとおもう。
あるいは、無名であっても、ひとりしずかに日曜日にでも絵を描くためにキャンバスを向かうような人・・・・・・対象そのものを静かに観察して、手指で脳で感じたことを、写して行く訓練をする人・・・・・・ 。
だから、私はいつもいきあたりばったりに、若き頃に乱読・乱鑑賞・乱試聴した文学映画音楽漫画絵画をその日の自分の胃袋の好き嫌い・体調にあわせて、食べて行く・・・。
朝こんな曲を聴いて、いろいろ考えていた。
「待ちくたびれた日曜日」
(作詞:小園江圭子、作曲:村井邦彦)
今。こんな歌は、若い人はどういうふうに聞くのだろうか?
個人的には、もしも、私が女だったら、こんなように相手を迎えてあげたいなと
おもう。
「あなたの好きなアネモネを、さかしておいたのに」
「お菓子もこんがりやきあがり、・・・」
時代的には、おそらく、男性が威張っていた??時代だから、こんなつつまやかしい女性の歌ができたのだろうが、個人的にはいつの時代でも、このような女性というか、人は、愛されるのだとおもう。
この歌は、「去年の人とまた比べている」と女性の心の変化を強調しているけれども、
歌っている歌手が、まったくそのタイプとは逆の、中森明菜や百恵ちゃんだからいいのだと思う。
すれっからしの、ヤンキーだったら、聞きたくもない歌だ。
この後、しだいに、「男に尽くす女の像」が、その逆に、「おんなに尽くす男性の像」に人気がでてきたように思える。しかしながら、個人的な意見だけれども、男も女も、
やはり、わがままで自己中心的な人はいつか滅んで行く・・・・・・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・
こんなアホなことを考えているうちに、時間はどんどんたっていく。
朝は、光が、入る時間がきまっているので、やることが多いのだから、・・・
今、一番興味のある「詩」と、「画像」のコラージュについて考えながら、
緑茶をがんがん飲む。アトリエの窓から入る自然光は二時間くらいだから、少なくても、
一時間は描きたい。
・・・
机の隣に積んである数百冊の本を、すこしずつ、写真をとったり、読んだり、イメージしたり、付箋をはりつけたり、そのまま、アカボールペンでカンガンと記録したり、・・・。
趣味のレコードは、井上陽水を今は聞いている。
「飾りじゃないのよ 涙は」
私は泣いた事がない
本当の恋をしたことがない
誰の前でもひとりきりでも
瞳の奥の涙はかくしていたから
いつか恋人にあえる時
私の世界が変わる時
私、泣いたりするじゃないかと感じている
きっと泣いたりするんじゃないかと感じている。
この「感じている」というのがいいですね。
中森明菜のバージョンも好きですが、ききくらべると最高です。

ブラッジャックのピノコが好きなので、朝からめずらしく着物姿の彼女がかわいいな、と見ていたら、朝曇っていた岩見沢市、なんと昼頃から晴れてきた。雑用も終わっていたので、この「奇跡のような光」を自分のものにしたいというムラムラとした欲望が・・・
全身にこの光をあびたい!!!!!!!!!
(安スマホですので、360角度にひろがる、この地球の丸さと円球のひかりの渦は感じられないとおもいますが・・・北欧ではたまにこんな日があります。雪の粉がきらきらしています。)



正月。
昨日は、すばらしき晴れでした。
光が、岩見沢市のすみずみにまで、溢れ、雪やつららや屋根から舞い散る雪の粉までが、ひかりかがやき、もうこれは「すべてオレのものだ」とばかり、散歩していました。
自然の素晴しいところは、心の中や魂のなかで、感動した美しさは、そのままそこに残りますから、そのような気持ちの余裕がある人ならば、私と同じような気持ちで昨日をすごしたとおもいます。
ひさびさに、血圧検査。
異常なし。
これにすこし油断して、好きな珈琲をちょっぴり飲みながら、大好きな多数手観音像の絵を描いていました。
幸福な時です。
しかも。散歩の途中でいつもの小さな本屋に寄ると、
芸術新潮 2016年 01 月号 [雑誌]/新潮社
¥1,550
Amazon.co.jp
が並んでいるでは在りませんか。一冊のみ。
あわてて、買いました。雪がふりはじめていましたから、大切にリュックにいれて・・・・。
ぬれないように。
そして、光あふるるココ北欧の自然の中の散策というか、ほっつきあるきが、二時間ほどで完了したあと、ちらり、と見て、そのまま書庫へ。
あとで、じっくり見る予定。楽しみ。
最近はまっている、「すんきそば」。
買うと、バカみたいに高いので、自分で、すんきを作っては、あじを確かめていましたが、キャベツでもいけますね。
昨日、すんきのキャベツで、焼きそばをつくりましたが、美味いコト美味い事!!!!!!!
31日に、はやめに、神社へ行くと、誰もいなかったので、さすが田舎。
12時近くになって再度、でかけると、そろそろ人のではいりが。
神社に入ったら、まず御手洗(みたらし,水舎(みずや)とも)で左手から手を洗い、正式には手 ... 拍一礼」といって、二回おじぎをした後、2回柏手を打って、最後にもう1回おじき。
といっても、むちゃくちゃ流です。
心をこめましたが。
おみくじなどをひいて、賽銭。
好きなモーツアルトとバッハざんまいの元旦。
雪かきはしましたが、おせち料理は三日分つくりましたので、
三日間は、好きなことをやらせてもらいます。
すこし、テレビをつけると。やはり。げんなり・・・・・・・・・・
学生マラソン以外は、まったく駄目。
駄目な理由を業界人が話し合っていたが、まるで、漫才。
世界はもうすでに100チャンネルを超えたメディアをたくさん持っているわけだから、
もう「きめられた」「限定された」「つまらん」テレビは見たくない。
どこのチャンネルを見ても同じ顔、顔。
はやく100チャンネルになって、好きな番組だけを特化してみたい。(ネットが今そのかわりをしてくれていますが、・・・・・)
個人的には、「ニュース番組」を深くみたい。
しかも、意図的に編集されたものではなくて、事実に肉薄するもの。
共◎通信ニュースなんか、あれなにかと思いますね。朝日同様ぜったいに信じられないメディア。
野球賭博。
相撲の暴力。
サッカーの世界の詐欺。
自民の油断と分裂。
ロシアの好き放題、中国の好き放題。
アメリカの世界の警察放棄。
埋もれて行く国。
巨大化していく台風に、水害に、干害。
絶滅種。外来種にやられっぱなしの日本種。
経済が人生の基本だというのは理解できなくもないけれども、そのために、いろいろなことが
犠牲になる。
マスゴミなどは、10年くらい前には、「フリー」「アルバイト」的な若者の生き方を絶賛して、起業にしばられない新しい生き方とか言って、もてはやしてから、はや10年。
今や、マスゴミが、なぜ非正規社員が増えないんだとか言っている。自分のやってきたことも忘れて。
自民党の談合政治・派閥政治を批判してきたマスゴミたちもまた、それをぶっこわした小泉首相や安倍首相に対して、派閥から文句がでている・・・などと偉そうにのたまう。
マスゴミはほんとうにこまったもんだ。
ところで。
経費をだまして号泣して記者会見するバカな政治家がどんどん増えている。
国民をバカにしているとしか思えない。
かとおもえば、これらのことをさかんに発しては、われわせれはぶれないとか、偉そうに言っている、共◎党。
2600年の日本文化を認めない頭でっかちのマルクス主義政党に、感情と大義に熱い、日本人の誰が投票するか。
ことしの希望は、はやく、インチキ自民党と、本物の自民党が別れて、しっかりした、日本をつくりあげてもらいたいと思う。
そうしないと手遅れになるぞ。
麻薬を子どもに飲ませるバカ親。
タバコをふざけて子に飲ませてFBにアツプする狂った親。
いじめの定義をはっきりしないから今回の事件はいじめではないと、頑固で、古くさい体質、子どもの魂のことをまつたく考えない今の学校の多く。
こんな学校なんか行かなくてよいのだよ。
人生なんかは、ひとりでも、勉強できるし独学こそが真の学問だ。
自分を磨くのに金もかからない。
他人の目をきにしないこと。
親も今や、子どもを金を産む卵としか考えていないバカ親も多いので、
これも、その場合は家出をすすめる。
そこにある危機。
たしかに、ひとりではなんにもできないわけだが、自分が世界にできる最大の貢献は、ただただ、普通に当たり前のことをあたりまえに最大限に一生懸命、自分ひとりで、やるだけのこと。
主義政党思想はなんであれ、私は「日本を愛する人」であれば、とりあえずは、話しはできるし、認める。
陛下の映像。
ノーベル賞関連の話し。特にニュートリノ。
元素番号のニュース。
・・・・
テレビをちょこっとつけたら、古本屋の世界をやっていて、めずらしく、興味深かった。
リアルでのお客様との出会いを大切にしているとのこと、それは納得できるのではあるけれども、ヤフーに出品するロシア語の古書についての言葉はちょっと気になった。「本そのものよりも、装幀で売るんだ」というようなニュアンスのことを呟いていた。
古いなと、思ったけど。(もうみんなやっているし)
竹村健一の言葉ではないけれども、マクルーハンが言うように、もはや、古本を買う人も含めて消費者が商品の中身そのものよりも、パッケージデザインなどに惹かれて買ってしまうというのは、あたりまえすぎる・・・・。
そこから、はじまるはずでしょう。
常連のおじいちゃんが、かつて大学かどこかで学問した、ロシア語の作家を見つけて、顔を近づけて見ていて好ましく感じた。いつでもどこでも、このような人はいるのだと確信する。小林秀雄氏がいつも書いているように、チープなものよりも、難しいもののほうが、人間の脳を強く刺激するのだと思う。
入門編としては、装幀でもなんでもよいのだけれども、本質的に学問好きな人がこの世に増えることが望ましいのではないだろうか。
では、そのためには何が必要か・・・?
答えは、子供に読書を強要する前に、大人が本を読む事である。
まるで、ひとりの女を愛するように本を読むことである。
そして、そんな環境をつくるためにも、テレビのスウィッチは、なるべく消す癖をつけることだろう。
寺田寅彦氏の本を読んでいてもそれを感じる。

私は、映画と、絵画とクラシックと、jazzと、漫画と、文学を、区切ったりはしないし、
違う範疇とは思わない。
むしろ。いろいろ混じっていた方が楽しい。
寺田寅彦氏のエッセイなんかは、ほんとうは映画化されると良いと思う。
谷口ジローが漫画にしても良いと思うくらい。(孤独のグルメはいまいち。もっち立原正秋氏の小説を読んでもらいたい・・・じつに、ママや客や料理人との関係をときめいて書くのが巧い)
描いていることをむずかしいそうだが、本質的なところから、日常のひとつひとつの小さなことをきりとって、わかりやすくその感銘を描いてくれている。
個人的に最近強く読んでいる本をすこしあげると。
もっと本気で遊びなさい。―遊びかたひとつで人生が豊かになる (サンマーク文庫)/サンマーク出版
¥503
Amazon.co.jp
『仕事と遊びは掛け算でいけ ゆきづまった脳の働きを刺激する本』大和出版 1987
『一流の人間は女の本心が読める "しつけ"のよさで決まる女の能力・26のキーワード』大和出版 1988
などの本もあるけど、この本「遊びかたひとつで人生が豊になる」が一番好き。
龍角散社長だけあって、言う事がでかい。
最近のあたまでっかちで、女の心理もまったく共感できないような、糞まじめ学者などはおよびもつかない。・・・・・・・・・
よみがえれ、バサラの精神―今、何が、日本人には必要なのか?/PHP研究所
¥1,296
Amazon.co.jp
これは名著だと思う。
上にも書いてきた今そこにある日本の危機を救えるヒントがある。
死=生。
これをある意味ひとつの冗談のようにしてとらえて、のりこえていきすさまじい生き方。
かつて日本人が実際にやっていた生き方。
ヒントにならないはずがない。
ひとにめくるめく感動を与えるものは、合理で計算されてたくみにつくられた東京都庁ではなくて、ひとつの霊のために人智を総動員したまさにバカアホ的行為=ピラミッドなのだから。
「無秩序の読書」
この人はあまり知らないけれど、共感できるところがある。
小林秀雄氏と同じようなことを言っている。
大正的体系的読書なぞ、否定して、自分なりの好きな好きなどうしょうもないくらいの宇宙を見つけて行く・・・・
三浦じゅんのように。・・・
ちょっとおもしろいと思えました。ヒントもらえます。
彼が言っていた、
高円寺の腐ったような本屋。知っている。
私は、ここで、ドストエフスキーの白痴を買ったところですが、
モラヴィアをここで彼が発見したということを聞いて、おおおおっ、と思いました。
やはり、居る人はいるものですね。嬉しくなってしまいました。
本は、自分との愛の偶然=必然の交流ですからね。他人がなんといおうと、嫌いなものは嫌いなんですよね。
私は自分の書庫の本は、すべて、三島由紀夫・渋沢竜彦・つながりで、いもづり式に揃えたものです。
・・・・・・・・・・・・
不思議と三島由紀夫氏は、「音楽」はあまり得意ではなかったようだ。好きな音楽家は、ワーグナーだけだったし、カラオケでは、黒猫のタンゴを歌うだけだっよう。
ただ、彼の、視覚的な彼の好きな画家はきになるところ。
少し、三島由紀夫氏の好きな画家を調べてみました。
油絵の構想を練りつつ、構図を何回も描きなおしていて、疲れたのでぼんやり澁澤龍彦氏の追悼号を読んでいたら、mizueのNO945号の彼のエッセイに、三島由紀夫氏の愛したデカダンスの作家が紹介されていたので、調べてみた。
まあ、皆知っている作家ですが、ここに並べて確認してみよう。
三島由紀夫氏のデカダンス論については、その作品などを読んでいただくとして、これらの彼好みの絵は、まあ、いつも私が言っているように「好き嫌い」は、いわゆる傑作・名作の視点とはまったく違うものですね。
イギリスの某作家が言っているように好き嫌いという人間の本能的な原始的な行為こそ、彼の血や生の本能などがそこに露呈されているのかもしれないので、しっかり見ておくことにする。

これらの絵は、私も専門でもないし、詳しくもないのだが、澁澤龍彦氏は「大蘆芳年」と書いているが、この月岡芳年のことなのか?
ただ、この絵を見ていて、この「残酷趣味」「怪しさの表現」などを見るとそうだと私は勝手に思っているが、誰か詳しい人に聞きたいものだ。


竹久夢二もまた、三島由紀夫氏が好きだった作家。
だいたいが、日本画家は、大家になって「花と鳥」しか書かなくなり、マンネリして、つまらなくなることが多いし、そのあたりにたいするアンチ・テーゼとしての岡本太郎氏や、横尾忠則氏の存在価値があるのだとしたら、この竹久夢二もまたその部類に属する異端の作家だと思う。
文壇はつまらない、臭い、といつも言っていた三島由紀夫氏、偽善や「生温さ」を嫌い、世間で認められていなくても、自分の嗜好と合えば「息」を吹きかけていた。
確か、詩人の春日井健氏だったか、三島由紀夫氏に褒められて、嬉しい反面ものすごい緊張したというようなことを書いていた記憶があるが、違うかもしれない。

そして、ビアズリーは、有名ですね。
しかしながら、当時はさほどの評価がなく、ワイルドからも敬遠された時期もあったらしいですから、
まさにビアズリーは時代をさきどりしていたのだと思う。
ワイルドの嫌われ者の栄光という言葉も三島氏は確か好きだった筈。
モンス・デシデリオは17世紀のナポリの作家。
廃墟ばかり描いた作家らしい。

あまり情報はとれませんが、なんとかこれくらいの情報です。聞いた話では、澁澤龍彦氏が三島由起夫氏に教えたと聞きました。
フランス幻想作家というグループがあることはうすうす聞いていましたが、やはり、
イタリア・フランスのラテン気質の画家達・・・廃墟をテーマに描いていました。
デシデリオの作品は少し見ましたが、このアラン・マルゴトンという作家の作品は初めて見ました。
彼はデッサンにこだわる画家です。
確かディマシオにかなり影響をうけたのではないでしょうか。
三島由紀夫氏にぜひ見せたかった作品群です。この女性のポーズも 世界的な奇書の「薔薇刑」の表紙によく似ているような気がします、そう感じるのは私だけでしょうか。

三島由紀夫氏が大好きだった、作品そのものはここに資料としてあげておきます。
ネットでは画像が探せませんでした。
また見つかり次第、スキャンして、載せたいと思います。
ビアズレイの「僧侶」、竹久夢二の「長崎十二景」から「阿片窟」、大蘇芳年(1839~1892。幕末から明治初期にかけての浮世絵師。月岡芳年)の「英名二十八衆句」から「笠森於仙」、モンス・デシデリオの「火災」の四枚。
ところで。
ピカソと、シャガールと、マチス。
この三人はおもしろいですね。
個人的には、バルテュスと、シャガールと晩年のマチスが好きだな。
特に、晩年のマチスの協会の絵ときたら・・・・・・

もう手足も完全に動かせなかったから、ながい杖のような、棒にチョークをつけてかいたものですね。
マチスの作品というよりも、むしろ、ほぼ天使になりつつ脱皮していたマチスの作品かな。
日本では、明治と大正の挿絵画家たち。みんな。
中原淳一も素晴しい。
金子さんも自分のスタイルがありましたね。
金子さんは、中原さんのようにあまりにもポピュラーになることをいつも極度に恐れていましたが、
結局は、中原さんの詩情あふるる絵は、古くなりませんね。おもしろいものです。
ピカソの妻はartはエニグマだと書いているし、ピカソ本人も私の絵は共産主義の絵だろうと
言っていて、それを知ってから、私は個人的にはピカソからはなれていった。・・・妻の言葉は大好きだが、ピカソの思想は興味なし。ただ、あれだけ、絵の構造と色彩を駆使したことがすごいのだと思う。
ピカソの絵には、愛がない、いつもシャガールはそう言っていたそうです。
そりゃあそうでしょう。キャンバスの白の強迫観念にいつも悩まされていたピカソにとってみれば、町で歩いている美女も皆、自分のアートのキャンバスの白の強迫観念から救ってくれるモデルたちですから。
シャガールは、もっと普通ですね。良い意味で。
国を愛し、自然を愛し、妻や家族や友人を愛して、個人的には個人の心理や思想を超えたところまで到達した昇華絵画を描きたいと思っていた事でしょう。
・・・・
日本ではまだまだ、真面目な国ですから、クリムトやシャガールは人気がありませんが、
もっともっと評価されても良い作家達です。
・・・・・・・・・・・・・
30代の頃。
パルコで働いていたので、昼飯の時間ともなると、本屋へ飛び込む。
もちろん。
画集をぱらぱらと見るためだ。
この頃、よく見たのは、石岡瑛子・・デザイナーの佐藤氏。
あとは、やっぱりこのエリック・フィッシェルだろうな。
A Review of ‘Eric Fischl - Beach Life,’ Eric Fischl: Early Paintings/Skarstedt Fine Art
¥3,844
Amazon.co.jp
Eric Fischl: Paintings and Drawings 1979-2001/Hatje Cantz Pub
¥4,011
Amazon.co.jp
Dive Deep: Eric Fischl and the Process of Painting/Pennsylvania Academy of the Fine
¥5,125
Amazon.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・
{エリック・フッシェルクリップ・・・}
自分では、特に、彼の、「バッドボーイ」という作品に惹かれた。
影響されて、何作か、書いたものである。
横尾忠則氏も彼から何か学んだような形跡がある。
絵の上手い下手を超えて、理性をひょいと乗り越えた感覚がすきだった。
確かに、デイビッド・ホイックニーも嫌いではないけれども、飽きる。
ワイエスは飽きない。そして、このフィッシェルも、原始的で、飽きない。
この絵のテーマは、たしかに、映画「卒業」と同じなんだろうけれども、そのような、
説明や、分析を、無視して、不思議な、静けさもあると思う。
日本でいえば、横尾氏よりも、私は、つげ義春に近いと感じる。
感じるだけなので、違っているかもしれないけれども、私がそう感じるので、それで、良いのだ。
見たい映画が、机の横に積んである。
ああ、はやく、見たい。・・・・・・・
体の調子もよくなってきたので、すこしずつ、絵画と漫画と映画と外国語学習と散歩、がんばろうと思う。
序の舞
小早川家の秋
新源氏物語
青い沼の女
蔵
蔵の中
続忍びのもの
大病人
大菩薩
中心蔵
天守物語
桃太郎サムライ
豚と軍艦
目が悪くなって来たので、眼鏡もなおしてもらった。
パソコンも、五年もたつと、調子がわるくなって、見ていると途中でぷつんと切れたりもする。
しかしながら。
それらすべてをふくめて、楽しむことにしている。・・・・・・・
人生では、どんなことであろうと、すべてが、肥やしになるのだからこそ。
「負け惜しみではなく、女の人のことを知りすぎた」 淀川長治
FIN
中島みゆき ファイト Connoisseur Elac PX4
ひといきつきながら・・・・・・・・
ジャンヌ・モロー 「クロワッサンで朝食を」「恋人たち」 吹石一恵「新撰組」「デスノート」
年をとるにつれて、誰でも自分らしくなるのだ。年とともに、良くなるとか悪くなるとかではない。 ロバート・アンソニー

この言葉を思い出しながら、「クロワッサンで朝食を」というフランス映画を見ました。
主演は、なんと、あの大女優、ジャンヌ・モロー。
私の大好きな「ラ・マノン」のファーストシーンからのナレーションは彼女。
その低い声に味があり、素晴しい出だし。
フランス映画の魅惑がとことん、つまっています!!!! 私の好みの映画のひとつです。
感想のひとつも書いてみようという気持ちになりました。
昔、アテネフランセで、英語字幕の彼女の映画を見て感動した記憶があります。
「恋人たち」「突然炎のごとく」の二本です。
独特の美しさ。
流れるような、新鮮な映像。
ほんとうに感動しました。
書物の方もまた、良いです。たしか、「ジュールとジム」とかいう題名がついていました。
惜しいことに、売り払ってしまいましたが。
またこの本には、出会うでしょう。
もうひとつは、これも、また私の愛するデュラスの作品ですが、
なかなか見る事のできない映画ですが、ここ最近やっと見る事が出来ました。
「雨の忍び逢い」です。
備忘録はまたのちほど。
フランスのあの頃の名女優といえば、バルドーや、カトリーヌ・ドヌーブ・・そしてやはり、ジャンヌ・モローでしょう。
「クロワッサンで朝食を」というあいかわらず、観客の受け狙いの題名でうんざりしますが、原題は、Une Estonienne à Paris・・・・・「パリのエストニア」このまま、で良いと思うのですが。
・・・・・・・・・・・・
(見終わった後に、ネットで、感想を探すと・・・・・・・・
やはり、この映画も、賛否両論のレヴューでした。)
この映画、何回も書きますが、フランス映画なんです。
ですので、現在、今の、フランスの国の空気や、風景やら、ひとびとのファッションやら、通行人の雰囲気、パリの現在の生き生きした動き、エッフェル塔の美しさなどが、見れる嬉しさもあります。
私は、人生で、二回しかフランスには言った事がありませんが、その目的は、美術館めぐりでした。
でも、この映画のひとりの主人公、モロー扮するフリーダは言います。
「地元のパリ人は、ルーブルなんかはいかないわ」
なんていっても、ここは、パリなんですから。
ニューヨーカーという言葉もありますし、東京人という言葉もあります。
フランスのとある名言ジョークに。
how can you be expected to govern a country that has 246kinds of cheese?
フランスには246種類ものチーズがあるんだ。こんな国を統治できると思うかね?
というのがありますが、そんな国の映画、それが、「クロワッサンで朝食を」。
まず、題名が、なにやら、優しく温かいヒューマンドラマかと想像させます。
あるいは、ヒット作品の、老いた男性のもとへ、ひょんなことから雇われた黒人との、友情物語・・・・・・・そんな物語を連想もしましたが。
やっぱり、モローの映画なんです。
難解ではありませんが、深いです。
嫌いな人は嫌いでしょう。
バルト三国からパリ人になった主人公のフリーダ(モロー)。85歳本人と同じ年齢の役柄。
これがまずすごいですね。
この年齢で、言葉は矛盾しますが、凍り付く程孤独ではあるもののいぶし銀の老年です。
すっかりパリっ子になって、まるで、「化身」の霧子のように、愛人のステファン50くらい?
に、店をまかせて、自分はのんびりと朝はかならず、クロワッサンと紅茶の生活を続けています。
我がままで、個性的で、他人から強制されることが大嫌いな道をこれまで歩んで来た成功者の金持ちですから、自分の人生に後悔はないのですが、とにかく、誰も、寄ってこない。
孤独。
老い。
これまで、愛人のステファンが何人も召使いをやとっても、すぐに、辞めてしまう。
普通の日本人の視点からこの映画を見ると、不道徳な道を歩んできた昔は美女であっただろうが、今は老いてしまっているモローにあまり共感できる人が、多いとは思いませんが。
日本人のように、近所付き合いやら、人間どうしの絆を第一に考える民族の視点だけでこの映画を見てもつまらないと思います。
やはり、西洋は、我の世界。個人の世界。その個が、直接に神様につながっているわけですから、人づきあいでも、良い意味で、合理的で、言いたいことを言い合い、喧嘩するときはがっちりするわけです。
それで、そこで、おわりではないのですね。フランスは。
こんなことわざも思い出します。
「フランスでは、けんかは愛情関係を強くするが、アメリカはけんかで愛が終わる」 ネッド・ローレム
最近の日本の若者達もまた、アメリカ式が多いですから。・・・・・・・
フリーダは、自分のことをさておいて、エストニアからパリにやってきて長く住んでいるエストニア人が嫌い。
そんな連中から、とあることを批判されると、即、持論をぶちまける。
「愛国者ぶるのはやめて」と・・・・
そんなに好きならエストニアに帰ればいいじゃないのと。
まあまあが、嫌い。なあなあが嫌い。孤独であっても、寂しくとも、老いても、とにかく、モロー扮するフリーダは、妥協せずに、生きているのですね。
まれに、彼女も、薬を飲んで、自殺未遂のようなこともしますが、ライネ・マギというエストニア出身の、これまた少し老いたアンヌ・・・・・に、最初のころは冷たく接して、まるで、試験のようなことをいろいろするのですが。
アンヌが、出て行った後に、モローが、「アンヌ アンヌ」と彼女にプレゼントしたパリのしゃれたコートを抱きしめるところとか、・・・・・・・
愛人の、年齢的には息子のような、髭面のパトリック・ピノー扮するステファンが、アンヌが出て行ったあとに、ベッドに添い寝するところ・・・
名場面ですね。涙がでます。ちっとも感傷的な描写はありません。むしろ、ぞっとするくらいに、むきだしの老いがでてくるのですが。
泣けます。
たしかに、健康で、笑のたえない、フランスのことも知らない、日本の歴史や日本人についてあまり普段考えたこともないような、人が見ても、おもしろいとは思えないかもしれせん。
でも、昔の光り輝くジャンヌ・モローのことを少しは知っている人。
フランスに興味がある人。
両親の介護を少しはしたことがある人。
自分自身の「死」について、いろいろ、考えた事がある人。
そういう人が見ると、まるで、宝石のような映画に変容していきます。
そして、エストニアからやってくる、お手伝いさん。
ライネ・マギ・・・・・・ジャンヌ・モローの存在感にすこしも、負けていませんでしたね。たいしたものです。
・・・・・・・・・
つい最近は、日本では、原節子さんが、亡くなって、日本人は、彼女が芸能界・映画界を去ってから、完全に普通人になり、マスコミにまったく姿をあらわさないままに逝ったことを、絶賛していました。
お国柄です。
それとは、まったく対照的なフランスの国のジャンヌ・モロー。
85歳になっても、彼女の表情から、昔のあの神秘性やら、冷たい強さ、強情ともとれるような知性、わがままな美、そんなもののある意味「残骸」を、堂々とまき散らすんです。
それが、素晴しい!!! お国柄の違い。それがまた楽しく、おもしろい。
・・・・・・・・「本物の大人の映画」だと思いました。
◎エストニアの位置は北海道よりも北のヨーロッパ。フランスは雪がふらないのではない。私が行った二月には雪がふるなかで、珈琲を飲んだ記憶がある。
◎カセットテープはよく洋画にでてくる。日本は電化製品はすすんでいる。
◎以前見たフランス映画によく女中には、スペイン人が多くでたり、イタリア映画にはポーラン時人が大工としてよく出ていた。
◎「私が愛したのは夫とステファンだけ。
◎アンヌの表情は非常によみずらい。常に相手の表情を読み取る訓練をしている日本人から見るとそういうことになる。
◎マニキュアの意味
◎エストニアはロシアから独立。
◎美男のインテリに口説かれてもあなたはなにも感じないの? フリーダ
◎なぜ、男は変わらないの 女は変わるの ? フリーダ
◎エストニアの子どもの子守唄がでてくる
◎エストニアの母の墓のとなりで死にたい
◎あなたが孤独なのは自分のせいなのよ アンヌ
◎アンヌ来て どこにいるの フリーダ
◎死を待たれるモンスターとしての存在・・・・・私も母の死をねがっていたわ
アンヌ&フリーダ 複雑な立場 心理状況
ところで。
「写真」について。
基本、わたしは、写真家で言うと、篠山紀信も悪くはないけれど、アラーキーのほうがおもしろいと思っているのだけれど、篠山の「サンタフェ」「ヴィスコンティ」なんかは好きだ。
毎日の日課ですので、
ブルータスの古書を朝から、いろいろ書庫の整理整頓をしていますと。
あらら、おもしろい写真が、味のある、・・・そう私の好きな写真の一枚をみつけました。
吹石一恵、、、「ときめきメモリアル」でデヴュー、伊東四朗と親子役で、「新撰組」で共演。


ただ、ここ最近、映画をどっぷりつかりはじめているので、この吹石一恵という女優さんのことは、まったく知らなかった。
この写真なかなかいいな、と古書を整理整頓しながら、魅入った。
「伊東四朗さんは理想の男性です」と、朝から調べていた、2010年発売のブルータスで、のたまうていた。
あれ? 雰囲気のある女優さんだなと、感心して、ちょいと調べてみると、・・・・・驚愕。
福山雅治と結婚していたんだ・・・・・・・・・・・・ほんとうになにも知らない私でした。
お恥ずかしい。
東京都港区のne plus ultra六本木店 ・・・・・このあたりは、なつかしい。
ここは、自分の管轄するお店がメルサに入っていたので、このあたりは、けっこう歩きました。
中原淳一展などは、銀座の松屋でやっていましたし。
退職後、このあたりはよくまわっては、友達と食事したりしたものです。
でも、この店は知りませんでした。
この写真は、計算すると、吹石は、当時28歳。伊藤は、73歳。・・・
さすが、篠山紀信。えぐるようにしてふたりの瞬間の、空気感をとらえています。
吹石一恵・・・・・・も、実に味のある雰囲気を漂わせています。
彼女は、不思議な美人さんだと思います。
なにやら、ただの美人ではなく、少し、文学少女的なところもあって、良いですね。
「紀子の食卓」にも出ていました。
田舎に住む17歳の平凡な女子高生・島原紀子は、家族との関係に違和感を覚えていたが、ある日インターネットのサイト「廃墟ドットコム」を知る。彼女はそこで知り合った女性を頼って東京への家出を敢行、「レンタル家族」という虚構の世界で生きていくが…。
この監督、興味深いのは漫画も描くんですね。
愛知県豊川市出身。17歳の時に詩人として、『現代詩手帖』や『ユリイカ』等に投稿、20歳の時には漫画雑誌『ガロ』に漫画を二度持ち込むも二度とも入選を逃す(一応は90年代に映画監督としてガロにコラム「東京ガガガ新聞」の連載を持つ)[1]。23歳の時に自主制作映画『俺は園子温だ!』を製作し、ぴあフィルムフェスティバルに入選する。
また大河ドラマ初出演作品となる『新選組!』では初めての男装役に挑戦しています。(2005年に卒業した大学の卒業論文のテーマは「脚本における日本語」で、三谷幸喜によるこの大河ドラマの脚本を取り上げた)。
また、「ゲゲゲの鬼太郎」にも。
映画『ゲゲゲの女房』予告編
話しはそれますが、私は、水木しげるの漫画のコレクターなので、ほとんど彼の作品は持っていますが、
・・・・・・・・・
以前。
こんな記事も描きました。「デスノート」の物語とよく似た作品があるのです。
「デスノートの元ネタかも」
水木しげると言えば、「ゲゲゲの鬼太郎」と「悪魔君」が二大代表作とされているが、実はそれ以外にも、私の大好きな作品がたくさんある。
「縄文少年ヨギ」「猫楠の生涯」「ヒットラー」「雨月物語」「近藤勇」「ラバウル小唄」「カッパの三平」「異界への旅」など、他にもまだまだ、傑作があるのである。白戸三平のマルクス主義の絵解きの忍者武芸長とは違い、彼の「忍法屁話」などは自由な発想が快い。
さて、今回のテーマである「デスノート」とよく似た作品のことであるが、私の水木の蔵書をこれかなと一冊とりあげてみると、やはり、神秘と幻想の作家だけあってその顔をすぐに見せてくれる。この偶然も水木の作品らしく、これもシンクロニシティのひとつではあろうが、題名が、「風刺の愉しみ」 呉智英編の中央公論社から出ている1200円の愛蔵版である。
諷刺の愉しみ (水木しげる作品集 (2))/中央公論社
¥1,258
Amazon.co.jp
この愛蔵版の中に、三十四作の作品が忍法屁話からはじまり、ねこ忍、コブ、未来をのぞく男など、名作が詰まっている中に、このデスノートとテーマがよく似ている「不思議な手帳」がある。
笑えるのは、怖い女房の憂さ晴らしで飲んでいた主人公の山田さんが、酒に酔って家に帰ると女房に怒られるので、しょうがなく、あるほこらで、ひと休みしていて、ノートを拾うのである。
そしてその横にはなんと男性の死体!!
そのようにして、知る人ぞ知るガロの編集長の花田勝一さんがこのデスノートをなぜか持ち歩いていたのだが、彼の怪死とともに、三島や川端などの有名人の名前が書いてある不思議な手帳を平凡な公務員の山田が拾うのである。
山田はそこに自分によく吠えつく隣の家のポチの犬の名前を書くと、なんと翌日、ポチが犬狩りにひっぱられていくではないですか。
このあたりは、よく「デスノート」とよく似ています。
天才少年ライト君みたいな格好良さのまったくない山田さんという水木漫画に必ず登場する冴えないおじさんが、主人公なんです。それが逆に親近感を感じさせるし水木の漫画の独特の世界の開放感につなげさせるんです。
呉さんは、「ゲゲゲの鬼太郎」と「悪魔君」は代表作ではない、とまで、書いてますが、これはこれで傑作です。
ひとつのパターンの中に、目玉の親父と鬼太郎とそして妖怪達との戦いをとうして子供心に怪物や妖怪に対する愛情や好奇心や神秘に対する興味を湧かせる力を持つ作品です。
「悪魔くん」も、天才的な少年が悪魔の力を利用してこの世の中に理想の楽園を造り出すという作品のテーマからして、デスノートの原作者がこの「悪魔くん」や「不思議な手帳」だけではなくて、水木の作品に通暁していることはほぼ、間違いないでしょう。
ただ、その事自体はまったく問題はなくて、もともとの自分の愛する作品を換骨奪胎してそれがまったく分らない程にまで噛み砕いてて昇華した作品は盗作ではありません。それが盗作ならば、ピカソもゴッホも、三島由起夫も村上春樹も、皆盗作者になってしまいます。
ジェームズ・W・ヤングという世界的なアイデアの達人は「アイデアとは新しいくみあわせ」だと、はっきり断言しております。
つまり、Aからまったくそれとは違うGは、生まれず、AがA1になり、A2になり、A8ぐらいになってはじめて、それが、Bに見えるというイメージでしょうか。
いちばん難しいのは自分が大好きな作品を、特に絵ですが、勉強のために模写しているうちにだんだんそれが自分が作り上げた作品と錯覚していくという「やつ」がこまりもんですが。
以前これで盗作疑惑になった日本画家がいました。本人は「自分の尊敬する画家へのオマージュ」という言葉で逃げていましたが。
水木しげるがこの作品で、短編の名手であることが更に世に知られ、そして、彼のような、「汚さ」の中に潜む「美しさ」や、「偽善」をさらりと笑い飛ばす柔らかい心や、「日常」の退屈の中に実は「神秘の扉」があるのだという彼の遊び心には敬服するファンが増えればいいですね。
余談ですが、水木さんの奥様とお嬢様とご本人には以前お会いしたことがあり、確か右手が戦争で無くしたために残りの手で漫画を書いていることを発見しました。
ほんとうに感動しました。
金儲けのためだけの漫画家が不勉強な漫画編集者によって、量産されている今、こんな漫画もあるんだということは忘れないでほしいですね。
「新撰組」 これは、見ていません。仕事でこの時間帯は無理でした。
「漫画」ですが・・・・・・・・
「新撰組」は、手塚治虫氏の傑作名作があります。
新選組 (手塚治虫文庫全集)/講談社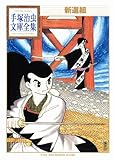
¥950
Amazon.co.jp
喪失と再生。
日本人の歴史の中で、戦後の我々の魂の状態とは?
世界のその他の国のように、リアルに家族が殺されたり、戦争に自分の子供達が参加したりするようなこともなければ、キリスト経の伝統の中で常に神の存在や不在について考えている国とは違って、飽食日本は心のむなしさを一番敏感に感じ取っているとよく言われます。
小さな頃に脳幹、つまり体の奥の奥を鍛えなければ人は大人になれないという説もありますし。
河合隼雄氏の意見では、のほほーんと育った人もいつかは「旅」に出るときが必ず人生にはあるとも示唆しています。
もちろんそれはいわゆる実際の「旅」でなくとも、「不倫」だったり、「退社」だったり、あるいは、「独立」だったり、いろいろ心の状態の中での旅のことである。
その旅の中で出会うさまざまなる人や、事件が彼や彼女を鍛えるのである。いわばイニシエーション的なものでもあると思う。
たんなる備忘録なのだが、この手塚治虫氏の「新撰組」の中で萩尾望都氏が、こんな解説を書いている。
「おさないころから不安な夢を見ていた。誰もいない、何もない、窓の外には霧しかない。世界はあるのか。私は存在するのか。成長しながらも何かが指の間からサラサラと失われていく虚無感がつきまとう。その喪失はどこから来たのか。世界からだろうか。両親だろうか。あの大戦の終了後、世界は何かを閉じ込めてしまったのだろうか。言語化も、視覚化も、意識化もできない無意識の中に浮遊する何か。
私にとっての手塚治虫作品は、その何かを言語化し、絵として視覚化し、物語として意識化した、具体的なものにみえた。不安を不安なものとして自覚させてくれたのである。」
さすが萩尾望都女子。
すごいと思う。
若い頃は妙な言葉だが、「苦労したがる」のです。
生きている実感をつかみたいのである。それができない、自分の目的を明確に萩尾望都のように見つけることが出来ない人は、仕事に夢中になる。
そこまでは良いが、その仕事からあぶれた人がやはりあぶない。あるいは、もんもんと悩んでいる敏感なる人達。
以前確か、神戸の殺人事件、酒鬼薔薇聖斗事件でしたか、「透明な」という言葉を自分の心の分析に使っていましたね。中学生が・・・・
リアルな実体験に乏しく、仕事もせず、友達もできず、つきあう異性もいなければ、その浮遊するパッションはまさに無目的な性行動にもつきあたることとなる。<例えば小説で言えば、限りなく透明なブルー>
1949年5月12日、萩尾望都は生まれている。
1949年1月12日、村上春樹。
1952年2月19日、村上龍。
経験が何もないまさに透明なる私の学生時代には、「生は単なる現象にすぎない」と、たわいもない議論ばかりしていました。
(小林秀雄氏もたしか、若い頃は、舌で壁をなめたりして、その確かな実在を感じとろうとしていたらしいことを何かの本で読んだ記憶がある)
やはり生きて行くということは、人間同士の絆の中のしっかりした実感の中で生きることが、体にとってのビタミン剤のように、魂にとってのビタミン剤になるのでしょう。
「クロワッサンで朝食」も同じ。
それは、ある時には、喧嘩であったり、軋轢であったり、恋だったり、たいていが人間関係の問題でもあるが、人はそこから逃げればあとは、何も残らないということも知る必要があるのではないでしょう。
先日も書きましたが、村上春樹氏が、誰とも会わずに創作をする中において、あまりにもすらすら小説が書けた時期があり、こんなことをやっていると人間としてダメになるのではないかと、不安にとらわれたことを何処かで読んだ記憶があります。
ところで、萩尾望都は、この手塚治虫氏の「新撰組」を読んで、たった二行の「大作、許してくれ」に衝撃をうけ、「何か」を具体化する目的を持つ、ひとりの漫画家になろうと決心したのですから。
「ノルウェイの森」ではないが、「喪失」と「再生」、軽く使いたい言葉ではないが、最近なにやら、私の頭をふらふら、飛び交うのである。
「ノルウェイの森」
・・・・・・・・・・・
「苦しい目に遭うと、どうしても「なんで俺だけがこんな苦労を…」って思っちゃうけど、そんなことないね。
みんな、あるの。
死ぬまであるもんなの。
だいたい苦労がなかったら、面白くもないし、人間じゃないよね。」
・・・・・・・・・・・淀川長治
FIN
「見られる存在としての」女優「見る存在としての」監督 チューバッカとソロ「神の仮面」
アインシュタインは、死とはモーツアルトが聞けなくなることだと書いたけれど、
私にとっては、死とは好きな映画が見れなくなることだ・・・
「ソラリス」のバッハと・・
「ブレードランナーの彼女」に会えなくなるなんて・・・寂しすぎる。
・・・・・・・・・
不思議なことに、こんな緊急の時って、くだらないことを考える。
市民病院に搬入の時にはなんにも注射もせずにほったらかしで、7000円。
こんどは、労災で、ちゃんと夜勤の先生とナースがふたりもついて、ワソラン注射もしてくれて3000円。ありがたい。・・・・・・・・・そんなことどうでも良いことを、考える。
きっと、精神安定剤のせいかな。
あしもとがふらふらして、一日に、椅子から三回はぶったおれる。
・・・・・・・・
新しき発見は、精神安定剤のおそるべき効果
を飲んでいるが、レスタス・・・・、酒と飲むとかなり効果が高くなる。
ほんとうは飲んではいけないのだが、気がつくと、飲んでいる。
時期が時期なので、忘年会で酒を飲んでいたら、二次会でもはやダウン。
知らぬ間に、寝てしまう。おそるべき効果。
(これまで、飲み会の最中に寝たのは、30歳の頃に、ウィスキーまるごと一杯、ぐびぐび、一気飲みしたときだけだ) 、だから、それだけの催眠効果があるということだろう。
あまりにもすごいので、今日から寝る前だけ飲むようにした。・・・朝は飲むとすぐに眠たくなる。
せっかく撮った、写真がたくさんはいった、iPhoneを失くしてしまう・・・とほほ。
・・・・・・・・・・・・・・



これらの写真は、忘年会に出かける前に、パソコンに移動しておいてよかったよかった。
つるつるの道なので、よくすべる・・・きっと携帯は今頃、雪に埋もれて春を待っていることだろうに・・
ところで、月に10000円もかかるスマホに嫌気がちょうどさしていたので、神様から変更せよという指示なんだろうと自分勝手に判断。
サッポロビックカメラにて、月に、3700円の格安のスマホに変更。これで、年間で、8万は浮く計算。たっぷり絵の具を買えるし、映画も見れるし・・・いうことなし。
ただ、マックとの連携が悪く、これから少し勉強が必須。
「スターウォーズ新作」見ました!!!!
はっきり言って、ハリソン・フォードと森林星から来た年齢200歳のチューバッカが、出て来た時は、涙がでました。
涙、不思議だ。
意味なく出てくる。
「オレもまだ生きているぞ」みたいな感覚かな。
そういえば、シュワちゃんの、「ターミネーター新作」を見ていて、シュワちゃんが、あまりにも古いデザインであるのに関わらず頑張っているのを見て涙がでてきた。
レイヤ姫は大好きだったから、もう少し、以前の雰囲気を残してでてきてもらいたかったが、まったく名残りはなくて残念。おののこまちの心境だ。
女の人はその意味ではなかなか花の美しさを維持するのは大変なよう。
男は、そのあたり、楽というか、ほっといてもさほど変わらないような気もする。
(頭の毛だけは別だが・・・) まあそんなことはどうでもよいのだが。
売り子の女の子が、席をなるべく空いているところが良いと希望すると、今は満席だから
指定はできませんとのこと。
しょうがないかと、席につくと、なんと、まわりはガラガラ。
はじまって、数時間たってもそのまま。
マニュアルどうりにしか語れない女の子。こまったものですね。
これでは、いずれは、切符売り場の人間は、すべて、Androidになってしまうほうが
良いと思う。
「プレードランナー」の出てくる美人のAndroidが、美しい声と笑顔が、瞬時にお客様の希望の席を、見つけてくれて、微笑みながら、楽しんで下さいと呟く。
きっと、何回も何回も、その映画館に足を運ぶだろう事になるだろう私。
昨日も、ソフトバンクの携帯屋に行って、解約をしていると、なんとpepperがいるではないか。
可愛い。
すぐに、近くによって、はじめて触ってみた。あごをこちょこちょして、頭をなでなでして、「かわいいね、かわいいね、ほしいなぁ」と呟くと、
peper 君は、こらちを大きな目でじっと見て、少し考えたあとに、「「ロボット」と話すのは、はじめてですか?」と質問された・・・・。
もっと話したかったけれど、
時間の関係で、お別れのまたくるねと、言って、バイバイをした。
あの感覚で、女の子のAndroidだったら、きっともっと爆発的に売れると思う。・・・
というわけで、「スターウォーズ」は、未来の地球、いや、未来の宇宙について、深く深く考えさせられる作品だ。
神の仮面〈上〉―西洋神話の構造/青土社
¥3,024
Amazon.co.jp
神の仮面〈下〉―西洋神話の構造/青土社
¥3,024
Amazon.co.jp
この「神の仮面」もAmazonで即買いして、すこしずつ、読んでいるけれども、個人的には、東洋哲学の方が深いような気がする。
理力とか、フォーカスとか、・・・少し幼稚。
かつて、古来の人間達は、犬なみの嗅覚を持ち、ほんとうかどうかはしらないが今の現代人の三倍の視力を持ち、数倍の筋力を蓄え、右脳を使って神の声と交流していたというから。
文明が進化するということは、ある意味何かが欠落することでもある。・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・ ところで。今回のテーマ。女優と監督の恋愛と結婚。
J・J・エイブラムスは、心の旅やスタートレックもつくった有名な監督ですが、やはり、女優と結婚しています。
ケイティ・マクグラスさんです。
『 THE TUDORS~背徳の王冠~』での仕事の間に、マクグラスは演技に取り組んでみるよう助言を受けた。彼女はアイルランドの方々の代理人へ写真を送った[5]。そして、第 2 シリーズ第 3 話において小さな役を獲得した[4]。
マクグラスは、次のように述べている。
“私は、何人かのプロデューサーから役者にならないかと勧められた。私はただ「いいですとも」と思った。それは、いわばサーカスに加わるために走り出すようなこと、若く、しかし一方で成長し適職を得ようとするときに誰もが求めることだった。しかし、誰かがそれをしなければ、誰もサーカスには加われないだろう。”
マクグラスはフィーチャー映画の『エデン Eden 』と『フリークドッグ(英語版) Freakdog 』に出演した。2008年には、 BBC One が制作したテレビドラマ『魔術師 MERLIN』でメインキャストを射止めた。このドラマは世界中で放映され、マクグラスにとっては最初の代表作といえる出演作となった。
2009年上半期には、チャンネル4 が制作した 5 編からなるエリザベス2世の生涯についてのドキュメンタリードラマ(英語版)にも出演した。そこでは、若い頃のマーガレット王女を演じた[6]。同年下半期には、『魔術師 MERLIN』の仕事に戻り、第5シリーズまで放送された。
2013年には、ホラードラマ『ドラキュラ』に出演し、2015年には、映画『ジュラシック・ワールド』に出演した。
日本で、女優と監督さんの結婚恋愛といえば、すぐに私はこのふたりを連想してしまいます。
「心中天網島」1969 より
だれであれ、こんな深刻な映画を実話をもとにしたであろう近松の作品を、食事前に見たいとはおもわないだろうが。
監督:篠田正浩
製作:中島正幸、篠田正浩
原作:近松門左衛門
脚色:富岡多恵子、武満徹、篠田正浩
音楽:武満徹
撮影監督:成島東一郎
美術:粟津潔
録音:西崎英雄
助監督:小栗康平
だから、私は、岩下志麻のキモノの着方や小物の色デザイン、小さな小道具に目をやりながら、楽しむようにしている。
パゾリーニ監督だったかが、日本のとある作品から彼のあの独特とのギリシア神話物語の顔の白パックのヒントをつかんだと聞いた事が在るが、西は東から東は西から、インスパイアされながら、作品をより豊饒にしていけばいいのだと思う。
好きで好きでたまらないふたりなのに、この世ではむすびつくこともならずにあの世で、一緒になることを信じて、首をつる。
運命を象徴するからのような文楽の人形達黒子達がその手伝いをする。
小林秀雄氏は、ニーチェの言葉を引用してこんなことを書いています。
ニーチェについて小林秀雄氏が書いている文章があるが、こんな文章です。
大学時代に読んで、感動して、いまでも、よく覚えているのです。
「ニーチェは、ギリシア人がりっぱな悲劇を書いたということこそ、ギリシア人が厭世家ではなかったというはっきりした証拠だといいます。ちょっと聞くと、反語のようにも聞こえますが、それは、悲劇と厭世というふたつの概念を知らず知らずのうちに類縁のものと私たちが思っているからでありましょう。
おそらく、ニーチェは、そのことを頭において強く主張する、悲劇は、人生肯定の最高の形式だと。人間になにかが足りないから悲劇は起こるのではない、何かがありすぎるから悲劇がおこるのだ。否定や、逃避を好むものは悲劇人足りえない。何もかも進んで引き受ける生活が悲劇的なのである。不幸だとか、災いだとか、死だとか、およそ人生における疑わしいもの、嫌悪すべきものをことごとく、無条件で肯定する精神を悲劇的精神という。こういう精神のなす肯定はけっして無知から来るのではない。そういう悲劇的智慧を掴むには勇気を要する。勇気は生命の過剰を要する。幸福を求めるがために不幸を避ける、善に達せんとして悪を恐れる、
さような生活態度を理想主義というデカダンスの始まりとして軽蔑するには、不幸や悪はおろか、破壊さへ肯定する生命の充実を要する。
そういうディオニソス的生命肯定が、悲劇詩人の心理に通じる橋である、とニーチェは言いきるのであります。ニーチェの激しい気性は、アリストテレスのカタルシスの思想に飽き足らなかった。」
要するに、「幸福」だけを狙って「引き寄せる」なんていうのはとんでもないことで、間違って「悲劇」を引き寄せても人はその運命を愛するべきなのだということですネ。
これは恐るべき言葉です。
心中天の網島は、こうするように行動するしかないだけの愛の過剰があったということでしょうか。
現代のように、すべてが、薄味で、偽物である世界で、なにかにつけてただ長生きだけを目的とするような悪式健康社会では、このような「愛の過剰」など、見向きもされませんね。
・・・・・・・・・・・・・・
ただ言えるのは、「死」について考える時「生」は不思議とそのレベルを上げるということでしょう。
篠田さんの作品は、大島渚や、吉田よりはずっとすきです。
なんといっても、川端康成の作品を映画化するところがいいですね。
「化石の森」、なんという素晴しいチョイス!!!
「少年時代」
『少年時代』(しょうねんじだい)は、藤子不二雄Ⓐによる日本の漫画および、1990年に公開された映画。1978年(昭和53年)から1979年(昭和54年)まで『週刊少年マガジン』(講談社)に連載された。
その他。桜の森の満開の下 (1975年) 原作:坂口安吾
はなれ瞽女おりん (1977年) 原作:水上勉
夜叉ヶ池 (1979年) 原作:泉鏡花
悪霊島 (1981年) 原作:横溝正史
瀬戸内少年野球団 (1984年) 原作:阿久悠
なども作成しております。
ほんとうに好きな映画のテーマばかり。
さっそく、DVDを注文しました。・・・・TSUTAYAには在庫はもうありません。
「少年時代」はあると思うので、100円で借りてきます。
藤子不二雄に、川端康成に、泉鏡花に、水上勉に、坂口安吾ですから。
とくに、「安吾の桜の森の満開の下」は、暗い部屋のなかで、大学時代に夢中で読んだ懐かしき作品です。
岩下志麻は、特に好きな俳優ではありませんが、やはり、「心中天の網島」と
鬼龍院花子の生涯(1982年)が好きですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「岩下志麻」さんと「篠田正浩」監督 、再婚しております。
昔、神奈川大学のキャンパスにあった小さな喫茶店で、白川かずこの詩の朗読を楽しんだことがあったけれども、あの頃には、もう篠田は彼女と、別れていたのかもしれない。(1969年といえば、私が、ちょうど高校生の頃でしたから。)
最近のこの「ユリシース」のような音楽をまじえての朗読ではなく、まだそらころは、細身の体に皮のジーンズをはおって、詩はともかく、かっこ良かったです。・・・
しかしながら。
女優さんと監督さんのカップルは非常に多いですね。
個人的な意見ですが、「女性は耳から恋に落ち、男性は目から恋に落ちる」とよく言いますね。
女性はその意味でも、「見る」ことよりも、「見られる」存在なのかもしれません。
そして、監督はその逆で、「見る」ことが専門ですからね。男はもともと「見る」ことが得意なんですが、目が女性よりも極端に発達しているのにもかかわらず、監督はさらにさらに、「見る」プロですから。
その分。
女性は、男性の顔や容姿の好き嫌いは当然あるでしょうが、生き抜くためにも、見えないところを見ています。
気質やら、性格やら、マイナス性格やら、バランス感覚やら、じぶんとの相性やら・・・食欲睡眠欲性欲そんなものを直感的に把握するのが女性なんではなんでしょうか。
そして、あまりにも、バランス感覚にとびすぎた男性は、基本、排除されます。(名誉やら金銭やらが極端にある場合はともかく・・・)
ゴダール監督と、アンナ・カリーナ・・・・
このふたりについて、最近、いろいろと考えていました。
おそらく、私の勝手な推測ですが、アンナ・カリーナは、谷崎潤一郎のナオミのような女だったでしょう。
父親に捨てられた彼女は、三島由紀夫氏のように祖母祖父に不思議な育てられたことでしょうし、家出フェチだと言いますから、自由にあこがれ、自在のなにか口には言えないような才能にかけようとしたのでしょう。
じっさいには、短編映画では、カンヌで映画賞を取っていますし、アンナ・カリーナという名前は、ココ・シャネルから授けられたといいますから、きっと並の凡なる美ではなく恐らく、廻りの人達をおどろくべきほど巻き頃くらいの美がきっと彼女にあったのだと思います。
「見られる存在」としての美。
自分は子どもはつくれないからこそ、自作に命を描ける監督たちの目にかなう美のスペクトル。
特に、ゴダール。
Jean-Luc Godard interview
彼は、食事中でも、考え始めると、まわりのことなどまったく気にすることなく、考えに没頭したと言います。
よくいえば、芸術家タイプ。仕事ホーリック。
悪く言えば、センスの悪い、頑固な変人。
まったく作品をつくりあげていくということは、他人がどういおうがなんと言おうが
、作品が成功すれば作家の勝ち。
最初は、アンナ・カリーナにひとめぼれで、彼女の一挙一動からインスパイアされていたということは間違いないでしょう。
・・・・・
上記のタバコのクリップを見ているだけで、当時の、新人類の女性という刺激をもらえます。
このクリップなんとかも素晴しいと思います。
なんという大胆、放蕩、不条理・・・・・恐るべく魅惑。
ナオミではありませんが、頑固で、センスのないゴダールにたいしてだんだん冷たくなる、アンナにゴダールは困り果てていたようですね。
「気違いピエロ」まではなんとかやっていたようですが・・・・
その後は、まるで、ゴダールは捨てられたも当然になり、別人のように暗くなっていったようです。(女子大生ヴェロニク役で主演しているアンヌ・ヴィアゼムスキーは、同年7月21日、ゴダールと結婚しているが、彼女があらわれなければ、彼は自殺していたかもしれない。)
あたまでっかちで、思想を偏愛する彼をアンナが愛せなかったのは実によく理解できますね。
トリフォーに言わせればゴダールのアンナに対する思いは、「死に対する思い」だというくらいだ。
「アンデルセンの国の女性は泣いてはいけません」という熱烈な花束とカードをゴダールからもらって、結婚をきめたアンナだったのに・・・・・・・・・・・・。
まこにと、芸能人の「恋と愛」は不可思議なものだと思う。
「男と女のいる歩道」アンナがいるからこそ、できた傑作。
音楽も素晴しい。レコードがすりきれるくらい聞きました。
・・・・・・・・・
あなたの脳にはクセがある―「都市主義」の限界 (中公文庫)/中央公論新社
¥720
Amazon.co.jp
養老さんの「あなたの脳にはクセがある」を読んでいて、あっこれ、昔オレが考えていたことと似ているとふと思った。
まあ、人間なんていうものは、そのときそのときの流行に流されるものですから、しょうがないといえばしょうがないのですが、彼の言うように、なんでもかんでも、アメリカ式というグローバリゼーション化は、そろそろ、限界に近づきつつありますね。
藤娘を踊る玉三郎さんみたいな長い長い日本の歴史。
アメリカにはまったくありません。
養老さんも書いていますが、自然そのものというのは、どうなんでしょうか??
それは、もう文化の否定です。
フロイトが書いているように、「欲望の否定」が文化ならば、「自然そのもの」は、人間にとってやっかいなものです。
やっぱり、少しばかりは、人の手がはいって、工夫された自然が一番美しい。そして、楽しい。
手がはいるということを、もっと私たちは考えても良いですね。男と女の問題のなかにも。
坂東玉三郎さんの意見を聞いても、やっぱり、女になろうとする限りない努力というものが感じられますから。
ただ、自然のまんまの女性というのは、それは女性ではありません。
男のなかで組み立てられた女。
女のなかで組み立てられた男。
もっともっと、文化として、昇華してもらいたいものですが、女ははたして、そこまで、男に理想を求めるものでしょうか??
・・・・・・・・・・・
1975年の5月のヴィレッジバンガードの録音。
あんまりいいんで、ずっと聞いていました。
五木寛之は、なかなか、いいことを言う。
「本来、私は事実というものにあまり信を置かないたちの人間なのである。まして人間の記憶や、人間の手になる記録などほとんど信じることをやめて生きてきた」
修羅場を生きた人間の言葉として私の好きなアフォリズムなのですが、このキースの「ヌード・アンツ」つまり「裸のアリ」もまた、要は説明のいらぬ聞けば納得の一枚かもしれません。
1975年の5月のヴィレッジバンガードの録音。
ソプラノとテナーサックスにヤン・ガルバレクが入っていますから、いやでも、期待しますね。
ベースもパレ・ダニエルソン、ドラムスとパーカッションがヨン・クリステンセンです。
最近私は、北欧にすごい興味をもっております。
昨日の北海道新聞にもスウェーデンの福祉や、男と女の生き方のサクセスストーリーが載っており、福祉国家としての誇りみたいなものも感じました。
ロハスという言葉もいま流行ってますが、経済がここまでひどくなれば、あとは、人は金ではなくて自分の実在の根拠を芸術や宗教に求めるのも当然のことだと思います。
日本人の世界に類を見ないこまやかさのアビッールが、世界にどう広がるか、私はやはり若い人に期待します。
私ももちろんがんばりますが・・・。
まずい。気持ちが負けている。
私は負けません。
やります。
最近の若者は可哀想。
すぐに「 キモイ」と虐められますね。
人が何かに聖的にとらわれて何かを一心不乱にやればキモイといわれるかもしれませんが、そんなこと言わせておけばいいんですよ。
ファッションセンスがないとか、
気配りがないとか、
優しさがないとか、
よけいなことを最近の若い女は言い過ぎ。
男は女よりもすべてがのろいのは、それだけ、熟成が必須の樽ということ。
じっくり男の子の発酵を待てずにぶーぶー言う女の人多すぎ。
人を育てるのは愛ですから。
男は女、女は男に対して、もう少し、興味を持ってつきあうべきですね。
虫に興味を持ったり、くだらないことに集中したり、自分の興味の体系学を男の子はつくりあげるのが
得意なんです。
女の子のようにファッションセンスも良くありませんし、口下手でもありますし、要領もよくなくても、
男の子は必死に自分だけの体系をつくりあげようと考えておりますから、味方と言えば、もはや母親と
彼女や妻しかいないんですが、今や彼女達もそれらの男の子たちに、不満愚痴ぶつけておりますから、
大きな男の子が育つはずがありませんね。
男の子が生まれたからガッカリ、と私は先日もこの耳ではっきりその言葉を聞きました。
つまり女の子はいつまでも母とつきあってくれる。
男の子はいつかびゅーといなくなってしまうと、だから女の子が欲しいと。
昔のお母さんは嘘でも、「うちの息子は将来の総理大臣か学者か」と子供に夢を与えておりましたね。
尊敬できる女性もたくさんおりますが・・・・今の母親のなかには、国のことも何も考えてませんものね。自分のことばかりでしょう考えているのは。
でも昔の女はそんな女の欠点・どうしょうもないところは自分で自分をわかってましたよね。だから、馬鹿な男にでも尽くしたでしょう。
女だけでは世の中うまくいかないとこころの奥で実感してました。
つまり、昔の女はすごいということです。
昔の女とは、多分、今の70以上の奥様達のことでしょうね。
60代ぐらいから日本の女性は、まともな人とおかしな人に、はっきりわかれるんです。
自民党がどうしたとか、先生が悪いことしたとか、まるでワイドショーのコメンテーター見たいなお母さんが多い。
いろいろ情報知っている割には、子供に対する言葉の使い方を知りません。
子供は母親が自分に対して限りない愛と計算外の愛とを与えてくれることに対して深い情緒と愛をこころに刻み込んでいくんですね。
だから、打算と計算の世の中にその男の子が出ていっても、その刻み込まれた深いloveの保存の栄養のおかげで、誰からいじめられようと、ライバルが打算の戦略をうってでようが、四面楚歌で苦しんでいるときにも、彼はくじけないんです。
美輪明宏さんが言っているように女の子は強く男の子はいくじなしなんですよ。
でもそれは、女は生活と現実に強く、男は夢と前人未到の道に強いように神が考えたんですからね。
男と女、お互いに尊敬の念を大切に生きていきたいものですね。
こんなことを考えさせるキースの「ヌード・アンツ」でした。
好かれのもナンバー1、嫌われるのもナンバー1、
林真理子の意見。(日本のなかで、本を書くだけで食べて行ける40人のなかのひとり)
これは日頃女性の気持ちが今一歩理解できない私にある程度の納得をもらった意見がある。
「そもそも男にはあり女にはないものに「教えたい願望」がある。
異性を教育し、調教したいという心理は「源氏物語」の時代からすべての男性に共通しているようなものだ。女にはこれが全くといっていいほどない。」
この意見を最近読み直して、明晰な女性だな、と見直した。
続けて、
「それでも昨今は、経済力がある女性の中に、若い男の子をいろいろと教育する者が現れたりするが、それを聞いても多くの女はうらやましがったりはしない。若い男を囲って、いろいろ仕込み、自分好みの男に仕立てたいと考える女性は何万人にひとりであろう。」
これも、普段のもやもやした気持ちにはっきり、ノーといってくれた。
実は私はこれから未来になれば、若い男を教育するような女がたくさん現れるだろうと思っていたのだ。それを彼女はノーとはっきり言う。
もろちん、女の本質は、マリア型とマドンナ型に別れるというので、どんな女性も、これらにまっぷたつに別れるというのではなく、これらの要素が少しのパーセントずつ、はいっているということだろうと思う。
少なくても、日本に、アンナ・カリーナのようなタイプの女性は、良くも悪くも、少ない。
なぜならば、日本では、まだ「個」の確立が天に向かってそびえていないから、生涯にわたって自分の哲学をつらぬきとうそうというような女性がたくさんあらわれてくるには、まだまだ、現われてくるには数十年かかると思う。
それに、個人的には、「個」の確立なんというカッコいい言葉は、今の日本では、かっこわるいと私は思う。
人は一人では生きては行けない。
そんな簡単なシンプルな哲学を世界の人は忘れている。
そうでなければ、こんなにあちこちで、戦争やらテロが続いているはずがない。
どんなことでも、どんなものでも、ありとあらゆる「モノとコト」は、タペストリーのように、複雑にこの世界・宇宙に編み込まれている因果応報の織物なのだ。
・・・・・・・・・・・・・・
「それよりも女は仕込まれることを望む。年上の素晴しい男性に、贅沢さやセックスを教えてもらいたいと願う気持ちは、女がどれほど強く経済力を持つ時代になろうと関係ない。」
フランスの遊び人であるドン・ジュアンなどに言わせると、「教育の本質はセックスの調教である」と書いているので、先生が妙なる事件を起こすのもある意味では先生の本質はそれなのかもしれない。しかしながら、そうだからこそ、理性で押さえ込むのであって、意思と理性のない先生ばっかりになる学校の生徒は不幸と言わねばならない。
ただ、この林真理子の意見に私は少しプラスすると、だからといって、女がそのままその男について行くというわけではなくて、霧子が結局のところその自分を育ててくれた男性から独立していくように、女性の方が男性よりも一枚も二枚も現実性は上手なのだから、最初は可愛がられながら、子猫を演じながら、いつかは虎として巣立って行くのが女なのかもしれない。
実際に子供を生み、結婚生活をするようになると、女性はまことに強くなる。
現実に足をきちっとつけて、一歩一歩歩むようになる。
まあ、普通これが始まると、冒険心の強い男は一般的にはその女には興味を失ってしまうのだ。
なぜかというと、渡辺さんが言うように、男というものは「夢」に生きるものである。
自分が育てた女というところさへ、きちんとその女性が男をたてて、お世辞の一つでも言っていれば男は本気でぶれたりはしないものだ。
今の世の中、少しまわりを見渡せば、「あんなお父さんになったら駄目よ」とか「あなたっていう人は・・」と、うんぬんかんぬん、女は、「ほんとうのことを言うようになる」のである。
女の方が言語能力が高いことは言うまでもない。
口喧嘩したら男は負けるのだ。
<だから口で負けた頭の悪い男は、暴力でその女に勝とうとする心理を女性は学ばないといけませんね。そうすれば、わけのわからぬ男に殺されたりしないですみます>
最後の最後に、逃げ道を、女性は作ってあげてくださいね。
「窮鼠猫を噛む」ということわざがあるくらいですからね。
昔の女性はだから負けたふりをしたのだがね・・・
日本の女性は「賢く」「けなげに」「男の本質を知った上で」「子供を育ててきた」のである。
尊敬する女性に褒められた男性の気持ちはどれだけ嬉しくがんばろうと言う気持ちになることだろうか。
昔の女性は好きな男が一生「虫」だけを追い続けていっても黙ってついていったのだ。
今の女性ならば、「虫ばっかりおっかけていないで少しは仕事しなさい」とか「少しはおしゃれでもしたら」とか「清潔さが足りない」とか、いわゆる、常識的なことを頭ごなしに言うことだろうと私は推測する。
そしてその男性は「虫」の研究を辞めてしまうだろうね。
あのファーブル昆虫記の奥様は確か二人いた筈。
再婚した時は、23歳年下の女性と一緒になった筈です。
ふたりとも黙ってファーブルの研究を支えていたんですね。
もともとマニアックなことは男性の18番の世界です。
女性には逆立ちしたってかなわない世界ですよ。
女性が、化粧や服装のコーディネートが上手だったり、コミュニケーションが得意なように、男性にもその得意分野というものはあるんですネ。
お互いがお互いの得意な面をわかってあげた上で、人生、仲良く生きて行きたいものです。
ファーブル昆虫記〈1〉ふしぎなスカラベ (集英社文庫)

¥740
Amazon.co.jp
だから、アンナ・カリーナはマリアタイプではなく、マドンナタイプです。良いか悪いか、そんな野暮なことはいいません。
1960年、ジャン=リュック・ゴダール監督の作品『小さな兵隊』に抜擢。以後もゴダール作品に数多く出演している。二人は1961年に結婚し、1964年には共同で映画製作会社「アヌーシュカ・フィルム」を設立した。第一回作品は『はなればなれに』(1964年)。ゴダールとは1965年に離婚。その後四度の結婚歴がある。1970年代後半にはライナー・ヴェルナー・ファスビンダー作品の常連だったドイツ人俳優兼映画監督ウリ・ロンメルと交際し、共に映画製作を行っている。
1961年の『女は女である』で、ベルリン国際映画祭女優賞を受賞している。
それにしても、女優と監督。
「見られる女」と「見る男」の組み合わせ。
ゴダールとアンナのことも含めて、考えれば考えれるほど、興味深いです。
「岡田茉莉子」「吉田喜重」監督
「八千草薫」「故・谷口千吉」監督
「神楽坂恵」「園子温」監督
「高橋恵子」「高橋伴明」監督
「とよた真帆」「青山真治」監督
「満島ひかり」「石井裕也」監督
「宮本信子」「故・伊丹十三」監督
「草刈民代」「周防正行」監督
「新藤兼人」「故・乙羽信子」。
フェデリコ・フェリーニ ジュリエッタ・マシーナ
ジョン・カサベテス ジーナ・ローランズ
もっともっと書きたいことがあるのですが、三日前に、またまた、不整脈で、真夜中に救急車で運ばれてしまったのです、どうも頭が働きません。笑えます。
でも、精神安定剤を飲んでいると、少し酒を飲んでいるようで落ち着きます。
なにやら、平和な感覚が、胃袋あたりにおちてきて、嬉しくなります。
最後は、最後の最後迄、夫婦というものについて考える時にいつも連想する映画・・・・あたりにとっても、最後の映画であり、またまた、そこにでているジェーンフォンダが、実の父親であるところの、フォンダとの確執もふくめて、名作中の名作をここに、アップしておきましょう。この夫婦はほんとうの夫婦ではありませんが、ほんとうの夫婦以上の夫婦に見えます。
三回見ても、不思議な感銘をもらえる傑作です。
三人ともに、人生のなかで、その美しさを輝かしたが故に、
黄昏ともいえる、人生の最後の最後の季節、
小さな湖のほとりで、しずかな時間をすごすときに、
圧倒的な、存在感と、過去の美しさへの思慕が、思い起こされ、
じーんとした幸福な感覚にとらわれます・・・・・・・・・・・・・
キャサリン・ヘプバーン

ジエーン・フォンダ(ヘンリーフォンダの実の娘)

ヘンリ-フォンダ (ジェーンの実の父親、娘の政治問題のコメントなどで疎遠となっていた)

「黄昏」すでにTSUTAYAにはありません。
文学というものにもしも、「毒」がなかったら、だれもそれを読む人はいなくなるでしょう。
そもそも教会に通って、神父の話を聞いて満足していれば良いのであるから。
愛の倫理 (角川文庫 せ 1-2)/瀬戸内 晴美

¥441
Amazon.co.jp
この本の中に、こんな毒の文句があり、昔読んだ時にはどきっとしたものですね。
「人間の愛などというものが、そもそも不確かなもので、心は移ろいやすいものである以上、一人の男や女が、一生にただ一人の相手しか愛さないなどいう方が、むしろ奇跡的で、そういう心の方が片輪かもしれないのである」
しかしながら、長く人生を生きてくるとこの文句が確かなことは理解できます。
形として離婚するしない、とかそういうことではなくて、しっかりした夫婦であっても、心のなかでは
違う異性に胸をときめかしているものだということを、真っ正面から見つめることができるかどうかであります。
河合隼雄氏もまた、夫婦というものの心の中での儀式というものの大切さを語っておりますね。
もっとも文学というものの性質上、悪人かと思われた人の中にきらりと光る善が浮き出るのであり、一見善人かと思われた人の心のなかにダークで深い悪がある、それを書ききるのが文学の技でもあります。
この世のなかで、まるっきりの悪人がいるとも思えないし、また完全なる善人などがいるはずもないですね。
映画で言えば、この「黄昏」。
この映画はたくさんの人に感銘を与えました。
まさに、人間がああはうまくはいかないと思っているからこそ、皆が、映画の中での、現実ではなかなかありえない、理想的な夫婦に拍手をするのかもしれませんね。
原作は1978年2月にブロードウェイで舞台化されたアーネスト・トンプソンの同名の戯曲(原題:On Golden Pond)である。父と娘の確執を取り扱った作品であるが、それは実生活におけるヘンリー・フォンダとジェーン・フォンダの不和を思い起こさせるものだった(詳細はそれぞれの記事を参照)。ジェーンが父親のために戯曲の映画化権を取得したとされる。
ジェーン・フォンダは父親の相手役として大女優のキャサリン・ヘプバーンを推薦した。数十年の芸歴がありながらも、一度も同じ映画に出演したことのなかったフォンダとヘプバーンの大物俳優二人の共演が、本作品で初めて実現することになった。
公開後本作品は批評家たちから絶賛され、興行的にも予想外の大成功を収める。1981年度の第54回アカデミー賞では作品賞を含む10部門の候補となり、そのうち主演男優賞、主演女優賞、脚色賞の3部門で受賞した。キャサリン・ヘプバーンが自身の記録を塗り替え史上最多となる4度目の主演女優賞、ヘンリー・フォンダが史上最高齢の76歳での主演男優賞と記録尽くめの受賞になった。2009年現在もこの二つの記録は破られていない。
本作品で念願の主演男優賞を獲得したものの、ヘンリー・フォンダは授賞式を健康問題で欠席。娘のジェーンが代わりに出席して賞を受け取った。フォンダは式の数ヶ月後の1982年8月12日に子供たちに見守られながら心臓病で死去、彼にとって本作品が最後の映画出演となった。
たしか、ジェー・フォンダの政治的な発言で、ピーターフォンだが怒り、その後は、ギスギスした関係になってしまいましたが、この映画のなかで、ふたりはまた、新しい関係をふみだしたようにも見えてきます。
そのようなことも考えれることができるのも、映画のおもしろいところですね。
Jane Fonda On Golden Pond
「映画だけを見るのは駄目です。文学や音楽や絵画や日本舞踊を見て、勉強していきましょう」
淀川長治 FIN
男と女の相性「あした来る人 」深津絵里 CM 「女の子ものがたり」「悪人」
「映画に説明やオチなど必要ない」(ミヒャエル・ハネケ)
「あしたくる人」見ました。
原作は、井上靖です。
監督は、 川島雄三 。
昔の映画ですので、白黒ですし、スピードもリズムもなく、じっくりじっくり、物語はすすみます。
でも、そこがいいですね。
男女には相性というものがあると思います。
反撥したり、くっついたり、理由はわかりませんが、まるで磁石のように、
プラスマイナスが人にはあるようです。
この映画もそんな人間模様を、丁寧に丁寧に、描いているのだと思います。
物語資料から
実業家梶大助のホテルへ彼の娘八千代の紹介で、曾根二郎という青年がカジカの研究資金を出して貰うためにやって来た。心よく迎え入れた梶も、決して金を出すとは云わなかった。八千代は夫克平に不満を持っていたが、その夜も遅くなって一匹の小犬をかかえて帰ってきた彼と冷い戦争をはじめ、八千代は大阪の実家へ戻ってしまった。克平は八千代がいなくなってから、相棒の三沢やアルさんとカラコルム山脈征服の計画を実行しようとしていた。ある日例の小犬を見ず知らずの女性が連れているのを見つけた。なつかしさに近寄ると、それは洋裁店に働く杏子だった。八千代は梶に叱られて東京に戻ってきたが、克平の登山計画をなじった。梶の世話を受けていた杏子は、それが克平の義父とも知らず、克平と結婚したい旨打明けた。名前を云わなかったため梶も色々と杏子を励ますのであった。克平は鹿島槍登山に出掛け、直後新聞がその遭難を伝えてきた。早速杏子は遭難現場に急行したが、克平は無事で思わず二人は抱き合った。克平が帰宅したとき曾根が来ていた。その後八千代が余りに曾根をほめるのと、遭難のことに冷淡であったため、克平も感情を害したが、八千代は杏子と彼の仲を知ってのことであった。曾根の取持ちも空しく克平の心も最早八千代にはなかった。その頃杏子は偶然八千代に会い、克平が梶の娘の夫であることを知って悩んだ。克平は遂に山の征服の雄途に乗り出すべく羽田を出発した。結婚のことは最後まで云い出せなかった杏子だった。
上の資料の物語を読むより映画のほうがずっとおもしろいのは、井上靖の小説をじっくり読むのと、また、ヒロインなどの美しさに魅惑されながら、映画を楽しむという、まったく別の楽しみ方を私はしているからでしょうか。
監督の川島雄三。好きです。
いいんです。軽くて・・・・・・・
作風
日本軽佻派を名乗り、独自の喜劇・風俗映画を中心的に、露悪的で含羞に富み、卑俗にしてハイセンスな人間味溢れる数々の作品を発表した。
人間の本性をシニカルかつ客観的な視点で描いている作品が多く、弟子の今村昌平の作品ともども「重喜劇」と称されることが多い。川島の場合、脚本を担当した藤本義一が命名したとも、フランキー堺が呼称したとも言われる。今村がムラといった地方の土着社会に関心が移行していったのに対し、『洲崎パラダイス赤信号』や『しとやかな獣』に見られるように川島は都市に関心を持ち続け、都会に生きる現代社会の人間達をテーマの中心に据えていた。
作家・織田作之助と親交が深かった。一方で同郷の小説家としばしばみなされた太宰治は嫌いであり、太宰より織田の作品を読むことを薦めていた。また井伏鱒二のファンであり、強く影響を受けていた。「サヨナラダケガ人生ダ」という詩訳の科白を愛用しており、『貸間あり』の中で桂小金治にこの科白を言わせている。
死亡時、寝床にはインタビュー記事が載った中央公論と、次回作に考えていた写楽を主人公にした「寛政太陽傳」用の青蛙房版の江戸風俗資料が置かれてあった。[2]この映画で主人公写楽を演じる予定だったフランキー堺は、後年、篠田正浩監督で「写楽」を製作・出演。完成後の1996年6月10日にこの世を去った。
勧君金屈巵 君きみに勧すすむ 金屈卮きんくつし
満酌不須辞 満酌まんしゃく 辞じするを須もちいず
花発多風雨 花はな発ひらけば 風雨ふうう多おおし
人生足別離 人生じんせい 別離べつり足たる
この漢詩です。
井伏が、この詩を自分の好きなように、訳したのが、有名になりました。
コノサカヅキヲ受ケテクレ
ドウゾナミナミツガシテオクレ
ハナニアラシノタトヘモアルゾ
「サヨナラ」ダケガ人生ダ
月丘夢路は、三島由紀夫氏の「美徳のよろめき」にでているところも、シンクロの糸を感じます。
新玉三千代は、そうなんです、「霧の旗」に出ていました。なつかしい。

まるでフランス映画、ヌーヴェルヴァーグの作品を見ているような、白黒の美しいシネマ。
何回もテレビでも放映されたようで、筋書きそのものは誰でも知っている復讐もの。
私は、三島由紀夫が、「日本文学全集」を川端康成などと一緒に、作家を選んでいる時に、松本清張を断固として拒んだということをふと、思い出した。
三島由紀夫は、「あるべきもの・ことを描くのが小説」というのが持論。
松本清張は、「現実の裏側にあるもの・ことをえぐりだす」のが得意だったから、小説に対する美意識が違ったのだろうと思う。
そのことが悔しくて、松本清張は、のちほど、とある賞を獲得したとか。
まあ、そんなことはどうでも良いのだが、私は、倍賞千恵子の演技に感心した。
獲得が山田洋次で、カメラも、撮影:高羽哲夫とくれば、「寅さん」を連想すると思うけれども、「さくら」のイメージで、最初、私はこの古い日本の白黒シネマを見てしまった。
素晴らしい!!!! 倍賞千恵子。
この作品の少し前に作られた松本清張の、「張り込み」にも感心したが、やはり、印象に残っているのは、高峰秀子の美しさ。
現代の日本映画の女優達も、皆美しいけれど、やはりシネマ界にも、歴史があり、女性美の長い歴史があってこそ、今の女優達がいるのだと再認識。
倍賞千恵子は、フランスの、ブリジット・バルドーや、ジェーン・フォンダや、たちにも、ひけをとらない。日本の美だ。


たしかに、ブリジット・バルドーは、わたしたちの時代のアイドルだったし。
ジャンヌ・モローの独特の美も印象深い。
黒衣の花嫁は好きだった。
雨の忍び逢いも良かった。
フランス映画と言えばやはり、この女優。
見事なフランス人の美しさがある。
でも、やっぱり、私は日本人の女性美が良い。
タモリではないけれど、吉永小百合を超える日本女優はまだいないと思っている私だ。
◎霧の旗物語資料から
殺人事件の容疑者として逮捕された兄の無実を信じ、高名な弁護士に弁護を依頼する妹。 しかし、貧しさゆえに断られた妹は弁護士に復讐を誓う。 松本清張原作の映画化。山田監督初のそして唯一のミステリー映画。
◎資料
映画『張込み』の製作以降、著者と面識のあった橋本忍の発言によれば、当時著者は、アラブ人男性のフランス人医師に対する復讐を描くフランス映画『眼には眼を』を観て非常に感心し、こういう(趣向の)ものを書きたいとさかんに言っており、そうした発言ののちに著者が本作を執筆したとされている[2]。
本作は単行本化の際、最終回連載部分に原稿用紙30枚分の加筆がなされた。特に大塚の懇願に対する桐子の態度の描写や、第二の殺人に関する大塚の推理部分、桐子が検事に宛てて送った手紙の部分が大幅に加筆、精緻化された[3]。
詩人・翻訳家の天沢退二郎は、小説の描写において、桐子の意識に入り込んだ描写と、大塚・阿部の意識に立ち入りつつ桐子に関して外面模写のみに終始する描写が振り分けられ、二つの異なる桐子像が小説内で峻別されていることを指摘している[4]。社会学者の作田啓一は、本作において大塚弁護士の側に罪があるとすればそれは「無関心の罪」であり、現代人の多くがひそかに心あたりのある感覚であると分析している[5]。評論家の川本三郎は、本作が発表された時期には、現在の東京一極集中に通じる、地方と東京の大きな格差が生まれていて、桐子の大塚弁護士に対する恨みの背景には、地方出身者の東京に対する恨み(と強い憧れ)があると指摘している[6]。
このあたりが、松本清張の良いところであり、悪いところ。評価が別れると思う。
シンプルにするのであれば、もっとユーモアを入れると良いと思うのだが・・・
原作:松本清張
監督:山田洋次
製作:脇田茂
脚本:橋本忍
撮影:高羽哲夫
美術:梅田美千代
編集:浦岡敬一
音楽:林光
ところで。
・・・・・・・・・・
最近このコマーシャル、なかなかいいな、と思ってみていました。シリーズもののCMです。
テレビもあまり見ないですし、ここ五年間は、多忙でしたから、女優の名前も浮かばず、・・・・・・・・。
アホです。
それで、調べてみると、深津絵里。
資料を見ると、なかなかおもしろいというか、ユニークな感じでしたので、
・・・・・・・・
それに、42歳にしては、かわいすぎる。

◎資料から
大分県大分市出身であり、『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』で1シーンだけ大分弁を話すシーンがある。同シリーズでは同じ大分市出身のユースケ・サンタマリアとも共演している。
映画『阿修羅のごとく』で酔っているシーンを撮影する際、実際にお酒を顔が赤くなるまで飲んで撮ったという。本人は酒好きであり「お食事を頂いているときにちょっと飲む程度。好きなのはシャンパン。酔っぱらうことはありません」とインタビューで話している。
JCBのCMで激辛トムヤンクンを食べるシーンで、スタッフが空のお皿を食べている演技をしてもらうつもりだったが「それではリアルさが伝わらないのでは?」と自ら提案し辛さ20倍のスープを涙ながらに飲んだというエピソードがある。
同じ事務所所属の福山雅治に自身の1月11日の誕生日に111本のバラをプレゼントしてもらったことがある。
女優の握力を予想するゲームにおいて、周りの予想を上回る32kgをだし場内を沸かした。
ドラマ『カバチタレ!』は、かつて『悪魔のKISS』で共演した常盤貴子が、「また深津と共演したい」という希望が叶ったドラマであり、話を聞いた時お互いが逆の役をやるのとばかり思っていた。
常盤貴子とはドラマで共演して以来仲がよく、プライベートでも一緒に遊んだりしている。天海祐希とも仲がよい。天海が30代の時、常盤も含んだ3人で「カッコよく楽しく生きる三十路会」を開いていた。
木村拓哉、福山雅治、田村淳、臼田あさ美、佐藤健、水川あさみ、星野真里など芸能人にファンが多い。木村拓哉は「深津絵里さん=女優。 優れた女と書いて女優。」と評している。また臼田あさ美は自身のブログで憧れているとコメント、同じアミューズ所属の佐藤健は原宿でスカウトされた際、アミューズが深津の所属する事務所だと知って芸能界入りを決心したほどであり、『恋するハニカミ!』にゲスト出演した際、「中学の頃からのファン」「ハニカミデートしたい」と語るほど深津のファンである。
三谷幸喜は深津を映画『ザ・マジックアワー』に起用した理由について、2007年(平成19年)に公開した映画『西遊記』で共演し会話をした際「感じが良かったから」だと話す。劇中で深津はアフレコではなく撮影時の生歌を披露しているほかエンディングにはロングバージョンも歌っている。このことについても「深津さんは歌でも芝居でもホントにカンの良い人でした。(アドリブも)深津さんは絶対に笑わない。彼女はNGも出さない。もう、鉄の女。絶対に崩れないタイプ」「耳もいいし、英語の発音も完璧。エンディングは圧巻でした」と評している(『ザ・マジックアワー』オフィシャルブックより)。
彼女が、主演している作品をとりあえず、2本。
「おんなのこものがたり」と「悪人」を見てみようと思い、まずは、ゲオへ。
「おんなのこものがたり」
2009年に封切りされたのに、今頃みている、わたし。
ということは、もともとは、縁のない映画だったんです。
でも、深津絵里のCMを見ていたら、自分の好きなジャンルではないのですが、見たくなってしまい・・・・・・・・
西原女史の自伝的漫画がもともとの作品なんで。
漫画家というのは、しかしながら、おもしろい職業だなあ。そう思います。
ある意味。女性の枠を、超えて、男性に近い考え方ができて、それでいて、女性のこころもありますので、かなわないところがありますね。
普通は、「女子の友情というものはなかなか続かない」と、言われているわけですが、
言われているだけで、私の妹なんかも、小学校時代の友達たちと今でも、月1くらいのペースで、食べたり飲んだりして仲良くやってますから、一概に友情はないとか言えないのでしょう。
作品にするわけですから、自分のリアルな過去の記憶をすこしばかり、小麦粉で膨らませてみたり、ひっぱったりのばしたり、小さく切ったりしていることは当然のこと。
ただ、残念なのは、深津絵里は、今現在で漫画家になっており、過去を思い出すという視点で、作品が出来上がっていますので、印象的には、なっちゃんという若き日のイメージは、
高原菜都美(現在):深津絵里
高原菜都美(あだ名はなっちゃん。高校生時代):大後寿々花
きみこ(あだ名はきいちゃん。高校生時代):波瑠
みさ(あだ名はみさちゃん。高校生時代):高山侑子
となっております。
私は、テレビが見る暇がないので、まったく、邦画やCMの女優達を知りません。
が、たまに、おっと思う存在感のある女優を見つけると、だれかな??と調べてみるだけ。
深津絵里さんもそうだったように。
この大後寿々花さん。
「サユリ」で、新人賞を獲っているんですね。それに、以前の記事で書いた「北の零年」にも出演していたとか言われると、えっ、まったく覚えていません。
あわてて、調べ直すと、子役でした。

「sayuri」の、小森和子賞は、すごいと思います。
きみこ(あだ名はきいちゃん。高校生時代)役の波瑠さん。テレビドラマでも、ここ最近がんばっていますね。
朝ドラの。
NHK連続テレビ小説『あさが来た』のヒロイン・白岡あさ役に決定したわけですから、これはすごいと思いました。
それに、役柄のきいちゃんは、死んでしまいますが、ドラマが変われば、また再生するところが、嬉しいです、再会できるわけですから。ファンにはたまらないでしょう。
おんなのこものがたりのなかの、詩のような描き方の映画で、ほんわりほんわかムードの映画でしたが、最後の三人のケンカするところ・・・・ここは素晴しいかったですね。
義父がいうところの、「人と違う人世をおくれるかもしれん」という言葉を胸に、なっちゃんは上京するわけですが、たしかに、たくましく、自分の限界をきちんと知って、自分の立場をしっかりと知っている友達達との・・・・・・・・距離感はたまらなかったでしょう。
あと、
高山侑子さん。
父親は、航空自衛隊新潟救難隊の救難員でしたが、2005年4月、訓練中の墜落事故で殉職しています。同年秋に防衛庁(当時)で実施された自衛隊殉職隊員追悼式に出席するため家族で上京した際、原宿でスカウトされたこと、・・・・
2008年、映画『空へ-救いの翼 RESCUE WINGS-』で映画初出演・初主演を果たしたこと・・・
2015年、「新・戦国降臨ガール」にて初舞台・・・・・などなど。
父親の追悼式でスカウトされたことや初主演映画が航空自衛隊を扱った作品であることに運命的なものを感じるそうで、「父に導かれたような気がする」と語っている。
深津絵里。
もう一本のビデオを見ながら、最初のシーンで、あれれ?
これ見たという感じでした。
記憶力というのはほんとうにあてにならないものです。
どうしようもないアホです。
しょっちゅう、一度見た作品をまた、借りてしまいます。
二度見るのは楽しいので、あまり気にはしていませんが、ボケはじまっているかも。
彼女は、この作品で、ふたつ賞を獲っています。
なかなかないことらしいです。
第34回モントリオール世界映画祭最優秀女優賞、並びに第34回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞(尚、日本アカデミー賞での最優秀主演/助演女優賞のダブル受賞は桃井かおり・大竹しのぶ・小柳ルミ子・倍賞美津子・原田美枝子・和久井映見・樹木希林に次いで史上8人目)。
映画が小説とするならば。
でも、CMも、なかなか素晴しい、一編の詩・和歌短歌。
こんな記事を書いておりました。記事まで書いているのに、すっかりわすれているんだからどうしょうもありません。
日本映画の売り上げが外国映画より多くなったという逆転劇から、数年。
今はどうなっているのか?
「フラガール」の監督だったから以前から見たかったが、見たい映画が多過ぎ、今頃見る。
レヴューを見ても、自分の気持ち・気分・鑑賞フイーリングと添うものがないというのは、やはり、映画は見る人によっていろいろな見方があると言うことだろうと、思う。
撮影笠松則通
美術監督種田陽平
美術杉本亮
装飾田口貴久
照明岩下和裕
音楽久石譲
音楽プロデューサー岩瀬政雄 、 杉田寿宏
主題曲/主題歌福原美穂
とまあ、資料にもあるように、かなりの画像のハイレベルシネマ。
切ない音楽のタッチや、切々と流れてくる音の迫力やら、雨の音などの効果も高いのが印象的。
これはやはり、映画館で見た方が良い映画かも。
深津絵里はまさに適役。妻夫木聡を完全に食っている。
不思議だが、私はなにやら、この映画の途中、深津絵里のキャラに日本人特有?の任侠映画によく出てくる「待つ女」の原型みたいなものを感じていた。
ただ、個人的な意見としては、小説とはまったくの別物としての映画としてコメントすると、この金髪男性がなぜあの娘を衝動的にでも殺してしまうのかがちょいと不明、理解できない。
ひょっとするとカミユだったか、太陽がまぶしかったから殺人をしたというような不条理な人間の悪の心理なのかもしれないが・・・
それにしても、普通の常識からこの映画の登場人物を見てみると、あの樹木希林が演ずるおばあさんの人物の設定からすると、とても、あのような殺人鬼の子を育て上げるとは思えない。
確かに、解体屋という職業のイメージから、彼の未来を暗示しているのかもしれないけれど、土木作業員やら解体屋やらの、世間的な信用のなさや、世間的な下位の職業として設定しているところに古さを感じてしまう。
離婚歴などの家庭、異性感からもたらされるコンプレックス、下位の職業などのいわゆる「環境」に、犯罪を犯す本質的な要因があるなどと、表現されるのは、どうも昔の「左翼的な発想」を無理矢理押し付けられている感じがしてとても嫌だ。
むしろ現代を表現するならば、あの非常にクネクネした、岡田将生なんかの方が、まさに太陽がまぶしいから人を殺したみたいなことが似合うかもしれない。
満島ひかりにしても、あの父親からあんなような娘が育つとはとてもとても思えない。
小さな頃に、父母が朝から必死に働いているような両親の後ろ姿を見ていると子供はぐれないと、よく言われる。
だからこそ、中流の、親が権威をかさに自分の正しさを子供たちに押し付けるような親が、子供をおかしくするとも言われているこのごろだ。
確かに、孤独な二人はそれを接点にして、要に引きつけられるということはあると思うが、どうも 、深津絵里と妻夫木聡が、それだけ、孤独だということがこちらに前半の物語だけからは、伝わってこないので、後半の二人の、愛の逃避行や、せっかくの深津の素晴らしい演技力、迫真の表情などが、100%の、クライマックスとして納得できないのだとも思う。
携帯サイトで、ナンパする連中を深津の姉?が、批判するシーンがあるが、これもまた、彼女の決めつけた極論で、時代が変われば、道路でナンパするアナグロ・ナンパからデジタル・ナンパに変化していったということだけでしょう。
うーん。
やはり、あの二人の、恋が成就していくプロセス、スタンダールの恋愛の塩の結晶のプロセスが、もっときちんと描かれていればなあと思う。
安物紳士服売り場の販売員と、建築解体屋の恋。
これは現実的には、販売員はもっと明るく、これだけの孤独を心の奧に持っている人はいるようなイメージ作りの職業としてはどうかなとも思う。
建築解体屋がコンプレックスを持つような職業というのも理解しがたい。
私の友だちにもたくさんそのような関係の人間がいるが、もっともっと「大人」で、あの
妻夫木聡が心に持っているような孤独はまたまた、理解しがたい。
どうもそんなわけで、二人の恋の逃避行にだけはついていけなかった。
そして、なんで、また深津の首を締めるのか? わからない。
しかしながら。
深津の演技力には見ていて、かなり引き込まれ、彼女の顔に時折現れる狂気にまで到達するような「過剰」性に感動した。
ニーチェについて小林秀雄氏が書いている文章があるが、こんな文章です。
大学時代に読んで、感動して、いまでも、よく覚えているのです。
「ニーチェは、ギリシア人がりっぱな悲劇を書いたということこそ、ギリシア人が厭世家ではなかったというはっきりした証拠だといいます。ちょっと聞くと、反語のようにも聞こえますが、それは、悲劇と厭世というふたつの概念を知らず知らずのうちに類縁のものと私たちが思っているからでありましょう。
おそらく、ニーチェは、そのことを頭において強く主張する、悲劇は、人生肯定の最高の形式だと。人間になにかが足りないから悲劇は起こるのではない、何かがありすぎるから悲劇がおこるのだ。否定や、逃避を好むものは悲劇人足りえない。何もかも進んで引き受ける生活が悲劇的なのである。不幸だとか、災いだとか、死だとか、およそ人生における疑わしいもの、嫌悪すべきものをことごとく、無条件で肯定する精神を悲劇的精神という。こういう精神のなす肯定はけっして無知から来るのではない。そういう悲劇的智慧を掴むには勇気を要する。勇気は生命の過剰を要する。幸福を求めるがために不幸を避ける、善に達せんとして悪を恐れる、
さような生活態度を理想主義というデカダンスの始まりとして軽蔑するには、不幸や悪はおろか、破壊さへ肯定する生命の充実を要する。
そういうディオニソス的生命肯定が、悲劇詩人の心理に通じる橋である、とニーチェは言いきるのであります。ニーチェの激しい気性は、アリストテレスのカタルシスの思想に飽き足らなかった。」
要するに、「幸福」だけを狙って「引き寄せる」なんていうのはとんでもないことで、間違って「悲劇」を引き寄せても人はその運命を愛するべきなのだということですネ。
これは恐るべき言葉です。
職業とあの孤独が、むすびつく論理は、納得はできないけれども、もしも、あのふたりが、なにやら、小さな頃から「過剰性」を持っていて、何をするにしても、人の数倍も夢中になっていく気質があり、そのおかげで、皆から少し変人扱いされていてひしひしと孤独を感じているという心理設定。
ならば、納得いくわけです。
西部邁と栗本氏の対談で、日本女性はもう男を愛する力を失ったとまで書かれた、最近の若い日本女性。
この深津理恵のようなキャラが、男性から強く求められているのか、それとも、演歌的でダサイと思われているのか、そのあたりは興味深いことである。
以上、自分自身のための記憶強化のための記事でした。
記憶強化のため、と書いておきながら、忘れているんだから、そうなっていないわけですね。
私は、前ばかり見て戦って来たいわばサラリーマン戦士でしたから、一年前、二年前などのことはすっかり忘れているのかもしれません。
ここ最近のこと、今日のこと、明日のこと、・・・・・・それだけで。
とにかく、思い出せて良かった。
「"好きになることが相手を助ける""知識は(異文化への)恐怖を取り除く"」「これらは全て映画が教えてくれた事」 淀川長治
FIN
◎深津絵里 CM資料
人工知能の世界=トランセンデンス ジョニー・デップ レベッカ・ホール
ホーキング博士
次なる映画は、テーマがむずかしすぎるけれど。興味深く観れた。
いつかは人類が直面する問題そのものだろう。
深くえぐることができなかったのは、残念。
「トランセンデンス」
◎トランセンデンス
くだらない批評家の意見はともかく、映画は好き嫌いなので、普通にこの映画を観れば、いろいろ不満はでるかもしれない。
たとえば、
ジョニー・デップが出番が少ない。
ヒロインの魅力が最高にアップされていないような気がする。
物語に必然性があまり感じられず、現実味をしみじみと感じられない。たとえば、ブレードランナーや、2001年宇宙の旅ならば、あれだけ、バーチャルの世界を描いていながら、まるで、現実感はそのまま残る。圧倒的に、普段の生活の視点や考え方に影響を及ぼす。
それはない。
そこまでいかない。
と、いろいろ文句はあるかもしれない。
それでも、やはりSF映画はみるべきだと思う。
近い将来に、起こるべきしておこるかもしれないことに、チャレンジしているので、たくさんのヒントがもらえるのだ。
今一番世界のひとびとが注目している人工知能の世界を描いているからだ。
たしか「tay」だったか、世界最高の人工知能ということですこしずつ学習していくと、人類の悪い学習をもそのまま学習してしまうというミスをおこしてしまった事件は誰しも知っていることだと思う。
「人類の悪意」をも取り込むことができる。
「人類の善意=思いやり・優しさ・自己犠牲」をもとりこむことができる」
つまり、人口知能というのは、人類そのものには興味を持たないけれど、自分に与えられた演算計算を100%正確にやろうとするある意味、悪魔であり、天使でもある。
つい先日、テレビで、将棋の天才の羽生さんが、人工知能ロボットをつくっている人、研究している人と対談する番組を観て、こんなことをも感じた。
朝の曇って入るけれども優しい光に刺激されて目がさめてしまう。
昨日見た、羽生さんの「人工知能」の番組についてのアイデアをなぐり書きしたカードをじっと見てみる。
もう何を書いたのかわからないくらいの下手な字がミミズのように這っているのを解読しながら。
目が覚めるのを待つ。
昨日飲み残しの紅茶を飲む。
中国のシャオアイスという原始IT のスマホに羨ましさを感じる。
あれなら私も欲しい。
ペッパー君も可愛いけれど、高すぎ。
私が生きている間にどれくらいのITロボットが生活のなかにはいってくるか、ある意味愉しみでもある。
地下で本を立ち読み。
A4の箱くらいのテレビを見ながら死んで行った母ではないけれど、私もまた日々A4前後から、文庫サイズのバーチャル箱の中をのぞきながら、生き続けている。
ただただひたすらに、情報は楽しい。
知識は快楽。
考えることは人にあたえられた最高の幸福。
ダライ・ラマが言う。
「贅沢なんてつまらない」
考えることの楽しさを知ってしまうと、もう、その他の愚痴不満、環境に対する怒りなんかに興味がなくなってしまう。




若い頃は、友達と遊んでは、自分の好きなことを見つけておく事。
これができれば、人生は最高に楽しい。
日本人は特に、完璧主義で、「楽しむ」ことが苦手。
対人関係でも、小さなことばかり気になってしまう。もっとおおらかに、笑い、のびのびと、語り合いたいものだと思う。
人工知能について書いてきて、わけのわからない自分の幸福についての気持ちやら、人生の楽しみ方まで、ふと、考えてしまう。
人工知能と違って、私の不完全自然脳は、我がままで、いいかげんで、正確なんていうものではないテキトーな「脳」という人類の数億年かけてつくりあげてきたありがたき産物なのであった。
そんなことをかんがえながら、この「トランセンデンス」を観ると、それなりに、興味深い。
ジョニー・デップもまた、俳優の人気をもってして、好きな音楽活動をすることを嫌っているので、彼の自然体の映画というのは、意外に、少ないのではないだろうか。
彼が、自然に得意のギターをつまみながら、ビノシェと愛を語る「ショコラ」の素晴しさはそこにあると個人的に思っている。
彼は、結婚相手の元恋人であった、(信じられないが) ニコラス・ケイジの薦めで、映画界に入ったという。やはり、人生は、縁、縁、縁これしかない。不思議な縁だなぁと感激する。
ニコラス・ケイジは大好きな俳優なので、興味のある方はこちらの記事で・・・
◎この有名な「エルム街の悪夢」が、ジョニー・デップのデブュー作と言われていますが、「暗いベイビー」という人もいます。
・・・・・・・・ 私にはどちらでも良いことですが。
そして、
彼のイメージをつくりあげた偉大なシネマ。
私のフェボリットといえば、この映画でしょう。
「シザーハンズ」
ボクは個人的には、童話でも、「マッチ売りの少女」とか「スズの兵隊」とか「人魚姫」とか、あのタイプの物語にはめっぽう弱い。
ワイルドの「幸福な王子」なんかは、何回泣いたことか。
ワイルドの題名は忘れてしまったが、子ども達を自分の庭から追い出そうする鬼?の話し。
あっ思い出しました。「わがままな大男」でしたね。
これらの物語の一環として、「シザーハンズ」を感じてしまう。
つまり、普通の仲間のなかに、なかなか入って行けない特殊な人達。しかしながら、その技能は、あるときは非常に危ないけれども、あるときには、非常に有能に使える武器にもなる。
父親が、土方で、母親がウェイトレスで、彼が小さな頃に離婚している彼の、複雑な人生を感じていると、映画のなかの、シザーハンズの彼が、なんと愛おしいことかと、思ってしまう私がいる。
今や、テレビでも、政治でも、二世ばやりで、親の七光りで芸能界に出てくるアホな輩がつぎからつぎへとでてくるけれども、やはり、自分の力と、自分がひきよせた運で、縁で、細いロープをよじのぼってくる彼のような才能には、拍手をするし、ボクは彼のようなタイプの俳優にはケイジ同様に弱い。
「ショコラ」で、ジプシーのリーダーをしている彼が、カソリックの歴史の強い村で、ある意味村八分されるなかで、ジュリエット・ビノシェ親子に次第に、おたがいにひかれていくシーンは大好きだ。
まさに、彼にぴったりの役柄。
その意味でも、この「トランセンデンス」の彼、異能で、とんでもないイマジネーションにとらわれている変態科学者役にはうってつけの彼。
その意味でも、ファンならば観るべきだと思う。
私はそれだけでも、この映画を借りた意味があると思っている。
よく言われることだけど、原宿で拾われるような普通の少女や少年が、映画に抜擢されて人気がでてくると、まるで頭脳が明晰になっていくような錯覚にとらわれるのは、実は錯覚ではなくて、「言葉の豊饒力」なのだ。
朝から晩迄、映画のシナリオという、いわば、一冊の作品としての物語の言葉の固まりを、自分と他人との台詞を身体と頭脳で、丸暗記してしまおうということを日々やっているのだから。
頭が、左脳的な意味で、良くなってくるのは間違いない。
右脳的な意味での、頭脳の進化は、またまた別の様々なる事柄だと、私は勝手に考えているが。
(まったく演技技法の違う相手のとの演技の競い合いやら、ファッションデザイナーからのアドバイスやら、音楽に合わせての踊りやらその他もろもろの力)
「トランセンデンス」のヒロインでもある、
「暮れ逢い」にでておりました。



ルコント監督です。
彼は、けっこう映画を撮っていますが、初期の作品が私は好きです。
その中でも、まずは、「暮れ逢い」ですが。
ツヴァイクの小説を映画化したもの。
テーマは忍ぶ恋。
現代のように簡単にメイクラブしてしまう時代だからこそ、忍ぶ恋のテーマが生きてきます。
「髪結いの亭主」「イヴォンヌの香り」など、恋愛映画を得意とするフランスのパトリス・ルコント監督が、自身初の英語劇として、第1次世界大戦前夜のドイツを舞台に、孤独を抱える若妻と、美しい青年の8年間にわたる純愛を描いた。1912年、初老の実業家カール・ホフマイスタ―の屋敷に、個人秘書として若く美しく、才気にあふれた青年フレドリックがやってくる。カールの若き妻ロットは、裕福で優しい夫や可愛い息子にも恵まれていたが、孤独を抱えており、フレドリックにひかれていく。ひとつ屋根の下で暮らすうち、フレドリックもまたロットにひかれるが、許されない恋であることから、2人はその思いを口にすることはなかった。しかし、フレドリックが南米に転勤することになり、それをきっかけに2人は胸にしまっていた互いの気持ちを告白。2年後にフレドリックが戻るまで、変わらぬ愛を誓うが……。
ルコント監督は、尊敬する映画監督として、なんといっても、ジュリアン・デュヴィヴィエとゴダールをあげています。
ですので、昨年封切りになった、この最新作の、「暮れ遭い 」が、デュヴイヴィエの「望郷」と、ゴダールの「勝手にしやがれ」みたいな感じになれば・・・と、語っています。
デュヴイヴィエの「望郷」
ルコントの愛するギャバンがペペルモコ役で、出ています。
ゴダールの「勝手にしやがれ」 ジャン・ポール・ベルモンドいいですね。フランスでは、アラン・ドロンよりも、当時、彼の方が、人気があったとか。・
あと、レベッカの代表作は。
「それでも恋するバルセロナ」
アメリカ人のヴィッキーとクリスティーナは、親友同士。共通項が多い二人だが、恋愛に関する考え方だけはまったく違っていた。ヴィッキーはカタルーニャに関する論文を書くため、クリスティーナは短編映画を撮り終えて気分を変えたかったため、二人でスペイン・バルセロナを訪れる。ヴィッキーの親戚の家に滞在する二人だが、ある画廊で開かれたパーティで画家のフアン・アントニオと出会う。フアン・アントニオはいきなり二人をこの週末、オビエドに連れて行きたい、もしその気になったら二人と寝てもいいと語る。ぶしつけな申し出にヴィッキーは怒るが、クリスティーナは彼に惹かれ、結局二人はフアン・アントニオと共にオビエドを訪問することになる。しかしオビエドでクリスティーナは体調を崩し、フアン・アントニオとヴィッキーは二人きりで過ごすことになってしまう。最初は反発していたヴィッキーだが、次第にフアン・アントニオに惹かれていき、婚約者がいるにもかかわらず一夜を共にしてしまう。
そんな経緯を知らないクリスティーナは、バルセロナに戻ってからフアン・アントニオと同棲を始める。そこへフアン・アントニオの元妻マリア・エレーナが現れる。
人工知能PINNの開発研究に没頭するも、反テクノロジーを叫ぶ過激派グループRIFTに銃撃されて命を落としてしまった科学者ウィル(ジョニー・デップ)。だが、妻エヴリン(レベッカ・ホール)の手によって彼の頭脳と意識は、死の間際にPINNへとアップロードされていた。ウィルと融合したPINNは超高速の処理能力を見せ始め、軍事機密、金融、政治、個人情報など、ありとあらゆるデータを手に入れていくようになる。やがて、その進化は人類の想像を超えるレベルにまで達してしまう。
◎特別映像
いい線言っているのだが、最後のシーンのまとめ方に不満あり。
『トランセンデンス』(原題: Transcendence)は、ウォーリー・フィスター監督、ジャック・パグレン脚本による2014年のイギリス・中国・アメリカ合衆国で製作されたSF映画、サスペンス映画である。人工知能と化した科学者の姿を通して、過度に高度化した科学技術がもたらす危機を描いている。タイトルのTranscendenceは、日本語で「超越」を意味する。出演はジョニー・デップ、レベッカ・ホール、ポール・ベタニー、モーガン・フリーマン。
レベッカ・ホール(Rebecca Hall, 1982年5月19日 - )は、イギリスの女優。
2002年にジョージ・バーナード・ショーの『ウォレン夫人の職業』で舞台デビュー。2006年にデイヴィッド・ニコルズ原作の『Starter for Ten』に初出演し、続くクリストファー・ノーランの『プレステージ』で好演し、数々の新人賞候補となる。また、フォード・マドックス・フォードの愛人でもあったジーン・リースが『ジェイン・エア』のベルタをモデルとして描いた小説『サルガッソーの広い海』のテレビ版のヒロインも熱演した。
続いてウディ・アレンは『それでも恋するバルセロナ』のヒロイン、ヴィッキー役に抜擢し、これ一躍脚光を集め、ゴールデングローブ賞 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門)にノミネートされた。以来、次々と国内外の注目作の役を得、2012年はフォード・マドックス・フォード原作『パレーズ・エンド』での好演で英国放送記者組合賞の最優秀女優賞を受賞。2002年にジョージ・バーナード・ショーの『ウォレン夫人の職業』で舞台デビュー。2006年にデイヴィッド・ニコルズ原作の『Starter for Ten』に初出演し、続くクリストファー・ノーランの『プレステージ』で好演し、数々の新人賞候補となる。また、フォード・マドックス・フォードの愛人でもあったジーン・リースが『ジェイン・エア』のベルタをモデルとして描いた小説『サルガッソーの広い海』のテレビ版のヒロインも熱演した。
続いてウディ・アレンは『それでも恋するバルセロナ』のヒロイン、ヴィッキー役に抜擢し、これ一躍脚光を集め、ゴールデングローブ賞 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門)にノミネートされた。以来、次々と国内外の注目作の役を得、2012年はフォード・マドックス・フォード原作『パレーズ・エンド』での好演で英国放送記者組合賞の最優秀女優賞を受賞。
ホーキング博士は、この人工知能に、危険視している。
出典Yahoo!ニュース - 「人類の終わりの可能性」ホーキング氏、人工知能開発に警告 (AFP=時事)
筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis、ALS)を患い、音声合成装置を使って発話するホーキング博士は、現存する科学者の中で最も才能ある一人と認知されている。
"「ひとたび人類が人工知能を開発してしまえば、それは自立し、加速度的に自らを再設計していくだろう」" ホーキング博士
ユセフ・ラティーフ【Yusef Lateef 】
STAP細胞の特許出願、米ハーバード大学が世界各国で…今後20年間、権利独占も
この世の中。。。
何がおこるかわからない。・・・・・・・・
STAP細胞の特許出願、米ハーバード大学が世界各国で…今後20年間、権利独占も
文=上田眞実/ジャーナリスト
【この記事のキーワード】STAP細胞, ハーバード大学, 小保方晴子
「Thinkstock」より
米ハーバード大学附属ブリガムアンドウィメンズホスピタルが、STAP細胞の作成方法に関する特許出願を、日本、米国、EPO(欧州特許庁)、カナダ、オーストラリアなど世界各地で行っており、更新料、維持料が支払われている。これについて5月9日、弁理士でITコンサルタントの栗原潔氏は、同大学が日本国内でも特許出願に関して実体審査請求をしていることを明らかにした。出願審査請求は4月22日に提出されている。
これまで理化学研究所の公式発表では、「STAP細胞論文はほぼ事実ではなかった」「STAP細胞の実験結果はES細胞の混入したものによる」として、その存在は完全に否定された。
しかしハーバード大は日本の「STAP細胞は存在しない」という大合唱を他所に、粛々と特許の申請を進めていた。小保方晴子氏の代理人である三木秀夫弁護士は語る。
「ハーバード大は世界各国での特許申請にかかる費用や維持に、推測で1000万円程度の費用がかかっているようです」
ハーバード大が特許を申請する研究内容の範囲は広く、細胞にストレスを与えて多能性が生じる方法のメカニズムに対する特許請求である。
STAP細胞論文での小保方氏の実験担当部分「アーティクル」のプロトコルは「オレンジジュース程の酸性の液に細胞を浸すと細胞が初期化する」が有名だが、それ以外に細胞にストレスを与えるさまざまな方法が試されており、「アーティクル」でその成果を報告している。これは理研がSTAP細胞論文を発表した当初の「報道発表資料」にも明示してある。
再生医療での実用化
ハーバード大がSTAP現象の特許を出願し、その審査要求をするのは当然、再生医療での実用化を睨んでのことだとみられる。 そして「人工的な外的刺激で体細胞が初期化するのではないか」というアイデアを思いついた小保方氏は再生医療の新たな扉を開いたことになる。特許は認定されると、出願後20年間の工業的独占権を認められる。
実体審査では申請された特許の内容が特許の要件を満たしているか、その内容の記述的専門家である審査官が行う。この実験が特許の取得が前提であれば、共同で行った発明や実験の知的財産権を侵害する恐れがあるため、小保方氏によるハーバード大での共同実験部分のノートやデータを、理研や早稲田大学の博士論文不正調査に提出できなかったのは当然だろう。
