老齢は山登りに似ている。登れば登るほど息切れするが、視野はますます広くなる。
・・・ イングマール・ベルイマン
ほんとの自分にもどる115のヒント/主婦の友社
¥1,836
Amazon.co.jp
いつも、のんびりする時には、この本、「ほんとの自分にもどる115のヒント」と「タオ」をぺらぺらとめくる。
人にはいろいろな気質があって、それがおもしろいので、人間みんな同じこと考え同じように感じるのであれば、人生に意味はなくなってしまうと思う。
私の気質は、すこし、無理をしてしまう性格だと自分では思う。
だから、自分を良く見せたいと思うあまりに、無理をしてしまうのだ。
それの良い点は、仕事では良いかもしれないけれど、人生という大きな視野で考えると、疲れてしまうことの連続になることも多い。
無理はもうしない。
丁寧に生きる。
のんびりする。
そんな時間が日々、もっともっと、あればいいなと思う・・・・・・・・・・・
そして、こころが「静止」して、魂の井戸におりはじめてくると、ほんとうの自分のイメージについて発見があると思う。
たとえば、私がjazzをなんでいつも好きで聞いているのだろうかと、考えると、それは、やはり植草甚一さんの影響だということと、彼がよく行っていてた横浜のたとえば、ダウンビートとか、ちぐさとか、りんでんとか、そんなjazz喫茶店に、私は大学時代に、昼飯代を削っては、六角橋から、横浜までよく歩いたものだった。自宅から歩くことも、しょっちゅうだったから、二三時間はかるくかかっていたと思う。
学生時代はツライ思いでが多かった。
自律神経をやられて、対人恐怖や視線恐怖になったのも、やはり、本ばかり読んでいただからだと思う。(植草甚一さんも、晩年、本の読みすぎで自律神経をやられて入院したとか、たしか書いていたと思う。)
そこの「ダウンビート」に行くと、よくかかっていた曲が、このコルトレーンの「My Favorite Things」だった。
聞いた話しでは、その当時のオーナーが、このコルトレーンの大ファンで、朝の1曲目と最後の曲はコルトレーンで〆るとか。
ここで、ちょいと、「私」を「ボク」に変えてみましょう。そういうテーマで書いていますから。・・・・・・・・・・・・・
だからボクの魂のかなり深いところに、やはり、青春時代のjazzばかり聞いて居た頃の残りかすみたいなものが、ゆらゆら、浮遊しているにちがいないと思っている。
そして、こんど、クラシック。
これは、やはり、退職後、好奇心が旺盛なためか、ど真剣に聞いてみようと思って、これまた、jazz同様、本日まで、一日に、三時間くらいはきいただろうか。
最初は、ピアノばっかり。くだらない計算をすると、一年で1000時間は楽に聞いていたので、
この五年で、5000時間は聞いている計算になります。
楽譜のことなどさっぱりわからず、ただ好きで、ピアノを好きな曲を数曲ひいたりの楽しき毎日なのですが、おかげで、クラシックは今は大好きになりました。
それでも、さきほどのjazzが、青春時代につながっているように、クラシックは、ボクの退職後の少し解放された嬉しさと、将来に対する不安感や、何かをやりたいと思ったそんな、複雑な心境さに、つながっているのだと思う。
気違いのように聞いて、最後の最後は、モーッアルトと、バッハにいきつきましたけど。・・・・・・
クンツさんの「思い出す」「静止」「歩みを一度止めてみる」なんかというイメージで考えると、そういうことになると思う。
だれにでも、特に、音楽は、歌謡曲であろうが、ポップの場合などは、その曲を一緒に聞いていた相手とか、当時の空気感まで思い出すから不思議だなあと思う。
身体は、どんどん、衰えていきますが、魂の方は、高校生の時と同じような気がします。
だから、あんまり、ボクは成長がないタイプなんでしょう。
友達からも、お前は変わっていると、よく言われますものね。
そして、この北海道の独特の空気感。はりつめた冷気。豪雪地帯でたまたま育った事。
そんな小さな頃から、雪と氷にいそしんできたことは、
やはり、ほんとうのボク、という魂の奥の奥まで、しみこんでいる情景です。
これは、よっぽどのことがないかぎり、抜けることのない、原体験とも言える光景でしょう。
誰しもが知っていることですが、太陽のひかりにはたくさんセロトニンを脳から分泌してくれるのです。
だから、良く言われるのは、北欧にすんでいる人たちには、鬱の人が多いと。
作家でも、芸術家でも、幻想的で暗いイマジネーションが得意だと・・・
ただ、これは、やはり、人によるので、そのような傾向はたしかにあると思いますが、散歩で、太陽のひかりを身体中に、浴びるような時間を持っている人は、ここ北海道でも、気分が壮快になりますし、鬱の症状は癒されていきます。
ボクの場合でも、毎日、365日、7000歩から15000歩くらいの感じで、太陽光を浴びているとと、鬱感覚は激減しています。
ありがたいことですね。
・・・・・・・・
というわけで、北欧の監督のなかでも、世界の三大監督と言われているベルイマン監督、彼の、
「冬のひかり」を今、興味深く、見終わりました。
◎物語の骨組み
スウェーデンの小さな町の冬の日曜日の朝。古めかしい教会の礼拝堂で、牧師トマス(G・ビョルンストランド)は会衆を前にミサを行っている。風邪をひいて体調は最悪だったが、無事ミサを終えてほっとしていると、漁師の夫妻が相談に乗ってほしいという。妻のカリン(G・リンドブロム)は、夫のヨナス(M・V・シドー)が中国も原子爆弾を持つというニュースを新聞で読んで以来口をつぐみ続けるので魂の安らぎを与えてやってほしいという。しかし牧師自身も最愛の妻に先立たれてから失意のどん底にあり漁師の悩みを解決してやれる状態ではなかった。夫妻はもう一度出直してくるといって帰ったが、そこに女教師マルタ(I・チューリン)が来て、彼のことをあれこれ気づかう。マルタは妻亡きあとの彼の愛人だったがトマスにとってはそんな心づかいもマルタの過剰な自意識とともに辟易しているのが本心だった。だから前日、彼女から届いた手紙も読まずポケットに収めたままだったが、ヨナスを待つ間、それを読み始めた。そこには、二年越しの二人のいきさつが愚痴ともつかず愛の告白ともつかぬまま、くどくどと並べられていて、トマスの焦立ちは深まるばかりだった。再び訪ねて来たヨナスと向きあったが牧師としての自信が揺らいでいる彼は常識以上のことは何もいえずヨナスには何の力にもならなかった。ヨナスはそれから間もなく、激流が音をたてる河辺でピストル自殺で命を絶った。そして、マルタは彼の煮えきらない態度に決断を迫り、ヒステリックな言葉のやりとりの末、トマスとの訣別を知らされる。それから数時間後、隣の教区の礼拝には一人の会衆も見出せぬ教会にそれでも型通りの式を進めていく牧師トマスの姿があった。いや、そこには、たった一人の聴聞者は別れたばかりのマルタだった。
◎資料によると。
ベルイマン作品の最高傑作といわれ、病を押して神の栄光を説き続ける牧師のうつろな姿を通して一貫したモティーフである“神の沈黙”を描き出す。原題は「聖体拝受者」という宗教用語で、「冬の光」は海外用の題名。一九六三年度OCIC国際カトリック映画局グランプリ、同年第八回ウィーン宗教映画週間で最優秀外国映画賞を受賞。
「冬の光」では、ビョルンストランド演じる牧師と男女の関係があり、男に執着する独身の女教師の役。・・・・・
「野いちご」の彼女とはまったく違う、凄みのある、存在感のある。良い意味での、女性の盲目的な生きる本能と知性さへも感じさせる演技。
ビョルンストランド演じる牧師に、愛されたいと、二年間つきあうが、結局は愛されない。
君のことは愛していないとはっきり言われたりもする。
しかしながら。
けなげに、珈琲を彼-牧師に届けたり、風邪をこじらせている彼のために、喉を楽にする薬を
持って行ったりする。
徹底して尽くす役柄を上手に演技している。
音楽でいえば、「ロンリー・ウーマン」とでもいうべき、生涯孤独で、男性からはあまり愛されないタイプの今の言葉で言えば、さえない女性を実に正確に演じきっていたと思う。
地味な服装でダサい眼鏡
特に、教室でビョルンストランドと痴話喧嘩をして、彼に執着する姿をさらすところがみどころ。
黒沢監督の「ドデスカデン」でも、たしか、ボクのぼんやりとした記憶では、あったと思うけれど、亭主を徹底していじめる、こわーーい、奥さん。
友達があまりのすごさ、サディスックな奥様に別れたらいいのにと言うと、亭主は、愛しているという、たしか、そんなようなニュアンスのシーン。
おとこと女の愛情って、複雑なのだ。
相手が発する一言に、いちいち敏感に反応していたら、恋愛もうまくいくはずもなく、結婚生活もあまりにも単調だと思う。
聞くべきところはきちんと聞いているが、そうでなければ、一瞬の気分も、高まる感情もあるだろうから、涙をながしたからと言って、慌てる事もない。
自分のこころの奥をしっかり見ていること。
そのことを、ビョルンストランド演じる牧師は、やろうとしている。この映画、「冬のひかり」のなかで・・・
だから、少し重たくもあるけれども、見応えのある作品ともなっている。
誰もが知っているように、西洋社会でさへも、今やキリスト教を単純に信じて毎日曜日にミサに行くような人は確実に減っているのだろうと思う。
それに、例のフランスのイスラム教のテロではないけれども、自らの信仰こそが正統であり、異端は許さないという、かたくなな考え方が今でも、あるんだと思う。かつては、それが、強烈だったあまり、血で血を洗うような戦いを西洋社会のどこでも、あったんだと思う。
(イギリスのプロテスタントとアイルランドのカソリックの派の争いを言う迄もなく)
かと思えば、アメリカのとある州というか、けっこうな地区で、いまだに、ダーウィンの進化論を学校で教えずに、この世界は神様がおつくりになったと教えている学校があるらしい。
日本には、やおろずの神様がいらっしゃるおかけで、「もののけ姫」のような傑作映画ができたわけだし、「せんとちひろ」の映画も、日本の神様の考え方が今、世界に浸透しつつある。
聞いた話しでは、ヨーロッパでも、仏教形式で、葬式をする人も増えているとききます。
・・・・・・・・・・・・・
そんなわけで。
冬の光のなかで、牧師は、悩んでいます。
自分はしっかりした信仰を持って、皆に、説教をしているのだろうかと。
みずからの協会にやってくる人の数も、どんどん減っています。
今や、四五人の人数のひとのための説教を説くのみ。
オルガンパイプを弾く男性も、もはや、アクビをしながら、テキトウに、音楽をかなでます。
牧師。死んだ妻。その後、彼を追いかけるイングリッド・チューリン。オルガン弾きの男性。人生の悩みを相談する鬱っぽい男性とその妻。牧師にアドバイスをする友達。
そんな連中が、冬のよく澄んだ夜の空の星のようにして、ぐるぐる、牧師のまわりをまわりながら、ドラマを演じています。
ドナルド・キーンさんが、日本人の特質の五つとして。
◎あいまいさ
◎勤勉
◎はかなさのこころを理解できる 共感できる
◎清潔
◎礼儀正しい
をあげています。
そのとうりだと思います。今、世界から外国人がやってきて、私たちが、ほとんど無意識にやっているようなことを、見て、驚いて、自分の国にもどっていっては、世界にネットやTwitterで、広めてくれています。
ありがたいことですが。
この5つが、ない人もふえているような気もしますね。
こんな日本とは、ちがい、スウェーデンの牧師は、悩みに悩みます。
まさに、二元論。逃げ道を自分でふさぐような、論理的な考えをつづけなから。
そこへ、わずらわしいとさへ思ってしまう女の愛情。妻のことをまだ忘れられないというのに。
そして、信者の自殺。
・・・・・・・・・・
美しい映像です。
世界の黒沢・フェリーニ・そして、ベルイマンと言われるだけある作品だと思います。
この牧師の、挫折と敗北、とよく似ているのですが、あるいは、牧師の挫折と敗北そして、視点をフレキシブルに変容させて新しき出発をする、そして、その起爆剤は、ひとりの女性と娘家族・・・そんな映画がありました。
「ショコラ」です。
断食の期間。ミサにも参加しようとせず、私生児であるアヌークを連れたヴィアンヌの存在は、敬虔な信仰の体現者で村人にもそれを望む村長のレノ伯爵の反感を買ってしまう。この村は伝統と規律を守る厳格な村なのだ。レノは村人たちに、ヴィアンヌのチョコレート店を悪魔的で堕落したものだと説いて出入りを禁じ、またジョセフィーヌの夫のセルジュを信仰の力で更生させようと躍起になる。
この部分ですね。
私の大好きなフェボリットのひとつです。
ジュリエット・ビノシュがでているだけで、それだけで、満足なんです。
彼女は、世界三大映画祭の女優賞をすべて獲得しています。もちろん、この「ショコラ」で主演女優賞を。
イングリッド・チューリンとジュリエット・ビノシュをよくよく、見比べると、飽きないですね。
「冬のひかり」の主演女優、ベルイマン監督にはかかせない女優であるイングリッド・チューリンは、スウェーデン生まれ。北欧ばりばりというところでしょうか。


私は、「地獄に堕ちた勇者ども」の彼女も好きなせいか、なんとなく、ドイツ人ではないかと思っていましたが、この映画は、ビスコンティの三部作のひとつですし、イタリア映画ですから、思い違いというのは恐ろしいものです。
なんか、ドイツっぽい。
もちろん。映画そのものがドイツの歴史ですから。
それでも、やはり、スウェーデン人の顔。
つぎに、ジュリエット・ビノシェ。


そして、またまた、勘違い。
「存在の軽さ」・・・・・・・・・大好きな映画ですが、アメリカ映画だとは思えず。
個人的には、この映画、「ショコラ」と「存在の耐えられない軽さ」と、「ダメージ」と「トリコロール 私の記憶が曖昧ですが、たしか、青の愛」
トリコロールは青・赤・白。要はフランス国旗ですね。
青は、「青の愛」:自動車事故で同時に作曲家の夫と娘の二人を亡くしたジュリーは、すべての財産の処分を弁護士に任せ、一人暮らしを始めるが、やがて夫の残した欧州統合の協奏曲を完成させる。
トリコロール/赤の愛は、
女子大生でモデルのヴァランティーヌは自動車で犬を引いてしまったことから、飼い主の退官判事ジョゼフと出会う。ジョゼフは屋敷に一人で暮らす隣人の電話を盗聴していた。若いヴァランティーヌと、過去に縛られてきた判事は少しづつお互いに心を開いていく。
トリコロール/白の愛は、
「白の愛」:離婚したポーランド人の美容師カロルとフランス人のドミニク。故郷へ帰ったカロルは土地の売り買いで成功したが、妻だったドミニクが忘れられず、自分の死を装って、ドミニクをポーランドへ呼び寄せることを企てる。
「トリコロール」3部作は、それぞれの作品が「自由(青)・平等(白)・博愛(赤)」を象徴しており、最終作となるトリコロール-白の恋、は、全てを包む「博愛」がテーマとなっています。
しかしながら。
前2作赤と青、がヴェネツィア国際映画祭・ベルリン国際映画祭で受賞。
したがって、この「トリコロール白の愛」の作品も、また、三大映画祭での受賞が期待されたのですが、カンヌ国際映画祭では無冠に終わってしまいます。総合的な評価は、むろん、高いですが・・・・・・・
22年前の映画群です。
私もよく渋谷に出入りしていましたから、たしか、BUNKAMURAで、見た筈なのですが、記憶がはっきりしておりません。情けない。
ちなみに、その年の最高賞に輝いたのは、クエンティン・タランティーノの「パルプ・フィクション」というのですから、やはり、紋切り型を嫌うフランス人気質かなあと思ってしまいました。
たしかに、この作品は、ずばり、楽しめますしね。
それにしても、イングリッド・チューリンとジュリエット・ビノシュの、ふたりを見比べてみると、ほんとうにおもしろいです。
ビノシェの「ダメージ」はすごいですよ。
あまり、彼女のイメージと合わないと、評価がありましたが、彼女は自分の役柄のイメージをとりはらうがごとく、自在に、演技しています。
その後、 大女優になりました。
原作の本もまた、素晴しい。
ダメージ/文藝春秋
¥1,782
Amazon.co.jp
ことばも交わさぬうちに、一目で燃えあがる恋がある。意志にさからって破滅へと突き進む、運命的な愛というものがある。たとえ男が、フィアンセの父親であろうと、たとえ女が、息子のフィアンセであろうと。男も女も身につまされる愛のベストセラー。
あと、このベルイマンの人生を描いた素晴しいドキュメンタリー映画があります。
「リヴ&イングマール ある愛の風景」
残念ながら、いろいろと、探したのですが、恐らくマイナーな渋谷あたりの映画館でしか、やっていないでしょうし、DVDも発売はされないのかもしれません。
「ひとつの言葉で喧嘩して、ひとつの言葉で仲なおり、ひとつの言葉に泣かされて、ひとつの言葉であやまった。
ひとつの言葉はそれぞれに、ひとつの心を持っている。」・・・・・・淀川長治。
◎資料
ベルイマン
一般的に、イングマール・ベルイマンは20世紀を代表する映画監督の一人とみなされている。2002年に『Sight & Sound』が行ったアンケート調査によれば、ベルイマンは映画監督が選ぶ映画監督ランキングで第8位にランクインした[3]。デンマークの映画監督であるビレ・アウグストは、黒澤明とフェデリコ・フェリーニに並ぶ三大映画監督として、ベルイマンの名前を挙げている[4]。ウディ・アレン[5]やクシシュトフ・キェシロフスキなど、ベルイマンに影響を受けたと告白する映画監督は枚挙に暇がない。
『第七の封印』や『沈黙』のような、形而上学的とも言われる代表作から難解な作家とも評されるが、一方で(時に難解なテーマを伴ってはいても全体的には)わかりやすい作品も多い。また、女性を主役に据えた作品が多いのも特徴である。ベルイマンは正式な結婚を少なくとも5度行っており、そのような自身の女性遍歴を反映したかのような作品も数多く見られる。
ベルイマンの映画は舞台劇的と評されることが多いが、ベルイマン本人はあるインタビューの中で、自作の映画『ある結婚の風景』を舞台化するときに、構成やセリフのほとんどを書き換えなければならなかった例を挙げて、映画と舞台は別物であると訴えている[6]。ちなみに演劇では主にウィリアム・シェイクスピアとアウグスト・ストリンドベリを好んで取り上げ、自らの劇団を率いて日本で大胆な解釈に基づく『ハムレット』とストリンドベリの『令嬢ジュリー』、三島由紀夫の『サド侯爵夫人』を上演したこともある。
リヴ・ウルマン
エンジニアの父親の仕事の都合で東京で生まれる [1]。2年後にトロントに移る[2]。しかし4年後に父親が脳腫瘍で亡くなり[2]、ノルウェーに戻る。ロンドンで演技を学び、1950年代よりノルウェーで舞台に立ち、1957年に映画デビュー。
北欧からの移民農家の妻を演じた1972年の『移民』(或いは『移民者たち』)でゴールデングローブ賞 主演女優賞(ドラマ部門)を受賞、アカデミー主演女優賞にもノミネートされた。幻覚に襲われる精神科医を演じた1975年『鏡の中の女』で2度目のアカデミー賞ノミネート。7年間も母に会えず怒りを爆発させる娘を演じた1978年の『秋のソナタ』(ベルイマン監督)では実力派のイングリッド・バーグマン(本作が最終作品)を圧倒する演技を見せた。2000年には『不実の愛、かくも燃え』を監督している。この作品の脚本はベルイマンである。
早くからイングマール・ベルイマンに出会い、公私共にパートナーとなる。二人は10本の映画を製作した。二人の間には娘が一人いたが結婚はせず、ウルマンは1985年に結婚した二人目の夫と共にニューヨークに住んだが、1995年に離婚。しかし2人は2007年まで共に住んでいた[3]。
2010年12月10日に行われたノーベル賞授賞式に出席し、平和賞を受賞しながら出席を果たせなかった劉暁波が前年12月に書いた文章を代読した[4]。
「冬のひかり」「ショコラ」牧師の苦悩 神の不在 「トリコロール」 北欧とラテン
復讐について・・・「美しさと哀しみと」「96時間レクイエム」「ジャンパー」「死と老いと・・」
高橋留美子を読み、石森手塚を読み、・・・・・ぼんやり。
そして、「アダムの肋骨」を熟読。
彼独特の世界に魅惑される。五十嵐大介のように・・・・・・


11光年の近くに、地球とよく似ている惑星が最近発見されたそうだが。
想像力を刺激してくれる。
・・・・・・・・
エイリアンだろうがなんだろうが、生きている生命体には、生があり死があり老いがあり、こころの葛藤、嫉妬、復讐などがあることには違いないだろう。・・・・・・・・
うっかり他人のことを真に
理解しようとしだすと、
自分の人生観が根っこあたり
でぐらついてくる。人間理解
は命がけである。 河合隼雄
死について深く考えた遠藤周作さんも似たようなことを言っていますね。taoや、正負の法則なんかを連想してしまいます。
謙虚なこころ。
わからないことはわからないと言えば、良いのです。
最近。不条理な事件も多いですが、素直に見て聞いて、
自分がけっこう読んでいるのではないかと思われる作家の意見を参考にしたり、友達に意見を聞いたり、親が生きている人は少し尋ねてみたりしたり・・・・・・・。
この三島由紀夫氏のクリップにしても、彼は、生まれ変わったらプレスリーになりたいとか書いていますし、安部譲二にボクシングを教えてくれと頼んだりもしています。
音痴であることを自認し、好きな歌は、「クロネコのタンゴ」のみ。
タクシーにのった時に、たしか、動物の面をつけてドライバーをおどろかせて大笑いしたとか。・・・・・・・・・・・・・
そんな、ひょうきんで、ユーモアのある、楽しいことの大好きな彼が、日本そのものを守るために、自刃するわけですから・・・・・・。
私は、だから、分析しません。
彼が大好きなので、まるごと、愛そうとしているだけです。これからも、彼の作品はすべて何回も何回も読む続けるつもりです。
(谷崎や、川端も、源氏物語も、澁澤も、言うまでもなく)
人のこころは、Androidではありませんから、わからなくてあたりまえなんです。
だから、文学や映画やマンガや音楽が、どんどん、誕生するのではないでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
サラリーマン時代は、ほとんど、家にたどりつくと、12時をまわっていたので、映画を借りて来ても、見るのは休みの日のみ。
それも、見ないでそのまま返却したりすることもたたあった。
ああ、もったいない。しかしながら、それまたしょうがないのだった。
10枚のCDを借りて、そのまま、二三日延滞したら、5000円くらい獲られたこともある。
・・・・・・・・・・・若き頃の笑い話。
今は、好きなだけ映画も見れるし、CDやレコードも聞けるのだが、不思議と、以前と同じように、朝起きて掃除をして、雑用をやり食事をして、散歩をし、父親の介護食をつくり、母の日の花を買い、野草に見とれていたりすると、あっというまにこんな時間。
だから、映画を見るのは、いつも夜。本を読むのは、そのつど。朝昼晩。
マンガを見るのも同じ。
絵とマンガを書くのは、今のところ、午前の浅の光の中。あとは気が向いた時に・・・・・・
ここ岩見沢市にもどってきて、最初の頃は、老人の町だなあとそんな感想でした。
しかしながら。
真冬を何回も経験していくと、その厳しい自然のなかで、生きているある意味共感というか、一緒に生きているみたいな感覚が生まれてくる。
小さなソリに、たくさんまとめ買いした食品のリュックを載せて、ひいひいひっぱっているおばあちゃん。
杖ひとつで、つるつるの雪斜面を器用に、どうどうと歩き回るおじいちゃん。・・・
「芸術つて、何なんだ」 伊藤整・・・・・・・
ジョイスのダブリナーズではないが、ここには、80才の親父お袋をはじめとして、田舎独特の倦怠、死想、説教、香、が渦巻いていた。
北海道のここ、岩見沢市のはなし。
母親は、一昨年なくなる。
・・・・・・・・・
時間が静止している中、岩見沢ラーメンをいただく。
味噌ラーメンは面が太い岩見沢独特の、スープ。
店名ラピタ、が、漢字になっている。
雉子ラーメンも有名らしいが、いまだ、食せず。
ただし、わたくしはそれほどこのような脂身の多い味噌ラーメンより、サッパリ醤油がすきである。
そんなうちに、とある本屋で、北海道文学ドライブマップなるもの発見。
北国ははたしてどのような詩人や作家をつくるのか?
興味はつきない。
今特に読みたい小樽の作家は伊藤整だ。『このような作品を許して良いのか?』と『卍』『鍵』が、国会で追求されたことに言及し、芸術は人生にとってどうなんだ?
と持論を展開する。
三島由紀夫も小説が人に与える影響のマイナス面をも強調する。
作家はそうやって、腹を切ったり、自殺したり、遊び過ぎてC型肝炎で死んだり、女と入水したり、70才になって女研究に精出したり、骨董品にはまったり、やっていることは決して教科書に立派に紹介されることではない。
だから、モノ書きは、この世のCircusの住人として
、その挫折や失敗や、馬鹿さ加減で、なにかしらの『勇気』を人に与えることができるのかもしれない。
馬鹿を大切にフアルス精神。
合理だけではこの世は楽しくない。
日本人に一番欠けている気質。
楽しむこころ。
「卍」「美しさと哀しみと」など、川端康成の作品を読んだり、映画を見ていると、
こまごまとした日常生活を離れて、完全に、非日常のなかで、こころを自由に泳がせている自分を発見する。
たしかに。
中年男の設定やら。
キモノ姿の京ことばの女優達。
それだけでも、辟易する人もいるかもしれないけれど。
私にとつては、そのワンパターンが良い。楽しんでいる。
ちょうど、歌舞伎を愉しみ、浄瑠璃の人形を楽しむようにして。
ワンパターンは偉大だ。
ここで大事なことは、舞台俳優の言ういっけん軽く言われる言葉をそのまま聞いては行けないということだろうか。
もっと大きな、深い、井戸のなかから、見るようにして、映画のファルス的な混沌を包み込みたい。
要は、理屈で見る事はしない。
たとえば、この「美しさと哀しみと」
以前も書いたけれども、Sという言葉を発明したのもたしか、川端康成ではなかったろうか。
女性同士の愛のこと。
ただの英語ではなく、三島由紀夫氏の「潮騒」などのように、自分の宇宙をつくりあげるために、
自分の作品そのものをとりこんでいったり、原罪みたいなものまでも、深くほりさげて、ちりばめてあるような気がする。
現代のミステリー作品のように、ただ、奇をてらったり、物語で驚かせようとするよりも、
妻と愛人のふたりの子どもたちの死について、たんたんと、静かに、そして、深く深く、
描き上げようとしている。


・・・・・・・・・・・・・
「46時間」のリベンジものを三作そろって、再視聴したあとだったので、
不思議な気持ちがした。
同じ、「復讐劇」であるのに。
もちろん。こんな違うジャンルの作品を勝手に、比較するのは馬鹿げたことなのだけれども、たまたま、見たことが偶然とは自分には思えないのだ。
かたや、フランスの活劇もの。アクションもの。
かたや、日本の古典文学の映画化。深刻で京都そのものの美を追求した作品。
それでも、「復讐」がテーマなのだった。・・・・・・・・・・・・
興味深い。
それこそ、世界の復讐ものの古典も読み直したくなる。
「巌窟王」に「ハムレット」・・・他にもたくさんあることでしょう・・・・・・
でも、今回は、このまったくタイプの違う映画のことを自分なりに考えるだけです。・・・・・・・・・・・・・・・・・
好きな川端の言葉。
「少女時代のことっとなにか「片輪」みたいなところがあるでしょう。それが年をとってなくなっていくのは嫌なのよ」・・・・
さすが、川端だと思う名言。
・・・・・・・・・・・・・・
自分の頭の整理のためにも、ここにコレクションしておこう。個人的には最初の作品が好きなのは言うまでもない。
娘・・・をなんとかあの手この手で、胸がすくように助けるわけだが、
「美しさと哀しさ」とでは、娘は、助けようにも小さな頃に、流産したり、亡くなったりしているわけだ。
そして、「男なんか大嫌い」と豪語する加賀まりこが、執拗に自分の思いを成し遂げて行く。
聞いた話しでは、谷崎が、源氏を頭において「細雪」を書いたように、川端もまた源氏を頭において「美しさと哀しみと」とを書いたと言われています。
川端康成の同名小説を「暗殺」の山田信夫が脚色「暗殺」の篠田正浩が監督した女性ドラマ撮影もコンビの小杉正雄。
個人的な見方だけれども、勝手に、フランス映画の96時間と比較したりして楽しんでいる。
鎌倉に住む作家大木年雄は、新しい年を京都で迎えたいと心誘われていた。大木の心の中には、京都で絵筆をふるう上野音子の面影がよぎった。二十年前大木は、妻子ある身で少女であった音子を愛した。大木の子供をみごもった音子は、その日から平凡な女の倖せを奪われ、死産というショックを経て、自殺を計った。そして大木はこの事件を描いた作品で文壇に地位を築いたのだった。大木が京都を訪れた時、迎えに出たのは音子の弟子の坂見けい子だった。そして音子と会った大木は、その冷やかな態度に、ある虚しさが残った。唯、「少し気違いさんです」と紹介されたけい子の妖しい魅力に、惹かれるものがあった。けい子は、音子を姉のように慕っていたが、音子から大木の話を聞くと、彼女は大木への復讐を誓った。梅雨の頃、けい子は自作の絵をもって、鎌倉の大木の家を訪ねた。私立大の講師をする一人息子太一郎の案内で、けい子は楽しい日を過した。その夜けい子は大木に抱かれた。けい子から大木との、一夜を聞いた音子は、なぜか嫉妬心にかられた。年月がたつにつれ、音子の心の中で大木との交情が浄化されていた。そして、妖しいけい子との同性愛に溺れる音子であった。夏のある日、京都を訪れた太一郎を、けい子は琵琶湖へ誘った。「音子先生の復讐を太一郎さんでやるんだ」けい子の心は高なった。小倉山の二尊院で太一郎はけい子を抱いた。翌夕、モーターボートに乗った二人は、沖へと出た。音子がラジオのニュースを聞いてかけつけた時、けい子はベッドに寝かされ、太一郎は行方不明のまま、捜索船が動きまわっていた。けい子の寝顔に涙がひと筋光っていた。
歌謡曲が古いとか。
能はよくわからないとか。
キモノの着方がわからないからめんどうとか。
魚の三枚おろしがわからないとか・・・・・
なんでも、チャレンジしてみる。
どんなものでも、新しき発見がある。
自分の何かが広がって行くのがわかる。
・・・・・・・・・・・
決まった時刻にめざましを押して、決まった道を決まった歩数で歩いて、決まった時刻で会社に行き、さかわらず、文句も言わず、いつも笑顔で、遅刻せず、仕事せず。
こんなつまらん人生はないだろう。
とある作家はいう。
「家を一歩でるとそれは旅だ」と。
いつもと違う道を歩いてみる。
いつもと違う喫茶店で、違う珈琲を飲んでみる。
いつもと違う人と、昼飯を食べに行く。
文句があれば、されげなく、上司に言う。
・・・・・・・・・・・
そして、今、少ない時間でちらちら読んでいる本や、
家で、眠い目をこすりつつ見ている映画などは、かならずや、
きっと、「血や肉に」なっていく。
・・・・・・・・・・自分を信じる。
たしかに、この「美しさと哀しみと」をじっくり見ていると、当時の、観客ならば、この俳優・・・
八千草かおると、加賀まりこの演技には驚愕したのではないだろうか?
原作と比較していないので、なんともいえないが、三島由紀夫氏なぞは、原作の一字一句も、違う言葉にアレンジさせなかったように、川端も言葉にこだわったのだろうか、
興味深い。
ただ。
川端は加賀のリハーサルの演技を見て、「加賀さんの熱つぽい激しさに私はおどろいた」、「私がまるで加賀まりこさんのために書いたやうな、ほかの女優は考へられないやうな、主演のまりこがそこに現はれた」[21]と述べ、登場人物の「けい子」というエキセントリックで妖精じみた娘に、「演技より前の、あるひは演技の源の、加賀さんの持つて生まれた、いちじるしい個性と素質が出てゐた」と褒めている。
「けい子」は、ある意味、川端康成の書いているほとんどの作品のたとえば、伊豆の踊り子の少女のようなキャラの「原型」ともいえるイメージなのだが、それだけ褒めているわけだから、ある意味、自分のイメージを超えた魅力なども許していたのかもしれない。
美しさと哀しみと
美しさと哀しみと
Beauty and Sadness
著者川端康成
イラスト装幀・挿画:加山又造
『美しさと哀しみと』(うつくしさとかなしみと)は、川端康成の長編小説。ある中年小説家と、彼がかつて愛した少女で現在日本画家となった女、その内弟子で同性愛者の若い娘の織りなす美しさと哀しみに満ちた人生の抒情と官能のロマネスク物語[1][2]。愛する師のために、レズビアンの女弟子が男の家庭の破壊を企てる復讐劇を基調にしたストーリー展開で、川端の野心的な代表作とは見なされてはいないが、川端という作家の主題や技法が特徴的に示されている作品だといわれている[1][2][3]。
1965年(昭和40年)2月28日に篠田正浩監督で映画化され、1985年(昭和60年)にはフランスのジョイ・フルーリー監督により映画化された。
本のコレクションの愉しみ。
ブリジットバルドーと、ヘプバーンと、グレースケリーは、かならずと言って、買ってしまいます。



私にとっては、これらの、ヌーベルバーグ調の色彩の洋書の愉しみと、日本版の昭和初期の映画などの、カタログやらブロマイドやら、すでにぼろぼろではありますが、稀少なる映画雑誌の画像とは、まったく同次元のものです。
大好きです。
見ほれます。
18歳の頃だったでしょうか。
月の仕送りもたしか、20000円ほど。
5000円の汚いアパートに住んで、毎日キャベツしか食していませんでしたから、
仕送りがあると、すぐに、10000ほど持っては、古本屋に飛んで行ったものです。
この二冊の本はもうぼろぼろですが、当時でも、珍しい、邦画と洋画のエロティシズムシーンを集めた稀少な絶版本。
どこにもありません。
たしかに今見直してみると、こんなfreeな愛が反乱する時代ですから、たいしたことのない写真ばかりなんですが、すでに、没していたり、一度きりで行方不明になったりするようなきまぐれな女優達がたくさん載っていて、実に楽しく、インスピレーションをもらえます。


その他。
本の方の収穫と言うと、司馬遼太郎さんの文芸春秋の「日本人を考える旅」へという冊子が安く買えました。
あとは上に、アップしている「オードリー・ヘップバーン」の二冊が掘り出し物でしたね。
パメラ・クラーク・キオというニューヨーク州のロングアイランドで生まれた<麗しのサブリナ>脚本家ですね。彼女があますところなくオードリーの魅力について語っております。
私の映画の見方は少し変わっていて、ほとんどが、原作=文学などがあるわけですから、それをしっかり読んでから見ます。そう、どうこの原作を監督の世界に紡ぎだしているか、と。
もちろん原作を見ないで映画を先に見ることもありますが、映画は映画の表現力・原作は文学としての完成度としてつい見てしまいます。これはもう気質ですからしょうがありません。
そして、私のシネマの楽しみ方は、実は、「情報収集」の方に傾きます。
フランスの今のパリの町並み。
ニューヨークの街角を歩いている人のファッション。
外車の種類
食べ物などのさまざまなる色彩 食べ方 レストランの雰囲気などなど
そして、最後の楽しみは、やはり美男美女の視覚としての楽しみでしょうね。
人がきれいな異性に憧れるのはどこの国でも老若男女、同じです。
二時間の間にうっとりして、映画館の外に出れば、幸福なる時間がやってきます。
そんな時には、スタバにでも入って、ゆきかう人々を見ながら男優や女優の素敵な台詞を思い出してはにやりとするのがいいんではないでしょうかね。
いやあ、映画っていうのは、こころの旅ですね。1800円ほどのお金でたっぷりアラスカや、ロシアや、イタリアや、ギリシャや、世界のどこへでも、映画のなかではすーっと行けるのですからね。
その意味では、「ジャンパー」という映画も愉しかったですね。
絵・・・・・・・

この橙をメインとした独特の色合いがまず目をひきます。
つぎに、なんといっても、その線画です。
私も二紀の油絵の先生によく言われたものです。「線で書くな、面で書きなさい」、忘れもしませんね。
でも日本画は線ですね。
私もだからいつかは日本画やりたいなあと思います。

この作品の青はではどうしたのでしょうか ? 気になるところですよネ。
たしか、染色では、藍やら野草の青で書けるはずなんですが・・
藤原敏行の名歌が上の方にかいてありますネ。
「秋きぬと目にはさやかに見えぬとも 風の音にそおどろかれぬる 」
拙訳、「秋はまだまだ訪れたようには風景は目には見えないが、よく耳をすますと、風の音が秋の気配をしっかりはこんできて、びっくりしてしまう。近づいているんだネ」
春信の描く女性は、どこか、少年的で消えいりそうなあやうさが好きですね。
秋の風を、風呂上がりにうけて、気持ち良さそうな女性の表情。
平安の1シーンが見事にえがかれておりますネ。
三島由紀夫が、言っておりますように、西洋の恋愛はゴリラが胸毛をかくして、最後の最後のそれを楽しむようにステップを楽しむ傾向があります。
ところが、日本のそれは、秋の空に舞いあがってきえてゆく、とんぼみたいに、空でちょこんっと、くっついては離れ、離れては、くっつくそれでありますネ。
日本文化はやはり情緒と、間ですよ。
むこうのそれは、スポーツみたいなところがありますね。
ミューシャの「四季」見てみると、もちろん、同じ、女性の輪郭をアール・ヌーボーの独特の曲線で描いているのですが、春信のような中性的なアンドロギュヌスのイメージよりも、肉感的な、女性ホルモンとオーラがばっちりでていてそれはそれで、素敵な作品になっております。

「春」はリズムにのって

「夏」はどことなくアンニュイで

「秋」は思いがふくらみ

「冬」はつつましやかに
アール・ヌーボー、デコ、は大好きで、目白の庭園美術館はよく行きました。
あの美術館のすぐちかくに、デッサン教室がありまして、私は、週に一度から二度は、そこで、裸婦デッサンをやっていたことを懐かしく思い出しますね。
いつか、庭園美術館でおこなわれた、小磯良平展では、ほんとうに絵とは素晴しい芸術だなあと、感銘しました。神戸の匂いが彼の絵からしましたよ。
話が脱線しましたネ。
ともかく、ミューシャーにも日本の影響はまちがいなくありますね。
もうこんな現代になれば、どこそこに、どこの国の影響があるとチェックするのが大事なのと同様に、
もう混沌としてクロスオーバーしているわけですから、ほんとの意味での「地球人」が誕生するのも
間近なのかもしれませんね。
ところて゛ここ岩見沢市はとんでもない田舎です。最初にも、書いたように、 年寄りの、町。
・・・・・・・・・・・
若い人はあまりいません。たこつぼのなかに隠れているようです。
祭りの時なんかは、かなりそこから、出て来て踊るのですが・・・・・・・
それでも、私は、真冬に、食用品の買い出しを「ソリ」のつんでは、ひっぱって歩いている80歳代のおばあちゃん。
杖を器用にあやつりながら、私でさへ、つるつるの歩道で辟易しているのに、どうどうと歩いているどう見ても、90歳くらいの紳士のおじいちゃん。
70歳後半のおばあちゃんが、80歳くらいのおばあちゃんの車いすをおしながら、仲良くおしゃべりをしている老人の友達どうし。
素晴しい風景です。ここにきて、まったく老人達への見る目が変わってしまいました!!!!!!
あこがれます。私も、あんなように、年をとりたい。
かっこ良くもなく、きどりもなく、金もなく、ただひたすらに、吹雪のなかを、
買い出しに、日々、歩き回る。
ほんとうにかっこ良いと思う。
よく上野駅で、昔、80歳くらいの腰のまがったおばあちゃんが、自分の身丈の二倍はあるような、品物を背負っては歩いていましたが、あれに近い、感動をうけます。
個人的な意見ですが、
いつもおしゃれで、安心安全な家で、平安に暮らして、お金の心配もなく、孫や子どもにもめぐまれてという人は、羨ましいとは思いません。
むしろ。
ある意味。青春が終わった人なんだなと・・・・・・同情してしまいます。
笑えますが、私なぞ、今でも、この年になっても、借金を返しながら、バイトをやり、好きな絵を描き、マンガに没頭し、小さな頃からの夢であるところのマンガの作品をいつかはひとつと・・・・・・・・、不整脈の持病もありますし、介護父もいますから、好きなところへもでかけれませんし。
ただ、家人と友達には恵まれていると思いますので。
近所の猫にミルクをやり、
雨露をしのぐ家があり、
好きな酒とツマミがあって、いつの季節もそれなしにはやっていけない本と友達がいれば。
私はいま、私なりの悩みがありますが、それがあるという事自体が、青春のど真ん中の証拠だと思っております。
あくまでも、個人的な意見ですが。
感謝!!!
「老いる」とはどういうことか (講談社プラスアルファ文庫)/河合 隼雄
¥672
Amazon.co.jp
あるひとりの男性が長いサラリーマン生活を終えて、ある一種独特の深い感慨にうたれ、これからのんびりしようという期待感とともに、愛する孫と息子との家まで用意して老後をスタートしたとあるので、よほど、
恵まれた環境の中で仕事をしてきた男性なんでしょうね。
そこで問題は発生する。
新聞などでも騒がれている、「老人問題」の記事を長男夫婦も読んでいるし、孫と言っても、10歳ぐらいであろう。
その孫からは「おじいちゃん、なにか楽しいこと見つけたら」と言われたらしい。
息子となると、もっとはっきりと、「父さん、何か生き甲斐見つけてみたら」と言われた。
この男性は、ずっと働いてきて、孫や息子と一緒に住むことを楽しみとしてきたふしがある。
そして、一番楽しみにしてきた筈のふたりから、そんなことを言われる。
彼にしてみれば、「ぶらぶらする」ことが楽しいのである。
それを「生き甲斐」だとか、「楽しいこと」とか、うるさく言われれば、悲しくなる。
だいたいが、ぶらぶらするなんていうのは、まさに、理屈を越えて、自由の境地に遊ぶことなのだから、誰かにアドバイスされるなんてことではない。
しかも、一番可愛いと思っているふたりから言われると、なおさら、やっかいですね。
世の中、皆、利口になってきて、知識ばかりがどんどん、ふえてくる。
禅でも、タオでも、それらは「減らしなさい」「捨てなさい」と教えているというのに。
ぶらぶら、子供の境地で好きに遊ぶ、酒がその伴侶となることもあろう、歌がその友人になるかもしれない、どちらにしても、やっとサラリーマン生活のストレスと、社会の束縛からのがれて、やったーと思った時にこれである。
「老後」この漢字がいけない。
明治大正ならば、いざしらず。
いまや、80代の女優が舞台ででんぐりがえしをやり、山登りを楽しみ、70代でもたくさんの芸術家達がさかんに作品を作り続ける時代です。
「老後」
この言葉が、逆に老人をつくっているのかもしれません。
そして、「生き甲斐」
この言葉が、老人を更に老化させるのを追い打ちする。
うちにも、今、階下に89歳を迎えようとするつれを失くした父親「老人」がいますが、タバコは毎日ふたりしてスパスパ、毎日インスタントラーメンが大好きだと納豆と一緒に食ています。
朝と昼はほおったらかしです。
夜は、バランスのとれた食事をつくろうとこころがけておりますが。
今夜は。
ヒジキと、豆と、野菜と、シャケ。キノコ汁と、蕎麦。そんなものですが・・・・・
生き甲斐などというしゃれた言葉も使いませんが、日々、巨人戦を最大の楽しみとし、勝てば慈悲のお釈迦様、負ければ怒濤の鬼を演じる両親は、ぷらぶら、毎日を好き放題に生きております。
年寄りは眠れないなんていう世間のたわごとはよそに、真夜中の一時二時まで起きてます。
朝は、10時になって、のそのそ、起きてくる。
11時から大好きな水戸黄門を観る。イモトを観る。
夜の食事の準備。最大の楽しみの巨人戦の観戦。
ビデオ録画のチェック。明日のテレビチェック。風呂。
そして、
「今日も無事に終わりました。ごくろうさん」という呪文とともに、ベットと移動。
私も、なんにも言いませんし、彼らも私に何もいいません。
河合隼雄さんの「老いるとは」からのヒントですが、好きなことは人それぞれ、ゲームが命という人も素敵だし、絵をのんびり戸外で描くのもいいですよね。将棋もいいし、碁もいいね。釣りも良いと思うし、社交ダンスもかっこいいと思う。ボランティアに精を出すのもまた偉いと思う。
屋根の上で雲を見ながら酒を飲む、これなんか最高ですね。
各自が好きなことすればいいのではないでしょうかね。
<性格と気質と考え方皆違いますからね。>
それが、ほんとうの意味での、ライフスタイルだと思います。
ところで、最近。
妙なる子供をひきこむ事件があとをたたない。
私は子供は天使だと信じているので、こんな事件は許せない。
一番嫌なのは、子供を犠牲にす事件である。先日も、アホな母親が、13歳の男の子を紐で
首をしめて殺害。ああ、なんと可哀想なことか。
自分だけで死ねばいいんだよ。その母親。「将来を悲観して」なんて言っていたらしいが、
子供なんて、ほおっておいても元気にたくましく育つんだから。心中ではなくて、殺人です、これは。
そして自分だけは、死ねないなんて言っているんだから馬鹿な女だ。
次の気になる事件は、確か北海道か。やはり、13歳前後の男の子。
母親が浮気して、若い男を家につれこむ。
その男は優しいので、確か姉だか、弟だかが、なついている。
父親のノートを偶然見ると、<たぶん日記>、母親を許せず、長男をはじめ、皆をみちずれにして死ぬ、とかそんなことが書いてあったらしい。
驚いた少年は、その若い男になついていた姉と弟、そして母親を殺害。
これはもう、父親まで情けない男でしょう。その若い男と殴り合いの喧嘩すればいいだけの話ですよ。
負けようが、勝とうが、とにかく、戦う自分を見せる。そして、子供達の前で、お前たちを失いたくないとはっきり言う。
それだけの話だ。ノートに、子供をみちずれに死ぬなんていうのは、結局その若い男に負けたということだろう。もしも、どうしてもというのならば、子供をみちづれは駄目、若い男とその女と自分の三人だけ死ねばいいんだ。子供たちの未来を奪うことは絶対に許せない。
そして、最後。やはり13歳ほどの少年。父親に、たしか、妻とうまくいかずに、あちこち車でつれまわらされ、一緒に死のうとばかり、一週間ほど、山の中などをふららふしていたらしい。最後の日、父親が金もつきたので、一緒に死のうと、その子供の首をしっかりとしめようとした時、その少年は遠のく意識の中でこう言ったのだ。
「パパ、大好き」
父親は、はっとし、驚き、自分の手を見ながら、子供を抱きしめ、泣いたと言う。結果として少年はその究極の言葉を発して、生きることができた。
そして、その父親を我にかえしたことになる。
「言葉の力」はすごい。
ほとんどの情けない暗い心中の事件の裏には、健康なる言葉の喧嘩や掛け合いや洪笑がないのだ、と思う。
皆、愛が欠乏している。その傷口にしっかり塗るこころの薬は愛しかないということを忘れてはいけないだろう。
そしてその愛を表現するには「言葉」と「ハグ」しかないと私は考えている。

こんな本を読みました。
「無為の力」 河合隼雄 + 谷川浩司
心理カウンセリングというのは大変な商売なんです。
ただ、待ってるだけの商売です。
ほんとうに気が遠くなるぐらいの気がながい話です。
ただ、ひとつ、希望をもちながら、待っている。
いらいらしない。
すると、悩みの相談者はとうとう、自分から解決策を見つける。
そのお手伝いをするだけ。
彼は何もしない。無為。
カウンセリングを語る〈上〉 (講談社プラスアルファ文庫)/河合 隼雄

¥882
Amazon.co.jp
心理分析という職業は大変な商売ですね。
私も若い頃はさんさんユングにフロイト、アドラーとかマズロー、フロムいろいろ読みましたが、
小林秀雄さんの「偽心理学は人を酔わせる、そして二日酔いにする」という言葉で目が醒めました。
それ以来、河合隼雄さんの本だけに、絞って本を読んでますが、今夜も気になる一言ありました。
記録用に書いておきます。<自分のヒント>
癲癇の少年をあづかり、彼の両親からなんとかしてくれと頼まれる。
いろいろカウンセリングで良くなり、彼は「普通の人になる」のだ。
そこで、河合隼雄さんは考えるのだ。
はたして、「普通の人にすることが心理療法の目的なのだろうか」と。
このあたりが、彼の洞察の深いところですネ。
私のブログのテーマである、脳内麻薬の活性化とか、至高体験とかいうテーマから書くと、彼の言う
「癲癇の時のその少年の神々しさ」という言葉さへ使っている。
たしかに、本人にしてみれば、敏感すぎる生活やら精神やらが、辟易しているのだから、はやく「普通の人」になりたいのだろうが、河合さんは自問する。
普通の人っていうのは、「満員電車で通勤し、野球をビール飲みながら観戦し、たまにゴルフをやって、友達と麻雀に興じる人」のことであると。
そんな人になるよりも、今の彼の方が魅力的である、そう河合サンは言う。
自分よりも大きな物体を力任せに投げつけたり、驚くべき腕力を発揮することがある。
あるいは、難しい哲学書を読みきちんと分析したり、人の知らないことを体系的に研究もする。
しかし、精神的な苦しさから彼らは一応に、「普通人」になりたがるのだ。
逆に言うと、そこから、にげなかった人が天才だと言う事もできるでしょうネ。
三島由紀夫が言うように、もともと、ゲイジュツ家というものは、リスク=危険なるものに、ギリギリまで近づいていって、そのまさに「まるこげ」になる寸前に、その炎を書ききるのが職務なのでしょうね。
だから、そこに落ちて、まっくろにこげてしまう人がたくさんいましたでしょう。
犯罪人に、革命家に、精神病患者に、鬱病、怪しげなジゴロ、スリ、詐欺師、泥棒、
コズルイ商売人・・・あげたらきりがありませんヨネ。
ビュッフェは、最後の死で、ビニール袋で窒息死しましたし、あの最後の絵には狂がありました。
パゾリーニはホモの少年に殴り殺されましたし、三島は割腹。
ニーチェは狂死。異常なる死はべつにめずらしくもありませんネ。
脱線です。
河合隼雄さんが紹介したアメリカユング派心理療法家のリース滝さんの一言。
「酒やドラッグをやめたからと言って、人間的に貧しくなったのでは意味がないのではないか。やめたあとでも酒のパワーみたいなものを使えないと・・・」
「癲癇の症状がなくなった時、この子はほんとうはさびしいのではないか」
「心理療法家がクライアントを普通の人にしようなんていうのは、大きな思い違い、傲慢である」
たいしたものですネ。
こんな人に私もこころを見てもらいたかったですけど、こんな人ははやく逝っちゃうんです。昨年なくなりました。ほんとうに残念です。生きている内に一度講演でも行きたかった。
心理カウンセリングというのは大変な商売なんです。
ただ、待ってるだけの商売です。
ほんとうに気が遠くなるぐらいの気がながい話です。
ただ、ひとつ、希望をもちながら、待っている。
いらいらしない。
すると、悩みの相談者はとうとう、自分から解決策を見つける。
そのお手伝いをするだけ。
私は何もしない。無為。
思い通りにならないことこそ
ほんとうにおもしろいことだ
と思っているんです。 河合隼雄
FIN
「山の音」 川端康成原作 成瀬喜男監督
「日本の子供には、もっと孤独を教えないと、思想は生まれませんね」 川端康成
映画「山の音」、小説川端康成「山の音」再読しました。
YouTubeにもすでに「山の音」はない。
資料によると、
『山の音』(やまのおと)は、川端康成の長編小説。戦後日本文学の最高峰と評され[1]、第7回(1954年度)野間文芸賞を受賞[2][3]。川端の作家的評価を決定づけた作品として位置づけられている[4][5][6]。老いを自覚し、ふと耳にした「山の音」を死期の告知と怖れながら、息子の嫁に淡い恋情を抱く主人公の様々な夢想や心境、死者の夢を基調に、復員兵の息子の頽廃、出戻りの娘など、家族間の心理的葛藤を鎌倉の美しい自然や風物と共に描いた作品[1]。繊細冷静に捕えられた複雑な諸相の中、敗戦の傷跡が色濃く残る時代を背景に〈日本古来の悲しみ〉〈あはれな日本の美しさ〉が表現されている[1][6][7][8][4][9]。
『山の音』は海外でも評価が高く、2002年(平成14年)にはノルウェー・ブック・クラブ発表の「史上最高の文学100」に、近代日本の作品として唯一選出された[10]。・・・とある。
やっと、DVDを手に入れて、じっくり観てみた。
山の音 (新潮文庫)/新潮社
¥637
Amazon.co.jp
本も再読。
物語などは、ネットのどこにでも、あるけれども、ノルウェイブッククラブの100冊の本の一冊に選ばれているとは!!!
野間文芸賞を獲得している。
昨日は、SF映画についてなにやらアイデアが湧いて来て、ずっと考えていたけれども、平行してこの「山の音」を観ていたというのも変な気がする。
まったく違う映画だから、平行して観れるのかもしれない。
ジョニー・デップの方は、ホーキンス博士が心配している人工知能の自己増殖というのがテーマのひとつであったけれど。
人間の魂のようなものを書いたのが、この「山の音」である。
レヴューを観ると、「わからない映画」というのが多くて、おかしかった。
小林秀雄氏が言うように、なんで、現代人は、すぐに、何かをわかろうとするのだろうか、・・・・・・・何かの意味をさぐろうとするのだろうか・・・・・・・。
共感。感じる心。まるごと飲み込むこと。
それらの力がどんどんなくなって来ているということだろう。
たしかに、テレビなんかのドラマは、わかりやすく、シンプルで、五分ごとに笑があったり、叫んだり、抱きついたり、泣いたりして、飽きもこないし、
起承転結がはっきりしていて、西洋のシネマ同様、カタルシスを感じやすいのだろうと思う。
比較すると。
この「山の音」
源氏物語や、細雪、と同じく、まるで、起承転結がない。
個人的には、「掌の小説」が大好きなので、それの長編という感じかも。
ある意味、ベルイマンの「野いちご」を連想した。
野いちごは、1957年作。(つげ義春が、この映画を観ていて、無意識に「ねじ式」を書いたと思っていたが、たまたま調べたら、ねじ式は、1968年作なので、つげ義春の夢のイメージの方がずっと先立った。)
この、「山の音」は、1954年なので、ベルイマンの「野いちご」よりも、先。
成瀬のこの映画作品や、川端の作品はたしかサイデンステッカーさんにより英訳されているので、読まれていたのかもしれないがわからない。
三島由紀夫氏は、こう小説の「山の音」を評価している。
三島由紀夫は、『山の音』を川端作品のベストスリーの首位に挙げることを当然とし、「もはや贅言を要しまい。その美と鬼気と芸術的完璧さは、すでに巷間周知の事実である」と述べ[25]、同じくベストスリーの2位に挙げた『反橋』連作(反橋、しぐれ、住吉)は、『山の音』の母胎となった作品だとし、「氏(川端)は『山の音』から『反橋』の連作を通じて、はじめて、古典の血脈にふれ、日本文学の伝統に足を踏まへた」と解説している[25]。
また三島は文章の特徴について、信吾が〈山の音〉を聞き恐怖に襲われる場面の描写における「頻繁な改行の技法」を、「琴の弦が突然切れたひびきや、精霊をよび出す梓弓の弾かれた弦の音のやうなもの」だと形容し、そういった「音の突然の断絶の効果」のある「音楽のない」文章を、「一種の鬼気を生む」ものとして[26]、「行を改められた文章の突如の変調」と「構成の乱雑さ。故意の重複と、故意に抒述を前後させてあること」が、死の恐怖が急に襲ってくる「鬼気」を生む効果の原因だと解析し、初期作品(掌の小説)から看取されるこの技法が、この『山の音』の場面において、「一そう手が込んで、一そう蒼古な味を帯びてきた」と評している[26]。
このように、ひとつの日本の「家庭」を直截に、真摯に、真っ正面から書くという当たり前のことは、今の現代小説にはあまりみあたらない。
皆、個人としての主人公を書く事はあっても、もう家庭は書かないのだ。
よく日本人は完全主義完璧主義と言われるので、英語を完全にマスターしないと喋らないのだというジョークがあるけれど
笑える話しではなくて、こんなところにも、日本人の完璧主義がでてきているのかもしれない。
イタリア人のように、たとえば、相手の小さな欠点には目をつぶって、なんであれ、とにかく、ハグ ハグ ハグ、・・・キス・・・・そしてお互いに褒め合って、人生をワインを飲みつつ、楽しむ・・・。
そんな生活にあこがれたりもするのが日本人。
(ところが、実際には、簡単にサンドイッチでパーティなどをすませる外人と比較して、なにからなにまで、手作りで、料理はフルコース、花を飾り、服装はああでこうで、音楽はこうで・・・と、考えすぎるから、それこそおもてなしだけで、胸いっぱい腹一杯、げんなりしてしまうのが、私たち日本人の欠点のひとつかもしれない)
以前も書いたけれども、ドイツに住む、日本人の家族が、ドイツ人の隣人に招かれて、「美味しい夕飯をいかが」といわれ、楽しみにして家族で遊びにいったら、とれたばかりの、ジャガイモが、ほかほかにゆでてあり、それだけを皆で、皮を向きながら、食べながら談笑したという。
それでいいのではないか????
素晴しいエピソードだと感心して、今でも、記憶している。
・・・・・・・・・
「山の音」
そんなわけで、日本の家庭の、やや陰気なところ、複雑な関係、男と女の浮気の話しも含めて、家族の心情をじつに丁寧に書いている。
「夫婦というものは、どこか親子だよ。時には亭主が父親のつもりになったり、時には細君が母親のつもりになったり。それでないと上手くゆかない」
この川端の言葉を思い出す。
ポイントは、昔憧れていた妻の姉が死んだので、その後に、そのダンナの面倒を観ていた保子だったが、結婚する感じがなかったので、尾形信吾つまりこの映画の主人公の60歳の男が、保子と結婚したのだったが、いまでも、その死んだ姉のイメージが忘れられない。
そこに、息子修一の嫁になった菊子=原節子が、その死んだ妻の姉にそっくりだっために、彼は、淡い恋心をもちながら、親切に接するようになる。
・・・・・・・・
物語は、もうかなり複雑。それがまた、不思議と、慈童面やら、
息子の復員やら、
中絶やら、もみじの盆栽やら、
ベルイマンが夜になると観る陰気な死の夢ではないが、尾形信吾が最近聞くようになった「山の音」つまりしずかな地響きのような音についてて・・・・・・・・
さまざまなる、ディテールの言葉が、散らばっていて、想像力を刺激してくれる。
ハリウッド映画のように、見たあとに、スカットするような映画ではないけれども、よく、川端康成の「山の音」という「雪国」に匹敵する複雑な小説を映画にしたなぁと感心する。
監督は成瀬喜男。
キャスト
尾形菊子:原節子
尾形修一:上原謙
尾形信吾:山村聡
尾形保子:長岡輝子
谷崎英子:杉葉子
池田:丹阿弥谷津子
相原房子:中北千枝子
相原:金子信雄
絹子:角梨枝子
信吾の友人:十朱久雄
北川町子
斎藤史子
馬野都留子
となっています。
結局は、この三人が中心となって、映画がまとまってくるわけです。
上原は、じつに、嫌な男をじつにうまく好演していますね。原節子を嫌う理由は、
その「子ども性」にあるらしいですが、ここらあたりは小説を読まないとよくわからないでしょう。このような美しい奥様をほったらかしにして、浮気をするというのは。
ただ、ベルイマンの、「野いちご」にも、ありましたが、好きな女にふられる初老の男の回想シーン。
あなたは偉すぎる、賢すぎる・・・・・・・・・立派すぎる・・・・・・。
わたしにかまってくれない・・・・・・
そんなニュアンスはちがいますが、そのようなセリフがありました。
ふと、上原の役柄に、連想しました。
そこに、復員したという上原の経験が、重なってきます。複雑です。
品があります。
やはり、男というものは、何歳になっても、理想の女性にあこがれつづけるものなんです。・・・・・・・・・・
原 節子(はら せつこ、1920年6月17日 - 2015年9月5日)は、日本の女優。「永遠の処女」と呼ばれ、戦前から戦後にかけて活動し、日本映画の黄金時代を体現した。代表作に『わが青春に悔なし』、『青い山脈』、『めし』、『東京物語』などがある。
1963年に女優業を引退し、2015年に死去するまで隠遁生活を送っていた[2]。
2000年に発表された『キネマ旬報』の「20世紀の映画スター・女優編」で日本女優の第1位に輝いた。
◎資料 ネットからおかりしました。ありがとうございます。
2012年に、10年おきに行われている英国映画協会の[世界で最も優れた映画50選]で、358人の映画監督が選ぶ(監督部門)で『東京物語』が1位に、また世界の批評家846人が選ぶ(批評家部門)でも3位に選ばれている。
どこにでもある普通の生活。普通の家庭。普通の風景に普通の時間。
しかしながら。
そこに隠れるなにか。
男女の仲というのは、夕食を二人っきりで三度して、それでどうにかならなかったときはあきらめろ。 小津安二郎
FIN
YouTubeの動画を何回も続けて聞きたい BGMのように
YouTubeの動画を何回も続けて聞きたい BGMのように・・・
といつも思っていた。
あさは、いつも白檀を焚いて、少しぼっと深呼吸瞑想してから、熱い紅茶を飲むようにしている。
珈琲も好きなのだが、交感神経を刺激しすぎると、私の場合は、不整脈がでるから気をつけている。
・・・・・・・
このアリスコルトレーンの曲を数回聞いてから、雑用に入るのだが、いちいち元に戻すのが面倒だなあと思っていたら、なんと、続けて聞く方法があったとは。
ただ、youtubeのあとに、repeatという言葉を入れておけば良いだけだと。そしてもenterボタンを押すと、リピートサイトに飛ぶ。
ほお。
一神教と八百万神・・神隠しとは「千と千尋の神隠し」×「レフト・ビハインド」 「シンデレラ」
八百万神(やおよろずのかみ)とは
数多くの神,すべての神のこと。類似の語に八十神(やそがみ),八十万神(やそよろずのかみ),千万神(ちよろずのかみ)がある。森羅万象に神の発現を認める古代日本の神観念を表す言葉。
「三度やって駄目だったからもう一度やるんだ 」
Three times isn't enough.
史上最大の作戦
The Longest Day
北海道の今、またゆりかえしが、きたように、雪国になっております。
植草甚一のエッセイに、「雨ふりだからミステリーでも読もう」というのがありますが、
ここでは、「雪だから漫画でも読もう」という気持ちになるもんです。
もう絶版の「ビックゴールド」というおそらく、「ビックコミック」の前身みたいな漫画本。
創刊号から持っておりますが、そのナンバー2を、ぺらぺら見ておりました。
瀬戸内晴美原作の、「みずめ」を、牧美也子が描いていたり、(いやあほんとうに絵がうまいですね。)、
水野英子の「薔薇達」とか、すごい傑作漫画ばかり。
今の若者は、ジャンプかもしれませんが、昔の若者は、こんな漫画を読んでいたんです。
楳図かずおといえば、まことちゃんとか、ホラーのイメージがものすごく強いですが、
「smile」という傑作漫画が、この号にのっています。
とにかく、天才としか、思えない短編です。
絵は例によって、緻密。
コマが小さいのに、ぐいぐい、ひっぱっていく愛の童話物語のような。
レヴューでも、「火の鳥」と比較している人がたくさんいましたね。
今では、「イアラ」「内なる仮面」「ドアの向こうに」の三冊の短編集がでていますので、おそらく、このどれかの中に、含まれていることでしょうが。
手塚治虫の「火の山」。
なんと、この「昭和新山」物語なんですが、北海道に住んでいる私は、しょっちゅう、
行きましたし、修学旅行などのコースにもなっていました。
手塚治虫が、わざわざ、昭和新山の資料館の三松三郎氏や、役場の担当の方に、取材をして、このビックゴールドに、一挙に、100ページで発表した作品です。
今は、よく古本屋でも、見かける作品ですが、当時は、ものすごい意気込みで、手塚治虫氏がこの作品にチャレンジしていたということが、よく感じられる作品です。
それに、今では、文庫本くらいの大きさでしか読めませんが、このビックゴールドは、A4ですので、迫力があります。

以前も記事に描きましたが、男と女の不思議な縁。
どうしようもないろくでなしの男と、あばずれの女が、不思議と、ケンカしながら一緒に暮らし始める・・・・・・・・・最後は夫婦になって、火の山を守ろうとする。
その男の名前は、たまたま、昭和=としかず。
それで、尊敬する三松さんが、昭和新山という昭和にちなんでつけた名前は、「オレの名前をつけてくれたんだ」と感激するところ、やはり、上手いです、手塚治虫。
・・・・・・・・・・・・
あと・・・・・・・
私の好きな「トワイネラの白鳥」。
「トォネラの白鳥」を扱った作品といえば、水野英子。
それが、手塚治虫にもあるとは知らなかった。
「0次元の丘」だ。
いまでこそ、輪廻の科学的な研究もされるようになってきたけれども、
この宇宙、人間の知っていることなど、軒先の一本の草木の露みたいなものだろう。
解説の夢枕獏のあこがれにも似た手塚治虫の10の天才の秘密みたいなもの。
なかなかだと思う。
手塚治虫名作集 (5) (集英社文庫)/集英社
¥627
Amazon.co.jp
・・・・・・・・・・・
映画ですが。
この手塚治虫氏は、一時、400人程が働いていた虫プロダクションの社長。
管理がやはり苦手だったのか、つぶしてしまいます。
アニメ制作に、彼が、ぞっこん惚れ込んでいたのは、ディズニーに会いに行っていたことも記録に残っていますし、夢中で作品をつくっていたのですが、やはり高尚すぎる作品は、一般大衆の受けが弱いのでしょう。
それで、また、初心にもどって描き始めたのが、ブラック・ジャックという傑作です。
手塚治虫氏が死ぬ数年前の作品ですから、凄みがあります。
ガンもその頃、種がでていたのでしょうか、・・・・・・私にはわかりませんが、作品を描くのには、胃に負担がかかりますから。
宮崎駿氏の作品は好きですが、彼は暴言がおおいですね。
手塚治虫氏にも批判の言葉を投げつけていますので、けっこう、嫉妬心の強い人なんだろうと想像します。
それでも、「千と千尋の神隠し」はおもしろいです。
これは、英語版では、spirited awayと、訳されていますが、ちょっとこの言葉にひっかかったのです。
それは、たまたま、映画「レフト・ビハインド」という映画を見たのです。
(ニコラス・ケイジが、出ていたので見ただけなんですが・・・・・・・・)
神隠しの映画でした。・・・・・・・
不思議な映画。
でも、やっぱり西洋映画、一神教映画。
「千と千尋の神隠し」と比較すると、あまりにも、神の概念がちがいすぎる・・・・・・・
この「レフト・ビハインド」の挿入歌。
jack lenzは歌う・・・・・「こころを入れ替える暇はない、神はあらわれ、ひとびとは取り残された」
最初から、一種の飛行機のパニック映画だと思っていたし、なんせ、ヒロインが、私の好きなニコラス・ケイジなので、わくわくしながら見ていたのですが、不倫中の彼が、仕事に没頭するあまり、そして、神に夢中の妻に嫌気をさして、娘と息子との約束を反古にして、飛行機に乗るところまでは、どんな展開をするのかと・・・・・・・見ていたのですが、飛行機内で、子ども達が、突然、消え去るシーンがあり、びっくり。
これ、どうやって映画をまとめるのかなと、少し心配して見ていたのですが、神様の仕業ということになりました。
やはり、私たち日本、正月には、神社にお参りし、お盆の行事や、葬式は仏前なのに、クリスマスもみんなで、祝う・・・・大騒ぎ、そんな民族から見ると、せんとちひろのほうがなにやら、こころが、落ち着きます。
・・・・・・・・・・
最初の頃は、見ていて、神様に夢中になる物語のあらすじに対して、なにやら、その家族に不幸になった裏の伏線があって、たとえば、以前この記事で紹介した、「火宅の人」の檀一雄の妻のように、子どもが、突然、重病になって、そのために、祈祷をしたり、精神を少しわずらうような、振る舞いをしたり、そんな連想をしていたのですが、・・・・・
最後は、しっかりと、「神を信じるのであれば、ここで祈って下さい」というパニック状態でのニコラス・ケイジの言葉に、逆に、あまりにも単純ということで、おどろいてしまいました。
やはり、調べてみると、
さすがキリスト教の西洋・アメリカ・・・
『レフトビハインド』( Left Behind )とは、ティム・ラヘイ、ジェリー・ジェンキンズの共同著作によるアメリカの小説。およびその続編からならシリーズ。
公式サイトによれば全米で6,500万部を売り上げたベストセラーである[1]。アメリカ本国では映画化、ゲーム化もなされている[要出典]。日本語訳はいのちのことば社から刊行されている。
時は近未来、最後の審判が迫り「ヨハネの黙示録」の預言が実現していく世界を描く。「患難前携挙説」の立場をとっており、「携挙」によって信心深い人々や幼い子供が姿を消すところから物語が始まる。
「患難前携挙説」とか、「携挙」とか、エヴァンゲリオン用語みたいな響きの言葉です。
映画では、日本語字幕ですので、あんまりマニアックな言葉は省略したのかもしれません。
あとで、また、じっくりチェックしたいとは思っていますが。
たとえば、このような言葉は映画のなかでは、強調されてはいなかったと思うのですが。
原作のなかでのオリジナルの用語定義でしょう。
トリビュレーション・フォース (Tribulation Force)
患難時代(トリビュレーション)に備えて結成された。聖書を研究し、人々を信仰に導くだけでなく、反キリストとの戦いを目的とする。
グローバル・コミュニティー (Global Community)
ニコライ・カルパチアを「主権者」と仰ぐ世界政府。イラクの地に新たに建設した「ニュー・バビロン」を首都とする。人類の統合と世界平和という美しい理想をかかげつつ各国の武装解除をすすめるが、自らは兵力・暴力をもって、コミュニティーに反発する国家・個人を潰していく。
エニグマ・バビロン・ワン・ワールド・フェイス (Enigma Babylon One World Faith)
グローバル・コミュニティーにおいて事実上の国教の地位にある新しい宗教。世界中の宗教を寄せ集め統合した教義を持つ。この宗教の聖職者を信道士(フェイス・ガイド)という。その祈りでは「宇宙の父母」や「動物神」が語られる。聖書の記述もあくまで象徴や比喩として解釈し、トリビュレーション・フォースが信じるような「原理主義的」解釈を狭量なものとして否定する。
ニコラス・ケイジは、どんな映画でも、こなしてしまいますので、ちょっと、びっくりするような感覚もありますが、名作だけではなくて、このような映画でも、必死で演技しているところが好きです。
「せんとちひろの神隠し」
これの英語題名は、Spirited Awayとなっていますので、まさに、「レフト・ビハインド」同様に、突然消えてしまう子ども達そのものなのかもしれません。
「レフト・ビハインド」では、子ども達は、あっという間に、天国にまさに「携挙」されるわけですが、同じ「携挙」でも、ちひろは、異世界に迷い込み、神々の訪れる湯屋で働くことになった少女、でした。
宮崎駿監督作品。2001年7月20日に日本公開。興行収入300億円を超えた日本歴代興行収入第1位の大ヒット作品ですが、とにかく、その異次元異世界の神々の不思議さ・多様さに・西洋人は驚愕したようで、たまたま、見た番組では、宮崎監督は、フランスの女性ファン達からの絶賛の嵐を浴びていたと思います。
フランスの宗教。
調べてみますと、
宗教面では、国民の約7割がカトリックといわれている。カトリックの歴史も古くフランス国家はカトリック教会の長姉とも言われている。代表的な教会はノートルダム大聖堂、サン=ドニ大聖堂などが挙げられる。パリ外国宣教会はその宣教会。フランス革命以降、公共の場における政教分離が徹底され、宗教色が排除されている。
と、ありますので、やはり、プロテスタントと違って、フランスやアイルランドは、どこか、ケルトの自然への愛・・・つまり、日本人の自然の神秘への傾倒と近いところが、わたしには感じられますが。
どうなんでしょうか???
以前、ブルターニュの森のなかにいる妖精のことについての、自然観察の素晴しいドキュメンタリーを見ましたが、このブルターニュは、おもしろいです。
伝説と伝統の大地
海の国であると同時に森の国であるブルターニュ地方は、変化に富んだ気候と驚きの風景に満ちています。ブルターニュの生き生きとして力強い風に身を任せ、浜辺や、断崖絶壁、荒地、中世の町を訪れましょう。ブルターニュならではの風物と奥深いその歴史に触れ、文化と自然を満喫しましょう。馬に乗ったり、潜ったり、船に揺られたり、祭りやフェスティバルのリズムに合わせてスウィングしたり、パブの和気あいあいとした雰囲気に浸ったりしましょう。そして何より、心から安らいでくつろいでください。
独特の雰囲気を持つブルターニュの沿岸地帯
海賊の町として知られ城壁に囲まれたサン・マロのコード・デメロード(エメラルド海岸)から神秘的なコート・ド・グラニット・ローズ(バラ色の花崗岩海岸)まで、ブルターニュの沿岸地帯は、ほかのどこにも似ていない独特の雰囲気を持っています。税関吏の道は、ブルターニュ特有の荒地と断崖の間を歩くハイキング・コースで、気候の良い時には、ハリエニシダやエニシダの香りが、さわやかな海風と交じり合います。沖合では、ブルターニュの島々が魅力を競い合っています。グロワ島、ブレア島、グレナン諸島、ウェサン島、ベル・イル・アン・メール島で、野生のままの浜辺や自然保護区の入り江、灯台などを見学しましょう。セット・イル(七つ島)は、フランスで最大の鳥類保護区です。ニシツノメドリ、ヨーロッパヒウメ、シロカツオドリが、優雅に暮らしています。フレエル岬からは、海と荒地の間で踊る鳥たちのバレーが見物できます。ブルターニュ地方の言葉で「小さな海」を意味するモルビアン湾を臨む海岸に沿った100㎞ほどの遊歩道を、保護された自然を眺めながら散策しましょう。イル・オ・モワンヌ(修道士の島)などの野生のままの自然が残る場所がいくつも隠されています。
伝説と歴史遺産の狭間で
この地方の歴史の証人でありシンボルであるブルターニュ高等法院は、今では控訴院となっていますが、ブルターニュ地方の中心都市であるレンヌの主要な建築遺産です。ポン・タヴェンの美術館では、モーリス・ドニからポール・ゴーギャンに至るブルターニュ地方を描いた画家たちの作品を見ることができます。ブルターニュ地方はあらゆる年代の人々に愛されている観光地です。子供たちは、サン・マロの大水族館やポン・スコルフの動物園やブレストの水族館オセアノポリスが大好きです。ブロセリアンドの森で、伝説の魔術師マーリンと妖精ヴィヴィアンとアーサー王の足跡をたどり、フジェール城では、妖精メリュジーヌの魔法の虜になりましょう。伝説と遺産といえば、モン・サン・ミッシェル修道院(ノルマンディー地方ですが、ブルターニュ地方からわずか4㎞です)や、ロカマドゥールやカルナックの巨石群もあります。キリスト受難群像や、パルドン祭り、礼拝堂など、ブルターニュ地方には宗教の伝統が根強く残されており、中でもボーポールの海の修道院とヴァンヌのサン・ピエール大聖堂は、中世の宗教建築を代表する建物です。
ブルターニュ地方のスペシャリテ
伝統と民俗芸能によって形作られているブルターニュ地方は、食の伝統も大切に守っています。たとえば、そば粉のガレット、シードル、ブルターニュ風蜂蜜酒、豪華なシーフード・プレート、ブルターニュ風ポトフのキ・カ・ファース、焼き菓子のファー・ブルトン、そしてクイニー・アマンなどなど・・・。
こんな資料を読むと、やはり、フランス人は、「せんとちひろの神隠し」は理解できてあたりまえなんだなあ、と妙に感心してしまいます。
モンサンミッシェルも、一度だけ行きましたが、実に、思い出深いところです。
パリから、たしか、六時間くらいバスに乗って、ついて、二三時間の自由時間だけで、また六時間かけてもどってきただけですが、写真はたくさん撮ってきました。
日本の伊勢神宮。
ここだけは、死ぬ前に一度は行きたいところです。
五十鈴川で、手を洗う。・・・・・
みそぎ。
日本の水道水は、昔ほど、きれいではないにしても、十分に飲むに耐えうる。
外国の水はひどいですから。
水。
外出して家にもどったら、誰しも、日本人ならば、手を洗う。
トイレに入ったら、手を洗う。
神社の入り口で手を洗う。
茶道でも、手を洗う。
天照大神つまり、アマテラスオオミカミのことを、最近の若者は、テンテルダイジンとよぶそうです。
それでも、光、太陽の光が、私たちをなにか守ってくれている、見守っていてくれている、
日本人が死んだら、墓のなかにじっとしているんではなくて、この自然界のなかで飛び回れる、・・・・・・・・そう、日本の豊かな自然界こそが、日本人の天国というか、ゆっくり永劫の休息場所という感覚が、個人的な意見ですが、私にはあります。
「千と千尋の神隠し」は、「霧のむこうのふしぎな町 」
柏葉 幸子をアニメ化しようとした話しかジブリにあったときに、宮崎駿氏が、断念したあとに、ライバル意識を持って「千と千尋の神隠し」を制作したということらしいです。
私もこんな年になってから、初心にもどり、高校生の時の夢をおいかけています。
それが、なにか?
「北国のふたり」
「シンデレラ」
ディズニー・・・・・・・
以前記事に書いた「ファンタジア」の他の短編も素晴しいですね。
最近は、それをすべてまとめた、DVDも発売になったということ。
でも、シンデレラのディズニー版はやはりちょっとすごすぎます。
特に、この後半。
ネズミたちや、犬たちが、協力しあい、いじわる猫をやっつけて、継母に閉じ込められたシンデレラに、部屋の鍵を渡すシーンなどは、こんな年になっても、感激します。
そして、単純ではありますが、彼女の夢の実現するあたりの、彼女の表情や動き。
いまでも、これだけ、何回見ても、感激するわけですから、
制作発表当時の、私の記憶を思い出しても、もうびっくりしました。
なんで、こんなスムーズな動きが、アニメーションでできるのだろうかと・・・
そして、あの有名な歌。
女性でなくても、わくわくします。
テレビをつけると、朝から晩まで、マイナスな情報ばかり。
そこに、いつもの言葉の乱暴な、そして、勝手なことばかり言うコメンテイター。
あんなものばかり見ていると、俗な自分が、さらに、俗俗になる感じがしますので。
なるぺく良き番組を見つけて見るようにしています。
ところで・・・・・・・・
森有正という文学者。
好きなのですが、ずっとパリで暮らしています。
森氏の母親はピアノを弾くし、牧師であった父親もヴァイオリンを弾く。
そんな環境のなかで森氏は成長し、文学と音楽がひとつになったような自己の体験を、信じるようになったのかもしれない。
彼はボードレールとリルケの「文学+音楽」の仕様に感じ入る。
しかしながら。
日本人でありながら、日本の楽曲をまったく知らずに、環境の中から育ったとはいえ、森氏のような日本人はおもしろいと私はいつも思う。
日本人は果たして魂まで西洋人になれるのか?
確かに、私が、絵本と言えば、やはり、「マッチ売りの少女」や「人魚姫」の圧倒的な印象は、脳裏に焼き付いて離れない。

「ぶんぶくちゃがま」かな、日本の絵本で怖いような不思議な印象を持つのは。
私が、幼稚園の頃。
読んだ記憶がある。
あとは「サルカニ合戦」。
なぜ、日本の民謡を皆はあえて、聞くことはしないのだろうか?
昔お世話になった三味線奏者の三宅氏の「牛追い」の民謡歌は素晴らしかった。
三味線には日本の魂があると思う。
三宅良二氏。
奥様にも、お世話になりました。
ほんとうにいまでも、感謝しています。
ふたりの舞台のバックの絵まで、描かせていただいて、感謝感謝でした。
そんなわけで、西洋東洋・・
せめて、半分西洋、半分日本。それくらいの比率で音楽や映画や文学を楽しみたい。
想像妄想空想。
しかしながら、外国の子供達も日本のアニメを観て育つ。無国籍ということの、メリットとデメリット。根無し草のメリットとデメリット。
根無し草という生き方もまた、あるのかもしれない。日本人。
悩むところ。
まあ、「流れる」ように交互に聞きつづけよう。読み続けよう。
「女性は我々の作品を評価できる最良の判断者である。
彼女たちの好みは非常に重要だ。
映画館に足をよく運び、男性たちを引っ張って来てくれる」
女性たちが好んでくれれば、男がなんと言おうがかまうものか!!!!
ウォルト・ディズニー
FIN
漫画から漫画の勉強するのはやめなさい「私は夜を憎む」「四分間のピアニスト」音楽映画の魅惑
君たち、
漫画から漫画の勉強するのはやめなさい。
一流の映画をみろ、
一流の音楽を聞け、
一流の芝居を見ろ、
一流の本を読め。
そして、
それから自分の世界を作れ。
手塚治虫
手塚治虫は、自分でもピアノを弾くし、大のクラシックファン、いや音楽ファンだったということは、意外に知られていないのではないだろうか。
カーペンターズや、ピンキーとキラーズも聴いたし、ダーク・ダックスも聴いたというが。
レコードボックスには、ぎっしり、クラシックのレコードが。
これが、コレクションのレコードのリストです。・・・興味深いです。
そして、このレコードを聴きながら、この愛用のペンを使いながら、傑作を描き続けました。
この写真は実際の彼の遺品です。
彼は、ベートーベンが大好きでしたから、遺作の「ルドヴィヒ」を描いていた時は、わざわざドイツのベートーベンの実家まで、行ったくらいです。
写真が残っています。・・・・・・・・
私の大好きなルドンが、音楽について、このような言葉を残しています。・・・・・
音楽は夜の芸術であり、夢の芸術だ。
絵画は太陽の芸術であり、光の芸術だ。 ルドン
大学時代。
好きな10人の作家の名前を書いて、壁に、はりつける。
三島由紀夫
小林秀雄
開高健
渋沢竜彦
花田清輝
吉行淳之介
谷崎潤一郎
川端康成
植草甚一
コクトー
その10人の作家たちに、サラリーマンになると、画家が入って来て、つぎに哲学者なども入って来て、どんどん変遷していった。今は、古典が多いですね。
でも、結局は、いまでも、三島由紀夫や小林秀雄はまったく変わらない。
そして、植草甚一も。
彼は思想者とかいうよりも、淀川長治さんと同じく、好きて好きでしょうがないことを、根気よくやっていた人ですので、憧れました。
私が、退職後、jazzとクラシックを日々、六時間くらいずつ、毎日聴いたのも、彼の影響。
彼は、大の音楽好きでしたから。
音楽がないと生きて行けないくらいの人でしたから。
その意味では、手塚治虫氏と同じ。
・・・・・・・・・
映画・ジャズ・サブカルについて、
毎日新聞 2013年03月24日 00時03分
懐かしくて思わず手にした人も多かろう。映画・ジャズの評論や欧米文学の紹介で知られる植草甚一(じんいち)さんのコラム集「ぼくは散歩と雑学がすき」が初めて文庫(筑摩書房)になった。行きつけの東京・神田神保町(じんぼうちょう)の書店では文庫部門で先週売り上げ1位だった▲単行本が出たのは1970年。後に「サブカルチャーの元祖」と呼ばれることになる植草さんは既に還暦を過ぎていたが、「ぼくは目をまるくしてしまったんだ」といった軽妙な文体は今読み返しても新鮮だ▲紹介しているのはスタンリー・クブリック監督(植草さんはこう表記した)の映画「2001年宇宙の旅」やフィリップ・ロスの新作小説など。「(最近は)金には不自由しないニューヨークのインテリ・クラスが、マリファナ・パーティーをやるようになった」等々の情報も満載だ▲世界を結ぶネット社会が来るとは想像もできなかった時代。この明治生まれの不思議なおじさんを通じて若者たちはまだ遠かったアメリカを知った。「政治の季節」が終わり始めるころの空気を今の若者が知るのにも格好の本だろう▲同書出版から9年後、植草さんは亡くなった。財はなさなかったが、集めた4000枚ものレコードをタモリさんが買い取ったという「ちょっといい話」も残る▲終戦直後、東京・渋谷に「恋文(こいぶみ)横丁」という一角があり、植草さんは洋書を求めて横丁の書店によく通ったそうだ。渋谷はその後「サブカル」の拠点となり、今また再開発が進む。今日は日曜。渋谷の街を久々に散歩してみようか。「最近の若造は」とか説教はたれず、植草さんのように新しい何かを探しに。
親しいartのともだちから、こんな記事がおくられてきた。
なつかしき、植草甚一さん。
この題名から発せられるオーラ。
私の時代は、誰しもそうだとは思うが、中学生頃までは、まだまだ、フランスの映画や、イタリア映画、ヨーロッピアンの文化がたくさん、ラジオから流れ、映画もそれらの映画が多く、
学校帰りに、そのボスターを見ては、まだ見ることのできない年齢だけに、ドキドキするような
ときめきを感じたものだった。
中学から戻り、親が仕事から帰宅するまでの間に、テレビで、当時、洋画を中継していたので、
「穴」「わたしは夜が憎い」
「チャップリン」「カサブランカ」などだったであろうか。
夢中で見たものだった。
そして、なぜか、母親が帰ってくると、不思議と、慌てて、悪いことをしているかのようにテレビを消した。
たしかに、洋画を見ることは親はあまり良い顔はしなかったような気もする。
高校生になり、映画も自由に見ることができ、ロックやjazzやらのカルチャーがどっと、仲間の間で広まる。
今のゲームの話と同じで、当時は、流行のそれらのアメリカの文化を聞かねば皆の話についていけなかったのである。
自律神経、視線恐怖にやられていた私は高校時代は、自閉の学校生活だったせいか、音楽ばかり聞いていて、大学に入ってからステレオのない部屋で、植草甚一さんなどの本にはまっていった。
当時は、横浜に植草さんがよく現れると聞いていたので、「ちぐさ」「りんでん」「ダウンビート」などにさかんに行ったものだった。
今からふりかえると、この当時はもうアメリカアメリカアメリカ。
フランスの、イタリアの、ドイツの、伝統と歴史のパイにはさみこまれた重厚な料理というよりは、まさに、インスタント的な、破壊的な、瞬間的な、・・・感性のみの、文化ではあったが、
当時の若者には大受けしたのだった。
植草さんは、三日間連続徹夜でアメリカの小説を読みふけって自律神経をおかしくするような、大の本好き。
しかも、変わっているのは、ベストセラーや古典よりも、アメリカの新人作家のみを漁っては、珍本を探して、紹介するのが非常に上手だった。
彼の良いところは、若者と自分の間に線をまったくひかないところ。
いつも派手なTシャツを着ては、たぶん、今でも生きていれば、渋谷にしやがんでいる女の子や男の子たちと、ファッショングッヅについて楽しくおしゃべりをするようなこともしたのではないか。
丸谷才一氏との対談でも、その驚くべき博学と、雑学、独特の美意識には感銘した記憶がある。
私はミステリーをあまり読まないので、ほとんど彼の洋書や、古本の買い方を、学んだ。
今でも、最初に飛び込んだ古本屋で、一冊も買わないとその日一日が不漁、という言葉は私も信じていて、必ず一冊は買うようにしている。
30代の頃にも、神田の神保町で、洋書を見て回った日々。
懐かしい。
この写真はサラリーマン退職後に、50代の時の神田で古本を買っていた頃のもの。・・・

今でも、彼の愛した喫茶店があって、私も東京に出るときには必ず寄るところだ。
喫茶「さぼーる」。同じ店がふたつある。増築したのだと思う。
ここのスパゲッティも彼はよく食したと聞いていたが、あまり美味しくないので、というよりも、自分でつくったスパゲッティが一番だと思っているせいか、神田に行くときには、この「サボール」の前にあるラーメン屋に入る。
値段と味のバランスは良いと思う。
オリジナルの大きさの写真です。


「マザー・ウォーター」見ました。
音楽は、金子隆博。
◎資料
金子 隆博(かねこ たかひろ、1964年3月22日 - )は、日本のサクソフォーン奏者、作曲家、アレンジャー、プロデューサー。米米CLUBではサクソフォーンやキーボードを担当。2012年4月に「職業性ジストニア」であることを告白。サクソフォーンを休業し、キーボードを中心にしたマルチプレイヤーとして活動することを発表した。ホーンセクション・BIG HORNS BEEを主宰。
米米CLUBではフラッシュ金子の名義を用いており、現在は主にスタジオ・ミュージシャンとして活動している。
妻で米米CLUBメンバー(SUE CREAM SUE)のMINAKOは米米CLUBのヴォーカル・石井竜也(カールスモーキー石井)の実妹。よって石井は金子の義兄に当たる。
彼の音楽を聴いていると、不思議と、静寂を感じました。・・・・・・・
ヴァレリー・アファナシエフのことも。
リンク・・・・・興味在る方は・・
◎「マザー・ウォーター」資料から
「かもめ食堂」「めがね」「プール」など、人と場所との関係をテーマにした作品を撮り続けてきたプロジェクトが、豊かな水の流れを持つ街・京都を舞台に描いた人間ドラマ。ウイスキーしか置かないバーを営むセツコ、コーヒー店を開いたタカコ、豆腐屋のハツミら“水”にこだわる3人の女と、彼女たちにかかわる人々の日常をつづる。監督は本作が長編デビューとなる新鋭・松本佳奈。出演は小林聡美、小泉今日子、加瀬亮ら。
監督は女性。松本佳奈。
ひじょうに女性の視点からとったと思われる優しい映画。
もともと、京都の街は、私も仕事でよく行ったので少しは知っているが、誰もがその美の空気感を認める歴史の深さ、日本の本質的な深さを肌で感じる事の出来る場所であると同時に、いちげんさんには、排他的な街という欠点があると思う。これはコインの両面でもありますが。
聞いた話では、三代続いたお店の大将の話でも、もともとそこに住んでいた京都の人から観れば、まだまだ京都人とは認めてもらえないそうだ。
しかしながら、それはそうと、私も呉服の作家の先生たちにいろいろ料亭なども連れて行ってもらったり、アトリエなども見せてもらって、皆親切な人だとは思う。
その京都に、根無し草のように集まって来た三人の女達。
彼女たちが、豆腐屋、珈琲屋、バーという水に関連する職場で静かに暮らしながら、地元の人との交流をたんたんと描いているのだが、これは賛否両論別れる映画だと思う。
私はたまたま、この映画のレヴューを観ていて、皆の意見はたいしたものだと感心した。
皆同じことを感じている。
癒し系の映画として認めながらも、やはりこれで無料ならともかく、何も起こらない映画に料金を払うのはどうかという意見と、京都が描かれていないという意見。
実はこれは私と同意見。
好きな小泉キョンキョンも出ていて、不思議な空気感はとにかくあふれていると思う。
ただ、気になるのは、天然として沸きでているというよりも、こんなものでいいかという人工の温泉の匂いが時折する。
キョンキョンも東京ソナタの方が良かったなあ。
この映画では、なにやらシナリオや空気のなかに埋没しているような感もした。
だから、ターゲットは、人間関係に少し疲れたお客様は感動すると思います。
ただ、総合芸術として、岡本太郎ではないですが、込み上げてくるような感情や、慟哭や、はらはら感は少し足りないというのが本音だと思いますね。
最近このタイプの映画や、テレビ番組が多すぎるというのも気になる所。
観客の眼はどんどん肥えてきますので、少しひねったほうが良いのかもしれません。
私は実はこの映画を観ていて、この一週間くらいたまたま観ていたイタリア映画がありました。
その映画をどういうわけか思い出したのです。
「魅せられて」です。
このタイプの映画は私は実はこよなく愛していて、たとえば、「魅せられて」「トスカーナの休日」
「食べて、祈って、恋をして」などの映画は、ほんとうに楽しめました。
その中の、「魅せられて」とこの「マザーウォーター」を比較してみます。
まず、この「魅せられて」は、この映画もまた「マザーウォーター」と同じように、母親の自殺した原因を探しにイタリアのトスカーナへ行くまでは同じようなもの。
ただ、はっきり書くと、「魅せられて」は全編どこにもエロティシズムの欠片や匂いが、さりげなく描写されています。 
少女から大人の女へと変容していく主人公が、さまざまなる若者や大人、あるいは死に直面する老人に好かれ、惚れられ、アグレッシィブなアプローチを受けます。
不安と恍惚のなかで、しだいに彼女は心と体をトスカーナの自然とそこにおとこたちに開いていきます。
そのさりげない、自然の中で繰り広げられるたとえば、追いかけっこ、オリーブの農場、うさぎ狩り、自転車からおちた傷と血、ガラスを舐めながら演技指導をする親戚の男性、そんなように、彼女をとりまくありとあらゆるシンボルがセックスと関連を持ち、彼女の成熟を祝福しているようです。
浮気な男に怒りまくる妻、マリファナを月の夜に皆でまわし飲みしながら愛について語り合うトスカーナの家族たち、太った素朴なおばさんたち、無邪気なアリスの子どもたち、そこでは、可愛いウサギはしっかりと捕まえられ、皆のご馳走として晩餐に出されます。
そんなたくしまい自然の本質みたいなものが、画面のどこかここかにも、まぶされています。
自然の本質。
淘汰・厳しさ、弱肉強食、残酷。
そして、それらの要素が、実に自然=光、雨、風、樹々、森、のなかで生き生きとしている。
それと比較すると、この「マザー・ネイチャー」、良く言えば世界の人が驚くようなノン・セックスの香り。悪く言えば、人間が書かれていませんね。
同じように自然を書いているのに・・・・・・・不思議。
まるで、自然がそのまま時をとめて、凍り付いているよう。
まるで、エロティシズムの伏線が少しはありますが、具現化していません。
せっかく、バーの節子さんと若者のキャラはふくらませても良いのではと思ってしまいます。
静寂の世界。
時間のとまった至福の世界。
まるで、恍惚とあの世の果てのような画像。
でも、坂口安吾があるエッセイのなかで、私は自然のなかでは生きないんだと、徹頭徹尾、人間の中で生きるんだと言う意味においては、「魅せられて」の古都、田舎の自然の描き方と人間の関わり合いにおいては、ランクが上かなと思いました。
まあ、最後は好き好きなんでしょうが。
豆腐を売る少女。
山崎しか置かないバーの女。
珈琲屋のママ。
根無し草の三人。
それぞれの理由で京都にやってきて、たぶん、またどこかへ消えていく。
京都の芸妓さんがひとりも出てこない。
たまに、背景にほんの少し出てくる京都の人並みのなか、すこしはずれた、川縁の近くの櫻の下で、もたいまさこ扮するおばあさんや、ポプラと言う赤子が、皆に愛されながら育っていく。
中上健次が模索したような、「物語」、グリム童話や、ユングが探したグノーシス派のような異端の教義、日本の遠野物語、安吾のファルス、それらの対極にあるシネマです。
聞いた話では、けっこう人気のシリーズだと言う。
余談だが、世界最大規模の性意識・実態調査「デュレックス グローバル セックス サーベイ」によると、世界で一番sexの回数が多いのは、ギリシャ人。ラテン系の人々、まあイタリア人もはいるでしょう。日本はなんと世界最低レベル。
昨日の読売新聞でも、ヨーロッパでは、その元気のない日本の特集として、老人国家として日本は果たしてどうなるのか?という記事でした。・・・
つまり、もう日は昇らないが、世界でも一番はやく老人シルバー国家になる日本に対しての注目はそんなことなんですね。^^
この「マザーウォーター」の女性監督には失礼だが、その日本人のセックス観を見事に反映しているのではないでしょうか?
マザー・テレサは「愛の反対は無関心」と言っています。
これは真実ですね。
たとえ、喧嘩であっても、憎しみであっても、嫉妬であれ、感情を持つという中には愛も含まれています。
まったくの愛がない相手には憎しみすら持てませんね。
この映画、その意味では、菩薩の作った映画のようで、「悟り」を開いたような言葉を、バーの女、喫茶の女、おばあさんが、若者にぼそっと言うのですね。
これはいけません。
悟りを開くにはまだまだ、早過ぎ。
もたいまさこが、100歳くらいなら、それらの言葉がちょうど似合うとは思いますが。
街からすこしはずれた庶民の喜怒哀楽を描いた映画と言えば「寅さん」。
では、この「マザートーク」は、喜怒哀楽をせいいっぱいに、押さえつけて、いつも静かに生きることを心がけ、不思議な言葉を連発する根無し草のインテリ知識人たちが、主人公ということなんでしょうか?
わかりません。
映画に詳しい人の意見には、「なにも起こらない映画」だから、そこがいいのだと言う人もいるそうですね。でも、それならば、過去にはそのような「なにも起こらない映画」の系列ってたくさんあるんですよね。^^
それにも少し飽きています。
ただ、映画を観ている間の二時間ちかくの空間と時間はやっぱりいいものですネ。
命の洗濯まではいかずとも、気分転換には最適です。
私の好きな、音楽映画。・・・・・
音楽好きな私には最高のシネマである。
「シャネルとストラビンスキー」
シャネルの生誕を祝ってか、昨年あたりに五本くらいつくられたなかの一作らしい。
たまたま、これをピックアップして、仕事のあとに見たのだが、なかなか素晴らしい映像美。
私のベスト10にはとうてい入らないが、しかしながら、十二分に見応えのある、緊張感があり、何かを刺激してもらえる。
春の祭典のあまりの奇抜さに1913年の観客がついていけず、ブーイングの嵐になるあたりは、非常におもしろい。
ストラヴィンスキーのイメージ、そして、彼の愛人だったシャネルのイメージがひとつ、増えた。
このような不倫ものの映画は何もあえて家族で見る必要はなく、その二人の間に起こった魂のドラマを見れば良いだけの話。
「見ていて辛くなるなど」のコメントもあるが、道徳的にこのような映画を見る程、つまらないものはない。
この世は正しいものと正しくないものしかないという発想自体が、幼稚。
不倫というレッテルつけもまた、単純すぎ、悲しい。
病気で体ではなく心でストラヴィンスキーを支える妻も美しいし、体と金で支えるシャネルがいたからこそ悪魔のような曲も生まれようというもの。
では、シャネルとストラヴィスンキーの間にあったのはなんなのか?
そこらあたりの、複雑で、なんともいえない葛藤と苦悩が美に昇華しているかどうかが、作品の分かれ道。
世間の常識に結局は・・・・?
この世のなかのどう見ても普通とは思えないもの、常識から外れたもの、不条理なもの、それらの素材を作家は自分の魂の美のフィルターをとうして作品をつくりあげる。
オスカー・ワイルドが言うように、道徳的な作品などないのだ。道徳的に書かれているだけのことだ。
その意味ではこの映画は美を扱いながらも道徳的に葛藤する分、まじめな映画なのかもしれない。
そこが逆にこの映画の限界なのかもしれないが。
●楽譜の線を手で刷るシーンが新鮮。
●シャネル社のアーカイブに眠っていた珍しいスカーフカラーのスーツや、服と同じ黒白で統一されたアールデコ調のインテリア等、本物の衣装と克明に再現された美術は、偉人に対する敬意。
●シャネル&ストラヴィンスキー(2009)そして、デブノーの森へ(2004)NOVO/ノボ(2002)に出ているらしい、この女優、独特の美しさ。
●ニジンスキーはこの曲で、19世紀のクラシック・バレエでは考えられなかった、足を内股にし、頭を曲げるという振り付けを行う。20世紀バレエの幕開けであった。よく渋谷の街頭でなされるパフォーマンスを連想させる。
今日の朝、たまたま、読んでいたジュネの本の栞のなかで、三島由紀夫氏が、20世紀最高の野人として、このニジンスキーとジュネをあげていたのがシンクロ二シティ。
・・・・・・・・・・・・・
次なる映画は、マイフェボリット。音楽映画のなかでは、最高峰の傑作。ただ、不思議なことに、ゲオなんかでは、このDVDは置いていない。マニアックすぎるのだろうか。
「四分間のピアニスト」
意外と見ている人は少ないと思うけれど。傑作であると、個人的に思う。
これは彼女ハンナーが弾く、シューマンのピアノ協奏曲・・・・
「四分間のピアニスト」で、ラスト、ハンナーが、試されるはずの古典クラシック。
しかしながら・・・・・・・
私は古典が音楽でも、文学でも、絵画でも大好きなタイプ。
しかしながら、この映画における、古典+αの
発想にはまいった。
ハンナーの個人の魂の発露がここではメイン。
ただ、古典を圧倒的に弾けるという大前提があり、
そこに、プラスがあるので、適当に弾いているというような前衛とはまったく違う。
最後の四分間。
好き嫌いはあるだろうけれども、私は個人的には大好きなシネマ。
古典と前衛についてつくづく考えさせられる。
◎資料
獄中の天才ピアニストと、ピアノ教師の魂のぶつかり合いを描いた映画。ドイツアカデミー賞では8部門でノミネートされた。
クリューガーは実在する人間である。監督クリス・クラウスが脚本執筆の参考にするため気になる人間についての情報を収集していた際に、刑務所でピアノを教えるクリューガーの写真を見つけ、そこから構想を練ったのだという。
ハンナーは1200人のオーディションから選ばれた。ピアノは触ったことがなかったといい、撮影前6ヶ月で特訓した。
あらすじ[編集]
80歳のピアノ教師トラウデ・クリューガーは、女性刑務所内で、殺人罪の判決を受けた21歳のジェニーと出会う。ジェニーは天才ピアニストと騒がれた過去があったが、道を踏み外し、刑務所内でもたびたび暴力を振るう問題児となっていた。しかしジェニーの才能を見たトラウデは、所長に頼み込んでジェニーとの特別レッスンを始めた。
私はこの「音楽映画」ともいうべきジャンルに実に弱い。
涙腺がすぐに弱くなる。・・・・・・・大好きなジャンルだ。
ハンナー・ヘルツシュプルングが、じつに、迫真の演技。ラストのシーンは、今朝も見たけれども、背筋ゾー。素晴らしい。実在する音楽家のクリューガー役のモニカ・ブライプトロイもまた、すごい。
赤ワインを舌なめずりしながら飲むアル中でありながら、ことクラシックに関しては、ハンナー・ヘルツシュプルングを我が娘のように溺愛する。
最後には裏切られるともいえるシーンなのであるが、それが、また彼女の最後の仕草で救われるという仕組み。
ドイツアカデミー賞8つ、というのは、うなづける。
ドイツ映画らしく、複雑に物語のなかに、戦争体験みたいなものも含めて、サブリミナル効果というか、挿入されていて、それがまた、物語の厚みと深みを増す。
「愛を読む人」も個人的なフェボリットなのだが、ここに、ハンナー・ヘルツシュプルングが娘役ででていたらしい。
まったく気がつかなかった。
ハンナー・ヘルツシュプルングが、ラストで弾いていた曲は、これ。シューマン。
前衛的にしなければ、これを弾くはずだったのですね。
Schumann Piano Concerto in A minor, Op.54
音楽大国ドイツの秀作。フェボリット。何回見ても良し。5回試聴。
◎資料
獄中の天才ピアニストと、ピアノ教師の魂のぶつかり合いを描いた映画。ドイツアカデミー賞では8部門でノミネートされた。
クリューガーは実在する人間である。監督クリス・クラウスが脚本執筆の参考にするため気になる人間についての情報を収集していた際に、刑務所でピアノを教えるクリューガーの写真を見つけ、そこから構想を練ったのだという。
ハンナーは1200人のオーディションから選ばれた。ピアノは触ったことがなかったといい、撮影前6ヶ月で特訓した。
ところで、ルドンが、このような言葉を発しています。
音楽は夜の芸術であり、夢の芸術だ。
絵画は太陽の芸術であり、光の芸術だ。 ルドン
まあ、これについてはいろいろな意見がありそうですが。
ただ、ルドンは50歳前後までたしか、黒と白しか色をつかわなかったそうですから。
それが、岡本かの子ではないですが、50歳を過ぎてから一気に色彩画家に変容していきます。
その裏に女の陰が・・・?これはわかりませんが。
ただ、ココ・シャネルとストラヴィンスキーの恋ではありませんが、恋は作品に艶を与えますね。
画家とモデルというのは実に不思議な関係です。
モデルで絵の価値がぐっとあがった作家もいます。
というよりも、モデルが良いと、パッションが増大するんでしょうね。
その意味でも女性という生き物はたいしたものです。
男を振り回し、男に情熱を沸き起こし、男に作品を産ませる。
その分、飽きられて忘れられてしまうのも女性ですが。・・・・・人生は残酷な面もまたありますね。
女性の詩人画家が歌っているのですから・・・・・・・・ほんとうなんでしょう。
マリー・ローランサンです。
鎮 静 剤
マリー・ローランサン
堀口大學 訳
退屈な女より もっと哀れなのは 悲しい女です。
悲しい女より もっと哀れなのは 不幸な女です。
不幸な女より もっと哀れなのは 病気の女です。
病気の女より もっと哀れなのは 捨てられた女です。
捨てられた女より もっと哀れなのは よるべない女です。
よるべない女より もっと哀れなのは 追われた女です。
追われた女より もっと哀れなのは 死んだ女です。
死んだ女より もっと哀れなのは 忘れられた女です。
LE CALMANT
Marie Laurencin
Plus qu'ennuyée Triste.
Plus que triste Malheureuse.
Plus que malheureuse Souffrante.
Plus que souffrante Abandonnée.
Plus qu'abandonnée Seule au monde.
Plus que seule au monde Exilée.
Plus qu'exilée Morte.
Plus que morte Oubliée.
彼の馬。
じつにいいです。
さまざまな影響受けました。
このオレンジ。
光の捉え方が印象派とはまったく違う。
モローとそのあたりが似ているのです。
そのまま目に見えたように描くことからの、
一歩前にコマの進め方がそこにはあります。
映画を見る楽しみ。
それはいろいろあると思うが、私の場合は、最近は物語よりも、歴史背景となるその地域・国・などの描き方、舞台衣装、食事、バックに流れる曲、俳優たちの演技、それらを楽しむ。
たしかに、名監督と名俳優たちが、演じれば、賞を獲るような素晴らしい映画になるのだと思うが、そうでない映画でも、見所はたくさんある。
音楽好きな私にとって、クラシックの古典を描く映画はどれを見ても、非常に、印象深く見てしまう。
物語がいまいち、つまらなくても、かまわない。
その音楽家の生きた時代の空気がすこしでも吸えたらそれで満足と言っても良い。
「 クララ・シューマン」
ブラームスの描き方がいまいちだと思うが、この純愛はなかなか良いと思う。
音楽という楽譜から感じる理想や美や真理へのあこがれみたいなものが、動物としての人の激情を抑えてくれるのだろうと思う。
資料
女性の社会進出が困難であった19世紀のドイツに生きる女音楽家の生き様は現代にも通じるテーマであるが、これをドイツの名匠ヘルマ・サンダース=ブラームスが女性ならではの的確な視点と、ブラームス一族の末裔としての大胆さでもって魅力的に描いている。主演は『マーサの幸せのレシピ』などで脚光を浴びたマルティナ・ゲディック。偉大な作曲家であるロベルト・シューマン、ヨハネス・ブラームスという二人の間で揺れるクララを見事に演じきっている。シューマンの「交響曲第3番 ライン」やブラームスの「ピアノ協奏曲第1番」など、ドラマを魅力的に浮かび上がらせるお馴染みの楽曲群、豪華セットや衣装などの美術にも注目したい。
次なる音楽映画は・・・・・
音楽映画の大傑作は、「アマデウス」、モーツァルトの人生の映画だということはまちがいない。
ただ、ラフマニノフやら、ショパンやら、シューマンやら、の音楽に魂を奪われた音楽家たちの
小品の映画群も、物語はともかく、見ていて、心惹かれるものがある。
伝記で読んだあとに、シューマンと、クララと、ショパンの映画を見る・・・・・
ああ、なんという贅沢であろうかと、ふと、思う。
音楽は文学から、文学は音楽から、その「宝」を獲得しては、自分の芸術の次元を高めようとする。
男は女、女は男から、(同性愛者は同性から)獲得した愛を触媒として、作品が誕生する。
きちんとした普通の人生をおくり、幸福なる家庭から生まれたつ子供たち。
そんな普通の立派な生活がみんなが出来れば、苦労はない。
この世の芸術など存在する意味がなくなる。
苦悩があり、トラウマがあり、いやがおうでもポーの「大渦」のなかに飲み込まれていく人間がいる。
そんな人たちの中に、「海の中に埋もれていく自分を、いや、結果としてその他の多くの人が救われることを可能にする」作品を作る人がいる。
芸術家だと思う。
モジリアニも、シーレも、クリムトも、女性を媒介に作品をたくさん生み出した。
なかには、道徳にどうかという点で、世間から避難された作品もある。
しかしながら。
いつのよにも普遍の道徳があるわけでなし、道徳もまた、時間の流れのなかで変容していくものかもしれない。
要は、魂がふるえるほどの、感激、感銘、涙があってこその人生なのではないだろうか。
この世に生まれて、悩みひとつなく、涙なく楽しく平凡に人生をすごしている、そんな人はいないと思う。
だからこそ、芸術は、人を救う魂の調律剤なのだと思う。
実際にどう生きたかということは
大した問題ではないのです。
大切なのは、
どんな人生を夢見たかということだけ。
なぜって、
夢はその人が死んだ後も
いき続けるのですから。
ココ・シャネル
FIN
イタリア映画 「ひまわり」 フェリーニ「道」 「カザノバ」・・モニカ・ベルッチ を見て
イタリア映画が好きです。
最近では、たしか、昨日あたりに、ソフィア・ローレンが、高松宮殿下記念世界文化賞」をとりましたね。これはイタリア映画好きにとっては、しみじみと感じることがあります。
この「ひまわり」の素晴らしいこと!!!!!!
戦時中にひきさかれた、恋人達が、その後、夫を探し出すと、すでに、別の女性と暮らしている・・・
しかしながら、ソフィアは、子どもには、アントニオとつけて・・・、涙涙。
この音楽がまた、素晴らしく印象的です。
ソフィア・ローレンがまた迫真の演技です。まさに、イタリアの最高の女優だと思います。
彼女いわく・・・
「実は、私は日本に行くと、まるでわが家にいるような気がするんです。それくらい居心地がいいわ。皆、いい人たちだから。私は日本人が大好き。本当にとても素晴らしい人々です。独特の座り方で食事をしたり、お茶をいただいたりするのが好きだし、日本の方たちと言葉を交わすのもたのしいです。そして、日本ではイタリア映画がとても知られていますね。私の映画についても大勢の人が話していました。たとえばマルチェロ・マストロヤンニとロシアで撮った映画など、ずっと泣き通しの女性がいて、本当に素晴らしかったです。(注 おそらくこの「ひまわり」だと思われます。)ですから、今回の受賞のためにまた日本を訪れることができて、とても、とてもうれしいです。日本は、本当にわが家のように感じられる国ですから」
そんわけで、このところ、イタリア映画について考えています。
たとえば、「カザノバ」。
淀川長治さんは、いつも言っていました。
「映画ばかり見ていてはダメ」
「文学や、音楽や、美術をよく勉強すると、映画の素晴らしさが何倍にもなる」
ガザノヴァについての三島由紀夫氏の言葉なんかも、思い出しながら・・・
彼の魂の孤独。悲壮。ぎりぎりの死のところでなんとか間に合った創作。
生涯に数千人もの女性を愛した男だったが、常に魂は孤独。
余白の心の道を歩みながらも、あらたな女性に夢と希望をつなぎながら。・・・・
( 違うジャンルではありますが、フィギア。
フィギアは、音楽が演技とからみあうところがすごく良いです。特に、「道」のような古い映画を、高橋選手が選んで、スケートをしたということに、時代や年令を超えた、映画芸術の力を感じました。)
ところで。この昔の映画ですが。
イタリア映画には、他にも、たくさん傑作がありますが、
「道」「鉄道員」「アポロンの地獄」・・・
どれも素晴らしきすでに古典的名作といわれています。
特に、このやはりフェリーニの「道」
サーカスの男と気がつくと旅をしながら無為の生活をおくっている少女。
少し頭が悪いのかもしれない、そんな無垢の彼女にしだいにひかれていく・・・男。
最後のシーンが素晴らしい。
泣きながら彼女をさがしつづける・・・・・・・・・。
イタリア映画には、かつての日本映画のなかに遺伝子的につながる「あはれ」の美というか、余情の美しさがあります。
そして、進化しつづけるイタリア映画。
そして、この「リメンバー・ミー」。今年の映画ではありませんが、考えさせられる素敵なシネマです。
世界で最高の美女と噂されるモニカがヒロインです。
イタリア。
ユーロ圏では、けっこうな優等生ぶりを、ギリシアやスペインと違って見せてくれています。
イタリアの国民の柔軟性、明るさ、美的センスの良さ、そんなものが国の経済を比較的強くしているのでしょうか。
たしかに、「祈って食べて」の映画でも、プロヴァンスの関連のたくさんの映画でも、
アメリカ人にとっての、イタリアは、人の良い、神経症などのない、おおらかで、自然に恵まれた、美食とおしゃれと本能のままに生きれる国なのかもしれませんね。このヒントは、
「マイ・インターン」にも書きましたが。
最後には、イタリアの現代の作品。「リメンバー・ミー」
◎テーマ 映画「リメンバー・ミー」を見て・こんな感想を持ちました。
(喜怒哀楽 と 冷静 の間に)
喜んだり、怒ったり、悲しんだり、うわーっと喜ぶ・・・つまり、自分の魂の底から発せられる感情そのものに乗っかって、この世に発信する。
当然、日本では、まわりの人からは、うるさがれることが多いと思いますが。
私の知る限り、外国人の方はこの表現が実に激しく、そして、まわりの人達も、あっけらかんとして、それを受け止めてけらけらしていますね。
こんどは自分が受け止めてもらえるからでしょうか。
ブラジルに嫁に行ったかつての友人は、ブラジルの子供たちが自分の子供をまきこんでくれて、非常にあたたかく遊んでくれるということをメールで書いていました。
なにかわかる気がしますね。
観察したり、自分がどう相手に見えるかとか、考えすぎずに、なかに溶け込んでゆくそんな生活習慣。
いいもんです。
でも、日本では、無理でしょうが。
ただ、日本人も、喜怒哀楽を出したくないのではなく、日本人独特の感性、つまり、シャイな他人からの視線を気にしすぎるとか、めだちすぎる連中にたいしての少しいじわるな無視なんかもあるのかもしれません。
心の底では、だれしも、子供の心は持っている筈。
司馬遼太郎氏も、宮崎駿との対談のなかで、「心の中に子供こころが残っていない人はダメだ」ともどこかで書いていましたね。
だから、日本人は、宴会とか、居酒屋では、なんでもかんでも言い合って、そこにいる連中がひとつの輪になるように、気持ちを打ち解け合わせることを一番にするのかもしれません。
イタリア映画の「リメンバーミー」。
自分の嫉妬心をだしまくる男女。喜怒哀楽のなかで、闘っているような映画でしたね。
すごいです。
それがひとつの文化になりえる、ということは。
ただ、日本人には日本人の素晴らしいところがあるはず。
(イタリアのサッカー。
ゴール・キーパーのあの感情の塊のような闘士。
イエローカードまでもらってしまうほどまでに、熱い気持ちをぶつけてきますね。
そんな選手とはまったく対照的に、日本のゴールキーパー、始終冷静に、自分の気持ちをじっと押さえつけたかのような表情。
昔、日本に来たあるjazzピアニスト。
日本人の観客が持つ不思議な沈黙のような感覚、について語っていました。
外国の観客とはまったく違うと言っていましたね。
そして、また、最近は日本の観客がすこしずつ、変化してきたとも。
はたして、それが良いのか悪いかの、わかりませんが。)
私はそんなわけで、あこがれつつも、何かのライブ会場へ行っても、立ち上がって踊ったり、サッカーの応援サポーターのように顔に何かを塗り付けて、ずっと、声を出し続けることはできません。
それで、良いのだと思っております。自然体で、いつでもどこでも。
リメンバー・ミー [DVD]/モニカ・ベルッチ,ファブリッツィオ・ベンティヴォリオ,ラウラ・モランテ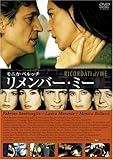
¥3,990
Amazon.co.jp
■イタリア映画ジャーナリスト協会賞3部門受賞!
モニカ・ベルッチは元より、彼女と関係となるカルロ役には、
ヴェネチア国際映画祭にて男優賞を受賞したこともあるファブリッツオ・ベンティヴァリオ、
そしてその妻ジュリア役には、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールに輝いた『息子の部屋』での好演が光ったラウラ・モランテと、
監督を始め、イタリア映画界最高のスタッフとキャストが集結!
現代の家族が抱える問題をそれぞれの愛にまつわる物語を絡ませながら見事に演出!
◎資料「道」
主題曲を始めとする本作の音楽は、フェデリコ・フェリーニ監督作品を数多く手掛けたニーノ・ロータが作曲した。
日本語歌詞が付き、本作が日本で公開された1957年(昭和32年)の第8回NHK紅白歌合戦で中原美紗緒が歌っている(『ジェルソミーナ』として)。
2010年のバンクーバー冬季オリンピックでフィギュアスケート男子シングルの高橋大輔選手がこの曲を採用し、同種目日本人選手初のメダリスト(銅メダル)になった。
谷口ジロー「新しい人生のはじめかた」ややこしい題名の理由「男と女」「ぼくの大切な友達」
食うのは自分で決めること
他人にその自由を奪う権利はない… 孤独のグルメ 谷口ジロー
最近、読んでいるマンガはフランスでも、彼の作品が、映画になっていますが、
谷口ジロー。
個人的には絵は好きですが、原作ものが多いので、その意味では、絵師という感じ。
私の大好きな、上村一夫氏のアシスタントをしてから独立。
漫画家のアシスタントで、ここまで、くる人ってけっこう少ないかも。
最近では、「坊ちゃん」を再読しましたが、坊っちゃん (小学館文庫)/小学館
¥473
Amazon.co.jp
やはり、夏目漱石の作品を読むのは敷居が高いけれど、とりあえず入門編として、マンガでも読んでみようという人向きなんでしょうね。
いつも言うように、原作の小説と、映画がまったくの別物であるように、夏目漱石の作品群と、谷口ジローのマンガはやはり別物。そう考えた方が良さそうです。
しかも。
この作品、マンガの原作者が別にいて、そのマンガ原作者=彼のイマジネートした夏目漱石ということですらか、ややこしいです。
しかし、谷口ジローの、
「遥(はる)かな町へ」は、原作なしのオリジナル。
遥かな町へ (ビッグコミックススペシャル)/小学館
¥1,512
Amazon.co.jp
欧州で評価が高い漫画家の谷口ジロー。代表作「遥(はる)かな町へ」は東京に住む48歳の主人公が昭和30年代の郷里の町にタイムスリップする物語だ。作品の舞台になった鳥取県倉吉市には昭和のレトロな街並みがそのまま残る。
フランス映画の「QUARTIER LOINTAIN 」谷口ジロー
谷口ジロー。恐らく、彼はメビウス(ジャン・アンリ・ガストン・ジロー)からかなり影響を受けているので、ジローはそこからとったのだと思う。


まさに、「フィフスエレメント」の世界。
逆に、メビウス(Moebius)のペンネームでも知られるフランスの漫画家ジャン・ジロー(ジャン・アンリ・ガストン・ジロー)は漫画家やイラストレーターに多大な影響を与えた漫画家ですが、一方で、日本の漫画に感銘を受け影響を受けてもいており、手塚のアニメを見てショックを受け、手塚の作品量の多さに驚愕し、また、自身が影響を与えた宮崎駿氏の大ファンでったようで娘に「風の谷のナウシカ」にちなんでノウシカと名付けている。
メビウスは、私が小さな頃、田舎から電車に乗って、札幌まで出ないと彼の作品は見れなかった。最初見たときは、ああこれはもはやartだなあと感激したことを覚えています。
彼のおかげで、フランスでは、古くから、マンガ=artと認識されていて、日本のマンガが世界的に広がることの、きっかけは、やはり、フランスマンガが大きく媒介したのだと個人的には考えています。
日本の、宮崎駿や、大友克洋、そして、谷口ジローがメビウスのことを尊敬している。
谷口ジローは、ここ最近は、フランスでも人気が出て来て、ルーヴル美術館からも依頼がきたりしてている。千年の翼、百年の夢 豪華版 (ビッグコミックススペシャル)/小学館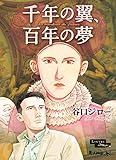
¥2,160
Amazon.co.jp
年齢もたしか、70歳ちかいので、漫画家としては、石森章太郎や手塚治虫ほど多作ではないことが早死にせずに、健康面で、良かったのだろうと思う。(手塚治虫氏は、三日間で三時間くらいしか寝れない生活を、40年間続けていると、どこかで書いていたが、ほんとうだろう。)
メビウスなどのマンガartは、BDと呼ばれている。
BD=バンド・デシネ(Bande Dessinée)とは、フランス語圏のマンガのこと。
しかし、今では、フランスにおける日本のコミックもすべてBDと呼ばれている。
◎資料によると・・・・・・
第二次世界大戦後のBDの流れを3つの世代にわけて分類。
【1】子供向け作品が主流の世代 (1950~1980年代)
・・・『タンタンの冒険』『スマーフ』
【2】ビジュアル面の優れた大人向けの作品の世代 (1970~1990年代)
・・・メビウス、エンキ・ビラル
【3】BD多様化の世代 (1990年代~現在まで)
・・・作家性の強いオルタナ系、娯楽色の強い大手出版社作品
ネットからお借りした資料によると、このように変遷してきている。
しかしながら。
専門誌は、廃刊があいつぎ、これだけで食べて行けるartistは少ないらしい。
やはり、漫画家は大変な仕事。
漫画家になりたくてもなれないから小説家になったという人は、日本にも、限りないほどたくさんいます。
・・・・・・・・・・・・・・
ところで、映画。
ダスティ・ホフマン健在!!!!
新しい人生のはじめかた [2010年2月6日公開]
いまさら、こんな古い映画を楽しむ。
離婚して一人暮らしをしているハーヴェイ・シャインは、一人娘の結婚式のためにロンドンを訪れた。 だが、ハーヴェイは仕事の関係で携帯電話をさわってばかりで、親族の集まりで浮いた存在になってしまう。しかも、娘からバージンロードは義父と歩きたいと言われ、ハーヴェイは落ち込んだ。 そんな中、ハーヴェイは同じく孤独を抱える女性ケイトと出会い、彼女に声をかけた。
ダスティ・ホフマンと言えば、「卒業」。
誰がなんといおうと、私の青春の映画。
中学生の頃に、神戸に妹とふたりで、母方の親戚の家にかなり泊めてもらったのだが、
神戸の風景の美しさ、坂道のロマンが忘れられない。
港。
空の青さ。
細い山に続く坂道。
坂道横に流れる苔むした水源。
六甲山だったか、夜景を今でもはっきり覚えている。
そのオジさんが私の好きだった、「卒業」の「サウンドオブサイレンス」のレコードを
買ってくれて、毎日のように聞いていた。
女がストッキングを足高くあげて履いているシーンのジャケットだったのに、何も驚いたような顔もせずに、笑いながら、一緒に聞いてくれた。
子供さんのいない家だったから、ずいぶん、可愛がってもらった。
今はふたりとも、この世にはもういないが。・・・・
エレーンを追いかけて、教会から花嫁を奪ったあのラストシーンから数十年もたつ。
彼は、今や、離婚経験者であり、
jazzピアニストになる夢が破れ、コンピューターでCMの曲をいやいや作っている。
感受性が人並み以上にあるせいか、彼は、実の娘と会っても、かつての前妻の彼氏を観ていると、どうも引ける。
このあたりのエピソードつくりが実に上手いなぁ。
「最後の初恋」にせよ、この「新しい人生のはじめかた 」にせよ、中年の恋は美しい。そして、笑えるから、また、味がある。
だいたい、若者の恋なんか、私から言わせると、肉欲の愛。
肉欲の愛が終わってくるあたりに、相手に対する「思いやり」が本当にできてくるのではないだろうか?
肉欲の垢尽きて道見える。
このヒロインの女性は実に魅力的だ。
そのけなげ。
不器用。
一所懸命。
落ち込み。
自信のなさ。
先日、男子友だちと、バカ話をしていると、今、「熟女バー」がおおはやりとか。
そりゃあそうだろうと、私は言ってやった。
自分のことがきれいだと思い込んでいて、男子にあれこれ注文ばかりつけているような最近の若い女性に、うんざりしている若者の男性も増えているとか。
比較すれば、けっして、美人ではないけれど、相手に対する思いやりがあり、自分のことを客観的に観れて、自分の顔や体のことを少し貶したり、笑い飛ばしたりするような、大人の女性は、いつの時代でも、男性は惹かれていくのだと思う。
少し大柄で、自分につねに自信が持てないキャラを実に上手く演じていますね。
そして、ヒーローのダスティ・ホフマンのまたまた、余計なことをついつい、言ってしまう、不器用な時代遅れの男をこれまた上手く演じています。
不器用。
へそまがり。
雰囲気にすぐになじめない。
感受性が強過ぎる。
時代の波に乗るのがへたくそ。
いつでも子供の心を持っている。
自分の娘の結婚披露宴には出なきゃダメ、とか言いながら、飛び入り参加したものの、幸福そうに踊っている皆の群れに入れきれずに、ひとり、ホテル会場から去ろうとするシーン。
すると、ダスティ・ホフマンが、ピアノを惹き始める。
サティではないですか。^^
派手なキスも、濃厚なベッドシーンもなし。
それでも、実に、ふたりは、おろおろと、愛の周りを低空飛行している。
その姿は、素晴らしく感動的。
器用に、カッコ良く今はやりの服を着こなし、話題のテーマでまわりを盛り上げて行くような 若者のグループと比較すれば、ダントツに、カッコいいのは実は、こちらのふたり。(あくまでも私の意見です。)
最後はハッピーエンドで終わって良かった。
ここは、「最後の初恋」のアンハッピーエンドになるかとふと思った私の心を軽くしてくれました。
河合隼雄の「中年クライシス」は何回読んでも、素晴らしい第二の青春のスタート本ですが、
これらのシネマもまた、第二の青春のスタートシネマとしては最高ですね。
少なくとも、私の魂にとってですが。
「恋愛小説家」
「恋愛適齢期」
「アバウトシュミット」 以上ジャック・ニコルソン。
「最後の初恋」 ダイアン・レイン
「新しい人生のはじめかた」 ダスティ・ホフマン
「新しい人生のはじめかた」資料A
名優ダスティン・ホフマンとエマ・トンプソンが演じるハーヴェイとケイトは出会ったばかりの他人同士。しかも、初対面の印象は最悪だ。それでも、一旦、言葉を交わせば会話は尽きることなく楽しい時間が過ぎてゆく。これぞ一生に一度あるかないかの運命の出会いか。もちろん、なんの確証もないけれど。これまでに充分過ぎるほど落胆と悔恨を繰り返し、夢よりも諦めを口にしてしまう大人の男女の心の機微を繊細さとユーモアを交えて描いたのは、イギリスの新鋭監督ジョエル・ホプキンス。トンプソンが惚れ込んだ希有な才能の持ち主はオリジナル脚本も手がけ、人生の仕切り直しに遅過ぎることなんてないと希望の光を与えてくれる。
ところで。
名前が良く似ている、こちらの、映画もまずまず好きだが、やはり、ダスティ・ホフマンの方が好きだな。
この「素敵な人生の始め方」という映画は、まさに、モーガン・フリードマンのためにつくられたような、独特のユーモアとペーソスのある映画です。
ある意味、「悲観」の女が、「楽観」の男に、刺激と教育を受けて行く映画です。
ここに記憶のコレクションをしておくて、似たような名前の映画がさらにもう一本。
「最高の人生のつくり方」
「最高の人生の見つけ方」のロブ・ライナー監督が、マイケル・ダグラスとダイアン・キートンという二人の名優を迎え、家族やパートナーといった“成熟した恋愛”をテーマに描いたラブロマンス。笑い合える人生を再び見つけようと心を開いてゆく男の心理を丁寧に描く。
自己中心的で、周囲からはガンコで変わり者と思われている不動産エージェントのオーレンの元へ、疎遠になっていた息子から孫娘を預かってほしいと依頼が来る。孫の存在さえ知らなかったオーレンは、9歳の少女に対して戸惑いを隠せず、隣人の女性リアに助けを求める。こうして奇妙な3人での生活が始まることになるのだが…。
洋画の現代そのままで良いものを、なにやらヒットさせたいがために、似たような名前をつけて、二匹目のドジョウを狙っていると思われますが、見ている方は、題名が似ているのですぐに忘れてしまいます。
そこで、ここに一気に、まとめて、自分の映画記憶コレクションをがっちりと強固にしたいと考えています。
「最高の人生の見つけ方」
余命6ヶ月を宣告された二人の男(ジャック・ニコルソン、モーガン・フリーマン)が、死ぬ前にやり残したことを実現するために二人で冒険に出るハートフル・ストーリー。
アメリカでは2007年12月25日に先行上映、2008年1月11日に拡大公開され、週末の全米興行収入で1位を記録。日本では2008年5月10日に公開され、初登場2位を記録した。
原題の「The Bucket List」は、“Kick the bucket”のイディオムが元になっている
これは、かなり傑作に入るのではないでしょうか。
個人的な意見ですが、ダスティ・ホフマンもそうですが、 の出ている映画は、びしっと画面がきまります。そこに、モーガン・フリードマンが加わるわけですから。脚本も良いですね。
そして、さらに。
こんなまた似た題名の映画があります。題名だけだと、混乱してきます。
「最高の人生のはじめ方」
著名な作家であるモンテ・ワイルドホーン(モーガン・フリーマン)は酒に溺れ、創作意欲を失っていた。あるとき彼が湖畔にあるキャビンを訪れたところ、隣家にやってきたシングルマザー(ヴァージニア・マドセン)とその娘達と知り合う。
「最強のふたり」
2011年10月23日、第24回東京国際映画祭のコンペティション部門にて上映され、最高賞である東京サクラグランプリを受賞し、主演の2人も最優秀男優賞を受賞した。また、第37回セザール賞で作品・監督・主演男優・助演女優・撮影・脚本・編集・音響賞にノミネートされ、オマール・シーが主演男優賞を受賞した。
フランスでの歴代観客動員数で3位(フランス映画のみの歴代観客動員数では2位)となる大ヒット作となった。日本でも興行収入が16億円を超え、日本で公開されたフランス語映画の中で歴代1位のヒット作となった。
題名を現代で調べますと、
「新しい人生のはじめかた」= Last Chance Harvey
「素敵な人生のはじめかた」=10 Items or Less
「最高の人生のつくり方」=AND SO IT GOES
「最高の人生の見つけ方」= The Bucket List
「最高の人生のはじめ方」=The Magic of Belle Isle
「最強のふたり」=Intouchables フランス映画
ここまで、書いてきて、わかったのは、このよく似た名前の題名、要は、同じ監督の作品なのでした。
みんな知っているのでしょうが、私は今迄まったく知りませんでした。
ロブ・ライナー監督です。
作品のつくられた年をここに書いて、その順番どうりに、並べると、
A「最高の人生の見つけ方」= The Bucket Listが、2007年。
B「最高の人生のはじめ方」=The Magic of Belle Isle が、2012年
C「最高の人生のつくり方」=AND SO IT GOES が、 2014年
ほんとうは、このことを知っていたら、この順番に、映画を見れば良いのでしょうが、おもしろそうな映画をほとんど、直感的に、匂いでかぎわけながら、乱読いや乱視聴している、私にとっては、そんなことも考えず、ただ、ややこしい、題名にしているなぁと、不満だったのですが、
同じ監督とわかれば、納得もできますし、記憶しやすくなります。
この監督。
けっこう名作つくっております。あくまで、個人的な好みですが。
「恋人たちの予感」
(こいびとたちのよかん、原題:When Harry Met Sally...)は、1989年に公開されたアメリカ映画。
ノーラ・エフロン脚本、ロブ・ライナー監督。ニューヨークを舞台にした恋愛映画。本作で主人公の男女が食事をするカッツ・デリカテッセンは、日本のガイドブックで掲載しない例外がない程の名所となった。
日本ではみゆき座の上映300本記念作品として話題となり、約2か月半のロングラン・ヒットとなった。
2002年に木村佳乃主演で舞台化された。
・・・・・・・・・・・・・・
メグ・ライアン。
素敵な女優さんだと思います。
大学在学中にエージェントに見いだされ、映画『ベストフレンズ』(1981年公開)でデビュー。1982年から1984年まで連続ドラマ『As the World Turns』に出演。
1986年公開の『トップガン』に出演して注目を浴びる。翌年公開の『インナースペース』で人気を獲得して、同年公開の『プロミストランド/青春の絆』でインディペンデント・スピリット賞主演女優賞にノミネートされた。
1989年公開のビリー・クリスタルと共演した『恋人たちの予感』の大ヒットによって人気を決定付ける。それ以降も、トム・ハンクスとの共演で『めぐり逢えたら』(1993)や『ユー・ガット・メール』(1998)などのロマンティック・コメディに主演しヒットを飛ばし、「ロマンティック・コメディの女王」と呼ばれ人気を博す。また、この三作品ではゴールデングローブ賞 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門)にノミネートされた。 一方、作品選びの悪さが有名で、これまで『ゴースト/ニューヨークの幻』、『プリティ・ウーマン』、『誘う女』、『羊たちの沈黙』などのオファーを断っている。
しかし、後述する不倫騒動や演技派への転向を図って出演した『イン・ザ・カット』の失敗もあってか、近年は出演作にも恵まれず低迷している。低迷の理由には、他に整形手術を受けて顔が大きく変わったためとも指摘され、「整形でキャリアが終わってしまった」とも言われている。
このロマンティック・コメディの三部作。
誰しもが、見ている有名な映画ばかりですが、ここにコレクションしておいて、記憶の強固をはかります。
「ユーガッタメール」個人的にはこれが一番の好みです。
脚本が良いのか、何回見ても、感動で胸をうたれます。
特に、ラストシーン。
「ユーガッタメール」
「めぐりあえたら」
そして、彼女が、運が悪いのかどうかはともかく、オファーを断った映画もコレクションしておきます。
私は、目が悪いのと、年齢のせいか、外国人女優では、ジュリア・ロバーツと、アン・ハサウェイなんかは、たまに、混同してしまいます。
もちろん、別々に見ればすぐにああ、っとわかるのですが、普段は、思い起こす時に、よく混同してしまいますし、名前がすぐにでてきません。
こまったものです。・・・・・・
「誘う女」
『誘う女』 (To Die For) は、1995年製作のアメリカ映画である。ガス・ヴァン・サント監督。サスペンススリラー。1990年に実際に起きた事件を題材にした、ジョイス・メイナード(英語版)の1992年発表の小説『誘惑』 (To Die For) の映画化作品である。
主演のニコール・キッドマンは、本作でゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した。
「ゴースト」
ロマンス、コメディ、ファンタジー、ホラーといったいくつかのジャンルに含まれる。愛する人が幽霊となって目の前に現れるというアイデアは、この映画のメガヒットで多くの亜流映画・小説を生む。
ウーピー・ゴールドバーグがアカデミー助演女優賞を受賞し、作品自体もアカデミー作品賞、編集賞、作曲賞にノミネートされたが、『ダンス・ウィズ・ウルブズ』という強豪の存在のため他はアカデミー脚本賞(ブルース・ジョエル・ルービン)を受賞するにとどまった。
主題歌は、ライチャス・ブラザーズの「アンチェインド・メロディ」(もともとは、1955年の映画『Unchained』(日本未公開)の主題歌だった。作曲はアレックス・ノース)。
そして、メグ・ライアンが断った最後の映画。
「羊たちの沈黙」
『羊たちの沈黙』(ひつじたちのちんもく、The Silence of the Lambs)は、1991年公開のアメリカ映画。監督はジョナサン・デミ。原作はトマス・ハリスの同名小説。主演はジョディ・フォスター、アンソニー・ホプキンス。
第64回アカデミー賞で主要5部門を受賞。アカデミー賞の主要5部門すべてを独占したのは『或る夜の出来事』、『カッコーの巣の上で』に次いで3作目である。
結論ですが、これらの映画は、すべて大ヒットした要因は、やはり、ジュリア・ロバーツであり、ジュディ・フォスターであり、ニコール・キッドマンだったから、名作足り得るのではないでしょうか。
すべては運命のなせる業。
運命おそるべし。
不思議な事だが、私が若い頃は、映画はほとんど悲劇的なものが非常に多かった。
ロミオ&ジュリエット。明日に向かって撃て。ボニー&クライド。・・・
アランドロンの映画なんかもそうだった。冒険者たち。
心中天の網島、肉弾、ヤクザもののすべて。
比率的には、ハッピーエンドは、二割程度だったかもしれない。
涙とともに銀幕は降りたものだった。
映画館を出ると、外の空気が実に新鮮で、空の青さが目に沁みた。
jazz喫茶にそれから入って、コルトレーンなんかを聞きながら、さきほどのシネマの
中身を何回も何回も、コルトレーンのソロのように、反芻したものだった。
「ニーチェは、ギリシア人がりっぱな悲劇を書いたということこそ、ギリシア人が厭世家ではなかったというはっきりした証拠だといいます。ちょっと聞くと、反語のようにも聞こえますが、それは、悲劇と厭世というふたつの概念を知らず知らずのうちに類縁のものと私たちが思っているからでありましょう。
おそらく、ニーチェは、そのことを頭において強く主張する、悲劇は、人生肯定の最高の形式だと。人間になにかが足りないから悲劇は起こるのではない、何かがありすぎるから悲劇がおこるのだ。否定や、逃避を好むものは悲劇人足りえない。何もかも進んで引き受ける生活が悲劇的なのである。不幸だとか、災いだとか、死だとか、およそ人生における疑わしいもの、嫌悪すべきものをことごとく、無条件で肯定する精神を悲劇的精神という。こういう精神のなす肯定はけっして無知から来るのではない。そういう悲劇的智慧を掴むには勇気を要する。勇気は生命の過剰を要する。幸福を求めるがために不幸を避ける、善に達せんとして悪を恐れる、
さような生活態度を理想主義というデカダンスの始まりとして軽蔑するには、不幸や悪はおろか、破壊さへ肯定する生命の充実を要する。
そういうディオニソス的生命肯定が、悲劇詩人の心理に通じる橋である、とニーチェは言いきるのであります。ニーチェの激しい気性は、アリストテレスのカタルシスの思想に飽き足らなかった。」
この、悲劇は、人生肯定の最高の形式だと。人間になにかが足りないから悲劇は起こるのではない、何かがありすぎるから悲劇がおこるのだ。という、ニーチェの言葉が頭のなかをすうーっと、流れて行きました。
珈琲の味の苦いこと、苦いこと。
この世の中の、不条理な殺人事件。
いや、それだけではない、ありとあらゆる不条理な出来事。
はたして、神はいるのか? いないのか?
確か、聖書の中で、神を敬うこと大いなるとある人物。名前は覚えていませんが・・・・・・。
神様は、その信心ぶりを試そうとします。
彼の愛するものを殺してしまうわけですね。
そこで、彼の反応を見ようと・・・・・一神教の神様。
遠藤周作の本の中でも、日本人に西洋の文学が果たして理解できるのか? という投げかけがありました。
小林秀雄も、また、聖書がわからないと西洋文学は理解できないと書いています。
本人も、晩年に日本の古典ばかり読んでいるのもよく納得できます。
生まれた時から、キリスト教という信仰が生活の中のありとあらゆるところに、深く深く浸透している世界。西洋。
無意識からはては、理論構築がまるで天にそびえるゴシック建築のごとく、理論武装されている神学の意識の世界。
最近のテロ事件もまた、そのあたりを理解しないと、あれらの事件はまったく理解できないと思います。
「アマデウス」には、サリエリでしたか、神が女たらしのモーツァルトを選んで信心深い自分をなぜ選んでくれなかったかと、怒って、キリストの像を火の中にくべるシーンがありました。
まあ、この映画は、哲学をテーマにした映画でもありませんし、娯楽作品として作られた筈。
しかしながら。
かつて、貴族の肖像画を描かされていた宮廷画家達が、しだいにただ似せてキレイに描く絵に飽きて、自分の色彩とトーンの美を追求しはじめたように、この映画も、けっこう良い意味で、我がままにつくられてる。
・・・・・・・・・・・・・・・
ところで、次の映画。
仕事に疲れると、ふとレコード棚からひっぱりだすレコード群。
朝から聞く曲ではないなぁと思ったが、かけると、昔の記憶が次から次へと。
「ヨーロッパ映画の魅惑」というレコード。
男と女がいるからこそ、この世は楽しい。
クロード・ルルーシュ監督の一番油の乗っていた頃の作品二作。
しかも、みずから作曲・シナリオ。
無名の作家がいちやく世界にはばたくきっかけとなった作。「男と女」
スタントマンの夫を事故で亡くしたスクリプト・ガールのアンヌは、娘を寄宿学校に預け、パリで一人暮らしをしていた。ある日、娘に会うために寄宿学校に行った帰り、パリ行きの列車を逃してしまう。そんなアンヌにジャン・ルイという男性が車で送ると申し出た。ジャン・ルイも同じ寄宿学校に息子を預けており、また、妻を自殺で亡くしていた。
アヌーク・エメと、ジャン・ルイ・トランティニィアン。
バツ1同士の大人の渋い愛情が実に軽いタッチでお洒落に描かれていました。
仏蘭西人は昼まっぱからワインを飲み、恋人同士がボルノ映画館で手を握り合いながらいちゃつくお国柄。
日本とは相性が良く中国とは相性はめちゃくちゃ悪い。
恋沙汰の事件はそれだけで刑が軽くなるとか。
恋の達人ぞろいのフランス。日本は不倫は文化だとほんとうのことを言ったばかりにふくろだたきにあった俳優もいますが、フランス人なら笑ってそのまますますでしょう。
揚げ足ばかりとる日本人とは違い、人生を楽しむコツは仏蘭西人ならではかな?
「パリのめぐりあい」も、不倫をキャンディス・バーゲンと楽しむ主人公が、最後はやはり不倫相手とはうまくいかなくなり、妻のもとへも帰れないということで、ひとり孤独になるのですが、最後のラストシーンで、妻がニコリと待っているシーン。
こんな妻ばっかりならば世の中の男性すべてが甘えてしまって大変になることは眼に見えていますが、めったにいない妻をやはりクロード・ルルーシュ監督はうまく描いていますね。
アニー・ジラルド素晴らしい。キャンでス・バーゲンの美しさ。
いつも、そうなんですが、「男と女」は、「パリのめぐりあい」といつも混同してしまいます。
フランスのTV界でもトップクラスのニュース・リポーター、ロベール・コロンブ(イヴ・モンタン)は、妻のカトリーヌ(アニー・ジラルド)との間が、決して不満だらけというわけではないが、単調な日常生活の繰返しに耐えられず、時には恋のアバンチュールを楽しんでいた。そんなある日、彼はキャンディス(キャンディス・バーゲン)というファッション・モデルをしながらソルボンヌ大学に通う娘と出会い、そのみずみずしい知性的美しさに強くひかれた。TV局からの電話で、アフリカへ取材に出かけることになったロベールはキャンディスに同行を誘うと彼女はすぐに同意した。ケニア砂漠での二週間は、二人の間をさらに深く結びつけ、野生の猛獣撮影が成功した夜、二人は初めてベッドを共にした。パリに帰ったロベールは、カトリーヌの発案で、アムステルダムへ休暇旅行に発った。久しぶりで夫婦は語りあい、愛しあった。そしてある日、ロベールはアムステルダムまで彼を追ってきたキャンディスの姿を見た。彼は二日だけ仕事でパリに帰ると妻に告げてキャンディスの待つホテルに向った。しかし、帰ってきたロベールを見て、カトリーヌはすべてを察し、パリへ帰る途中のブラッセル駅で一人降りてしまった。パリへ帰ったロベールは、キャンディスと一緒の生活をはじめた。しかし、その生活はなぜか空ろで虚しかった。ベトナムへの取材旅行をきっかけにロベールはキャンディスとの別離を決意し、その旨を伝え出発した。日が流れた。ベトコンの捕虜になり解放されたロベールは、カトリーヌを探してアルプスの近くの町へ走った。カトリーヌはロベールを友達として暖かく迎えてはくれたが、その時ロベールは、彼女はすでに自分の妻としては遠い人であることに気づき、静かにわかれを告げて外に出た。だが、雪におおわれた車のフロント・ガラスをはらい落した時、彼は再びその中に妻の笑顔をみたのだった。...
もうひとつ、・・・・・・この映画を思い出していたら、ふと、北海道出身の渡辺淳一氏を連想いたしました。
彼はエロ作家とか、陰口をたたかれることも多いようですが、私は好きです。
彼の「資料をもとにした時代劇やら歴史物は簡単に書ける。一番むずかしいし、誰もが書きたがらないのは恋愛小説だ」と豪語しているところが好きですね。
「化身」はそのなかでも特に傑作でしょうか。
良くも悪くも「男と女」が描かれているし、男の「教育好き」が描かれている。
かつて三島由紀夫氏は、「エロティシズムの本質は教育だ」と書きましたが、男は好きな女にいろいろ教えるのが大好き。そして、女は男に教えられることが大好きと私は見ています。
そして、化身の女主人公が最後の最後に、見事に成長して、自分を教育してくれた男性を棄てるわけですが、「パリのめぐりあい」とは違って、妻も彼女も、完璧に彼を見捨てます。
その彼が最後に孤独になってパタリと寝床かどこかに倒れて放心?するシーン、しみじみしていて、いいですねえ。
育て上げ、教育し、美しくそだてあげた自分の愛人に最後は棄てられる。
しかしながら、後悔はしていない。
やることはやったし、自分はそれしかできないのだというプライドみたいなものもあるのかも。
現実はいつも、厳しく、甘くなく、これらの映画や小説のような男や女はなかなかいないでしょうから、だからこそ、映画や小説の中では、彼らの存在が優美に私たちに語りかけてくれるのかもしれません。
これらの映画に少しでも近い「恋の破片」みたいなものを心の片隅の宝石箱に隠して、前に突き進んで行きたいものです。
ところで、このあたりで、気分をかえて、音楽。・・・・・・・
この曲。
この女性歌手。
その意味では、まさに女性の良きところだしてます。
不思議感。
退廃感。
ラナ・デル・レイ 欧米で大ヒット 耽美で退廃的60年代路線
耽美で退廃的といえば、私の得意分野。
たしかに、不思議な雰囲気。
時代は廻る。
次なる最後の映画は。
喜劇。
私の尊敬するルコント監督。素晴らしいできばえ。
今頃、2006年の作品を見て、感動している自分が笑える。
「ぼくの大切なともだち」
当時は、仕事が忙しすぎて、シネマをゆっくり見る時間がとれなかった。・・・
なんでも、ひとつのことしか見えなくなる自分の性格。これだけは今でも、過去でも、そしておそらく未来でも、しょうがないことだと思う。
◎資料から
美術商のフランソワ(ダニエル・オートゥイユ)は、自分の誕生日を祝う夕食会の席で、葬儀の参列者が7人しかいなかった話をすると、友達がいないからフランソワの葬式には誰も来ないと言われてしまう。そこで自分にも親友ぐらいいると言い張ったため、フランソワは十日以内に親友を連れてこれるかどうか、共同経営者のカトリーヌ(ジュリー・ガイエ)と賭けをすることになってしまう……
◎小さな頃から、クイズに熱中する変人。
幸福な王子。。。のひとこと。小さな狐の話がキー。
物語もありふれているし、マンガ的なところもあるけれども、それはそれで良い。
これ
また、ひとつのことに熱中するとその他のことが見えなくなる、私みたいなタイプの男ふたりの友情物語、というところが好みの映画。
もともと、他人に接する態度といっても、悪魔のように冷たい人や、まったく愛のない人はそういないので、少しでも、心を変容する気持ちさへあれば、・・・・・
感謝の気持ちさへあれば。
それに、自分の葬式に何人来てくれるかとか、そんなことがその人の価値をきめるものではないだろうと思うが、どうなんだろうか。
ルコトンの作品は、やはり、たとえば、
この「イヴォンヌの香り」なんかはやはり彼の最高傑作ですが、この「ぼくの大切な友達」もまた、
味わい深いコメディ作品だと思います。
◎資料
監督 - パトリス・ルコント
製作 - オリヴィエ・デルボス、マルク・ミソニエ
原案 - オリヴィエ・ダザ
脚本 - パトリス・ルコント、ジェローム・トネール
撮影 - ジャン=マリー・ドルージュ
美術 - イヴァン・モシオン
編集 - ジョエル・アッシュ
音楽 - グザヴィエ・ドゥメルリアック
衣装 - アニー・ペリエ
キャスト
ダニエル・オートゥイユ - フランソワ・コスト(美術商)
ダニー・ブーン - ブリュノ・ブーレー(タクシー運転手)
ジュリー・ガイエ - カトリーヌ(フランソワの共同経営者)
ジュリー・デュラン - ルイーズ・コスト(フランソワの娘)
ジャック・マトゥー - ブリュノの父
マリー・ピレ - ブリュノの母
エリザベート・ブールジーヌ - ジュリア
アンリ・ガルサン - エティエン・ドゥラモット(テレビ番組プロデューサー)
ジャック・スピエセル - レテリエ
フィリップ・デュ・ジャネラン - リュック
◎資料
ダニエル・オートゥイユ(オトゥイユ)(Daniel Auteuil 発音例, 1950年1月24日 - )は、アルジェリア・アルジェ出身のフランスを代表する男優。
来歴[編集]
父アンリはアヴィニョンを中心に活動するオペレッタ/オペラのバリトン歌手。母は元合唱団員。
6歳で初舞台を踏み、その後もアヴィニョンの舞台に立つ。パリで演技を学び、舞台ではコメディ、ミュージカル、古典と幅広く出演。映画界からも注目され『ザ・カンニング [IQ=0] 』の大ヒットで人気を獲得。連作『愛と宿命の泉』でシリアス演技に挑戦し、セザール賞を受賞。以後、演技派としても認知される。
1996年の『八日目』ではカンヌ国際映画祭男優賞を、1993年の『愛を弾く女』と2005年の『隠された記憶』でヨーロッパ映画賞の男優賞を受賞している。
プライベート[編集]
元妻エマニュエル・ベアールとの間に娘が一人いる。
「最悪なのは失敗することじゃない。
それは自分が傷つかないよう
無難に仕事をこなすこと。
それは、罪。」 ダスティ・ホフマン
FIN
PR: 全国に53万箇所!?土砂災害キケン箇所-政府広報
クラシックを聴く男性はなにか嫌い
kate liu最近よく聴くショパン。
「クラシックを聴く男性はなにか嫌い」と、22歳の頃に、おさななじみの女性から言われたことがある。
1953年頃ではなかったろうか?
当時は、アメリカ文化がどっと入ってきていて、ロックや洋楽が主流だったし、北海道人は、気取ったように感じることはあまり好きではなかったのかもしれない。
私も、当時は、まわりの空気でロックやブルースや洋楽ばかりきいていたと思う。
しかしながら。
シネマ好きの私としては、たとえば、キューブリックの「2001年宇宙の旅」を見たりすると、さまざまなるクラシックがバックに流れていて、いいなと思ったし、「時計仕掛け」にいたっては、まさにベートーベンが映画とは密接な関係があり、インパクトがあった。
岩見沢市の「志乃」という、マル・ウォルドロンを確か呼んだjazz喫茶があったけれど、そこが、つぶれる少しまえに、これも記憶がはっきりしないけれど、「クラシック専門」の店になって、よく、雪の降る日に、バッハを聴いたものだった。30代の頃だった。
そして、「アマデウス」。
モーツァルトがいつも耳に鳴る日が続いた。
jazzでも、キースのような、ピアノ演奏家の曲ばかり聴いていたのが、40代、50代。
そして、退職後、三年間は、jazzばかり聴いていた。植草甚一の真似をして、一日に、6時間は聴いていただろう・・・これまで集めたjazzのレコードもほとんどききかえした。
そこで、ユーチューブに出会う。
そこは短くはあるけれども、宝の宝庫。
聴きたくても聴けなかった名演奏が即聴ける。
そして、3年前あたりから、jazzと平行して、クラシックを集中して聴くようになる。
やはり、jazzと同じように、一日に、三時間は聴いていると思う。
それが、3年間。
クラシックも最初は、バッハのピアノ曲。
モーツアルトのピアノ曲。
やはり私は基本、ピアノが好きなのだ。
そして、アダージョ。聴きやすく、また、崇高。
初心者向けの音楽とはとても思えない。シンプルこそ、最高だ。
奥が深い・・・・・・・
音楽は心の調律師。
これから死ぬまでずっと、お世話になると思う。感謝。
日々の創作



〈アートに対する想い〉
わたしたちの生の根源でもある「性」というものを日々考える。
そこから生まれる「エロティシズム」を最大のテーマとして、
宇宙のsomething greatが描いた、その「一筆」でもある、「わたしたちの
心の宇宙」を描きだしたいと思っています。フロイトの無意識・ユングの集合無意識など、
海上の氷山の一角ではなくその下に広大に広がる無意識を表現する。
リアルズムの伝統を大事にしつつ、そこに現代の日本の「新しい何か」を浮かび上がらせたいと
思います。
まずは油絵という遠近の基本からスタートし、いずれは、フレスコ画や、
日本画にもチャレンジしたいと思っております。
♬新作・最近の「創作」
night in Mont Saint-Michel (犬と少女)
「cosmic dance」 油彩 F100号 新世紀展入選作品
「起源への道」 F100号 新世紀展入選作品
●
最新作品「アイドルを探せ」
Ce soir, je serai la plus belle
pour aller danser, danser
pour mieux evincer toutes celles
que tu as aimees, aimees
★<アンダンテカンタービレ レンピッカへのオマージュ>


















<「こころのサプリ」主人「今日のおすすめ音楽」>
★キース・ジャレット関連の記事すべて 音楽の謎
<「こころのサプリ」主人「今日のおすすめ本」>
★河合隼雄関連の記事すべて 心の謎
<「こころのサプリ」主人「今日のおすすめ絵画」>
★パウル・クレー 関連の記事すぺて 絵の謎
<「こころのサプリ」主人「今日のおすすめシネマ」>
★童話民謡記事集めました インデックス 童話
★今日の箴言 2009.8.2~
★<創作>
私の油絵創作集 「起源への道 エロスの羽」
私のイラスト集 「戦士の休息に」
レモンイエロオの財布
天国からの手紙
★友人建築家T氏 武部建設 文化を語る 川俣正などなど
キノベス2008 ★ベストセラーが苦手な人のための、紀伊国屋の書店員がすすめるベスト 参考になります★
junkdo book web
紀伊国屋書店 book web
三省堂書店
<「こころのサプリ」主人「チェックランキング1 本>
新刊動向チェック
<「こころのサプリ」主人「チェックランキング2 ジャズ >
HMV jazz トップランキング20
<「こころのサプリ」主人「チェックランキング3 クラシック >
HMV クラシック ランキング
<「こころのサプリ」主人「チェックランキング4 ラテン >
HMV ラテン ランキング25
<「こころのサプリ」主人「チェックランキング5 映画 >
映画ランキング 国内興行トップ10
<「こころのサプリ」主人「チェックランキング6 DVD売り上げ >
映画DVD売り上げランキング20
「グノシェンヌ2」嫁ぐ
シリーズ グノシェンヌ 2
アートコンプレックス・創作者表現展作品紹介 SIZINGAKAさん解説
ドラード画廊 小さな絵の展覧会 2009年版 「月嫁」紹介
ユーチューブ huruhon channel
私はこのブログの双方向性やスピードの早いレスポンスに、魅力と未来の可能性を感じております。
人間の脳の可能性を信じて、この地球の現代の難問を乗り越えて行くためのお手伝いができたらいいなと思います。
花にみとれて五分間
庶民とテロ ミラ・ジョヴォヴィッチ ひとりで戦う勇気 「サバイバー」
テロ行為とは、文明が未熟であるから起こるのではない。
選挙による落選という手段を奪われているから、
やむをえずテロに走るというのでもない。
権力が一人に集中しており、
その一人を殺せば政治が変わると思えるから起こるのである。塩野七生 『ローマ人の物語18 悪名高き皇帝たち
・・・・・・・・・・・
9.11以来53人もの、テロリストをニューヨーク警察並びに秘密部隊が逮捕したということはおまりおおらかにはされていない。
一般のひとびとは、そのあたりはよくよく考えた方が良いと思う。
今や、ひとりでは自分の家庭だけでさへ、守ることも至難の技。
そのなかで、なんとか、必死に、生き抜いていこうと思う。
伊勢志摩サミットも、誰も褒めないが、あの成功の影には警察やら自衛隊やらその他さまざまなる
秘密部隊の活躍があったからこその、隙間のなさが、テロリストを呼び寄せなかったのだと個人的には思う。
そんな、テロリストの巧妙なる仕掛けに、勇気ある女性がひとりで、戦いを挑んでゆくという物語というので、DVDを観てみたが、ベストには入らないが、いつも私が書いているように、淀川さんいわく、「映画で人生を勉強」できるわけだ。
それに、物語とはまったく関係のない、ニューヨークの風景やら、飛行場の雰囲気、ひとびとの喜ぶ大晦日の雰囲気、・・・人によっては、英語の勉強にもなるということで、映画は素晴しい。
「 サバイバー」
ロンドンのアメリカ大使館駐在の外交官ケイトはある日、伝説のテロリスト・時計屋による爆弾テロのターゲットになってしまう。
ケイトはどうにか難を逃れたものの、爆弾テロ犯の濡れ衣を着せられてしまい、時計屋のみならず、アメリカ・イギリス双方の当局からも追われる羽目になる。
そんな中、時計屋が大晦日のニューヨーク・タイムズスクエアで次のテロを計画していることを知ったケイトは、人々の命を救うべく、また自らの汚名を注ぐべく、たった一人で立ち向かう。
配役は、
ケイト・アボット - ミラ・ジョヴォヴィッチ(本田貴子)
時計屋 - ピアース・ブロスナン(田中秀幸)
サム・パーカー - ディラン・マクダーモット(堀内賢雄)
クレイン駐英大使 - アンジェラ・バセット(高島雅羅)
ビル - ロバート・フォスター(樋浦勉)
アンダーソン警部 - ジェームズ・ダーシー(森川智之)
サリー - フランシス・デ・ラ・トゥーア
ということで、
アボット役の、ミラ・ジョヴォヴィッチくらいしか、私は知らないが、こうやって、すこしずつ覚えて行けば、ある日、ああ、あの映画の脇役に出ていたなあと、ピンとくるかも。
有名なる話しとしては、ヨヴォヴィッチと読んでもらいたいと彼女は、いつも嘆願しているらしい。 


最近のテロについては、あまりにも複雑なので、少し調べてみました。
調べてみたところで、私みたいな人間になにがわかるわけでもないのですが、
気になります。
◎資料
「terrorism テロリズム」という用語が使われるようになったのはフランス革命において行われた九月虐殺がきっかけであった。この虐殺事件では革命派が反革命派1万6千人を殺害する恐怖政治を行った[4]。
テロリズムは、左翼および右翼政党、革命家、ナショナリズム集団、宗教集団、そして政府側など、多岐に渡る政治的な組織が彼らの目的を達成するために実施している[5]。
「テロリズム」の語の正確な定義には多数の困難が伴っており、100を超える多数の定義が存在している[6][7]。
オックスフォード英語辞典(OED)はきわめて古典的な用法を真っ先に挙げている[8]。だがこのOEDの説明では現代的な用法を理解するにはもの足りないと感じられることになる[8]。 「テロリズム」という語の現代的な用法はpolitical 政治的なものである[8]。同一の集団が支持者からは「自由の戦士」、敵対者からは「テロリスト」と呼ばれる場合もある。テロリズムの概念は、しばしば国家の権威者やその支持者が、政治的あるいはその他の敵対者を非合法化し[9]、更に国家が敵対者への武力行使を合法化するためにも使用されている[9][10]。この語の用法には歴史的な議論があり、例えばネルソン・マンデラやホセ・ムヒカ、マハトマ・ガンディーなどもかつては「テロリスト」と呼ばれていたのである[11]。
13本が制定されているテロ防止関連諸条約の点からは、①航空機内の犯罪②航空機ハイジャック③民間航空機の安全に対する不法行為④国家代表等に対する犯罪行為⑤人質を取る行為⑥国際輸送中の核物質の窃盗⑦空港における不法な暴力行為⑧海洋航行の安全に対する不法行為⑨大陸棚プラットフォームの安全に対する不法行為⑩爆発物を公共の場所に設置する行為⑪放射性物質や爆発物装置を所持し、使用する行為、と定義づけられている[12][13]。
アメリカ国務省が発表した報告書『世界におけるテロリズムの現状』(Partterns of Global Terrorizm)によれば、世界のテロリズムによる犠牲者の数は、1998年から2003年にかけて毎年、1000-7000人程度であるとされる[14]。一方で対テロ戦争による犠牲者の数も多く、例えばイラク戦争の場合、アメリカの科学者チームによる集計で10万人の民間人が死亡したとされる[14]
語源
英語で「テロリズム (terrorism)」の語が初期に使用された一例。タイムズ1795年1月30日付け紙面より。「我々の自由を転覆しようとするしくみはひとつだけではない。過激主義は全ての情熱を引き起こし、王制はその希望をまだ諦めておらず、テロリズムはいまだかつてないほど大胆なようだ。」
「テロリズム」の語源はフランス語のterrorisme[15]で、1793年から1794年のフランス革命での恐怖政治(フランス語: La Terreur)に由来し、フランス語のterreurはラテン語のterreōから派生した語で「恐怖」を意味する[16]。
フランス革命ではジャコバン派が恐怖政治を行い、ジャコバン派の権力喪失後に「テロリスト」の用語は使用されるようになった[9]。
種類
テロの実行主体による分類には、権力者による自国民に対する恐怖政治、国家による他の国家に対する国家テロなどがある。(テロを支援する国家を「テロ支援国家」と呼ぶ場合もある。)
人数では、集団による「集団テロ」、個人による「個人テロ」などの分類がある。特に単独犯を「ローンウルフ」と呼ぶ場合もある。
背景や動機による分類としては、宗教的目的を背景とするテロリズムを宗教テロと言い、貧困(貧困の苦境や貧富の極端な差)が原因となって起きるテロリズムを「貧困テロ」と呼ぶことがある。また、自国内の社会問題などによって国民を苦しめることで国内で醸成してしまうテロリズムを「ホームグロウン・テロリズム」と呼ぶ。
テロの実行手段による分類としては、要人の暗殺や誘拐、交通機関などインフラへの打撃、無差別殺傷、実行犯が自爆する自爆テロ、核兵器または核物質を使用する核テロリズム、病原菌を用いたバイオテロ、コンピュータネットワークやコンピュータに対する攻撃を行うサイバーテロがあり、手製爆弾によるテロも増えた。
この「サバイバー」の監督。ジェームズ・マクティーグ!!!
ジェームズ・マクティーグ
James McTeigue
生年月日 1967年12月29日(48歳)
出生地 オーストラリアの旗 オーストラリア シドニー
職業 映画監督
ジェームズ・マクティーグ(James McTeigue, 1967年12月29日 - )は、オーストラリア出身の映画監督である。『ノー・エスケイプ』(1994年)、『マトリックス』三部作(1999年 - 2003年)、『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』(2002年)などでアシスタントディレクターとしてキャリアを積んだ後、2006年に『Vフォー・ヴェンデッタ』で監督デビューを果たした。
というわけですので、けっこうキャリアがあるので、期待したのですが、この映画については、
あまり、ディテールにこだわることもなく、
西洋映画の命とも言える、盛り上がりにも、欠けています。
仕事で疲れ果てたサラリーマンが、ピーナッツをつまみながら、テロについて考えてみるという意味では、いいのかもしれません。
世界に広がるテロ!!!
オバマ大統領の歴史的な演説に、私も感動したひとりですが、逆に言えば、もう核による、テロは、「すぐそこにある危機」ともいえるでしょう。
私たちの日本の平和は、口だけで戦争反対と叫ぶだけで維持されていることではないことは、知恵のある普通の日本人ならば誰しも気がついている筈。
この世界の現実。
・・・・・・・・・・・
たしか、中立国のスイスでさへ、軍隊をしっかり持って、竹村健一曰く、小さくても武装することで、敵の襲撃に対して一撃の効果を持つべきだということをどこかで書いていましたが、日本も、これまで、やるべきことをきちんとやってきたからこその平和の日本なんだと信じています。
フランスのテロについても、フランスの美しい女性や、たくましいおばさまおじさまたちが、「テロがあろうが、恐れずに一杯の珈琲を喫茶店で飲むことが、テロに対しての私たちの抵抗なのだ」と呟いていたことが思い出されます。
熊本の地震もふくめて、この人生は、・・・・・・・平穏無事で、楽に、すごせるわけがありません。
古来、敵から自分の身をどうやって守って行くか?
自然を普段から注意深く観察している人であれば生き抜くことの大変さは身体で震えるほどにわかることでしょうが。
・・・・・・・
ここ最近の、嫌なニュース。
日々を少し顧みても、安全運転をこちらがしていても、向こうのトラックが居眠り運転でつっこんでくる。
飲酒をする車が、背中から飛び込んでくる。
無垢で歌をうたいながら歩いている小学生の列に、免許をもどせばいいものを、自信過剰の70歳をすぎたアホ老人の車が突っ込んでくる。
軽飛行機が自家に突っ込んでくる。
普段何も連絡のない親戚や息子から電話が北と思えば詐欺。
・・・・・・・・
スーパーに行って、たまたま横の人のカゴを観てみると、皆がみんなではありませんが、多くの人が、甘パンの山をつくり、菓子のセール品を積み込み、タバコに酒に、肉に油たっぷの製品ばかりを・・・・・・・・・・・
まあ、人のカゴの中身などどうでもいいのですが。
飽食日本という言葉を連想します。
昨日観た「山の音」はそんな現代の狂ったような欲望の日々の描写もなく、人びとが、ただ、平凡に幸福に生きようとしている姿がしずかに書かれてあり、好感が持てました。
散歩する道に咲く野草に小さな喜びを見つけ、洋服のほころびを見つけては自分でなおし、旬の魚や野菜を上手に保存しながら、水に冷やした麦酒で一杯という昭和の時代。
・・・・・・・・
今夜の「サバイバー」は、別の意味で、実話ではないにせよ、ニューヨークの大晦日に、数万人規模のアメリカ人を殺害しようとするテロリストを、その作戦の数秒前に、ひとりの勇気在る女性が押し止める・・・・・・・・・・・その意味では、一見平和で、なにもないような幸福な日々の時間というものは、影ではだれかが、それを守っている・・・・・・そんなことも想像力を刺激するには、良いのかもしれません。
9.11以来53人もの、テロリストをニューヨーク警察並びに秘密部隊が逮捕したということはおまりおおらかにはされていない。
ホーキング博士が予言している、人工頭脳の自己再生能力の拡大の危険と。
恨みや個人の我の肥大によるところの、テロの恐怖、特に「核のテロ恐怖」は、
今、一番の世界が直面する、「そこにある危機」でしょう。
IRAをテーマにした映画だけでもこれだけあります。
あ
あの日の指輪を待つきみへ
お
男の敵
く
クライング・ゲーム
し
市街戦 (1936年の映画)
死にゆく者への祈り
シャドー・ダンサー
邪魔者は殺せ
ち
父の祈りを
て
ディボーシング・ジャック
デビル (1997年の映画)
は
パトリオット・ゲーム
ハンガー (2008年の映画)
ふ
ブラディ・サンデー
ブローン・アウェイ/復讐の序曲
ほ
ボクサー (1997年の映画)
ま
マイケル・コリンズ (映画)
む
麦の穂をゆらす風
ら
ライアンの娘
れ
レクイエム (2009年の映画)
あと、普通に、「テロ」をテーマにした、作品は、数限りなくありますが、
ここにコレクションしておきましょう。
あ
アイアンマン3
相棒 -劇場版- 絶体絶命! 42.195km 東京ビッグシティマラソン
相棒シリーズ X DAY
Under the Dog
え
エイトレンジャー
エージェント:ライアン
SP THE MOTION PICTURE
エッジ・オブ・ダークネス
エンド・オブ・ホワイトハウス
か
カウボーイビバップ 天国の扉
き
機動警察パトレイバー 2 the Movie
キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー
キングダム/見えざる敵
金田一少年の事件簿2 殺戮のディープブルー
く
クーデター (映画)
クリフハンガー (映画)
こ
ゴールデンスランバー
コラテラル・ダメージ
さ
ザ・イースト
ザ・グリード
サドン・デス (映画)
サバイバー (2015年の映画)
サボタージュ (1936年の映画)
ザ・ロック (映画)
し
ジェット・ローラー・コースター
地獄のコマンド
シャドーチェイサー/地獄の殺戮アンドロイド
シャム猫 -ファーストミッション-
シュリ
新幹線大爆破
す
スター・トレック イントゥ・ダークネス
た
ダークナイト
ダークナイト ライジング
大空港 (映画)
旅立ちの時 (映画)
ち
TUBE (映画)
沈黙の陰謀
沈黙の聖戦
て
ディル・セ 心から
テロリストゲーム1
テロリストたちの夜/自由への挽歌
天空の蜂
と
トイ・ソルジャー (1991年の映画)
トゥルーライズ
トータル・フィアーズ
DOG×POLICE 純白の絆
トップ・ドッグ
ドラゴン・スクワッド
ドローン・オブ・ウォー
な
ナイトホークス
は
バーダー・マインホフ 理想の果てに
ハードネス
パープルストーム 紫雨風暴
パズル (山田悠介)
バトル・ロワイアルII 鎮魂歌
パラダイス・ナウ
バンテージ・ポイント
ひ
ピースキーパー (映画)
ピースメーカー (映画)
ビッグゲーム 大統領と少年ハンター
ふ
フェア・ゲーム (1995年の映画)
フェイス/オフ
4デイズ
ブラック・サンデー (映画)
ブロークン・アロー
ブローン・アウェイ/復讐の序曲
ほ
北海ハイジャック
ホワイトアウト (小説)
ホワイトハウス・ダウン
ま
マーシャル・ロー (映画)
マッドマックス 怒りのデス・ロード
み
ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション
も
モンスターズクラブ
ゆ
ユゴ 大統領有故
よ
予告犯
れ
レンディション
ろ
ローン・チャレンジャー
「子供の頃から日本のアニメが好きで、キャラクターの絵をよく描いていた。お姫様キャラクターなのに空中戦というものすごいスタントをしてしまうミレディは、日本のアニメ的よね」ミラ・ジョヴォヴィッチ
「もともと日本のマンガ・アニメが大好きで、撮影の方法に影響を与えていると思う。『三銃士』に登場する空飛ぶ船は、大好きなシリーズ『宇宙戦艦ヤマト』と『オーディーン 光子帆船スターライト』にとてもインスパイアされたよ」ミラ・ジョヴォヴィッチの夫
FIN
草間彌生さん「水玉」 精神統合失調 描くこと 音楽で 魂の調律をする・・・・「チャーイ」
Everything that irritates us about others can lead us to a better understanding of ourselves.
他人に苛々することはすべて、私たち自身のよりよい理解につながり得る ユング
草間彌生さん「水玉」 描くことで救われた人生。
今の学校を観ていると、先生たちが、規範のルールからはみだすような大きな器の人もなし、自分を投げ打っても、子どもに尽くそうとする先生もなし、ただのサラリーマン社会と同じレベルになっている以上。
子ども達は、それを異常なほどに察知する。
愛のない学校のさむざむとした空気を。
18歳をすぎれば、少々世間の冷たい風もまた、スパイスになるのだろうが、
子どものにはまったくの、ぜったいに、つぶしあんこのような愛が必須だろうに。
先生たちも、ロマンがない。
自分のことしか、考えていない。
かつては、子どもが、貧乏で弁当を持たせてもらえない時には、先生がそれを察知して、自分の弁当を隠して、校庭で子どもと遊んだ時代もまたあったというのに。
それが、美談というわけではない。
日本人って、そんな民族なんだと思う。
今の先生だって、自分の子どもに対する考えがあると思うに、愛があると思うに、他人の意見やら批判やら、日教組やら、上司やら、さまざまなる対立軸にぶつかって、おしつぶされる。・・・・・・・・・・・・
そこで、人気のあるのは、器用で、口がうまくて、頭の良い、打算的な、社交的な、スポーツなどの得意分野のある、わずかなアイドルたちである。
彼らは、友達からも、先生からも人気があり、・・・・基本、
悩むことは少ない。
が。
そこにあてはまることのできない、不器用な、話しのできない、頭のあまり良いとはいえない、行儀の悪い、内向的な、そんな子どもたちがいる。
絵を描け、と言いたい。
歌を歌えと、言いたい。
書を書けと、言いたい。
友達をまきぞえに、死ぬな!!!!!
苦しい時は、学校なんかにいっちゃだめ。
かえって病状悪化する。
二三日、森をぶらぶらして、家で漫画を読んですかっとすること。
・・・・・・・・・・・・・
絵を描け、と言いたい。
歌を歌えと、言いたい。
書を書けと、言いたい。
友達をまきぞえに、死ぬな!!!!!
・・・・・・・・・・
先生も学校も、味方なんかしてくれない。
保身のかたまりだから。
いじめはありません。
そんなことしか言えない、こんぺいとうみいな、先生しかいなくなってきたんだから。
絵を描け、と言いたい。
歌を歌えと、言いたい。
書を書けと、言いたい。
友達をまきぞえに、死ぬな!!!!!
上手い下手なんかは関係ないのだから。
描いているうちに、あららふしぎ、そのひとつのものにたいする集中は、
魂をきれいにあらってくれる。
生きる楽しさを少しだけ、
感じさせてくれる。
あとは、それをながーく、続けるのだ。
つまり、ユングが言っているように、他人との、人間関係の軋轢や、ちょっとした摩擦などは、
自分を知るというか、自分の井戸を村上春樹ではないが、時間をかけて、ゆっくり掘って行くためには、最高のチャンスということもできる。
2014.7.28 11:30
背後の作品に同化して「自己消滅」してしまう草間さん。「いまも毎日制作しています。カンバスに向かっていると元気がでます」と語る=東京都新宿区の草間彌生スタジオ(松本健吾撮影)
幻覚…見たものをスケッチブックに描いて、恐怖や驚きを鎮めた
水玉の作品で世界的に知られる前衛美術家、草間彌生さん(85)。1959年、美術の本場のニューヨークのギャラリーで開いた個展で水玉絵画を発表した。展覧会は美術評論家やメディアから高く評価され、まったくの無名だった草間さんは米国で一躍有名になった。この成功を契機に水玉のアーティストとして世界で活躍することになった。(渋沢和彦)
幼いころから水玉を描いていました。10歳ころにスケッチした母の絵が残っていますが、無数の水玉が顔や着物にあります。幻覚で水玉が見えたのです。田んぼのあぜ道を歩いていても景色の中に水玉が見えてきました。スミレの花が人間に見え、話しかけてきたこともありました。見たものをスケッチブックに描いて、恐怖や驚きを鎮めたのです。それが私の絵の原点です。
《個展など地元で発表を続けていた草間さんは、57年11月、28歳のとき、芸術家になることを目指して単身でアメリカに渡った》
画家になることに反対した母は、金持ちのところにお嫁に行け、と盛んに勧める。師弟関係がうるさく、しがらみだらけの画壇にも息が詰まり、アメリカなら仕事を続けられるかと思いました。戦後まもない頃、地元の松本市内の古書店でジョージア・オキーフの絵が掲載されていた画集を見つけたこともアメリカ行きにつながったのです。「この人が助けてくれるかも」と思い、東京のアメリカ大使館に行き、住所を調べ、自分の水彩画などを入れて手紙を書いたのです。そうしたら激励する返事がきました。それが渡米を決意させることにもなりました。 《57年12月、身元引受人のいるシアトルのギャラリーでアメリカで初めての個展を開いた。しかし、美術の中心だったニューヨークで勝負するため、個展を終えると飛行機でニューヨークに向かった》

ニューヨークでは、日本から持っていった金も底を突き、貧しい生活でした。冬は寒く寝つけないのでひたすら絵を描きました。スタジオでは早朝から夜中まで大きなカンバスに網を描き続けていました。どの絵も網でした。床や机から自分の体にも描いてしまいました。友人たちからは「大丈夫か」と心配されてしまいました。水玉をネガティブにしたのが網目で、白い網は黒の水玉を包み、無限に広がっていったのです。水玉は私の命。水玉の集積がつなぐ白い虚無の網によって満たされ、自らも他者も消去するのです。
《59年10月、ニューヨークのギャラリーで個展を開き、「無限の網」を発表。米紙ニューヨーク・タイムズや美術雑誌で取り上げられ、著名な美術評論家からも高い評価を得た。以後、ボストンやワシントンのギャラリーで個展が開かれ、60年にはニューヨークの一流画廊と独占契約を結び、前衛美術家として世界に羽ばたいていった》水玉の呪縛は私をとりこにしてしまったのです。61年頃からは絵画からソフト・スカルプチャー(柔らかい彫刻)へと表現が変化しました。長いすや肘掛けいすを詰め物の突起で覆ったのです。突起は男根で、セックスへの嫌悪感や恐怖心を治すために創りました。63年に、ニューヨークでの個展で「集積の一千のボート・ショー」というインスタレーションを行いました。無数の白い突起を大きなボートにびっしりとつけ、天井や壁にはボートを写したモノクロのポスターを貼りました。アンディ・ウォーホルがやってきて、「すばらしい」といってくれました。その後、ウォーホルは、牛の顔を刷ったポスターを天井や壁一面に貼った個展を行いましたが、私のまねだったのではないでしょうか。
《突起も水玉同様に無限や反復を意味する。異国の地で評価された草間さんは、現在も絵画や彫刻で水玉模様の作品を創り続け、世界各地の著名美術館で展覧会が開かれている》
水玉は当時だれもやっていなかった。命がけで、独創的なことをやってきました。母は画家になることに反対し、絵を破られ焼かれてしまいました。アメリカへ行ったからこそ芸術家になれたのです。おそらく日本にいたら自殺していたでしょう。自殺を忘れるために描き、描くことで救われたのです。
音楽もまた、水玉のように、人の魂を救う。・・・・・・・・
このpianistシフ・アンドラーシュ好きだ。
バッハの曲がまた新鮮に聞こえる。
この6つのフランス組曲は、詳しく知っているわけではないけれど、ただただ、好きな曲。
1717年頃の作品。
1720年に妻マリア・バルバラが亡くなり、1721年にアンナ・マグダレーナと再婚。
再婚したばかりで、愛する新妻のアンナ・マグダレーナのために、書かれたと伝えられているだけあり、音楽的な才能もあったという彼女が技術的な弾きやすいように・・・しかし、バッハらしい心の魂の井戸に深く降りて行くような神秘感があると、私は思っている。
吉行淳之介が、恋をしはじめたときに書かれた作品に対して友達が、なにやら艶が出てきたと評価したけれども、そんな、バッハには似合わない艶というようなフランス的雰囲気さへも、感じてしまう。
バッハ、ケーテン時代の作。
この時代。
97歳のラインケンの前で得意のオルガンを演奏して、感激させた。
音楽もまた魂の調律という、言葉がありますが。
バッハもまた、職業としての音楽をとうしてではあっても、
魂の癒しをふだんからしていたはず。
・・・・・・・・・
◎資料
シフ・アンドラーシュ(Schiff András [ˈʃifˈɒːndrɑ̈ːʃ], 1953年12月21日 - )は、ハンガリー出身のピアニスト。バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルトなどドイツのバロック音楽及び古典派音楽を中心とし、シューマンやショパンなどのロマン派音楽まで演奏するピアニストの一人。室内楽奏者としても知られる。室内楽団「カペラ・アンドレア・バルカ」 (Cappella Andrea Barca) の創設者、指揮者でもある。シフ・アンドラーシュの妻、バイオリニストの塩川悠子も第一バイオリン奏者を務める。
ブダペスト生まれ。5歳からピアノを始め、リスト・フェレンツ音楽大学でカドシャ・パール、クルターグ・ジェルジュ、ラドシュ・フェレンツらに学ぶ。さらに、ロンドンでジョージ・マルコムに師事。
1974年、第5回チャイコフスキー国際コンクールのピアノ部門で第4位入賞。
1975年、リーズ国際コンクールで第3位入賞。
1977年、初来日。
1988年、ザルツブルク音楽祭でシューマンを集中的に取り上げる。
1989年から1998年にわたって室内楽フェスティバル「ムジークターゲ・モントゼー」の芸術監督。
1991年、バルトーク賞受賞。
1996年、ハンガリー最高の栄誉であるコシュート(Kossuth)賞受賞。
1997年、コペンハーゲンでレオニー・ゾンニング音楽賞受賞。
主な活動[編集]
1970年代に各コンクールでの活躍が始まると、ほぼ同年代のコチシュ・ゾルターン、ラーンキ・デジェーと並んでハンガリーの「若手三羽烏」として売り出された。当時の社会主義国家ハンガリーはコンクール出場を若手ピアニストに強制しており、「このコンクール歴は必ずしも自分の本意ではありません」と当時を回想している。
最年少のシフは、当初は3人のうちでも目立たない存在だったが、1980年代にイギリスのデッカ・レーベルと契約後、モーツァルトのピアノ・ソナタ全集の録音で俄に注目を集め、続いて一連のバッハ作品の録音によって、「グールド以来のバッハ解釈者」との名声を得、確固たるものとした。その後、1990年前後にはシューベルトのピアノソナタの演奏・録音、バルトークのピアノ協奏曲全曲、1999年から2005年にかけて、ザルツブルク・モーツァルテウム創立記念モーツァルト週間に、シフ自身が編成したオーケストラとモーツァルトのピアノ協奏曲を全曲演奏するなど、スタンダードナンバー演奏で高い評価を受けた。
近年はハインツ・ホリガーと共演でヴェレシュ・シャーンドル作品を紹介したり、ペレーニ・ミクローシュとの共演など、祖国ハンガリーにちなむ活動も盛んである。
教育活動にも力を注ぎつつあり、現在はドイツのデトモルト音楽大学教授、ミュンヘン音楽大学の客員教授という要職ポストに就いている。 またザルツブルク・モーツァルテウム音楽大学や、母校であるフランツ・リスト音楽院をはじめ、各地でマスタークラスを開いている。
では、最後に、石森章太郎氏の物語。
無意識の世界、彼独特の世界観です。
石森章太郎氏の初期短編。「チャーイ」
不思議と印象に残る短編。
彼はもともと、喫茶店で大好きな珈琲をタバコをふかしながら、アイデアを
紙にかきつけることが彼の生活習慣となっていた。
そんな石森章太郎氏の現実と、夢想が、ごちゃまぜになってくるところが良し。
珈琲を運ぶ女の子。
明治や大正時代のアンチークな居酒屋?などの女給もそうだけれど、
彼女たちは、店の顔となって、男性客をひきつける。
石森氏もまたそんなことが多くて、そのお目当ての女の子に会うために、
日々、そわそわと、その喫茶店に通うこととなる。
マスターとふたりだけの喫茶店の運び娘、珈奈子。
珈琲のなかに、チャーイと呼ばれる珍しいパキスタンの茶葉を少し入れてくれる
珍しい珈琲屋だ。
そこにいけば、
アイデアがでてくる。
逆に言えば、その他の場所ではもうアイデアのアの字もでてこないということ。
それだけの短編なんだが、彼独特のimaginationのふくらみを次第につけて、作品は、
興味深いホラーのような物語の形をとってくる。
中国人のような細めで黒目のおとなしく、母のような匂いのする珈奈子。
何回か通よう中に、石森氏は、ふたりきりでどうしても会いたくなる。
珈琲。
タバコ。
そんなある日、土管のなかで、子供を孕んでいる猫を見てしまう。
猫は、びっくりして、盲目的な愛情のあまり子猫をむしゃむしゃ、食べてしまう。


石森氏は、その時の衝撃から、日々、悪夢に浮かされる。
もともと、不眠症があり、当然昼と夜が逆の生活、タバコと珈琲と締め切りに追われる
強迫観念などのためか、自律神経が乱れていたのか、ふと目覚めると、子猫をむしゃむしゃ食べる土管の中の母猫の幻想を見て、悩む。
友達にも相談するが、タバコと珈琲の吸いすぎとたしなめられる。
珈奈子は、いざ、デートをすると、娘の可愛らしさが素直にでて、石森氏は
夢中になる。
ところが、店に行けば、彼女はマスターの前なのか、しらっとした雰囲気しかださずに、 がっかりしてしまう。
その気持ちがまた、嫉妬心にからみつつ、その喫茶店に通ようはめとなる。
このあたりは、世の男性はよくよく理解できる心理。
ある朝。
マスターが、チャーイを背中からナイフで刺し殺す悪夢を見て起きる。
起きてもそこに幻想だけが残っている。
子猫をむしゃむしゃ食す母猫。
母のようなまなざしと、娘のような素直なチャーイが、マスターに刺し殺される。
悪夢なんだと信じようとするが、どうしても現実としか思えない石森氏。
あのマスターと珈奈子は、できていたのだ。
無意識のなかの、悪夢のようなシーンがトリガーとなったのか、つぎからつぎへと、
直感がシンクロニシティしながら、現実をつくりあげていくように感じて行く。
噂では、珈奈子は殺されて、店は閉店。
そんな噂がどんどん、彼の耳にはいってくる。
・・・・・・・・・・
不思議なことがおこりはじめる。
それ以来。石森氏が違う店に行っても、数ヶ月がすぎて、そう、その日がくると、
珈奈子に良く似た運び娘が、珈琲をはこんでくるようになる。
店を慌てて、変えて、違う店に行っても、また、とある時間がすぎると、珈奈子があらわれる。
寝る前に、ブラッドベリやら、ミステリーやら、なんでも良いがとにかくも、「活字」を読む事がなければ眠れないというほどの読書家。石森章太郎。
彼の膨大なそんな日々の読書のインプットが、無意識の魂の井戸のなかに、沈殿し、
発酵熟成し、ある日、顕在化されたイメージとして、脳裏に浮かんでくる。
彼はそれを言葉とコマ割りのなかに、埋め込んでいったのだった。
無意識の世界と意識の世界の繋がりを。
The creation of something new is not accomplished by the intellect but by the play instinct acting from inner necessity. The creative mind plays with the objects it loves.
何か新らしい発明とは知性で完成されたものではなく、隠れた必需性からの本能の働きである。想像力は物本自体に愛着がある
ユング
FIN
Joe Henderson - Fire (higher quality)
彼はケニー・ドリューとケニー・クラークとケニー・ドーハムと出会った。三人のケニー。
ある晩、彼らはバードランドで演奏していたデクスター・ゴードンに会いに行った。これが縁となる。
飛行機によくおいてあるお持ち帰りオッケー本。エッセイを読み返す。味わい深い。
モンサンミッシェル・・・死ぬ迄には一度は行きたいと思ってた。
25歳の時には、安旅にもともと、スケジュールにはいっていなかった。
なんせ、往復八時間のバスの旅だから、オプションになるのだった。
二回目の時は、仕事がいそがしすぎて、後輩にかわりにフランスにいかせた。
三回目、58歳のころ。
とうとうモンサンミッシェルについたことを思い出させるエッセイ。



最後には、浅田次郎たるもの、ギャンブラーで一環千金をものにしている彼が、意外にセコいことを描いていたけれども、名物に美味いものなし。
私は、食べなかった。
あんなものに、7000円はかけられない。
美味いワインと、日本では珍しい風スパゲッティを食した。かなりそれでも、油っぽい。
食事はやはり日本が世界でも一番美味いのではないだろうか。
たしかに、五つ星なんかのレストランはのぞくとして、ヨーロッパもアメリカも、日本のように、G級ランチで素晴しいものはないだろう。
アジアは、B級で美味いものはたくさんありそうだけど、基本、どうもどんぶりをバケツのなかで、どろどろになるまで、洗って、食するのは苦手。
・・・・・・・
というわけで、しみじみと、モンサンミッシェルを思い起こすエッセイだった。
いみじくも彼も描いていた。
「私はこのモン・サン・ミッシェルのオムレツにたどりつくまでの、おのれの人生を省みた」
・・・・・・・・・・・
「ハンガー・ゲーム 」「ビッグ」「エコライザー」「ウィンターズ・ボーン」「あの日、欲望の大地で」
昨日。友達との、飲み会があり、かなり飲んでしまった。それでも、歩きで家まで、帰宅し、一日に、13000歩は達成。気分も体もすっきりで、朝八時半起床。
ここ最近、「ハンガー・ゲーム」の1巻2巻3巻をレンタルして、細切れ視聴を繰り返していたので、ここに記録を残しておきます。
上のダイジェストクリップなどが、あり、今やYouTubeは、備忘録としても大助かり。
再度確認してから、記録。
このシネマは、疲れたサラリーマンさんやOLさんが、見てすかっとするというようなシネマではないですね。
監督は、私のフェボリット「ビッグ」の監督。ゲイリー・ロス・・・
この「ビッグ」は最高でしたね。
トム・ハンクスが子どもの魂のままに、大人に変身して、おもちゃの社長に抜擢されるというコメディでしたが、不思議なファーストシーンも含め、楽しい映画でした。
何回も見ました。
また、この監督は、大統領の影武者になってしまう平凡なる男を描く「デーブ」や「ラッシー」もつくっております。
でも、やはりこの監督では、「ビッグ」が一番おすすめですが・・・
さて、この「ハンガー・ゲーム」
たしかに、正義の味方が悪の巣窟に乗り込んで行って、徹底的に悪を叩きのめすというような、映画だけに許される21世紀の映像効果のなかで、見ていて、スカッとするというような
アクション映画は、人気があるでしょうが。
そんな映画とはちょいと、違います。
たとえば、「エコライザー」個人的に、私の大好きな映画ですが、ただのアクションだけではなくて、孤独な黒人の主人公が、ロシアマフィアに魂と体をとことん吸い取られている少女を助けるために、マフィアの巣窟のただひとりで乗り込んで行くというところなどが、圧倒的な映像で、これこそ、カタルシス映像となっていますが、
そのようなシネマではないということです。
この映画「ハンガー・ゲーム」は、ちと、違います。
それに、アメリカでは、観客動員数などでは大ヒットとなっておりますが、日本での、レヴューなどを見ると、ひどいものです。
駄作などという評価もけっこうありますね。
だから、スカッとするアクション映画を期待して見たらそのような評価になるのでしょう。
でも、淀川長治さんがいつも言っていたように、どんな駄作であっても、良いところがひとつやふたつはあるのです。
そういうところを発見して、映画と楽しくつきあっていく。
人間関係と同じです。
これだけの、金をかけてつくった大作ですから、小説とは違って、別の作品になっていることはあたりまえですし、この21世紀の映像の可能性という観点からのみ、見ても、なかなか
すごいシーンはたくさんあります。
ただ、スカっとする映画ではないということ。
連想を勝手にすると、「アメリカン スナイパー」でしょうか。
アメリカの9.11のテロに怒った、ひとりの男性が毅然とテロの敵地に乗り込み、彼の射撃の天才ぶりが、見物の実話をもとにした作品。
漠然とした敵のイメージ。
それが、しだいに悪人というイメージから、武器を持つ小さな子どもや普通の主婦までも、射撃せねばならないという立場に・・・・・・・・・
彼の心のストレスと、葛藤。戦いが皿な戦いという矛盾に考えさせられる。
さすがは、クリント・イーストウッド監督。
ただの戦争映画ではなく、戦争そのものの、矛盾性みたいなものをつかみだそうとしているのでしょうか。
ですので、ただの反戦映画みたいな薄っぺらい映画ではなく、見応えのある作品です。
◎資料から
クリント・イーストウッド監督最新作『アメリカン・スナイパー』はイラク戦争に4度にわたって遠征、アメリカ軍史上最多160人以上を射殺した伝説のスナイパー、クリス・カイルの半生を元に、残酷な戦場と幸せな家庭の狭間で精神が崩壊していく・
だから、私は、この「ハンガー・ゲーム」を見ながら、まったく違う映画ですが、なにやら、連想していました。勝手な連想は私の自由ですから。
映画は、「人生の勉強の場」ですから。=「淀川長治映画の10ヶ条 」
そしてまた、「頭で見るのではなくて、感覚で見よ」と・・
妹の身がわりになって、自身「ハンガー・ゲーム」に身を投じる、
ジェニファー・ローレンスがまた、個人的には素敵ですね。
愛がもらえます。
いわゆる、ハリウッド女優のような、気品のある美しさというよりも、逞しい生命力を持った少女というイメージでしょう。
この映画のなかで、悪役のスノー大統領を演じるサザーランドが、彼女については絶賛しております。
「ジェニファーと初めて会った時、ワクワクしながら彼女を見たんだ。彼女は最高に立派な女優だと思う。鋭い感性と他の人にはない才能からくるものだと思うよ」
「スノー大統領として再び戻ってきた撮影日の初日は、ジェニファーと二人きりのシーンだった。原作でも最初に来るシーンだ。私にとって最高に嬉しいシーンだったよ。
彼女は天才だから、情報に耳を傾け、それを自分の中で魔法のように混ぜ合わせることによってキャラクターを出現させるんだ。彼女は真理や誠実性を発信するたぐいまれな存在だよ。彼女が演技していると時が止まるんだ。時が止まって、外の世界の何物も彼女の邪魔はできなくなる」
そして、スノー大統領が少女カットニスや自分の役柄などをこんなようにも興味深く語っています。
「スノーはカットニスの存在がこれまで味わったことのない脅威だと初めから直観で分かっていたのだと思うね。彼女のことを最も恐れているが、一方で愛すべき脅威なのだ。私も77歳だからわかるんだが、突然人生の最後に自分を試される喜びを感じているんだよ。自由を求めて戦う彼女は、スノー大統領にとって他にはどこにもいない“特別な存在”であり、チェスゲームで負かそうとしている感覚を実は喜んでいるんだ。彼はもし彼女が自分の味方だったら、自分の後継者として完璧な人間だということを認識するんだ。そこで、それが出来るかどうかを見極めるのが彼の任務となる。彼は冷静で、“こうすれば、すべてが駄目になる。こうすれば、大丈夫だ。”とカットニスにとても明確に説明するんだ。彼がカットニスと一緒に居る時や、彼女を見る時に喜びを感じたりするところは実に面白いよ。彼が性的な男だったらカットニスを欲しがるだろうが、彼はそうではないからね。彼が求めているのはバラだけなんだ」
ところで。このヒロインカットニス演じるジェニファー。
彼女の映画は、なんといっても、「ウインターズ・ボーン」。
どこかで、見た顔だなあとぼんやり思っていたら、やはり、この「ウインターズ・ボーン」でした。
不思議な作品で、私は、一本見るのに、数日かけました。
小説を読むように。
『ローリング・ストーン』のピーター・トラヴァースは「『ウィンターズ・ボーン』は忘れ難い」と書いていますし、「グラニクはこの目を離せない激しさと感性を伴った、危うく際どい題材を捌いた」「グラニクはローレンスという若く優れた女優にリーが宿っていることを見出した。彼女の演技は演技を超えた、迫り来る風雲である」と記載されています。
また。
(サンダンス映画祭でドラマ部門のグランプリに輝き、第83回アカデミー賞では4部門ノミネートされた。そのほかベルリン国際映画祭で2つの賞を受賞、インディペンデント・スピリット賞で7部門にノミネートされ2部門を受賞するなど、あわせて92個の賞にノミネートされ、うち35個を獲得した。)
見た方も多いでしょうが、暗い冬の空のような映画ですが、じわじわと、考えさせられます。
日本は、ここまで酷い地区のイメージがわきませんのですが、実際にこのような村があるようなので、アメリカ人にとっては、魂に響くのでしょう。
ジェニファー・ローレンス・・・彼女でもっているような映画です。
この「ハンガー・ゲーム」。
東洋人顔というか。日本人的な雰囲気というか。
顔の彫りの深い、ジュリア・ロバーツのような顔ではありませんが。
味のある顔で好きです。
個人的には、ビョークのような不思議感覚オーラがでている彼女の顔。
10代の頃。
と、20代の今の彼女。洗練されてきました。・・・・・・・
あと。
私が見た彼女の作品としては。
この映画。
「あの日、欲望の大地で」・・・
これも、駄作とか、不倫の映画だとか、レヴューにはありますが、もともと、道徳を教えるために映画やその他の小説やマンガや音楽が、あるわけではありません。
道徳や社会の規律などを、超えたところにある、なにか、真の命みたいなもの、道徳を超えた美。
シェイクスピアではありませんが、キレイはキタナイ、キタナイはキレイ。
簡単に道徳を叫ぶのなら、映画を見なければいいのですから。
尊敬するオスカー・ワイルドは、こんな美についての言葉を残しております。ドリアングレイの肖像という小説の序文なのですが、二三、記載しておきます。
○道徳的な書物とか非道徳的な書物といったものは存在しない。書物は巧みに書かれているか、巧みに書かれていないか、そのどちらかである。
ただそれだけしかない。
○芸術家たるものは道徳的な共感をしない。芸術家の道徳的な共感はゆるすべからざるスタイル上のマンネリズムである。
○芸術家たるものはけっして病的ではない。芸術家はあらゆることを表現しうるのだ。
○美なるものがただ「美」をのみ意味しうる者こそ選民である。
この「あの日、欲望の大地で」のなかの、三人の女性達。
すごいです。
その末っ子の役を、ジェニファー・ローレンスが、やっておりました。
映画は、配役の俳優のことを少し予習してから見ると、映画のおもしろさが、数倍にもふくれあがりますね。
そのことを感じさせてくれた、この「ハンガー・ゲーム」でした。(ピーター役の男優やら、その他の俳優さんたちは、存在感がなぜか薄いです。きっと私が、彼らの他の映画のことをまったく知らないか、勉強していないからでしょうが・・・)
あと。
この映画は、日本の「バトル・ロワイアル」に作品の構造がよく似ているのではないか、と言われています。
下のクリップにもありますが、このような、物語の筋じたいが、不愉快という批評も、うなづけます。
「図書館戦争」に比較すると、戦闘シーンは、よく表現されていますが、この物語の設定自体が、残酷きわまりないものですから。
見たくない人は見ない方が良いと思います。
自然界を見回しても、「殺戮」を好んでやるなんていう獰猛なる生物は、人間くらいなものでしょう。
ただ、この殺戮シーンは限りなく、少ないです。
そのことだけが、目的ではないと監督が影で言っているようです。
革命という美名の下に隠れた名誉欲やら、マインドコントロールやら、人間のどうしようもない煩悩や、ウソや、偽善・・・・・・・・
そんなものもまた、描きたかったのかもしれませんね。
11月にこの映画の4というか、最終版がくるらしいです。
どうしましょぅか??? 見ようか見まいか、悩みます。
個人的には、これから見て行く映画はやはり、ハッピーエンドになってもらいたいものですね。
(過去の名作などには悲恋ものや、アンハッピーエンドが多いのは、それはもう見た映画ですから、いいのですが、歳をとると、もう悲恋ものや不幸ものは、心がついていけません・・・)
映画の楽しく見るこつは、偏見や、レヴューなどにまどわされることなく、監督や、俳優たちを見て、自分でピンときた映画を、丁寧に、見ることが大切ですね。
いろいろな見方があるのだと思います。
ひとつの映画をいろいろな人が見て、いろいろな感想を持つ。
小説を何回も繰り返して読むと、年齢とともに、味が違って感想を持てるようになるのと、同じく、映画も、好きな映画は、何回も繰り返してみると、また違う楽しみ方もできるということですね。
それに、洋画は、なんといっても、英語のヒアリングの勉強にはもってこいです。(私は、邦画の方がほんとうは好きなのでもっと映画の感想を記録したいのですが、今は、ヒアリングにはぴったりの洋画中心に見ています。この「ハンガー・ゲームは、ヒアリングとしては、非常に聞き取りやすいレベルです。)
「映画は人生勉強のテキスト・人生の勉強の場」ですから。=「淀川長治映画の10ヶ条 」
◎資料 「ウインターズ・ボーン」
サンダンス映画祭でグランプリ&脚本賞の2冠に輝き、アカデミー賞では作品賞、主演女優賞、助演男優賞、脚色賞の4部門でノミネートされた、インディペンデント映画界の意欲作。ダニエル・ウッドレルの同名小説を基に、ミズーリ州の山間部の村に住む17歳の少女が、家族を守るため父親を捜しに、そして真実を追い求めて旅をする。心のすさんだ大人たちから罵声を浴びようとも、暴力に打ちのめされようとも、くじけず、諦めず…
◎資料『アメリカン・スナイパー』
『アメリカン・スナイパー』は、アメリカ合衆国で製作され2014年に公開された伝記映画である。 原作はイラク戦争に4度従軍したクリス・カイルが著した自伝『ネイビー・シールズ最強の狙撃手』で、脚色はジェイソン・ホールが行った。監督はクリント・イーストウッドで、ブラッドリー・クーパーが主演を務める。
◎
資料『バトル・ロワイアル』
中学生達が殺し合いを強いられるという内容。第5回日本ホラー小説大賞の最終候補に残ったものの、審査員からは「非常に不愉快」「こう言う事を考える作者が嫌い」「賞の為には絶対マイナス」など、多くの不評を買い、受賞を逃す[1](選者の1人が後に書くところによると、最大の落選理由は作品的に落ちるからであり、しかし、おもしろいから売れるだろうと、別の場で語り合っていたとされる[2])。 その後、1999年4月に太田出版から刊行され、先述の事情と共に話題を呼ぶ。2002年8月には最低限の修正(ミス部分など)を施した上で文庫化され、幻冬舎より刊行された。
また、深作欣二監督、藤原竜也主演で映画『バトル・ロワイアル』が2000年12月6日に公開された。公開前には国会でこの映画に関する質疑がなされ、また西鉄バスジャック事件を初めとする“少年犯罪”が注目された時期でもあり、社会的関心を集めたことで話題を呼び、大ヒット作となった。
題名の「ロワイアル」はフランス語読み。執筆段階では「バトル・ロイヤル」と言う英語の題名だったが、作者が友人に見せて感想を求めた所、フランス語好きだったその友人による「フランス語で読むと『バトル・ロワイアル』だな」との返事から、語感がよかったので題名を変更した。正しく仏訳すると「Bataille Royale」(/ba.tɑj ʁwa.jal/, バタイ・ロワイヤル)になる。
以下、原作の設定を中心に記述する。漫画版、映画版もこの設定に準拠するが、体制、小道具の名前等々、異なる点は幾つも存在する(原作と漫画版は大東亜共和国という架空の国、映画版は現在の日本の体制の延長線上)。
この節にあるあらすじは作品内容に比して不十分です。あらすじの書き方を参考にして、物語全体の流れが理解できるように加筆を行ってください。(2014年9月) (使い方)
極東の全体主義国家「大東亜共和国」では、西暦1947年より、全国の中学3年生のクラスからランダムに選ばれた50クラスに対し、「プログラム」と称する殺人ゲームを実施していた。
西暦1997年、七原秋也ら香川県城岩町立城岩中学3年B組の42人は、修学旅行のバスの中で眠らされ、ゲームの舞台となる島「沖木島」へ送り込まれた。極限状態の中、クラスメイトによる究極の椅子取りゲームが始まる。
◎資料
ゲイリー・ロス(Gary Ross, 1956年11月3日 - )は、アメリカ合衆国の映画監督。
カリフォルニア州出身。父親は1980年の映画『ブルベイカー』(原案)でアカデミー脚本賞にノミネートされた脚本家アーサー・A・ロス。 ペンシルベニア大学に通う[1]。はじめ漁船上で働き、大統領選挙キャンペーンに関わる、そして小説も書いた。のち脚本家になる。スティーヴンの妹アン・スピルバーグと共同脚本の映画『ビッグ』で、第61回アカデミー脚本賞にノミネート。その後も度々アカデミー賞の候補となっている。
おもな作品[編集]
ビッグ Big (1988年) 脚本・製作
ミスター・ベースボール Mr. Baseball (1992年) 脚本
デーヴ Dave (1993年) 脚本
Lassie/ラッシー Lassie (1994年) 脚本 - 日本では劇場未公開
Mr.ダマー2
1
2
Trial and Error (1997年) 製作 - 日本では劇場未公開
カラー・オブ・ハート Pleasantville (1998年) 製作・監督・脚本
シービスケット Seabiscuit (2003年) 監督・脚本・製作
ねずみの騎士デスペローの物語 The Tale of Despereaux (2008年) 脚本・製作 - 日本では劇場未公開
ハンガー・ゲーム The Hunger Games (2012年) 監督・脚本
The Free State of Jones (2016年) 製作・監督・脚本
アホをそのまま包むバカボンの優しきママ 「男の子を元気にすると女の子も元気になるのよ」岡本敏子

基本私は女性を尊敬しています。
でも誰でもというわけではありません。
狡猾で、打算的な女性がテレビなどで、まるででまかせに、偉そうなことを言っているを見ている時や、
女性について・・・気持ちがめげたときなどは、バカボン、パカボンパパ、そしてはじめ君のことを、
どんなに彼らがバカであれ、
こよなく、無償の愛で優しく包みこむ、世界に誇る最高のやまとなでしこの母。
個人的にこよなく尊敬し、愛しております。立花ヨシコさん、つまり、パカボンママを・・・!!!
こんなママがいたら、子ども達、特に、疲れ果てたお父さんと、息子は、バカはバカなりに、 必死にがんばるだろうと思う。
子どもが他人に迷惑をかけたとき、規律的に当然、しっかり怒るのは父親だと思いますが、
理屈を言うのではなくて、子どもを信じて、手をにぎりしめて、子どもの気持ちになって、涙する母親。
そんな母親を見て、子どもはもう悪いことはしないと決心すると、個人的には思っていますし、
私もそうでした。
合理的な解決だけが、すべてではないのです。子どもは、親が思っている以上に、
親を見ているのです。何も言わずに、だまって子どもを抱きしめるだけで・・・それが子どもにどんなに生きていこうとする勇気を与えることでしょうか。
「幼年期から青春期に女性とのさまざまなる事件・経験が、その男性の一生を決定する」
某作家
・・・・・・・・・・・
ちょいと、調べたいことがあり、手塚治虫コミック棚からどーんと漫画をひっぱりだしてきては、もどしたり、またひっぱりだしたりして、読んでいましたが。
「SFミックス」という単行本にある、「宇宙からのSOS」は、地球外からのSOSを感知した天才パイロットが光子ロケットに乗り込み、光の速度を超えて、SOSの発信地・・・アルファケンタウリ星、0.3光年という設定ではあるけれども、そこに行くと、流星群にぶつかって、光子ロケットが故障してしまい、絶望の果に、地球に無線を打つ・・・・それを受けた彼がまたでかけていく・・・。
この作品は、「少年ブック」で、昭和37年というから、なんと、私が、8歳のころ。
小学生になったころに、すでに手塚治虫は今でもSF映画の基本となるようなアイデアを、ノオトに書き付け、そして、小品ではあるけれども、作品に結晶させていた。
1960年前後のSF西洋映画といえば・・手塚治虫氏が描いたような、宇宙の果の果てのドラマやら、量子理論ともいうべきヒント、あるいは、光子ロケット(たとえそれが理論的に不可能であろうとなかろうと・・)などというようなすさまじいアイデアの作品は皆無です。
シンプルで幼稚なSFばかりです。
・・・・・・・・・・
ちなみに、手塚治虫氏は、1928年(昭和3年)11月3日 - 1989年
アーサー・C・クラーく氏は、1917年12月16日 - 2008年3月19日
アイザック・アシモフ氏は、1920年1月2日 – 1992年4月6日
たしかに、クラーク氏は、「「前哨」(1948) で初めて宗教的テーマが導入され、『都市と星』などの作品でそれがさらに追究されている。「前哨」には、知的種族が進化すると神に近いものになるというもう1つのテーマがあった。これをさらに深めたのが1953年の『幼年期の終り」、ということで、どんどん深みがましてはいったけれど。
たしか、前哨のアイデアは、2001年宇宙の旅では、かなりイマジネーションが広げられているような気もする。・・・・・
ある意味、手塚治虫氏の惜しいところは、膨大なきらめくようなアイデアがあるのに、
それを深く深く、丁寧に、おしすすめていくには、多忙すぎたということと、つぎからつぎへと、脳から溢れ出てくるアイデアを書きとめるだけで精一杯だったのだろう。
(映画をつくるためのヒントとして、手塚治虫全集を揃えている映画監督の多い事!!!)
私のように、家人と遠く離れてくらしていて、日々同じことをただただ丁寧にしながら生きてはいるものの、普通のサラリーマンのように、軽口をたたいたり、友達と笑ったりすことが極端に減ってきて、静かに音楽を聞いたり、絵をじっと描いたりするような時間が多くなってくると、不思議と注意力が増すのか、非日常的なことを多く感じるようになります。
もう、神経が張りつめて来て良くも悪くも雲ひとつ、星一つ見ても、魂がゆさぶられるようになります。
もちろん、それは、私の望むところなので、そのような生活に憧れて、サラリーマンを辞めたあとは、いわば隠遁生活のようなライフスタイルをしようと考えていたので、自分なりにはすごく幸福なわけです。
・・・・・・・・・
今、一番好きなのは、「老子」などの本を好んで見ます。
20年前からの愛読書の「タオ自然学」も、ボロボロになってきましたので、それと合わせて、この「老子が教える 実践 道の哲学」を、原文と合わせて、ウィスキーを楽しむようにちょびちょびと、一章ずつ、読んで行きます。
老子が教える 実践 道の哲学/PHP研究所
¥1,836
Amazon.co.jp
コップ21Conference of the Parties。
後発の国はともかく、先進国は、このtaoの思想をすこしずつ学んで行かないと、地球は滅んでしまうでしょう。
私も学んでいる最中ですから、なんにも偉そうなことは言えませんが、とにかく、モノに執着しすぎる時代は終焉にちかづいているということでしょうか。
「星の王子様」 目に見えないことを感じる心。
「幸福な王子」ワイルドの、自己犠牲による他人への無償の愛の奉仕。
そんなものが、21世紀後半のテーマになるでしょう。・・・
いうまでもなく、悪魔と天使の中間でもある人間のことですから、一縄筋ではけっして簡単に、理想郷にはいかないでしょうが、くるくると、スパイラル的なラセン的な、ゆっくりとした歩みで、すすむしかありません。・・・・・
エリカ・ジョングという作家は、「もはや、人類に残された資源は想像力のみだ」と描いています。
私の大好きな言葉です。
どこで読んだのか忘れてしまいましたが。
テレビを見ても、この「想像力の欠けた」コメンテーターばかり。
つまらないです。
ある意味テレビというメディアは、膨大なる情報がありますから、日本人に必須の速報になどを瞬時に伝えるというメリットはあるものの、・・・・いろいろな事件の深い深い「闇」の真実などには到達できるできるようなメディアではありませんね。
それは、むしろ、漫画であり、文学であり、本であり、映画であり、音楽なんだと思います。
新聞でも書けない、テレビのワイドショーでも絶対描けない、そんな「人の暗い暗黒の領域」をこれらのメディアは描くべきだと思います。
ひとつの例をあげますと。
テレビは、基本、「見たものしか信じない」という似非科学の世界の上に、のっかっていますから、解離性同一性障害その他、魂の深い奥の奥にひそむ問題を、顕在化するということには不向きのメディアだと思います。
そこを深く掘り下げて、徹底して、調べ上げることのできる媒体。
それが、本であり、文学であり、漫画であり、映画なんだと思います。
「目に見えるものだけを信じる」・・・・・・・・・現代人の最大の陥穽でしょう。
先日亡くなった、水木しげるさんの作品を数冊でも読めば、彼が、いわば目に見えないものやこと・・・それらに夢中になって取り組んで来た、一生が、よくよく理解できるようになります。
Pen ( ペン ) 2010年 5/1号 [雑誌]/阪急コミュニケーションズ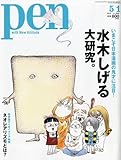
¥617
Amazon.co.jp
「夜を怖がる事」
子どもさんでも、恐がりの子どもさんがおります。
ひとりで、トイレに真夜中にいけないなどなど・・・・
水木さんや、その他の作家たちは口をそろえて言います。
「想像力の豊かな子どもさんだね」と・・・・・・・・・・・。
「私は今どこにいるんだろうか・・・」
「私はどこからやってきてどこへいっちゃうんだろうか」
「私はほんとうに今、ここに、実在しているのだろうか」
「死ぬっていったいどんなことなんだろうか」
私は、幼稚園の頃から、雪がちらちら窓の外からふってくるのを見ながら、ぼんやり考えていました。・・・・・
母からは、「おまえは、いつもぼんやりしているね」「夢みたいな子だよ」と、
よく言われたものです。
・・・
ゴーギャンのこの絵。
30歳頃に、サラリーマンをしながら、暇を見つけては絵を描いたり、美術館へ行ったりしていたときに、見つけました。
『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』
ええええ、私は、びっくりしました。・・・友達に聞いても笑われ、先生方に聞いても、無視され、ただただ仕事に忙殺されながら、敬愛する三島由紀夫氏は、答えも教えてくれずにに、逝ってしまったし(実は、彼の本をもっとしっかり読んでさへいれば、答えはあったのですが。今ならば、わかります。)
『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』を描き上げた後に自殺を決意していたゴーギャンは(自殺は未遂に終わる)、この作品に様々な意味を持たせた。絵画の右から左へと描かれている3つの人物群像がこの作品の題名を表している。画面右側の子供と共に描かれている3人の人物は人生の始まりを、中央の人物たちは成年期をそれぞれ意味し、左側の人物たちは「死を迎えることを甘んじ、諦めている老女」であり、老女の足もとには「奇妙な白い鳥が、言葉がいかに無力なものであるかということを物語っている」とゴーギャン自身が書き残している。背景の青い像は恐らく「超越者 (the Beyond)」として描かれている。この作品についてゴーギャンは「これは今まで私が描いてきた絵画を凌ぐものではないかもしれない。だが私にはこれ以上の作品は描くことはできず、好きな作品と言ってもいい」としている。
この作品はゴーギャンのポスト印象派の先駆けとも言える。自身の感情、印象派的な技法を強く追求するあまり、鮮やかな色彩、明確な筆使いといった印象派の手法を否定する結果となり、20世紀のキュビズム、フォービズムなどといったアヴァンギャルドの前兆となった。
その、実在感のなさ。・・・不安。バーチャルと、リアルの境目の不思議。
・・・・・・・・・・・
たしか中国の詩。
たき火をしていて、ふと目覚めたら、それが夢なのか、現実なのか、どちらなのかわからなくなってしまったという詩・・・・ありましたね。
以前のこと、わたし荘周は夢の中で胡蝶となった。喜々として胡蝶になりきっていた。
自分でも楽しくて心ゆくばかりにひらひらと舞っていた。荘周であることは全く念頭になかった。はっと目が覚めると、これはしたり、荘周ではないか。
ところで、荘周である私が夢の中で胡蝶となったのか、自分は実は胡蝶であって、いま夢を見て荘周となっているのか、いずれが本当か私にはわからない。
荘周と胡蝶とには確かに、形の上では区別があるはずだ。しかし主体としての自分には変わりは無く、これが物の変化というものである。
かつて。
三島由紀夫の「文章読本」を読んでいて、おやっと惹かれた記述がありました。
文章読本 (中公文庫)/中央公論社
¥596
Amazon.co.jp
彼一流のユーモアと皮肉で、「僕の登場人物は本など読まない」とか「本をわざわざ買って読んでも不安を買わされるみたいなものだ」とか言うような、文を書く人なので、皆だまされちゃうんですよね。
素直で純朴な男が好きなのに、そのような文章は書かないというか、不思議ですね。
三島さん曰く。
「チボーデは、小説の読者を2種類に分けております。ひとつは、レクトゥールであり、「普通読者」と訳され、他のひとつはリズールであり、「精読者」と訳されます。チボーデによれば、「小説のレクトゥールとは、小説と言えば何でも手当たり次第に読み、「趣味」という言葉の中に内包される内的・外的のいかなる要素によっても導かれない人」という定義をされます。新聞小説の読者の大半はこのレクトゥールであります。一方、リズールとは、「その人のために小説世界が実在するその人」であり、また「文学というものが仮の娯楽としてではなく本質的な目的として実在する世界の住人」であります。
リズールは食通や狩猟家や、その他の教養によって得られた趣味人の最高に位し、「いわば小説の生活者」と言われるべきものであって、ほんとうに小説の世界を実在するものとして生きて行くほど、小説を深く味わう読者のことであります。実はこの「文章読本」を、今まで、レクトゥールであったことに満足していた人を、リズールに導きたいと思って始めるのであります。」
そして彼はここまで書いております。私は、まさに、この文章に出会った時に、
驚喜乱舞しました!!!!! 少し大げさでは在りますが、それくらい嬉しかった。
(私はなるたけ自分の好みや偏見を去って、あらゆる様式の文章の面白さを認め、あらゆる様式の文章の美しさに敏感でありたいと思います。三島由紀夫言)
というわけで、私は、私は、 私は、リズールでありたいと願います。
すでに、私の頭のなかの思い出の半分が、実体験の思い出だとすると、もう半分くらいが、映画・音楽・文学・マンガ・絵画・の作者・主人公・そして作品そのものです。
このふたつが拮抗しています。
もう、この場合、どちらがバーチャルで、どちらが、リアルかわからないくらいに。
それで良いと思っています。
若き頃に見た、アラン・ドロンのシネマの数々を夢見、白い恋人たちでかなでられる人類の華麗なる肉体美と、精神の緊張の闘いに酔いしれ、死刑台のエレベーターに登場するジャンヌ・モローの魅惑を感じ、淀川さんも絶賛した、髪結いの亭主の映像美に、覚醒される時間と空間。
それで良いと、思っています。
小さな頃に脳幹、つまり体の奥の奥を鍛えなければ人は大人になれないという説もある。
河合隼雄氏の意見では、のほほーんと育った人もいつかは「旅」に出るときが必ず人生にはあるとも示唆している。もちろんそれはいわゆる実際の「旅」でなくとも、「不倫」だったり、「退社」だったり、あるいは、「独立」だったり、いろいろ心の状態の中での旅のことである。
その旅の中で出会うさまざまなる人や、事件が彼や彼女を鍛えるのである。いわばイニシエーション的なものでもあると思う。
新選組 (手塚治虫漫画全集)/講談社
¥608
Amazon.co.jp
たんなる備忘録なのだが、この手塚治虫氏の「新撰組」の中で萩尾望都氏が、こんな解説を書いている。
「おさないころから不安な夢を見ていた。誰もいない、何もない、窓の外には霧しかない。
世界はあるのか。私は存在するのか。
成長しながらも何かが指の間からサラサラと失われていく虚無感がつきまとう。その喪失はどこから来たのか。世界からだろうか。両親だろうか。
あの大戦の終了後、世界は何かを閉じ込めてしまったのだろうか。言語化も、視覚化も、意識化もできない無意識の中に浮遊する何か。
私にとっての手塚治虫作品は、その何かを言語化し、絵として視覚化し、物語として意識化した、具体的なものにみえた。不安を不安なものとして自覚させてくれたのである。」
これまた、すごいと感激した!!!
若い頃は妙な言葉だが、「苦労したがる」のである。生きている実感をつかみたいのである。それができない、自分の目的を明確に萩尾望都のように見つけることが出来ない人は、仕事に夢中になる。そこまでは良いが、その仕事からあぶれた人がやはりあぶない。あるいは、もんもんと悩んでいる敏感なる人達。
以前確か、神戸の殺人事件、酒鬼薔薇聖斗事件でしたか、「透明な」という言葉を自分の心の分析に使っていましたね。中学生が・・・・
リアルな実体験に乏しく、仕事もせず、友達もできず、つきあう異性もいなければ、その浮遊するパッションはまさに無目的な性行動にもつきあたることとなる。<例えば小説で言えば、限りなく透明なブルー>
1949年5月12日、萩尾望都は生まれている。
1949年1月12日、村上春樹。
1952年2月19日、村上龍。
比べるのもおこがましいが、私は1954年。
経験が何もないまさに透明なる私の学生時代には、「生は単なる現象にすぎない」と、たわいもない議論ばかりしていた。(小林秀雄氏もたしか、若い頃は、舌で壁をなめたりして、その確かな実在を感じとろうとしていたらしいことを何かの本で読んだ記憶がある)
やはり生きて行くということは、人間同士の絆の中のしっかりした実感の中で生きることが、体にとってのビタミン剤のように、魂にとってのビタミン剤になるのだろう。
それは、ある時には、喧嘩であったり、軋轢であったり、恋だったり、たいていが人間関係の問題でもあるが、人はそこから逃げればあとは、何も残らないということも知る必要があるのではないか。
先日も書いたが、村上春樹氏が、誰とも会わずに創作をする中において、あまりにもすらすら小説が書けた時期があり、こんなことをやっていると人間としてダメになるのではないかと、不安にとらわれたことを何処かで読んだ記憶がある。
ところで、萩尾望都は、この手塚治虫氏の「新撰組」を読んで、たった二行の「大作、許してくれ」に衝撃をうけ、「何か」を具体化する目的を持つ、ひとりの漫画家になろうと決心したのであった。
実際の経験もまた、波瀾万丈の人生だったかもしれません。
ゴッホが精神の牢屋に閉じ込められ、サドが実際の牢屋に幽閉され、ベートーベンがまた
音のない世界のなかで孤独に戦ったように、私の33年間の起業生活もまた朝六時から深夜、ほぼ深夜までという「箱男」のような世界で20年くらいはすごしました。
自分では、ジャングルのなかで戦った戦争経験というくらいにかんがえていましたから、それはそれで良き、体験でした。
今のように労働環境を常に良くして行こうと皆がその方向に向かって行くような時代ではありませんでしたから、昼飯を抜いて、家についたら、午前様を過ぎていたなんていうのはザラ。
バーチャルと、リアル。
不思議な透明感と、肉体と魂の傷の相克。
そのようなテーマを映画にした作品。
「マトリックス」という素晴しき傑作がありますが、それについては、また書きたいことがありますので、いずれ。
「惑星ソラリス」。
「アバター」という名作もありました。・・・好きです。
◎話しはすこし飛びますが、このマトリックスに出ていた、キャリー・アンモスは、「ショコラ」のカロラインの役もやっているんですね。さすが女優です。
アメブロでもおなじみのアバターという名のシネマ。
当然ほとんどの人が見ている筈。
アメリカでもタイタニックの世界興行収入記録を超えましたし、日本でも五日間で13億かせいだと。
しかしながら、キャメロン監督さすがですね。
芸術性と商売が矛盾しない事をしっかりと実現できるんですから。
スピルバーグも押井守もギャフン。
備忘録としては、アメリカ人の本質を探していました。
やはり、男性観はこの映画のサム・ワーシントン、シガニー・ウィーパー、スティーブン・ラングにシンボライズさせているのかもしれませんね。
曰く、バカだけど真っ正直、酒に煙草に無鉄砲だけど女の真の方向性を身体に持つ、男の悪夢=戦う肉体としての環境破壊男。
1995年くらいからのシナリオを暖めていたキャメロン監督のことですから、当然の事すべてのキャラクターにはそれなりの意味をこめているんだと思うんですが、なかなか、宮崎駿の大ファンで「もののけ姫」へのオマージュもかなり意識したらしい。
これは素晴らしいことですね。
東洋のアニメが西洋の映画監督の頭脳を刺激して、作品にその影響を表現させる。
ある意味でこれは西洋の没落の映画版なのかもしれません。
これが世界興行収入記録第一位なんていうことになっているのを見るだけで、イラク戦争にいかにアメリカ人が嫌気をさしているかがよくわかりますね。
教会ではやはり予測されたように汎神論的なこの映画に対して反対意見が出ていると。
確かに、血を実際に流しているアメリカの軍人から見るとこの映画は少しはサム・ワーシントンがまさにラングに言われたように「裏切り者」なのかもしれませんが、芸術の役割はいつだってそうですから。
この地球の細かな科学的なことを理解していなくても、戦争のことも、宗教戦争のことも、よく飲み込めない人も含めてこのダイナミックで、わくわくするような3Dシネマは、大衆に「環境と一体になってくらしたい」という人間がもともと持っている欲求を満足させ、憧れるようなつくりになっております。
ナヴィは、しかしながら、少しインディアンのイメージがあります。
アメリカ人からみると、インディアン・コンプレックスみたいなものがあるのかな。
技術はともかく、科学的な知識はともかく、かれらにもナヴィのような自然に対する畏敬、自然とともに生きる智慧、謙虚な生きる姿勢みたいなものがありましたから、キャメロン監督の無意識にずっぼりとそれらがはめこまれているのでしょうね。
男性原理国家のアメリカ。
バカで無鉄砲な若者が、ひとりの原住民のナヴイ、ネイテイリの哲学に自然に染まっていくあたりは「かれらの憧れ」なんでしょうね。
正義感が強くて、少しおばかだけど、自分が行きたいと思った道をそのままつっぱしる。
良くも悪くもアメリカ人気質なんですか。
といっても、ユダアの教えが底辺に散在しながらも、さまざまなる人種がるつぼになっているアメリカ。
それらの民衆がこの映画を3Dという新しい映画技術とともに支持したということは、なにやら、未来の縮図を少しかいまみるような気もしますね。
政治が悪い時にこそ、芸術は栄えるのだという言葉をちょっと思い出しました。
気の遠くなるような未来。
もちろん私などはいるはずもありません。
地球が太陽に吸い込まれている頃ですね。
人類はどうなっているでしょうか・・・・・??
ひとつのヒントの映画は。
「バーチャリティ12」
不思議な映画、つまり、私の好みの映画。
ジャンルは違うけれども、キューブリックのシャイニングのような
不安感があり、楽しめる。
SFが好きで、imaginationがある人ならば、フェボリットになると思う。
私も、SF大好きなので、これは何回も繰り返して見ると思う。
英語字幕がないのが残念。
レヴューは、オチが?というのが多かったが、淀川さんが言うように、観客を裏切る映画があっても良いのです。たしかに、ヒットする映画は良い意味での、one patternがあるのですが、
みんながみんな、それに乗っかって映画がつくられるのでは、これはつまらない・・・。
「バーチャリティ12」
太陽系外探査ミッションを行う事となった宇宙船パエトン号とそのクルー12人の体験する奇妙なトラブルを描いた、SFサスペンス映画。
◎「惑星ソラリス」ではないけれども、人間=人類の心の奥の奥の力が、仮想アプリによって、あぶりだされてくる、そんな感じ。夢が現実なのか、現実が夢なのか・・・テーマ自体はそんなに新しくはない永遠のテーマ。
ここでも倫理を持ち出せば、仮想アプリによって、もしも、人の悪夢が呼び出されるのであれば、宇宙飛行士達のチョイスの幅は、知性や、知識・技能だけではなく、魂の底の愛のようなものまで、試されるようになるかもしれない。
もちろん、人には、愛だけではなく悪のさまざまが入っているパンドラの箱がそなわっているわけで、真善美だけの人はいないのではあるけれども、確率的に、やはり、悪が少ない人がチョイスされるべきなのかも。
◎ラストの15分ほどで、一気にクライマックス。結論も、良い意味で謎はそのまま。それは私の好みでもある。
この薬は効くと、信頼する人から言われて飲むと、たとえその薬がたんなるメリケン粉であっても、効果がでると言う。
世界は自分の脳がつくりだしている。
信念こそがその源だとも思う。
シネマ「dragonfly」の尼さんが言う、信じたことでこの世はつくられている。
たしかに、この机の上の「ボールペン一本」にしても、この記事を書いている「パソコン」にしても、
昼に食した「豆カレー」にして、この狂ったような暑い夏のせいで飲む冷たい水のはいった「コップ」も、一度は、人の頭のなかで、「考えられた」コトが、モノに、変容したのである。
この地球上のすべての人工物は、一度、人の頭のなかで考えられたからこそ、今、ここに「在る」。
これは考えれば考える程に、不思議なことだと思う。
思うことは実現する。そのことだとも思う。
聖書のなかの、信じるものは救われるという言葉の意味をみな取り違えている。
それは、キリスト教団体に入れば、宗教団体に入れば、気持ちが楽になって、魂が救われるという意味だけではないのだと思う。
だれしも、一次元高いところに、住む人の言葉を誤解する。(次元が違うのだから、言葉でわかる筈がない、)
言葉を分析するのではなく、「感じる」ことをしなくてはいけないと思う。
「ブレインストーム」
このような映画だって、実現する可能性もあるのかもしれない。
男と女の不思議・・・・・・
おんなは実はもともと、強い。
男は実はもともと、フラジャイル=弱い。
以前努めていた会社は、営業だったせいか、いろいろなお客様がいて、特に水商売の女性の方からおもしろい話を聞けた。
良くも悪くも体を張って生きている人間ということだと思う。
岡本太郎がこんなことを書いている。
「三島由紀夫氏は幸福ということばは男にはない」。そう書いているし。
「岡本太郎氏は幸福という言葉は偽善的で使った事はない」と、言う。
ふたりともに、偽善を徹底して嫌ったのだ!!!!!!
「異性がただのあこがれや羞恥心の対象であり、謎であるかぎり、私は決して自由ではあり得ないし、人生や芸術などの真の姿を結局は知る事ができない。異性を怖れぬこと、そして謎を解くこと、それが人生の深みに入る第一歩だと変に神妙に考え込んでしまったのである」・・・岡本太郎
このような考え方は、ちょいとおもしろいと思った。
作家にもいろいろあるが、やはり受け身で待つ、自分からは異性を口説かないタイプの作家もたくさんいるように思える。
つまりモテルわけだ。
だが、村上龍の言葉ではないが、「女にかんたんにモテルようだったら文学なんかやらない」という言葉もまた真実でもある。
そこで、必死に女を研究し、女性を喜ばせようとする積極的なアプローチをするタイプの作家もいる。
上が、カザノバ型で、下がドン・ジュアン型かもしれない。
この岡本太郎の「芸術と青春」を再読してみると、フランスの町で実に当然のごとく、16歳前後のフランスの若者が、積極的に町で歩いている女の子達にアプローチをしてのを眺めながら、驚き、そして深く考えさせられている岡本太郎氏がいる。
まさにドン・ファンタイプに変身しようとしているわけだ。
自分から、大きな女性という壁にたいあたりしていく!!!!!
彼の当時の文学上の仲間たるや、ピカソからはじまり、バタイユやらクロソフスキーやらの、人生の修羅をドツボで研究しているような作家や、実存派の作家が多かったせいだろうか、コチコチに固まった消極的な自分を修正していこうとする勇気ある岡本氏もまた、そこにいる。
最後の最後の岡本さんは、すべての煩悩を乗り越えて、自由自在そのものになったようだ。
素晴しい。
タモリでさえ、びびっている。・・・・・・
クロソフスキーとは、バルテュスのお兄さん。・・
バルテュスは、上野美術館にも来たので、即見に行った。21世紀最高の画家だと思う。
惜しくもなくなってしまったが・・。
バルテュス。
そして、バルテュスの妻。日本に来た時にひとめぼれと、バルテュスいわく・・・

゛
バタイユの哲学本のなかで、私の一番のお気に入りは、「エロティシズム」です。
バルテュスは、上野で彼の美術展を見たけれども、彼が、いかに東洋の美学にぞっこんだったか。
ぼろぼろになった源氏物語の古書を発見して驚愕した。
寛容な女性もいるだろう。
おおらかで、優しい女性もまたいるだろう。
そしてそのなかに、ノエミという彼がであったアルゼンチン系の女性は、岡本太郎をジラセ、くるくるまいさせ、彼を自信喪失に追いこんだ女性である。
彼は、そのどん底の失恋から立ち直って、ようやっと勉強に熱が入り始めた頃に、ノエミに再開し、彼女から、「ああ、あなたはもうスレタ男になってしまったのね」となじられる。
そんな女もまたいるのだと思う。^^
フラレルことを怖れるがあまり、自分の殻に閉じこもって、自分の心に傷がつかないようにすることもある時は、必須かもしれないが、おうおうにしてそれは成長の起爆剤にはならないものだ。
(美人でもどうにもならないくらいにつまらない女性もいる。
イケメンでも同じ。
もちろん見た目もイカさなく、中身もイカさない人間もいるが。
ただ、人生61年生きてきて、まだまだ、人生のひょっこではあるが、やはり、女性は自分との相性が一番だ。
ある人にとって最高の女性が違うある人にとって、最高の女性だということはない。
まことに神様はうまく男と女をつくったものと感心してしまう。)
このあたりは、今の10代20代の若者の性に対する考え方や、異性に対するアプローチはどうなっているのだろうか?
前回紹介した、私の好きなジャック・ニコルソンの出た、60歳になったある遊び人の男が、
昔遊んだ女性の家に花束を持って訪ねて行くシーンかあった。
過去に熱烈につきあったはずの、おんなたち、・・・それなのに。
ことごとく、花束をぶんなげられ、玄関から一歩もいれてもらえない彼が描かれている。
これはおもしろい女性の本質の描き方だ。
つまり、女性は、「今愛している家庭や夫、愛人が、一番なのであって過去の男達は、もう不必要」だということかもしれない。じつに現実的だ。(もちろん、女房や恋人がその場にいないのではあればだが)
男であれば、もう少し、だらだら、ひきずりながら、なつかしみつつも、お茶くらいはいれるのではないだろうか???
いや、そうではないという女性ももちろんいるとは思うが、そう多くはないだろう。
ところが、男性は、いつまでたっても、昔のつき合った女、遊んだ女、そんな彼女達のことを思い出すものである。
というのは、それが彼の生命力の源になっているからだと思う。
岡本太郎氏は最後の最後に、敏子さんというかけがえのない存在に出会ってほんとうに良かったと思う。
彼女のクリップをよく繰り返し見るけれども、女性の観客でさへ、泣いている。
男の本質と女の本質をしっかりとらえた言葉で話す人だからこその、観客へ涙をプレゼントできるのだろう。
なんという素晴しい言葉のかずかず・・・
こんな大きな視点から男性のことを巨大な愛情でつつんでくれる優しき女性はもうほとんど絶滅していると思う。
最後の私のフェボリット、傑作。
ダスティ・ホフマン健在!!!!
「新しい人生のはじめかた」「 [2010年2月6日公開]
いまさら、こんな古い映画を楽しむ。
ダスティ・ホフマンの味のある演技。見飽きない。
ダスティ・ホフマンと言えば、「卒業」。
誰がなんといおうと、私の青春の映画。
中学生の頃に、神戸に妹とふたりで、母方の親戚の家にかなり泊めてもらったのだが、
神戸の風景の美しさ、坂道のロマンが忘れられない。
港。
空の青さ。
細い山に続く坂道。
坂道横に流れる苔むした水源。
六甲山だったか、夜景を今でもはっきり覚えている。
そのオジさんが私の好きだった、「卒業」の「サウンドオブサイレンス」のレコードを
買ってくれて、毎日のように聞いていた。
女がストッキングを足高くあげて履いているシーンのジャケットだったのに、何も驚いたような顔もせずに、笑いながら、一緒に聞いてくれた。
子供さんのいない家だったから、ずいぶん、可愛がってもらった。
今はふたりとも、この世にはもういないが。・・・・
エレーンを追いかけて、教会から花嫁を奪ったあのラストシーンから数十年もたつ。
彼は、今や、離婚経験者であり、
jazzピアニストになる夢が破れ、コンピューターでCMの曲をいやいや作っている。
感受性が人並み以上にあるせいか、彼は、実の娘と会っても、かつての前妻の彼氏を観ていると、どうも引ける。
このあたりのエピソードつくりが実に上手い。
「最後の初恋」にせよ、この「新しい人生のはじめかた 」にせよ、中年の恋は不器用で、自信がないからこそ、尊い。そして、どこか笑えるから、また、味がある。
だいたい、若者の恋は、ある意味、肉欲の愛の要素は強い。
その、肉欲の愛がしだいに枯れてくるあたり、相手に対する「思いやり」が本当にできてくるのではないだろうか?
肉欲の垢尽きて道見える。
このヒロインの女性は実に魅力的だ。
そのけなげ。
不器用。
一所懸命。
落ち込み。
自信のなさ。
先日、男子友だちと、バカ話をしていると、今、「熟女バー」がおおはやりとか。
そりゃあそうだろうと、私は言ってやった。
自分のことがきれいだと思い込んでいて、男子にあれこれ注文ばかりつけているような最近の若い女性に、うんざりしている若者の男性も増えている。
比較すれば、けっして、美人ではないけれど、相手に対する思いやりがあり、自分のことを客観的に観れて、自分の顔や体のことを少し貶したり、笑い飛ばしたりするような、大人の女性は、いつの時代でも、男性は惹かれていくのだと思う。
笑いとは、自分を客観的に見る事のできる能力のことだからだ。
少し大柄で、自分につねに自信が持てないキャラを実に上手く演じています。
そして、ヒーローのダスティ・ホフマンのまたまた、余計なことをついつい、言ってしまう、不器用な時代遅れの男をこれまた上手く演じています。
不器用。
へそまがり。
雰囲気にすぐになじめない。
感受性が強過ぎる。
時代の波に乗るのがへたくそ。
いつでも子供の心を持っている。
自分の娘の結婚披露宴には出なきゃダメ、とか言いながら、飛び入り参加したものの、幸福そうに踊っている皆の群れに入れきれずに、ひとり、ホテル会場から去ろうとするシーン。
すると、ダスティ・ホフマンが、ピアノを惹き始める。
サティではないですか。^^
派手なキスも、濃厚なベッドシーンもなし。
それでも、実に、ふたりは、おろおろと、愛の周りを低空飛行している。
その姿は、素晴らしく感動的。
器用に、カッコ良く今はやりの服を着こなし、話題のテーマでまわりを盛り上げて行くような 若者のグループと比較したとしても、ダントツに、カッコいいのは実は、こちらのふたり。(あくまでも私の意見です。)
最後はハッピーエンドで終わって良かった。
ここは、「最後の初恋」のアンハッピーエンドになるかとふと思った私の心を軽くしてくれました。
河合隼雄の「中年クライシス」を読んでから、見るとますます味の深くなる映画群。
たくさんありますね。
少なくとも、私の魂にとってですが。
自分の頭、特に、左脳でもって、この世のことを「きめつけることはありません。」
我が頭脳には、右脳があります。
大人ぶって、常識人のごとく、範疇のなかに埋没することなく、無限界に「感じましょう。
なんていっても、「歴史の中に埋没してゆく人類を救うことがartの役目」なのですから。
「映画監督というのは、魂に効く毒の薬剤師なのよ。芸者遊びも知らない、streetgirlの買い方も知らない、bARに行った事もない・・・溝口監督はそのあたりは素晴しき毒を持っていたわ。今の映画監督は、おぼっちゃん、おじょうちゃんばっかり。
ただただ、女優にひざまずくだけだから、映画がつまらない。・・」
「溝口の「狂恋の女師匠」を見てから世界の監督に絶対に負けない日本の溝口を初めて尊敬した。 」 淀川長治。
FIN
悩みつつも「火宅の人」自由に生きる男 「千夜一夜物語」「プリティインピンク」「月曜日のユカ」
SWITCH vol.26 No.3(スイッチ2008年3月号)特集:手塚治虫が愛した音楽 手.../スイッチパブリッシング
¥756
Amazon.co.jp
散歩も終わり。
あとは、風呂へ入って、夕飯を食べるだけなので、少し、リラックスしながら・・・
「swich」をぱらぱら見ていますと、手塚治虫が愛した音楽という特集があり、興味深く読みました。
彼は、ベートーベンと自分はよく似ているというように思っていたようです。
晩年、遺作というか、ペンが持つのもツライ状況のなかで、たしか、「グリンゴ」、とか、
「ネオ・ファウスト」とか、そして、この音楽伝記漫画とも言える「ルードウッヒ・B」を書いていました。
ルードウィヒ・B/潮出版社
¥1,258
Amazon.co.jp
手塚 治虫漫画全集 グリンゴ 全3巻完結 [マーケットプレイス コミックセット]/講談社
¥価格不明
Amazon.co.jp
残念ながら、未完に終わってしまいましたが。
彼は、漫画についても、「漫画大学」という作品のなかでも、「革命的な漫画を誰か、書いてくれ」というようなことを書いていますから、ベートーベンが、パトロン的な貴族達にたいして、ぺこぺこもせずに、新しい音楽を作り出して行こうとしていたところに、惹かれたのでしょうか。
尊敬するアニメ作家としては、久里洋二氏をかなり認めていましたね。(私は、作品的には、手塚治虫氏の方がすごいと思いますが、彼は、作風の革新というものに価値を置く人でしたから)
個人的に久里さんの作品では、リズミカルな音楽に合わせたシュールな感覚にひかれます。
彼が漫画を書いていた頃は、PTAが、漫画は悪書ということで、漫画追放運動なんかをやっていた時代です。私も、その頃の人間ですから、漫画を堂々と読んだ記憶はありません。
こそこそと、親に隠れて読んだものです。
・・・・・・・
今や、日本の漫画やアニメは、世界でもさまざまなる芸術家にインスピレーションを与え、国や自治体でさへ、漫画創作を応援している時代、大学にも漫画科があるということだけでも、
時代は大きく変わりましたね。
映画的な手法を漫画に取り入れた人ですから、
トキワ荘の連中だけではなく、今の若い漫画家さんでも、浦沢直樹さんあたりは、かなり手塚治虫さんへ私淑しています。
・・・・・・・・・
隠れた手塚治虫氏の名作映画として、私が偏愛する作品は。
「千夜一夜物語」ですね。
この原画は、手塚治虫氏が、やなせたかし氏に、電話でたのみこんで、完成したとか。
もともと、やなせたかしさんは、メルヘン的な絵の作家ですから、よく、このような
大人向けのエロティックなアニメの原画デザインを手塚治虫氏が頼み込んだと、今は、思いますが、やはり、正解だったようです。
不思議なことに、やなせたかし氏は、本人も書いていますが、50代をすぎても、ヒット作品に恵まれずに、もんもんとしていたところ、手塚治虫氏が、なにかにつけては心配して、面倒をみていたということも、どこかの本で読んだ記憶があります。
(最後の最後に、アンパンマンをつくりあげることができて、ほんとうに良かったと思います。)
・・・・・・・・・・
今、アメーバーブログを見ていると、お金もうけのような記事が多いですね。
個人的には、ブログやネットをせずとも、普通の生活をしながら、子育てをし、日々、遅くまで働いている普通の人達が、好きですし、応援したくなりますが。
丁寧な生活に憧れます。
お茶碗を丁寧に洗う。
トイレをきちんと掃除する。
玄関の靴をしっかりそろえる。
友達への手紙などを忘れずに書く。
私がかつて、仕事をしていた時に、なしえなかったことばかりです。
朝六時に起きて、午前さままで、働いているからしょうがないという言い訳をしながら、生きていました。
それから比較すると、
今の若い人は、日々、携帯でつながっていますし。
年賀状なども書かずとも、メールで簡単にすますこともできます。
男性は、キレイ好きな男性が今は多いですし、奥様もそのようなことを男性に求めますから、
男性が、料理をつくったり、几帳面に部屋を掃除したり。・・・
人生には、彼らは、未来にむかってのレールがずっと続いていると思っています。
でも、ほんとうに、未来に向かってのレールって、??
燕のようにちいさな家庭という巣をつくって、ヒナたちに餌をあたえながら、こじんまりとした、幸福を感じていたい。
気持ちはわかりますが・・・・・・・
そうそう。
ダンナの浮気は絶対に許さないという、女性が最近は多いですね。
(反面。妻達の反乱とも言うべき、妻の不倫が週刊誌の話題になったりもします。)
私の人生観は、「人生は冒険だ」と思っていますから、
アーサー・ミラーの「一歩家を出れば、それはすでに旅だ」という言葉を信じて、
かわりばえのしない通勤生活を、駅までの10分くらいの距離であろうと、あっちから行ってみたり、こっちから行ってみたり、早めに会社にでかけて、途中の喫茶店をいろいろ巡ってみたり、確かに、モーレツサラリーマンでしたが、自分なりの、「プチ・冒険」は楽しめました。
そんな時代。
読む本は、安吾や、檀一雄みたいな、無頼派の本ばかり。
酒や薬や女に溺れながらも、人生の夢をおいかけていく、明治・
大正時代そして、昭和初期の男達のいきざまにあこがれていました。
「火宅の人」 傑作中の傑作です。
何回も書きますが、「芸術とは、歴史に埋もれたる人間を救い出す術をあみだす」ことですから、自分の「普通の生活」をこのような映画に重ね合わせる必要はありません。
感動すればいいんです。
それに、人生は、「一寸先は闇」ですから。
人生にレールなどひいても、そのとうりに行く筈がありません。
東北大震災のような大きな震災でなくとも、ひとりひとりの普通の人たちにさへ、
さまざまなる苦難は襲いかかってきます。
檀一雄氏のように、障害がある子どもを授かったり、大切な家族を事故で失ったり、
ガンや心臓病のような病もありますし、転勤やら、会社の仲間との人間関係のトラヴル、
上司とのストレス、近所付き合いの大変さ、もう、数えたらキリがありません。
人生は、「一寸先は闇」ですから。
この歌、いつも聞いています。
そう考えると、逆にホッとします。安心できます。
それが、人生の土台です。
そこから、どう自分なりに、たくましく生きて行くかです。
できれば、たくましく、これに、美しくをプラスした生き方ができれば最高です。
平安時代をふりかえりますと、
当時は、「恋ができない男」、つまり、一人の女性しか愛せない男は、粋ではない、という理由で、尊敬されなかったと言います。
読む歌が上手くて、楽器の演奏が器用にできて、品があって、漢文なんかの教養にあふれている貴族たちが、女性から愛されたようです。
女性達の歌も、現代人の目から、見ると、やっぱり、今夜は遭いにきてくれたが、これからのことを考えると、暗くなるとか、ウソをついた相手が地獄におちるだろうから心配だとか、女性の心理は現代人とさほど変わらないと思います。
やはり、時代時代の、約束ごとや、規律、法律、習慣、考え方がありますから、
それらに、翻弄されながらも、未来にレールがずっと続いているなんていうことは考えることもなく、(恐らく今のように長生きのできる時代ではありませんから)、15年から30年くらいの短い人生を、せいいっぱいに、美しく、粋に、あはれのこころを大切にしながら、
生きていたんだと思います。
そんなことをいつも考えていた私ですので、「いまここに」生きるという生き方で、ずっと今迄、つらぬいてきました。
いつか、イタリア人と結婚している日本人妻の番組を見ました。
実験で、奥様が、ほくろをつけたり、いつもとは違うカラーのネイルをしたり、
ブローチを変えたりして、仕事帰りのダンナの反応を見るという映画でした。
驚くのは、とにかく、イタリア人の男性は、「ほめてほめてほめまくる」のです。
そして、キスをしてもいいか、と聞きながら、10分おきに、キスをします。
そして、なんでこんなところにほくろがあるんだとか、ブローチを変えたね、とか、
ネイルの色がいつもと違って素敵だとか、全部発見して、気がつきました。
人生をほんとうに楽しんでいるイタリア人。いいです。
異性を愛し、言葉を豊饒に使い、体中をつかって自分の言いたいことをアピールする。
もちろん、日本人の我々にはできない芸当ではありますが、憧れはあります。
質素ではあっても、手作りの料理に舌鼓をうち、日々のワインを楽しむ。
音楽を聞き、ダンスを楽しむ。
以前にも書きましたが、アメリカ人などが、イタリアに行って、心を癒すという物語は、数多くあります。
食事のシーンで一番好きで思い出されるのは、イタリアではありませんが、フランスの傑作名画の一シーン。「ショコラ」
きっと、日本人の方が、生活のすべてにおいて、几帳面で、料理も上手だと思います。
でも。
他人のアラをさがさずに、他人の良いところだけを見て、人付き合いしたり、
音楽を聞いたり、語り合ったり、一緒に踊ったり、みんなで料理を楽しむ・・・
たとえ、立派な料理でなくても、・・・
そのあたりは、日本人は、繊細すぎて、苦手かもしれません。
(ドイツなんかでも、聞いた話しでは、近所の方を「ごちそうがあるから」と誘って、そこに、日本人が行くと、採れたてで、湯がいたばかりの、ホヤホヤのジャガイモが、皿にたくさんあったそうです。日本人は完璧主義ですから、それじゃあ、お客様に申し訳ないとか考えすぎて、きっと、気軽に、宴を囲めないのかもしれませんね。)
たしかに、インスタント食品は、簡単ですし、疲れた時には必須だと思いますが、
やはり、手間ひまかけて、手作りをすると、友達なんかと、楽しめますね。
私も、友達と、宴を開きます。
晩夏。
友達の畑でとれたクレソンなどで、サラダ。
イワシを焼いたり、蕎麦をつくる建築家の友達の夏にひいた蕎麦粉で、蕎麦を食べたり、
最後には、レンガをつんで、ピザを焼いたりして、楽しき時間をすごしました。
・・・・・・・


・・・・・・・・・・・・・・・
ところで。
私が、アメーガーブログに登録した、今から、10年前くらいは、まだまだ、アメーバーブログは認知度が低く、みんな、自分の日記のようなものを書いていたような気がします。
さらなる以前。・・・・・・
30代の頃。1985年前後。
パソコンなどもまだない時代。
ときおり、ブルータスみたいな雑誌に、「パーソナルコンビューターマックで、日記を書く」なんていう記事を見ては、あこがれていました。
それから、少しして、しだいに、パソコンが普及してくるのですが、当時は、
パソコン通信というのがありまして、「ハル」という名作もできましたね。
携帯メールなんかが普及するのは、まだまだ先。
インターネットなんてまだまだ、誰もやっていない時代です。
私が、40代になって、初めてマックを手にした時の喜びは忘れられません。漫画を描きたくて、買ったので、スキャナーやら、絵のソフトなんかを合わせると、100万くらいかかりました。
そんな時代。ネットをやったり、
(ネットサーフィンという言葉がありました。)
メールを初めて、新幹線のなかから、自宅へ飛ばした時の感激。
というのも、まだ誰もメールアドレスを持っていませんでしたから、メールを送る相手がいなかったのです。
・・・・・・・・・・
「プリティインピンク」。
あまり知られていませんが、実に、しみじみした、素晴しき青春映画です。
モーリーが、図書館のパソコンから、おそらくパソコン通信のようなことを、好きな男性にしているシーンがありました。
「プリティ イン ピンク」
1986年公開のアメリカ合衆国の映画。父親との二人暮らしで生活に追われる少女と、裕福な家庭に育った少年との恋の行方を描いた作品。ハワード・ドイッチ監督、ジョン・ヒューズ製作・脚本、モリー・リングウォルド主演。
この世は、男と女としか、いませんから、あまりむずかしいことは考えず、
好きな異性がいれば、アタックすれば良いし、異性の自分にはない、不思議な感性や、
考え方を素直に学べば良いのだと思います。
今の時代。
肩肘はって生きている女性があまりにも多すぎて、可哀想だといつも思います。
男性も、どこか、おどおどして、これまた、冒険心もなく、可哀想。
他人の目を意識しぎると、この人生、楽しくなくなります。
私は、大学時代に、「視線恐怖症」という大病をやりましたので、意識過剰の恐ろしさ・・・
とことん、知っています。
あの、二年間、誰とも口を聞かずにすごしました。
精神の病ですから、不眠に、生あくび、目眩、・・つらかった。
いつも、朝の六時くらいに友達が新聞配達をやっていましたので、バイクの音やら、彼の階段をトントンと、あがってくる音を聞きながら、まだ寝れないなあ・・・まいったなあ、そんな日々をおくっていました。
この病は、仕事について、必死に働いていたら、気がつくと、治っていました。
他人の目をのぞきこむ・・・そんな時間がなくなっていたからです。
意識過剰、恐ろしいですね。
ですから、私はこの人生、考えるまえに、行動というそんな言葉を自分に言い聞かせながら、ここまでやってきました。
悔いはもちろんありません。
自分なりですが、私にとっては、奇跡のような人生。感謝感謝の日々です。
というわけで。
男と、女。
とことん貧乏なヒロインが、金持ちのプレイボーイに惚れてしまうという、・・物語はありきたりですが、見ていて、気持ちのよいカタルシスが、味わえる、名作だと思います。
この女優さん。
当時は、青春女優のナンバー1と、すごい人気でしたし、彼女のファッションが女性雑誌なんかで、もてはやされていました。
いつのまにやら、いなくなってしまいましたね。
「1999年にフランス人作家のValery Lameignèreと結婚し、2002年に離婚。フランスに住んだこともあるのでフランス語が話せる。2007年にギリシャ系アメリカ人の脚本家のパニオ・ジアノポウリスと再婚し、2003年10月22日に女児(マチルダ)、2009年7月10日に男女の双子(アデーレ、ローマン)が誕生。」
がんばってもらいたいものです。
最後に、私の、大好きな映画のひとつ。
ジャック・ニコルソンが出ているので、ついつい、偏愛しているのかもしれません。
おもしろくない、という人もいるでしょうが。
でも、私にとっては、この映画は最高なのです。
それで、良いと思っています。
見る人によって感じ方がさまざま。
そうでなければ、映画なんか、つまらないでしょう。
音楽も、文学も、漫画も、絵画も、同じです。
見る人の、心、魂が、すべてなのですから。
ジャックニコルソンの「結婚適齢期」
若い女性しかつきあうことができない、ひとりの中年男が、
同年代の女性の素晴しさに気がついて行く・・・・・・
これは、傑作だと思います。
私の一番好きな、ジャック・ニコルソンが、あいかわらず、非凡なるコメディを演じていますね。
音楽業界で活躍する63歳のハリー・サンボーン(ジャック・ニコルソン)は、30歳未満の女性が恋愛対象の結婚経験ゼロの裕福な独身プレイボーイ。現在は、一度の結婚経験のある独身の54歳の人気劇作家エリカ・バリー(ダイアン・キートン)の娘マリン(アマンダ・ピート)と付き合っていた。そんなある日、ハリーはエリカの所有する海辺の別荘でマリンと過ごすために訪れるのだが、そこで突然の心臓発作に見舞われてしまう。何とか一命は取り留めたものの、医師(キアヌ・リーブス)の指示で、エリカやエリカの妹ゾーイ(フランシス・マクドーマンド)の世話になりながら、療養の為、そのまま別荘にしばらく滞在させられる破目になる。
ジャック・ニコルソンが若い娘としか遊べなかったが、ある娘の母親とのふれあいにより、自分を変えていく。ダイアン・キートンがなかなかの演技。
ここでの、見せ場は、彼が、昔つきあった若い娘たちを花束を持って訪ねていくが、ことごとく、玄関で、門前払いをさせられるシーン。
映画だから、現実ではないのですから、ただ楽しく見ればよいのだけれども、やっぱり、日本人は結婚してから、愛はそのまま干からびることが多いのは、セックスレスだからかとも思ったりもした。
・・・・・・・・・
中年の恋。・・・・・・・・・
実に傑作が多く、ふと思い出しただけでも、好きな映画は二・三作はすぐに出てくる。
物語を脳裡のディスプレーで、スライドショーさせてみる。
まず、先日も紹介しました、「アメリカンビューティ」。実の娘の友人に惚れてしまう中年のおやじ。彼は、それから、人が変わったように心と体を鍛え、変容しようとするが、結局、彼女との一夜を過ごす時に、遊び人と思っていた美少女は、バージンだったという物語。
次に、「昼下がり、ローマの恋」。アルパチーノ71歳が実に愛らしい。ストリッパーに、しだいに、心惹かれていく。彼女を口説くシーンは実に人生を感じさせて素晴らしい。
デュラスのエッセイなんかを読むと、地中海やら西洋の高級ホテルのプールなどには、
たくさんの金持ちのおばさんたちが、若いツバメをはべらせているというのだが、自分の目で確かめたことはないです。
まあ、ほんとうでしょう。
デュラス自身も、最後の言葉が、たしか40歳以上離れた若き恋人に、愛している、と言ったはずですしね。
女性ですら、こんな時代ですから、やはり、男性は、どうしても若い娘に気持ちがいくのはしょうがありません。
ダイアン・キートン、当時47歳くらい、セクシーさと、寛容さと、美貌があればまたまた、別ですが。
また、こんな映画もありました。
名優ファブリス・ルキーニ演ずる、「屋根裏部屋のマリアたち」。
これも良かったなあ。
二回見てみたいという映画はなかなかありませんよね。
(倶知安アメブロフレンズうさぎさんからの紹介された映画です。)
これまた、中年のフランスの資産家ファブリス・ルキーニが、名誉も妻も家も捨てて、スペイン人のメイドのところに、飛んでいく。
最後は洗濯物を干している彼女が、会いに来た彼ににこりとするところで終わるのがまたまた、良いですね。
この中年のおっさんもまた、60歳くらいの設定でしょう。
ケヴィン・スペイシーは、「アメリカンウーマン」を車で口ずさみながら、マックに転職し、若き娘の友達に近づこうとする。何もかも捨てて。・・・・
離婚し、バーベルを持ち上げ体を鍛え、娘の友達に笑われないように体をつくろうとする。
アルパチーノも、心臓手術であまり無理がきかない身体なのに、彼女に良いところを見せようして、彼女の家の前だけマラソンをして、汗を偽装し、休みながら、またまた、彼女の家に近づくと、マラソンの演技をする。
ほんとうに男は、可愛いというか、子供。
ファブリス・ルキーニなんかは、スペインメイドたちの自由奔放な生活やら、彼女たちの素朴で暖かい生活に心の氷をしだいに溶解させていく。
ただ真面目に、ひたすら、仕事や何か信じたことに、長いこと頑張ってきた男たちが、しばし、頑固になりすぎたり、遊ぶ気持ちをすっかり忘れてしまうことはよくあることです。
ある心理学者によると、心の中には、アダルト=規律や、大人としてふるまおうとする心。ペアレント=母や父のように子供に対する愛護心、子供を守ろうとする心。チャイルド=自由で好き放題の子供時代の心。
この三つがあるらしいですね。
アダルトの心が強ければ、裁判官になるのかもしれません。
ペアレンツの心が強ければついつい子供の教育に熱心すぎることにもなるかもしれません。
チャイルドの心が強すぎれば大人になれないモラトリアムですし、逆に、芸術家なんかはこの心が強くないと、無理ですね。
つまり、良いところと悪いところがありますね。
映画の男主人公たちは、みな、身体や心を、手術や、仕事のノルマや、金銭や株取引などを朝から晩までやっていることなどで、麻痺させていたのかもしれません。
それが、ひとりの女性に会って、心が溶けていく。
女性は偉大です。
本人が自覚しないにせよ、奔放な子供の心を持つ女性に、男性はまたまた、弱いのかもしれません。
人生は何回でもやりなおせる。
アルパチーノが、生まれてくる子供をしっかり抱いて、お前は幸せだなあ、頑固なパパと、甘優しいおじいちゃんと二人と会えるんだから。
確か、そんなセリフを言っていました。
年は関係ありません。あくまでも気力です。
こんなCMもありました。
私の好きなCMです。
男と女の逆バージョン
「恋は、遠い日の花火ではない」、このコピーは、実に素晴しいと思う・・・。
日本の恋、西洋の恋、それでも、濃さが違うようですが・・・・
日本のそれは、天空で、トンボがくっついているようなイメージがありますが、
西洋の場合は、・・・・・・・
もっと、もっと、ソースの濃い、フルコースみたいなものでしょうか。
日本の場合は、やはり、懐石料理でしょうか。
マストロヤンニが主演した「今のままでいて」・・・・・・・・
N・キンスキーを国際的に知られる存在とした伊製メロドラマ。元はネオリアリストの一人で、「芽ばえ」など青春ものを中心に商業映画で活躍したラトゥアーダが共同脚本も手がけ、演出に当たっている。妻子持ちの中年男と16歳の女子学生とのロマンスが、本当は実の娘相手の禁断愛ではないかという疑惑をさし挟んで、極めてアナクロなタッチで綴られる。いつもながら甘美なモリコーネのスコアで救われている一編。
私の個人的な意見ですが、そもそも、総合芸術である筈の映画についても、それは自由に制作されるべきなのですが、村上春樹が、あくまでも作品の中でですが、ちょいとタバコを捨てただけの描写で、そこの住民から苦情が来たり、
宮崎駿氏が、これまた作品のなかで、タバコを吸うシーンが多いという理由だけで、文句が来たりする、昨今。
当時はタバコを男性はほぼ吸っていましたし、当時の風俗も含めて、タバコを書く事でその時代の雰囲気が出るということです。
「カサブランカ」で、タバコのシーンがなければ、あれだけの傑作がだいなしです。
本も、音楽も、映画も、あくまでも、楽しき娯楽=夢として、楽しめばいいのに、
すぐに、自分のことを書かれているとか、若者への影響はとか、
単純にむすびつける昨今の風潮はどうなんでしょうか。
◎資料
1984年、俳優のヴィンセント・スパーノとの間に息子アリョーシャが生まれるが、同年結婚した映画制作者イブラヒム・ムッサとの間の子として育てられる[5]。ムッサとの間にはもう一人1986年に娘ソーニャが生まれているが、1992年に離婚している。1992年から1995年までミュージシャンのクインシー・ジョーンズと暮らし、1993年に娘ケーニャが生まれている[6]。恋多き女性として有名で、ロマン・ポランスキー[7][8][9][10][11]、ミロシュ・フォアマン、マルチェロ・マストロヤンニ、ルドルフ・ヌレエフ、ジェラール・ドパルデュー、ロブ・ロウらとの交際歴がある。
まさに、恋多き女!!!!
料理の素材が違いすぎますね。
つぎなる作品は、「白い婚礼」
「かごの中の子供たち」で注目を浴びたJ=C・ブリソー監督作。17才の少女マチルドは、ある日父親のように歳の離れた49才の哲学教師と出会い恋に落ちる。中年男に唯一の心の拠り所を見つける少女と、許されぬ恋にためらいを見せつつも、少女への恋の想いに戸惑いを覚える男の揺れる心情を描いた作品。当時、人気絶頂だったアイドル歌手V・パラディがヌードも披露する体当たり演技で、'90年のセザール賞新人賞の他、ロミー・シュナイダー賞も獲得した。
アイドル歌手V・パラディ が、シャンソンを歌っています。発音がきれいです。
V・パラディ
1998年にカナダでコカイン不法所持容疑で拘束されたことがある。
1998年から俳優のジョニー・デップと交際し、1999年5月7日に長女(リリー=ローズ・メロディ・デップ)を、2002年4月9日には長男(ジョン・クリストファー・“ジャック”・デップ三世)を出産。結婚はしていなかったがおしどりカップルとして知られていた。しかし2012年6月、ジョニー・デップと破局したことが代理人を通して明らかになる[1]。
2013年から歌手・プロデューサーのバンジャマン・ビオレと交際している。
妹のアリソン・パラディは女優として活躍中。
つぎなる作品は、「小さな唇」
小さな唇(ちいさなくちびる)は、1978年に公開された、イタリアとスペインの合作映画。戦争で心と体を病んだ青年が一人の少女に惹かれ、そして破滅する様子を描く。
つぎなる作品は、「ベビイドール」
巨匠エリア・カザン監督が『欲望という名の電車』に続いて再びテネシー・ウィリアムズの作品『27 Wagons Full of Cotton』を映画化、ウィリアムズも脚本に参加した。ミシシッピ州を舞台に、当時タブーに近かった「幼妻ベビイドール」をめぐる愛欲を描いた問題作。
主演のキャロル・ベイカーは当時既に25歳であったが、童顔だったこともあり、10代の妻を見事に演じきっている。また、イーライ・ウォラックの映画デビュー作でもある。
キャロル・ベーカー美しい。
1956年、『ジャイアンツ』に抜擢された後、続く『ベビイドール』では主演を務めてアカデミー主演女優賞にノミネートされるなど、この年は彼女にとって大転機となった。
1961年、日本人外交官の寺崎英成と結婚したアメリカ人女性のグエン寺崎(寺崎マリコ(マリコ・テラサキ・ミラー)の母)の著書を映画化した『太陽にかける橋』にグエン役で出演し、寺崎英成を演じたジェームズ繁田や丹波哲郎らと共演。また、来日もしている。
1964年に『大いなる野望』、1965年に『ハーロー』に主演。その後、イタリア、スペイン、ドイツ、イギリス、メキシコと海外の作品に出演する。 彼女はハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名を連ねている。
プラチナ・ブロンドの髪で知られているが、実際の髪の色は栗色である。
映画監督ジャック・ガーフェインとの結婚を機に、ユダヤ教に改宗した。
つぎなる作品は、「月曜日のユカ」
カメラワーク、まさに、ヌーベルバークです。
この頃の、加賀まりこは、素晴しい美しさです。
横浜の外国人客が多い上流ナイトクラブ“サンフランシスコ”では、今日もユカと呼ばれる十八歳の女の子が人気を集めていた。さまざまな伝説を身のまわりに撒きちらす女、平気で男と寝るがキスだけはさせない、教会にもかよう。彼女にとっては当り前の生活も、人からみれば異様にうつった。横浜のユカのアパートで、ユカがパパと呼んでいる船荷会社の社長は、初老の男だがユカにとってはパパを幸福にしてあげたいという気持でいっぱいだ。ある日曜日、ユカがボーイフレンドの修と街を歩いていた時、ショウウィンドウをのぞいて素晴しい人形を、その娘に買ってやっている嬉しそうなパパをみた時から、ユカもそんな風にパパを喜ばせたいと思った。ユカの目的は男をよろこばすだけだったから。だが、日曜はパパが家庭ですごす日だった。そこでユカはパパに月曜日を彼女のためにあげるようにねだった。月曜日がやって来た。着飾ったユカは母とともにパパに会いにホテルのロビーに出た。今日こそパパに人形を買ってもらおうと幸福に充ちていた。だが、ユカがパパから聞されたのは、取り引きのため「外人船長と寝て欲しい」という願いだった。ユカはパパを喜ばすために、船長と寝る決心をした。その決心を咎める修にユカはキスしても良いと告げる。ユカを殴り出て行く修。ユカは幼い頃母親の情事を見ていたのを牧師に咎められたことを思い出すのだった。修が死んだ。外人船長に抗議するために船に乗り込もうとして事故死したのだった。ユカは修にキスをして波止場を立ち去る。パパとの約束通りユカは船長に抱かれた。落ち込んだユカだったが埠頭でパパと踊り狂う。踊り疲れたパパは海へ落ちてしまう。溺れ沈むパパをしばらく見ていたユカだったが、やがて無関心に去って行った。
つぎなる作品は、「狂ったバカンス」
カトリーヌ・スパーク主演の青春映画。彼女がブレイクするきっかけになった映画で小悪魔的な美少女に翻弄される中年男を描いた作品である。スパークのロリータ的魅力で日本でもヒットした。
映画ってほんとうに素晴しいと思います!!!
「映画を頭で見たらつまらない。感覚でごらんください」 淀川長治
FIN
「マジソン郡の橋」「K-19 未亡人製造艦」「レッドコーナー」「花のようなエレ」「美しくも短く燃
男が本当に好きなものは二つ。危険と遊びである。
そしてまた、男は女を愛するが、それは遊びのなかで最も危険なものであるからだ。 ニーチェ
男はアホである。
女は、かしこい。
神様はうまく、男女を、つくりあげた、・・・と思う。
今、現代では、イケメンが喜ばれ、男女ともに、清潔、礼儀正しく、常識に添うことができる、
無難で、バランスの良い生き方が、尊ばれます。
そんな雰囲気のなかでは、異端の、アンバランスの、どうしょうもない、金欠病の、いつも頭のなかにあるのは女のことばかり、貧乏のなかであえぎながらユーモアを忘れずに、必死に生きているホームレスのような男は、人気がないのかもしれません。
この漫画も、ほとんど忘れられています。
少し、品がないのですが、松本零士のこの手の作品同様に、
異端作品であるだけに、個人的に、好きな作品です。

松本零士の「おとこ おいどん」と同じジャンルの作品でしょうか。
あと。
Amazonに注文していた「はなしっぱなし」が届いて今、読んでいます。・・・・・
五十嵐大介の「はなしっぱなし」は、もはや、漫画とは思えないほどの、絵画力。
素晴しいです。

テレビはつまりません。
なんでこんなテーマでやっているのだろうと、・・・・・・いつも思います。
やはり、視聴率という怪物に、ずっと支配されていますから。
ある意味、しょうがないでしょうが、テレビの限界でもあります。
たとえば、今話題の、不倫。
コメンテーターとしょうする、たくさんの人たちが、一億層評論家よろしく、偉そうに、
私こそは、決してバカなことはいたしません、私こそがただしい裁判官よろしく、「不倫はいけない」の大合唱。
それが、一度くらいの番組で終了ならともかく、だらだらと、何日も続く。
見ている方は、しだいに、脳を犯されて、自分も正しいことを言わねばならない・・そんな、気持ちになっていきますね。
わからないことは、わからない。それでいいんです。
すべてのことに、正しいことを言おうとすることほど、愚かなことはありません。
夫婦は、人それぞれ。
環境も、考え方も、おかれた立場も、こころのあり方、悩み、家族の規律、みんな違っているからです。
最近見たテレビでは、こんな番組がおもしろかったです。
◎宇宙があと何兆年も先には光を失って消え去ってしまう。
◎活火山をそのままスキャンする技術を発見した日本人。世界の研究者からの賞賛。
◎存在そのものを音楽、音にすることを可能にした起業家。
◎猫や犬の意味のない殺戮ゼロをめざしている自治体。あるいは、NPO。
◎ドナルドキーンの考える日本人とは。
◎ど根性かえるの作者の波瀾万丈人生。
◎浦沢直樹のマンガの勉強。漫勉。特に、五十嵐大介。
とにかく、絵がすごすぎます。
自然の彼独特の解釈が、病み付きになりそうな作品です。
▲YouTubeからのクリップ、すぐに、削除されますね。
・・・・・・・・しょうがありませんが。
花沢健吾と、五十嵐大介は、ほとんどひとりで、メインキャラを書いていて、そこが、大量生産の作品を数十人や、複数ののアシスタントに、書かせる漫画家との違いなので、
素晴しいです。
ベタや、アミなどはともかく、メインキャラの線を、本人が書いてこその、世界に誇れる日本漫画だと勝手に考えています。
たしか、スヌーピーの作者、シュルツもそうでした。
・・・・・・・
あまり、よくばらずに、最低限の生活ができるという視点から描いて行けば、今の現代ではあれば、その意味で、リスペクトされるような作品が生まれてくるのでは?
などなど。話しはそれましたが。・・・・・・・テレビ。
やはり、人は、自分の興味のある番組をついつい、見てしまいます。
自分の興味のないチャンネルは消してしまいます。
だから、番組の制作者が、視聴率をとるがために、「不倫」をテーマにする番組をだらだら流すということは、おそらく視聴者はこの記事をながせば見るだろう、テレビを消すことはないだろうと、予測していると思いますが、これは、視聴者をバカにしていますね。
視聴者が愚かだから、そんな番組のチャンネルを見続けるのか、そんな愚かな番組があるから視聴者がしだいに、愚かになっていくのか、どちらかは、私にはわかりませんが。・・・・
日本人は、好奇心が旺盛ですし、なににつけ、世界一、「反省」の好きな民族であるとは、故三島由紀夫が、どこかで書いていたことを思い出します。
こんな自分だけが、いつも正しい。そして、正しいことしか言わないようなコメンテーターの番組を見る暇があるんなら、この映画を再視聴したほうが、より深くて、さわやかな、そして、人生の深みを味わうことになります。
「マジソン郡の橋」です。20回以上見ています。・・・・・・・・
もしも、テレビでコメンテーターが自分だけは正しいとばかりに、不倫はいけない、と言い、
世間の人達もそう信じきっているのならば、なぜ、この映画が大ヒットしたのでしょうか?
善人はこの世で多くの害をなす。
彼らがなす最大の害は、
人びとを善人と悪人に分けてしまうことだ。
オスカー・ワイルド
アイオワ州の片田舎で出会った、平凡な主婦と中年のカメラマンの4日間の恋を描く。世界的ベストセラー(およびロングセラー)となったロバート・ジェームズ・ウォラーによる同名小説(日本語訳・文藝春秋刊)を、クリント・イーストウッドが製作・監督・主演を務めて映画化。この項目では主として映画について記載する。不倫をテーマにした大人のラブストーリーであり、米国のみならず世界的大ヒットを記録した。撮影は、小説に描かれた実在の場所、アイオワ州マディソン郡ウィンターセットに造られた特設セット『フランチェスカの家』(Francesca's House)にて、延べ42日間に渡って行われた。
田舎に家族とともに住んでいるフランチェスカ。
彼女は、その田舎に住んでいて、その美しい自然、近所の病気になればすぐにかけつけてくれる親切で、慈愛精神にみちあふれている隣人たちのことはありがたいと思う反面、
自分が小さな頃にいただいていた夢とは違う環境にいる自分に少々の不満を抱いていた。
抱いてていたというのはもちろん、無意識のことであって、クリント・イーストウッドが、ある日、突然、彼女の前にあらわれることによって、・・・・・彼と会話を交わす事によって、
彼女の無意識が、表面にでてきたということも言えます。
読書が好きで、もともと、開放的で、酒が好きで、詩を愛唱するような趣味を持つ彼女。
そのフランチェスカが、田舎の長い生活のなかで、しだいに、子育てなどに、麻痺するように疲れ、小さな不満の芽を摘まずに、そのままこころの井戸のなかに、ため込んでいく・・・そんな日々。
そこに、クリント・イーストウッドが、あらわれる。
普通であれば、橋の位置を教えて、グッドバイとおわるはずだったのですが、
野にさくどこにでもあるような花をプレゼントしてくれる彼に、子どものようにその花は毒花なのよと冗談でからかって、笑い転げている自分がいて、ハッとするわけです。
ビールをすすめられ、タバコはいかがと、そんな彼のやることなすこと、彼女のこころを刺激していくわけです。
ここで、彼女は、夫のことを語るときに、「クリーン」という言葉を使っています。
クリント・イーストウッドふんするロバート・キンケイドは、あれれと、いう顔をしますね。
ここがひとつの伏線になっていると思います。
普通であれば、夫や家族のことを語る女性というのは、こころが満足していれば、笑いながら、楽しそうに満ち足りた表情で話すはずですが・・・・・
少し暗さを暗示するような表情と、夫を「クリーン」と語り、最後に、「でも」と呟くフランチェスカ。
もちろんこれは小説や映画のことですから、創作なのですが、不思議なことに、良き小説良き映画というものは、実際の現実よりも、ときには、リアルに女性の内面をかもしだすことに成功するのです。
彼女が自分の好きなことを諦めて、いや、ダンナから止めろと言われて、田舎で暮らす生活を余儀なくされて、それで十分に幸福を感じる女性もいるでしょうし、またフランチェスカのような考え方をする人もいるわけで、人それぞれ、夢の重さが違うでしょうし、気質や性格などにも左右されるもの。
キンケイドが、ドアを閉めるときに、しずかに閉めるところ。
フランチェスカは、陶酔するような、なんともいえない表情をして、「very nice」と言いますね。
このような小さな小さな、「very nice 」が重なって、重なって、彼女の無意識の不満がどっと、せきをきったように、それから、あふれだすわけです。
これは、フランチェスカの場合です。
ですので、世界の人口、数十億人のひとりひとり、みんな違う環境のなか、こころの中、
いろいろな出会いのなかで、自分の人生を編んでいくわけでから。
それらをひとくくりにして、一般論として、「不倫」という言葉で、片付けてしまうのも、どうなんだろうか・・・・・・・そんな気持ちになる私ですが、あくまでも、もろちん、個人的な意見です。
フランチェスカが、最後の最後に、キンケイドと別れる道を選んで、自分の家族とそしてダンナとの道を最後まで、全うしたあとに、キンケイドといっしょに、マジソン群の橋のふもとの川、子どもたちに、灰を棄てさせるシーンは、感動的でした。
ひとは、そんなに「クリーン」なばかりの、存在でしょうか。
「ダーティ」な部分もたた、あるもの。
そのあたりの、女性の深くて、あいまいで、また切ない思いを描いて、
このマジソン郡の橋は世界的に、何百万人ものひとびとの涙を誘いました。
「不倫」がテーマであるのにです。・・・・・・・・・・・
「マジソン郡の橋」は誰しもが、もうすでに、一回は見たとは思いますが、
テレビの不倫報道告発番組に、あきあきしている人たちには、この映画をもう一回、再視聴してもらいたいものです。
メリル・ストリープは大好きな女優です。19回もアカデミー賞にノミネートされている女優はそういないでしょうから。
ところで。
この映画のなかで、こんな台詞もありました。
メリル・ストリープ扮する、フランチェスカが夕食に誘う少し前、「肉汁(グレイヴィ)をかけたジャガイモと赤身の肉を人によっては日に三度も食べるこの地方の住人とは対照的に、ロバート・キンケイドは果物と木の実と野菜しか食べないように見えた。強くてしなやかそうだわ」と思ったという。
この言葉の表現。いいですね。
これだけで、ドラマのキャラの設定が、なにやら、浮かび上がってきます。
・・・・・
作者の、ロバート・ジェームズ・ウォラーが、この小説のカメラマンに自分を重ねていることはまちがいなさそうなので、彼が木の実と野菜だけで生活しているかどうかはわかりませんが、肉汁があまり好きではないのでしょうか。
あと、フランチェスカは、肉が大好きな旦那に対する不満もあるのかもしれません。
栄養学的に見れば、肉をたくさん食べたから元気になるわけではないですからね。(レバーなどの内臓肉の方がビタミンなどが多いのでしょう・・・・)
身体に必須のタンパク質。
これはほんとうは動物から直接とるほかにも、植物性であれば、ビタミン類とミネラル、それと米・麦などを取っていれば身体の中で合成される筈。
それに、肉はとりすぎると肝臓に負担をかけますからね。
豆を食べて肝臓をいたわってあげたいものです。
次なる映画は。・・・・・・・
映画を見ていると、昔、かなり感動していたのに、すっかり題名を忘れてしまい、そのまま記憶の井戸のなかに・・・・・そんな映画があります。
私の場合は、二本。
ひとつが、パソコンの検索機能のおかげで、発見できました。
「核 潜水艦 ハリソン・フォード」でヤフー知恵袋に、私と同じように題名を忘れている人がいたので、発見できました。
原題: K-19: The Widowmaker, 「K-19 未亡人製造艦」
キャスリン・ビグロー監督、ハリソン・フォード、リーアム・ニーソンが出演したノン・フィクション作品。ソ連のホテル級原子力潜水艦K-19が1961年7月4日、北海グリーンランド付近で起こした事故を元に製作された。
キャッチ・コピーは「世界なんか、一瞬で終わる。」
米ソ冷戦下、ソ連の原子力潜水艦K-19は航行実験において、突然原子炉の冷却装置に故障をきたした。原子炉のメルトダウンも考えられた危機的状況に対して立ち向かう艦長(フォード)と放射能の危険と隣り合わせで修理に奮闘する搭乗員の活躍を描く。
これは傑作の部類にはいるのではないでしょうか。
実話であることも、作品を納得性のあるものにしている分、背筋がぞっとするだけの
事件。
この放射能拡散をなんとかしようとする乗組員の責任感にうたれます。
ここ最近の、テロの事件などを見ていると、核に絡んだ、事件がこの先、起こらないとは限らないでしょう。
それこそ、世界なんか、一瞬で終わるのです。
この監督、女性なんです!!
カリフォルニア州サンマテオ郡サン・カルロス出身。父は塗装工場を経営し母はノルウェー系で図書館司書。初期は現代アーティストとして活動し、1972年にサンフランシスコ・アート・インスティテュートを卒業後、ホイットニー美術館の学習プログラムに進み、リチャード・セラやローレンス・ウェイナーといった有名アーティストの下で学んだ。若い頃はロバート・ラウシェンバーグとも活動し、作曲家のフィリップ・グラスと共にマンハッタンの中古アパートをリノベーションして販売する事業を手がけたこともある。
その後コロンビア大学芸術大学院に入学し、映画理論と批評を学ぶ。在学中の1978年に短編映画『The Set-Up』で映画監督デビューし、当時教授だったミロス・フォアマンの好評を得、修士号の一部として提出した。1981年に初の長編『ラブレス』を制作。この頃GAPの広告モデルも務める。1989年にジェームズ・キャメロンと結婚したが、1991年に離婚した。
元夫キャメロンの小説を原作にした1995年の『ストレンジ・デイズ/1999年12月31日』は、1万5千人のエキストラを動員した大作だったが、制作費4,200万ドルに対し興行収入800万ドルという歴史的赤字となってしまう。2002年の『K-19』も制作費1億ドルに対し国内興行収入3,500万ドルとまったく振るわなかった。
イラクでの爆発物処理班の任務を描いた2009年の『ハート・ロッカー』は、制作費1,500万ドルの低予算映画ながらヴェネツィア国際映画祭で高い評価を受ける。本作は同年度公開となった元夫キャメロンの『アバター』と賞レースを争い、第82回アカデミー賞でも大きな話題となったが、結果的に『ハート・ロッカー』が作品賞、監督賞、オリジナル脚本賞、編集賞、音響編集賞、録音賞の6部門を制し、ビグロー自身も史上初の女性による監督賞受賞という快挙を成し遂げた。
彼女のデヴュー作は、これです。
オスカーを獲得した初の女性監督。
旦那さんと、オスカーを取り合ったいわくつきの映画、
「ハートロッカー」
もうひとつは、
検索で、「中国スパイ アメリカ映画 レッド」
これで、何回か、やっているうちに、発見。
ありがたいです。
「レッドコーナー」日本語題名は、「北京のふたり」。
これは、おそらく、ゲオやTSUTAYAにはもうないでしょうから。
奇しくも、2本ともに、ハリソン・フォードの出演作です。
「レッド・コーナー」
大好きな俳優ですので、いつまでも、忘れられないということもあるかもしれません。
DVDで買ってみたのですが、友達に貸してそのままもどってこないことに気がついたのが、最近。
また再視聴したいなと思っていて、題名をすっかり忘れていました。
たしか、「レッドなんとか」ということだけでしたが、これまた、発見して嬉しいです。
北京を舞台に、殺人犯に仕立て上げられたアメリカ人と中国人の女性弁護士の国境を超えた絆を描くサスペンス・ドラマ。国際企業の法律顧問のジャックは、交渉のために北京にやってくる。仕事を順調に終えた彼は、ある中国人女性と一夜をともにする。だが、翌朝彼女は部屋で死んでいた。ジャックは警察に連行され、裁判にかけられる。異国の地で頼る相手もいない彼の前に、法廷弁護人のユイリンが現われる。
次なる映画は、「花のようなエレ」。
大好きな映画です。
このタイプの映画は好きだ。モーツァルトの交響曲とぴったりあっていた「美しくも短く燃え」と少し雰囲気は似ているかもしれない。
ともに、実話。
この「花のようなエレ」は、ロジェ・ヴァディム。
はっきり描くけれども、いわゆる女好きの監督が作った作品のなんと豊饒なことか。
女性を愛し続けたことに対する、きっと女神様からの贈り物だと思う。
誰が誰を愛そうが自由でいいけれど、そのpassionが強い人はすごいと思う。
「エレ」。
どこの国にもいる、やや愚鈍というか、生まれつきの白痴なんだろう。
その村の男たちに遊ばれながらも、けっして「スレル」ことのない「花のようなエレ」なのだった。
耽美派のヴァディム。
かずかずの浮き名を流しただけあって、女性の美を描かせると、そのちょっと不思議な描き方、右にでるものはいないと思う。
つまり、現実的にどうこうということではなくて、彼の魂のなかの女達は、きっと、彼の理想の女たちなんだと思う。
若き愛人に夢中の母。
戦争体験にて発狂寸前の兄。
そして、エレに夢中のボク。
フランスだろうか、美しき森のなかで、その一家は花や蝶のように、日々生きている。
小さな小さな教会のなかで、エレは、しだいに「人間」の感情を育てていったのだろうか、
嫉妬によって彼女の生は、キリストとともに昇華していく、そのシーンは、まるで、
ジャンヌ・ダルクが磷付で火刑にされたのごとく、シンボルとして、生きる喜びにすすり泣いているかのように。
ただでさえ、フランス語の発音特にrはむずかしいのに、エレは、必死に発音しつづける・・・・・・・
ゲザ・アンダの芸術~ドイツ・グラモフォン・レコーディングス(4枚組)
¥2,600
Amazon.co.jp
ピア・テゲルマルク主演の「美しくも短く燃え」は私の青春の中でも、まだ岩見沢に映画館があったころ、
なんと美しい映画だろう、なんという美しい女性だろうと、ため息をつかせた映画である。
「美しくも短く燃え」
このピア・テゲルマルクはイングリッド・バーグマンの再来と言われたのだが、いつの間にかに結婚していなくなってしまいましたネ。
このスウェーデンであった悲しき悲恋の実話の映画のバックでかかっていたのが、ゲザ・アンダの「モーッアルトのピアノ協奏曲第21番」でした。
いつも思うのですが、私は、クラシックの愛好家が少ないのは寂しいですね。
たとえば、私はフィギアが大好きなのですが、あれのBGMにclassic曲が使われていないと盛り上がりませんよね。
真央さんの「月の光」でしたか、素晴しかったです。
あと、映画と言えば、やはりこれらのクラシック音楽で映画がきまっちゃうと思うんです。
惑星ソラリスのあの二人が空中をぷかりぷかり浮かび上がるシーンで使われるバッハ。
最近では「おくりびと」でも「Symphony No9」L.v.Beethoven「Wiegenlied」J.Brahms「Ave Maria」J.S.Bach/C.Gounodの他にも、久石譲さんのチェロの曲もありましたよ。
というわけで。<話が脱線>
ゲザ・アンダ。
この方のピアノ「ピアノ協奏曲 イ短調」 グリーグを朝から聞いておりました。
クララ・ハスキルから重奏の相手として高く評価されているだけあって、ひととおり聞いて、その自然さに共鳴ですネ。
「自然」というのは「人工」つまりartificial の極地ですから。
並大抵の才能と努力ではここまでこれません。
子供がめちゃくちゃに鍵盤叩くのはあれは自然でありません、あれは「拙い人工」です。
「自然」とは到底簡単には到達する事のできない神の領域をさすんだと私はいつも思っているんです。
ワイルドがいみじくも言ったように、「自然は芸術を模倣する」そして、「芸術は自然を模倣する」のですネ。
たんなる自然がつまらないように<リゾート地など>、たんなる人工もつまりません。
彼もまたスイスに第二次世界大戦中に亡命してます。
ハンガリー生まれのリストもそうですが、このあたりの方は、ほんとうに大変です。
リストもハンガリー生まれでしたから、19歳の時のフランツ・リスト賞を貰った時は嬉しかったでしょうネ。
ラフマニノフのスタイルを研究し、同胞であるバルトークの作品を盛んに弾いたらしいですから、そのあたりは私の宿題です。
最後は、モーツアルトはこの人しかいない、というところまできたようです。
こんどアンダのモーッアルト買う予定です。
55歳で亡くなっています。黙祷。
シューマン:クライスレリアーナ 他 [Import]/Geza Anda
¥1,486
Amazon.co.jp
モーツァルト:ピアノ協奏曲第8番&第9番/アンダ(ゲザ)
¥1,331
Amazon.co.jp
トリフォーと同じく、独特の耽美で私を魅惑する三島由紀夫。
この日本文学界において、彼がいないとおもしろくないとまで三島由起夫に言わせた渋沢竜彦。
彼も映画が大好きでしたが、絵画も好きでした。
彼独特の嗅覚で、チョイスしていて、それが好きでした。
澁澤龍彦のイタリア紀行 (とんぼの本)/澁澤 龍彦
¥1,575
Amazon.co.jp
澁澤龍彦との日々/澁澤 龍子
¥2,100
Amazon.co.jp
書斎派という言葉がぴったり当てはまるのはやはり澁澤龍彦さんです。
私も18才頃からずっと澁澤龍彦さんが好きで、金もないのに、全集を横浜の書店で勇気をもってえい!!と気合いを入れて買ったものです。
当時、仕送りは2万円でしたから、それもたまに、来ない時もありましたし、笑、全集に3万もの金を払うのはほんとうに悩みました。
でも、買って読んでいる時は空腹も忘れて、澁澤さんの世界にどっぷりつかりましたね。
彼はエリートコースではないところがステキでした。東大も二浪しておりますし、<そうはいっても東大ですから>、
就職試験も失敗、大学院に進むも父の死により挫折、肺結核にもかかっております。
サドの研究などをしたため、正統派からは白い目で見られ、出世もあきらめ、サド裁判では有罪になりましたからネ。
古今東西の何万冊という書物に囲まれ、深夜真夜中中世の魔女や、悪魔と天使、迷宮、マンドラゴラ、サド、コクトーなどの研究をしている彼が、不思議に、1970年頃から、美しい奥様とともに西洋やら日本の各地を廻る旅にでるのですよ。
ただ三島が、いつも書いているように、「世界旅行をしてもどってきた羽田の人たちは世界を失った人だ」と言うようなたんなるブランド買物旅行とか、つまらない観光旅行とはわけが違います。
彼の研究したヨーロッパの歴史の中に登場する様々なる彼の大好きなもの・ことの跡を見に行く、確認する旅だったんです。
ゲーテの「イタリア旅行」をポケットに忍ばせてイタリアを旅行する、いやあ、こんな旅ならば私もはやく行きたいです。
特に男性は頑張って自分の好きなものをしっかり同伴者に言うべきです。男性原理と女性原理の相克から楽しき旅は生まれる筈で、女性にまかせるとたんなるショッピングだけの旅に終わってしまいますから・・・・・・・
というわけで、この「澁澤龍彦イタリア紀行」を読んでましたら、おやっという奥様の文を見つけました。
「しかも、イスキアではうかつにもただ風光を愛でるだけで終わってしまったのだが、実はなんと、島の東端にカステッロという小島があり、ここはスイスのベックリンが滞在したことがあり、代表作の「死の島」シリーズのモデルとなった場所だったのである。澁澤も知らなかったようだが、バーゼルの美術館ではベックリンも見ていたし、知っていれば、当然興味があったにちがいない。私の準備不足は慚愧に堪えない。」
とあります。
やはり、けっこう、奥様は旅の細かいところはけっこう請け負っていたということでしょ。
そこで、私は「死の島」は知っておりましたが、この傑作を見て感銘してラスマニノフが「死の島」という曲を完成させたことを知り、それを探したのです・・・・・
ありました。
朝のクラシックはこれをさきほどまで一時間ほどずっと聞いて、澁澤龍彦さんの本をぱらぱらめくったり、奥様のお顔をじっと眺めたり、私の学生時代の懐かしき全集をひもといたりして、至高体験をしておりました。
芸術家は、絵画から音楽を創ったり、音楽を聞いて、文学が生まれたり、文学から絵画が生まれたり、お互いにレスポンスしながら、刺激しながら、高みにむかって進化していくんです。
コルトレーンが1926年生まれ、ドルフィが1928年生まれですので、澁澤さんが1928年とくれば、このあたりの芸術家はやはりシュールリアリズムの洗礼を皆受けた時代だということがわかりますね。
ところで。
ベックリンの「死の島」は世界に5作あります。
私の知っている限りでは、ニューユークメトロポリタン、パーゼル美術館、ベルリンナショナルギャラリー、そしてライプチヒ、あと一点はまだ知りませんね。こんど調べてみましょう。
<バーゼル版 「死の島」>
バーゼル版、こちらの方がラスマニノフの曲とあっているかもしれません。
<ベルリン版 「死の島」>
ギーガーが絶賛した「死の島」。
ギーガーの美術書、先日オークションで落札しそこねました。人気ありますね。残念
ヒットラーの部屋に彼が相当気に入った絵画だったせいか、いつも掛けられていた作品がこの「死の島」です。
三島由起夫が緻密な分析しておりますが、芸術家が政治家になると極端に走るそうです。
やはり会田雄次さんが良い事書いてましたが、政治がだめになり、官僚がだめになって、はじめて芸術が元気になる、と。政治などはやはり人のこころの細心なところ、フラジャイルなところには、はいるもんじゃありません。
私もいつか、この作品をドイツに見に行きたいと思っております。もちろん、ポケットのiPodにはラスマニノフの「死の島」をいれて・・
澁澤龍彦のイタリア紀行 (とんぼの本)/澁澤 龍彦
¥1,575
Amazon.co.jp
澁澤龍彦との日々/澁澤 龍子
¥2,100
Amazon.co.jp
次なる映画。邦画。
「愛のむきだし」
園子温監督の23作目の作品で、2008年の第9回東京フィルメックスにおいて観客の投票によって選出される「アニエスベー・アワード」を受賞。2009年の第59回ベルリン映画祭に出品され、「カリガリ賞」「国際批評家連盟賞」を受賞した。第83回キネマ旬報ベスト・テンにおいて、主演の西島隆弘が「新人男優賞」、助演の満島ひかりが「助演女優賞」をそれぞれ受賞し、日本映画ベスト・テンでは第4位であった。第64回毎日映画コンクールでは「監督賞」に園子温、「スポニチグランプリ新人賞」に西島隆弘、満島ひかりがそれぞれ選ばれた。また『映画芸術』誌上の批評家による2009年度ベストテンで第1位になった。
この園子監督は、ガロに漫画を出したりしていますが、落選、やはり、漫画家になれずに、映画監督になったという、最近多いパターンの監督です。
彼の作品のなかで、「自殺サークル」の原作者の、古谷兎丸もまた、ガロに漫画を書いています。
ガロは、昔よく読みました。
原稿料がもらえないという出版社が有名でしたが、けっこうこのガロから、たくさんの芸術家やら漫画家がでています。
その存在意義は、大きいです。
次なる邦画は、
「告白」です。
『告白』(こくはく)は、2010年の日本映画。湊かなえによる同名のベストセラー小説の映画化。監督中島哲也、主演松たか子。2010年6月5日に配給東宝で公開された。娘を殺された中学校教師が生徒を相手に真相に迫っていくミステリー映画[2]。少年犯罪や家庭内暴力、イジメなど、過激な内容や描写で映倫からR15+指定を受けた[3][4]。だが設定の関係上、キャストには15歳未満のものも多くおり、それらキャストは公開後に自分が出演した本作を見ることができなかった。第34回日本アカデミー賞では4冠を達成し、2010年度に日本で公開された日本映画の興行収入成績で第7位になるなど興行的にも成功した。
告白。小説と映画はまったくの別物です。
映画が良い意味で、一人歩きして、どんどんふくらんでいます。
個人的な意見ですが、現代では、普通に常識を持っている人から見ると、どう見ても、
狂気にしか見えないこと、・・・・・・それが、法律によって守られてるというよりも、
法のアミをうまく、くくり抜ける悪知恵のかずかず。
そんな悪い知恵者達に対する、復讐・・・・・・。
そのように最初は、先入観を無意識に持っていて、
このテーマは、批判もありますが、人気のあるテーマ。
逆に言えば、それだけ、不条理な殺人やら、いじめ、があるということでしょうか・・・・・・・・・・・そんなようにも考えてみはじめた。
「ダーティハリー」から、「デスノート」、そして、「霧の旗」やら、
「エコライザー」からはじまり、その他にたくさんある映画のたぐいだろうと。
しかしながら。
驚きました。小説は読んでいないのでは、別物として。
この映画。
悪夢の詩のようです。
法で、裁けない不条理ないじめや、殺人、そんなものに対して、一人あるいは、複数の
仲間で、復讐していく・・・・・・・・
たしかに、映画や読み物としてはこれらの復讐というのは、おもしろいですが、
実際の現実のなかでは、テロリストの事件=復讐というのもありますから、
なかなか、複雑で、賛否両論あるのも事実ですが。
目には目なのか。
右の頬をうたれたら左の頬をさしだせなのか。
難しい問題です。
この作品が、やはり、どうも重苦しくて、見たあとの感じが、良くないのは、
殺人者の心理を掘り下げすぎていて、それを合理的に、処理しすぎだからだと思います。
人のこころのなかのパンドラの箱を、あまりにも、軽く描いている感があります。
そこが、この作品の欠点でもありますし、怖いところでもあります。
ホラー映画なんか問題にならないくらいに、不気味に、怖さで、まさります。
しかしながら。
楽しんでみれません。
先ほど書きました、これまで世界各国でつくられた復讐ものの、傑作と比較すると、
あまりにも、爽快感に欠けます。
そこが、この映画の描きたかったところかもしれませんが、・・・・・・
ある意味、問題作。
人には見る事をすすめません。映画本来が持つ、カタルシス機能がないからです。
復讐という狂気を描く、その意味でだけは斬新です。
作者の湊かなえは、この「告白」での受賞後、この「告白」だけが代表作ではないことを
書きたいと言葉を残しているけれども、いまのところ、その念願は、達成されず。
「まず、作家であり続ける。そして『告白』が代表作でないようにしたい」・・・・・・
2005年 - 第2回BS-i新人脚本賞佳作入選[8]。
2007年 - 「答えは、昼間の月」で第35回創作ラジオドラマ大賞受賞。
2007年 - 「聖職者」で第29回小説推理新人賞受賞。
2009年 - 『告白』で第6回本屋大賞受賞、第2回大学読書人大賞第6位。
2009年 - 第3回広島文化賞新人賞受賞。
2010年 - 『贖罪』で第63回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)候補。
2011年 - 『告白』で第4回大学読書人大賞第3位。
2012年 - 「望郷、海の星」で第65回日本推理作家協会賞(短編部門)受賞[9]。
2013年 - 『母性』で第26回山本周五郎賞候補。
2013年 - 『望郷』で第149回直木三十五賞候補[10]。
2015年 - 『絶唱』で第28回山本周五郎賞候補。
2016年 - 『リバース』で第37回吉川英治文学新人賞候補。
ただ、音楽の扱い方だけは、感心しました。
「告白」・・・・・・・・・・・・・
西井幸人が、クラスで制裁を受けるシーンの選曲が素晴しいです。レディヘッドの「ラスト・フラワーズ」が使われています。
レディオヘッド 資料
1985年にオックスフォードで前身バンドを結成。1992年のメジャー・デビュー以降、外部ミュージシャンの起用は多いものの、同じパーマネント・メンバーで活動している。
彼らのルーツであるポスト・パンクやオルタナティヴ・ロックの大枠に、ポストロックや電子音楽、ジャズ、クラシック、現代音楽などを混交した多彩な音楽性や、アルバムごとの急進的な実験性・変化が特徴。また、ソロ活動も盛んである。
「ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティスト」において第73位。
幸人が、部屋で妄想するシーンは、the xxの「ファンタジー」。
言葉にならない気持ちを、日本人バンド、boris が上手く表現する。
レディオヘッドのトム・ヨークは言う・・・・・・
周りと上手くやるために
容姿やら性癖やらで差別する人たちが90パーセントを占めるこの世界で、
万人受けする作品を作って何になる?
トム・ヨーク
FIN




